

東京弁護士会所属。新潟県出身。
交通事故の影響で怪我や病気になってしまうと、体調の不安に加えて、経済的な不安も発生します。
慰謝料を請求するためには、法律上の知識や、過去の交通事故被害がどのような慰謝料額で解決されてきたかという判例の知識が必要です。
我々はこういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって、妥当な損害賠償金を勝ち取ることが期待できます。是非一度ご相談ください。
PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/kawasaki/
書籍:この1冊でわかる もめない遺産分割の進め方: 相続に精通した弁護士が徹底解説!
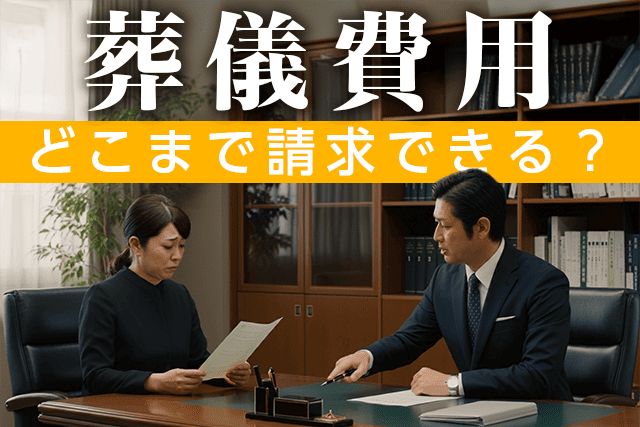
交通事故で被害者が亡くなってしまった場合、葬儀代や葬儀後の法要にかかった費用については、「葬儀関係費」として加害者側に賠償を請求できます。
もっとも、葬儀に関係する費用であれば無制限に賠償請求が認められるわけではなく、算定基準によって上限金額が設定されています。
この記事では、交通事故の被害者遺族が請求できる葬儀関係費の範囲や金額の相場、実際に葬儀関係費が認められた裁判例などについて、わかりやすく解説していきます。
目次
交通事故で被害者の遺族が請求できる葬儀関係費とは、葬儀や故人を供養するために必要となる費用のことです。
葬儀や法要(初七日法要、四十九日法要など)だけでなく、仏壇・仏具の購入費用や墓碑の建立費用など、故人を弔うためにかかった費用については、事故による損害として加害者側に請求できます。
故人を弔うためにかかった費用であれば、無制限に葬儀関係費として請求できるわけではありません。
葬儀関係費用として認められる主な費用は、以下のとおりです。
なお、遺体の処置・保管・搬送料や仏壇・仏具の購入にかかる費用については、葬儀関係費とは別の賠償項目としての請求が認められるケースがあります。
一方で、葬儀に関してかかった費用といえるものの、葬儀関係費としては請求できない項目は、次のとおりです。
香典として得た弔問客から得た収入は、社会的な儀礼行為として相当な範囲の金額であれば、葬儀費用から差し引かれることはありません。一方で、香典収入を受け取っている以上、そのお返しにかかる費用については、事故による損害としては認められません。
また、香典返しと同様の理由で、遠方からくる弔問客の交通費や、精進落としの際にかかる飲食費なども、葬儀関係費として請求することはできません。
交通事故における賠償金を算定する際の基準は、大きく3つあります。
| 自賠責基準 | 主に自賠責保険会社が用いる基準で、通常賠償額がもっとも低額になる |
|---|---|
| 任意保険基準 | 各任意保険会社が用いる基準で、通常自賠責基準よりも少し高いくらいの金額になる |
| 弁護士基準 (裁判基準) | 弁護士や裁判所が用いる算定基準で、通常賠償額がもっとも高額になる |
葬儀関係費用も賠償金の一部なので、この3つの算定基準のいずれかを用いて具体的な金額を算定します。
なお、どの算定基準を用いたとしても、葬儀関係費として認められる金額は、亡くなった被害者の年齢や境遇、家族構成、職業や家族構成などを考慮して、社会通念上相当とされる金額のみが、事故による損害として認められます。
この、「社会通念上相当な金額」について、3つの算定基準それぞれで認められる金額を確認していきましょう。
関連記事
自賠責保険から葬儀関係費を支払ってもらう場合、上限金額は100万円となります。
自賠責保険は、全ての運転者が加入を義務付けられた保険です。死亡事故の被害者遺族は、故人を弔うためにかかった費用について、最低でも上限100万円の補償を受けられるということになります。
なお、自賠責基準の改定に伴い、2020年3月31日までに発生した事故については、葬儀関係費として認められる金額は60万円までとなります。
ただし、領収書などで葬儀関係費として60万円を超える金額がかかったことを証明できれば、100万円まで請求することも可能です。
任意保険会社は、それぞれ独自に設定している算定基準を公表していないケースも多いですが、基本的に、自賠責基準と同額が、それよりも少し高い金額になるケースがほとんどです。
加害者側の保険会社は、少しでも被害者に支払う賠償額を少なくするために、葬儀関係費として必要な範囲を狭く主張してくるケースが多いです。
被害者遺族が適切な補償を受けるためにも、示談交渉で保険会社が提示してくる金額には安易に乗らないようにしてください。
弁護士基準で葬儀関係費を算定する場合、上限金額は原則として150万円となります。かかった費用が150万円に満たない場合には、実際に支出した金額を葬儀関係費として請求できます。
葬儀にかかる費用は人によって異なり、地域や慣習、被害者の社会的地位や遺族の規模によってさまざまです。葬儀にかかった費用を無制限に認めると、事故による損害以上の賠償を認めることにもなりかねません。
また、個々の被害者の状況ごとに、社会通念上必要かつ相当な葬儀関係費について客観的な金額を設定するのは、実際には困難を伴います。
交通事故がなかったとしてもいずれは葬儀関係費を支払う場面がくることや、香典収入などで葬儀費用の負担を抑えられることも加味して考えると、葬儀関係費としては150万円を限度とするのが妥当だと考えられているのです。
なお、葬儀関係費を請求する際には、実際にかかった金額を証明するために、領収書や振込票などが必要になる場合があります。
お布施や戒名料などの領収書が発行されない支出額については、支払日・支払先・支払額を記録しておくのが望ましいでしょう。
弁護士基準で請求できる葬儀関係費は原則として上限150万円ですが、被害者や遺族の社会的地位、複数回葬儀をおこなう必要性など、個別事情によっては、相場以上の葬儀関係費が認められるケースもあります。
ここでは、過去の裁判において、「150万円以上の葬儀関係費が認められたケース」「仏壇・仏具購入費・墓碑建立費が認められたケース」「遺体搬送料・遺体処置費用等が認められたケース」をそれぞれ解説していきます。
死亡事故の場合、葬儀関係費を含む示談交渉の全てを弁護士に任せることをおすすめします。
交通事故に精通した弁護士なら、葬儀関係費を含む賠償金を漏れなく請求できるうえ、弁護士基準で算定された金額を加害者側に請求できます。その結果、最終的にもらえる示談金の総額を大幅に増額できる可能性が高まります。
また、事案に応じて適切な主張をおこなうことで、相場以上の葬儀関係費を獲得できる可能性も高くなるでしょう。
交渉を含む保険会社への対応を全て任せることで、治療に専念できるのも、弁護士に対応を任せるメリット1つです。
死亡事故は、示談金が高額になるケースも多いので、交渉で損をしないためにも、早い段階から弁護士に相談・依頼することをおすすめします。
被害者自身が加入していた保険や遺族の保険に「弁護士費用特約」が付帯していれば、多くの場合実質タダで弁護士に依頼できます。
弁護士費用特約とは、保険会社が一定額の弁護士費用を負担してくれるサービスです。自動車保険などに付帯していることが多いですが、火災保険や生命保険についているケースもあります。
亡くなった被害者自身が加入していた特約を利用できるほか、遺族が加入している保険についてる特約も利用できるケースが多いので、弁護士に依頼する場合には、あらかじめ保険会社に特約の有無を確認しておくことをおすすめします。
なお、弁護士費用特約を使用しても、等級が下がって翌年の保険料が上がることがありません。
交通事故で被害者が亡くなった場合、遺族は葬儀にかかった費用や故人を弔うための費用を事故による損害として賠償を請求できます。
葬儀関係費は、弁護士基準で算定するなら上限は150万円であり、社会通念上必要かつ相当と認められる範囲内で支出した金額が、葬儀関係費として認められます。
一方、香典返しや四十九日法要を超える法要費用、弔問客の交通費や弔問客接待費については、葬儀関係費として請求できないので、注意が必要です。
死亡事故の場合、遺族が受け取れる示談金は数千万円単位になるため、葬儀関係費で多少減額されても、妥協して示談してしまうケースも珍しくありません。
死亡事故の被害者遺族として適切な補償を受けるためにも、死亡事故で示談交渉をする場合は、交通事故に精通した弁護士に依頼することをおすすめします。

