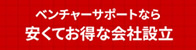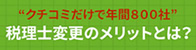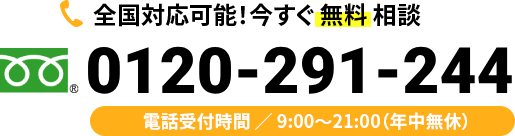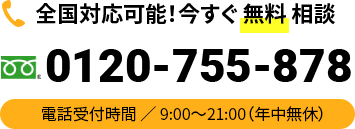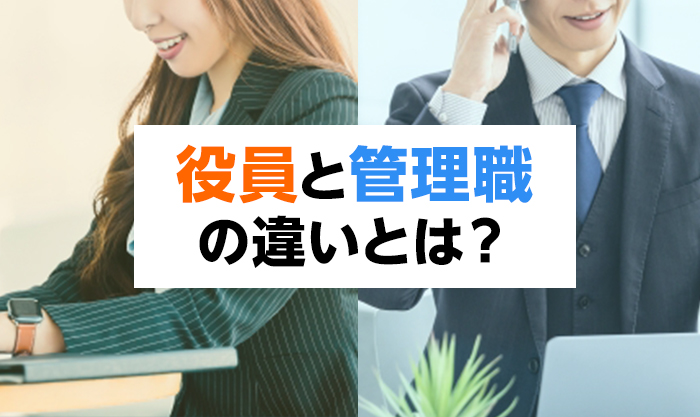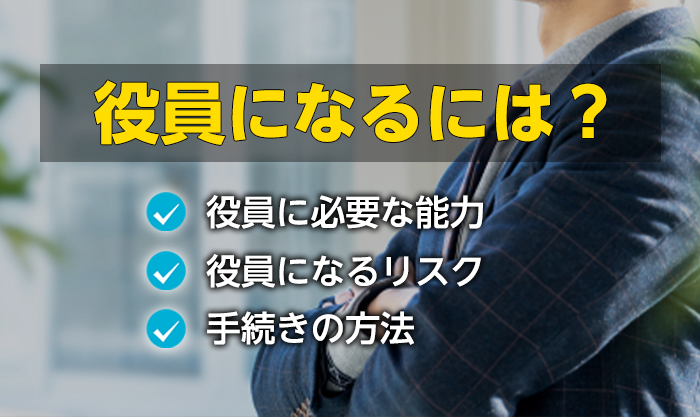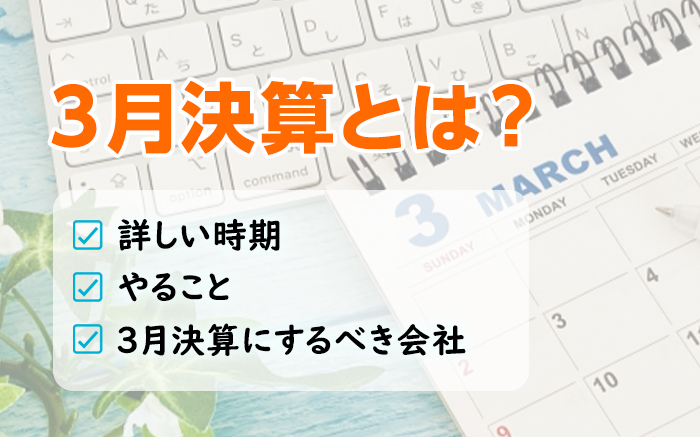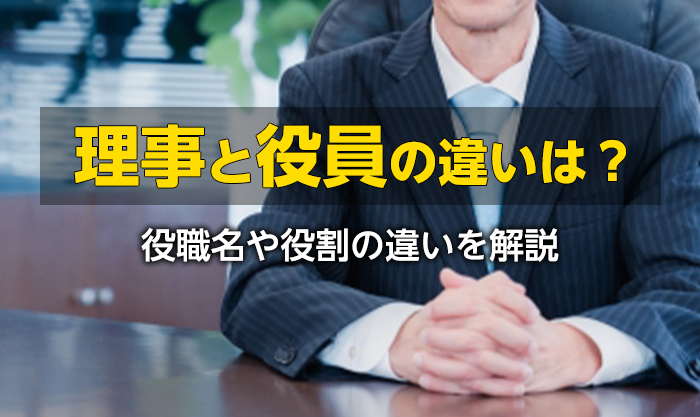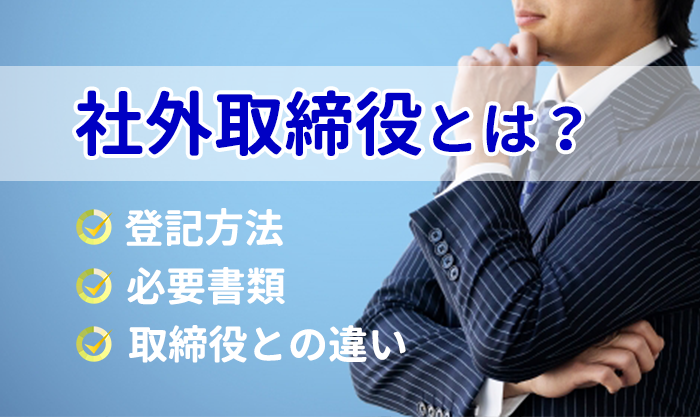最終更新日:2025/5/14
株式会社の役員の数のルールを徹底解説!役員の最低人数や平均人数を解説します

ベンチャーサポート税理士法人 大阪オフィス代表税理士。
近畿税理士会 北支部所属(登録番号:121535)
1977年生まれ、奈良県奈良市出身。
起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネルを運営。
PROFILE:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_writing/#p-mori
YouTube:会社設立サポートチャンネル【税理士 森健太郎】
書籍:プロが教える! 失敗しない起業・会社設立のすべて (COSMIC MOOK) ムック
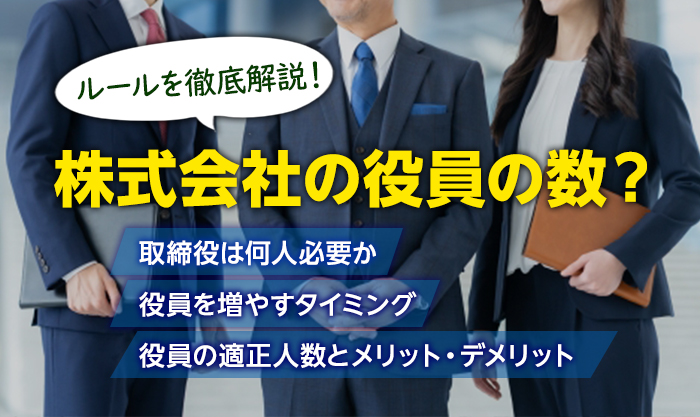
この記事でわかること
- 取締役は何人必要か
- 役員を増やすタイミング
- 役員の適正人数とメリット・デメリット
株式会社の役員の人数には、会社法で定められたルールがあります。全株式に譲渡制限がある会社では、取締役1人でも会社を設立・運営することが可能です。しかし、取締役会を設置する場合は3人以上の取締役が必要となります。このように、会社の種類によって求められる役員の数は異なります。
この記事では、取締役の最低人数のルールや、役員を増やす適切なタイミング、役員の適正な人数とそのメリット・デメリットについて詳しく解説します。会社を設立したい方や、役員の人数を見直したい経営者の方にとって有益な情報を提供します。
目次
取締役は1人でも会社を作れる
会社の経営陣である取締役は何人必要なのでしょうか?取締役の人数は会社の種類によって異なります。
株式の譲渡制限がある会社の取締役は1人でよい
会社の取締役の人数は、株式の譲渡制限の有無によって異なります。
会社法第326条は、すべての株式に譲渡制限がある会社(非公開会社)では、取締役は1人いれば問題ないと定めています。つまり、必ずしも複数の取締役を置く必要はなく1人の取締役だけで会社を運営することが可能です。
一方で、株式の全部または一部に譲渡制限がない公開会社の場合、取締役会の設置が義務付けられているため、取締役は3人以上必要になります。このように、会社の形態によって取締役の人数に違いがあるため、設立時や運営時には注意が必要です。
参考:会社法 第三百二十六条(株主総会以外の機関の設置)|e-Gov 法令検索
株式譲渡制限会社とは
株式譲渡制限会社とは、会社の全株式を自由に売買できない会社のことです。株式の譲渡を制限すると、会社を外部に渡さず、創業者一族や特定の株主による安定した経営を維持することができます。
株式譲渡制限会社がほとんど
中小企業のほとんどが「株式譲渡制限会社」です。弊社では2,000社以上の企業様とお付き合いさせていただいておりますが、このうちの99%が株式譲渡制限会社です。
株式の譲渡を制限することで、敵対的買収のリスクが低くなり、安定した経営を続けやすくなるため、多くの中小企業が株式譲渡制限会社の形態で会社を運営しています。
取締役会設置会社とは
取締役会を設置する会社では、取締役が最低3人以上必要とされており、さらに監査役または会計参与のいずれかを置かなければならないため、役員の総数は最低でも4人以上になります。
株式の全部または一部を自由に譲渡できる「公開会社」では、取締役会の設置が義務付けられています。そのため、公開会社を設立する場合には、取締役の人数や監査役の有無について事前に確認しておくことが重要です。
取締役会は、会社の経営方針を決定し、会社の重要な意思決定を行う機関です。規模の大きな企業では取締役会を設置することが一般的です。
取締役会の設置は任意
取締役会の設置は、すべての会社に義務付けられているわけではありません。
会社法上は、取締役会の設置義務がある会社と、任意で設置してもよいが義務ではない会社があります。
取締役会を置かなければならない会社
公開会社の場合は、会社法で取締役会の設置が義務付けられています。譲渡制限がない株式を一部でも発行している公開会社では、必ず取締役会を置くことになります。
一般的に、大企業や上場企業には取締役会を設置した公開会社が多いです。一方、中小企業や家族経営の企業には株式譲渡制限会社が多く、取締役会を置かないケースがほとんどです。もちろん、株式譲渡制限会社が取締役会を置いても問題はありません。
株式会社の役員とは?
株式会社の役員とは「取締役・監査役、会計参与」です。
会社内で「役員」という名称の役職で呼ばれていても、必ずしも会社法上の役員とは限りません。
役員については以下の記事で解説しています。
役員の構成
会社法上の役員である取締役・監査役・会計参与は、それぞれ異なる役割を持ち、会社の経営に関わっています。
取締役は、企業の成長戦略や事業計画を立案し、会社の重要な意思決定を行います。なかでも代表取締役は会社の「顔」といえる存在です。
監査役は、会社の取締役が適切に行われているかをチェックする役割です。取締役や代表取締役が定款や法に反していないかをチェックし、会社の財務についても把握しています。
会計参与は、会社の財務書類や会計に関する役職です。取締役とともに財務諸表を作って、株主や債権者の要望にしたがって必要であれば開示するのが職務です。
執行役員は役員ではない
「執行役員」という役職名を聞いたことがある人もいるでしょう。執行役員とは、経営陣である取締役と現場のリーダーである管理職の中間に位置する役職です。
役職名に「役員」と入っていますが、執行役員は会社の内部決定で任命される役職であり、取締役のように株主総会で選任されるものではありません。
執行役員は会社法上の役員ではないため、責任の範囲が限定的で会社と雇用契約を結んでいるケースがほとんどです。執行役員の設置は、企業の経営戦略に応じた任意の判断で行われます。人数に関する規定は特にありません。
執行役員については以下の記事で解説しているので、参考にしてください。
設立時取締役の人数について
会社設立時に選任される設立時取締役の人数について解説します。
設立時取締役とは
設立時取締役とは、会社設立前に発起人によって選任される取締役です。設立時取締役は、会社設立に際して必要な調査を実施し、設立後は取締役として会社の運営を担う重要な役職です。会社法に基づいて選任され、登記される役員です。
多くの場合、設立時取締役は、会社設立後に取締役となります。設立時取締役については以下の記事で詳しく解説しています。
役員を増やすタイミング
ここまで、役員の人数のルールを説明してきました。ここからは、役員を増やすための手続きやそのタイミング、注意点を解説します。
役員は増やせる
会社の役員は、必要に応じていつでも増やすことができます。株式会社の場合は、株主総会の決議で新たな役員を選任します。
また、役員の人数に上限は定められていないため、必要であれば何人でも役員を置くことができます。
役員を変更したら登記が必要
役員に変更があった場合は、株主総会の決議で決定した後、法務局で登記変更を行う必要があります。役員に変更が生じてから、2週間以内に登記しましょう。
役員の人数はどのくらいが適切なのか
株式の譲渡制限がある会社では1人でもよいとされている取締役ですが、実際に何人くらいの取締役を置くとよいのでしょうか。
役員の人数は2人のケースが多い
厚生労働省の調査によると、法人の役員総数は「2人」という会社が29.3%で最も多く、続いて「3人」という会社が23.9%となっています。
また、役員1人で運営している会社は16.3%あるそうです。中小企業では、役員が2~3人の会社が最も多いようです。
役員を少なくするメリットとデメリット
株式譲渡制限会社であれば、役員の数が1人でも会社の設立・運営ができます。役員を少なくするメリットとしては、意思決定がスムーズである点や、必要書類の準備がしやすい点などがあげられます。
反対に、デメリットは親族などの親しい者だけで会社を運営するため、新しいアイディアや客観的な視点を持ちづらいという点です。
役員を多くするメリットとデメリット
役員の数を多くするメリットは、多角的な視点を持てるという点や個性や能力がある人材を活かせるという点です。
デメリットとしては、人が増えることで意見の対立が起こりやすくなり、人間関係がこじれるリスクが大きくなる点があげられます。
このほか、役員の不祥事によって会社の信用度が低下するリスクも高まるといえます。役員は会社の重要人物であるため、犯罪などで問題を起こすと会社のイメージに傷がついてしまいます。
役員の数を増やすタイミングは?
役員は必要に応じて何度でも変更できます。では、役員を増やすタイミングはいつなのでしょうか。
役員を増やすタイミングの目安
役員を増やすタイミングのひとつの目安として、従業員の数が20名から30名程度に達した場合があげられます。業種や職場環境にもよりますが、この規模になると1人の役員だけで統率するのは難しくなることが多いです。
特に、部門ごとの業務が明確に分かれてくる段階では、それぞれの部門を適切に管理するために役員を追加することが必要になる場合があります。
会社の規模が大きくなると、少人数の経営者がすべての判断を下すことが難しくなるため、役員を増やして意思決定を分散させることで、より正しい判断ができるようになります。会社の運営では迅速な意思決定が求められるため、適切なタイミングで役員を増やすことが経営の安定につながります。
また、以下のような状況でも役員を増やすことが考えられます。
新店舗の展開や支店の設立
2店舗目の開店や支店の設立を行うと、業務範囲が広がり、意思決定のスピードや管理体制の強化が求められます。このような場合、店舗や支店を統括する役員を新たに迎え入れることでスムーズな経営が可能になります。
新規事業や新分野への進出
既存の役員だけでは適切な判断ができないような新しい事業領域に進出する場合にも、新たな取締役を迎え入れることが効果的です。特に専門知識が必要な分野(IT、海外進出、特定の技術分野など)では、その分野に精通したプロフェッショナルを役員として加えることで事業の成功率を高めることができます。
株主と役員は同じ人でもよい
株主と役員は、会社での立場も役割も異なります。株主は会社に出資を行なっている会社の持主です。それに対して、役員は会社の経営判断を行う立場です。
このように両者の役割は異なりますが、株主と役員が同じ人でも問題はありません。
特に中小企業では、創業者が会社の株を持ち、株主が自ら取締役として経営を担うケースがあります。こうすることで、経営の一貫性を保ち、迅速な意思決定を可能にするというメリットがあるためです。
また、家族経営の企業やオーナー企業の場合は、親族が株を持つケースもあります。
旧商法との違い
旧商法では、株式会社を設立する際の取締役の人数を最低3人とする規定がありました。以前は、取締役を3人以上置かなければ、株式会社を設立できなかったのです。
現在は、株式譲渡制限会社であれば、取締役が1人でも会社を設立できるようになっています。
役員の選任と任期について
会社の経営を担う役員は、どのように選ばれるのでしょうか。役員の選任方法や任期について、会社法の規定をもとに解説します。
役員は株主総会で選任する
会社法上の役員(取締役、監査役、会計参与)は、株主総会の決議によって選任されます。
これらの役職は、会社の経営を担う重要な役職であり、会社の持主である株主の意思に基づいて選ばれる必要があるからです。
株主総会の決議を行い、可決後に法務局で登記手続きをするのが、役員を選任するときの流れです。
役員の選任や構成については、以下の記事で詳しく解説しています。
任期は最長で10年
会社法では、取締役の任期は原則2年、監査役については4年と定められています。
すべての株式に譲渡制限がある非公開会社では、取締役の任期は最長10年まで延長できます。社外取締役の場合は最長で8年です。これは、中小企業や同族経営の企業が安定した経営を続けられるようにするための規定です。小規模の会社では、頻繁に選任手続きを行う必要がなく、取締役の任期を長くすることにメリットがあります。
一方、監査役の任期は原則4年とされており、取締役よりも長く設定されています。
役員は、任期が満了した場合、再任もしくは退任します。再任する場合は、株主総会での決議が必要です。
参考:会社法 第三百三十二条(取締役の任期)|e-Gov 法令検索
役員の数は非公開会社では1人でもよい
株式会社の役員の人数には、会社法の規定があり、会社の形態によって最低人数が異なります。
株式の譲渡制限がある会社は取締役1人でも設立できますが、取締役会を設置する場合は3人以上の取締役(4人以上の役員)が必要です。
また、役員はいつでも必要に応じて増やすことが可能です。役員を増やすタイミングとしては、従業員の増加、新規事業の展開、新店舗の開設時などがあげられます。
役員の人数が増えると多角的な意思決定が可能になりますが、経営の方向性の調整が難しくなることもあります。