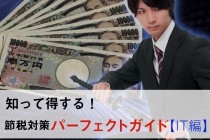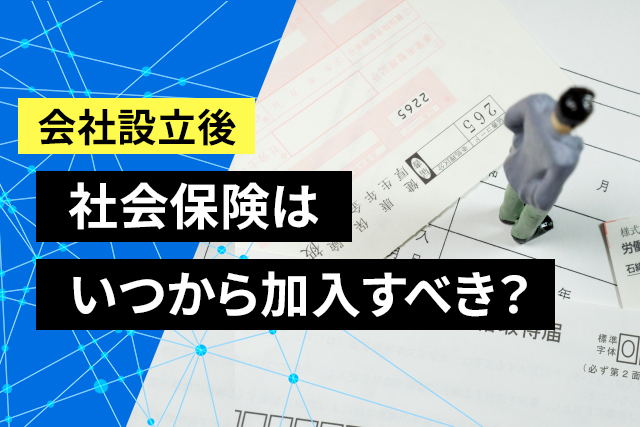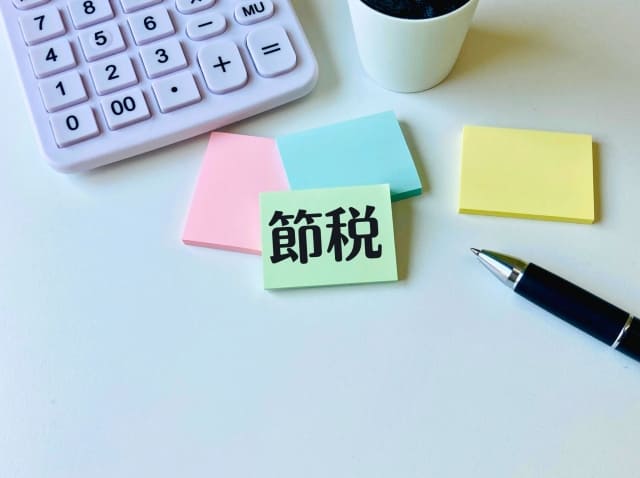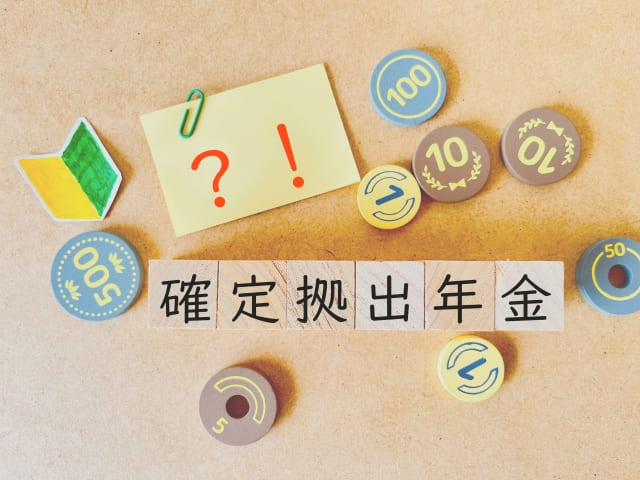最終更新日:2025/11/25
役員報酬とは|税金の計算や損しないための設定と節税ポイント【2025年最新】

ベンチャーサポート税理士法人 大阪オフィス代表税理士。
近畿税理士会 北支部所属(登録番号:121535)
1977年生まれ、奈良県奈良市出身。
起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネルを運営。
PROFILE:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_writing/#p-mori
YouTube:会社設立サポートチャンネル【税理士 森健太郎】
書籍:プロが教える! 失敗しない起業・会社設立のすべて (COSMIC MOOK) ムック
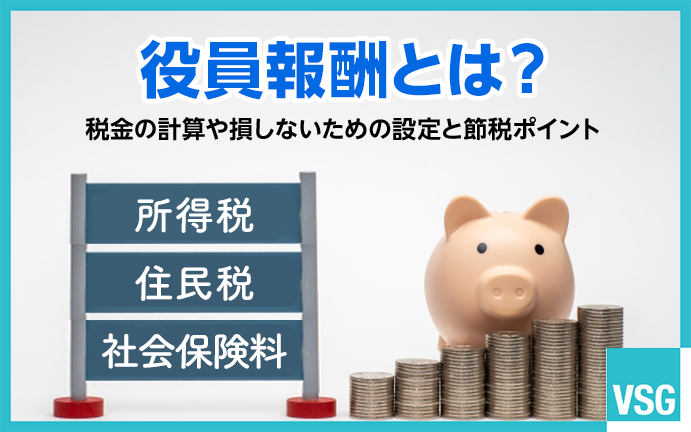
この記事でわかること
- 役員報酬の基礎知識
- 最適な役員報酬額の決め方
- 効果的な節税対策
役員報酬の額を決める際には、会社が支払う法人税と個人の所得税・住民税・社会保険料のバランスをどう取るかが重要になります。高すぎても低すぎても、全体としての税負担が増える可能性があるため、慎重な設計が必要です。
この記事では、2025年現在の制度に基づき、役員報酬の税金について初心者にもわかりやすく解説します。
税務リスクを避けて、正しく節税するためのポイントも紹介していきます。


目次
役員報酬にかかる税金の基本知識
役員報酬とは、会社の取締役や代表取締役といった役員が会社から受け取る報酬です。
この役員報酬には、所得税や住民税、社会保険料の税負担が発生します。
所得税
個人の所得に対して課税される国税です。日本では累進課税制度が採用されており、所得が増えるほど税率(5〜45%)が高くなります。
住民税
個人の所得に対して課税される地方税です。原則として一律10%(所得割)の均等割が課されます。
社会保険料
主に厚生年金保険料と健康保険料(40歳以上は介護保険料も加算)です。役員報酬に応じて金額が決まり、会社と個人が折半して負担します。
2025年版 基礎控除の変更点
基礎控除とは、個人の所得税・住民税を計算する際に、所得から一律に差し引かれる制度のことです。税負担は基礎控除の額によって変わり、この基礎控除額は2025年に改定されました。
| 年収 | 基礎控除額 (2025年・2026年) |
基礎控除額 (2027年~) |
|---|---|---|
| 200万円未満 | 95万円 | 95万円 |
| 200万円以上475万円未満 | 88万円 | 58万円 |
| 475万円以上665万円未満 | 68万円 | |
| 665万円以上850万円未満 | 63万円 | |
| 850万円以上2,595万円未満 | 58万円 | |
| 2,595万円以上2,645万円未満 | 48万円 | 48万円 |
| 2,645万円以上2,695万円未満 | 32万円 | 32万円 |
| 2,695万円以上 | 0円 | 0円 |
この基礎控除を含めた所得税・住民税・社会保険料のバランスを最適化し、損しない役員報酬額を具体的に考えていきましょう。
役員報酬の損金算入要件
会社にとっては、役員報酬が経費として認められるかどうか(損金算入できるかどうか)が非常に重要です。なぜなら、認められないと、会社の法人税負担が増えるからです。
役員報酬が損金算入できるようになるには、下記3つのいずれかの要件を満たす必要があります。
- 定期同額給与
- 事前確定届出給与
- 業績連動給与
1. 定期同額給与
定期同額給与とは、毎月決まった金額を決まった日に支払う給与のことです。
最も一般的な方法で、法人税法でも「損金算入が認められる基本形」となります。
ただし、一度設定した金額は、事業年度の途中では原則として変更できません。変更する場合は、事業年度開始から3カ月以内に行う必要があります。
2. 事前確定届出給与
賞与などのように、決めた金額が指定した日に支払われる役員報酬のことです。
事前に所轄の税務署に支給予定日・支給額を明記した届出を提出することで、損金算入できます。
届出を怠った場合や届け出た内容と異なる支給があった場合は、その全額が損金として認められないため注意が必要です。


届出に支給日を記載しますが、実際に支給する日と記載した支給日が違うと損金不算入となります。トラブルが多発しておりますので振込みの際には十分にお気をつけください。
3. 業績連動給与
会社の業績に連動して支払われる報酬です。
一定の開示義務や計算根拠の明示が必要なので、中小企業では適用されるケースが限られており、多くの場合、上場企業などが対象となります。
最適な役員報酬額の決め方
役員報酬の金額を決めるときには、会社の法人税と個人の所得税・住民税・社会保険料のバランスをどう取るかが重要となります。
高すぎても低すぎても、全体としての税負担が増える可能性があるため、慎重な設計が必要です。
所得税・住民税・社会保険料の負担を最適化する
個人の所得税は累進課税制度のため、役員報酬が増えれば増えるほど税率が上がります。住民税も所得に応じて税額が計算されます。
法人税は会社の利益にかかるため、役員報酬を出すことで法人の利益を減らし法人税負担を軽くできます。
また、社会保険料は、役員報酬が高くなればなるほど負担も増えていきます。しかし、会社と個人で折半して支払うため個人の負担は増える一方、会社の利益は減り、法人税率が低くなる可能性も出てきます。これらの要素は複雑に絡み合っており、具体的な数値を試算して、最適なバランスを見つけることが重要です。
最適な役員報酬額の決め方
実際に、役員報酬の税金がいくらかかり、手取り額がどう変わるかシミュレーションしてみましょう。
下記の表は、資本金1億円以下の中小企業、利益は2,000万円、東京都在住の40歳未満の単身者(扶養家族なし)をモデルに、2025年最新の基礎控除額を考慮して試算した金額となります。
| 役員報酬 (額面) |
所得税・住民税 | 社会保険料 | 個人の手取り (年額) |
個人の手取り (月額) |
|---|---|---|---|---|
| 300万円 | 約18万円 | 約43万円 | 約248万円 | 約20.6万円 |
| 400万円 | 約28万円 | 約57万円 | 約322万円 | 約26.8万円 |
| 500万円 | 約42万円 | 約72万円 | 約394万円 | 約32.8万円 |
| 600万円 | 約58万円 | 約86万円 | 約464万円 | 約38.6万円 |
| 700万円 | 約78万円 | 約100万円 | 約530万円 | 約44.1万円 |
| 800万円 | 約105万円 | 約115万円 | 約589万円 | 約49万円 |
| 900万円 | 約135万円 | 約129万円 | 約644万円 | 約53.6万円 |
| 1,000万円 | 約165万円 | 約143万円 | 約699万円 | 約58.2万円 |
このシミュレーションから、年収が増えるにつれて税金と社会保険料の負担割合も増えていくことがわかります。
特に社会保険料は役員報酬が一定額を超えると上限に達しますが、それまでは増え続けるため、手取り額に大きな影響を与えます。
効果的な節税対策7選
役員報酬の調整以外にも、会社と個人で税負担を軽減するための効果的な節税方法があります。
- 配偶者を役員にして所得分散
- 役員社宅制度の活用
- 通勤手当の支給
- 出張日当の設定
- ふるさと納税
- 小規模企業共済への加入
- 個人型確定拠出年金(iDeCo)
1. 配偶者を役員にして所得分散
配偶者を役員として加え、適切な役員報酬を支払うことで世帯全体の所得を分散し、所得税・住民税の負担を減らすことができます。


配偶者に役員報酬を支払う場合は、業務の実態があるかどうか税務署が厳しく確認します。名義だけの役員報酬は否認される可能性があるので、ご注意ください。
2. 役員社宅制度の活用
会社が契約した住宅を役員に社宅として貸し出し、役員から一定額の家賃を支払ってもらう制度です。
会社側は家賃の半額以上を経費として計上でき、結果利益が減るので法人税が下げられます。また個人側は、家賃が低く抑えられるので自己負担が減ります。
| 役員社宅制度の活用例 | |
|---|---|
| 市場家賃16万円のマンション | ・会社が全額払って、役員から一定額(8万円)を徴収 ・会社は8万円を経費計上、役員は8万円の実質負担のみ |
実際には、もう少し細かい規定があります。社宅の面積や、自己所有の社宅か小規模住宅の社宅かによっても、経費として計上できる金額が変わります。
詳しくはこちらをご確認ください。
3. 通勤手当の支給
非課税の通勤手当(最大月15万円まで)を設定することで、報酬とは別に支給しつつ節税が可能です。
通勤手当は原則として会社の経費になるので、課税所得が減り、法人税が少なくなります。
4. 出張日当の設定
「出張日当」とは、役員や従業員が出張した際に、交通費・宿泊費とは別に支給される手当のことです。
出張日当は課税されないため、適正な範囲で導入することで実質的な手取り増加になります。
会社としても、「福利厚生費」や「旅費交通費」などの経費として計上可能となり、結果、法人税の課税所得を減らすことができます。


・実際の出張に基づいて支給されている
・社内規定で日当の金額や支給条件が定められている(従業員にも役員にも支給する必要がある。金額は変えてもよい)
・日当が高すぎない(1万~2万円くらいが妥当)
・実費支給の交通費や宿泊費などとは別に、明確に区別されている
5. ふるさと納税
ふるさと納税は直接的な節税効果はありませんが、納める税金の納付先を選べ、寄付金額から2,000円を引いた金額が所得税・住民税から軽減されます。
また自己負担2,000円で返礼品が受け取れます。
6. 小規模企業共済への加入
小規模企業共済とは、中小企業経営者や個人事業主などが「自分の退職金」を積み立てるための制度です。
小規模企業共済に加入することによって、掛金が全額「所得控除」となります。
所得控除されることにより、課税所得が下がり、所得税・住民税を安くすることができます。
また退職時には、一括受取なら「退職所得控除」、分割受取なら「公的年金等控除」が受けられ、受取時も税制優遇されます。
小規模企業共済の節税効果シミュレーションの例
| 年収(所得) | 月額掛金 | 年間掛金 | 年間の節税額 (所得税+住民税) |
|---|---|---|---|
| 500万円 | 3万円 | 36万円 | 約7.2万円の節税 |
| 700万円 | 5万円 | 60万円 | 約12万円の節税 |
| 1,000万円 | 7万円 | 84万円 | 約18万円の節税 |
7. 個人型確定拠出年金(iDeCo)
個人型確定拠出年金(iDeCo)とは、自分で掛金を拠出し、運用する年金制度です。
掛金は全額所得控除され、所得税・住民税が軽減されます。また、運用中に出た利益は非課税となります。
そして、受取時も退職所得控除や公的年金控除の対象となり優遇されます。


原則、60歳まではお金を引き出すことはできません。毎月の金額に無理のない範囲で運用していきましょう。また、投資信託などの運用結果により元本割れする可能性もあります。
役員報酬の変更可能なタイミング
役員報酬の損金算入が認められるには、原則として事業年度開始から3カ月以内に金額を決定する必要があり、その後は変更不可となります。
ただし、例外として、期中での変更が可能なケースがあります。
- 役員の地位に変更があった場合
- 職務内容の大幅な変更があった場合
- 会社の業績が著しく悪化した場合
役員の地位に変更があった場合
取締役が代表取締役になったり、代表取締役から会長に昇格したり、役員の地位に変更があった場合は期中でも役員報酬を変更できます。
ただし、業務内容が昇格前とほぼ変わっていない場合や、肩書だけの昇格だった場合は、増額分の損金算入は認められない可能性がありますので、ご注意ください。
職務内容の大幅な変更があった場合
例えば、新規事業責任者への就任や子会社代表となるなど、職務内容に大幅な変更があった場合は、臨時改定事由が認められるため、期中であっても役員報酬を変更できます。
ただし、変更前後の業務内容に大きな差がない場合、増額分の損金算入が認められない可能性もあります。
会社の業績が著しく悪化した場合
会社の業績が著しく悪化した場合は、例外的に期中での役員報酬の減額が認められています。
ただし、単に一時的に業績が悪くなったというだけでは認められません。
新規事業2期連続赤字、売上高前期比50%以上減少などの、会社の存続が危ぶまれるような深刻な状態の場合のみ減額が可能となります。
もし、期中での役員報酬の減額を検討する場合は、要件があてはまっているか慎重に判断し、必ず税理士などの専門家に相談して具体的な状況を説明し、アドバイスを受けるようにしてください。
まとめ:税務リスクを回避し、賢く節税する
役員報酬の設定は、単なる給与の決定にとどまらず、会社と個人の税金・社会保険料の全体的な負担を最適化するための重要な戦略です。
定期同額給与などのルールを守りつつ、効果的な節税方法を取り入れ、税金と社会保険料のバランスを見ながら、会社にとって適切な金額を検討してみてください。
税理士などの専門家に相談すると、会社の状況にあわせた役員報酬をシミュレーションしてもらえます。ぜひ会社設立を検討している段階から相談しておくことをおすすめします。
よくある質問(FAQ)
Q1. 役員報酬で税金がかからない金額はいくらですか?
だいたい年間約100万円以下に役員報酬を抑えた場合、所得税・住民税はかかりません。ただし、社会保険料は別途考慮が必要です。
社会保険の加入には「106万円の壁」と「130万円の壁」があり、要件によって社会保険の加入義務が発生する給与が変わります。
106万円から加入義務が発生する要件はこちらです。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 2カ月を超える雇用の見込みがある
- 所定内賃金が月額8.8万円以上(年収約106万円)
- 学生ではない
- 従業員が51人以上の事業所に勤めている
130万円以上になると、この要件にあてはまらなくても社会保険の加入義務が発生します。
Q2. 役員報酬はいつでも変更できますか?
原則として、事業年度開始から3カ月以内に変更する必要があります。ただし、「職務内容の重大な変更」などの例外要件が認められる場合は、期中変更も可能です。
Q3. 最も節税効果の高い役員報酬額はいくらですか?
法人と個人の税負担のバランスを見ながら、報酬額を調整する必要があります。
会社の利益状況によって異なりますが、一般的には以下が目安となります。
- 会社の利益1,000万円:役員報酬600万円
- 会社の利益2,000万円:役員報酬800万円
- 会社の利益3,000万円:役員報酬1,000万円
Q4. 配偶者を役員にする場合の注意点は?
配偶者を役員にする場合、税務署は実際に業務に従事している実態があるかどうかを厳しく確認します。業務の実態がない場合は名義貸しと判断され、税務署に否認されるリスクがあります。
例)自分の役員報酬が月額100万円=年間1,200万円で、会社には160万円の利益が残っている場合(扶養家族が妻と16歳以上19歳未満の子ども2人、社会保険料は考慮しないと仮定)
このときの法人税等が約45万円、個人の所得税・住民税の負担合計が約206万円で、合計251万円が概算納税額になります。
自分が60万円、奥さんが40万円の役員報酬にしたとすると、二人の所得税・住民税の合計は約130万円ほどとなり、70万円も負担が少なくなります。
Q5. 役員報酬を0円にすることはできますか?
役員報酬を0円にすることは可能です。会社設立初期であったり、資金繰りが厳しい場合に役員報酬を0円とすることがあります。
ただし、社会保険に加入できないので、国民健康保険や国民年金に別途加入する必要があります。また、金融機関からの信用度が下がり、融資などを受けられなくなるリスクがあります。
会社にお金を残すために必要な節税方法
- 節税対策Vol.1 税金の世界は「知らない人は損をして、知ってる人が得をする」
- 節税対策Vol.2 税金の世界は「知らない人は損をして、知ってる人が得をする」 節税には種類がある
- 節税対策Vol.3 お金が出ていかない最優先の王道的節税 「役員報酬」
- 節税対策Vol.4 お金が出ていかない最優先の王道的節税 「旅費規程を作って出張日当を活用し、税金のかからない経費を作る」
- 節税対策Vol.5 お金が出ていかない最優先の王道的節税 「未払金・未払費用を今期に計上する」
- 節税対策Vol.6 お金が出ていかない最優先の王道的節税 「回収できない売掛金など不良債権を経費にする」
- 節税対策Vol.7 お金が出ていかない最優先の王道的節税 「期末の大きな売上を合法的に翌期に計上する裏ワザ」
- 節税対策Vol.8 お金が出ていかない最優先の王道的節税 「評価損」
- 節税対策Vol.9 お金が出ていかない最優先の王道的節税 「除却・廃棄」
- 節税対策Vol.10 お金が出ていかない最優先の王道的節税 「社宅」
- 節税対策Vol.12 お金が出ていかない最優先の王道的節税 「特別減税制度」
- 節税対策Vol.13 お金は出ていくが将来につながる投資型節税「短期前払費用」
- 節税対策Vol.14 お金は出ていくが将来につながる投資型節税「中古資産の減価償却」
- 節税対策Vol.16 お金は出ていくが将来につながる投資型節税「消耗品を購入しておく」
- 節税対策Vol.17 お金は出ていくが将来につながる投資型節税「社員旅行を経費にして節税」
- 節税対策Vol.19 お金は出ていくが将来につながる投資型節税「従業員社宅」
- 節税対策Vol.20 お金は出ていくが将来につながる投資型節税「決算が近くなれば広告宣伝費で節税」
- 節税対策Vol.22 お金は出ていくが将来につながる投資型節税「社内規定整備に投資して節税」
- 節税対策Vol.23 お金は出ていくが将来につながる投資型節税「別会社を設立して節税」
- 節税対策Vol.24 お金は出ていくが自分の会社を守るための保守的節税「 小規模企業共済に加入する」
- 節税対策Vol.25 お金は出ていくが自分の会社を守るための保守的節税「 中小企業倒産防止共済制度に加入する」
- 節税対策Vol.26 お金は出ていくが自分の会社を守るための保守的節税「中小企業退職金共済に加入する」
- 節税対策vol.28 『会社にお金を残すために、本当に使える30 の節税方法』