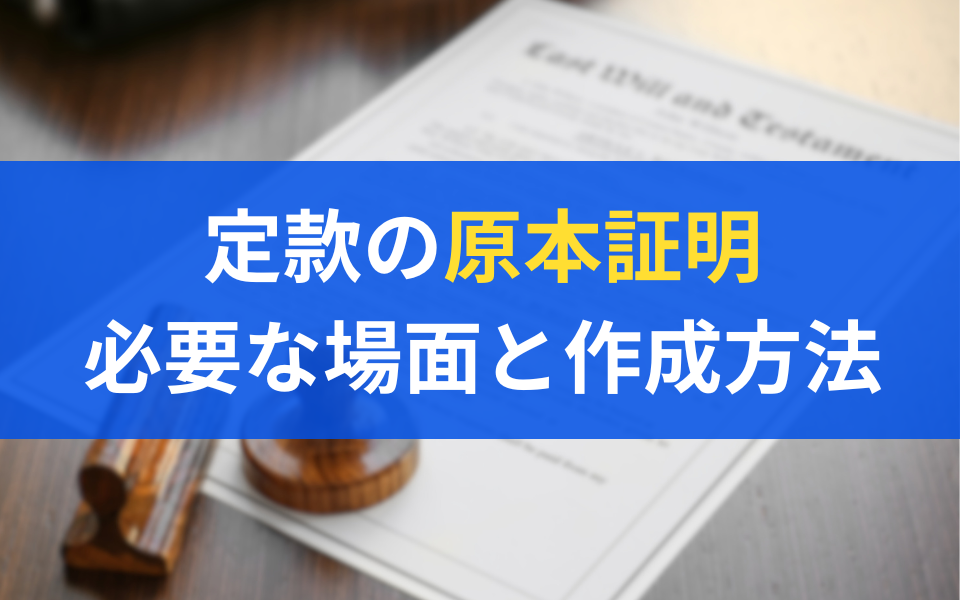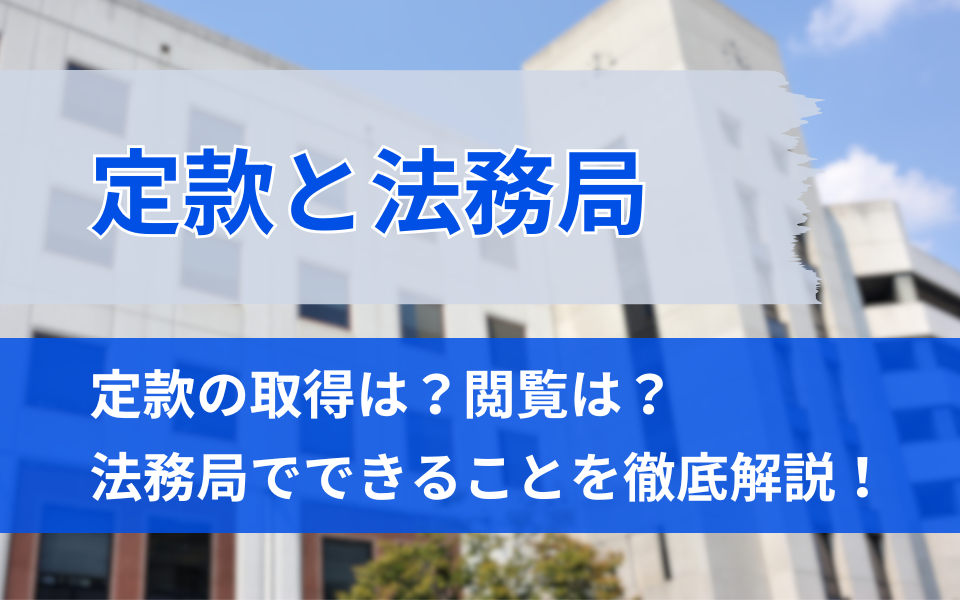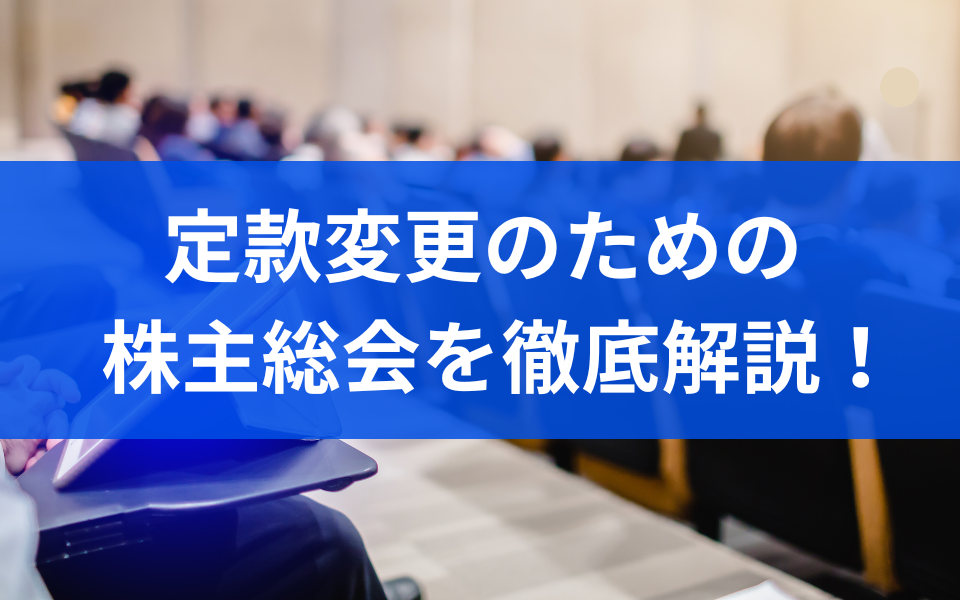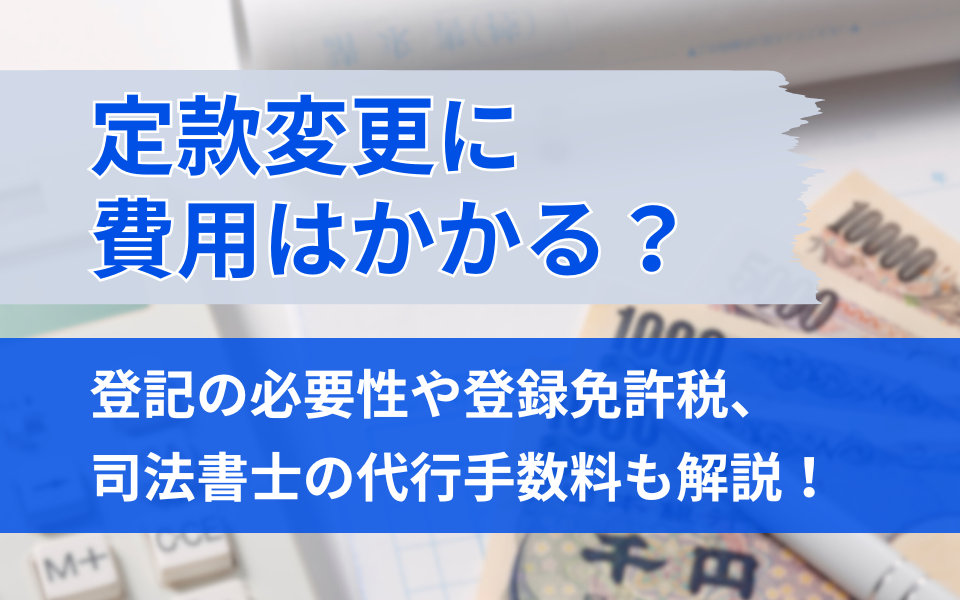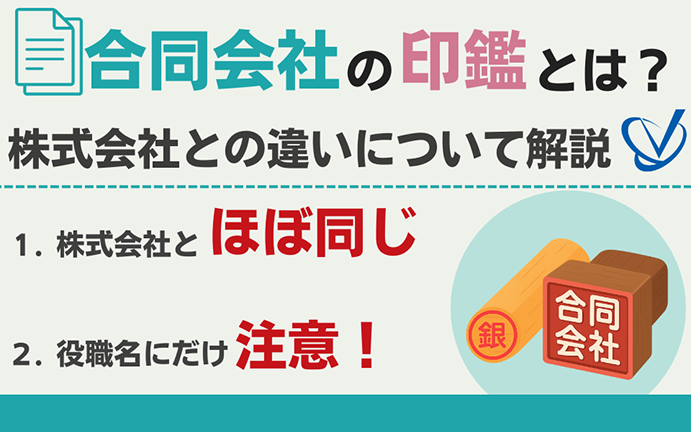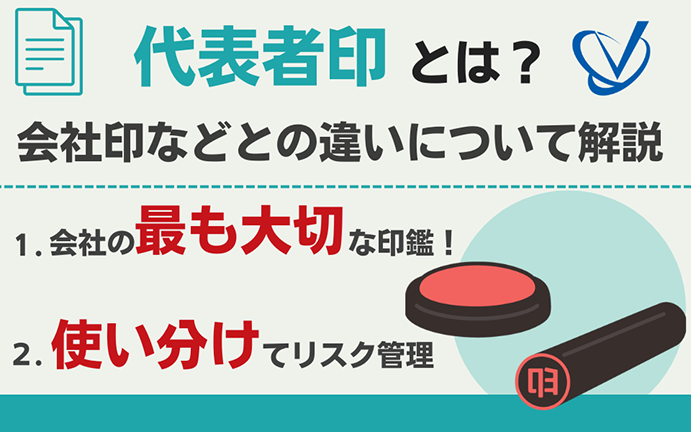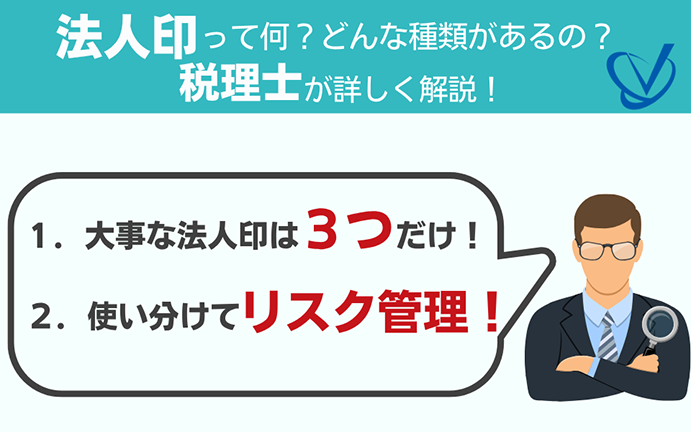最終更新日:2025/5/9
3月決算とは?詳しい時期・やること・3月決算にするべき会社などについて解説

ベンチャーサポート税理士法人 大阪オフィス代表税理士。
近畿税理士会 北支部所属(登録番号:121535)
1977年生まれ、奈良県奈良市出身。
起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネルを運営。
PROFILE:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_writing/#p-mori
YouTube:会社設立サポートチャンネル【税理士 森健太郎】
書籍:プロが教える! 失敗しない起業・会社設立のすべて (COSMIC MOOK) ムック
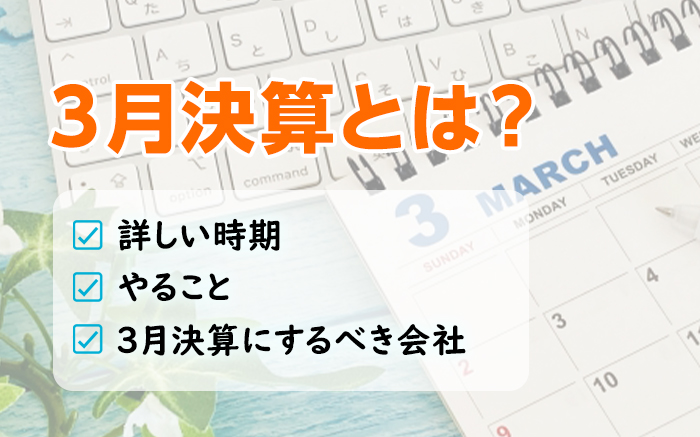
日本では、決算月の中でも、とくに3月決算という言葉が有名です。
決算が何かはよく知らないけれど、3月決算というのは聞いたことがあるという人もいるのではないでしょうか。
事業年度を決めるうえで、3月決算にするかどうかは会社の通常業務や会計に大きな影響を与えます。
今回はなぜ日本には3月決算が多いのか、そもそも3月決算とは何かなどについて詳しく解説します。
3月決算のメリットやデメリット、具体的にどのような企業が3月決算に向いているのかについても触れますので、会社設立や決算月の変更を考えている人は、ぜひこの記事を参考にしてください。
目次
3月決算とは?することや詳しい時期について
会社が決算を行うとき、対象となる一定期間のことを事業年度と呼びます。
法人は自身の事業年度を、1年を超えない範囲で自由に決めることができます。
そして事業年度の最後にあたる月を決算月(決算期)と呼びます。
では3月決算とは、具体的にどのようなことを指し、何をするのでしょうか。
3月決算とは事業年度の最後の月が3月のこと
3月決算とは、事業年度を4月1日~3月31日とすること、つまり3月を決算月とすることを指します。
日本はとくに3月決算が多く、令和4年の国税庁の発表によれば、法人全体で見ると18%ほど、大企業に限定すると50%ほどが3月決算を採用しています。
実際に3月に行うこと
3月決算はその名前から、そのまま3月に決算を全て完結させることだと、よく勘違いされます。
しかし、実際は決算が本格的に行われるのは4月以降がほとんどです。
なぜなら決算では、3月を含めた事業年度中の損益をまとめて決算書を作成する必要があるからです。
すべてのデータがそろってからのほうが決算しやすいので、3月中は棚卸しなどの決算に向けた準備を進めるだけに留める企業も珍しくありません。
大企業に関しては事業年度の移り変わりを重視し、3月中にできる限りの決算をすでに終わらせておくといった場合もあるのですが、中小企業の多くは4月以降に決算を行うことになります。
3月以降のほうが忙しくなりやすい
決算では貸借対照表や損益計算書を作成して、それらを元に支払うべき法人税や消費税が算出されます。
それらの税金の納付期限は決算月の末日(決算日)から2カ月以内のため、3月決算の場合は5月31日までに納税しなくてはいけません。
つまり3月決算の会社は、4~5月中に会計業務を終わらせ、滞りなく納税しないといけないため、その時期がとくに忙しくなりやすいのです。
日本で3月決算が多い理由
慣例として3月を決算月としている法人も少なくありませんが、実際に3月決算にはメリットとなりうる要素があります。
大まかには以下の3つが、3月決算が多い理由です。
- 国や自治体の会計年度に合わせるため
- 税制改正のタイミングに合わせるため
- 新卒採用する学生の卒業月に合わせるため
国や自治体の会計年度に合わせるため
国や自治体にも、会計年度と呼ばれる4月1日~3月31日の括りが存在します。
公的機関はこの期間に合わせて予算の計上や消化を進め、多くの事業を民間に発注します。
これらを請け負う法人は、事業年度を3月決算にして会計年度と合わせることで、事業運営をスムーズに進められるのです。
またそれらの民間企業と取引のある企業も、同じように決算月を合わせたほうが都合がよくなります。
そのため、結果的に3月決算の企業が連鎖して増えていくのです。
税制改正のタイミングに合わせるため
税制改正などの決算に関わる法改正も、行政の会計期間に合わせた4月1日から適用されることがよくあります。
このタイミングが事業年度の途中だった場合、税制の変更に伴ってそれ以降の会計処理も変わってしまい、決算業務が煩雑になってしまいます。
そうした事態を避けるために、4月1日が事業開始日となる3月決算を選ぶ法人も多いです。
新卒採用する学生の卒業月に合わせるため
新卒で採用した社員は、高校や大学の卒業月である3月以降の4月に受け入れることになります。
社内でもそれに合わせて4月1日付けで人事異動を行うことがよくあります。
3月決算にすると、そうしたスケジュールに沿って4月からの業務がよりスムーズに行えるようになります。また、人事異動の前後のデータ比較もやりやすくなるというメリットもあります。
3月決算のデメリットについて
3月決算にはメリットもありますが、無視できないデメリットもあります。
とくに大きなデメリットは、日本に3月決算の企業が多い分、それらの企業の決算を補助する税理士も3月にクライアントからの相談が増加し、スケジュールを調整しにくいという点です。
3月は個人事業主の確定申告の時期とも重なるため、税理士にとっては1年の中でもとくに忙しい時期になります。
決算は税金や経営状況を計るための大事なイベントなので、じっくりと税理士と話し合いたいという場合は、3月以外の時期のほうが税理士との時間をすり合わせしやすいでしょう。
また、企業自体にとっても、3月決算は実際の決算を行う時期とゴールデンウィークなどが重なり、日々の事務作業の負担が増してしまう可能性もあります。
決算時期と長期休暇があるタイミングをずらすことで、作業日数不足によるミスや残業を減らせるといった効果も期待できます。
3月決算にしたほうがいい会社とは
3月決算には、税理士とのスケジュールが合わせにくいというデメリットがあるものの、明確なメリットもあります。
3月決算にするかどうかは、自身の事業内容などと照らし合わせたうえで判断しなくてはいけません。
具体的にどのような会社が3月決算に向いているのか、解説します。
官公庁や自治体との業務がある
メリットについての章でも紹介したように、官公庁や自治体などと連携して業務を行う会社は、3月決算に向いています。
国の会計年度である4月1日~3月31日に、自分の会社の事業年度を合わせることで、関係各庁とのスケジュールも合わせやすく、業務をスムーズに行うことができます。
3月以降に売上が伸びやすい
3月以降に売上が伸びやすい業種も、3月決算に向いています。
大きな理由としては、企業は決算の最終日から2カ月以内に法人税や消費税などの税金を払わないといけないからです。
決算月の設定次第で、こうした税の納付時期をコントロールできるので、売上が伸びて資産に余裕があるタイミングと合わせれば、社内のキャッシュフローが安定します。
逆に3月以降にあまり売上が見込めない業種は、3月決算の場合に資金繰りが厳しくなる可能性があります。
会社のキャッシュフローを把握したうえで、余裕のある時期に納税を行えるように決算月を設定しましょう。
3月が繁忙期から遠い
繁忙期と決算業務が重なってしまうと、社員への負担が増して普段の業務が滞ったり、ミスが起きやすくなります。
そのため、3月が繁忙期となる会社は、別の時期を決算月にしたほうが効率的に決算を行うことができるでしょう。
また、繁忙期で売上が多くなると、それだけ利益が計上されることになり、法人税の税率も上がりやすくなります。
このとき、繁忙期と決算月が離れていれば、決算までになんらかの節税対策を施せます。
しかしこの2つが重なっていると、節税対策にかける時間的余裕がなくなり、有効な手を打てないまま高額な法人税を納める事態に陥ってしまう危険性があります。
決算月を決める際は、自分の事業の繁忙期と離れているかどうかも考慮しましょう。
決算月は変更もできる
決算月は会社設立時に定めたあとも、自社都合で自由に変更することができます。
法務局への変更登記申請なども不要なので、手続きも比較的簡単です。
会社設立時に3月決算にしたものの、繁忙期と重なってしまって手が回らなかったり、ほかの月のほうがメリットが大きいと感じた際には、決算月の変更を検討してみましょう。
ただし決算月の変更には、その年の決算業務が煩雑になったり正確なデータを取りにくくなるといったデメリットもあります。
さらに、あまり頻繁に行うと、会社の業績が良くないのかと金融機関などに疑惑を持たれる可能性もあります。
そうした事態にならないよう、決算月の変更は税理士などと相談の上、適切なタイミングで行うようにしましょう。
まとめ
3月決算とは決算月を3月にすることであり、実際の決算業務は主に4月以降に行われることが多くなります。
3月決算は国の会計年度や税制改正のタイミングと合っているため、企業にとってもさまざまなメリットがあります。
しかし一方で、同じように3月決算を採用する企業が多いため税理士を確保しにくいといったデメリットもあります。
決算月はあとから変更することもできますが、繁忙期や売上の多い時期などを会社設立時から予想して、自身の事業に合った月を決算月にしたほうが、効率的でスムーズなスタートを切れるでしょう。
3月決算にするべきか悩んだら税理士などに相談しよう
「会社を設立したばかりで売上などの予想が立てられず、どの月を決算月にすればいいのかわからない」「一度3月決算にしたものの、別の月に変更したい」という場合には、税理士などに相談してみるといいでしょう。
自身の事業に合った決算月がいつなのか、決算月変更の手続きをどう進めるかなど、決算月に関してさまざまなアドバイスを受けることができます。
ベンチャーサポート税理士法人では、会社設立・運営に関する無料相談を実施しています。
税理士だけでなく行政書士や司法書士、社労士も在籍しているためワンストップで相談が可能です。
レスポンスの速さにも定評があるため、初めての方もお気軽にご相談ください。