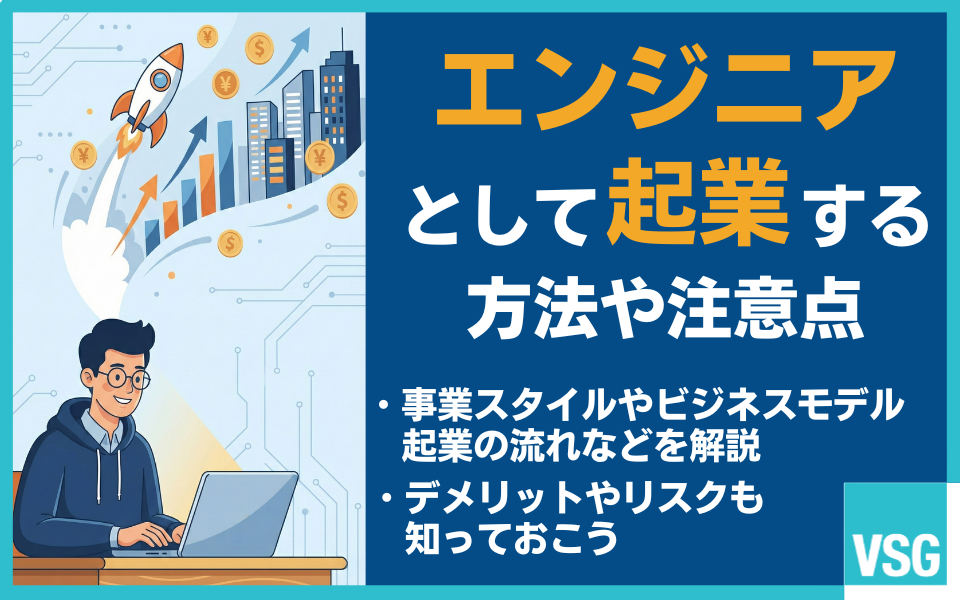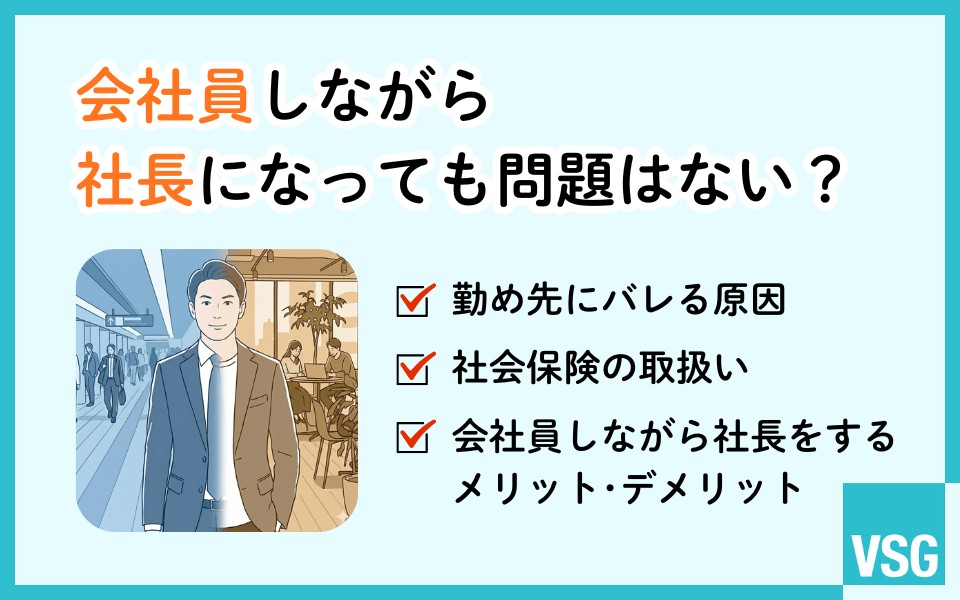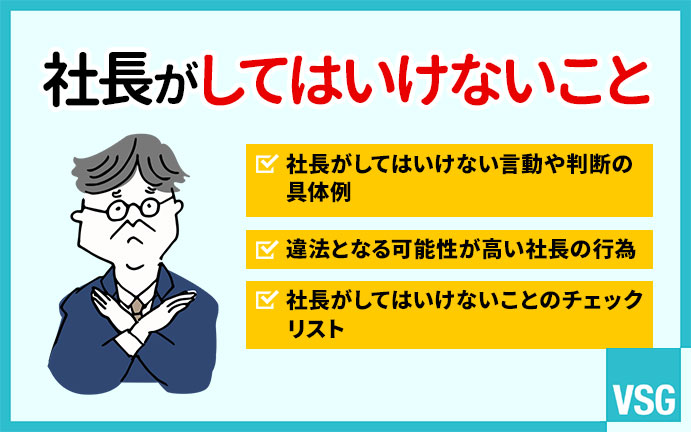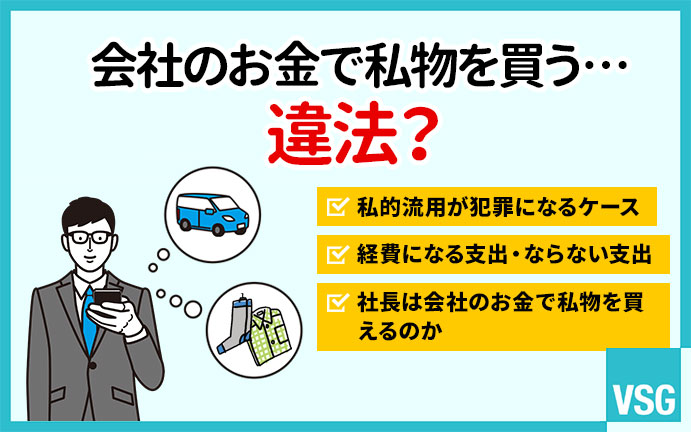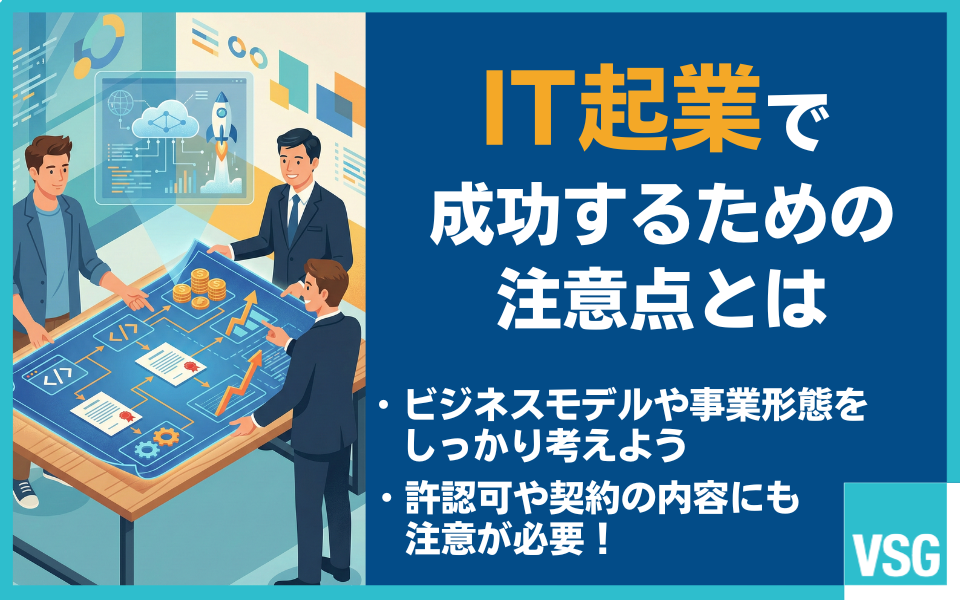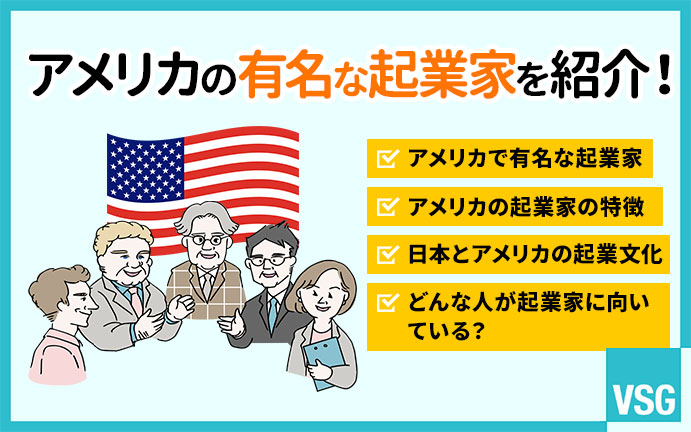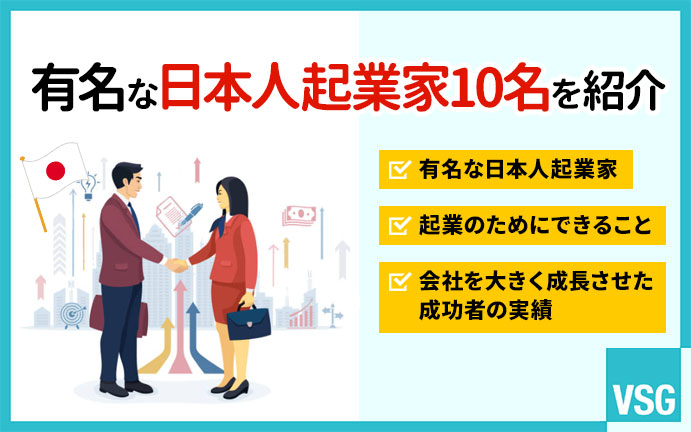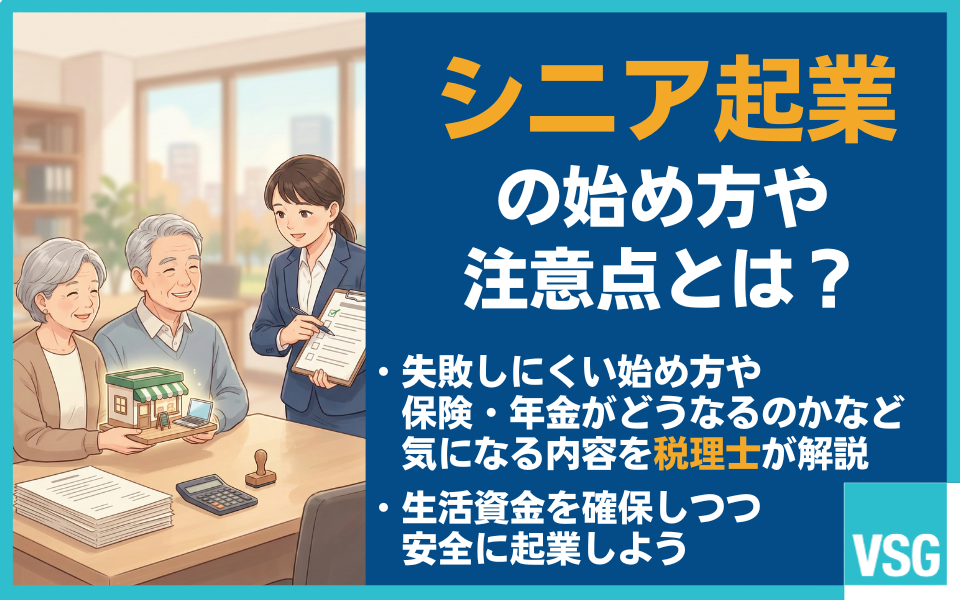最終更新日:2025/10/29
代表者印(丸印)とは?会社印との違いや使用場面・登録方法などを解説

ベンチャーサポート税理士法人 大阪オフィス代表税理士。
近畿税理士会 北支部所属(登録番号:121535)
1977年生まれ、奈良県奈良市出身。
起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネルを運営。
PROFILE:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_writing/#p-mori
YouTube:会社設立サポートチャンネル【税理士 森健太郎】
書籍:プロが教える! 失敗しない起業・会社設立のすべて (COSMIC MOOK) ムック
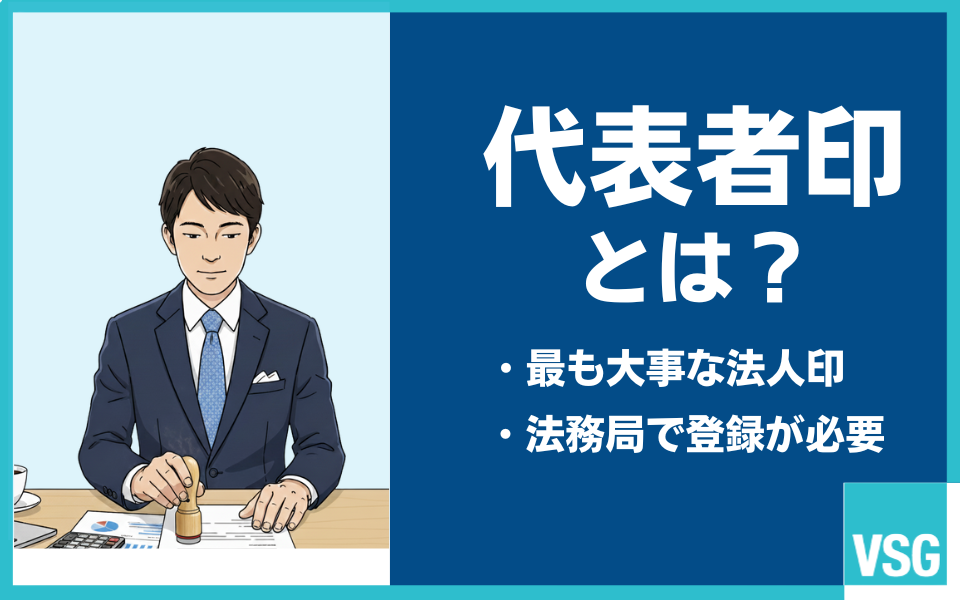
会社を設立する際に作る法人印の1つに、会社代表者印(以下、代表者印)があります。
代表者印は、法務局に印影を登録する唯一の印鑑です。
会社を運営するうえでとても重要な役割を持つ代表者印ですが、具体的にどのような場面で使えばいいのでしょうか?
この記事では、代表者印の使用場面や登録方法などについて解説します。
電子印鑑で代用できるのか、紛失や破損したときはどうするべきかなど、実際の代表者印の運用において気になる点も、税理士が詳しく解説します。
代表者印をどのように使えばいいのか悩んでいたり、ほかの印鑑との違いがわからないという人は、ぜひご覧ください。


目次
【要点まとめ】代表者印の全体像
代表者印とは法務局で登録を行った、法人格の意思を外部に証明するための印鑑です。
法人実印とも呼ばれ、会社の最も重要な印鑑と位置付けられます。
法人口座の開設、不動産取引、融資契約、官公庁への重要書類の提出など、会社の経営や財産に重大な影響を及ぼす場面に限定して使用します。
会社を設立する時点では、オンライン登記を行うのであれば代表者印はなくても問題ありません。
しかしその後の実務も考えると、設立時点で代表者印は作成しておき、法務局での登録も済ませておくべきでしょう。
近年は、電子印鑑を代表者印の代わりに使用できる場面も増えてきました。
しかし未だに実際の代表者印の押印と、印鑑証明書の提示が求められることも数多くあります。
また、代表者印の代わりとして利用できるのは法律が定める要件を満たした電子署名であり、代表者印の印影データは不用意に公開するとセキュリティ上のリスクになります。
代表者印とは
代表者印とは、会社の本店所在地を管轄する法務局で登録を行った印鑑のことです。
個人における「実印」は、市区町村役場に登録することで法的な本人証明力を持ちます。
それと同じように、法人は代表者印を法務局に登録することで、その印鑑が法人の公式な意思を表明するものであることを公的に証明できます。
重要な契約書に代表者印が押されている場合、その契約は当事者である法人の正式な意思に基づいて締結されたものであると、ほかの印鑑よりもより強固に推定されます。
万が一、契約内容を巡って争いが生じた際には、代表者印の押印が契約の正当性を証明する極めて有力な証拠となります。
代表者印は会社実印や社長印、丸印とも呼ばれる
その重要性から、代表者印は会社にとっての実印として「会社実印」と呼ばれることもあります。
また、一般的に社長の立場にある人が管理し使用する印鑑であることから「社長印」、円柱状の形状から「丸印」とも呼ばれます。
これらはすべて、代表者印のことを指します。
このように代表者印には多くの呼び方があるので、ほかの印鑑と間違えないように注意しましょう。
代表者印を使用する場面
会社の代表者印は、法的に最も重要で、拘束力のある意思決定をするときに使います。
個人の「実印」の法人版と考えると分かりやすいです。
代表者印の押印では、多くの場合で、法務局が発行する印鑑証明書もセットで提出を求められます。
印鑑証明書は代表者印の印影が本物であることを証明するための書類です。
銀行印・角印との使い分け
会社の印鑑(法人印)は、その権限のおよぶ範囲によって、代表者印と銀行印、角印(会社印)の3種類に分類できます。
それぞれの印鑑の権限の範囲や用途については、以下の表を確認してください。
| 印鑑の種類 | 登録先 | 権限の範囲 | 用途 |
|---|---|---|---|
| 代表者印 | 法務局 | 会社の法的な意思決定全般 最も広範で強力な権限を持つ |
会社設立登記、代表取締役の変更登記、不動産売買契約など、会社の根幹に関わる法的手続きや重要契約 |
| 銀行印 | 銀行などの金融機関 | 登録した金融機関との、会社の財産(預金)に関する取引 | 銀行口座の開設、預金の引き出し、手形・小切手の振り出し、融資の申し込みなど、資金管理に直結する業務 |
| 角印(会社印) | なし | 会社の日常的な業務での書類の承認・確認 法的な強制力は持たない |
請求書、見積書、領収書、納品書など、日常的に発行される書類への押印 |
このように、代表者印とそのほかの銀行印、角印は、用途が明確に分かれています。
これはそれぞれの印鑑に権限の範囲を振り分けて運用することで、紛失や偽造、盗難のリスクを軽減するためです。
法人印に関しては、以下の記事でより詳しく解説しています。
オンライン登記なら代表者印は不要なのか
以前は書面での会社設立の登記申請において、法務局で登録済みの代表者印の押印が必須でした。
しかし2021年の商業登記規則の改正によって、オンラインで登記申請を行う場合、印鑑を提出せずにマイナンバーカードなどの個人証明で手続きを行えるようになりました。
参考:商業登記規則が改正され,オンライン申請がより便利になりました(令和3年2月15日から)
これにより、現在はオンラインで会社設立登記を行うのであれば、必ずしも代表者印を作成する必要はありません。
しかしこの法改正は、あくまで行政手続きのオンライン化を推進する一環であり、ビジネスの現場における代表者印の重要性が失われたわけではありません。
不動産取引や金融機関との融資契約など、社会的な信用が求められる重要な取引の多くでは、依然として代表者印の押印と印鑑証明書の添付が必要とされるケースが大多数です。
こうした現状を考慮すると、代表者印の作成や登録は会社設立時点では不要なものの、その後の運営を考えると結局は必須と言えるでしょう。
会社設立で使用する印鑑については、以下の記事でより詳しく解説しています。
法務局で登録する際の代表者印の規定とは
代表者印を法務局で登録する際には、いくつかの規定をクリアした印鑑でなければいけません。
具体的にどのような規定があるのかについて、見ていきましょう。
代表者印のサイズ
代表者印のサイズは商業登記規則によって明確に定められており、「印影が1cmから3cmの正方形に収まる大きさであること」が求められます。
この範囲内の大きさであれば問題なく代表者印として登録できますが、実務上の代表者印のサイズは18mmまたは21mmが最も一般的です。
通常の印鑑の多くはサイズが15mm前後なので、代表者印はそれよりも一回り大きいサイズとなっています。
これは、代表者印には会社名と役職名の両方を刻印するので、印鑑のサイズが小さすぎると文字が潰れて見えにくくなってしまうためです。
また、個人実印など通常の印鑑よりもサイズを大きくすることで、パッと見たときに代表者印であるとわかりやすく、かつ重要な印鑑としての威厳を持たせられるといった理由もあります。
代表者印の刻印
代表者印の印影は、一般的に「二重丸」と呼ばれるデザインで構成されます。

外側の枠には、会社の正式名称(商号)を刻印します。頂点には読み始めの位置がわかりやすいように、「中黒」と呼ばれる点が配置されます。
内側の枠には、代表者の役職名を刻印します。
この刻印名は株式会社の場合は「代表取締役印」、合同会社の場合は「代表社員之印」となるのが一般的です。
代表者印という名前から誤解されることもありますが、印面に代表者個人の名前を刻印する必要はありません。
代表者印は、その役職に就いている個人の印鑑ではなく、法人そのものの印鑑です。
そのため、役職名のみを刻印しておくことで、将来的に代表者が交代した場合でも、印鑑を作り直すことなく継続して使用が可能です 。
代表者印の作成方法:素材の選び方から書体まで
代表者印はその重要性から、印面が変形しやすいゴム印や、シャチハタと呼ばれるような浸透印は、基本的に登録が認められません。
チタンや水牛角、柘(つげ)などの硬質かつ経年変化しにくい素材が用いられます。
また、代表者印の書体に関しては、単なるデザインだけでなく、偽造防止というセキュリティの面からも検討しましょう。
多くの代表者印では、篆書体(てんしょたい)という書体が用いられます。

篆書体は日常的に使う文字とは大きく異なる字形のため、判読が極めて困難です。
この可読性の低さが、第三者による印影の偽造を困難にし、極めて高いセキュリティ性を発揮します 。
また、篆書体は、秦の始皇帝が中国を統一した際、国家の権威を示すために公式書体として定めた2000年以上の歴史を持つ書体です。
日本のパスポートや紙幣に押される印にもこの篆書体が使われており、歴史的に「公的な証明」と「権威」を象徴する書体として使用されてきたという背景があります。
そうした理由から、会社にとっての権威の象徴でもある代表者印には、篆書体が用いられることが多いのです。
この篆書体から派生した書体として、吉相体・印相体(きっそうたい・いんそうたい)というものもあります。

文字が印鑑の枠に接する、八方に広がるようなデザインが大きな特徴です。
篆書体と同様に可読性が低いため偽造防止効果が高く、かつ文字と外枠が接しているため、落下などの衝撃にも強いとされています。
書体に関しては、特に規定などは存在しないため、事業者自身が自由に選択できます。
しかしセキュリティ面を考慮すれば、これらの複雑で偽造されにくいとされる書体を選ぶことを推奨します。
法務局での代表者印の登録方法
代表者印を法務局で登録するためには、「印鑑(改印)届書」を提出します。
これにより、代表者印は正式な効力を持ちます。
また、その代表者印が確かに登録済みであると証明するために「印鑑カード交付申請書」を提出して印鑑カードを取得する必要があります。
この印鑑カードを提示することで「印鑑証明書」が発行できます。
それぞれの詳しい手続き方法について解説します。
印鑑(改印)届書の作成方法
印鑑(改印)届書は法務局の窓口で入手するほか、Webサイトからもダウンロードできます。
書類の作成では、市区町村に登録済みの個人実印の押印と、3カ月以内に発行した個人実印の印鑑証明書が必要です。
また、印鑑(改印)届書には会社法人等番号を記載する欄があります。
これは登記情報の一部として法人ごとに割り振られる、12桁の番号です。
会社法人等番号は、「法人番号公表サイト」で検索できる13桁の番号から、先頭の1桁を除くことで確認できます。
ただしこの欄への記入はあくまで任意であり、空欄でも問題ありません。
印鑑(改印)届書の詳細な書き方については、法務局が公開しているPDFからも確認できます。
参考:株式会社の場合(印鑑提出者本人による届出) 印鑑(改印)届書|法務局(PDF)
また、登記・供託オンライン申請システムを利用すれば、オンラインで代表者印の登録を行うこともできます。
「印鑑カード交付申請書」の作成方法
代表者印の登録後、その印鑑が確かに登録済みのものであると証明するための「印鑑証明書」を発行するために、「印鑑カード」という磁気カードが必要になります。
印鑑カード交付申請書は印鑑(改印)届書と同様に、法務局の窓口またはWebサイトで入手可能です。
申請書に必要事項を記入し、登録した会社実印を押印して提出します 。
印鑑カード交付申請書は、現在はオンラインでの提出ができません。
法務局の窓口か、郵送によって提出しましょう。
ただし、郵送の場合は通常1週間ほどの時間がかかります。
窓口提出であれば原則即日、数十分ほどで印鑑カードが発行されるので、特別な理由がなければ法務局で直接手続きを行ったほうがいいでしょう。
印鑑証明書の発行方法
印鑑カードを取得したあとは、改めて「印鑑証明書交付申請書」を作成し、印鑑証明書を請求しましょう。
法務局の窓口に設置されている証明書発行請求機を利用すれば、申請書を事前に記入することなく、タッチパネル操作で手続きを進めることもできます 。
また、法務省の提供する「申請用総合ソフト」を利用すれば、オンラインでの申請も可能です。
印鑑証明書の取得方法については、以下の記事でより詳しく解説しています。
代表者印を紛失・破損したときの手続き
代表者印を紛失した場合、まずは警察に届出を行いましょう。
最寄りの警察署または交番に遺失届(盗難の場合は盗難届)を提出してください。
この際に警察から発行される受理番号は、このあとの印鑑変更手続きで必要となる場合もあるので、しっかりと控えておきましょう。
ただし代表者印を破損した場合は、警察への届出は不要です。
すぐに新しい代表者印を用意できるのであれば、法務局へ「印鑑(改印)届書」を提出することで、旧印は届出印としての効力を失い、新しい印影が照合対象として登録されます。
しかし多くの場合では、代表者印を用意する前に多少の時間がかかるはずです。
セキュリティ上のリスクを考えれば、まずは法務局に「印鑑・印鑑カード廃止届書」を提出して、旧印の効力を失効させておきましょう。
その後、新しい代表者印が準備できた段階で改めて「印鑑(改印)届書」を提出することで、安全に手元に有効な代表者印を確保できます。
また、印鑑証明書の発行に必要な「印鑑カード」を紛失した場合も、同様に法務局でカードの廃止と再交付の手続きが必要です 。
「電子印鑑」を代表者印にできる?
一般的な電子印鑑のなかでも、法律が定める要件を満たした「電子署名」であれば、多くの契約において代表者印の押印と同等の法的効力を持つことが認められています。
電子署名とは、電子文書に付与できる「この文章はたしかにこの人が作ったもので、途中で手を加えられていない」ということを証明する署名データのことです。
本人による適切な電子署名が行われた電子文書は、真正に成立したものと推定すると電子署名法で定められています。
参考:電子署名及び認証業務に関する法律 第三条|e-Gov 法令検索
ここで注意したいのが、電子署名はあくまでPDFなどの電子文書に添付する情報であり、印影データなどの目に見えるものではないという点です。
つまり、電子契約の世界では目に見える「印影」ではなく、目には見えない暗号技術に基づいた「電子署名データ」が、契約の正当性を法的に証明するのです。
2020年に政府が公表した見解でも、押印は契約成立の必須要件ではないことが再確認されています 。
代表者印の印影データを利用してはいけない
電子契約の普及に伴い、多くの人がつい直感的に行ってしまう、極めて危険な行為があります。
それは、「代表者印の印影をスキャナで読み取り、画像データとして電子文書(PDFなど)に貼り付ける」という行為です。
こうした印影データの流用は、社内文書用の角印の印影データなどであれば大きな問題はありませんが、代表者印で行ってしまうと重大なリスクを背負うことになります。
印影データは真正性の立証が難しい
代表者印の印影データをPDFなどに貼り付けたとしても、その印影は法的な証拠になりません。
単なる印影の画像データはコピーや改ざんが容易で、本人による作成を技術的に保証できません。
そのため、それを貼り付けただけの電子文書には、電子署名法3条における「真正に成立したもの」との推定が及ばず、証拠力が弱いと見なされます。
電子印鑑のうち、契約の有効性が担保されるのは、あくまで暗号技術に裏付けられた電子署名だけです。
セキュリティ上で深刻なリスクとなってしまう
会社の法的権限の象徴である代表者印の鮮明な印影データは、会社のマスターキーともいえる重要な情報です。
これを電子ファイルに貼り付け、取引先などに送信する行為は、会社のセキュリティにおいて非常に深刻なリスクとなります。
現代の技術を使えば、その画像データから物理的な印鑑を偽造することは決して難しくありません 。
偽造された代表者印によって、不動産の不正売却や身に覚えのない契約といった、壊滅的な被害を被る可能性もあります。


代表者印の印影は決して不用意に公開しないようにしましょう。
代表者印についてよくある質問
ここでは代表者印について多くの人が疑問に思う点、実務上での注意すべき点などについて解説します。
オンライン登記で代表者印の印鑑届書を提出しない場合にデメリットはあるのか
オンラインでの会社設立登記では、代表者印の印鑑届書の提出は任意です。
しかし印鑑の届出を行わず、正式な効力を持つ代表者印を作成しないままでいると、設立後の会社運営において複数の重大なデメリットが生じます。
たとえば、大半の金融機関での法人口座開設では、本人確認書類として印鑑証明書の原本の提出を必須としています。
日本政策金融公庫や民間金融機関から融資を受ける際にも、契約の締結において印鑑証明書の提出が求められます。
このほかにも不動産取引や社用車の購入と登録の際など、さまざまな場面で代表者印の押印や印鑑証明書の提示が求められます。
日本国内の商慣習では、法務局が発行する代表者印の印鑑証明書が「法人の実在」と「代表者の正当な権限」を証明する、最も信頼性の高い公的書類として長年にわたり利用されてきました。
多くの企業や金融機関の社内規程や業務フローは、この慣習を前提に構築されています。
設立後の実務的な支障というデメリットを回避するためにも、登記申請と印鑑の届出はセットで行いましょう。
代表者印と銀行印を兼用してもいいのか
代表者印と銀行印を物理的に1つの印鑑で兼用することは、法律上は可能です。
しかし、リスクマネジメントの観点から見ると、こうした運用は推奨されません。
兼用している印鑑の紛失や盗難があった場合、第三者によって会社の意思決定(契約締結)と財産の処分(預金引き出し)の両方が同時に可能となります。
これにより、不正な契約を締結されたうえ、その支払いを会社の口座から不正に引き出されるといった、重大な損害が発生する可能性があります。
また、頻繁に利用することで摩耗や破損するリスクも高くなり、金融機関や取引先から「健全な印鑑の運用を行っていない」として信用を失う要因にもなります。
代表者印と銀行印は必ず別々に作成し、可能であれば別々の場所に保管するなどして、リスクを抑えた管理を徹底しましょう。
代表者が複数いる場合は、代表者印も複数作れるのか
代表者が複数いる会社では、各代表者ごとに「代表者印(会社実印)」を登録できます。
最低でも1名が届出していれば登記実務上は問題ありませんが、代表者全員が届出することも可能です。
追加登録の手続きでは、追加する代表者ごとに印鑑(改印)届書と、個人の印鑑証明書を所轄法務局へ提出します。
ただし、同一の印鑑を複数の代表者で共用して登録することはできません。
代表者印を作り直さないといけないのはどんなときか
代表者印の作り直しが必要になるのは、主に以下のような場面です。
- 紛失や盗難があった場合
- 印面が欠けたり摩耗した場合
- 会社の商号を変更した場合
- 会社の形態(株式会社や合同会社など)を変更した場合
このように、物理的に代表者印を作り直さなければならない場合以外にも、刻印された内容に変更があった場合に、代表者印の作り直しが必要になります。
格安で販売している業者を利用しても大丈夫なのか
通販ショップでは、1本1,000円ほどで代表者印などの法人印を販売しているショップもあります。
これは印鑑の専門業者に頼むよりも大幅に安い値段です。
格安業者を利用したとしても、法務局での印鑑登録や実際の運用で特に問題になることはありません。
しかし、代表者印はその重要性から、印面の仕上げやデータ管理がしっかりした業者かどうかについては気をつけるべきです。
格安で印鑑を販売している業者の多くは、印面をレーザーによる機械彫りにしていることが多く、複製可能なフォントを使用していることもあります。
この場合、複製が容易となるため、代表者印などの重要な印鑑で使用するにはリスクが大きいです。
また、印面のデータを業者が削除せずに保存している場合、その管理がずさんだと、データの流出によって印鑑の偽造が行われる可能性もあります。
より安全に代表者印を作成したいのであれば、機械彫りではなく手彫りで印鑑を作成し、かつデータの保存期間や削除方針について厳格に取り決めがなされている業者を選ぶとよいでしょう。
代表者印の使い方や管理で悩んだら税理士に相談しよう
代表者印は、その会社の意思表示としての役割を持つ、極めて重要な印鑑です。
そのため、日々の管理や使用するタイミングなどは常に気にしておく必要があります。
会社の設立時には法務局での印鑑登録が必要になるうえ、万が一紛失した場合は早急に手続きを行い、既存の印鑑を廃止して新しい代表者印を登録し直さなくてはいけません。
もし代表者印の作成や管理などで疑問や不安がある場合は、税理士などの会社設立の専門家に相談してみてください。
ベンチャーサポート税理士法人では、会社設立・運営に関する無料相談を実施しています。
税理士だけでなく行政書士や司法書士、社労士も在籍しているためワンストップで相談が可能です。
レスポンスの速さにも定評があるため、初めての方もお気軽にご相談ください。
代表者印などの法人印について税理士に相談できることリスト
代表者印などの法人印について、税理士には主に以下のような内容について相談できます。
- 必要な印鑑の種類と役割の整理
- 印鑑の管理方法と内部統制の構築
- 印鑑の紛失・盗難時の対応
- 電子印鑑の導入と電子帳簿保存法への対応
これら以外にも、法人印の使い分けや注意点など、経営のパートナーとしてさまざまな悩みや疑問に対し、適切なアドバイスが可能です。
会社設立や運営でお困りの方は、ぜひお気軽にベンチャーサポートの無料相談までお電話ください。