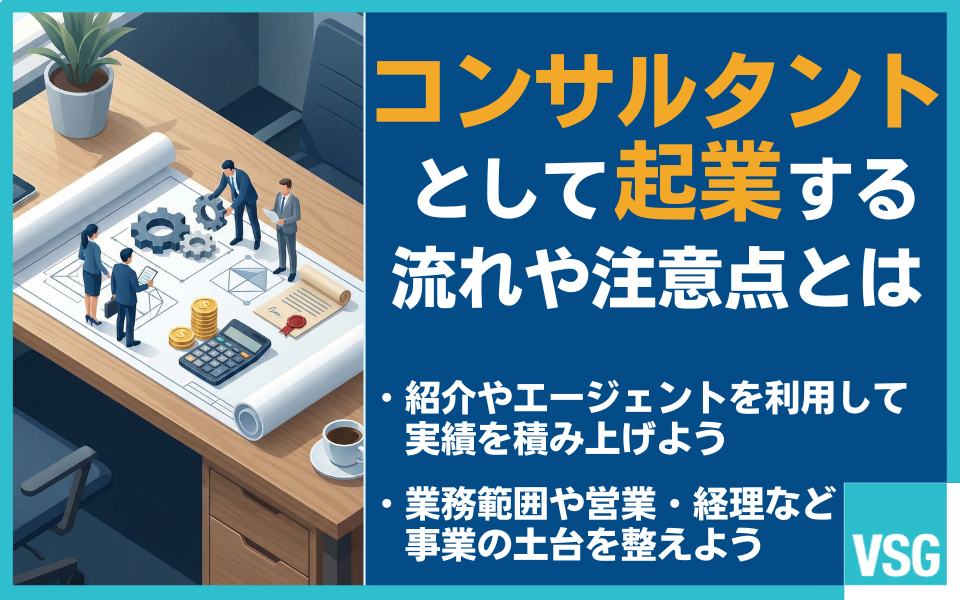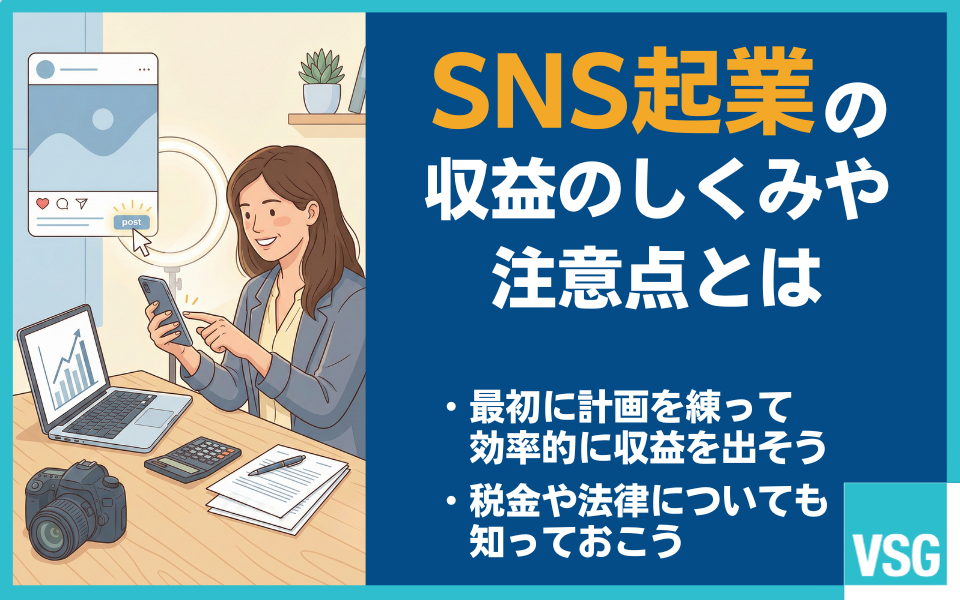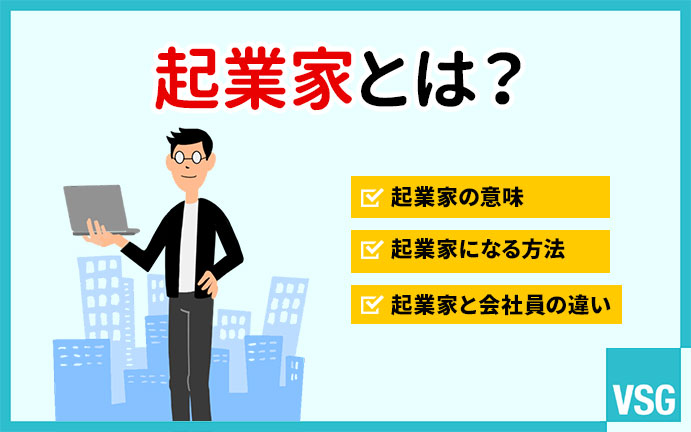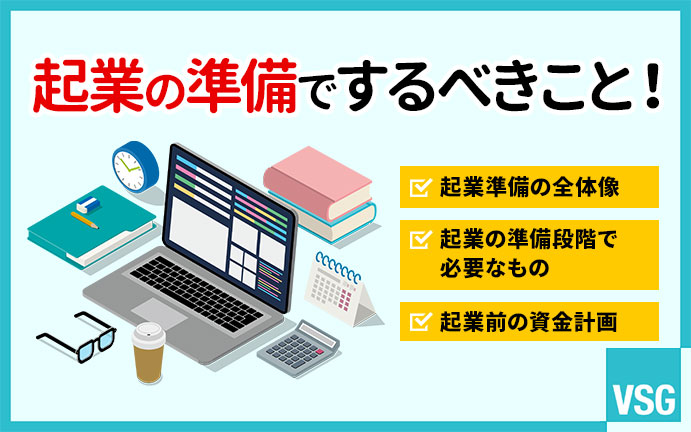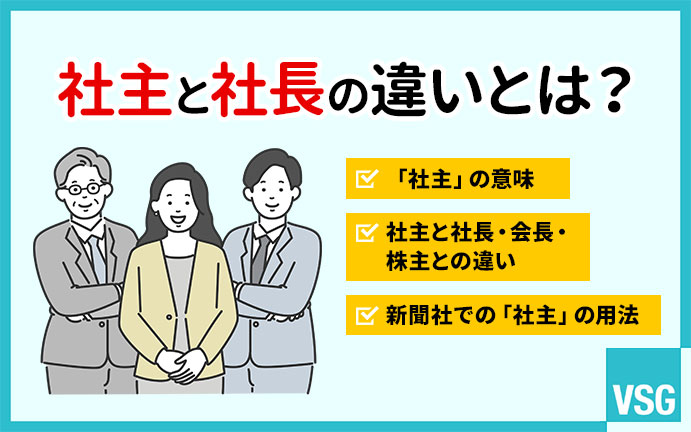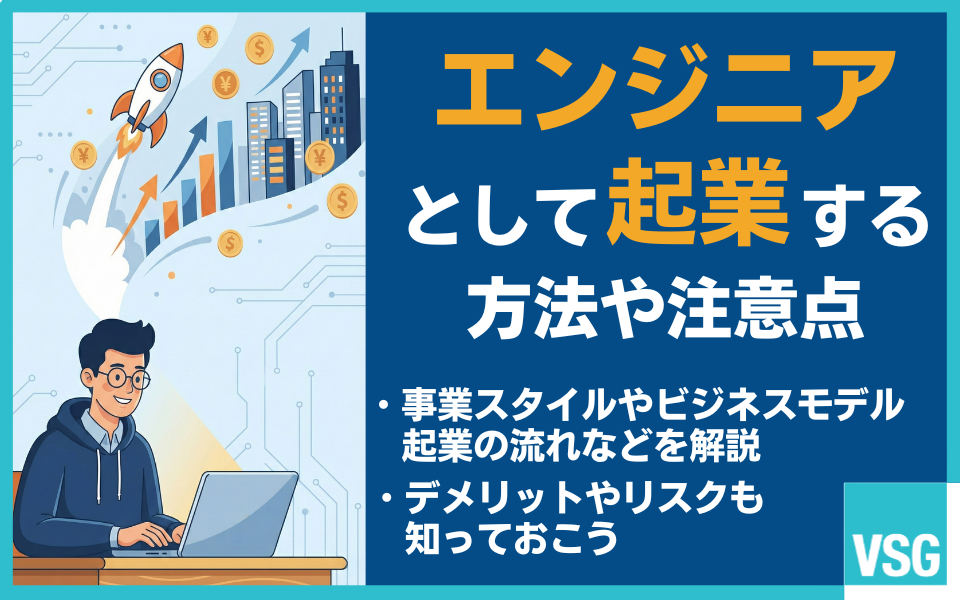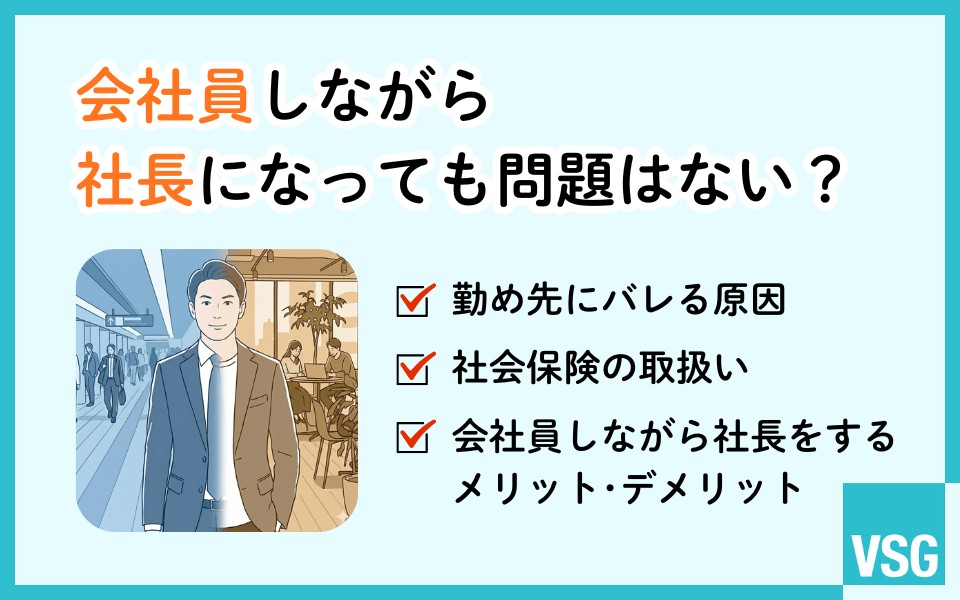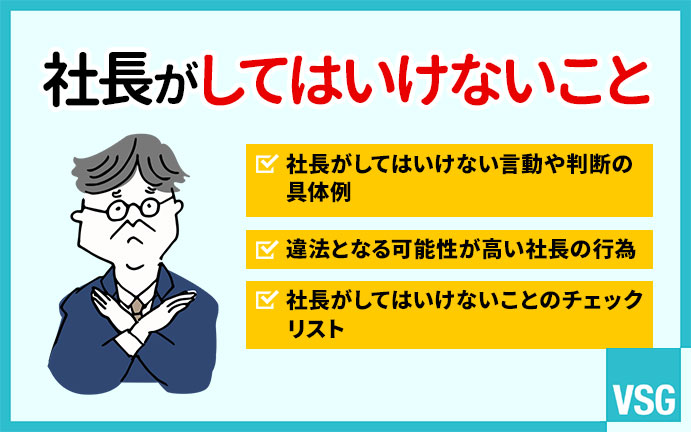最終更新日:2025/10/30
合弁会社と合同会社の違いは?基本的な知識と設立の流れを解説します

ベンチャーサポート税理士法人 大阪オフィス代表税理士。
近畿税理士会 北支部所属(登録番号:121535)
1977年生まれ、奈良県奈良市出身。
起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネルを運営。
PROFILE:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_writing/#p-mori
YouTube:会社設立サポートチャンネル【税理士 森健太郎】
書籍:プロが教える! 失敗しない起業・会社設立のすべて (COSMIC MOOK) ムック
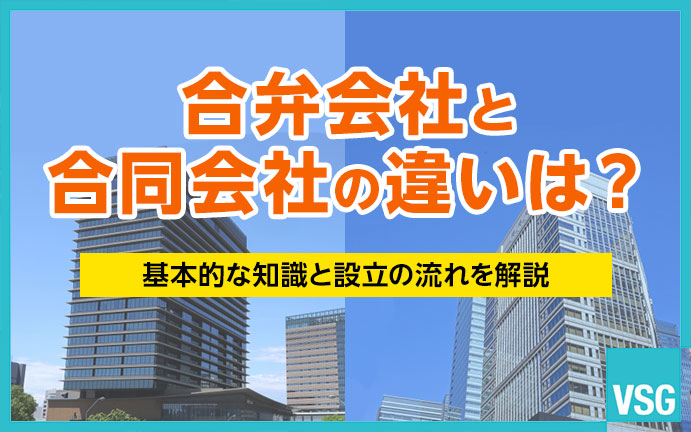
この記事でわかること
- 合弁会社(ジョイント・ベンチャー)と合同会社の違い
- 合弁会社の設立方法や活用事例
- 合弁会社と合同会社の設立時に注意すべきポイント
「合同会社」と「合弁会社」はまったく異なるものです。
合同会社は、会社法で定められた法人形態のひとつであり、個人でも設立が可能な法人組織です。
一方で、合弁会社は複数の企業が共同出資して設立する新会社のことで、株式会社や合同会社といった形式で新しい会社を作ります。こうして設立される会社の総称が合弁会社です。つまり「合弁会社」という法人名は存在しません。
この記事では、合同会社と合弁会社それぞれの仕組みと違い、設立の流れ、代表的な事例、メリット・デメリットなどをわかりやすく解説します。


目次
合弁会社と合同会社の基本
「合弁会社」と「合同会社」は似た言葉ですが、これらはまったく異なるものです。ここでは、合弁会社と合同会社それぞれの基本的な意味と位置付けを整理し、両者の違いを明確にします。
合弁会社(ジョイント・ベンチャー)
合弁会社とは、複数の企業が共同で出資して運営していく法人(会社)のことです。英語では「ジョイント・ベンチャー(Joint Venture)」と呼ばれています。あくまで総称であり、合弁会社と名が付く法人はありません。
合弁会社を作る目的は、複数の企業で設立・運営することで事業リスクや資本負担を分散させつつ、それぞれの得意分野を活かして事業を行うことです。多くの場合は新規事業のために設立されます。技術提携、販路拡大、海外進出など、ひとつの会社では実現が難しい事業戦略のために使われることが一般的です。
合同会社
合同会社は、出資者全員が「有限責任社員」となる法人形態です。「有限責任」とは、万が一、会社が多額の債務を抱えて倒産しても、出資者(社員)は出資した額以上の責任は負わないというものです。
この点は株式会社も同様ですが、株式会社との大きな違いは、出資者自らが経営を行うことができる点です。株式会社では出資者(株主)と経営者が分離されていますが、合同会社では出資者が直接経営を行います。
また、合同会社は設立にかかる費用が安く、手続きも比較的簡便であるため、コストを抑えて会社を設立したいというケースでよく選ばれています。
さらに、出資比率に関係なく、定款で自由に利益分配のルールを定めることができる点も合同会社の特徴です。
合同会社は、自由度が高く、かつ低コストでありながら、会社法上の法人格を持つ法人形態です。個人や家族経営というイメージが強い形態ですが、Amazonなどの大企業でも合同会社を採用している例があります。
合弁会社と合同会社は何が違うのか
合弁会社と合同会社は、まったく別のものです。
合同会社は法人形態の一種です。一方、合弁会社は「企業の共同出資により設立された会社」であり、株式会社や合同会社であることが一般的です。
ここでは、合弁会社と合同会社の違いを整理しましょう。
合同会社は会社法上の「法人」
合同会社は、会社法上の法人形態の一種です。合同会社そのものが法人であり、登記すると法人としての権利能力を持って契約などができるようになります。
対して、合弁会社は法律上の会社類型ではありません。株式会社や合同会社のように「合弁会社〇〇商事」と名乗れるものではないのです。
合弁会社は「複数の企業が共同で設立した法人」の総称です。つまり、合弁会社は合同会社や株式会社といった会社法上の法人形態をとっています。例えば「合弁会社として設立された合同会社〇〇」といった形になるわけです。
設立の目的
合同会社の設立目的は、個人事業の法人化や共同経営、新規事業のための起業などです。設立時の費用や手間が株式会社より少ないため、コストを抑えたいという場合にも選ばれています。
一方、合弁会社は「複数企業による共同事業の実現」という目的で設立されます。例えば、新たな市場への参入、技術協力、海外進出など、出資した企業それぞれが利益を追求するのが目的です。
ひとつの企業ではなく複数の企業が協力して設立・運営するため、戦略的な業務提携のような側面があり、単独経営とは性質が異なります。
子会社や合併・買収・統合との違い
合弁会社は、設立時の出資比率が複数社で分かれています。つまり、ある企業が別の企業を完全子会社とする形態ではなく、複数の会社がひとつの会社の株主や経営者になる「共同所有」の形態です。
また、合併や買収(M&A)、経営統合とも異なっています。合弁会社を設立する場合、それぞれの企業は存続したままで、新たに別の法人を設立する形となります。よって、互いの独立性を維持したまま連携できるのです。
株式会社との違い
合同会社と株式会社は、いずれも会社法上の法人です。合弁会社は会社法上の法人ではありません。
まず、合同会社と株式会社には、組織の構成と意思決定の仕組みに違いがあります。株式会社には株主総会が存在し、取締役に経営が委任されています。一方、合同会社では出資者が直接経営を行います。また、合同会社は株の発行ができません。
そして、合弁会社は複数の法人によって設立された会社の総称です。合弁会社が株式会社である場合も合同会社である場合もあります。株式会社であれば、出資比率に応じて株式が割り当てられ、意思決定は株主総会の決議で行われます。合同会社の場合は、定款で役割分担や利益配分を自由に決めることができます。
そのため、合弁会社を設立する際には、出資者間の関係や事業の性質に応じて株式会社か合同会社かを選択します。
合弁会社のメリットとデメリット
合弁会社は、企業同士の戦略的な連携として、新たな法人を設立するというものです。複数の企業が共同出資するため、経営資源やリスクを分配しながら、新しいビジネスへの参入や技術開発を見込めます。
一方、合弁会社には、デメリットも存在します。ここでは、合弁会社の主なメリットとデメリットを整理して解説します。
合弁会社のメリット
まずは、合弁会社のメリットを見ていきましょう。
複数の企業が出資して協力する合弁会社のメリットは、以下のとおりです。
メリット
- コストの分散
- 海外進出
- 技術やノウハウの結集
- リスクの分散
まず、事業開始に伴う初期費用や運転資金を複数の企業で負担し合うため、一企業あたりの負担は軽減されます。一社でスタートするより資金が集まりやすく、より大規模なプロジェクトに挑戦しやすくなります。
次に、海外の企業とパートナーシップを組めば、現地の商慣習や法制度への対応が容易になります。現地企業との合弁によって事業が展開しやすくなるのです。
また、技術やノウハウの結集も大きなメリットです。それぞれが異なる得意分野を持つ企業が連携することで、技術・販路・人材などを補い合うことができます。協力し合うことで、設立した会社の競争力が高くなります。
最後に、事業リスクの分散です。複数企業で出資するため、万が一の事業不振のリスクを分散させることができます。特に新規分野への進出や、不確実性の高い海外市場では、このメリットが大きくなります。
合弁会社のデメリット
続いて、合弁会社のデメリットについて解説します。以下がその一例です。
デメリット
- 経営方針の不一致
- 意思決定までのスピード感
- 情報漏洩
- 撤退する際の手続きの複雑さ
まず、複数の企業が出資するため、経営をするなかで経営方針の不一致が起きることがあります。特に経営方針や優先順位が異なる企業同士だと、対立が起きてしまうことも珍しくありません。話し合いで解決できずに対立が深刻になると、経営の停滞につながる可能性もあります。
次に、意思決定のプロセスです。合弁会社が重要な意思決定をする際には出資者全員の合意が必要となるため、スピーディーな意思決定ができないこともあります。
続いて、情報漏洩のリスクです。複数の企業が協力する以上、技術やノウハウを共有することになります。つまり相手企業に極めて重要な情報が渡ることもあるわけです。そのため、情報保護に関する契約は正確に結ぶ必要があります。
とはいえ、どんなに慎重に契約していても、一度流出した情報はもとに戻らないため、情報漏洩のリスクは合弁会社のデメリットのなかでも大きなものとなります。
最後に、撤退や解散するときの手続きが複雑になるという点です。共同で出資して設立した会社は、すべての出資者の合意がなければ事業を終了させることができません。設立時には撤退の条件や解散のルールを明確にしておく必要があります。
合弁会社設立の事例
ここでは、実際に設立された(あるいは設立予定の)合弁会社の事例を紹介し、どのような業界・目的で活用されているのかを見ていきます。
海外の企業と合弁会社を設立するケース
まず、SBIホールディングスとCircle社の事例です。
2023年11月に、SBIホールディングスと米国のフィンテック企業・Circle社が、日本市場でのステーブルコイン流通を目的として合弁会社を設立する契約をしました。これは、日本国内での暗号資産の新事業として注目されました。
続いて、JERAとBPです。
2025年8月に、電力事業者のJERAは、その子会社とイギリスの石油大手・BPの事業を統合し、共同出資による合弁会社「JERA Nex bp」を発足しました。JERA Nex bpは洋上風力発電事業を行う会社で、環境対応型ビジネスの国際展開の一例として注目されています。
参考:世界最大級の洋上風力発電事業会社 「JERA Nex bp」の発足について | プレスリリース(2025年) | JERA
国内企業同士で合弁会社を設立するケース
ここからは国内企業によって設立された合弁会社の事例をご紹介します。
まずは、リコーと東芝テックの合弁会社です。
リコーと東芝テックによって2024年7月に発足したETRIAは、業務用プリンタの開発・製造を効率化するために設立されました。各社の技術と販路の統合や商品開発が目的とされています。
続いて、SCSKと日本特殊陶業の事例です。
ITソリューション企業・SCSKと、自動車部品や半導体のメーカーである日本特殊陶業は、2025年度中に合弁会社を設立して営業を開始する予定です。この事例は異業種間の連携として注目されています。
最後に、パナソニックとヤンマーの合弁会社もご紹介します。パナソニックとヤンマーは、ガスヒートポンプエアコン(室外機)の開発製造のための合弁会社を設立する合意をしました。
参考:エトリア株式会社 発足のお知らせ|ETRIA株式会社
参考:SCSK株式会社・日本特殊陶業株式会社による共同プレスリリース(PDF)|SCSK株式会社・日本特殊陶業株式会社
参考:ヤンマーエネルギー - ニュースリリース|ヤンマーホールディングス株式会社
中小企業では
大手企業による合弁会社の設立事例を紹介しましたが、中小企業でも合弁会社を設立する事例はあります。
中小企業の場合でも、合意して共同で出資し、運営するという流れは同様です。ただし、中小企業の場合は大手のような明確なブランド力や資金余力がないケースもあるため、より慎重な準備と信頼関係の構築が必要になります。


合弁会社はどうやって設立するのか
合弁会社の設立は、複数の企業が共同出資をして新しい法人を作るというものです。そのため事前の調整と契約が重要となります。
以下では、合弁会社を設立する一般的な流れを説明します。
パートナー企業との話し合い
合弁会社を設立する際に、最も重要なのは綿密な話し合いです。
まず、出資する企業同士の将来設計や目的が一致しているかを確認しなければなりません。
目的や方向がずれていると、経営に大きな影響を与えることになります。事業の内容や事業展開の方針、出資比率や利益分配のルール、さらには意思決定権についても話し合いをする必要があります。
異なる企業が協力するため、合弁事業では信頼関係が非常に重要です。どちらか一方の負担が大きくなったり、役割分担が不明確になると不信感につながります。そのため、初期段階での相互理解と信頼関係の構築が極めて重要です。
契約書を交わす
合弁会社の設立に向けての話し合いが終了し合意した場合は、合弁契約を締結します。
新会社の出資比率や経営権、利益分配、役員の構成、情報開示のルール、知的財産の扱い、契約期間、解散条件などについて契約を行います。
合弁契約書の作成は、法的な観点からもきわめて重要であるため、弁護士などの専門家に依頼して作成するのが一般的です。
会社法が定める法人形態で会社を設立する
合弁契約を締結したあとは、会社法に基づく法人形態のいずれかで新会社を設立します。この点については、会社の設立手続きを進めていく流れです。
合弁会社はあくまでも合意によって設立された会社であって、それ自体が会社法で定められた会社形態ではありません。したがって、合弁会社の実体は、あくまで「株式会社」や「合同会社」などになります。
設立できる4つの会社の形態
日本で現在新しく設立できる会社の形態は以下の4種類です。
- 株式会社
- 合同会社
- 合資会社
- 合名会社
合弁会社を設立する場合は、これらのいずれかで登記します。ほとんどの場合、株式会社か合同会社が選ばれていて、合資会社や合名会社が設立されるのは稀です。
合弁契約に基づいた合同会社も存在する
合弁会社は、法人形態ではないため合同会社の形式で設立されるケースも存在します。つまり合弁会社として設立された合同会社ということです。
事前に合弁契約を締結し、出資比率や利益分配、役割分担などを明確にして設立します。
合同会社の設立の流れ
続いて、合同会社を設立する基本的な流れを整理します。
定款作成
まずは、定款の作成です。定款とは、会社の基本的なルールを定めた重要書類です。定款には以下のような項目を記載します。
- 商号(会社名)
- 本店所在地
- 事業目的
- 出資額とその割合
- 業務執行社員の氏名および業務範囲 など
合同会社の場合は、公証人の定款認証が不要なため、株式会社よりも手間と費用を軽減できます。
定款認証については以下の記事で解説しています。
登記
定款作成後は、法務局で会社の設立登記をします。
設立登記が完了すると、合同会社としての法人格が発生します。登記後は、税務署や年金事務所への届出が必要となります。
合同会社と合弁会社は別のもの!
合同会社と合弁会社は別物です。
合同会社は、会社法に基づいて設立される法人のひとつで、出資者が経営を行うという会社のことです。一方、合弁会社は、複数の企業が共同で出資して設立する新会社のことです。合弁会社である新会社は、合同会社や株式会社など、会社法上の形態のいずれかとなります。
合同会社は1人でも設立できますが、合弁会社は基本的に複数の企業で共同事業を行う会社です。そのため、合弁会社として新しい会社を作る場合は、契約締結から新会社設立という流れになります。
合弁会社にはメリット・デメリットがあり、事業の内容や規模によって最適な選択肢は異なります。