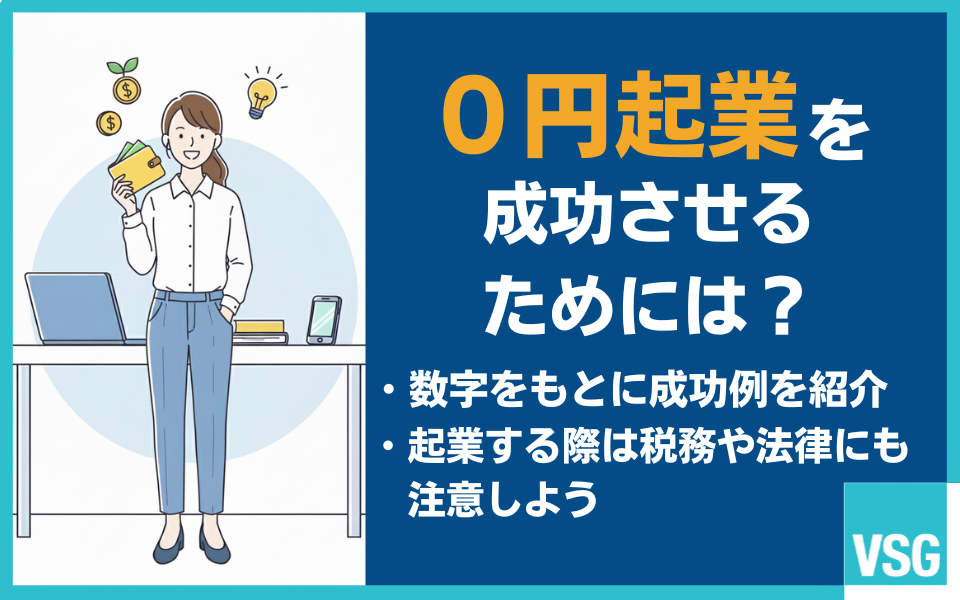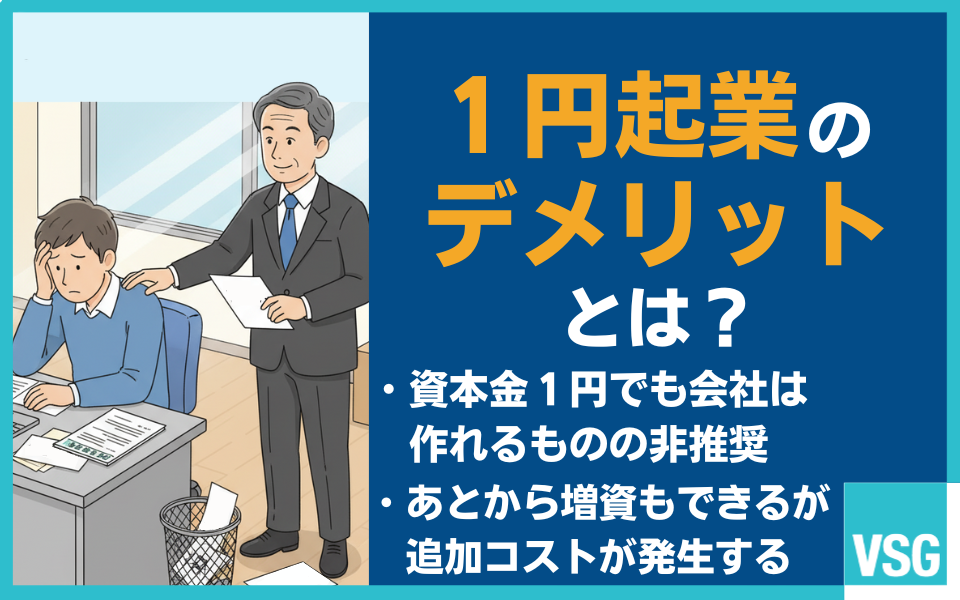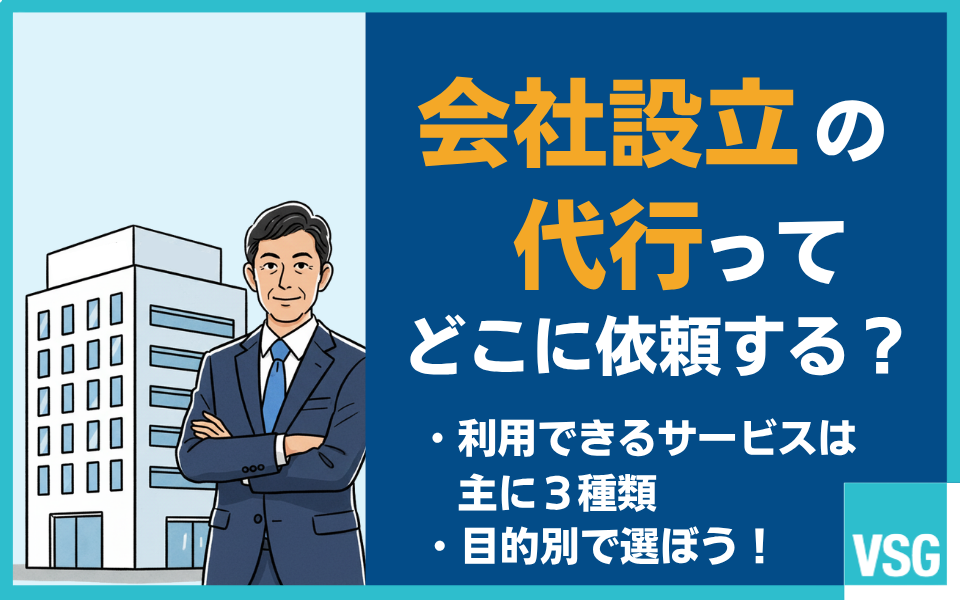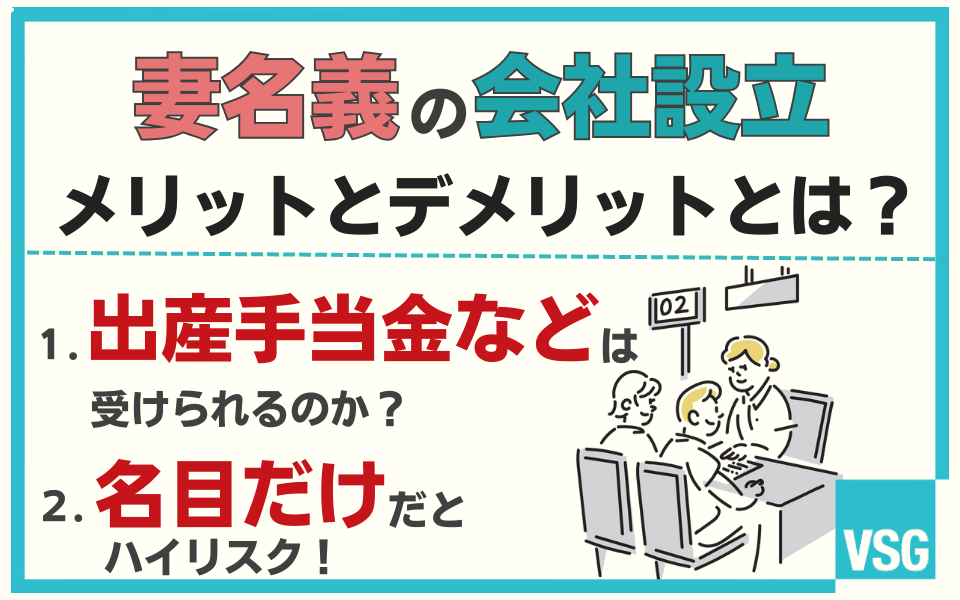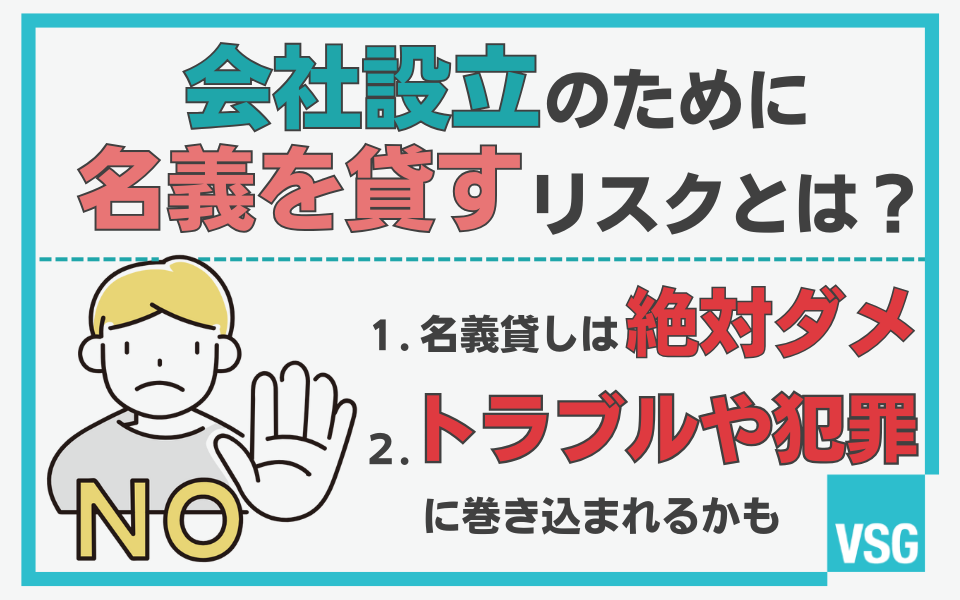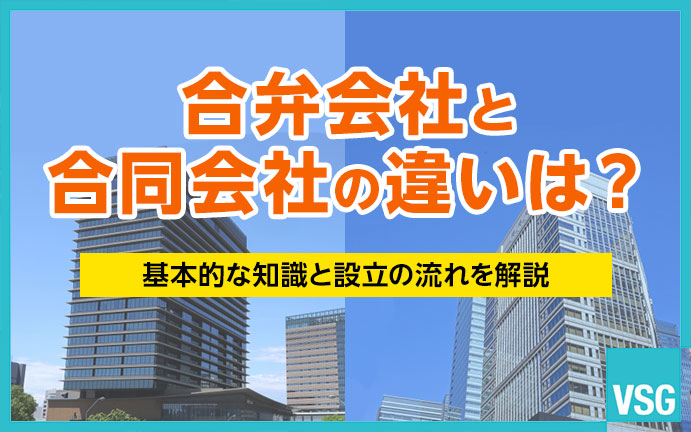最終更新日:2025/9/16
合資会社と合同会社の違いは?略称やそれぞれのメリット・デメリットを解説します

ベンチャーサポート税理士法人 大阪オフィス代表税理士。
近畿税理士会 北支部所属(登録番号:121535)
1977年生まれ、奈良県奈良市出身。
起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネルを運営。
PROFILE:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_writing/#p-mori
YouTube:会社設立サポートチャンネル【税理士 森健太郎】
書籍:プロが教える! 失敗しない起業・会社設立のすべて (COSMIC MOOK) ムック
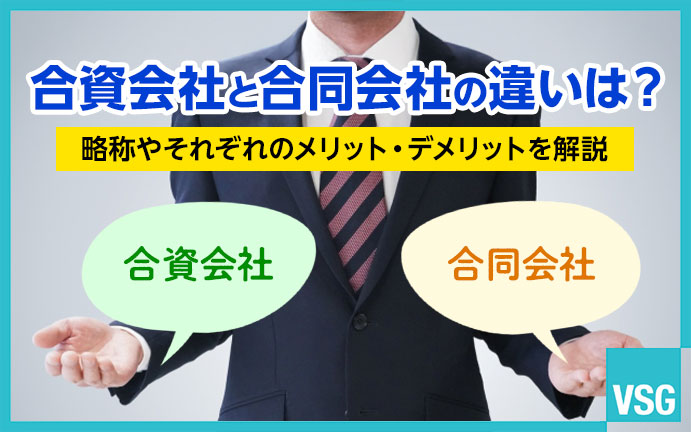
この記事でわかること
- 合資会社と合同会社の違い
- 合資会社・合同会社と株式会社の違い
- 合資会社と合同会社それぞれのメリット・デメリット
「合資会社」と「合同会社」は、どちらも会社法上の法人格を有する会社です。
名称は似ていますが、その制度や責任の範囲は大きく異なります。合同会社は平成18年の法改正で導入された比較的新しい法人形態であり、合資会社はそれ以前から続く古い形態です。
合資会社と合同会社は、株式会社に比べると社会的信用の面で劣りますが、設立自体は簡易です。また、それぞれ異なる実務上のメリット・デメリットがあります。
この記事では、合資会社と合同会社の基本的な特徴や違いをわかりやすく解説します。設立可能な会社の一覧や株式会社との違い、組織変更などについても整理します。


目次
合資会社と合同会社の違い
合資会社と合同会社は、制度上の仕組みや経営者の責任の重さに大きな違いがあります。ここでは、両者の違いを解説します。
責任の範囲が違う
合資会社と合同会社の最大の違いは、出資した社員の責任の範囲です。
合資会社には「無限責任社員」と「有限責任社員」の両方が存在します。
| 無限責任社員 | 会社が債務を抱えた場合に出資額以上の責任を負う |
|---|---|
| 有限責任社員 | 出資額以上の責任を負わない |
合資会社では無限責任を負う人が必ず1人以上必要です。無限責任社員は、万が一の場合は自分の財産を失う可能性があります。
一方、合同会社では、すべての社員が有限責任です。全員が出資額を超えて負担を負うことはなく、起業のリスクが限定されている点が大きな特徴です。
そのため、合同会社は現代的な経営ニーズに合った法人形態として利用されており、ベンチャー企業や士業事務所、個人事業主の法人成りなどにも選ばれています。
同じ「会社」であっても、出資者がどこまで責任を負うかという点で、合資会社と合同会社は大きく異なります。
設立できる会社の種類一覧
今、日本で設立できる会社には4つの形態があります。それぞれの会社の特徴を簡潔に整理します。
株式会社
株式会社は、日本で最も広く普及している会社形態ともいえ、上場企業から個人経営まで幅広く利用されています。株式会社の特徴は、株式の発行で資金調達できるという点や、所有と経営が分離しているという点です。
株式会社は、株式を発行して資金調達ができます。また、会社の所有者(出資者である株主)と経営者が原則として分離しています。株主は、会社に出資した金額の範囲で責任を負う「有限責任」です。経営については株主総会で選任された取締役が行います。
- 株式の発行で資金調達ができる
- 株主の人数制限がない
- 社会的信用度が高い
このような特徴があるため、小規模事業者から大企業まで、幅広い企業で株式会社が選ばれています。
合同会社
合同会社は、出資者かつ経営者である「社員」で構成され、総社員の合意で意思決定をします。合同会社では、社員全員が有限責任であり、出資額を超えて個人の財産で責任を負うことはありません。
- 設立時の定款認証が不要
- 役員の任期がない
- 株主総会がない
- 出資者=経営者
- 社会的信用度やブランド力は株式会社より低い
設立時の費用や手続きが簡素である点や、所有と経営が同一である点などから、小規模な店舗経営、ファミリービジネスや個人事業の法人成りの際に選ばれています。
合資会社
合資会社は、伝統的な会社形態で、最大の特徴は、社員の中に「無限責任社員」と「有限責任社員」が必要であるという点です。
現在では合資会社のメリットはほとんどなく、設立件数も少なくなっています。
- 株式会社や合同会社に比べて制度的に古い
- 無限責任のリスクが大きい
- 知名度が低い
新しく合資会社を設立するケースはまれで、今、運営されている合資会社は古くから合資会社を維持している老舗企業がほとんどです。
合名会社
合名会社は、出資者全員が無限責任社員となる会社形態です。合資会社以上にリスクが大きいため、現在ではほとんど設立されていません。
- 社員全員が会社の債務について無限責任を負う
- 合同会社や株式会社に組織変更するケースが多い
合名会社は、実務上ほとんど使われておらず、制度として存在しているにとどまるのが現状です。2024年では、合名会社の新規設立は11件でした。
合資会社と合同会社の略称
会社には、会社法上の正式名称と実務上の略称があります。誤解や表記ミスを避けるためにも、一般的な略称・略字・英語表記を正しく理解しておきましょう。
略称・略字・英語表記をチェック
下表は、会社形態ごとの一般的な表記の違いを一覧にしたものです。
| 会社形態 (正式名称) |
略称 | 略字 | 英語表記 |
|---|---|---|---|
| 合同会社 | 合同 | (同) | G.K.:GodoKaisha Inc.:Incorporated LLC:Limited Liability Company |
| 合資会社 | 合資 | (資) | GSK:GoShi Kaisha |
| 株式会社 | 株式 | (株) | Co., Ltd.:Company Limited Corp.:Corporation Inc.:Incorporated |
| 合名会社 | 合名 | (名) | limited partnership company |
契約書や印鑑証明書、登記簿謄本では、会社形態は正式名称で記載されます。略称が使用される場面は少ないですが、覚えておけば実務で役立つことがあるかもしれません。
合資会社と合同会社のメリット・デメリット
ここからは、合資会社と合同会社、それぞれのメリット・デメリットを見ていきましょう。
合資会社
まずは、合資会社のメリットとデメリットです。合資会社は設立件数が少なく、あまりメリットがないのが現状です。
メリット
他の会社形態と比較して合資会社を設立するメリットはほとんどありません。合資会社の設立件数はとても少なく、2024年の統計では設立件数は19件でした。
合同会社と比較した場合、わざわざ合資会社を選ぶことにメリットはほとんどありません。あえて挙げるとすれば、合資会社では労働を出資とする「労働出資」ができるという点です。


デメリット
合資会社のデメリットは、有限責任社員と無限責任社員がそれぞれ必ず1名ずつは必要であるという点です。つまり、合資会社はひとりでは設立できません。また、1名は必ず無限責任社員となるため大きなリスクが生じます。
合資会社は歴史ある法人ではありますが、あまり一般に浸透しておらず知名度が低いのもデメリットです。
合同会社
次に合同会社のメリットとデメリットを見ていきましょう。個人事業主の法人成りやセカンドビジネスの法人化に選ばれることもある合同会社には、メリットとデメリットがあります。
メリット
合同会社のメリットは、ひとりでも設立できるという点です。合資会社では最低でも2人必要ですが、合同会社はひとりで設立できます。
また、出資者は全員有限責任であるため、リスクが出資額に限定されます。
また、会社設立時の定款認証が不要であるため、株式会社と比較して手続き上のメリットもあります。
デメリット
合同会社のデメリットは、資金調達の際に株式の発行ができないという点です。株式会社では株式を発行して出資を募ることができますが、合同会社ではできません。そのため、資金調達をするときには、融資や補助金の利用がメインとなります。
また、「合同会社」という会社形態は合資会社よりは耳にする機会が多いものの、一般的な知名度としては株式会社よりかなり低く、ネームバリューとしての魅力はあまりないといえます。
株式会社との違いは?
合資会社と合同会社の違いが見えてきたところで、株式会社との違いも解説していきます。
所有や経営の方法が異なる
株式会社では「出資者=経営者」ではなく、所有と経営が分離しています。
一方、合同会社や合資会社では、出資者がそのまま経営者となるのが基本です。ただし、取締役が自社株を保有することに関しては制限がないため、株主が役員に就任するケースもあります。
株主が所有者
株式会社では、株主が会社の所有者となります。株主は出資によって株式を保有し、会社の経営方針を決める株主総会で議決権を持っています。ただし、株主が自ら経営を行うわけではありません。
株主はあくまで「所有者」としての立場にあり、出資額を超えて責任を負うことはありません。また、株式は譲渡可能であるため、会社の所有者が頻繁に入れ替わったり多数の所有者(株主)が存在するというケースもあります。
取締役が経営をする
株式会社では、株主総会で選任された取締役が会社の経営判断を行います。この「所有と経営の分離」によって、出資者はお金を出すだけという立場になります。
一方、合同会社や合資会社では、出資者がそのまま社員として業務に携わります。
株式を発行できるか
株式会社では、資金調達の手段として株式を発行することできます。
これにより、多数の投資家から資金を集め、事業を大きく成長させることができます。
一方、合同会社や合資会社には株式制度がないため、融資や補助金などで資金を用意する必要があります。
会社の組織変更について
設立時に最も適していると判断して選んだ会社形態が、事業内容や成長にともなって合わなくなっていくことがあります。その際にできるのが組織変更です。ここでは、会社の組織変更について解説します。
会社の組織変更は可能
会社法では、会社の形態を変更する「組織変更」が認められています。
持分会社から株式会社、あるいは株式会社から持分会社に変更するのが組織変更です(持分会社から他の持分会社への変更は種類変更といいます)。
設立時の会社形態をずっと維持しなければならない決まりはなく、必要に応じて変更ができるようになっているのです。
ただし、組織変更をする際には次のような手続きが必要になります。
- 株主総会や社員総会での決議
- 新しい会社形態に即した定款の変更
- 登記
- 税務署などへの届出
会社の組織変更には一定のコストと時間がかかりますが、現状に最も合った組織に変更することで得られるメリットはあります。
合資会社と合同会社の違いを理解しましょう
合同会社と合資会社は混同されやすい会社形態ですが、実態には大きな違いがあります。
最大の違いは、経営者(社員)が負う責任の範囲です。合同会社ではすべての社員が有限責任となりますが、合資会社では少なくとも1名が無限責任を負う必要があります。
合同会社のほうが柔軟で現実的な設計が可能であり、無限責任のリスクもないため、設立数は合資会社を大きく上回っています。もちろん、会社法上は、どちらの会社も新しく設立できる形態として存在しています。
設立時には、名称の印象だけで判断せず、実際の責任や運営の自由度、資金調達のしやすさなどを比較したうえで、目的に合った法人形態を選ぶことが大切です。