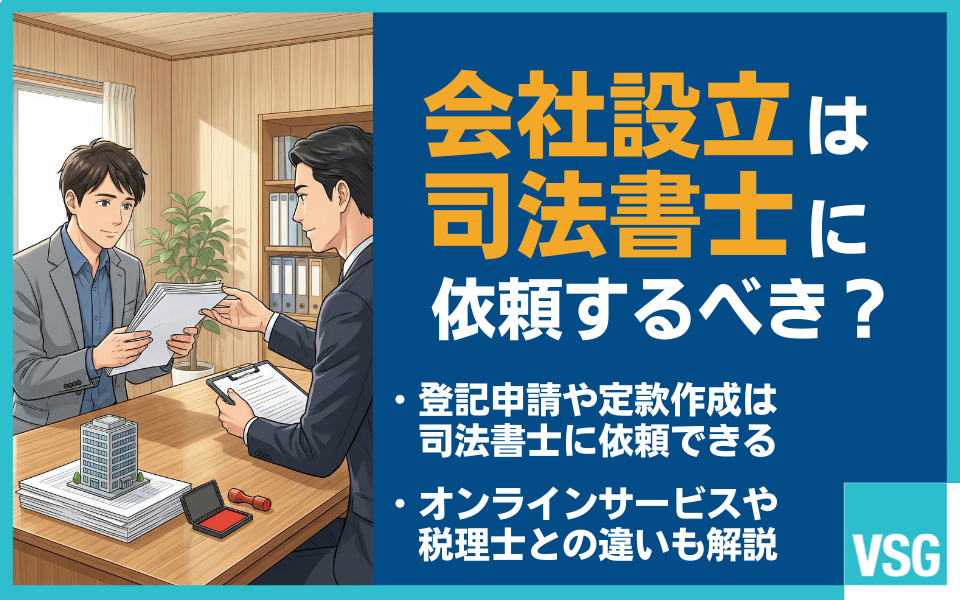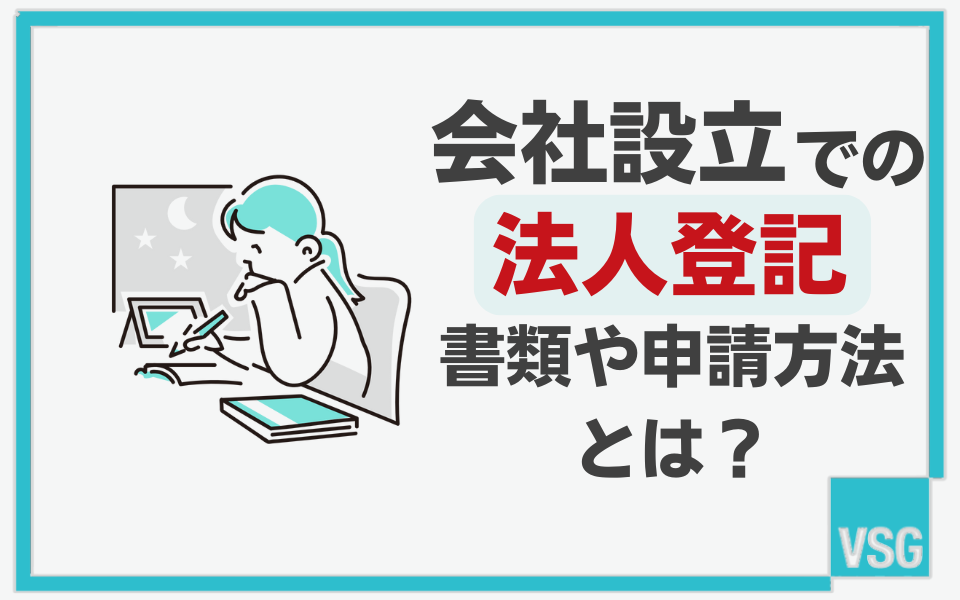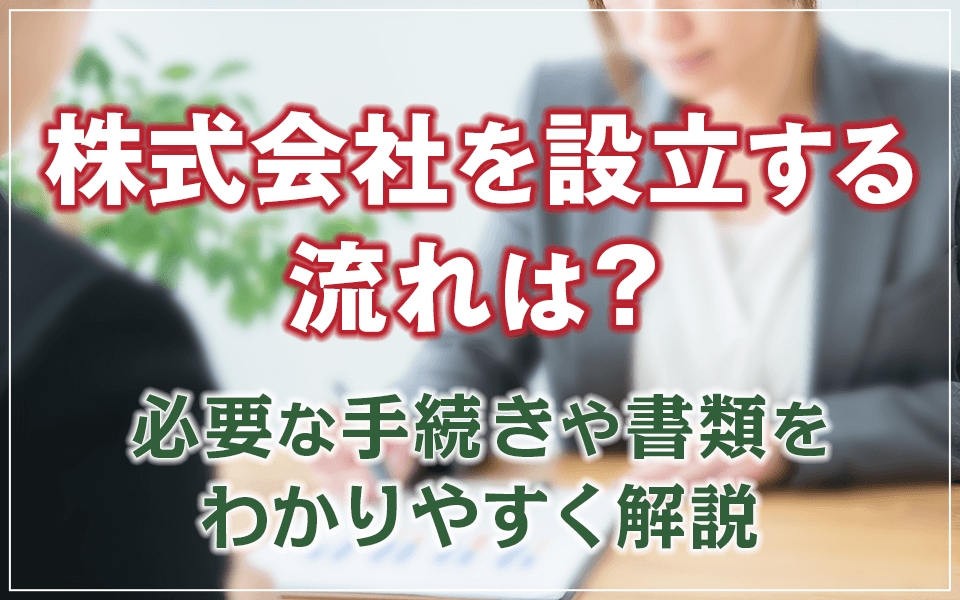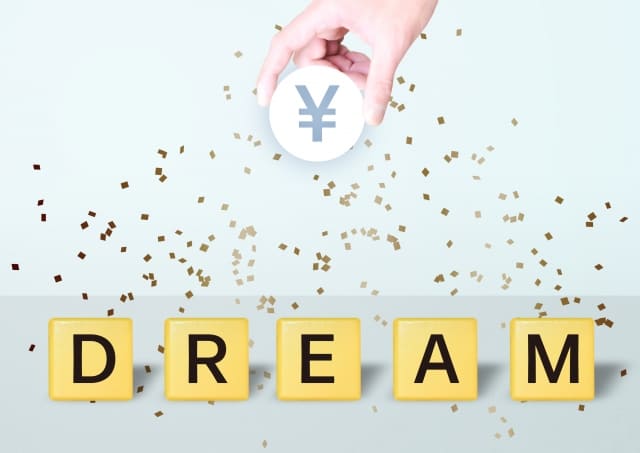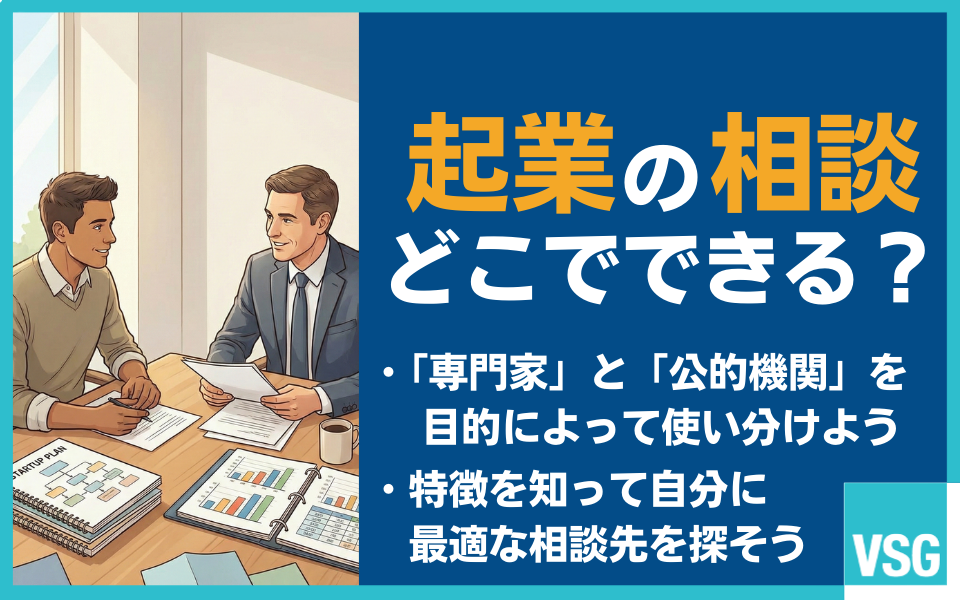最終更新日:2025/9/22
会社設立で税理士への起業相談は必要?費用相場や損しない選び方を解説!

ベンチャーサポート税理士法人 大阪オフィス代表税理士。
近畿税理士会 北支部所属(登録番号:121535)
1977年生まれ、奈良県奈良市出身。
起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネルを運営。
PROFILE:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_writing/#p-mori
YouTube:会社設立サポートチャンネル【税理士 森健太郎】
書籍:プロが教える! 失敗しない起業・会社設立のすべて (COSMIC MOOK) ムック

会社設立を誰かにサポートしてほしいと思ったとき、どのような人に頼るべきでしょうか?
設立だけを見据えるのであれば、登記申請を代行してくれる司法書士に依頼するのも一つの手です。
しかし、会社を設立するということはその会社で大きな利益を生みたい、あるいは個人事業主よりも低い税率で事業を営みたいといった目的があるはずです。
その目的を果たすためには、税理士への相談がおすすめです。
この記事では、会社設立において税理士に相談し、契約を結ぶ具体的なメリットについて詳しく解説します。
税理士との契約の形態や費用相場、税理士を選ぶときのポイントについても触れるので、会社設立を考えている人はぜひ一度目を通し、参考にしてみてください。


目次
会社設立に税理士は必要か
会社設立は、資金と時間があれば誰でも行うことができます。
しかし、あらかじめ税金対策ができているか、資金繰りの計画があるかによって、数年後にその会社が存続している確率は大きく異なります。
また、日本政策金融公庫が行った2024年の新規開業に関する調査によると、開業時に苦労したことのトップ3は「資金繰り・資金調達」(59.2%)、「顧客・販路の開拓」(48.1%)、「財務・税務・法務に関する知識の不足」(36.7%)となっています。
参考:2024年度新規開業実態調査|日本政策金融公庫 総合研究所
近年は使いやすい会計ソフトがあるので、会計や決算申告業務だけなら、事業者自身で行うことも可能です。
しかし、資金調達や税金に関しての専門的な知識を持ち、個人では把握しきれない部分のアドバイスをしてくれる相手としては、税理士が最も適しています。
単に経理を任せる相手ではなく、会社の設立から経営までを支え、主に税金面から事業者をサポートしてくれる相手として、税理士と契約を結ぶことには大きな意味があるでしょう。
会社設立前から税理士と相談・契約するメリットとは

事業者のなかには、会社設立は自分で行い、最初の決算のときに税理士と契約をする人も数多くいます。
最初の決算までの契約料を節約できるので、非常によい選択肢の1つですが、一方で会社設立前から税理士に相談や契約をすることで得られるメリットもあります。
- 無料で会社設立について相談できる税理士が多い
- 設立前しかできない節税対策がある
- 時間と費用をかけずに設立できる
それぞれについて詳しく解説します。
無料で会社設立について相談できる税理士が多い
「税理士に相談はしてみたいけれど、高額な相談料を取られそうで心配」という人もいるかと思います。
しかし近年は多くの税理士が、会社設立に関する相談を初回無料で受け付けています。
相談したからといって必ず契約する必要はないので、気軽に利用することが可能です。
「対面ではスケジュールが合わせにくい」「契約を勧められたら断れないかもしれないし怖い」という場合は、Webでの相談に対応している税理士を探してみましょう。
より気軽に、会社設立について相談することができます。
また、初回無料相談は税理士の態度や実務能力、コミュニケーションの取りやすさを確認する絶好のタイミングでもあります。
時間に余裕があるのであれば、複数の税理士の無料相談を利用し、比較検討しながら自分に合う税理士を探してみましょう。
その場では契約を結ばなかったとしても、自分では解決できない経理や税務上のトラブルが起きたときに安心して任せられる相手として、ストックしておくことができます。
設立前しかできない節税対策がある
資本金の額や役員報酬、事業年度などは、設立時に事業者が自由に決められます。
しかし税金に関する知識がないままに決めてしまうと、将来支払う税金が高くなったり、消費税の免除などを受けられなくなってしまうこともあります。
こうした、一般の人が知らない節税対策について教えてもらえるのが、税理士に相談する大きなメリットの1つです。
ほかにも、税に関する知識がないと損をしてしまうケースはあります。
たとえば、会社設立をする前の準備段階でかかった電車代やカフェでのコーヒー代といった費用も、創立費として経費に算入できます。
しかし、このような経費にできるものとできないものに関する知識がないと、本来はできたはずの節税を行えず、資金が不足しがちなスタートアップ段階の企業にとって大きなマイナスとなります。
こうした知識を1から学んでいると、会社設立がどんどん遅れてしまいます。
結果としてビジネスチャンスを逃したり、せっかくの起業への熱意が冷めてしまうかもしれません。
税に関することはすべて税理士に任せ、自分は事業に集中することで、余計な税金の支払いを回避しつつ会社を発展させることができるでしょう。
時間と費用をかけずに設立できる
会社設立にできるだけお金と時間をかけたくないという場合、税理士に設立代行を相談するのが最も効率的です。
なぜなら、会社設立を行う税理士のほとんどは司法書士などほかの士業と連携しているので、多くの提出書類の作成を丸投げできるからです。
しかし「書類作成さえ自分で行えば、税理士に任せるより費用がかからないだろう」と考える人も多いと思います。
実際のところはどうなのか、確認してみましょう。

上の表は、株式会社を設立するときにかかる主な費用をまとめたものです。
ほかのサイトでは、こうした表で「税理士なら定款印紙代の4万円がかからないのでトータルで安くなる」と書かれていることがよくあります。
しかし、電子定款の作成は個人でも可能です。
もちろん手間と時間はかかりますが、じっくりと学びながらであれば決して不可能な作業ではありません。
そのため、できる限り費用を抑えて自分で設立した場合、税理士に依頼した場合よりも「税理士および司法書士への報酬」の5万~10万円ほどを節約できることになります。
しかし、近年では多くの税理士事務所が「0円設立」というサービスを行っています。
これは会社設立において「税理士自身の報酬を0円にする」&「司法書士や行政書士への報酬を税理士が肩代わりする」というものです。
これを利用すれば、税理士への相談や書類の作成・提出代行などさまざまなメリットを受けつつ、会社設立でのトータルの支払いは個人で行った場合とまったく同じになります。
なぜ税理士は「0円設立」を行えるのか
もちろん、税理士側も何らかの形で報酬を得ないと、0円設立は成り立ちません。
基本的に0円設立は、税理士との顧問契約がセットになっています。
顧問料は月に約3万円が相場のため、税理士側からすると約2~3カ月の顧問契約で、0円設立で割引した金額を回収できるのです。
なので、0円設立を利用する場合は顧問契約の内容が非常に重要になります。
もし0円設立を行う税理士の顧問契約の内容が薄くてメリットを感じられない、あるいはもともと税理士と契約するつもりがないのであれば、0円設立を利用するべきではないでしょう。
しかし、顧問契約の内容が自分に必要なものであり、設立後もぜひ利用したいと感じたのであれば、0円設立はとても魅力的なサービスです。
また、0円設立を利用する際は、サービスの内容はもちろん、「最短でも何カ月は契約が必要」といった縛りがないかといった点も必ずチェックし、納得したうえで利用しましょう。


0円設立に関しては以下の記事でより詳しく解説しているので、ご確認ください。
税理士との契約内容とは

0円設立を利用すれば、費用を抑えながら税理士とともに会社設立を行うことができます。
しかし、それにセットで付いてくる「顧問契約」とは、具体的にどのようなサービスなのでしょうか?
税理士と結べる契約の内容について理解しておきましょう。
税理士との契約には「顧問契約」と「スポット契約」の2種類がある

税理士との契約には、主に顧問契約とスポット契約の2種類があります。
それぞれの違いや注意点について解説します。
顧問契約とは
税理士との顧問契約とは、その名のとおり特定の税理士を「顧問」として、さまざまな税務アドバイスや書類作成・提出の代行などを受けられる契約のことです。
また、経営上の悩み相談や融資に関する情報も、顧問契約を結ぶことで得られます。
税理士と顧問契約を結んでいる会社は、作成する税務関連の書類の信憑性も高いとみなされます。
融資の際にも決算書の精度を担保し、結果的に融資の実行に有利に働きます。
このようなメリットのある顧問契約ですが、費用に関しては基本的に月払いとなり、およそ3万円が相場とされています。
注意点としては、顧問契約の内容はそれぞれの事務所や税理士によって異なるという点です。
「顧問になってくれる=なんでもしてくれる」というわけではなく、多くのケースで記帳代行や決算申告、消費税の申告などは別料金(スポット契約)です。
契約内容によっては、節税提案や補助金などの紹介が別料金となることもあります。
また、融資審査のサポートを依頼した場合には、成功時に融資額の数%を手数料として支払うケースもあるため、思わぬ出費となるかもしれません。
とはいえ、こうした別料金を請求しない税理士も数多くいます。
顧問契約を結ぶのであれば、表面上の料金だけで判断せず、オプションや別料金がどのようになっているのかについて把握しておきましょう。
スポット契約とは
スポット契約とは、会社設立の手続きや決算業務など、税理士が行う業務の一部のみを依頼する、その場限りの単発契約のことです。
「顧問契約は結びたくないけれど決算だけは税理士に手伝ってほしい」「取引の多い繁忙期だけ会計処理を任せたい」といった場合に、事業者にとって必要な税務のみを依頼できます。
一般的には決算申告業務で15万~25万円、記帳代行で2万~3万円、年末調整では基本料1万~3万円+従業員1人あたり2,000~3,000円ほどがスポット契約の相場です。
ただし、税務アドバイスなどは相談時間によって報酬額が加算されることもあるので注意しましょう。
設立前に税理士に聞けること・相談できること

会社設立を税理士に依頼したとき、具体的にどのようなことを相談できるのでしょうか。
ここでは、一般的に設立前の段階で税理士から受けられるサポートについて解説します。
個人事業主と会社設立のどちらがいいか
起業に関するよくある悩みに、「個人事業主として事業を始めるべきか、それとも最初から会社を作ってしまったほうがいいのか」というものがあります。
会社の設立や維持には手間や時間がかかりますが、所得によっては個人事業主よりも税率が低くなります。
社会的信用も高く、個人事業主よりビジネスを発展させやすいといったメリットもあります。
すでに個人事業主として活動している場合、年間の利益が500万円を超えたころが会社設立のタイミングです。
起業する時点でこの500万円以上の利益が見込める場合や、会社設立することで取引先を確保できる場合などは、最初から会社を作るのもいいでしょう。
しかし実際に会社を設立することでどれほどの節税になり、それが会社の設立や維持をする手間やコストに見合っているのか、そもそも設立したあとに継続して事業を営めるのかといった判断を、個人で行うのは困難です。
事業にかかる手間や経費、用意できる自己資産、そして起業する人の事情などを含めて、本当に会社設立が正しい選択なのかを判断するためには、経験豊富な税理士への相談が確実かつ安心できる選択肢です。
株式会社と合同会社のどちらにするか
会社設立の際に、株式会社と合同会社のどちらにするべきかというのも非常によくある相談内容です。
合同会社は設立時に定款の認証が必要なく、必要な費用も株式会社より安いため、近年は増加傾向にあります。
一方で株式会社も、将来的に上場すれば資金を広く集めやすいことや、知名度が高いのでマーケティングや採用活動で有利といったメリットがあります。
株式会社と合同会社のどちらを選ぶかは、設立する会社の事業内容や規模感によります。
「なかなか自分では判断できない」といった場合は、税理士と事業計画を共有することで、税理士が最適な会社形態を選んでくれます。
株式会社と合同会社の違いについてもっと詳しく知りたい人は、以下の記事をご覧ください。
融資・補助金・助成金
税理士には、金融機関からの融資をどのように受ければいいかといったことも相談できます。
また、補助金や助成金について相談を受け付けている税理士もいます。
補助金や助成金は数多くありますが、それぞれ期限や要件が大きく異なります。
創業してから◯年以内の事業者のみ、あるいは創業準備段階の人が対象になっていることもあるので、うまく活用できたケースと知らずに逃してしまったケースとで、資金繰りに数百万円、数千万円の違いが出てきます。
こうした情報を会社設立前に聞けること、さらに審査のために提出する事業計画書などの作成のサポートを受け、採択率を大きく上げられることなども、会社設立前に税理士と契約する大きなメリットの1つです。
会社設立時に利用できる補助金・助成金に興味がある人は、以下の記事もご確認ください。
節税方法
個人で会社設立を行う場合、最もネックになるのが「正解がわからない」ことです。
出すべき書類や節税について、ある程度は自分で調べて学んだとしても、その情報が本当に正しいのか、もっとほかにできることがあるのではないかといった不安は拭えません。
会社を設立することでどのような節税ができるのか、あらかじめしておくべき税金対策は何かなどを、専門家である税理士に相談しておけば、会社設立に対する不安を大きく取り除けます。
税務署への届出やその他の提出書類
会社設立にはさまざまな書類を作成し、提出しなければいけません。
その中には、税務署や都道府県税事務所、市町村役場に支払う法人税に関する書類や、青色申告承認申請書などの、提出を忘れてしまうと将来的に大きな損失につながる書類もあります。
これらの書類の作成や提出の代行は、税理士のみが行える独占業務です。
会社設立直後の忙しい時期に、これらの書類に関する手続きを税理士に丸投げできるのは、時間的にも大きなメリットになるでしょう。
会計のやり方・ベース作り
新しく事業を始める人のなかには、今まで会計や経理に関わってこなかった人も少なくありません。
面倒な帳簿付けや決算はすべて、経理担当を雇うか税理士に丸投げすることもできます。
しかし、もし自分である程度できるようになっておきたいというときには、税理士に会計のやり方や帳簿ソフトの使い方について相談できます。
設立後も税理士と顧問契約を結ぶメリットとは

会社設立を税理士に頼むことには大きなメリットがありますが、では会社設立後に結ぶ顧問契約には、どのようなメリットがあるのでしょうか。
顧問契約の内容と、その具体的なメリットについて解説します。
状況に合わせた節税のアドバイス
会社設立時にいったん節税対策を講じても、事業フェーズが進むにつれて最適な税務戦略は必ず変わります。
税理士と顧問契約を結び、長期的にやり取りを重ねていれば、それに合わせた節税対策を行いやすくなります。
さらに日本の税制は、毎年度の税制改正で手が加えられます。
かつて有効だった節税対策が廃止・縮小される一方、まったく新しい優遇策が生まれることも珍しくありません。
忙しい事業者に代わって最新動向を継続的にモニタリングし、今の状況に合った節税のアドバイスができるのが、税理士の大きな強みの1つです。
資金繰りについてのアドバイス
会社経営と切っても切れないのが、資金繰りです。
日々の仕入れや営業に必要な資金はもちろん、実際に経営をしていく中では急なトラブルでまとまった額が必要になることもあります。
また、法人税・消費税などの支払いや売掛金の回収、買掛金の支払いなど、会社設立をするまでは気にかける必要のなかった資金の出入りについても、あらかじめ把握して対処しなくてはいけません。
これらを管理し、健全なキャッシュフロー(お金の流れ)を構築するには、税理士の持つ税に関する専門知識や、経験に基づく経営戦略へのアドバイスが大きな助けになります。
税務調査対応
2023年の法人税の申告件数は318万件でしたが、そのうち実地で税務調査が行われたのは5万9,000件だったと国税庁は公表しています。
参考:令和5事務年度 法人税等の申告(課税)事績の概要|国税庁
このことから、1年のうちに税務調査が来る確率は単純計算で約1.8%ほどになります。
しかし、これはあくまで1年間に税務調査が来る確率です。事業を5年、10年と続けていけば、それだけ税務調査が来る確率も上がります。
また、実際に税務調査が来るかどうかは、その会社の業種や取引内容によっても変化します。
たとえば輸入・輸出業や建設業などは、消費税の還付を受けられます。この部分でミスや不正が発生しやすいとして、税務署はそのほかの会社よりも入念にチェックする傾向があります。
同じように、海外取引や暗号資産のやり取りがある会社なども、税務調査が来やすい会社といえます。
万が一税務調査が来た場合、税理士を挟まずに事業者本人が対応すること自体は可能ですが、多くの場合でやり取りに膨大な時間がかかったうえ、高額な追徴課税が発生してしまいます。
税務調査の連絡が来たときは、できるだけ早めに顧問税理士に相談するか、税務調査に詳しい税理士とスポット契約を結びましょう。
支払う金額を大幅に減らせる可能性があります。
定期的なレポートや面談
税理士からさまざまなサポートやアドバイスを受けるうえでは、気軽に、定期的に相談できる環境があるかどうかも重要です。
顧問契約のプランによっては、数カ月に一度、あるいは毎月必ず面談を実施し、直近の数値や課題を共有できるしくみが用意されています。
また、会計データをもとに会社の業績をレポートにまとめ、経営状況を可視化して分析してくれる税理士もいます。
税理士の選び方・注意点

税理士との契約にはさまざまなメリットがありますが、なかにはあまり契約するべきでない税理士がいるのも事実です。
あらかじめ事務所を検索して、口コミを確認することである程度はどのような税理士か判断できますが、それ以外の選び方や判断基準について知っておけば、自分にとってよりよい税理士と巡り会える確率が上がります。
コミュニケーションが取りやすいか・レスポンスが早いか
税理士は、会社を設立したあとも何度も節税や経理、経営について相談し、悩みや不安を打ち明ける相手です。
その税理士が、返事が遅かったり横柄な態度を取ってくるのであれば、ストレスになるうえに会社の経営にとっても大きなマイナスになります。
現在は税理士業界でもデジタル化が進み、遠方からでもオンラインでやり取りを行えるようになったため、地元の税理士以外の選択肢も検討しやすくなりました。
気持ちよくコミュニケーションが取れる、気の合う税理士を会社設立時点で探しておくのは、とても重要なことの1つです。
また、レスポンスの速さもとても大事です。
たとえば青色申告の申請書類など、提出期限のある重要な書類は数多くあります。
それらについて相談したいのに、返事に数日もかかっているようでは、期限に間に合うか心配しながら過ごさなくてはいけません。
税務調査の連絡を受けた場合や、融資・補助金の審査で急に書類の提出を求められた場合、資金繰りが厳しいので一刻も早くこの状況を改善したい場合など、税理士とのやり取りにはスピードが重要になるケースも少なくありません。
こうしたコミュニケーションやレスポンスの速さは、多くの税理士が行っている初回の無料相談である程度見極めることができます。
またその際には、「契約後のやり取りはオンラインでも行えるのか」「担当税理士が休暇や病気のときはどうなるのか」なども質問しておくと、その事務所の体制やユーザビリティをより的確に把握できます。


思った以上に事業に影響を及ぼすこともあるので、初回の相談時点で税理士からのレスポンスのスピードには少し注意しておきましょう。
会社設立と会計、税務調査対応の実績があるか
税理士は、会社設立や会計などの法人業務に加え、相続税の申告やコンサルティングといった業務にも携わります。
また、ひと言で法人といっても、公益法人や建築業、海外取引など分野はさまざまで、課される税や特例なども違います。
これらすべてを一人の税理士が完璧に行うことは不可能なため、基本的にそれぞれの税理士は得意分野に特化して業務に当たります。
普段は会計処理ばかりしている税理士が、急に会社設立のサポートを頼まれた場合、やはりどうしても経験が足りず、何らかのミスが発生するリスクも高くなってしまいます。
会社設立と設立後のサポートを任せる税理士を選ぶ際は、まずは事務所のホームページなどを確認して、何を専門としているのかを把握しましょう。
さらに無料相談で、担当してくれる税理士が会社設立や会計、税務調査対応の実績があるか、関連する士業との連携体制が整っているかなどについて確認しておきましょう。
専門性と実務経験を見極めて契約すれば、設立時の手続きやその後の経営サポートも安心して任せられます。
料金形態が明確か・顧問契約やスポット契約の範囲がわかりやすいか
事務所のホームページやパンフレットから、詳しい料金形態を確認できるかも、いい税理士を見つけるために重要です。
税理士事務所のホームページは、料金表が載っていないこともよくあります。
これは、税理士の業務の幅広さゆえに「何をどこまでやるか」によって値段が変動しやすいことや、税理士同士での価格競争を避けるためです。
値段を改定すると既存の客との価格差が明白になり、クレームに発展しやすいといった理由もあります。
とはいえ、税理士を利用する事業者側からすると、全体の料金がわからないのは非常に大きな不安材料です。
わざわざ電話をして確かめたり、初回の無料相談で聞き出すのも、手間がかかるでしょう。
料金表をWebで公開し、その内容に不明瞭な点がなく、事前に概算額を確認できる税理士事務所は信頼性が高いと考えられます。
また、顧問契約やスポット契約で対応してくれる業務の内容が公開されているかも重要です。
事務所によって契約の内容は違うので、その内訳がわからないと実際の費用も想定できません。
料金や契約内容が確認できて、利用者が必要なサービスを選びやすい設定にしている税理士と契約を結ぶことをおすすめします。
税理士との会社設立でよくある質問
実際に会社設立をする際、税理士について多くの人が疑問に思う点や、よくある質問をまとめて解説します。
小さい会社でも税理士は必要なのか
会社の規模によっては、個人事業主でいたころと経理の難易度がそれほど変わらず、事業者自身で行えることもあるでしょう。
ただし、法人を設立した際には、主に以下のような業務や届出の作成を行わなければいけません。
- 社会保険の加入
- 役員報酬の決定
- 法人税の計算と納付
- 税務署への各種届出
- 法人特有の経費の帳簿付け
これらも個人で行うこと自体は可能ですが、あまり知識がない状態から取り組もうとすると膨大な時間と労力がかかってしまいます。
また、内容にミスがあった場合は書類を作り直したり、場合によっては受けられるはずの補助や特例を逃し、経営に大きなダメージとなることもあります。
もし「自分には税理士は不要だ」と判断したとしても、無料相談などを活用して信用できる税理士を見つけておくことをおすすめします。
後々の会社経営でどうしても個人で対応できない問題に直面したときに、その税理士にスポット依頼をすることで乗り切れるでしょう。
税理士は必ずしも必要ではありません。
しかし、会社の経営に少しでも不安があるのであれば、信用できる税理士は経営者にとって最良の相談相手になってくれます。
税理士と司法書士、会計士の違いとは何なのか
税理士と司法書士、会計士はどれも「士業」と呼ばれる職業ですが、専門とする分野がそれぞれ異なります。
税理士は先述したように、税の専門家です。主に法人税・相続税などの税務申告や会計業務、さらに会社に対する経営コンサルティングなども行います。
一方で司法書士は、登記や供託に関する専門家です。会社設立においては商業登記に関する業務を担当します。
登記に関わる業務は、司法書士の資格を持つ人しか書類作成や提出の代行ができないと法律で定められています。
会計士は会計の専門家であり、主に監査業務を行います。
この監査とは、企業が作成した財務諸表に誤りや不正がないかチェックすることを指します。
また、公認会計士資格を持つ人は、税理士試験に合格しなくても税理士として登録し、税務に関する業務を行うことが可能です。
とはいえ財務諸表は大企業や上場企業にのみ作成が義務付けられているため、会計士のクライアントもそれらの企業が対象になります。
会社設立に関する知識や経験は、会計士よりも税理士や司法書士のほうが豊富でしょう。
税理士法人と個人の税理士のどちらに会社設立を依頼するべきか
法人所属と個人の税理士のどちらに依頼するべきかは、最終的には個々の税理士の力量や事業者との相性次第です。
しかし、複数の士業が集まって活動している「士業グループ」は、そのなかで税務や登記、社会保険、許認可申請など、会社設立で必要になるさまざまな専門分野にワンストップで対応できるため、設立までのスピードが早いという特徴があります。
また、仮に担当してくれている税理士が病気や怪我で休業したとしても、すぐにほかの税理士がフォローに入れるといったメリットもあります。
何割くらいの会社が税理士と契約しているのか
事業者と税理士の契約率を示す明確なデータはありませんが、令和5年度の国税庁の実績評価書では、法人税の申告書に税理士が関与した割合は89.8%とされています。
参考:令和5事務年度国税庁実績評価書 実績目標(大)3(税理士業務の適正な運営の確保)|財務省
また、納付に税理士が関与していないとする10.2%の企業に関しても、必ずしも事業者自身が法人税の納付業務を行っているとは限りません。
規模の大きい企業では、もともと社内に税理士を従業員として雇っていることも少なくありません。
その税理士はあくまで従業員なので、決算や法人税の納付を任せたとしても、関与税理士として申告書に署名押印を行わないのです。
現場感覚でいうと、税理士でない事業者が本当に自分だけで申告書を作成しているのは5%ほどです。この点も考慮すると、およそ95%ほどの企業が、決算申告などの業務を税理士に任せていると推察できます。
この記事のまとめ
会社設立の際に税理士と契約を結べば、税務署などへの書類の作成や提出、節税対策、融資や補助金・助成金に関するアドバイスなど、さまざまな専門的なサポートを受けられます。
また、そもそも会社設立するべきかを税金という観点から判断してくれます。
多くの税理士が初回相談を無料で受け付けているので、自分と相性のいい税理士を見つけるためにも活用してみましょう。
ただし、税理士との契約には顧問契約とスポット契約があり、どの業務が顧問契約に組み込まれているのかなどは必ず確認しておかなくてはいけません。
その税理士が何をしてくれるのか、支払う契約料に見合っているのか、コミュニケーションが取りやすいかなどを見極め、納得してから税理士と契約を結びましょう。
会社設立を税理士に依頼するときは無料相談から
税理士と契約する最も大きなメリットは、「自分の知らない知識をもとに、会社の設立や運営を助けてくれること」です。
ほとんどの人にとって、会社設立は生まれて初めて行う、人生の一大イベントです。
その中にはまるで知らなかった分野や、なかなか1人では対処できないものも含まれています。
忙しく、不安も多い設立時だからこそ、特に気がかりな資金面を税理士に相談できることは大きな支えになります。
まずは無料相談から、気軽に連絡しつつ、自分にとって最良の税理士を探してみましょう。
ベンチャーサポート税理士法人では、会社設立・運営に関する無料相談を実施しています。
創業以来20年以上、3万社以上の会社設立をサポートしてきた経験と実績から、起業を成功させるノウハウをお伝えします。
また、「士業はサービス業」という共通理念のもと、起業家の方々の悩みや不安に即レス、即対応できる体制も整えています。
初めて会社設立を行う方や、できるだけ早めにミスなく設立を行いたい方、そして税理士との会社設立に興味を持っていただけた方は、ぜひお気軽にご相談ください。