

東京弁護士会所属。
メーカー2社で法務部員を務めた後、ロースクールに通って弁護士資格を取得しました。
前職の経験を生かし、実情にあった対応を心がけてまいります。 お気軽に相談いただければ幸いです。
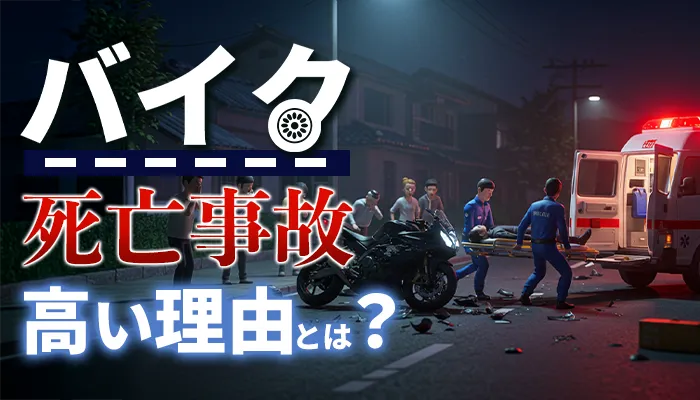
車とは違う魅力があるバイクですが、身体が剥き出しになっていることから事故に遭うと重傷を負いやすいです。事故の原因を知っておけば、事故に遭いやすい状況を回避することができるでしょう。
この記事では、バイク事故の原因や死亡率・重傷率を下げるための対策について解説します。バイク事故に遭ってしまった場合の対処法もご紹介しているので、ぜひ最後までご覧ください。
バイク事故の主な原因は、以下のとおりです。
バイクは車体が小さく小回りが効き、車よりも加速しやすいという特徴があります。特性を活かしてすり抜けや追い越しなどをしようとしたときに、事故に遭いやすい傾向にあります。
たとえば、以下のようなケースが挙げられます。
バイクのすり抜けや追い越しは必ずしも違反行為ではありませんが、交通ルールによっては違反になり反則金や違反点数が加算される場合があります。
また、無謀な運転行為で事故を誘発したとして、過失割合で不利になる可能性もあります。
バイクの運転者にはヘルメットの着用が義務付けられていますが、ヘルメットの形状によっては視界が大きく制限されます。死角が広くなっていることを考慮せずに運転すると、接触事故を引き起こす原因になるでしょう。
また、バイクによっては運転姿勢が前傾になり視野が狭くなるケースがあります。目線が下がることで遠方の注意がおろそかになり、追突事故を起こしたりカーブで曲がりきれないなどの事故を起こす可能性があるでしょう。
スポーツタイプのバイクや、フルフェイスのヘルメットを着用する際には、運転者本人が視野が狭くなっていることを十分に認識しておく必要があるでしょう。
バイクは車体が小さいため、車の死角に入ってしまう可能性が高いです。特にトラックなどの大型車の側面をすり抜けようとした場合、車のサイドミラーにバイクが写らず、気付かずに車線変更をして事故になるケースがあります。
死角に入ってしまった場合、車はバイクの存在を認識しないまま事故になります。スピードを落とさず接触・衝突するので、重傷・死亡の結果につながりやすいです。
バイクは車体が軽いため、ブレーキをかけた際に車よりも短い距離で停止できます。そのため、車間距離を詰めて走行しているケースも多いです。
この特徴を車の運転者が理解していないと、バイクが急ブレーキをかけた際に、後続車のブレーキが間に合わずに追突事故になる恐れがあります。
万一に備えて車間距離を十分に確保して走行してください。後続車が車間距離を十分に取っていないと感じた場合、可能であれば道を譲ることなども検討しましょう。
スピードの出しにくいバイクの場合、あおり運転の対象になってしまうケースも珍しくありません。あおり運転により焦って急ブレーキをかけてしまうと、後続車に追突されて大事故につながる場合があります。
あおり運転をされたら、焦らず冷静に対処しましょう。道を譲ったり走行車線を変えたりするなどして、あおり運転者を刺激しないようにしてください。
バイクのメンテナンス不足が事故につながるケースもあります。特に車検のない250cc以下のバイクの場合、多少バイクに異変があっても、気にせず運転してしまうケースが多いです。
走行中にハンドル操作やブレーキが効かなくなると、大事故につながる可能性が高いです。
バイク事故では、他の事故よりも被害が大きくなる傾向にあります。
令和3年度版交通安全白書(内閣府)によると、2020年(令和2年)に起きた交通事故の死亡率・重傷率は以下のとおりです。
【死亡率と重傷率の合計】を見てみると、バイク事故の重傷率・死亡率は自動車事故の5倍以上になっていることがわかります。
バイクは車のように身体が守られていません。エアバッグなどの安全装置もないため、事故の衝撃で身体は大きく投げ出されてしまいます。頭部や胸部を強く打ち付けられる可能性や、路上に引きずられることにより全身火傷を負う可能性もあるでしょう。
車よりも加速しやすいという特性上、スピードが出ている状態で事故に遭うケースが多いのも特徴です。また、風の影響や操作ミスによりバランスを崩しやすいこともあり、他の運転者が予期できないタイミングで転倒することで大事故につながる可能性もあるのです。
バイクを運転する際は、万一に備えて以下の対策をおこないましょう。
警視庁が公表しているデータによると、2018〜2023年の5年間に起きたバイク事故の致命傷部位は、以下のとおりとなっています。
バイク事故では、頭部や胸部を負傷する確率が非常に高いです。ヘルメットやプロテクターを正しく装着することで、死亡する確率や重傷を負う可能性を低くできます。
ヘルメットを着用する際は、事故の衝撃でヘルメットが脱げないようしっかりあご紐を締めてください。顔を覆う面積の広いヘルメットの方が、事故時の衝撃を和らげやすいです。ただし、視界が狭まるリスクもあるので、自分がより安全に運転できるヘルメットを選ぶようにしましょう。
バイクを運転する際は、車以上に安全運転を心がけてください。交通ルールを守るのはもちろん、譲り合いの精神を持って運転することで、あおり運転の対象になりにくくなります。
心に余裕があれば、重大な事故につながるような無謀な運転もなくなるでしょう。
定期点検やメンテナンスは忘れずにおこなうようにしましょう。故障に気づかないまま運転すると、いざというときにブレーキが効かないなどのトラブルにつながる可能性があります。
12ヶ月点検・24カ月点検などの法定点検や250ccを超える場合の車検など、定期的なメンテナンスを必ずおこなうようにしてください。それ以外にも、少しでも異変があればすぐに整備をしてもらうようにしてください。ブレーキの効き具合やライトの点灯、オイル漏れなどは自分でも確認することができます。
警視庁の統計データによれば、バイク事故は出勤時間である午前8時から10時まで、退勤時間である午後4時から午後8時までに多く発生しています。
通勤・通学の時間帯は交通量も多く、急いでいることから運転も荒くなりがちです。渋滞を避けるために無謀なすり抜けをするケースも多く見られます。焦って運転すると、信号や一時停止を見落とす可能性もあり事故のリスクはさらに高くなります。
退勤時には夜間で見通しが悪くなっている場合も多いので、「もしかしたら自分の存在に気づいてないかもしれない」と常に考えて運転をするようにしてください。
もしバイク事故で被害者になってしまった場合には、以下の対応をおこないましょう。
バイクを運転中に事故に遭ってしまったら、大きなけがをしていなかったとしても必ず警察に通報してください。小規模な事故でも警察に通報すべき理由は、以下のとおりです。
警察に通報したら、事故現場や事故車両の写真・動画を撮影しておきましょう。また、バイク用のドライブレコーダーを搭載していた場合には、事故時の記録が消えないよう保存しておくのも忘れないようにしましょう。
事故後の対応が一通り終わったら、なるべく早く病院で受診してください。外傷がなかったとしても、頭や身体を強打している以上、精密検査を受けておくことは重要です。
交通事故の場合、あとから症状が出てくるケースも多いです。事故直後に受診しておかないと、「事故で負ったけがではない」と保険会社に主張されてしまい、治療費や慰謝料を減額される恐れがあります。
治療の結果、医師に症状固定と判断された場合には、後遺障害等級の認定申請をおこないましょう。後遺障害慰謝料や後遺症逸失利益などの賠償金を請求できるようになります。
バイク事故では、保険会社との示談交渉において過失割合でもめるケースも多いです。
車とバイクで事故になった場合、より危険なバイクの方が過失割合で有利になる可能性が高いです。一方で、バイクによる危険なすり抜けや追い越し、ヘルメットの未着用などが原因で重大な事故を引き起こした場合、過失割合が車に有利になるよう修正される可能性があるのです。
定期的にメンテナンスをおこない、事故時も安全な運転を心がけていれば、過失割合でも有利な主張を認めてもらえる可能性が高いです。
過失割合は賠償金額に大きく影響します。事故状況によっては数百万円単位で損をすることになるため、過失割合でもめたら専門家である弁護士に相談しましょう。
バイクは車体が小さく小回りがきくことから、車の死角に入りやすいです。危険なすり抜けや無謀な追い越しをおこなうと、重大な事故につながるでしょう。
バイクの運転者は身体が剥き出しなことから、事故が起こった場合に頭部や胸部の強打による死亡率・重傷率も高くなっています。万一に備えてヘルメットやプロテクターをしっかり装着しておきましょう。
もし保険会社との事故交渉でもめたら、早めに交通事故に強い弁護士に相談しましょう。特に死亡事故や重度の後遺障害が残るような事故では、弁護士に依頼することで大幅に示談金を増額できる可能性が高いです。


 人身事故の罰金・罰則と違反点数は?物損事故との違いや事故後の対応も解説
人身事故の罰金・罰則と違反点数は?物損事故との違いや事故後の対応も解説 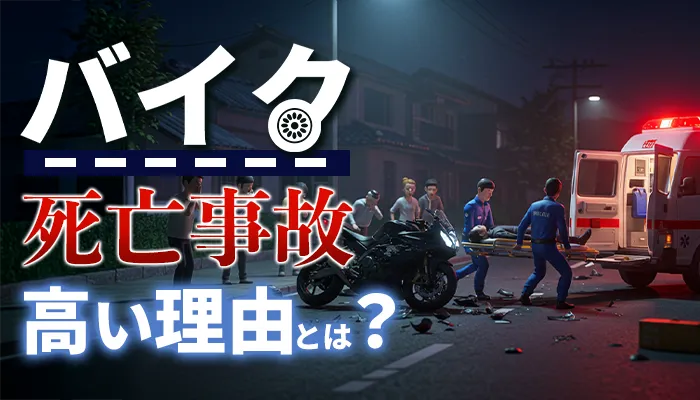 バイク事故の死亡率はなぜ高い?原因や事故時の対処法を解説
バイク事故の死亡率はなぜ高い?原因や事故時の対処法を解説 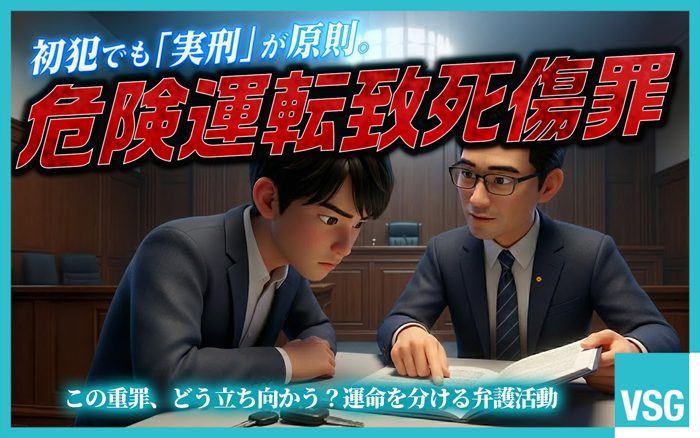 危険運転致死傷罪とは?初犯でも実刑はある?量刑や判例を解説
危険運転致死傷罪とは?初犯でも実刑はある?量刑や判例を解説  自転車と自動車の事故の過失割合はどう決まる?事故状況の例と併せて解説
自転車と自動車の事故の過失割合はどう決まる?事故状況の例と併せて解説 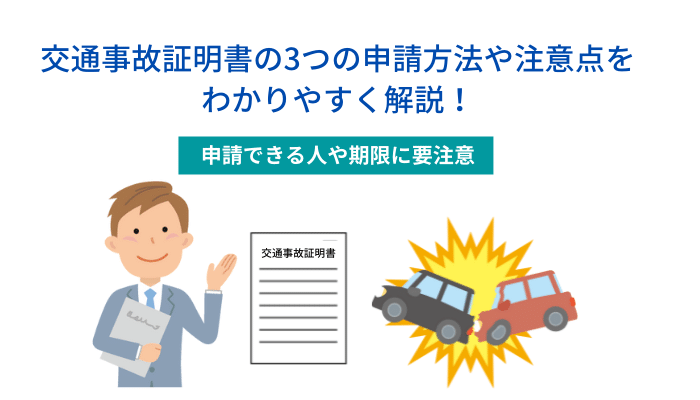 交通事故証明書の3つの申請方法や注意点をわかりやすく解説!申請できる人や期限に要注意
交通事故証明書の3つの申請方法や注意点をわかりやすく解説!申請できる人や期限に要注意  交通事故における少額訴訟の費用と手順
交通事故における少額訴訟の費用と手順 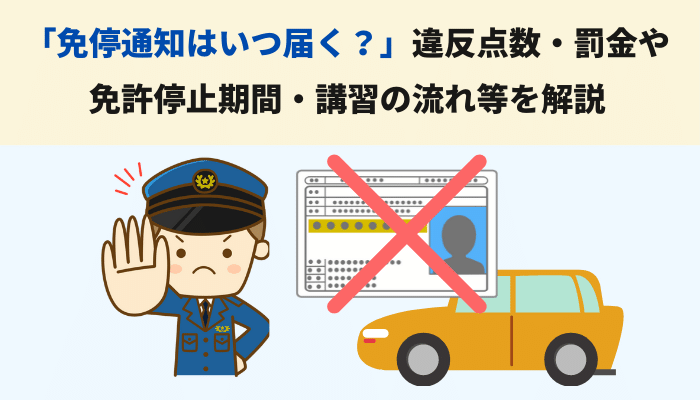 「免停通知はいつ届く?」違反点数・罰金や免許停止期間・講習の流れ等を解説
「免停通知はいつ届く?」違反点数・罰金や免許停止期間・講習の流れ等を解説  都内の自転車事故による死亡事故統計 事故に遭わないために知っておくべき交通ルール
都内の自転車事故による死亡事故統計 事故に遭わないために知っておくべき交通ルール 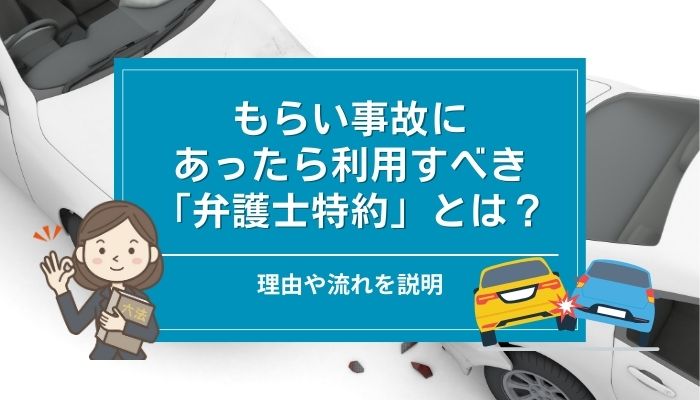 もらい事故にあったら利用すべき「弁護士特約」とは?理由や流れを説明
もらい事故にあったら利用すべき「弁護士特約」とは?理由や流れを説明