

東京弁護士会所属。
交通事故の程度によっては、入院が必要になったり、定期的な通院、精神的にも疾患を負ったり、PTSDとして現れることもあります。
こうした状況の中で、交渉ごとを被害者本人でまとめようとすることは非常に大変です。
弁護士に示談交渉を依頼することで、直接示談交渉をしたり、資料を準備したりする精神的負担が軽減できます。
つらい事故から一日でもはやく立ち直るためにも、示談交渉は弁護士に任せて、治療に専念してください。

交通事故の示談書とは、事故の当事者がお互いに合意した内容を記載した書面のことです。
示談書は、お互いの合意内容を証拠として残すという意味で非常に重要です。
しかし、交通事故に初めて遭う人からすると、示談書の書き方や書くべき内容などで迷ってしまうことも多いでしょう。
被害額の小さい物損事故では、保険を使わずに自分で示談書を作成しなければならないケースもあります。
この記事では、保険を使わずに自分で示談交渉を進めるメリットやデメリット、示談書の書き方や書くべき内容などについてわかりやすく解説していきます。
目次
被害の小さい物損事故の場合、保険を使わずに当事者同士の話し合いで示談するケースもあります。
保険を使うべきかどうかを適切に判断するためにも、保険を使わないで自分で交渉を進めるメリットとデメリットをしっかり把握しておきましょう。
保険を使って修理代として保険金をもらった場合、等級が下がり翌年からの保険料が高くなります。治療費や慰謝料で賠償金が高額になる人身事故と違い、けががなく修理代もそこまで大きくない物損事故で保険を使うと、かえって損をしてしまうことがあるのです。
また、保険会社によっては忙しさを理由に対応を後回しにされてしまうケースもあります。保険会社に示談交渉を任せると、交渉を早く終わらせるために、事故状況を十分に検証せず適正でない過失割合で交渉をまとめてしまうこともあります。
保険を使わず自ら示談交渉をおこなえば、保険料が上がったり、納得行かない条件で示談したりすることを避けることができます。
交通事故による示談交渉を自らおこなうとなると、大変な労力と時間がかかります。相手によっては交渉が長引くこともあるうえ、心無い言葉を浴びせられて不快な思いをさせられることも珍しくありません。
なかには「こちらに有利な条件で交渉に応じないなら、家族がどうなっても知らないぞ」などと、脅迫まがい交渉をしてくる人もいるかもしれません。自分で交渉をするとなると、そういった危険性があることも考慮しておく必要があります。
交通事故に遭うと、加入している保険会社が示談交渉を代行してくれるケースが多いです。この示談代行サービスにより、相手方との交渉による精神的ストレスを軽減することができます。
しかし、事故の種類によっては、保険会社の示談代行サービスを利用できない場合があります。
いわゆるもらい事故で過失が一切認められない場合、保険会社の示談交渉をサービスを利用することはできません。
もらい事故とは、被害者に一切過失がなく相手方のみに過失が認められる交通事故です。信号待ちで後ろから追突された場合や、停車中に相手が中央線を越えて接触してきた事故などが、もらい事故の例として挙げられます。
お互いに過失が認められる事故の場合、被害者も加害者に対して損害を賠償する義務を負います。過失割合や損害の程度によっては被害者のみが賠償責任を負うケースもあるため、被害者の保険会社は自社の損失を少なくするために示談交渉を代行できます。
一方、もらい事故で被害者に過失が一切認められない場合、被害者側の保険会社が損失を負うことはありません。被害者の利益のためだけに示談交渉をおこなうことは弁護士法で禁止されているため、もらい事故の場合には示談代行サービスを使えないことになるのです。
交通事故の示談交渉を自分でおこなった場合でも、示談書は作成することをおすすめします。示談書を作成すべき主な理由は、「合意した示談内容について証拠が残ること」です。
法律上、示談は口約束でも成立します。つまり、当事者間で示談に合意できるのであれば、わざわざ示談書を作成する必要もないことになります。
しかし、示談書を作成しておかないと、あとで合意内容について争いになった場合にお互いの主張を証明する証拠がありません。「言った、言わない」の水掛け論になった場合、余計なトラブルになってしまう可能性があるでしょう。
「交渉で決まった内容を変更したい」「払いすぎたから返してくれ」と言われてしまうと、せっかくまとまった話も振り出しに戻ってしまいます。こうした問題が起こらないように、合意した示談内容を明確にした書面を残しておく必要があるのです。
自分で示談書を作成する場合、示談書が無効になるケースも頭に入れておく必要があります。
示談書が無効になるケースとは、主に「詐欺または脅迫による示談や公序良俗に反する場合」と「示談時に予想できなかったことが起きた場合」です。
加害者側が被害者に対して脅迫まがいのことをしてきた場合や、騙されて示談をしてしまった場合には、成立した示談を取り消すことができます。
たとえば、加害者が被害者に対して「示談しなかったらどうなるかわかってるだろうな」と脅迫した場合や、「必ずあとで払うから、とりあえずこの書面にサインして欲しい」などと嘘をつき、示談金ゼロの示談書にサインさせた場合などがこれに当たります。
また、示談書の内容が公序良俗に反するような場合も無効になります。たとえば、軽微な事故で慰謝料額を1億円とするなど明らかに相場からかけ離れている場合には、その示談は無効となる可能性が高いです。
交通事故では、事故直後は痛みがなかったものの、時間が経ってから突然症状が出始めることがあります。もし示談時に予測できないことが起こった場合には、示談内容とは別に追加の賠償が認められる場合があります。
交通事故の示談書は、示談金の金額や支払方法について、被害者・加害者双方が合意した証拠を残す非常に重要な書面です。
この示談書は、一度でも署名・捺印すると基本的に撤回できません。あとになって「内容を勘違いしていた」「金額を訂正したい」と思っても訂正することができないため、作成する際は丁寧に内容を確認する必要があります。
示談書の書式は自由ですが、あとあとトラブルにならないよう記載内容はしっかり把握しておく必要があります。
なお、物損事故における示談書の書き方については、こちらの記事もご参照ください。
→【テンプレート付き】物損事故で示談書の簡単な書き方は?注意点を解説
当事者(被害者・加害者)の氏名と住所を正確に記載しましょう。記載内容に誤りがないよう、免許証やマイナンバーなどを確認しながら作成するのがおすすめです。
示談書には、交通事故が起きたときの状況を詳細かつ正確に記載しなければなりません。
記載する具体的な内容は、主に以下のとおりです。
ここで間違った内容を記載してしまうと、示談書としての効力を失ってしまうこともあります。「交通事故証明書」を見ながら示談書を作成すると、誤った内容で示談書を作成してしまうのを防げます。
なお、「交通事故証明書」は各都道府県の交通安全運転センターから発行してもらえます。
また、保険会社から示談書の雛形が送られてくる場合もありますが、交通事故証明書の通りに正確な内容が記載されているか、サインする前に必ず確認しておくようにしましょう。
示談書には示談の条件についても記載する必要があります。まずは、事故の過失割合について記載しましょう。加害者と被害者が負うべき責任割合を、「10:0」や「7:3」といった具合に記載します。
次に具体的な示談条件ですが、ここには示談金の金額・支払方法・支払いの金額などについて記載します。事故によって生じた損害として、車の修理代やレッカー代、代車費用などを算出し、合計した示談金額を記載します。また、支払方法については、銀行の支店名や口座番号、支払いの期限などについて記載します。
もし仕方なく分割払いになる場合には、支払いが滞った場合に備えて連帯保証人をつけておくと安心です。また、いざというときに財産を差し押さえられるよう、示談書を公正証書にしておくとよいでしょう。
なお、保険会社が示談書を作成し送ってきた場合には、示談金の内容について注意が必要です。保険会社としてはできる限り支払い金額を抑えたいと考えているため、本来被害者がもらえるはずの適正な賠償金額より少額であるケースが多くみられます。
もし相場からかけ離れた金額を提示された場合には、早めに交通事故に強い弁護士に相談してみましょう。
お互いに合意し示談書を作成したにもかかわらず、支払い期日を過ぎても相手が示談金を支払わずに踏み倒そうとしてくる場合があります。このような場合に備え、支払いが滞った場合の違約金に関する条項を付け加えておきましょう。
「期日までに支払いがなかった場合には、年率○%の遅延損害金を支払う」旨の条項を記載することが多いですが、利率や督促について適切な内容を記載するには法的知識が必要不可欠になるため、弁護士のサポートを受けた方がよいでしょう。
交通事故における示談書とは、「交通事故に関連する賠償などにつき、お互いに合意したことの証明書」です。示談書を作成したにもかかわらず、あとになって「あなたにも過失があったのではないか」「やっぱり金額が納得いかないから返せ」と主張されると、何のために示談書を交わしたのかがわからなくなってしまいます。
こういったトラブルを防ぐために、「この示談書で取り決めた内容で、今回の事故に関する交渉は終わりにし、この取り決め以外に再度金銭などの請求をしない」といった旨を記載します。この条項を「清算条項」といいます。
精算条項が記載された示談書にサインした場合には、原則として示談金の追加請求が認められなくなります。
清算条項がある限り、示談後は原則として追加請求が認められません。しかし、示談当時に予期できなかった、あるいは予期された以上に症状が悪化し後遺障害が発生するなど、著しく事情が変わってしまうこともあります。そのような場合には、例外的に損害賠償などの追加請求が認められる場合があります。
とはいえ、示談書に記載していない追加請求となれば、相手側も不満に思いトラブルになる可能性も高いです。あとあとのトラブルを避けるためにも、予期していなかった後遺障害に関する「留保事項」を入れておきましょう。
留保事項とは、「もし示談書の締結後に後遺障害などが生じたときは改めて追加の賠償について協議する」といった内容の条項のことです。精算条項と合わせて留保事項についても必ず記載しておきましょう。
示談書作成は複雑で手間がかかるため、つい手を抜いてしまいトラブルになってしまうケースが多くみられます。無用なトラブルを避けるためにも、以下の注意点をしっかり確認しておきましょう。
示談書を作成するタイミングは、被害額が確定したときです。
保険会社によっては、全ての損害が確定する前に示談を持ちかけてくる場合があります。交通事故に遭うと何かと時間も取られるうえ、精神的な負担も大きくなります。このときに保険会社から示談の申し出があると、断ること自体が面倒に思ってしまい、即座に示談してしまうこともあるでしょう。
損害が確定していないにもかかわらず示談を成立させてしまうと、本来もらえるはずだった適正な金額よりもはるかに少ない金額で示談してしまう危険性があります。示談成立後に修理箇所が新たに見つかることも少なくないので、修理費などの被害額が確定してから示談交渉を開始しましょう。
保険会社との間で示談をした場合はあまり心配ありませんが、当事者同士で示談をした場合、相手が示談金の支払いを踏み倒そうとしてくる可能性があります。
示談書があれば安心と思いがちですが、ただ示談書があるというだけでは、強制的に示談金を支払わせることはできません。示談書があるからと強引な方法で督促や取り立てをすると、逆に訴えられることもあるため注意が必要です。
相手側が示談書に基づく支払いをしない場合には裁判を通して賠償請求する必要がありますが、裁判をするとなると時間も手間もかかってしまいます。
そのため、裁判にする時間と手間を省くためにも、示談書を「公正証書」にしておくのがおすすめです。公正証書は、公証役場で公文書として作成された契約書のことです。示談書を公正証書にしておくと、支払い期日に金銭が支払われなかったときに、裁判の手続きをすることなく相手側の財産を差し押さえることが可能となります。
公証人手数料などがかかるものの、後々のリスクを下げるためには公正証書の作成も検討してみましょう。
示談書に一度でもサインしてしまうと、あとになって不満があっても基本的に訂正することはできません。
そのため、自ら示談書を作成するときはもちろん、保険会社から示談書が送られてきたときは内容を慎重に確認し、少しでも不安や疑問な点があれば弁護士に確認してもらうようにしましょう。
賠償金の請求には時効があり、この時効が過ぎると、相手側に損害の賠償を請求できなくなってしまいます。物損事故の場合、事故発生日から3年経過すると賠償請求ができなくなります。事故から時間が経っている場合には、時効が完成する前に速やかに賠償請求をおこないましょう。
なお、刑事処分への影響を考えて、時効期間を過ぎていても加害者側の希望で賠償金が支払われることがあります。ただし、これはあくまでも加害者の任意で支払われるものなので、基本的に時効が過ぎたら賠償請求はできないと考えておきましょう。
示談の代理人として交渉するのは保険会社や弁護士、親族などですが、弁護士以外の人が報酬を得ることを目的として他人の事件を処理することは、法律で禁止されています。にもかかわらず、「事件屋」「示談屋」と言われる人が、示談交渉に現れることがあります。高額な報酬を得るために代理人となり、なかには高圧的な態度で示談を有利に進めようとしてくる人もいるでしょう。
こういった類の人と示談交渉をすると、余計なトラブルになることがあります。事件屋や示談屋かもしれないと疑いを持ったら、示談交渉自体を拒否した方がよいでしょう。困ったら早めに弁護士に相談しましょう。
示談書は、交通事故の当事者双方が合意した内容を書面にしたものです。
示談には複雑な裁判手続きをしなくても良いというメリットはありますが、中立な立場である裁判所が間に入らないためトラブルになる可能性も高いです。示談書にサインすると原則として示談のやり直しができないので、細心の注意を払って示談する必要があるでしょう。
少しでも示談書作成に不安があるなら、交通事故に強い弁護士に相談することも視野に入れた方が良いかもしれません。交通事故に強い弁護士なら示談金を引き上げることができるケースもあるうえ、一人で手続きを進めなければいけない精神的負担から解放されます。
弁護士費用特約を使えば多くのケースで無料で弁護士に依頼できます。相談したからといって必ずしも依頼しなければいけない訳ではないので、まずは気軽に相談してみましょう。


 物損事故とは?人身事故との違いや損害賠償、事故から示談までの流れについて
物損事故とは?人身事故との違いや損害賠償、事故から示談までの流れについて  物損事故の示談書に記載すべき内容・書き方【保険を使わないで自分で交渉を進めるメリット・デメリットも解説】
物損事故の示談書に記載すべき内容・書き方【保険を使わないで自分で交渉を進めるメリット・デメリットも解説】 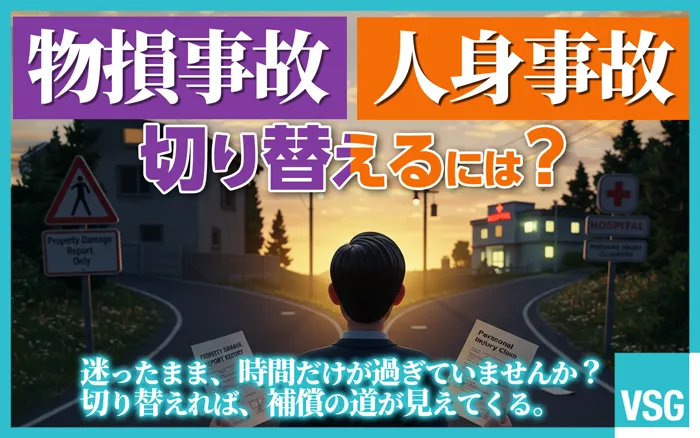 物損事故から人身事故への切り替え方法は?メリットや手続きの流れを解説
物損事故から人身事故への切り替え方法は?メリットや手続きの流れを解説  交通事故で車の修理代を払えないと言われたら?踏み倒されたときの対処法
交通事故で車の修理代を払えないと言われたら?踏み倒されたときの対処法  駐車場で当て逃げされたが気づかなかった時の対処法【加害時の対応も解説】
駐車場で当て逃げされたが気づかなかった時の対処法【加害時の対応も解説】 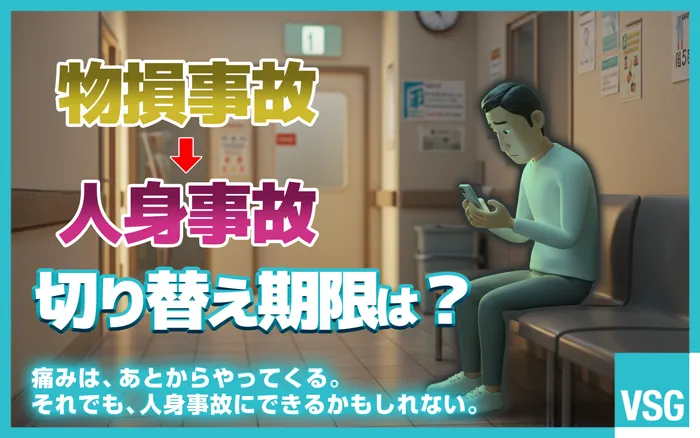 物損事故から人身事故への切り替え期限は?1カ月後でも変更できる?
物損事故から人身事故への切り替え期限は?1カ月後でも変更できる? 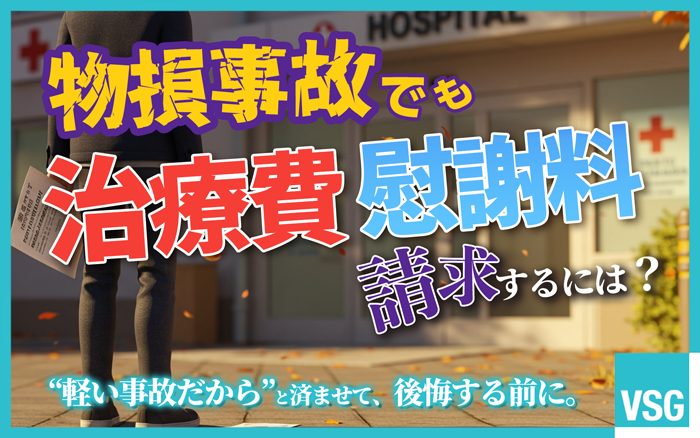 物損事故でも治療費や慰謝料は請求できる?方法や人身事故への切り替え方を解説
物損事故でも治療費や慰謝料は請求できる?方法や人身事故への切り替え方を解説  交通事故の物損事故の修理費は誰が払う?相場や払ってもらえないケースまとめ
交通事故の物損事故の修理費は誰が払う?相場や払ってもらえないケースまとめ  交通事故の物損事故で念のため病院に行くべきケースとは?行けば人身事故になる?
交通事故の物損事故で念のため病院に行くべきケースとは?行けば人身事故になる?