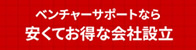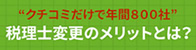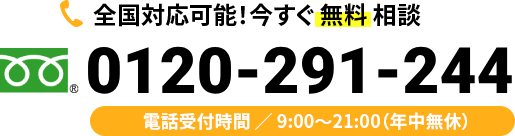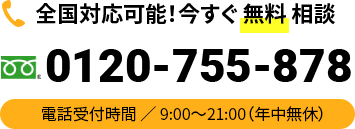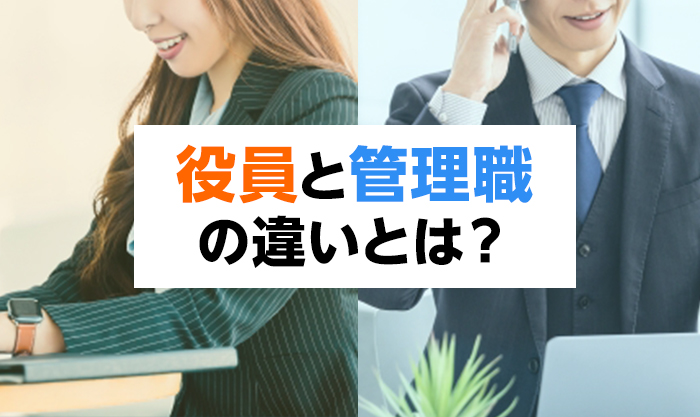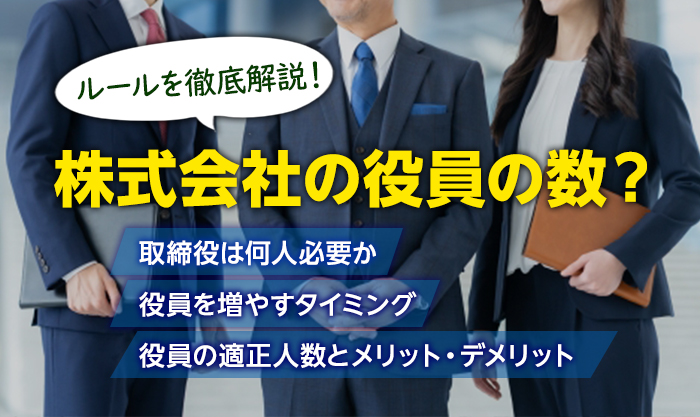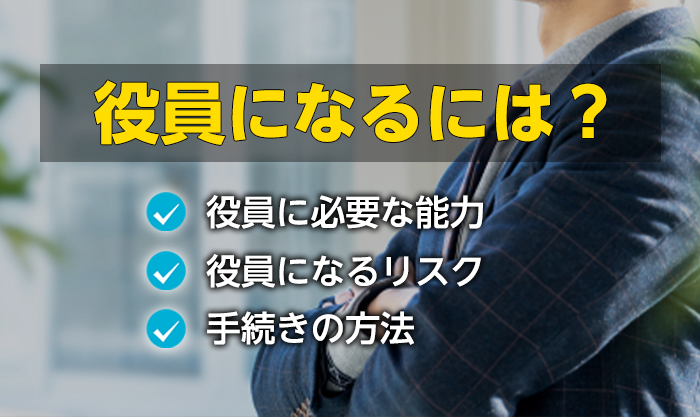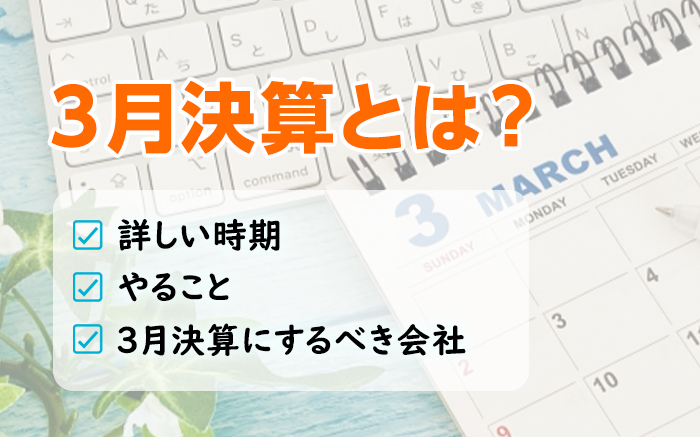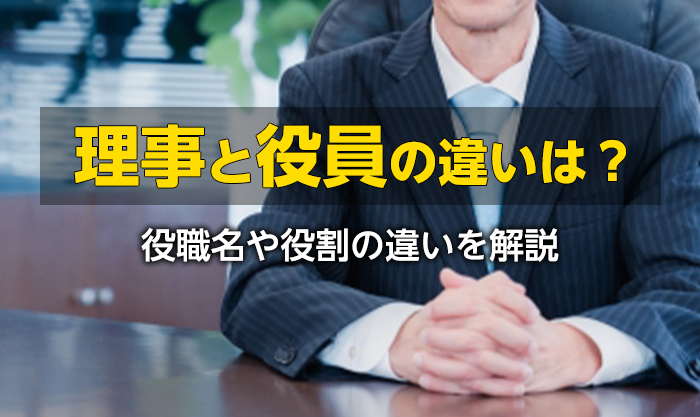最終更新日:2025/5/21
親の会社の役員になっていても副業できる?役員と副業の疑問や問題点を解説します

ベンチャーサポート税理士法人 大阪オフィス代表税理士。
近畿税理士会 北支部所属(登録番号:121535)
1977年生まれ、奈良県奈良市出身。
起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネルを運営。
PROFILE:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_writing/#p-mori
YouTube:会社設立サポートチャンネル【税理士 森健太郎】
書籍:プロが教える! 失敗しない起業・会社設立のすべて (COSMIC MOOK) ムック
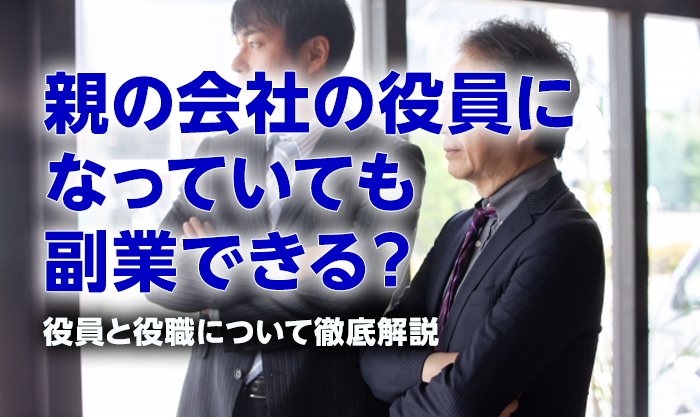
この記事でわかること
- 役員の副業は可能なのか
- 副業が禁止されるケース
- 役員が副業をするとどのような影響があるのか
「親の会社の役員になっているけど、副業はできるの?」と疑問に思う人も多いでしょう。
一般に、会社経営に関わる役員は副業をしてはいけないように思われがちですが、法律で役員の副業が禁止されているわけではありません。ただし、会社の就業規則や役員としての委任契約、競業禁止規定には違反する可能性があるため注意が必要です。
また、副業をすると、税金の負担が増える、保育料や高額療養費制度の上限額が上がるといった負の側面もあります。この記事では、役員の副業に関する法律や就業規則、税金や社会的影響、公務員の副業制限について解説します。役員の副業について知りたい方はぜひ参考にしてください。
親の会社の役員になったら副業できない?
会社の役員が副業できるかは状況によって異なります。役員という立場は会社経営に深く関わっているため、一般の会社員とは異なる制約がある場合があります。しかし、法律上、役員が副業をすることが一律に禁止されているわけではありません。これは、親の会社の役員になっている場合も同様です。
ただし、副業が本職の競業にあたる可能性がある場合や、会社の規則で副業が制限されている場合は注意が必要です。
原則として職業は自由
日本の憲法では「職業選択の自由」が保障されています。基本的にどのような職業に就くかはすべて個人の自由です。そのため、会社の役員でも法律で副業が全面的に禁止されるわけではありません。
会社の役員が別の会社と雇用契約を結ぶことも、会社員が親の会社の役員になることもできます。もちろん、フリーランスとしての副業も可能です。
ただし、会社の業務と競合するような副業をした場合や、就業規則や役員としての委任契約の内容によっては問題になるケースがあります。
役員の副業が禁止されるケース
職業選択の自由が保証されているため、役員の副業に法的な問題はありません。ただ、会社の就業規則や委任契約の内容によっては副業ができないケースもあります。
会社の就業規則や契約
役員が副業をできるかは「会社の就業規則」と「委任契約の内容」がポイントになります。
まず、親の会社などですでに役員になっている人が別の会社で副業しようとする場合、その会社の就業規則で副業が禁止されていないかを確認する必要があります。もし会社で副業が禁止されていたら、別の会社の役員が従業員として働くことを受け入れない可能性があります。副業がフリーランスの場合は就業規則がないため特に問題はありません。
また、役員として会社と締結した委任契約において、同業他社での副業が禁止されている場合は、同業の会社への就職はできないと考えたほうがいいでしょう。フリーランスとして副業をする場合も、委任契約の内容はチェックしましょう。
会社員として働いている人が別の会社の役員になろうとする場合も、就業規則と委任契約の内容には注意が必要です。
不正競争防止法について
役員が副業をする場合、不正競争防止法という法律に抵触しないか注意する必要があります。これは、副業の形態に関わらず注意すべきポイントです。
例えば、会社から顧客情報を持ち出したり、会社の機密事項を漏洩させてしまうと不正競争防止法に触れる可能性があります。
名前だけ貸している役員の場合
役員のなかには、親の会社で役員になっているケースで、名前だけ貸しているという場合があります。
たとえ名前だけ貸しているという状況であっても役員であることには変わりないため、就業規則や不正競争防止法には抵触しないように注意が必要です。
会社員が役員になる場合
ここまで、役員が自社以外の会社で副業をするケースを想定して解説しました。ここからは、会社員が自社以外の会社の役員になろうとするケースについて解説します。
会社員が役員になることは違法ではない
役員の場合と同様に、会社員が自社以外の会社の役員になることを禁止している法律はありません。
会社員として働きながら親の会社の役員になることもできます。もちろん、会社から役員報酬を受け取っていたとしても違法ではありません。
会社に知られてしまうとペナルティーがあるケース
会社員が自社以外で役員になる場合は、会社の就業規則をチェックする必要があります。
就業規則に副業禁止とある場合は、法律に違反していなくても就業規則に違反していると会社から社内的なペナルティーを受ける可能性があります。
名前だけ貸していて無報酬の場合
役員のなかには、家族や親戚、親しい人から頼まれて無報酬で名前だけ役員になっているというケースがあります。
「無報酬なら問題ない」と考えてしまうかもしれませんが、このような場合に会社からのペナルティーがあるかはケースバイケースです。就業規則での副業禁止は法律によるものではなく会社ごとに判断するものであるため、会社によってはペナルティーの対象になるケースもあります。
たとえ名前だけを貸して役員としての活動は一切していない無報酬のケースでも、就業規則に違反していると判断される可能性はゼロではありません。
会社にバレる原因
会社員が自社以外の役員になったことを会社に必ず報告しなければならないというわけではありませんが、役員であることを知られてしまう可能性はあります。
登記を見られてしまう
会社法上の役員は、必ず登記しなければならないと会社法で決められています。
そして、登記されている内容は、会社と無関係の人であっても法務局に行けば閲覧することができるため、登記を見られると会社に自社以外の役員であることが知られることになります。
税金の通知
給与所得者の場合は、税金の通知で会社に知られてしまう可能性があります。これは、給与所得者の場合、会社が住民税を給与から差し引いて納付しているためです。
各自治体から「給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収税額の決定通知書」という書類が送られます。
副業の役員報酬にも当然税金がかかるわけですが、所得が増えると住民税の金額が上がるため、ここで「別の収入がある」と知られてしまうのです。
うっかり話してしまう
役員であることをうっかり話してしまってバレるというケースがあります。
例えば、飲みの席などでお酒が入ってうっかり話してしまったり、会社の人が近くにいるときに電話の内容を聞かれてしまうといったケースもあります。
就業規則で副業が禁止されているが役員になっているという場合や、親の会社の役員として報酬をもらっていることを会社に伏せておきたいという場合は、自分から話してしまわないように注意しましょう。
会社員が副業をするとどんな影響があるのか
会社員が自社以外で役員をするなどの副業をした場合、さまざまな場面で影響が出るため注意しましょう。
所得が増えると税金が増える
役員報酬を得て所得が増えると、所得税や住民税の負担が増加します。
日本は累進課税を採用しているため、所得が上がると税率も上がります。税金の負担が増えれば、さまざまな場面で影響が出ることになります。
保育料が上がる
副業をして収入が増えると保育料が上がる可能性があります。
認可保育園の保育料は各自治体が決定しますが、多くの場合「住民税所得割額」を基準に計算される仕組みになっています。
そのため、役員報酬で全体の収入が増えると、保育料の負担が増える可能性があるのです。
高額療養費の上限
副業をして所得が上がると、高額療養費で支払う自己負担額が上がる可能性があります。高額療養費制度とは、1カ月で支払う保険適用の医療費が上限を超えた場合に、その超えた金額が還付されるという制度です。
この制度の自己負担額の上限は前年度の収入によって決められるため、役員報酬で所得が増えると、翌年度から高額療養費の自己負担額が増える可能性があります。
奨学金
一部の奨学金には、親の収入で制限が設けられているものがあります。
子供が奨学金を受けようとしている場合は、その奨学金制度に親権者の収入に関する基準があるかを確認しましょう。
家族を役員にする場合の注意点
ここからは、家族を会社の役員にする場合に注意したいポイントについて解説します。
会社の就業規則に違反していないか
まず、役員にしようとしている家族が会社員の場合は、会社の就業規則に違反していないかをチェックする必要があります。
特に、同業にあたる場合は競業禁止のルールについてしっかりと確認する必要があります。
確定申告が必要になる可能性
役員になって役員報酬を得た場合は確定申告が必要です。会社員の場合は、自分で確定申告をする必要はありませんが、役員報酬を受け取ると確定申告をして納税しなければなりません。
年に一度、確定申告の手間がかかるということを知っておきましょう。
公務員の場合は原則として副業はできない
ここまで、役員と副業について解説してきましたが、会社員ではなく公務員の場合は法律で副業が禁止されているため役員になることは原則としてできません。
公務員はなぜ副業禁止なのか
公務員の副業は、法律で禁止されています。
国家公務員の場合は「国家公務員法」、地方公務員の場合は「地方公務員法」でそれぞれ副業が禁止されています。
公務員の副業が禁止されている理由は、公平性を保ち国民からの信頼を損ねないようにするためとされています。
参考:国家公務員法 第百三条|e-Gov 法令検索
参考:地方公務員法 第三十八条|e-Gov 法令検索
任命権者の許可がなければ禁止
公務員は副業が禁止されているため、会社の役員になることも禁止されています。たとえ、無報酬であっても会社の役員(兼業役員)になることはできません。
農業や不動産賃貸などの自営の場合であっても、任命権者の許可がなければなりません。
公務員でも副業が認められるケース
公務員の副業は禁止されていますが例外もあります。
例えば、著作物の権利によって発生する印税などの報酬は副収入として認められています。その他、株・仮想通貨への投資、家業なども例外的に副業として認められています。
ただし、会社の役員になることが必ずしも例外にあたるというわけではありません。そのため、公務員が親の会社の役員になろうとする場合は、任命権者の許可を取ったほうが安心です。
役員は兼業できるが就業規則に注意が必要
役員が副業することは法律では禁止されていません。ただ、会社の就業規則や役員としての委任契約の内容によって制限されるケースはあります。特に競業禁止のルールや不正競争防止法に抵触しないように注意が必要です。
また、会社員が別会社の役員になることも法律上問題はありませんが、会社の就業規則で制限されている場合には、会社の判断で社内的なペナルティーが発生する可能性があります。
また、副業によって収入が増えると、税金や保育料の増加、高額療養費の自己負担額の上昇などにつながることもあります。役員報酬を得る場合は確定申告が必要になるため、手間が増えることも考慮すべきです。一方、公務員は原則として法律で副業が禁止されているため、役員になることはできません。