

東京弁護士会所属。新潟県出身。
破産してしまうかもしれないという不安から、心身の健康を損ねてしまう場合があります。
破産は一般的にネガティブなイメージですが、次のステップへのスタート準備とも言えます。
そのためには、法律上の知識や、過去の法人破産がどのように解決されてきたかという知識が必要です。
法人破産分野を取り扱ってきた弁護士は、こういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって納得のいく措置をとることができます。
PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/kawasaki/
書籍:この1冊でわかる もめない遺産分割の進め方: 相続に精通した弁護士が徹底解説!
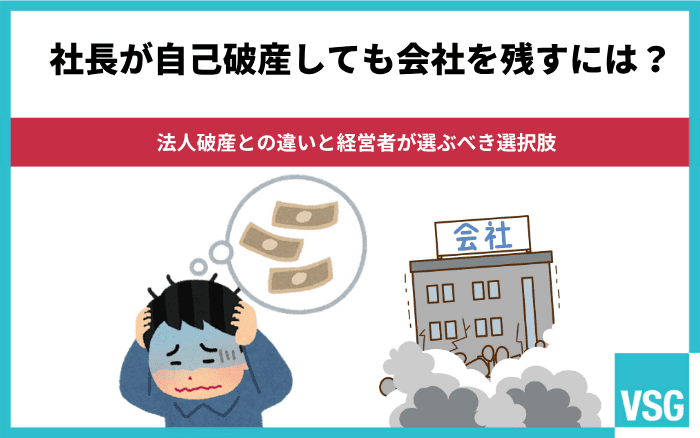
中小規模の企業の場合、会社=代表者個人だと思っている経営者の方が多いようです。
社長である代表取締役が自己破産した場合、その会社も併せて倒産するのか。会社が破産すると、社長に法的責任が発生するのか気になるところではないでしょうか。
この記事では、社長個人の自己破産と会社の法人破産との違いや、会社を存続させる方法について、くわしく解説していきます。
また、自己破産した後に再起する方法もあわせて解説します。
自己破産後も会社を存続させたい経営者の方へ、VSG弁護士法人の実績豊富な専門チームが経営者の立場に立ち問題解決をサポートします。まずは無料相談をご活用ください。
Contents
法人破産には、弁護士費用や前払いする運営費などの費用がかかります。それぞれの費用について見ていきましょう。
法人破産における弁護士費用とは、申立の準備から清算実務の伴走費にあたります。
裁判所の手続きだけでなく、破産手続きに必要な書類準備や債権者の対応も含まれています。
費用の目安は30~50万円程度で、手続きの難易度によって加算される場合が多いです。
費用の支払いは、一部を着手金として先に支払い、残りを手続き終了後、または段階的に支払う方法が一般的です。
分割支払いに対応しているかは、事務所の方針によるため弁護士事務所ごとに異なります。
詳細はこちらの記事をご参照ください。
破産手続きでは、裁判所選任の清算弁護士の活動費を前払いで支払う必要があります。
法人破産は原則、管財事件となり、裁判所選任の清算弁護士の活動費は、会社の負債額や手続きの難易度により異なります。
一般的な中小企業でおおむね50~150万円、大規模な事案では200万円以上となる場合もあります。
詳細は各地方裁判所の最新基準表を確認してください。
個人破産の手続きでは、裁判所選任の清算弁護士の活動費が20万円~25万円程度におさえられる、少額管財の制度を利用する方法もあります。
運用されている裁判所が限られるため、各地方裁判所の運用規定を確認しましょう。
法人破産では、事案によって弁護士費用以外にも様々な費用が必要です。
たとえば以下のような費用があります。
これらの費用は、会社の財産や契約の状況により異なるためケースバイケースと言えます。
法人破産では、社長が会社の保証人であるときなど、社長個人も会社と同時に破産手続きを行う場合があります。
この場合、会社と社長個人の破産手続きは別々で行い、費用もそれぞれで必要です。
2つまとめての手続きはできません。
なお、裁判所選任の清算弁護士の活動費が20万円~25万円程度ですむ少額管財は、個人破産で利用可能です。
法人破産には適用されません。
法人破産の費用が工面できない場合、早期に弁護士への相談が解決の糸口になります。
自己判断で資産を換金したり、一部の債権者への返済はやめましょう。
資産売却や債権を回収する場合は、弁護士の指示の下で行います。
また、分割支払いの可否も弁護士に相談してみるといいでしょう。
夜逃げや帳簿廃棄など不正に手を染めないよう、まずは専門家とともに、支出の優先順位を見直して計画を立てましょう。
破産手続きの費用でお困りの場合は、SVG弁護士法人の無料相談をご活用ください。
法人と社長個人の破産は別物です。
社長個人が破産しても会社は残せます。
ここでは社長が破産した場合の会社への影響や、会社存続のための近年の制度改革について解説します。
会社をたたむか迷っている方は、VSG弁護士法人の無料相談をご活用ください。
最高裁判例を含め、法律上、会社(法人)と代表取締役社長(個人)は別人格とみなされます。
どちらかが破産手続きを行ったとしても、他方も破産しなければならないわけではありません。
代表取締役個人の自己破産によって清算対象財産に組み入れられ換価されるのは、代表者個人が所有する不動産や預貯金などの個人資産のみであり、法人存続は可能です。
また、不動産等の名義が、個人ではなく会社名義となっている場合は清算対象財産に組み入れられ換価されません。
会社に対し、社長が個人保証をしている場合、社長の自己破産が会社に影響する場合があります。
しかし近年では、改定された経営者保証に関するガイドラインの運用が本格化し、保証解除の動きがみられるようになりました。
個人保証の整理や解除の運用が広がり、社長個人の破産が会社に影響を及ぼさないしくみが出来上がりつつあります。
そのため社長が自己破産しても、会社を存続させられる可能性が高いです。
さらに保証に依存しない融資慣行を促進する動きも広まっており、会社と個人が互いの影響を最小限にできる方向に進んでいます。
会社と社長個人は別人格であるとはいえ、現在でも多くの中小企業では、社長が会社の融資に対して個人保証をしています。
そのため社長個人の自己破産が、会社の信用や資金繰りに影響を与えるケースが少なくありません。
そこで経営者保証に関するガイドラインで保証解除の動きの広まりに加え、中小企業活性化協議会のスキームの活用も重要視されています。
第三者機関である協議会が関与し、客観的な事業再生計画の策定や、金融機関との交渉を円滑に進めるしくみです。
破産を回避しながら事業再生や円滑な廃業を目指す可能性が広がっています。
会社の資金繰りが悪化する中で社長が自己破産をした場合、法人は残せるでしょうか。
ここでは社長が自己破産したときの会社への影響や注意点を解説します。
社長個人が自己破産をすると、会社の借入金などで保証人となっている債務も整理対象になります。
自己破産手続きによって、個人保証の債務は免責となり、最終的に支払いを免除されます。
支払い免除になれば社長個人の負担は大きく減るため、メリットと言えるでしょう。
ただし、会社の借金がなくなるわけではありません。
社長が保証人となっていた債務については、その支払いを会社に請求される可能性が高いです。
法人と社長個人は別人格のため、社長が自己破産をしても、基本的に既存の法人名義の借り入れや契約に影響はありません。
そのため事業継続が可能な場合もあります。
ただし、個人保証をしていた場合は別です。
保証人である社長が破産すると、金融機関が会社に対して借入金の一括返済を求めてくる可能性があります。
また、社長の自己破産は、会社の信用に影響が出る場合もあるため注意が必要です。
社長が自己破産すると、会社との委任契約が終了するため、代表取締役を退任します。
株主総会で再任されれば復帰できますが、再任されなければ代表交代の可能性があるでしょう。
また、社長の自己破産により会社の信用力が下がると、金融機関からの新規融資などが難しくなる場合があります。
社長個人の自己破産により、会社の資金繰りが悪化する可能性に注意が必要です。
関連記事
東京商工リサーチによると、2020年度に破産した5,552社のうち、68.2%にあたる3,789名の社長が個人でも破産手続きを行いました。
理論上は別人格である法人と社長が、同時に破産するケースが半数以上を占めています。
ここでは法人と社長個人の破産に関する具体的な事例と、破産の判断を下すための視点について解説します。
社長個人は膨大な個人保証がもとで自己破産を行った一方、会社の事業はスポンサーが設立した新会社が引き継いだ事例があります。
元の会社は特別清算により清算しましたが、会社の事業と従業員の雇用は新会社に引き継がれました。
その結果、事業価値を維持したまま会社の再建までこぎつけました。
社長が自己破産をしても会社を存続させられた珍しいケースです。
小売業の法人が負債7000万円を抱えて破産した事例です。
負債が多く、破産手続きの費用は膨らみましたが、会社の資産を売却し、売掛金を回収して破産費用を捻出しました。
社長個人は資産がほとんどなかったため金融機関と交渉し、あえて自己破産はおこなわず、会社のみ清算をしました。
この結果、法人破産だけですみ、社長は自己破産を回避したため、生活再建への影響が最小限でした。
経営していた工務店が赤字続きで、債務超過に陥っていた事例です。
社長個人が会社の債務を連帯保証しており、返済の見込みも立たなかったため、法人・個人ともに自己破産を選択しました。
手続きの結果、法人は消滅し、社長個人は残った生活再建に必要な財産で再起を果たしました。
実際、法人・個人ともに破産するケースが最も多いパターンです。
いずれにしても、法人破産には初期費用が必要です。
破産費用について不安がある方は、VSG弁護士法人の無料相談をご活用ください。
破産について判断に迷ったときは、以下の3つの視点を意識してみましょう。
まず、引き継ぎや譲渡、M&Aなどにより、法人を継続できる可能性があるかどうかが一つの基準になります。
法人として継続性があれば、民事再生など再生型の手続きも選択肢に入るでしょう。
また、会社と同時に社長自身も破産するケースが多いため、破産後に生活再建の見通しがあるか、よく考える必要があります。
破産は社長だけでなく、従業員や家族への影響も大きいです。
雇用や生活、精神的な負荷も考慮し、判断する必要があるでしょう。
どの選択肢が最適化は個別の状況により異なります。
法人破産の初期費用に不安がある方も、まずはVSG弁護士法人にご相談ください。
会社が倒産し、破産した場合に代表取締役社長に法的責任はあるでしょうか。
ここでは法的責任の有無と、責任が発生するケースについて解説します。
会社と社長は法律上、別人格のため、原則として会社が破産しても社長個人は法的責任を負いません。
法律上、社長が会社の負債を弁済する義務はないためです。
ただし、あくまでも原則で、例外的に社長個人が責任を追及されるケースが存在します。
これらの行為があった場合、裁判所選任の清算弁護士から損害賠償を請求される可能性があります。
損害を受けた金融機関や取引先は、経営責任を負う代表取締役に損害を賠償できるように思えます。
しかし、通常範囲内の経営判断等の失敗について、社長個人は会社の責任を負いません。
また、代表取締役等の取締役は、会社とは委任関係にありますが、債権者とは直接の委任関係もありません。
一方、代表取締役などの取締役個人が職務執行上、悪意もしくは重大な過失によって債権者へ損害を与えた場合は、損害賠償責任を負います。
たとえば、会社の倒産が明白である状態で以下のような行いをした場合です。
【善管注意義務・忠実義務違反】個人的な資金流用
会社の資金を趣味やギャンブルに流用したり、個人的なローンの返済にあてていた
無謀な投資やずさんな経営
根拠のない思いつきで多額の投資を行い、無担保で多額の貸し付けを行っていた
法令違反
粉飾決算などの違反を行い、金融機関から多額の融資を得るなどの脱法行為をしていた
【詐害的行為】財産隠し
破産前後で会社の財産を知人や家族の名義に変更したり、市場価格より極端に安い価格で売却していた
偏波弁済(へんぱべんさい)
一部の債権者にだけ支払いをしたり、親族に迷惑をかけられないからなどの理由で先に返済していた
上記の場合は、会社が破産しても、取締役が負う損害賠償責任がなくなるわけではありません。
この責任は清算対象財産の一部として扱われ、代表取締役などは裁判所選任の清算弁護士から損害賠償請求を受ける場合があります。
回収された賠償金は、破産債権者への配当に充当されるケースが一般的です。
会社破産手続きでは、裁判所から選任された裁判所選任の清算弁護士が、会社の資産や債権をすべて換価処分して債権者へ配当します。
代表者が前述のような違法行為を行うと法人破産が認められません。
さらに、悪質な行為に関しては「詐欺破産罪」として刑事的な責任を問われる場合もあるため、違法行為は行わないようにしましょう。
自己破産は終わりではなく、再出発をするための法的な手段です。
全ての財産を失うわけではありません。
また、自己破産後にこれまでの経験や繋がりを活かした再起ができるよう後押しする公的支援も数多く存在します。
破産手続き後に日常生活を維持しながら、会社の再興も可能です。
ここでは破産後に残る財産や、具体的な公的支援制度について詳しく解説します。
個人が自己破産しても、すべての財産を失うわけではありません。
基本的に、個人が抱える債務が免責される代わりに個人の資産の大部分を失いますが、生活に必要な最低限の財産は手元に残ります。
この財産を「自由財産」と呼び、以下のような財産が認められています。
自由財産と認められる財産
99万円以下の現金
差し押さえが禁止されている生活に必要な財産
新得財産:破産手続開始決定後に新しく取得した財産
裁判所選任の清算弁護士が放棄した財産
拡張財産:自由財産の範囲の拡張が認められた部分
自由財産は、再度会社を立ち上げる資金とは言えませんが、最低限の財産が残り生活を維持できます。
再挑戦支援資金は、その名の通り、廃業歴のある経営者の再挑戦をサポートする日本政策金融公庫の融資制度です。
この再挑戦支援資金を利用するためには、新たに開業する方または開業後概ね7年以内の方で、以下の条件を全て満たす必要があります。
再挑戦支援資金を利用できる条件
廃業歴のある経営者が営む法人である
廃業時の負債が新事業に影響を与えない程度にまで整理される見込みがある
やむを得ない理由、事情で廃業した
個人事業主や小規模企業などの国民生活事業にあたる場合の融資額は、最大7,200万円(うち運転資金4,800万円)までです。
中小規模事業にあたる場合は、最大7億2千万円(うち運転資金2億5千万円)までの融資を受けられます。
融資額はあくまでも目安です。
最新の要件は公式ホームページをご確認ください。
参考:「再挑戦支援資金(再チャレンジ支援融資)」(日本政策金融公庫)
新規開業・スタートアップ支援資金は、新たに事業を始める人や、事業開始後おおむね7年以内の人を対象とした融資制度です。
融資限度額は7,200万円(うち、運転資金4,800万円)で、原則無担保・無保証人で利用できます。
以下の要件に該当する場合は特別利率が適用されます。
最新の要件は公式ホームページをご確認ください。
参考:「新規開業・スタートアップ支援資金」(日本政策金融公庫HP)
再チャレンジ支援事業は、事業再生や再起を目指す経営者のために中小企業庁が行う支援制度です。
全都道府県に設置された中小企業活性化協議会では、弁護士などの専門家が無料相談を行いながら、再生計画の策定をサポートします。
破産を回避し事業を再生したい場合や、保証債務を整理し円滑に廃業を進めたい場合など、経営者のチャレンジを後押しする制度です。
事業再生にあたり、中立的な立場で金融機関との調整も行ってもらえます。
法人破産と社長の自己破産について、よくある質問とその回答をご紹介します。
前払いした運営費は、原則として戻ってきません。
これは破産手続きを行うための実費にあてられる運営費用だからです。
裁判所選任の清算弁護士の報酬や、財産調査・換価、債権者への配当など、実務には多くの費用がかかります。
手続きを行う上での必要経費のため、手続き終了後でも費用は戻りません。
費用は、破産申立前後に必要な場合がほとんどです。
弁護士費用は契約時に着手金を支払い、裁判所には申立時に運営費の前払いを行います。
手続き完了後には、弁護士の成功報酬などが必要な場合があります。
基本的に費用は、一括支払いが一般的です。
分割支払いについては、弁護士事務所ごとに対応が異なるため相談してみましょう。
資産が全くなくても、法人破産は可能です。
破産の目的は、資産の配当だけでなく、債務を整理し法人格の消滅でもあるからです。
ただし、資産がなければ、運営費の前払いができない問題が出てきます。
破産できるかどうかは、負債の状況や手続きを進める必要性などにより、個別の判断となります。
まずは弁護士に相談してみましょう。
法人破産そのものは、社長個人の信用情報に影響を与えません。
法人と個人は別人格だからです。
しかし、日本の中小企業では、会社の債務に対し社長が個人保証をしている場合が多いため注意が必要です。
個人保証をしていると、会社と同時に社長個人も破産手続きを行うケースがほとんどです。
社長個人が自己破産すれば、信用情報機関に事故情報として登録されます。
社長の自己破産と法人の破産は法律上、別の手続きであるため、社長個人が自己破産しても会社を残せる可能性はあります。
しかし多くの中小企業では、社長が会社の個人保証を行い、連帯保証人になっているケースが多く、会社にも大きな影響を与えます。
会社を残すには、経営者保証に関するガイドラインなどを活用し、保証債務を整理する方法が有効です。
VSG弁護士法では無料相談を実施しています。
法人破産と自己破産、両方を見据えた現実的な選択をするためにも、お困りの場合は早期に弁護士にご相談ください。