

東京弁護士会所属。新潟県出身。
破産してしまうかもしれないという不安から、心身の健康を損ねてしまう場合があります。
破産は一般的にネガティブなイメージですが、次のステップへのスタート準備とも言えます。
そのためには、法律上の知識や、過去の法人破産がどのように解決されてきたかという知識が必要です。
法人破産分野を取り扱ってきた弁護士は、こういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって納得のいく措置をとることができます。
PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/kawasaki/
書籍:この1冊でわかる もめない遺産分割の進め方: 相続に精通した弁護士が徹底解説!
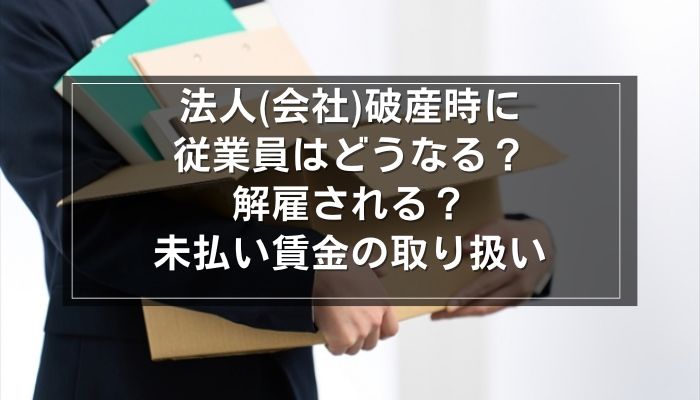
会社の事業継続が困難になり、取引先への支払不能や債務超過に陥った場合、法人破産を検討しなければならない場合もあるでしょう。
法人破産をすると会社の法人格は消滅し、従業員との雇用関係を維持できないため、従業員は全員解雇されます。
未払いの賃金や退職金がある場合、破産手続きの中で清算される財産から弁済されます。
法人破産による解雇では、従業員説明会の開催など通常とは異なる手続きが必要になるため、流れを事前に確認しておきましょう。
ここでは、法人破産で従業員を解雇するときの流れや注意点などを解説します。
Contents
法人破産をすると、勤務していた従業員は全員解雇されます。
法人破産は、裁判所の手続きで会社の法人格を消滅させる手続きです。
法人格とは、会社が取引先や従業員と法律上の権利義務を持つために与えられる資格です。
法人格が消滅すると、会社は従業員との雇用関係を維持できません。
一般的には、従業員説明会を開催して法人破産の決定を伝え、期日を定めて裁判所への申し立て前に解雇します。
正社員だけでなく、パートやアルバイト、契約社員、派遣社員など、すべての従業員が解雇の対象となります。
法人破産時の従業員を解雇する流れは、以下の通りです。
それぞれの流れについて見ていきましょう。
従業員説明会とは、法人破産で解雇される従業員へ説明を行う場です。
破産に至った経緯や未払い賃金の支払い、解雇までのスケジュールなど、従業員が不安を感じる点について説明しましょう。
従業員説明会の開催日に決まりはありませんが、破産の申し立て日から逆算して設定する方法が一般的です。
従業員と協力して法人破産の手続きを進めるときは、破産の決定後すみやかに説明するケースもあります。
一方で、会社の規模が大きく社内の混乱や情報の流出を避けたいときは、申し立ての直前まで説明会を実施しないケースもあるでしょう。
解雇通知・解雇予告手当は、突然の解雇によって従業員の生活が困窮しないように労働基準法で定められた制度です。
従業員を解雇するときは、法的な義務として以下の通知または手当の支払いをしなければなりません。
法人破産では、解雇を伝えた当日に従業員を即時解雇し、解雇予告手当を支払う方法が一般的です。
正社員だけでなく、アルバイトやパート、有期契約社員、嘱託社員など、すべての従業員が対象となります。
債権者一覧表とは、破産する会社に債権を持つ債権者の氏名や住所、債権残高、担保の有無などが記載された一覧表です。
債権者一覧表は法人破産の申し立てに必要な申請書類であり、裁判所が会社の負債状況を把握するための重要な資料となります。
従業員への未払い賃金がある場合、対象となるすべての従業員を債権者一覧表に記載しましょう。
記載が必要となるのは未払いの賃金だけでなく、未払いの退職金や手当、賞与、残業代なども含みます。
従業員は法人破産による解雇で失業した場合、雇用保険の失業給付を受けられます、
法人破産は会社都合の離職となり、失業給付を受けられる期間が通常より延長されるため、早急に手続きをしたい従業員もいるでしょう。
従業員が失業給付を受けられるように、会社は以下の資料をハローワークに提出します。
提出後に発行される離職票を従業員に交付し、従業員がハローワークで申請すると失業給付を受給できます。
従業員は解雇されると、社会保険・厚生年金保険の被保険者資格を失います。
資格の喪失後、従業員は健康保険を使用し続けるために以下の3つのうちどれかを選択します。
会社は、以下の資料を管轄の年金事務所へ提出し、社会保険の適用事業所の廃止手続きを行いましょう。
従業員からは保険証カード(被扶養者のカードも含む)を回収し、管轄の年金事務所へ返却します。
従業員には、法人破産の手続きの開始前までに貸与品の返却や私物の持ち帰りを依頼しましょう。
法人破産の手続きが開始すると、債権者へ分配をするために破産管財人によって会社の財産が調査されます。
会社の財産と従業員の私物が混在していると調査に支障が出る可能性もあるため、なるべく早い段階で返却や持ち帰りをしてもらいましょう。
従業員は解雇された後、確定申告などで前職の給与所得を証明するときには源泉徴収票が必要です。
従業員がすでに他社へ転職している場合も、転職先の年末調整で前職の源泉徴収票を提出しなければなりません。
源泉徴収票には、従業員へ退職するまでに支給した年間の給与所得や税金の源泉徴収額などを記載しましょう。
交付が遅くなると従業員に迷惑をかける可能性もあるため、解雇と同時か、もしくは解雇後すみやかに交付するのが望ましいです。
従業員の解雇手続きで困っているときは、VSG弁護士法人にご相談ください。
全従業員が集合可能な従業員説明会を開催し、一斉に告知を行います。
代理人弁護士の同席の有無は、経営者と従業員との関係性や規模などを考慮し、無用な混乱を招く恐れがあるかで決めてください。
従業員にとっては突然の解雇となるため、以下のような伝えにくい内容でも真実を誠実に丁寧に説明しましょう。
従業員の失業保険受給、再就職のために必要な書類の交付など諸手続きも速やかに行ってください。
賃金が未払いのままでは、従業員が生活に困窮する可能性があるかもしれません。
以下の給料や退職手当は財団債権といい、破産手続きによらず優先的に弁済されます。
上記以外の未払い賃金は優先的破産債権と呼ばれ、財団債権よりも順位は劣後しますが、一般的な他の債権より優先して弁済を受けられます。
財団債権はいつでも弁済を受けられますが、優先的破産債権は破産法所定の手続きに従ってのみ配当の分配が可能です。
未払賃金立替払制度とは、倒産した会社に資金が残っていないとき、国が従業員の未払い賃金を立替払いをしてくれる制度です。
立替払いの対象は退職日から6カ月前までの定期賃金と退職金のみで、解雇予告手当や賞与などは対象となりません。
立替金の支給を受けるときは、要件を満たした上で運営元の独立行政法人労働者健康安全機構へ従業員から申請しましょう。
未払賃金立替払制度を利用するには、以下の会社側と従業員側の要件をそれぞれ満たさなければなりません。
<会社側の要件>
・事業を一年以上継続している
・労災保険の適用事業である
・会社が倒産している(法律上の倒産だけでなく、事実上の倒産も含む)
<従業員側の要件>
・従業員として雇用されていた
・退職日が、倒産日の6カ月前の日から起算して2年以内である
会社が法人破産を申立て、破産法に基づく破産手続開始の決定がされると、法律上の倒産とみなされます。
対象となる従業員には、正社員だけでなく派遣社員やアルバイト、パートタイマーも含みます。
支給される金額には、退職時の年齢で以下のように上限額が設定されています。
実際の支給額は、未払い総額の80%です。
たとえば、未払い総額が300万円のケースを考えてみましょう。
退職時に45歳の場合、未払い総額300万円×80%の240万円が支給額です。
一方で、退職時に35歳のときは上限額が適用されるため、上限額220万円×80%の176万円が支給額になります。
会社倒産時には、給料の支払いや告知以外にも、できる限り従業員の気持ちに寄り添った対応をしましょう。
長年働いてきた従業員の中には、自社の商品やサービスに誇りを持ち、懸命に支えてきた方も少なくありません。
解雇となる従業員は今後の生活について心配をしますが、従業員が前向きに再出発できるような支援も大切です。
たとえば、退職金を少しでも多く支払う、取引先へ受け入れを相談する、有給の取得に配慮するなどの対応を行いましょう。
経営状況の悪化などで事業の継続が困難になり、再出発するためにやむを得ず法人破産を選択するケースもあるでしょう。
一方で、法人破産によって解雇される従業員のために、経営者は様々な対応や配慮をしなければなりません。
法人破産の対応を経営者が1人で抱えるのは精神的な負担も大きいため、破産手続を検討するときは早めに専門家に相談しましょう。
法人破産に強いVSG弁護士法人では、無料相談をお受けしております。
従業員への告知をどうしたらよいかわからない、法人の破産手続きの進め方がわからず困っているなど、法人破産の悩みはお気軽にご相談ください。