

東京弁護士会所属。
弁護士は敷居が高く感じられるかもしれませんが、話しやすい弁護士でありたいです。
お客様とのコミュニケーションを大切にし、難しい法律用語も分かりやすくご説明したいと思います。
お客様と弁護士とが密にコミュニケーションをとり協働することにより、より良い解決策を見出すことができると考えております。
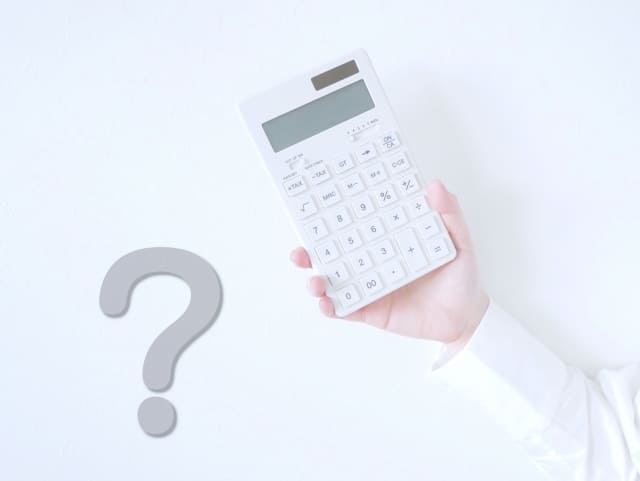
会社の経営に行き詰まった場合には、その会社は倒産してしまいます。
ただ、会社の経営は順調な場合でも、次の展開を考えて会社を解散・清算することもあります。
会社の経営がうまくいっている状態で会社をたたむ場合、その会社に残された財産を処分するための手続きが定められています。
ここでは、会社を解散・清算する際の手続きや、その時に個人に発生する税金について解説していきます。
Contents
会社が解散すると、会社に残された財産を使って債務者に対する返済を行わなければなりません。
たとえば、仕入先に対する買掛金や、金融機関からの借入金などの債務をすべて返済しなければ会社を清算することはできません。
会社の財産を使ってすべての債務の返済が完了すると、残された財産は本来の会社の所有者である株主に返還されます。
特別な株主がいないのであれば、すべての財産は株数に応じて株主に分配されます。
このように、会社に残った財産を株主に分配することを「残余財産の分配」といいます。
残余財産の分配が行われなければ、会社を清算することはできないのです。
残余財産の分配を行うと、会社から株主に金銭による支払いが行われることとなります。
株主が法人の場合は、その法人に対して法人税の課税が行われます。
また、株主が個人の場合は、その個人に対して所得税の課税が行われます。
一般的な中小企業では、ほとんどが個人株主であるため、ここでは株主=個人として説明を行います。
個人である株主が会社から金銭を受け取るといっても、その中身は大きく2つにわけることができます。
なぜならば、株主は会社を設立した際に資本金となる金銭の支払いを行っているためです。
会社が解散してなくなるということは、株主が保有する株式の価値もゼロとなることを意味します。
ただ、その解散・清算の過程で、当初出資した金額を払い戻してもらえばお金が戻ってくるだけの話となります。
したがって、残余財産の分配の金額のうち、当初の出資金額までの金額については課税対象にはなりません。
一方、残余財産の分配により、当初の出資金額を超えて払い戻される金額がある場合は、所得税の課税が発生します。
この金額については、株主という地位にあることを理由として、その会社から利益を受けることができたと考えられます。
つまり、株主として会社から配当を受け取ったのと同じであると考えられるのです。
そのため、残余財産の分配により出資金額を超えて受け取った金額は、配当所得となります。
決算配当などと同じく、会社から支払われる際には所得税の源泉徴収が行われ、源泉徴収後の金額を受け取ることとなります。

それでは、実際に会社が解散・清算する際の手続きや、必要となる書類について確認していきましょう。
会社の解散を決議するのは株主総会です。
会社は、株主宛に株主総会の招集通知を送付した後、株主総会で解散の決議を行います。
解散を決議したら、会社の清算を行うために清算人の選任も行わなければなりません。
清算人には、会社の代表者が就任するのが一般的です。
また、専門知識を有した弁護士などに依頼するケースもあります。
いずれにしても、会社の決議をしたらすぐに清算人を選任しなければなりません。
会社が解散したら、それから2週間以内に解散の登記を行う必要があります。
この時、清算人の登記もあわせて行います。
2週間という時間はあっという間に過ぎてしまいます。
登記申請書や株主総会議事録などの必要書類は、できるだけ事前に準備しておくようにしましょう。
清算人は、清算を開始した会社の清算開始時点の財産目録と貸借対照表を作成しなければなりません。
作成した財産目録・貸借対照表については、株主総会で承認を得る必要があります。
会社がある日突然清算してなくなった場合、会社に対して債権を有している人が返済を受けられない可能性もあります。
そこで、会社は清算を行うことを広く世の中に知らせる義務があります。
このことを公告といい、会社が清算して消滅することを官報に掲載しなければなりません。
ただ、実際には金融機関や不動産業など特定の業界を除いては、官報を見ている人はほとんどいません。
そこで、清算する会社は債権者に対して、個別に連絡しなければならないと定めています。
このことを催告といいます。
催告により、債権者に対して債権の内容を会社に届け出るように依頼をします。
その結果、債権の回収ができない債権者が発生することを防ぐのです。
清算事務とは、会社が消滅することを前提とした契約の終了や、会社の債権・債務の処理などをいいます。
具体的には、以下のような作業を行うこととなります。
取引先との契約については、会社が解散した時点でその取引は終了しているものが多いでしょう。
ただ、最終的な契約の終了手続きを行い、場合によっては金銭による解決が必要となることも想定されます。
また、賃貸借契約やリース契約なども終了する手続きを行わなければなりません。
会社が売掛金や未収入金などの債権を有している場合には、その代金を債務者から回収しなければなりません。
逆に、会社が買掛金や未払金などの債務を有している場合には、その代金を支払う必要があります。
そして、最終的には未収・未払ともにゼロとする必要があるのです。
会社が不動産や有価証券を保有している場合は、そのままでは清算はできません。
これらの財産を売却して金銭に換える必要があるのです。
清算事務の結果、すべての債務の弁済を終えても残った財産については、株主に分配することとなります。
みなし配当が発生する場合には、会社として源泉徴収を行い、税務署に納付する必要があります。
清算事務が終了し、会社にすべての財産がなくなったことを報告しなければなりません。
決算報告書を作成し、株主総会で株主の承認を得る必要があります。
清算事務が終了し、決算報告についての承認を得た場合は、清算結了登記を行わなければなりません。

会社を解散・清算する際には、会社や株主に通常とは異なる金銭のやり取りが発生することがあります。
その結果、思わぬ税金が発生する場合もあるので、どのような税金が発生するのか確認していきます。
解散・清算を行う事業年度にも、会社は普通に法人税の計算を行う必要があります。
清算を行っている間は売上は発生せず、人件費や家賃などの費用が大きくなるため、法人税の負担はほとんどないはずです。
ただ、会社の財産を売却した際に、簿価より高く売却できた場合には、法人税が発生することも考えられるので注意が必要です。
会社が課税事業者に該当するか否かは、2年前の課税売上が年間1,000万円を超えるかどうかにより判定します。
解散しても、しばらくは消費税の課税事業者に該当するケースもあるのです。
特に、清算中に消費税が発生する建物や機械、車両などの売却がある場合は注意が必要です。
会社から残余財産の分配を受ける個人の株主は、出資金額を超える分配を受ける場合のみ所得税かかかります。
配当金に相当する部分の金額については源泉徴収が行われていますが、原則として確定申告が必要となります。
会社をたたむ際に、個人に税金が発生するというと、違和感を覚えるかもしれません。
しかし、会社に対して出資した個人と、出資を受けた会社との関係を考えると決して不思議なことではないのです。
ただ、絶対に株主に課税が発生するとは限りません。
会社の残余財産の金額によって、個人に対する課税関係は異なる結果となるのです。
会社の解散・清算は、専門家に相談しながら進めるのがおすすめです。