

東京弁護士会所属。
弁護士は敷居が高く感じられるかもしれませんが、話しやすい弁護士でありたいです。
お客様とのコミュニケーションを大切にし、難しい法律用語も分かりやすくご説明したいと思います。
お客様と弁護士とが密にコミュニケーションをとり協働することにより、より良い解決策を見出すことができると考えております。
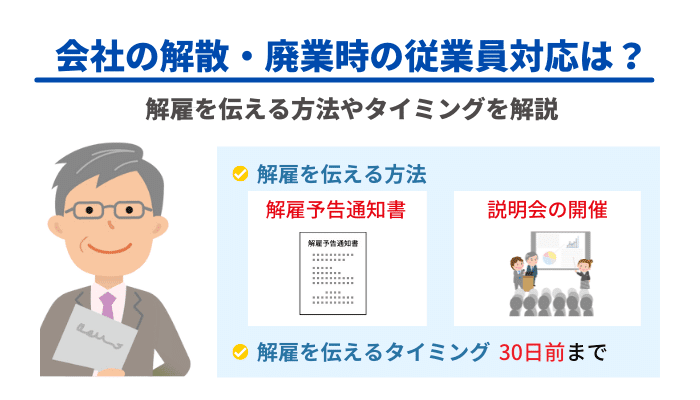
Contents
最初に、同じような意味で使われることもある「廃業」と「解散」の違いについて説明します。
廃業とは、企業の経営者もしくは個人事業主が、自ら事業をたたむことを指します。
廃業を選択する理由に制限はなく、売上減少に伴う経営不振はもちろん、事業が黒字でも廃業することがあります。
近年では、中小規模の企業で、経営者の高齢化、後継者問題等、経営状態の悪化以外の理由で廃業するケースが多くなっています。
解散とは、会社の営業活動を終了し、事業をやめるための手続きのことをいいます。
会社を消滅させるためには、清算手続きを完了しないといけないという法律があるため、会社を解散したからといってすぐに会社がなくなるわけではありません。
株主総会で解散が決議されると、会社は借金などの債務を清算する目的の範囲内で存続することとなり、清算手続きが開始されます。
会社廃業に伴って行う従業員の解雇は、基本的に整理解雇として認められます。
廃業に伴う従業員の解雇は、使用者側の事情による解雇となりますので、次のような要件に照らして、整理解雇が有効かどうか判断されることになります。
整理解雇として認められるかどうかは、下記の四つの要件に当てはまるかによって判断されます。
- ・人員削減の必要性
人員削減措置の実施が不況、経営不振などによる企業経営上の十分な必要性に基づいていること- ・解雇回避の努力
配置転換、希望退職者の募集など他の手段によって解雇回避のために努力したこと- ・人選の合理性
整理解雇の対象者を決める基準が客観的、合理的で、その運用も公正であること- ・解雇手続の妥当性
労働組合または労働者に対して、解雇の必要性とその時期、規模・方法について納得を得るために説明を行うこと
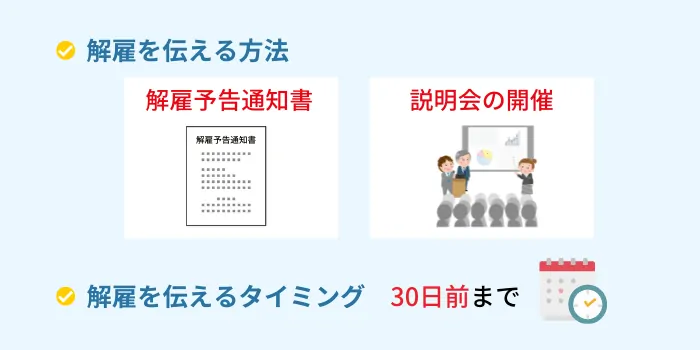
従業員に廃業、解雇を伝えるときは、「解雇予告通知書」という書面の形で伝えるようにしましょう。
また、従業員に伝える内容や時期がバラバラになってしまうと、従業員の間に間違った情報が出回ったり、混乱したりします。
したがって、そういった事態を避けるためにも、従業員全員を集めた説明会を開くことをお勧めします。
会社が廃業に至った経緯や経営状態について、十分に従業員に納得してもらうことが重要です。
十分な理解を得ないまま、廃業、解雇を進めてしまうとトラブルを招きかねません。
また、廃業日まで従業員のモチベーションを維持することも大切です。
理解を得ないまま説明会を終了してしまうと、廃業日を待たず従業員が次々と辞めてしまう場合や、勤務態度が悪くなる事態となって、廃業日までの営業に支障をきたす恐れがあります。
廃業と解雇についての告知は、解雇の30日前には行いましょう。
30日に満たない日数で解雇する場合は、不足する日数分の賃金を支払う必要があり、これを「解雇予告手当」といいます。
また、解雇予告手当等の保証の他にも、未払いの賃金や残業代などが残らないように確認しましょう。
従業員が、それらを会社へ請求してきた場合は、請求内容や時間の算定方法が正しいか等、就業規則や雇用条件通知書の条件に合致しているか、細かく確認する必要があります。
対応方法に不安を感じる場合は、労働基準監督署に相談することもできます。
また、1カ月以内に30人以上の従業員が離職するような場合は、「再就職援助計画」や「大量雇用変動届」をハローワークに提出する必要もありますので、事前に確認しておきましょう。
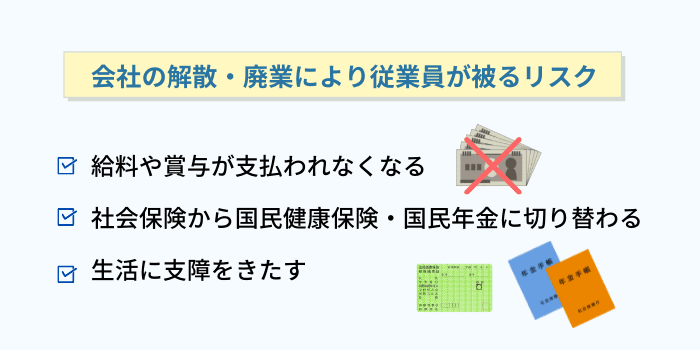
会社が解散・廃業すると、従業員には以下のような影響が出ることが考えられます。
会社の解散・廃業になると従業員は解雇されるため、給料や賞与が支払われなくなります。
そのため、従業員はなるべく早く新しい就職先を探さないといけなくなります。
会社に解雇された場合、社会保険から国民健康保険・国民年金に切り替える必要があります。
保険証は退職時に返却しないといけないため、次の就職先が決まるまでの間は国民健康保険に加入することになります。
解雇されると収入がなくなるため、家族の生活にも支障をきたします。
これまでと同じような日常生活を送ることが難しくなるような場合もあるかもしれません。
会社などで雇用されていた方が離職した場合、一定の条件を満たすことで「基本手当(失業給付)」を受けることができます。
これを一般的に「雇用保険を受給する」といいます。
雇用保険の基本手当は、再就職活動をするにあたり、失業中の生活の心配をしなくても済むという目的のために支給されます。
雇用保険の支給を受けることができる資格を受給資格といいます。
受給資格者となるためには、以下のいずれにも該当していることが必要です。
雇用保険の受給資格
2つ目の期間についてですが、廃業に伴って解雇されたような方は「特定受給資格者」に該当し、離職の日以前の1年間に、被保険者となっている期間が通算して6カ月以上ある場合でも可となります。
特定受給資格者に該当するかどうかは、細かく設定された条件に当てはまるかによって判断されます。
廃業に伴って解雇された方は、「解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く)により離職した者」に当てはまるため、特定受給資格者となります。
自己都合での離職や、懲戒解雇などの場合は、特定受給資格者とはなりません。
また、雇用保険は、離職の理由等に関わらず、離職票と求職申込をした日(受給資格決定日)から待期期間(7日間)が満了するまで支給されません。
自己都合退職や重責解雇などの場合は、3カ月間の給付制限があります。
しかし、特定受給資格者の場合は、給付制限を受けることなく基本手当の支給を受けることができます。
前述の雇用保険の被保険者期間が緩和されますので、一般の受給資格者と比較して優遇されているといえます。
なお、実際に雇用保険として初めて現金が振り込まれるのは、給付制限を受けない特定受給資格者であっても、ハローワークで求職の申込みをしてから、約1カ月後となりますので、ご注意ください。
廃業に至った経営者としては、何よりも先ず、廃業せざるを得ない理由について、従業員が納得いくまで真摯に説明することが大切です。
その上で、退職金の上乗せや、未消化の有給の買取り、慰労金の支給などを解雇する従業員のために行うこともできます。
経営不振により資金が乏しい場合でも、従業員の再就職のために、関連企業や同業他社などへの就職を斡旋することも可能です。
また、ハローワークへ再就職援助計画を提出することもできます。
一つの事業所において、1カ月以内に30人以上の離職者を生じさせようとする場合に、作成・提出することが必要ですが、離職者が30人未満の場合でも任意で作成可能となっています。
廃業に伴って従業員を解雇する際には、解雇告知や廃業告知を行う説明会をしっかりと実施するとともに、廃業に至った経緯と今後の処遇などについて、真摯に説明し理解を得ることが重要です。
退職金や慰労金などの金銭的なフォロー以外にも、解雇することになる従業員への心理的、精神的なケアも可能な限り行いましょう。
また、トラブルを避けるためには、事前に就業規則や雇用条件通知書等の内容をしっかりと把握し、適正に記載されているかを確認することも重要です。
従業員が個別に残業代の未払金の清算や、有給休暇の未消化分の買い上げなど、会社側に交渉を行うこともあります。
これらの交渉には、個別に対応するのではなく、就業規則や雇用条件通知書に基づいた共通の計算方法により、すべての従業員に同じ対応ができるように準備しておきましょう。
再就職援助計画の作成は、経済的事情によって事業規模の縮小等で整理解雇する場合などに必要になりますが、事業規模の縮小等には、事業の廃止も含まれますので、廃業に伴って従業員を解雇する場合も必要です。
離職者の人数は30人以上と規定されていますが、30人未満でも作成することはできますので、経営者として従業員の再就職支援を行うことが可能です。
再就職援助計画とは、解雇する従業員の再就職活動に対して、事業主が行うべき援助が、有効的、計画的になるように作成するものです。
具体的には、下記のような内容の記載が必要です。
再就職援助計画に必要な内容
作成した再就職援助計画は、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長(ハローワーク)に提出して、その認定を受けなければなりません。
認定を受けると、ハローワークが必要に応じて求人情報を提供してくれますし、解雇する従業員を雇い入れ、継続して雇用することが確実である事業主には、助成金が上乗せされます。
解雇された従業員に対する助成金ではありませんが、新しく雇用する事業主が助成金を上乗せ支給されますので、少しは再就職がしやすくなる可能性があります。
また、解雇に伴う労働問題を避けるためにも、再就職援助計画の提出とともに、ハローワークもしくは労働基準監督署で相談することをお勧めします。
会社を廃業する場合、雇用している従業員を解雇することは避けようがありません。
しかし、従業員への解雇通知から説明会、未払い賃金や未払い残業代の清算、ハローワークへの書類提出など、トラブルを避けるために、経営者がすべきことはたくさんあります。
特に、廃業・解雇を検討する際には、就業規則や雇用条件通知書の内容が適正かどうか事前に確認し、解雇によるトラブルに発展しないようにしましょう。