

東京弁護士会所属。
弁護士は敷居が高く感じられるかもしれませんが、話しやすい弁護士でありたいです。
お客様とのコミュニケーションを大切にし、難しい法律用語も分かりやすくご説明したいと思います。
お客様と弁護士とが密にコミュニケーションをとり協働することにより、より良い解決策を見出すことができると考えております。
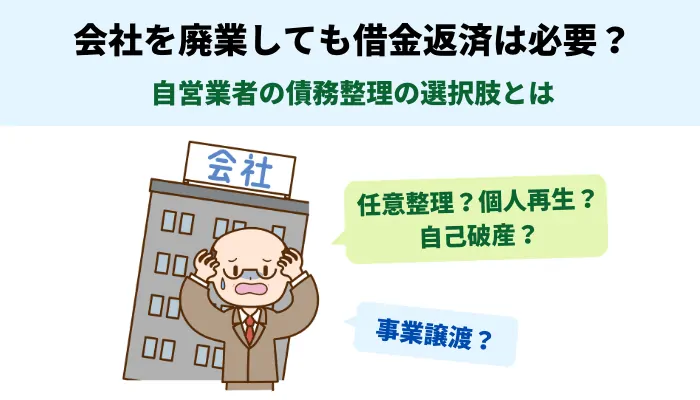
Contents
倒産と廃業は、何が違うのでしょうか。
倒産とは、債務超過や支払い不能状態に陥り、会社継続が困難となる状態のことを指します。
一方、廃業とは、自らの意思で事業をやめることです。
倒産とよく似た言葉に「法人破産」「自己破産」がありますが、破産は倒産のうちの1つの方法です。
倒産には、事業を終了する場合の清算型と、事業を継続する場合の再建型がありますが、清算型で最も一般的な倒産方法が破産です。
財産を処分しても債務(借金)が残ってしまう場合、法的な破産手続によって、借金の支払い義務をなくすことができます。
廃業は、自らの意思で事業をやめることになりますので、設備や商品の在庫、店舗などの資産を売却しても債務が残る場合、その債務超過分は廃業しても残る借金ということになります。
個人事業主の場合、事業での借金であっても、個人の借金と同一ですので、廃業しても借金はそのまま残ります。
法人の場合は、事業の借金は会社の借金ということになりますので、廃業した場合、法人破産を選択すれば会社の借金は消滅します。
ただし、中小規模の会社の場合、融資を受ける際などに代表者の個人連帯保証を求められることがあります。
会社の借金を個人保証している場合は、代表者個人の返済義務は残りますので、ご注意ください。
廃業の手続きとしては、まず「営業の停止」をします。
営業を停止したからといって、すぐに会社がなくなるわけではなく、会社には資産や負債、従業員の雇用契約などが残った状態となっています。
これらを整理していくことが、精算です。
売掛金や店舗(自己所有の場合)、商品在庫などの資産を売却してお金に換え、負債を支払います。
法人の場合は、この清算によってお金が残った場合は、株主に配当して清算終了となります。
この清算によって、資産と負債の両方をゼロにしなければ、会社を消滅させることはできません。
会社が廃業して借金が残った場合、会社の代表者である社長が借金を背負わなければならないと考えている方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、会社を法人(株式会社など)として経営していた場合、会社と社長個人は別人格です。
そのため、法人格を持った会社の借金を、社長個人が返済する必要はありません。
ただし、法人の場合でも、社長個人が会社の借金の連帯保証人となっている場合は別ですので、ご注意ください。
自営業(個人事業主)の場合は、法人の場合と異なり、事業と事業主は同一人格ですので、事業の借金も個人資産で支払う必要があります。
自営業の廃業後、資産を売却しても債務が残ってしまうと、残った借金の返済方法について考える必要があります。
もし、個人の資産を使って精算できるのであれば、債務者へ迷惑や負担を強いることなく、会社や事業を消滅させることができます。
しかし、個人資産を処分しても借金を支払うことができない場合、債務整理を行うことになります。
債務整理にはいくつか方法がありますが、借金額が少ない場合は、任意整理を選択することができます。
各債権者に、借金の減額や分割返済など、返済条件を変更する交渉を行うことを任意整理といいます。
任意整理での分割返済期間は、3年の36回払いが一般的ですが、交渉次第では5年の60回まで認めてくれる債権者もいます。
ただし、任意整理は分割返済の承認を得られるとしても、返済能力がないといけません。
返済能力とは、3年~5年の期間に定期収入を得られる見込みのことをいいます。
定期収入の見込みがない場合、任意整理が承認されることは非常に困難です。
また、任意整理は信用情報機関に情報登録されます。
情報登録されると、5年間は新たな借金やローンが組めなくなりますので、注意が必要です。
任意整理が難しい場合、法的整理を行うという方法があります。
ここでは、「個人再生」と「自己破産」について説明します。
債務者(廃業した個人)が、裁判所へ申立てをして、借金の大幅減額と、減額された残りの借金を原則3年間の分割返済としてもらう手続きのことを、個人再生と呼びます。
住宅などの財産を保持することも、条件付きではありますが可能です。
ただし、個人再生の場合も、任意整理と同じように定期収入がないと認められるのは困難です。
また、信用情報機関に事故情報として登録されますので、新規の借り入れやローンは5~10年間利用できなくなります。
債務整理の中でも、最終手段といえるのが自己破産です。
自己破産とは、破産する人の保有する財産を処分して、そのお金を債権者に配当するという法的な手続きです。
財産を換価(お金に換える)して、債権者に配当しても残ってしまった借金については、免責手続きにより、借金の返済義務が免除されます。
つまり、自己破産によって借金がなくなるということです。
しかし、自己破産はメリットばかりではありません。
家、土地などはもちろん、家具などの生活必需品を除くすべての財産を処分しなければなりません。
また、官報には氏名住所が記載されますし、自己破産手続中は、引っ越しや旅行などに様々な制限がつきます。
そして、任意整理や個人再生と同じく、信用情報機関に事故情報登録されますので、新たな借り入れやローンは10年間利用できません。
廃業の場合、一般的には営業を停止し、資産と負債の債務整理を行っていきます。
しかし、資産を換価して負債を支払うという通常の清算方法ではなく、会社の事業を借金ごと譲渡してしまうという選択が可能な場合もあります。
個々の資産を売却する手間や費用をなくし、店舗などを運営している場合は、それを活かすこともできます。
そのため、原状回復する費用を低減することもできます。
また、事業譲渡することで、従業員の雇用を維持してくれる可能性もあります。
事例
例えば、5店舗の飲食店を経営していたが、高級志向の料理を売りにしていたところ、徐々に客に飽きられ、そのままの経営維持が難しくなり、廃業を検討するしかないとします。
通常であれば、これらの店舗や設備、従業員も整理して借金を返済しなければなりません。
従業員は、事業がなくなる以上、解雇せざるを得ませんし、店舗が賃貸物件であったとしても原状回復する必要があります。
結局のところ、これらの費用が掛かった上で設備を売却しても、あまりお金は残りません。
ですが、これら5店舗の飲食店と条件の合う従業員を、そのまま違う会社に事業譲渡できたら、どうでしょうか。
廃業の理由が、5店舗の立地条件や従業員の質の低下などではなく、提供する料理に需要が見込めないからだとします。
そのような理由のある事業でも、別の料理店を展開している会社であれば一気に店舗を拡大でき、従業員を継続雇用できる可能性があります。
細かくはその店舗の設備等の内容にもよりますが、個別に店舗の設備等を切り売りするよりは、事業を丸ごと譲渡できた方が、お互い利益になるでしょう。
事業譲渡を受ける側も、自分で同じものを作ろうとすれば、相当な時間と労力が必要になります。
ですから、両者にとってメリットとなる事業譲渡である場合は、借金を含めた事業の譲渡が可能になります。
ただ、借金すべてを含めて事業譲渡できるかは、借金額の多さによります。
あまりにも、借金額の方が大きければ、借金丸ごとの事業譲渡は難しいので、借金額が残る場合もあります。
具体例のように、事業譲渡することで通常通り資産を換価するよりも多くの借金を返済できたとしても、借金の完済に至らず残ってしまう場合があります。
そのような場合は、事業譲渡を行う前に、大口の債権者であることが多い銀行などの金融機関に打診することをおすすめします。
通常通りの清算よりは銀行などの金融機関の借金回収額が増えることを強調し、会社が廃業することも含めて、しっかりと情報を提供しましょう。
丁寧に内容を伝えれば、相手方も聞く耳を持ってくれます。
そして、関係者にメリットがあるものであれば、合意もしてくれるものです。
事業譲渡する場合は、金融機関等の合意を得ることで、スムーズに進めることができます。
事業譲渡を行っても、銀行などの金融機関に会社の借金が残る場合は、2つの方向性があります。
1つは、前記した法的手段「自己破産」です。
どんなに分割できたとしても、返済できる見込みが立たない場合、最終的には自己破産するしかありません。
2つ目は、金融機関と交渉して「分割返済」することです。
通常の返済が不能と判断された時点で、借金は「保証協会」によって銀行に代位弁済されます。
保証協会が代表者にかわって銀行に返済し、債権が銀行から保証協会に移されるということです。
保証協会というのは、原則として各都道府県に設けられている公的機関です。
その役割は、中小企業等が銀行から融資を受けるときに、担保や保証人を用意できない中小企業のために、保証人になってくれるというものです。
保証協会が代位弁済した借金の返済は、保証協会へ行うことになります。
当然ながら、保証協会は一括で返済して欲しいところですが、現実的に無理があります。
結局、分割返済の具体的な話を進めるしかありませんので、いくらなら月々の返済が可能かという話になります。
この額は、返済総額によりますのでケースバイケースですが、債権カットについては、あまり応じてくれないようです。
保証協会付きの融資(借金)ではない場合、債権が「サービサー」に売られることがあります。
「サービサー」とは、法務大臣から営業許可を得ている民間の「債権回収専門会社」のことです。
サービサーは、金融機関などから、債権を譲り受けて管理回収を行っています。
少し怖い印象があるかもしれませんが、サービサーの業務には、サービサー法(債権管理回収業に関する特別措置法)による厳格な規制があります。
法令を遵守し、適正な回収をすることが義務付けられているのです。
銀行などの金融機関は、サービサーに債権を売ることで、一部ですが債権回収ができ、早期に決着させることが可能になります。
一方のサービサーは、額面よりもずっと安価に債権を入手することができます。
ですから、債権が売られた後は、サービサーへ交渉することになります。
保証協会と同様に、分割支払い等の交渉も可能ですし、場合によっては、一部を支払い残りを放棄してくれる可能性もあります。
事例
例えば、サービサーが800万円の債権を5%の40万円で買ったとします。
この債権に対し、何とか80万円を工面して一括で支払った場合、サービサーは「元はとれた」ということで、残りの債権を放棄してくれるかもしれません。
金額はあくまでも例ですし、状況にもよりますが、このような処理ができる場合もあるようです。
自らの意思で事業をやめる「廃業」を選んだ場合、資産を売却し負債に充てても、借金が残ってしまうことがあります。
残った借金の返済については、任意整理、個人再生、自己破産、事業譲渡などを検討することができますが、それぞれにメリット、デメリットもあります。
様々な借金の清算方法を検討した上で、廃業することが大切です。