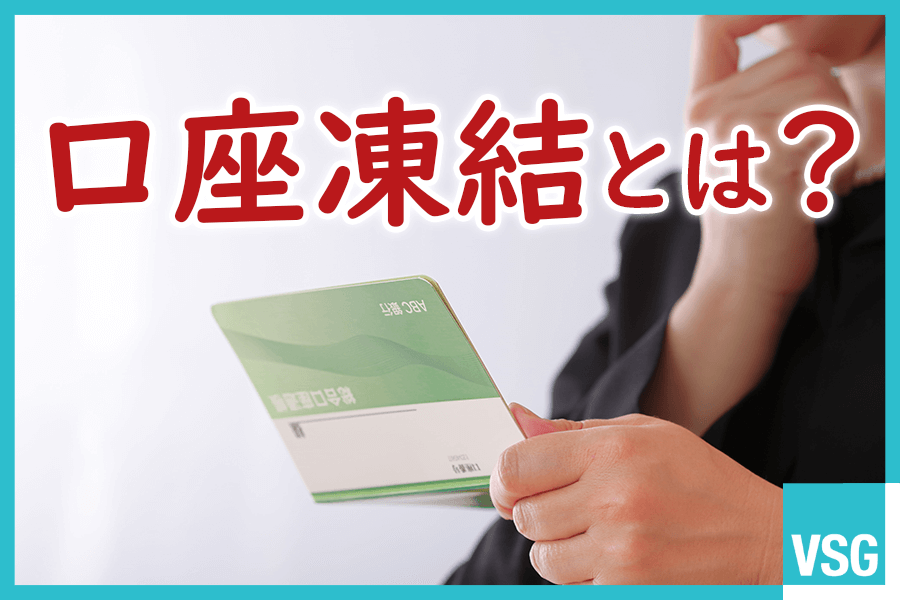記事の要約
- 口座凍結とは、名義人が亡くなった後に「預金引き出し」などのサービスが止められること
- 「相続トラブルの発生」や「相続放棄ができなくなる」といったリスクを避けるため、名義人の死後は早めに口座を凍結すべき
- 口座を凍結しても、「仮払い制度」を利用すれば預金を引き出せる
「亡くなった人(被相続人)の銀行口座は、すぐに凍結すべきと聞いたけれど本当?」
このような疑問をお持ちの方へ向けて、本記事では口座凍結についての基礎知識や、凍結すべきかどうかの判断方法をお伝えします。
なお、VSG相続税理士法人では、相続に関する相談を無料で受け付けておりますので、ご不明なことがございましたら、下記からお気軽にご連絡ください。
目次
▼口座凍結については、こちらの動画でも解説しています
口座凍結の基礎知識
口座凍結とは、銀行などの金融機関の口座で、下記のサービスが止められてしまうことです。
- ATMや窓口での預金の引き出し
- 口座への入金
- クレジットカード代金などの自動引き落とし
口座を凍結されるタイミングの1つが、「金融機関が口座の名義人の死亡の事実を知ったとき」です。
もっともよくあるのは、遺族の方が金融機関に「口座の名義人が亡くなった」旨を連絡することで凍結されるケースです。
ほかにも、下記のようなきっかけで、金融機関側が名義人の死亡を知り、自発的に口座を凍結することがあります。
- 名義人の死亡が新聞の訃報欄に載る
- 遺族が相続手続きのために残高証明書の発行を依頼する
一度、口座が凍結されると、その預貯金を相続する人が決まってから所定の手続きをするまで、前述のサービスはストップします。
ちなみに、口座が凍結されるのは相続のときだけではありません。以下のようなケースでも、凍結されることがあります。
- 口座名義人の認知症が確認されたとき
- 自己破産など債務整理の対象になったとき
- 振り込め詐欺などの犯罪に利用された疑いがあるとき
なお、「死亡届」を提出することで自動的に口座凍結されると思われている方もいらっしゃいますが、基本的には金融機関に連絡しない限り凍結はされません。
口座凍結は絶対にするべき?
口座が凍結されると、預金の引き出しができなくなったり、自動引き落としが停止したりするため、なにかと不便を感じる場面が多くなります。
このことから、「口座の名義人が亡くなっても、銀行には黙っておいて、凍結を避けよう」と考える方も少なくありません。
しかし、口座の名義人が亡くなったときは、基本的には「すみやかに口座を凍結する」ことをおすすめします。
これは、口座凍結をしないと思わぬトラブルに発展してしまうことがあるからです。
口座凍結をしないリスク
口座を凍結しないと、故人のキャッシュカードを持っていて、暗証番号も知っている人がいれば、ATMなどで自由に預金を引き出せてしまいます。これには、次の2つのリスクが伴います。
- ほかの親族と相続トラブルになる
- 相続放棄ができなくなる
まず1つ目のリスクは、「ほかの親族と相続トラブルになる」ことです。
誰かがほかの親族に黙って預金を引き出したことが発覚すると、「遺産分割前に使い込んだのではないか」「財産を自分のために隠したのではないか」と疑われかねません。
親族がお互いに不信感を持った状態では、その後の遺産分割協議などがスムーズに進まなくなります。
2つ目のリスクは「相続放棄ができなくなる」ことです。
故人に多額の借入金などがあった場合、その債務を相続人が引き継がないために「相続放棄」が検討されます。
しかし、故人の預金を使ってしまうと、「亡くなった方の財産も借金も、すべて引き継ぎます」と意思表示した(単純承認)とみなされ、相続放棄ができなくなるおそれがあります※1。
以上のことから、基本的には名義人が亡くなったときには、なるべく早めに口座凍結をするのがおすすめです。
「預金を下ろせなくなると不便」と感じるかもしれませんが、実は口座凍結をしても引き出す方法はあります。
- ※1
- 引き出しの目的が「葬儀費用」など社会通念上やむを得ない範囲の出費であり、使途が明確に証明できる場合には、相続放棄が認められるケースもある
凍結後も「仮払い制度」で預金を引き出せる
「口座凍結した後で、葬儀費用や当面の生活費などのためにお金を下ろしたい」
そのような場合には、「遺産分割前の相続預金の払戻し制度(通称:仮払い制度)」を活用することで、凍結した口座から預金を引き出せます。
この制度で1つの金融機関から引き出せる金額は、「相続開始時の預金残高 × 1/3 × 手続きをする相続人の法定相続分」と「150万円」のいずれか少ない額が上限です。
具体例
・預金残高:1,000万円
・相続人:妻(法定相続分1/2)、長男(相続分1/4)、長女(相続分1/4)
(1) 妻が手続きをする場合
1,000万円 × 1/3 × 1/2(妻の法定相続分) = 約167万円
計算結果が150万円を超えているため、妻が引き出せるのは150万円まで
(2) 長男が手続きをする場合
1,000万円 × 1/3 × 1/4(長男の法定相続分) = 約83万円
計算結果が150万円を下回っているため、長男が引き出せるのは約83万円まで
この上限額は、手続きを行う金融機関ごとに適用されます。たとえば、A銀行とB銀行にそれぞれ口座がある場合、各銀行で上記の計算を行い、それぞれ上限まで払戻しを求めることが可能です。
手続きは、口座の金融機関の窓口で行い、一般的に以下の書類の提出が求められます。
ただし、必要な書類は金融機関によって異なる場合がありますので、事前に電話などで確認しておくとスムーズです。
なお、どうしても上限額を超える金額を引き出す必要があるときは、家庭裁判所に申し立てることを検討しましょう。
必要性を認められれば、ほかの相続人の利害を害しない範囲で、預金を引き出せます。
あえて口座凍結しないのも一手
ここまで記事をご覧いただいても、「原則は、口座凍結すべきとわかっていても、手間や不便を考えると手続きしたくない……」と感じるのが正直なところかもしれません。
実際、すぐに口座凍結せず、必要なお金を引き出している方が少なくないのも事実です。
相続人の間で信頼関係が確立されており、「相続放棄の可能性がまったくない」といった状況であれば、リスクを許容したうえで、あえて口座を凍結しないのも一つの手ではあります。
ただし、預金を引き出したときは、必ずお金の使途をすべて記録しておきましょう。
なお、故人が個人事業主として事業をされていた場合は、亡くなられた後でも売掛金や賃料などが、しばらく口座に入金されることがあります。
この状況で口座を凍結してしまうと入金が滞り、後継者の事業に支障が出かねません。そういった事情から、あえて口座凍結を遅らせるケースもあります。
ただし、しつこいようですが、口座凍結をしないことにはリスクもあることを忘れてはいけません。
「口座凍結しない」ことを検討する際は、ご自身だけで判断せず、弁護士などの専門家に相談してみることをおすすめします。
口座凍結を解除する手続きの流れ
凍結された口座を解除するためには、次の3つのステップを踏みます。
これらの手続きをすることで、「故人の預金」を「相続人の口座」に移せます。
具体的な手続きの内容を、詳しく見ていきましょう。
ステップ1:金融機関に連絡する
まずは金融機関に連絡して、口座凍結を解除するための必要書類を確認しましょう。これは、凍結させるために、名義人が亡くなった旨を連絡した際に案内してもらえることも多いです。
金融機関によって多少異なりますが、一般的には下記のような書類を求められます。
ステップ2:遺産の分け方を決める
続いて、亡くなった方の遺産の分割方法を確定させます。
遺言書がある場合には、基本的にその内容のとおり分割します。一方で、遺言書がない場合は「遺産分割協議」をして、相続人全員で話し合わなければなりません。
遺産分割協議がまとまったら、その内容を「遺産分割協議書」にまとめて、相続人全員が署名・押印します。
ステップ3:預金の払い戻しを受ける
遺産の分け方が決まり、必要な書類もすべて揃ったら、金融機関の窓口に提出します。
書類に不備がなければ、通常は2週間程度で手続きは完了し、故人の口座の預金が、指定した相続人の口座に振り込まれます。
以上、口座凍結を解除する手続きを紹介しましたが、これはあくまで一般的な流れです。
金融機関によって多少手続きは異なりますので、実際に行う際には必ず窓口や電話で確認しましょう。
なお、ゆうちょ銀行での手続きについては、下記の記事で詳しくお伝えしています。
口座凍結に関するよくある質問
最後に、口座凍結に関してよくある、下記の質問にお答えします。
Q1:故人の口座が凍結されているか、確認する方法は?
もっとも簡単な方法は、故人のキャッシュカードを使ってATMで「残高照会」をしてみることです。
凍結されていれば、「このカードはお取り扱いできません」といったエラーメッセージが表示されます。
Q2:口座が凍結されたまま放置すると、どうなる?
最後の取引から10年間、入出金などの動きがない口座は「休眠預金」として扱われ、預金は「預金保険機構」という機関に移管されます。
移管された後でも、預金が没収されるわけではなく、金融機関の窓口を通じて手続きを行えば、いつでも引き出すことが可能です。
しかし、引き出しの手続きに時間や手間がかかるため、遺産分割協議がまとまったら、速やかに払い戻し手続きを行うことをおすすめします。
Q3:証券口座やネットバンクも凍結される?
証券口座やネットバンクを含め、すべての金融機関は「名義人が亡くなった事実」を知った時点で、その口座を凍結します。
Q4:凍結前に、葬儀費用を引き出すのは問題ない?
葬儀費用の引き出しであれば、凍結前に引き出しても、後で問題になるケースはありません。
実際に、ご家族が亡くなる直前や、亡くなった直後に葬儀費用を引き出しておく方は多いです。
引き出した際は「何にいくら使ったのか」を証明できるよう、必ず領収書を保管しておきましょう。
また、ご近所の方に葬儀を手伝っていただき、心づけを渡した際なども「誰にいくら支払ったか」をメモしておくことをおすすめします。
引き出した現金については必ず「相続財産」として計上し、遺産分割協議や相続税申告の対象にしてください。
なお、相続税の申告をする際、葬儀費用は「債務控除」が可能です。たとえば、引き出した現金が150万円で葬式費用が100万円であれば、差額の50万円が課税対象となります。
口座凍結で不明な点は、専門家に相談!
この記事では、口座凍結の基礎知識や、解除するための手続きについてお伝えしました。
手続きを進めるうえでわからないことが出てきたら、一人で悩まず専門家に相談することをおすすめします。
VSG相続税理士法人には、弁護士・税理士・司法書士・行政書士といった相続のプロが多数在籍しております。初回の相談は無料ですので、お気軽にご連絡ください。