

東京弁護士会所属。
交通事故の被害者にとって、弁護士は、妥当な慰謝料をもらうための強い味方になります。
特に、加害者の保険会社との示談交渉がうまくいかず悩まれていたり、後遺症が残ってしまい後遺障害慰謝料請求を考えていたりする方は、 ぜひ検討してみてください。
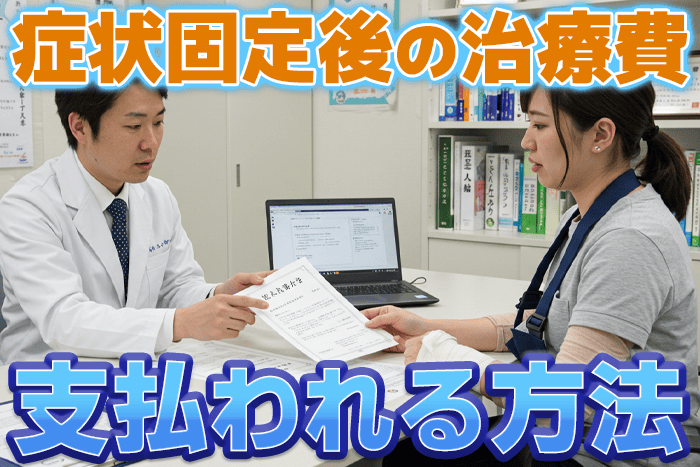
目次
交通事故における症状固定とは、けが治療を継続的に受けてきたものの身体に症状が残ってしまい、もうこれ以上治療を続けてもけがの完治は望めない状態のことをいいます。
加害者側の保険会社が被害者に支払う治療費を確定させる必要があることから、症状固定日を確定させてそれ以前を「傷害部分」として、治療費や休業損害などを請求することになります。
症状固定後は、身体に一生残ってしまう後遺症に対する賠償金を「後遺障害部分」として、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益などを請求することになります。
なお、後遺障害部分の賠償金を請求するためには、後遺障害等級に認定してもらう必要があります。
症状固定は、もうこれ以上治療を続けても症状が改善する見込みがない状態のことを指します。そのため、それ以降の治療は基本的に必要ないとみなされてしまい、保険会社が治療費を支払ってくれないのが原則です。
例え症状固定の判断に納得が行かずに通院を続けていたとしても、自己判断での治療は治療費を支払う必要性・相当性が認められないケースがほとんどでしょう。
なお症状固定を決めるのは治療を担当している医師ですが、まだ医師が症状固定を診断していないにもかかわらず保険会社が独断で症状固定による治療費の打ち切りを打診してくるケースがあります。
保険会社の圧力に負けて治療を中断すると賠償金額の減額などさまざまなデメリットがあるので、くれぐれも対応に注意してください。
症状固定後の治療費は支払ってもらえないのが原則ですが、治療の必要性や相当性が認められれば治療費の支払いが認められる場合があります。
具体的には、次の3つのケースに該当すれば症状固定後の治療費も支払ってもらえる可能性があります。
症状固定後も何らかの理由で治療の必要性が認められる場合には、その治療費を保険会社に支払ってもらえる場合があります。
例えば、次のようなケースが挙げられます。
なお、症状固定後の治療の必要性は、症状の内容や程度、治療の経過などを総合的に考慮して決定することになります。
将来治療費とは、症状固定後の治療費の中でも、とくに長期間にわたって治療の必要性が見込まれる場合にかかる費用のことです。将来治療費は、事故による損失として保険会社に賠償請求できる可能性があります。
将来治療費が認められるのは、被害者が植物状態や半身麻痺などの重篤な後遺障害を抱えて、半永久的に介護やリハビリが必要になるケースが典型的です。この場合、長期間にわたり生命維持にかかる治療費を保険会社に請求できる場合があります。
また、義手や義足を装着したケースでは定期的に義手や義足の交換が必要となるため、交換にかかる費用の見込み額が将来治療費として認められる場合もあります。
症状固定後は治療を続けても症状は改善しないはずですが、現実的には症状固定後の治療によって回復が見られるケースも少なくありません。
症状が改善したということは、治療を受ける必要性も相当性もあったということになります。つまり、症状固定の判断に誤りがあったということになります。
本来であれば症状固定の時期を改めて判断し直すのが原則ですが、その場合、損害賠償額を算定するうえで複雑な計算を強いられる恐れがあります。そこで、便宜的に症状固定後の治療費を認めることで、損害賠償額を算定しやすくする場合があります。
ここでは、症状固定後の治療費が実際に認められた裁判例をご紹介します。
事例義足を作成するための治療費が認められたケース
右大腿部(太もも)を切断して症状固定したあと、義足を作成するための通院中に切断部の治療も受けていました。義足ができるまでに1年6カ月かかりましたが、その間の治療費全額が認められています。
参照:名古屋高裁判H2.7.25 判時1376.69
事例介護リハビリ費用が認められたケース
下半身麻痺が残ったため症状固定後も治療を継続していましたが、一定の範囲で治療の必要性と相当性が認められ治療費として24万円が認められました。
参照:浦和地平7.12.26 交民28・6・1870
事例症状固定後1年3カ月の治療費が認められたケース
肩関節や頸部(首)の運動制限や痛みなどで後遺障害12級の認定を受けたケース。症状固定後の治療状況や症状の経過などを精査して、症状固定後も治療を受けなければ悪化していた可能性があり、保存的治療として必要であったと判断されました。その結果、症状固定後の治療費が全額認められています。
参照:神戸地判平10.10.8 交民31.5.1488
事例症状の悪化を防ぐための治療費の支払いが認められたケース
四肢麻痺、意識障害等で後遺障害等級1級の認定を受けたケースです。症状固定後も手足の拘縮を防ぐためのリハビリが不可欠であったことと、日常生活には全介助が必要であり、自宅で生活するには自宅の改修や導尿・経管栄養の技術を家族が修得するなど在宅介護への移行準備の期間が必要であったこと、などが考慮されました。その結果、468万円の治療費の支払いが認められています。
参照:さいたま地判平21.2.25 交民42・1.218
事例症状固定後に症状が改善したため、一定期間の治療費の支払いが認められたケース
精神障害等で後遺障害等級併合9級の認定を受けたケースです。医師が症状固定後も通院治療の必要性を認めていたこと、実際に症状固定から約1年半後までは症状の改善が認められるとして、その時点までの治療費に限って支払いが認められました。
参照:東京地平23.10.24 自保ジ1863・50
事例症状固定後の治療費や個室利用料の支払いが認められたケース
四肢麻痺で後遺障害等級1級に認定されたケースです。症状固定後の約2年6カ月の入院治療はけがの程度から考えて必要性・相当性が認められるとして、症状固定後の治療費の支払いが認められました。また、主治医が個室利用も認めていたことから個室利用料の賠償も認められています。なお、症状固定後の食事負担金については認められていません。
参照:大阪地判平成28.8.29 交民49・6・1570
事例転院先を探す期間の治療費の支払いが認められたケース
後遺障害等級に認定されたあと適当な転院先が見つからなかった場合に、医師の指示のもとで自宅介護の体制が整うまでの間の入院費用の支払いが認められました。
参照:大阪地判平成15.12.4 交民36・6・1552
事例保険診療が認められていない治療費について支払いが認められたケース
意識障害等で後遺障害等級1級の認定を受けたケースです。症状固定後に保険診療が認められていない電気刺激療法による治療を継続していたが、この治療は医師の医学的判断を基におこなわれたものであり、退院時には明らかな症状の改善が見られるとして、症状固定後の治療費792万円が認められました。
参照:神戸地判平成29.3.30 交民50・2・369
症状固定後の治療費は基本的に認められませんが、治療の必要性・相当性が認められれば一定の治療費の支払いが認められる場合があります。
ただし、医師が治療継続の必要性を認めていたとしても、保険会社が素直に治療費を支払ってくれるケースはそう多くありません。
この記事でもご紹介したケースは、裁判で争った結果やっと支払いを認めてもらったケースです。示談交渉で保険会社に症状固定後の治療費を支払ってもらうためには、裁判例を正確に理解し適切な主張をしていく必要があります。
医師に指示された治療にもかかわらずどうしても保険会社が支払いを認めてくれない場合には、交通事故に精通した弁護士に相談してみることをおすすめします。

