

東京弁護士会所属。
破産をお考えの方にとって、弁護士は、適切な手続きをするための強い味方になります。
特に、周りに相談できず悩まれていたり、負債がかさんでしまいそうで破産を考えていたりする方は、ぜひ検討してみてください。
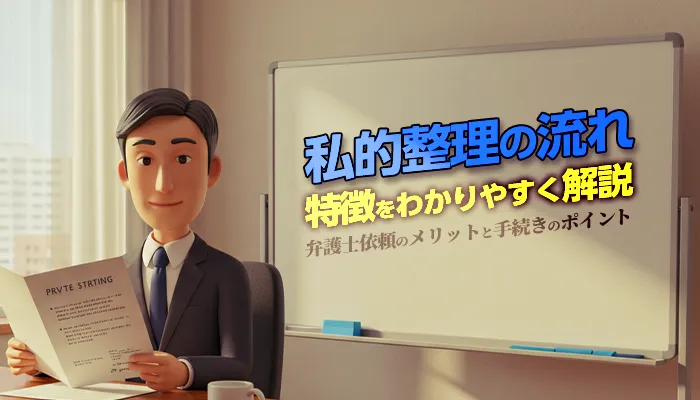
債務超過などを理由に経営状態が悪化した場合、もはや自力での再建が困難になってしまうケースがあります。この場合、弁護士などに依頼して事業再生を検討することになるでしょう。
会社の再建方法は大きく「私的整理」と「法的整理」の2つに分けることができます。どちらを選択すべきかはそれぞれのメリット・デメリットだけでなく、経営状態や事業継続の可能性などの観点から総合的に判断する必要があります。
この記事では、私的整理の中でも特に「私的整理ガイドラインに沿った私的整理」について解説していきます。私的整理全体の流れについてもわかりやすく解説しているので、ぜひ最後までご覧ください。
私的整理ガイドラインとは、私的整理を進める際の基本的な考え方をまとめたガイドラインです。法的拘束力があるわけではありませんが、主要債権者である金融機関だけでなく、全ての利害関係人が自発的に遵守することが期待されています。
具体的な関係者間の調整手続きや対象となる企業の選定基準、再生計画の要件などが取りまとめられています。ガイドラインを活用することで、いわゆる純粋私的整理よりも透明性を確保しながら再建を目指せます。
私的整理は、企業が各債権者と個別で交渉を行う「純粋私的整理」と、一定のルールに従って進める「準則型私的整理」の2つに分けられます。
| 純粋私的整理 | 任意整理による私的交渉 |
|---|---|
| 準則型私的整理 | 事業再生ADR |
| 整理回収機構(RCC)による企業再生スキーム | |
| 中小企業再生支援協議会による再生支援手続 | |
| 地域経済活性化支援機構(REVIC)の事業再生支援 | |
| 特定調停 | |
| 私的整理ガイドラインに沿った私的整理 |
純粋私的整理では、ルールに縛られることなく交渉を進められます。自由度が高く柔軟に問題を解決できるメリットがある一方で、手続きが不透明になりやすく、他債権者からの疑義が生じやすくなるというデメリットがあります。
従来型である純粋私的整理のデメリットを補った手続きが、準則型私的整理です。一定の準則(ルール)に基づいて手続きが進められるため、私的整理でありながら手続きの透明性を確保することができます。お互いの認識を共有しながら手続きを進められるので、合意形成が比較的容易なのが特徴です。
私的整理と法的整理の大きな違いは、裁判所が主導の手続きであるかどうかです。
私的整理の場合、裁判所の関与なしで手続きが進みます。当事者間で話をすることになるので、交渉次第では簡易・迅速に再建を目指せるでしょう。また、私的整理なら各債権者との交渉内容が公になることがないので、秘密裏に手続きを進められることもメリットの一つです。
その反面、手続きの透明性を確保しづらいというデメリットがあります。
法的整理では、裁判所主導で手続きを進めることになります。裁判所が関与するため不正が入り込みにくく、手続きの透明性・公平性を確保しやすいというメリットがあります。
一方で、法律に従って再建を目指していくため、手続きが複雑で迅速性に欠けるというデメリットがあります。倒産手続きが公になることにより、事業価値が毀損される可能性があることも法的整理のデメリットといえるでしょう。
私的整理と法的整理のどちらを選択すべきかは、経営状態や事業継続の可能性などを総合的に判断して決める必要があります。
従来型の純粋私的整理の場合、手続きの透明性や公平性を確保できないことが大きなデメリットでした。しかし、準則型私的整理であれば、それらを確保しながら各債権者が納得する形で手続きを進めることができます。
法的整理の場合、民事再生や会社更生などの再建型手続きをとったとしても、「倒産企業」というマイナスのイメージがつく可能性は拭えません。取引先からの信頼回復に時間がかかったり、事業価値の既毀損があることも考えると、まずは私的整理による事業再生を検討するのがおすすめです。
私的整理ガイドラインの主な特徴は、以下の4つです。
私的整理ガイドラインの適用を受けるためには、「経営者の経営責任」と「株主の責任」を明確にしなければなりません。
経営者は、私的整理の流れの中で債権放棄を受ける際に、取締役などの地位を失うこととされています。今後は、新たな経営者が取締役に就任し、会社の再建を担うことになります。
また、事業再生を進めていく際には減資や増資が行われます。減資により株式の価値がゼロになることもあるでしょう。さらに、増資により新たな株主が増えた結果、従来の株主が保有する株式の価値が大幅に減少するケースも考えられます。
私的整理の場合、各債権者は債権の償却損失を計上することになります。
この償却損失は、法的整理を行った場合と違い債権者の損金になるとは限りません。案件ごとに個別に判断をしなければならず、場合によっては損金にならないケースもあるのです。税務当局によりその損金が否認されることも考えられます。
一方、私的整理ガイドラインに沿って手続きを行っていれば、合理的に債権放棄が行われたと判断される可能性が高いです。そのため、債権者側で損金に計上することができ、無税での償却が可能となるでしょう。
法的再生では法律に基づいて実行力のある再生計画が実行されますが、私的整理ガイドラインによる場合でも、同じように強力な再生計画が実施されます。これは、私的整理ガイドラインで、再建計画成立後の3年以内に、一定の成果をあげることが求められているためです。
場合によっては、法的再生を行った場合より実行力のある再生計画となるケースもあります。
私的整理ガイドラインによる場合でも、再生スキームによっては債権者の同意が得られないこともあります。私的整理では債権者の同意のもとで手続きを進める必要があるため、この場合には、法的整理に移行する必要が生じます。
私的整理ガイドラインに規定されている利用条件は、以下の4つです。
過剰債務などが原因で経営困難な状況に陥っており、自力での再建が困難である必要があります。金融機関などから支援を受けることで債務超過を解消できるのであれば、私的整理による会社の再建が可能であると判断されます。
事業価値や営業利益などから再建の可能性が認められることも必要になります。重要な事業部門で営業利益を計上しているものの、多額の債務から発生する費用で資金繰りが苦しい状況などがこれに当たります。
本業としては利益を計上していることから、支援を受けて債務を圧縮すれば本業の利益で再建できるという道筋が描けるのです。
会社の信用力の低下や事業価値の毀損により再建に支障が生じる恐れがあるため、法的整理での事業再生は難しいと判断される必要があります。
私的整理の方が、法的整理よりも経済合理性があるケースでなければなりません。たとえば、私的整理の方が債権者の回収金額が大きくなるケースがこれに当たります。
法的整理を行うと、債権者の保有する債権はすべて切り捨ての対象となり、債権者にとっての損失が大きくなります。金融機関などと私的整理で合意すれば、債権放棄の金額を最小限に抑えられ、債権者にとっても負担が少なくなります。
なお、私的整理ガイドラインに沿って債務整理を行う場合、債務者の負担が相当大きくなります。そのため、実際にはメガバンクがメインバンクとなっている会社でなければ、実行が難しいという現実があります。
弁護士に依頼した場合における私的整理の主な流れは、以下のとおりです。
債権放棄を伴う純粋私的整理における手続きの流れになりますが、具体的事情によって対応や流れは異なります。
また、粉飾がある場合や多額の債権カットが必要な場合、収益力が乏しく返済原資に余力がないケースでは、事前準備や金融機関との合意形成に時間がかかることもあります。その場合、目安期間よりも時間がかかることを頭に入れておく必要があります。
再生計画の合意に至るまでには、最低でも4カ月から6カ月程度はかかると思っておきましょう。
まず、事前打ち合わせで現状把握と方向性の確認を行います。状況把握する際には、主に以下のようなことを確認していきます
これらの全体の状況を把握したうえで、私的整理による再建が可能かどうかを専門的見地から判断していきます。
事業再生の大まかな方向性が決まったら、事前準備として資金繰り表の作成や預金避難を行います。
自力での再建が困難になっている以上、初期段階における資金繰りの管理は極めて重要です。過去の実績だけでなく、事業収益や今後の見通しも考慮した資金繰り表の作成が必要になります。
また、金融機関によっては、弁護士の介入により会社や保証人の預金口座が凍結されてしまうケースもあります。預金がロックされると事業継続に必要な資金を使えなくなる恐れがあります。このような場合には、前もって金融債務のない金融機関に預金を移しておくことも考えられます。
ただし、この預金避難により金融機関との信頼関係を失う可能性もあります。預金対策については、弁護士とよく協議したうえで対応すべきでしょう。
さらに、状況によっては主要債権者である金融機関に事前相談するケースもあります。
キックオフミーティングとなる第1回金融機関説明会では、各債権者に対して、借入金の返済ができないことについて真摯に謝罪します。そのうえで、私的整理への協力要請と借入れ金の支払猶予などを要請します。状況によっては、元金だけでなく利息の支払いも含めた返済の猶予を要請することになるでしょう。
再生スキームの提案や手続きのスケジュール感を共有し、各債権者と歩調を合わせることになります。
私的整理での事業再生について債権者の同意が得られたら、デューデリジェンス(DD)を実施します。
デューデリジェンス(DD)とは、事業再生を行う会社に対する企業調査のことです。公認会計士が財務状況の実態を把握する「財務DD」や、中小企業診断士などの経営コンサルタントらが事業の実態を把握し、事業改善の方向性を検討する「事業DD」が行われるケースが多いです。
財務DDを適切に行えば、金融機関が債権カットの必要性や具体的なカット額を適切に判断できるようになります。
また、事業DDで事業継続における課題を抽出し、収益改善の方向性や事業改善施策(アクションプラン)が固まれば、スムーズに事業再生を実現できることになります。
なお、事業者の規模や再生スキーム次第では、財務DDの中で必要な事業分析を行うケースもあります。
第2回目の金融機関説明会では、実施されたDDの結果を報告したうえで、事業計画のたたき台などについて説明することになります。財務状況や事業継続の可能性、営業利益段階までの損益計画などを発表し、具体的な金融支援の大枠について話し合いを行います。
各債権者と話し合った内容を基にして、具体的な事業再生計画を策定していきます。事業計画は、基本的に貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書の財務三表の形で作成していきます。こうすることで、単なる損益予測にとどまらず、純資産やキャッシュの見通しも可視化できるようになります。
また、事業DDにより浮き彫りになった経営課題に対する改善施策についても、適宜実施していくことになります。
第3回金融機関説明会では、事業再生計画を提示して債権者との合意形成を図ることになります。抜本的な改革が必要な場合には、経営責任に関して説明を求められるケースもあります。状況によっては、今後のガバナンス体制が有効に機能することを、適切に主張しなければならないこともあるでしょう。
また、中小企業の経営者などで会社の連帯保証人になっている場合には、経営者保証ガイドラインに基づく弁済計画についても同時に提示するケースが多いです。
すべての金融機関から事業再生計画に関する同意を得るためには、全体の説明会だけでなく、各債権者と個別に交渉を進めていく必要があります。それぞれの債権者に対して真摯かつ丁寧に向き合うことで、全行同意の可能性を高めることができます。
同意が取れた場合には、第4回金融機関説明会においてその旨を報告することになります。
再生スキームを実行し、事業再生を目指します。
事業再生手法の一つである第二会社方式を採用した場合には、事業譲渡や会社分割における手続きを別途進めることになります。そのため、第二会社方式ではさらに1〜2カ月程度の時間を要することになります。
資金繰りが悪化し事業再生を目指す場合、まずは民事再生や会社更生法にもとづく手続きを想像するでしょう。ただし、法的整理を行うとそのことはすぐに取引先に知られてしまい、事業再生計画が頓挫してしまうことも珍しくありません。
そのようなデメリットを回避したい場合には、私的整理ガイドラインによる債務整理を検討してみましょう。手続きの透明性や公平性を確保しながら、しかも事業価値の毀損を最小限に抑えることが可能です。
資金繰りが完全に破たんすると、事業再生ができずに倒産しか道がなくなってしまいます。経済状態が悪化したら、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
相談先に迷ったら、弁護士・税理士・司法書士が連携して対応できる”ベンチャーサポート法律事務所”にぜひお気軽にご相談ください。