

東京弁護士会所属。
弁護士は敷居が高く感じられるかもしれませんが、話しやすい弁護士でありたいです。
お客様とのコミュニケーションを大切にし、難しい法律用語も分かりやすくご説明したいと思います。
お客様と弁護士とが密にコミュニケーションをとり協働することにより、より良い解決策を見出すことができると考えております。

飲食店経営者の中には、さまざまな理由により廃業を検討している方もいます。
しかし、実際に飲食店を廃業するにはどのような手続きをすればよいのかわからない方も多いのではないでしょうか。
この記事では、飲食店の廃業手続き方法と必要書類について詳しく紹介していきます。
また、飲食店が廃業・閉店に踏み切る理由や、廃業せずに生き残るお店の特徴についても解説していきます。
飲食店の廃業手続きの方法や必要書類の内容について詳しく知りたい方は、参考にしてみてください。
飲食店が廃業してしまうのには何かしらの理由があります。
理由なく廃業する飲食店はほぼ皆無です。
なぜ、飲食店経営者はお店の廃業を決断するに至るのか、その理由を4つ紹介していきましょう。
飲食店を開業後、販売不振を理由に廃業してしまうケースです。
飲食店が販売不振に陥るのは、営業開始前の想定よりも集客数を増やせないことによるものです。
2017年の「東京商工リサーチ」の調査結果では、飲食店の倒産件数は766件ありましたが、そのうちの621件は販売不振を理由に倒産しています。
上記のデータによると、全体の約81%が販売不振で倒産したことになり、飲食店が廃業する理由の大半は販売不振によるものと言っても過言ではありません。
では、販売不振に陥ってしまう理由にはどんなものがあるのでしょうか。
飲食店は、世の中の環境や客の需要の変化に対応できないと販売不振に陥りやすくなります。
たとえば、当初はお店の近くに企業や学校があり、昼の時間に多くの社会人や学生が来店して販売数も増やせていたとしましょう。
しかし、お店の近くにあった企業や学校が環境に変化によってなくなれば、社会人や学生の来店数も激減します。
その結果、飲食店の販売数も激減してしまうのです。
また、一時的にブームとなった料理を提供して飲食店の営業をしていたとします。
提供していた料理がブームの中にあるうちは客の需要も多く、来店数を増やすことができるため、販売数も伸びていきます。
しかし、ブームが去ってしまうと、来店数が下降線をたどり、それとともに販売不振に陥ってしまうのです。
飲食店を開業してから数年後になると、利益を重視して営業してしまいがちです。
その結果、客の満足度が下がって販売不振になってしまうケースも少なくありません。
飲食店が利益重視で営業しようとする場合、コストをできるだけ抑えようとします。
たとえば、食材の質を下げることでコストダウンをはかれば、その分利益率も上がるといった具合です。
しかし、そのような形で作った料理を客に提供しても、食後にその味の変化を気づかれてしまいます。
客が味の変化を感じると、料理に対する満足度が下がってしまう場合も多いでしょう。
それにより、客の来店数が少なくなって、販売不振に陥ってしまうのです。
飲食店を開業後、運転資金不足を理由に廃業してしまう場合もあります。
飲食店は開業するときだけではなく、お店を経営していくためにも資金が必要です。
たとえば、料理を作るための食材を常時仕入れなければなりませんが、そのための費用がかかります。
従業員を雇うための人件費や、お店の宣伝をするための広告費も準備しておかなければなりません。
その他、店舗の家賃や水道光熱費も固定費として毎月発生します。
飲食店を開業してからお店が軌道に乗るまでは、赤字が続くケースもめずらしくありません。
そのため、飲食店の経営を継続していくには、赤字が続いても上記の費用を支払えるだけの運転資金を準備しておく必要があるのです。
しかし、運転資金をあまり準備しないで飲食店を開業してしまう経営者も一定数存在します。
また、開業するときの費用がかさんで、運転資金に回せるお金が少なくなってしまう場合もあります。
このような形で飲食店の経営を始めると、運転資金不足が生じやすくなり、廃業の道をたどってしまうのです。
お店の経営が軌道に乗った後に経営戦略を誤って廃業してしまうケースもあります。
飲食店を開業後、売上や利益が順調に上がっていくと、それをさらに伸ばすために事業拡大を考えるケースも少なくありません。
たとえば、事業拡大を考えて立地条件のよい場所に複数の店舗を出したとしましょう。
しかし、新たに出した店舗の近隣に競合のお店があって、期待通りの売上が出ないこともあります。
それにより、出店費用のほうが大きくなって、これまで黒字だったお店の経営状態が赤字に転落してしまう場合もめずらしくありません。
そして、経営戦略の失敗でお店の経営状態が赤字に転落後、資金繰りも厳しくなり、廃業せざるを得なくなってしまうのです。
2017年の「東京商工リサーチ」の調査結果でも、事業上の失敗による飲食店の廃業件数が、1位の販売不振に次ぐ多さとなっています。
飲食店の経営者が高齢の方である場合、後継者不在を理由に廃業するケースもあります。
2020年の「帝国データバンク」の動向調査によると、全国の全業種26万6,000企業のうちの65%程度にあたる約17万の企業が後継者不在の状況でした。
さらに、飲食業に限ってみてみると、後継者不在の企業の割合は71.6%でさらに高水準となっています。
職業の多様化や少子化などの影響で、後継者を見つけられない経営者も少なくありません。
その結果、やむを得ず廃業の決断するに至るのです。
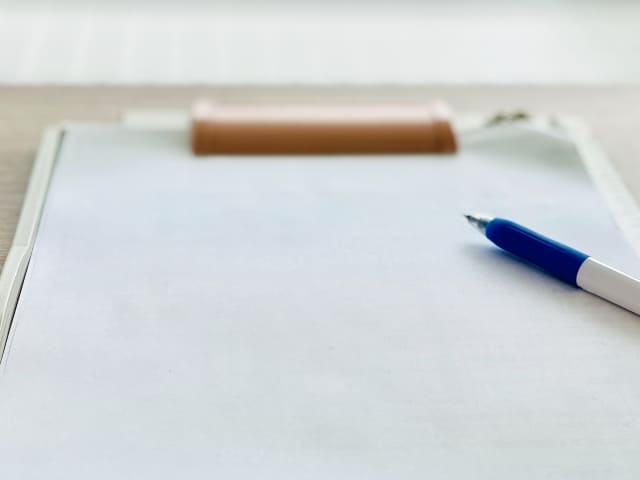
飲食店が廃業する場合、そのお店が個人事業主なのか法人なのかによって手続き方法が異なります。
飲食店が個人事業主である場合、個人事業主の廃業手続き方法によって行います。
一方、飲食店が法人経営である場合、法人の廃業手続き方法によってしなければなりません。
そこで、飲食店が個人事業主である場合と法人である場合の、廃業手続き方法と必要書類について見ていきましょう。
個人事業主の飲食店が廃業する場合、事前準備をした上で、廃業後に各役所へ届出を行なわなければなりません。
廃業に関する届出をしなければならない期間は、各役所によって異なります。
個人事業主の飲食店が廃業する前に、取引先に廃業する旨の連絡をしておく必要があります。
借入がある場合、融資を受けている金融機関に対しても廃業前に相談しておかなければなりません。
従業員を雇っている場合、廃業する旨の通知を事前に行なっておく必要があります。
なぜなら、従業員を廃業による整理解雇をする場合、30日以上前に解雇予告通知をしておかなければならないからです。
また、店舗関係の処理なども廃業の事前準備作業の1つです。
賃貸店舗のオーナーや管理会社への解約通知、電気、水道、ガス、店舗総合保険の解約、原状回復工事などの作業を廃業前に行ないます。
個人事業主の飲食店は廃業してから10日の間に、複数の雇用保険・健康保険関係の届出をしなければなりません。
雇用保険に加入していた場合、廃業から5日以内に「雇用保険適用事業所廃止届」を公共職業安定所に提出します。
さらに、廃業から10日以内に「雇用保険被保険者資格喪失届・離職証明書」の提出が必要です。
健康保険に加入していた場合は、「健康保険・厚生年金保険適用事業所全喪届」を廃業から5日以内に年金事務所へ届けなければなりません。
個人事業主の飲食店は廃業してから1ヶ月以内に「個人事業の開業・廃業等の届出書」を税務署へ提出しなければなりません。
また、従業員や家族などに給与を支払っていた場合、廃業から1ヶ月以内に「給与支払い事務所廃止届出書」を税務署へ提出します。
その他、消費税の課税事業者に該当する場合、「事業廃止届出書」を廃業後速やかに税務署へ提出する必要があります。
雇用保険または労災保険に加入している場合、「労働保険確定保険料申告書」を廃業より50日以内に労働基準監督署へ提出しなければなりません。
また、所得税の青色申告承認を受けていた場合、廃業(青色申告をやめたとき)した翌年の3月15日までにその旨の届出書を税務署に提出します。
法人経営の飲食店が廃業する場合、各役所へその旨の届出をする他、法人の解散と清算の手続きをしなければなりません。
各役所への届出以外の法人の解散と清算手続きの内容とその流れについて見ていきましょう。
廃業の事前準備後、決議によって解散する旨を決定します。
法人が株式会社である場合は、株主総会で解散をする旨と清算人の選任の決議をするのが原則です。
解散および清算人選任の決議後、2週間以内にその旨の登記手続きを行ないます。
手続の際には、法人の本店所在地を管轄する法務局に、解散と清算人選任登記の申請書と必要書類を提出しなければなりません。
解散および清算人選任の登記手続き後、債権者保護のために解散公告をします。
解散公告は官報に掲載する方法で行ないます。
そのため、解散公告を官報に掲載してもらうための手続きをしなければなりません。
解散公告の他、法人側で把握している債権者に対しては個別に催告手続きをする必要があります。
また、それと同時に解散時の財産目録と貸借対照表を作成後、承認を受けなければなりません。
法人が株式会社である場合、株主総会で承認を受けることになります。
解散の諸手続きが済んだ後、解散から2ヶ月以内に解散確定申告をします。
清算手続きでは、事業による業務を終了させた後、債権の取立をしたり、債務を返済したりして、法人の権利関係を整理します。
状況によっては、法人の保有財産を処分換価して債務を返済するケースもあります。
債権者への返済後も法人の保有財産が残った場合、残余財産を確定させて分配手続きをしなければなりません。
残余財産の確定と分配手続きが終わって、法人の債権と債務をゼロにすることができれば清算手続きが終了となります。
また、清算手続き中においては、解散から1年ごとに決算書類を作成して承認を受けたり、確定申告手続きをしたりしなければなりません。
清算終了後、手続きは清算結了へ移行します。
清算の手続き終了後、決算報告を作成してその旨の承認を受ければなりません。
法人が株式会社である場合、株主総会で承認を受けることになります。
上記承認を受けてから2週間以内に清算結了登記の手続きを行ないます。
清算結了登記も解散および清算人選任の登記と同様に、法人の本店所在地を管轄する法務局に登記申請書と必要書類を提出して手続きしなければなりません。
登記完了後、税務署、都道府税事務所、市区町村に清算結了した旨の届出をして、手続き終了となります。
法人の廃業手続きや必要書類の中には、飲食店ならではのものもあります。
そのため、飲食店が廃業する際、通常の廃業手続きや書類提出に加えて、それらに関する手続きをしたり、書類を提出したりしなければなりません。
そこで、飲食店ならではの廃業手続きと必要書類について解説していきます。
廃業する飲食店の管轄保健所に対して、廃業届を提出しなければなりません。
また、それと同時に「飲食店営業許可書」を保健所に対して返納します。
上記の手続期限は、廃業から10日以内となっているケースが多いです。
防火管理者を置いていた飲食店が廃業する場合、消防署に対して「防火管理者解任届出書」を提出しなければなりません。
防火管理者の解任日は廃業した日付を記載することになります。
防火管理者解任届出書の提出期限に関する規定はありませんが、廃業後遅滞なく提出するのが好ましいでしょう。
開業時に「深夜酒類提供飲食店営業開始届出書」を提出している飲食店が廃業する場合、その旨の「廃止届」を提出しなければなりません。
提出先は、廃業する飲食店を管轄する警察署になります。
また、廃業する飲食店が風俗営業許可を受けている場合、許可書を返納の理由書と一緒に管轄警察署へ返納する必要があります。
上記手続きは、廃業日より10日以内にしなければならないのが通常です。
そのため、廃業後速やかに届出や返納の手続きをしたほうがよいでしょう。
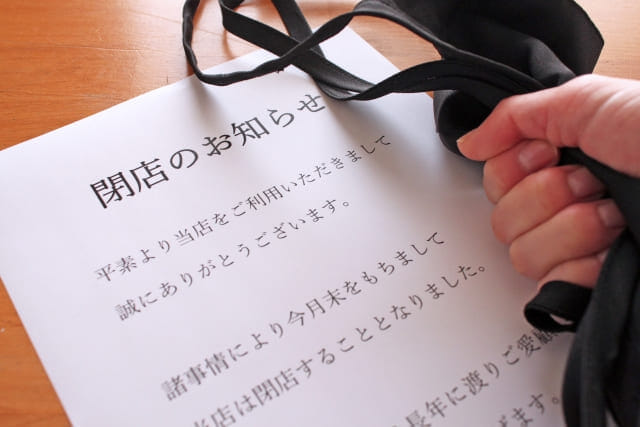
2020年に国内で感染拡大した新型コロナも飲食店の廃業に大きな影響を与えています。
「帝国データバンク」の調査結果によると、2020年の飲食店の倒産件数は780件で過去最多を更新しています。
上記データの対象に含まれているのは、法的整理により廃業手続きを行ない、かつ負債が1,000万円以上の個人事業主または法人経営の飲食店だけです。
それ以外の飲食店を含めると、2020年に新型コロナの影響を受けて廃業した飲食店の件数はさらに多くなると考えられます。
飲食店の業種別で見てみると、「酒場・ビヤホール」「中華・東洋料理店」「西洋料理店」の倒産件数は年間で100件を超えています。
西洋料理店は、2000~2019年の間において、年間倒産件数が100件を超えたことはありませんでした。
しかし、2020年の倒産件数は120件と100件を大幅に超えていて、新型コロナの影響が大きかったと考えられます。
2020年、新型コロナの影響で廃業する飲食店の件数が最多を更新し、今後も厳しい状況が続くと考えられます。
しかし、そのような環境でも廃業せずに生き残る飲食店があるのもまた事実です。
そこで、廃業せずに生き残る飲食店の特徴をいくつか解説していきます。
新型コロナの感染防止対策として時短営業が要請され、それにともなって夜の時間の売上が減少している飲食店も少なくありません。
「帝国データバンク」による2020年の飲食店倒産件数の調査結果でも、夜の時間をメインに営業している酒場・ビヤホールがその影響を受けていることがわかります。
しかし、そのような中でも、昼の時間をメインに営業している飲食店には、人が集まってきています。
地元客を大切にしている飲食店ほどその傾向が顕著です。
このことから見ても、ランチ提供をメインに営業する地域密着型の飲食店は、今後も残っていくと考えられます。
新型コロナの影響で外出自粛が要請される中、インターネット上でお店を検索する機会がこれまで以上に増えました。
飲食店もその対象の例外ではありません。
インターネットで検索をして利用する飲食店を探そうとする際、お店の評判を基準に選択する方が多くなってきています。
提供する料理と接客の質が高い飲食店は、多くの利用者から高評価を得られます。
したがって、提供する料理と接客の質が高い飲食店は、今後も利用される機会が多いと考えられ、生き残っていく可能性が高いでしょう。
飲食店の廃業手続きは、事前準備をした上で各役所に廃業する旨の届出をして行うのが基本です。
法人経営の飲食店の場合は、それに加えて法人の解散と清算の手続きをしなければなりません。
廃業に踏み切る理由は、各飲食店によってさまざまです。
しかし、廃業を決めた後に行なう手続き方法やその内容の大枠は各飲食店共通です。
廃業後、スムーズに手続きを進められるように、その方法や必要書類の内容をしっかり把握しておきましょう。