

東京弁護士会所属。新潟県出身。
破産してしまうかもしれないという不安から、心身の健康を損ねてしまう場合があります。
破産は一般的にネガティブなイメージですが、次のステップへのスタート準備とも言えます。
そのためには、法律上の知識や、過去の法人破産がどのように解決されてきたかという知識が必要です。
法人破産分野を取り扱ってきた弁護士は、こういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって納得のいく措置をとることができます。
PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/kawasaki/
書籍:この1冊でわかる もめない遺産分割の進め方: 相続に精通した弁護士が徹底解説!
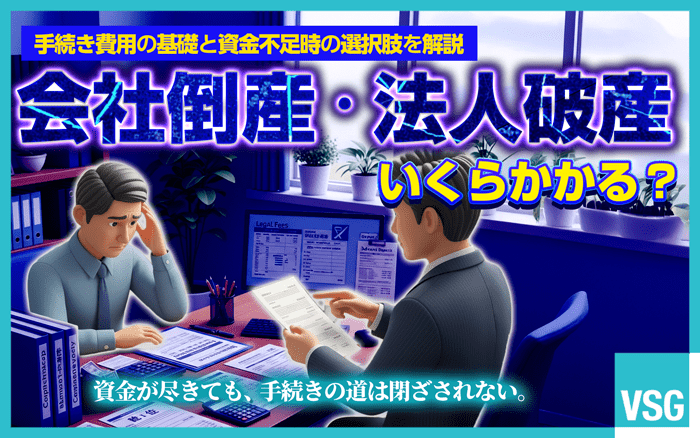
Contents
法人が破産手続きを行う場合、さまざまな名目で費用が発生します。破産に関する費用は大きく分けて、以下の3つのカテゴリーに分類できます。
ここでは、それぞれにかかる費用項目や相場を紹介します。
法人破産を申し立てる際、裁判所に対して手続き費用を納める必要があります。これらは手続きにかかる公的なコストであり、企業の規模や資産状況によって金額が変わる場合もあります。
法人破産の申し立てを裁判所に行う際には、申立手数料として1,000円が必要です。
申立手数料とは、裁判所に法人破産の申し立てを行う際に支払う手数料のことです。破産手続きの開始に必要な手続き費用の一部であり、裁判所に提出する申立書に貼る収入印紙で納めます。
予納金とは、裁判所が選任する破産管財人(弁護士など)の報酬や調査費用に充てるための費用です。法人破産の場合、もっとも大きな金額を占める費用がこの予納金です。
東京地方裁判所では、下記のような目安が示されています。
| 負債総額 | 予納金 |
|---|---|
| 5,000万円未満 | 70万円 |
| 5,000万円~1億円未満 | 100万円 |
| 1億円以上 | 200万円~700万円以上 |
予納金の金額は会社の資産や負債、事業の複雑さによって大きく変動します。費用が払えず手続きが進まないことを避けるためにも、あらかじめ弁護士に見積もりを出してもらうのが安心です。
予納郵券とは、破産手続きに関連する書類を裁判所から関係者に郵送するための切手代です。郵券とは「郵便切手」の略称で、あらかじめ一定金額の切手を裁判所に提出します。
法人破産の場合、予納郵券の相場はおおむね4,000~6,000円程度ですが、債権者の数が多い場合や通知件数が増えると、それに応じて必要な切手代も増えます。
会社が倒産すると、国が発行する情報誌「官報」に倒産した情報が掲載されます。これは、倒産する会社の債権者や利害関係人に、破産手続きに参加するための機会を与える目的があります。
法人破産の場合、官報公告費はおよそ15,000円ほどかかりますが、裁判所によって多少違いがあります。公告は法律で義務づけられているため、必ず支払う必要があります。
会社が破産手続きを進める際には、弁護士に依頼するのが一般的です。弁護士費用にはいくつかの項目があり、会社の規模や負債の金額、債権者の数などによって変わります。以下は、法人破産にかかる弁護士費用のおおよその目安です。
これらすべてを合わせた弁護士費用の総額は、60万円〜100万円程度となるのが一般的です。あくまで目安のため、依頼前に見積もりを取り、内容をよく確認することが大切です。
上記のほか、ケースによっては以下のような費用が発生することもあります。
これらは企業ごとに発生の有無が異なるため、一律の相場はありませんが、数万円~数十万円規模でかかることもあります。
法人破産や会社倒産にはまとまった費用がかかります。しかし、現実には「その費用すら用意できない」というケースも少なくありません。経営が悪化し、資金繰りに困窮している会社にとって、破産手続きにかかる支出は大きな負担となります。
ここでは、費用を用意できない状況であっても、破産手続きを諦めずに進めるための具体的な対処法を紹介します。いずれも現実的な方法であり、できることから一つずつ対応していくことで、解決への道が見えてきます。
会社名義で保有している財産がある場合は、それを現金化して破産費用に充てる方法が考えられます。たとえば、以下のような資産が対象になります。
売却方法としては、専門業者への買取依頼、オークションへの出品、債権者との協議による任意売却などがあります。利益の出る事業を譲渡する手法も、会社倒産ではよく使われる手法の一つです。
ただし、市場価格とかけ離れた安値での売却など、不適切な処分をすると破産管財人に否認権を行使される可能性があります。本来であればもっと高値で売却できたにもかかわらずそれを怠ったことが、債権者に配当すべき会社の資産を不当に減らす行為だと見なされるからです。
また、売却して得た現金を借金の返済に回したり、事業の継続に使ったりすると、その行為自体が問題視され、同様に否認権行使の対象となる場合があります。
取引先に対して売掛金が残っている場合、それをできるだけ早期に回収することで資金を確保できる可能性があります。売掛金とは、取引先に納品やサービス提供をしたにもかかわらず、まだ支払われていない未回収の代金のことです。
通常業務の延長線上での回収ですが、破産予定の企業に対して債務者が支払いを渋るケースもあります。必要であれば、内容証明郵便を送ったり、弁護士の名前で督促したりと、強めの手段を取ることも選択肢です。
法人と代表者の財産は法律上は別々の存在ですが、代表者個人が法人破産の費用を立て替えることも珍しくありません。特に中小企業では、代表者が自己資金を会社に投入して費用を捻出するケースがよく見られます。
ただし、代表者が法人の連帯保証人になっている場合、自身も自己破産を検討しなければならないケースがあります。会社のために代表者個人の資産を使うことは、代表者個人の債権者を害することになるため、基本的には認められません。
そのため、個人資産の提供に関しても、弁護士と十分に協議したうえで進める必要があります。必要であれば、親族などから援助を受けることを検討しましょう。
原則として予納金は一括で納めることが求められますが、例外的に裁判所の判断で分割払いが認められる場合があります。ただし、これはあくまで例外的措置であり、すべてのケースで認められるわけではありません。
分割が認められるためには、以下のような条件が影響すると言われています。
また、簡易な事件で破産管財人の業務負担が少ないことを理由に、予納金の減額を交渉できるケースもあります。運用や判断基準は裁判所によって異なるため、具体的な申立ては弁護士に依頼して慎重に進める必要があります.
「少額管財(しょうがくかんざい)」とは、通常の管財手続きよりも簡略化された破産手続きです。管財人の業務内容が限定されるため、予納金の金額も抑えられます。
法人の場合でも、資産や負債が少なく争いのある債権などがなければ、少額管財で手続きが進むことがあります。これにより、予納金を20万円程度にまで減額できる可能性があります。
ただし、少額管財事件で手続きを進めるためには、弁護士が代理人となることが条件とされています。裁判所や個別の事情ごとに判断は異なるため、状況から見て少額管財事件になりそうか、まずは弁護士へ相談してみることをおすすめします。
弁護士から各債権者に対して受任通知が送られると、直接の取り立てが法律上禁止されます。それ以降は返済をする必要もなくなるため、それまで返済に充てていた資金を破産手続にかかる費用として積み立てることが可能になります。
破産手続きに必要な書類の準備や調査には、ある程度の時間がかかります。現状では経済的に余裕がない会社でも、計画的に手続きを進めれば毎月の積立で費用を捻出することもできるでしょう。
ただし、弁護士が受任通知を出すタイミングには慎重さが求められます。「破産準備中」という情報が債権者や取引先に広まれば、支払いを求める訴訟が起こされたり、担保権を行使されたりするなど、状況が一気に悪化する可能性があります。
さらに、取引先や顧客が離れたり、従業員が不安を感じて離職するなど、事業の継続が難しくなるリスクも考慮しなければなりません。正式に依頼するタイミングについては、弁護士と慎重に相談しながら、最適なタイミングを見極めて進めることが重要です。
弁護士費用は原則として一括払いが基本ですが、法律事務所によっては分割払いに応じてくれるケースもあります。たとえば、着手金を数回に分けて支払えるよう契約を調整すれば、経済的な負担を軽くすることができます。
ただし、分割払いの可否は事務所ごとに異なるため、初回の相談時に費用の支払い方法について率直に確認することが大切です。柔軟な支払い計画に対応してくれる弁護士を選ぶことが、安心して破産手続きを進めるうえで重要なポイントとなります。
法人破産や会社倒産は、経営者にとって大きな精神的・経済的負担をともないます。破産に至るまでにできる対策を講じておくことで、その後の影響を最小限に抑えることが可能です。
ここでは、法人破産で経済的な困難を避けるために重要な2つのポイントを解説します。いずれも早めに行動することがカギとなるため、「まだ何とかなる」と思わず、兆候が見えた時点で真剣に検討していくことが大切です。
法人破産に陥る多くの企業は、「もう少し頑張れば何とかなる」と考えて判断を先延ばしにする傾向があります。しかし、資金繰りが完全に行き詰まってからでは、破産手続きに必要な費用すら確保できなくなり、結果的に破産できないという状況に陥るおそれがあります。
こうした兆候が見え始めた段階で、経営状況を冷静に分析し、必要であれば破産という選択肢を現実的に検討すべきです。早い段階で決断すれば、資産の処分や売掛金の回収などもスムーズに進み、手続き費用の確保がしやすくなります。
法人破産をする際には、破産手続きにくわしい専門家のサポートが不可欠です。弁護士に早い段階で相談することで、自社の状況に適した解決策を一緒に検討することができます。
早期相談には以下のようなメリットがあります。
弁護士への相談は、破産に踏み切るかどうかを決める前でも問題ありません。まずは現状の経営状況や資金繰りについて率直に話し、破産手続きの流れや費用、メリット・デメリットなどを説明してもらうことから始めましょう。
「もっと早く相談していればよかった」と後悔する経営者は少なくありません。早めの行動が、経済的なダメージを最小限にとどめる重要な鍵になります。
法人破産には、申立費用や予納金、弁護士報酬などがかかります。手続き費用が確保できない場合、破産を進めることが難しくなってしまうでしょう。その結果、以下のような問題が発生する可能性があります。
こうした状況を避けるためにも、破産に必要な最低限の費用は確保しなければなりません。前述のように、会社の資産や売掛金を活用して資金を準備したり、弁護士費用を分割してもらうなどの対応を検討することが重要です。
法テラス(日本司法支援センター)では、収入の少ない個人を対象に無料法律相談や弁護士費用の立替制度を提供しています。そのため、法人破産の場合、原則として法テラスの支援対象にはなりません。
ただし、代表者個人の破産手続きを並行して行う場合には、個人の破産についてのみ、法テラスの立替制度を利用できる場合があります。
とはいえ、弁護士事務所によっては、法人と個人両方の手続き費用について、立替払いを検討してくれるケースもあります。費用について不安があるなら、まずは専門家に直接相談してみることをおすすめします。
法人破産の申立てを代表者が行うことも可能ですが、現実的には弁護士なしでの破産手続きは非常に難しいといえます。理由としては、以下の点が挙げられます。
とくに法人破産は基本的に「管財事件」として扱われるため、破産管財人が選任されます。やりとりには専門的な知識が求められるため、弁護士のサポートを受けることがほぼ必須と考えたほうがよいでしょう。
費用の問題で弁護士への依頼をためらっている方も、まずは法律相談を受け、分割払いや少額管財制度の活用について検討してみてください。無理のない範囲での進行方法が見つかる可能性があります。
法人破産や会社倒産の手続きを進めるうえで、手続き費用の負担は避けて通れない重要な問題です。裁判所に納める申立手数料や予納金、官報公告費、さらには弁護士費用など、必要な支出は多岐にわたります。経営が厳しい状況にある中で、こうした費用をどう準備するかに悩む経営者も多いでしょう。
しかし、破産や倒産を必要以上に恐れる必要はありません。早期に行動し、資産の整理や債権の回収を行えば、費用の確保が可能になる場合もあります。また、弁護士と相談しながら手続きを進めれば、少額管財制度の適用や費用の分割払いなど、負担を抑える方法も見つかるかもしれません。
資金繰りの悪化が深刻化する前に破産を検討し、早い段階で弁護士に相談することで、より有利な条件で再出発の準備を整えることができます。「破産できない状況」に追い込まれる前に、適切な判断と行動が何よりも重要です。
法人破産についてお困りごとがあれば、法人破産に強い”VSG弁護士法人”に、ぜひお気軽にご相談ください。