

東京弁護士会所属。
メーカー2社で法務部員を務めた後、ロースクールに通って弁護士資格を取得しました。
前職の経験を生かし、実情にあった対応を心がけてまいります。 お気軽に相談いただければ幸いです。
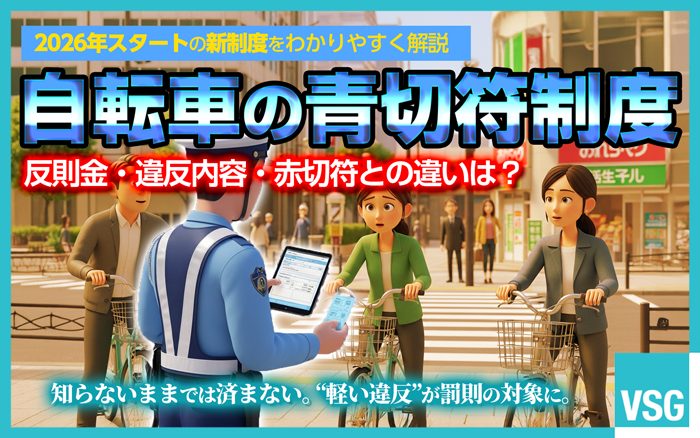
自転車の交通違反に対する取締りが強化される中、2024年5月に公布された改正道路交通法により、自転車にも「青切符」制度が導入されます。これまで指導警告カード(いわゆるイエローカード)による注意で済んでいた自転車の交通違反が、反則金を伴う処罰の対象となります。
自転車事故の増加傾向を受け、より実効性のある取締りを目指すこの制度改正。しかし、多くの自転車利用者にとって、青切符制度の詳細や対象となる違反行為、赤切符との違いなど、不明な点が数多く存在するのが現状です。
本記事では、自転車の青切符制度について、対象となる違反行為から反則金の金額、年齢制限までを弁護士がわかりやすく解説します。
目次
自転車の交通違反で青切符を受け取った場合、どのような手続きが必要で、どのような影響があるのでしょうか。まずは青切符制度の基本的な仕組みからくわしく解説します。
交通反則通告制度とは、運転者が行った一定の道路交通法違反について、反則者が警察本部長の通告を受けて反則金を納付した場合、公訴が提起されない制度です。この制度で交付される交通反則告知書が青い色をしているため、一般的に「青切符」と呼ばれています。
青切符制度の最大の特徴は、反則金を納付すれば前科がつかない点にあります。通常の刑事手続きとは異なり、簡易迅速な処理により違反処理を終結できるため、違反者と警察双方の負担軽減につながります。
この制度が創設された背景には、昭和42年当時の交通違反の急増があります。交通事故の増加に伴い、通常の刑事手続きによる処理で「一億総前科者」となる事態を防ぐため、比較的軽微で現認可能、明白かつ定型的な違反行為について、簡易な処理方法として導入されました。
この制度の対象は自動車と原動機付自転車であり、自転車を含む軽車両は対象外でした。しかし、自転車関連事故の増加を受け、2024年5月に公布された改正道路交通法により、自転車も対象に加わることが決定しました。同制度は2026年4月1日から施行される予定です。
自転車の青切符における反則金の具体的な金額は、2025年6月17日の閣議で決定されています。自転車の青切符における具体的な反則金は、以下のとおりです。
反則金の納付は「任意」であるため、反則金を納付しないことにより、通常の刑事手続きによる処理を選択することも可能です。この場合、検察庁に送致され、起訴・不起訴の判断を受けることになります。
交通違反の処理方法には青切符と赤切符の2種類があり、それぞれ適用される違反行為や処理手続きが大きく異なります。
青切符は比較的軽微な交通違反に適用される制度です。対象となるのは現認可能で明白、定型的な違反行為約150種類で、反則金を納付すれば前科がつかず、簡易迅速に処理を終結できます。自転車の場合、信号無視、一時不停止、通行区分違反などが主な対象となります。
一方、赤切符は比較的重い交通違反や悪質な違反行為に適用されます。交通反則通告制度の適用外となるため、通常の刑事手続きにより処理されます。自転車の場合、赤切符の対象となる非反則行為には、酒酔い運転や妨害運転などがあります。
青切符では反則金を納付するか刑事手続きを選択するかを違反者が決められますが、赤切符では必ず刑事手続きによる処理となります。
自転車の青切符制度では、どのような違反行為が対象となり、誰が処罰を受けるのでしょうか。対象となる違反行為と運転者の条件についてくわしく解説します。
自転車の青切符制度では、113種類の違反行為が反則行為として指定されています。これらは現認可能で明白、定型的という基準に基づいて選定されており、自動車等と共通する違反行為と自転車固有の違反行為で構成されています。
特に危険性・迷惑性が高い違反行為については重点的な取締りが実施される予定で、日常的な自転車利用において注意すべき重要なポイントとなります。詳細な違反行為の一覧と反則金については、警察庁の公式資料をご確認ください。
なお、酒酔い運転、妨害運転、自転車運転者講習受講命令違反などの特に悪質な行為は、青切符の対象外として通常の刑事手続きによる処理が行われます。
自転車の青切符制度では、16歳以上の自転車運転者が対象となります。この年齢設定には明確な理由があり、教育的配慮と実効性の観点から決定されています。
16歳以上の者は義務教育を修了しており、基本的な自転車の交通ルールに関する最低限の知識を有していると考えられます。また、交通反則通告制度による画一的な処理になじむ年齢であるとの判断も背景にあります。
さらに、16歳は特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の運転が可能な年齢であり、原付免許や自動二輪免許の取得も可能です。これらの車両については既に交通反則通告制度の対象となっているため、一貫性の観点からも16歳以上が適当とされました。
16歳未満の自転車運転者については、交通ルールに関する知識の程度や交通反則通告制度の効果等に関する理解度に個人差が大きいことが考慮され、引き続き青切符制度の対象外となります。
自転車の青切符制度と並行して、危険な違反行為を繰り返す運転者に対する自転車運転者講習制度も継続されます。
自転車運転者講習制度は、平成27年6月1日から施行されている制度で、交通の危険を生じさせるおそれのある一定の違反行為(危険行為)について、3年以内に2回以上検挙された違反者に対して都道府県公安委員会が講習の受講を命じるものです。
自転車運転者講習の対象となる危険行為は16種類で、2024年11月1日からは「酒気帯び運転」と「ながら運転」が追加されています。
反則行為に分類される危険行為には、以下のようなものがあります。
非反則行為に分類される危険行為には、酒酔い運転、酒気帯び運転、妨害運転があります。
青切符もしくは赤切符により処理された違反であっても、危険行為を3年以内に2回以上犯した場合は講習の対象となります。
講習時間は3時間で、受講手数料として6,000円(標準額)が必要です。受講命令を受けたにもかかわらず正当な理由なく受講しなかった場合は、5万円以下の罰金が科されます。
自転車の青切符制度導入と併せて、近年、自転車の交通違反に対する罰則が大幅に強化されています。
2024年11月1日から施行された改正道路交通法により、自転車の酒気帯び運転に対する罰則が新設されました。
酒気帯び運転とは、血液1ミリリットルにつき0.3mg以上または呼気1リットルにつき0.15mg以上のアルコールが検出された状態での運転を指します。一方、酒酔い運転とは、血中や呼気中のアルコール濃度にかかわらず、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれのある状態での運転を指します。
自転車で酒気帯び運転をした場合「3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」を科される可能性があります。さらに、ほう助行為についても罰則が規定されました。
なお、酒酔い運転については従来どおり「5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金」が科されます。
警察庁のデータによれば、自転車事故における死亡重傷事故率(第1当事者)は、飲酒なしの場合が15.50%であるのに対し、酒気帯び運転の場合は29.51%と約1.9倍に上ります。こうした危険性の高さから、自転車に対しても自動車と同様の厳しい取り締まりが導入されました。
自転車運転中のスマートフォン使用による交通事故の増加を受け、2024年11月1日から罰則が大幅に強化されました。
改正により道路交通法第71条第5の5号の規制対象に自転車が追加され、通常のながら運転で「6カ月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金」、交通の危険を生じさせた場合は「1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金」となっています。
ながら運転として規制対象となる行為には、自転車運転中にスマートフォンで通話することや、スマートフォンに表示された画面を注視することが含まれます。ハンズフリー装置を利用した通話は規制の対象外です。
警察庁のデータによると、自転車運転中の携帯電話使用などが原因となった交通事故は、平成25年から29年までの累計で295件でした。これに対し、平成30年から令和4年までの累計では454件となり、約53.9%の増加が見られます。こうした事故件数の増加が、近年の道路交通法改正や罰則強化の大きな背景となっています。
自転車への青切符制度は、2024年5月に公布された改正道路交通法に基づき、2026年4月1日から施行されます。
ヘルメット着用は2023年4月から努力義務となっていますが、現時点では罰則の対象外です。そのため、ヘルメットを着用していなくても青切符を切られることはありません。ただし、交通事故時の過失割合に影響する可能性があります。
青切符制度の対象は16歳以上の自転車運転者です。16歳未満については従来通り指導警告や交通安全教育が中心となります。ただし、14歳以上で危険行為を繰り返した場合は自転車運転者講習の対象となる可能性があります。
青切符による反則金処理は前科にならず、自動車免許の点数制度とも別の制度です。そのため、自転車で青切符を受けても自動車のゴールド免許には影響しません。
ただし、自転車で重大違反をして赤切符を交付された場合は刑事処分の対象となるため、その結果によっては自動車免許にも影響が及ぶ可能性があります。
自転車の青切符制度導入は、増加する自転車事故を抑制し、安全な交通環境を実現するための重要な施策です。反則金という金銭的負担が生じることで、これまで軽視されがちだった自転車の交通ルール遵守に対する意識向上が期待されています。
自転車は便利で環境に優しい移動手段ですが、道路を走る以上「車両」としての責任が伴います。万が一事故を起こせば、損害賠償や刑事処分に発展し、生活や仕事に大きな影響を与える可能性もあります。
もし自転車事故でトラブルに直面したり、対応に不安を感じたりした場合は、一人で抱え込まずに専門家へ相談してください。相談先に迷ったら、交通事故で豊富な実績を持つ「VSG弁護士法人」までぜひお気軽にご相談ください。


 人身事故の罰金・罰則と違反点数は?物損事故との違いや事故後の対応も解説
人身事故の罰金・罰則と違反点数は?物損事故との違いや事故後の対応も解説 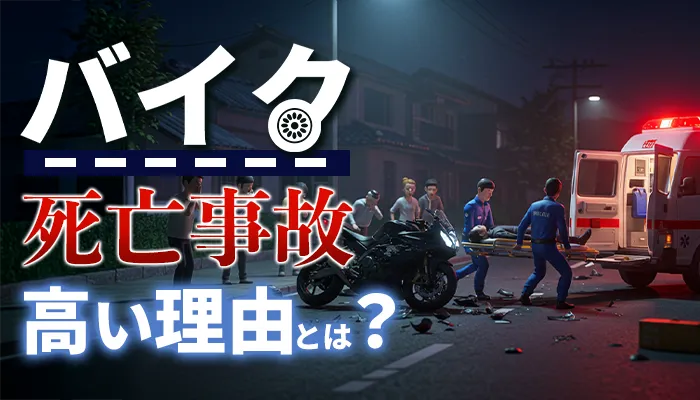 バイク事故の死亡率はなぜ高い?原因や事故時の対処法を解説
バイク事故の死亡率はなぜ高い?原因や事故時の対処法を解説 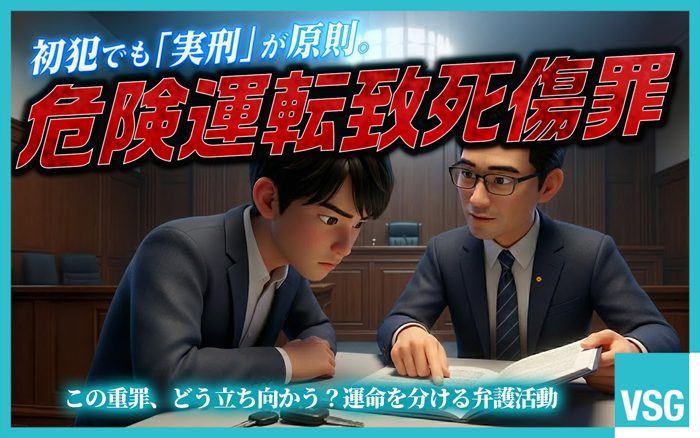 危険運転致死傷罪とは?初犯でも実刑はある?量刑や判例を解説
危険運転致死傷罪とは?初犯でも実刑はある?量刑や判例を解説  自転車と自動車の事故の過失割合はどう決まる?事故状況の例と併せて解説
自転車と自動車の事故の過失割合はどう決まる?事故状況の例と併せて解説 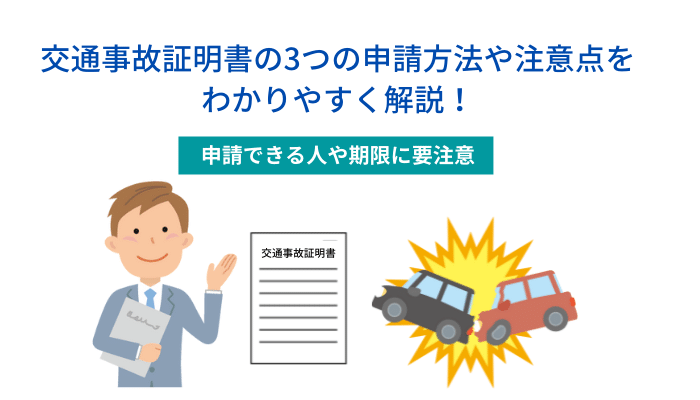 交通事故証明書の3つの申請方法や注意点をわかりやすく解説!申請できる人や期限に要注意
交通事故証明書の3つの申請方法や注意点をわかりやすく解説!申請できる人や期限に要注意  交通事故における少額訴訟の費用と手順
交通事故における少額訴訟の費用と手順 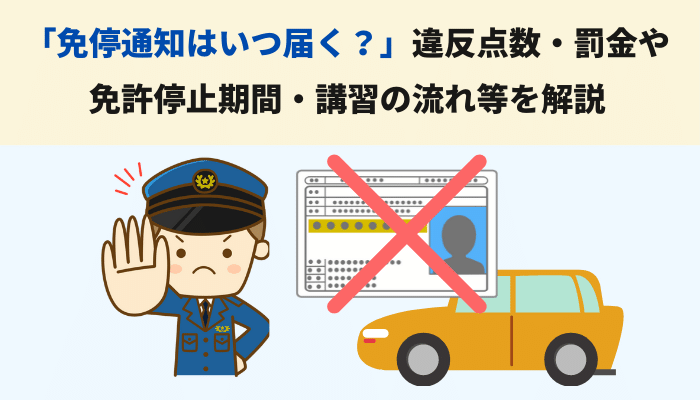 「免停通知はいつ届く?」違反点数・罰金や免許停止期間・講習の流れ等を解説
「免停通知はいつ届く?」違反点数・罰金や免許停止期間・講習の流れ等を解説  都内の自転車事故による死亡事故統計 事故に遭わないために知っておくべき交通ルール
都内の自転車事故による死亡事故統計 事故に遭わないために知っておくべき交通ルール 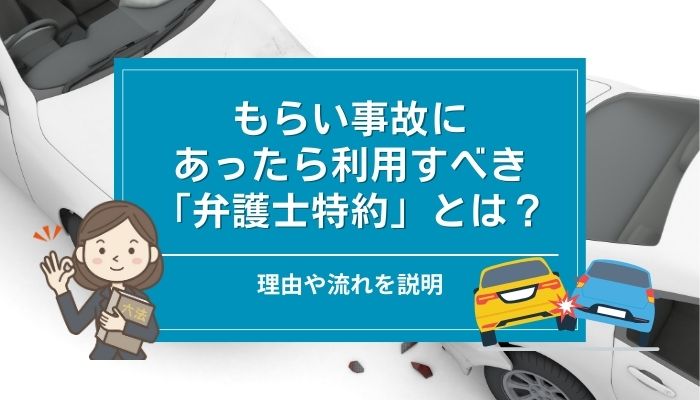 もらい事故にあったら利用すべき「弁護士特約」とは?理由や流れを説明
もらい事故にあったら利用すべき「弁護士特約」とは?理由や流れを説明