

東京弁護士会所属。新潟県出身。
破産してしまうかもしれないという不安から、心身の健康を損ねてしまう場合があります。
破産は一般的にネガティブなイメージですが、次のステップへのスタート準備とも言えます。
そのためには、法律上の知識や、過去の法人破産がどのように解決されてきたかという知識が必要です。
法人破産分野を取り扱ってきた弁護士は、こういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって納得のいく措置をとることができます。
PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/kawasaki/
書籍:この1冊でわかる もめない遺産分割の進め方: 相続に精通した弁護士が徹底解説!
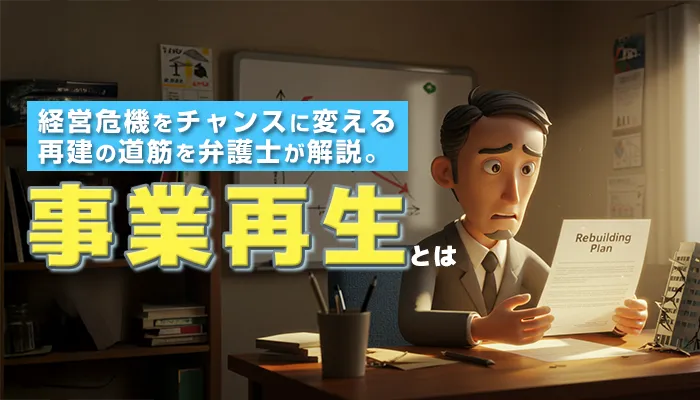
Contents
事業再生は、特定事業の選択と集中・負債のリスケ・事業譲渡など、事業単位の再建に焦点が当たる場面で使われることが多い語です。
一方の企業再生は、事業再生に加えて、財務・ガバナンスの再構築まで含む広い概念として用いられることがあります。
もっとも、実務では厳密に区別されないことも多く、文脈に応じて読み替えるのが一般的です。
実務では、法的再生と私的再生を軸に、状況に応じてM&A(事業譲渡)やプレパッケージ型のスキームを組み合わせます。
| 観点 | 法的再生(民事再生/会社更生) | 私的再生(ガイドライン/ADR 等) |
|---|---|---|
| スピード | 中〜長期(数か月〜) | 短期に動きやすい |
| 開示・風評 | 公告・開示が前提 | 非公開性が高い |
| 強制力 | 計画に裁判所の強制力 | 合意ベース(反対で頓挫) |
| 担保・差押の停止 | 保全処分等で停止を図れることがある | 原則なし(合意で調整) |
| 経営陣の継続 | DIP(民事再生)/管財型(更生) | 基本継続(合意次第) |
| 取引先への影響 | 大きい傾向 | 比較的小さい |
| 費用感 | 相対的に大きい | 相対的に小さい |
※期間は事案により大きく前後します。プレパックの準備に数週間〜数か月、申立〜可決・認可まで数か月〜のイメージです。
取引停止や賃金未払いが迫る局面では、法的保全(差押・取立の停止)を確保できる手続きが適する場合があります。もっとも、スポンサーの用意や債権者の構成により最適解は変わるため、個別に検討が必要です。
一般に、再生スキームとあわせて「経営者保証に関するガイドライン」の適用を検討します。財産状況・法人と個人の分離・返済可能性等の要件を満たすかがポイントです。
非公開性の高い私的再生や、プレパッケージ型と民事再生の組合せで短期に実行する方法等が考えられます(事案により)。
事業再生は、法的再生(民事再生・会社更生)と私的再生(ガイドライン・ADR 等)のいずれか、または組合せで実行します。
最適解は、資金繰りの猶予・債権者構成・担保/保証・スポンサーの有無で変わるため、早い段階の診断と設計が重要です。
VSG弁護士法人では、原因分析から計画立案、債権者調整、申立・実行まで、状況に応じたスキームをご提案します。