

東京弁護士会所属。
メーカー2社で法務部員を務めた後、ロースクールに通って弁護士資格を取得しました。
前職の経験を生かし、実情にあった対応を心がけてまいります。 お気軽に相談いただければ幸いです。

2020年に民法が改正され、交通事故の損害賠償計算に使用されるライプニッツ係数にも変化が生じました。
ライプニッツ係数とは、逸失利益の計算で重要な数値であり、被害者が適切な賠償を受け取るために欠かせません。
この記事では、ライプニッツ係数のしくみや計算方法、またホフマン係数との違いを詳しく解説します。
さらに、民法改正後の法定利率の変更が賠償額にどのような影響を与えるのかを見ていきます。
目次
ライプニッツ係数は、交通事故の逸失利益を計算する際に使用される重要な数値です。
逸失利益とは、事故がなければ将来得られたはずの収入のことで、賠償額を公平に計算するために使われます。
ここでは、ライプニッツ係数の意味や使い方、ホフマン係数との違いをわかりやすく解説します。
逸失利益とは、交通事故が原因で後遺障害が残った場合や死亡した場合に、被害者が将来得られなくなる収入のことを指します。
たとえば、事故によって仕事ができなくなり、収入が減少した場合、その損失分を加害者に請求することができます。
これが逸失利益です。
労働能力が一部制限される場合や完全に失われる場合、または死亡による収入減少も含まれます。
逸失利益を計算する際には、以下の3つの要素が必要です。
ライプニッツ係数は、逸失利益を計算する際に中間利息を控除するために使用されます。
賠償金は通常、一括で支払われることが一般的です。
しかし、本来の収入として受け取る場合、それは本来毎年少しずつ受け取るはずだったお金です。
それを一括で受け取ることで、受領者に「運用利益」が発生してしまいます。
この運用利益を差し引くために用いる数値がライプニッツ係数です。
ライプニッツ係数とホフマン係数は、どちらも交通事故の賠償額を計算する際に中間利息を控除するために使用されますが、その計算方法には明確な違いがあります。
ライプニッツ係数は、複利を基準として計算されます。
この方法では、元本だけでなく、利息にもさらに利息をつける形で計算が進められます。
そのため、より正確かつ公平な結果を得ることが可能です。
この特徴から、現在の交通事故賠償の実務では、ライプニッツ係数が一般的に使用されています。
一方で、ホフマン係数は単利を基準に計算されます。
この方法では、元本のみに利息を付ける形で計算されるため、複利計算を行うライプニッツ係数に比べて控除額が少なくなる傾向があります。
たとえば、10年間の賠償額を計算した場合、ライプニッツ係数を使った場合の方がホフマン係数よりも控除額が大きくなります。
そのため、現在の賠償実務では、ライプニッツ係数が主に採用されており、より公平な計算方法とされています。
ここでは、ライプニッツ係数を用いた「後遺障害逸失利益」、「死亡逸失利益」の計算方法を紹介します。
後遺障害が残った場合、次の式で逸失利益を計算します。
計算式
後遺障害逸失利益=基礎収入 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数
| 後遺障害等級 | 労働能力喪失率 |
|---|---|
| 第1級 | 100% |
| 第2級 | 100% |
| 第3級 | 100% |
| 第4級 | 92% |
| 第5級 | 79% |
| 第6級 | 67% |
| 第7級 | 56% |
| 第8級 | 45% |
| 第9級 | 35% |
| 第10級 | 27% |
| 第11級 | 20% |
| 第12級 | 14% |
| 第13級 | 9% |
| 第14級 | 5% |
別表Ⅰ 労 働 能 力 喪 失 率 表 自動車損害賠償保障(国土交通省)
| 年齢 | 就労可能年数 | ライプニッツ係数 |
|---|---|---|
| 18 | 49 | 25.5017 |
| 19 | 48 | 25.2667 |
| 20 | 47 | 25.0247 |
| 21 | 46 | 24.7754 |
| 22 | 45 | 24.5187 |
| 23 | 44 | 24.2543 |
| 24 | 43 | 23.9819 |
| 25 | 42 | 23.7014 |
| 26 | 41 | 23.4124 |
| 27 | 40 | 23.1148 |
| 28 | 39 | 22.8082 |
| 29 | 38 | 22.4925 |
| 30 | 37 | 22.1672 |
| 31 | 36 | 21.8323 |
| 32 | 35 | 21.4872 |
| 33 | 34 | 21.1318 |
| 34 | 33 | 20.7658 |
| 35 | 32 | 20.3888 |
| 36 | 31 | 20.0004 |
| 37 | 30 | 19.6004 |
| 38 | 29 | 19.1885 |
| 39 | 28 | 18.7641 |
| 40 | 27 | 18.3270 |
| 41 | 26 | 17.8768 |
| 42 | 25 | 17.4131 |
| 43 | 24 | 16.9355 |
| 44 | 23 | 16.4436 |
| 45 | 22 | 15.9369 |
| 46 | 21 | 15.4150 |
| 47 | 20 | 14.8775 |
| 48 | 19 | 14.3238 |
| 49 | 18 | 13.7535 |
| 50 | 17 | 13.1661 |
| 51 | 16 | 12.5611 |
| 52 | 15 | 11.9379 |
| 53 | 14 | 11.2961 |
| 54 | 14 | 11.2961 |
| 55 | 14 | 11.2961 |
| 56 | 13 | 10.6350 |
| 57 | 12 | 9.9540 |
| 58 | 12 | 9.9540 |
| 59 | 12 | 9.9540 |
| 60 | 12 | 9.9540 |
| 61 | 11 | 9.2526 |
| 62 | 11 | 9.2526 |
| 63 | 10 | 8.5302 |
| 64 | 10 | 8.5302 |
| 65 | 10 | 8.5302 |
| 66 | 9 | 7.7861 |
| 67 | 9 | 7.7861 |
| 68 | 8 | 7.0197 |
| 69 | 8 | 7.0197 |
| 70 | 8 | 7.0197 |
| 71 | 7 | 6.2303 |
| 72 | 7 | 6.2303 |
| 73 | 7 | 6.2303 |
| 74 | 6 | 5.4172 |
| 75 | 6 | 5.4172 |
| 76 | 6 | 5.4172 |
| 77 | 5 | 4.5797 |
| 78 | 5 | 4.5797 |
| 79 | 5 | 4.5797 |
| 80 | 5 | 4.5797 |
| 81 | 4 | 3.7171 |
| 82 | 4 | 3.7171 |
| 83 | 4 | 3.7171 |
| 84 | 4 | 3.7171 |
| 85 | 3 | 2.8286 |
| 86 | 3 | 2.8286 |
| 87 | 3 | 2.8286 |
| 88 | 3 | 2.8286 |
| 89 | 3 | 2.8286 |
| 90 | 3 | 2.8286 |
| 91 | 2 | 1.9135 |
| 92 | 2 | 1.9135 |
| 93 | 2 | 1.9135 |
| 94 | 2 | 1.9135 |
| 95 | 2 | 1.9135 |
| 96 | 2 | 1.9135 |
| 97 | 2 | 1.9135 |
| 98 | 2 | 1.9135 |
| 99 | 2 | 1.9135 |
| 100 | 2 | 1.9135 |
| 101~ | 1 | 0.9709 |
年収1000万円の会社員で、40歳で後遺障害等級10級の後遺障害が残った場合の後遺障害逸失利益は、以下のように計算します。
計算式
後遺障害逸失利益=基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数
上記の計算式に当てはめると、後遺症逸失利益は1,000万円×27%×18.3270=4,948万2,900円となります。
被害者が死亡した場合、逸失利益の計算式は以下の通りです。
計算式
死亡逸失利益=基礎収入×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対するライプニッツ係数
先ほどの年収1,000万円の会社員(40歳)が、交通事故で亡くなった場合の死亡逸失利益を計算しましょう。
既婚で、扶養家族は2人とします。
計算式
死亡逸失利益=基礎収入×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対するライプニッツ係数
上記の計算式に当てはめると、死亡逸失利益は
1,000万円×(1-0.3)×18.3270=1億2,828万9,000円となります。
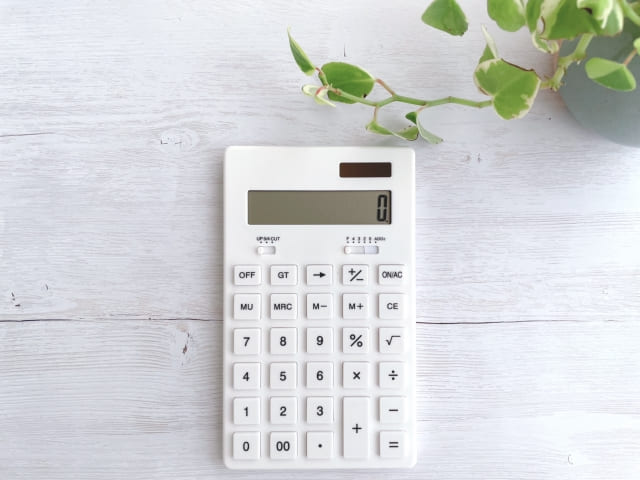
2020年に民法が改正され、ライプニッツ係数にも変化がありました。
これにより、損害賠償の金額が増えることがあります。
具体的に見ていきましょう。
2020年4月1日から、法定利率が5%から3%に引き下げられました。
また、中間利息控除を計算するとき、この新しい法定利率を使うことが決まりました(民法417条の2)。
さらに、法定利率は固定ではなくなり、3年ごとに見直されるようになりました。
2024年の時点では3%ですが、2026年以降の利率はまだ決まっていません。
法定利率が下がることで、損害賠償額にも影響があります。
中間利息控除の額が減るため、逸失利益は増加します。
これは被害者にとってプラスです。
一方で、遅延損害金の利率も引き下げられるため、遅延損害金の金額は減少します。
ただし、多くの場合、逸失利益の増加額のほうが遅延損害金の減少額を上回るため、全体的には被害者にとって有益に働きます。
ライプニッツ係数を理解することで、交通事故での損害賠償計算における基準やしくみを把握できますが、正確な金額を導き出すには専門知識が必要です。
特に、法定利率の変動や民法改正の影響を踏まえた計算は、個人で対応するのが難しいこともあります。
事故後に適切な賠償を受け取るためには、まず自分のケースに合った基礎収入や労働能力喪失率を把握することが重要です。
そのうえで、信頼できる弁護士や保険会社の担当者に相談し、逸失利益や慰謝料の具体的な計算を依頼しましょう。


 人身事故の罰金・罰則と違反点数は?物損事故との違いや事故後の対応も解説
人身事故の罰金・罰則と違反点数は?物損事故との違いや事故後の対応も解説 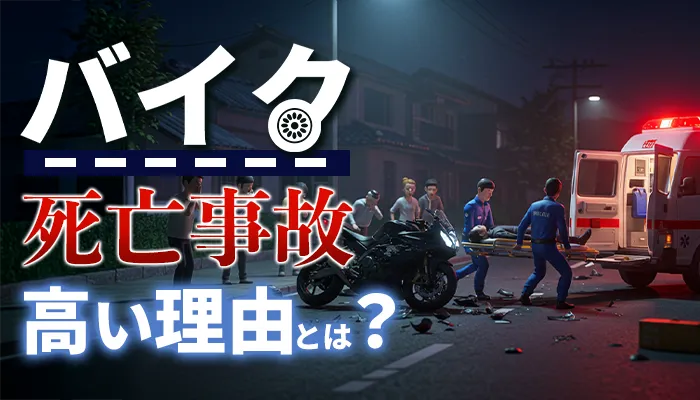 バイク事故の死亡率はなぜ高い?原因や事故時の対処法を解説
バイク事故の死亡率はなぜ高い?原因や事故時の対処法を解説 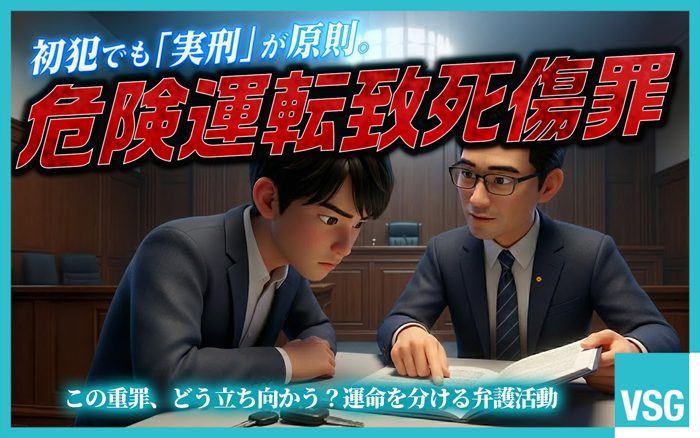 危険運転致死傷罪とは?初犯でも実刑はある?量刑や判例を解説
危険運転致死傷罪とは?初犯でも実刑はある?量刑や判例を解説  自転車と自動車の事故の過失割合はどう決まる?事故状況の例と併せて解説
自転車と自動車の事故の過失割合はどう決まる?事故状況の例と併せて解説 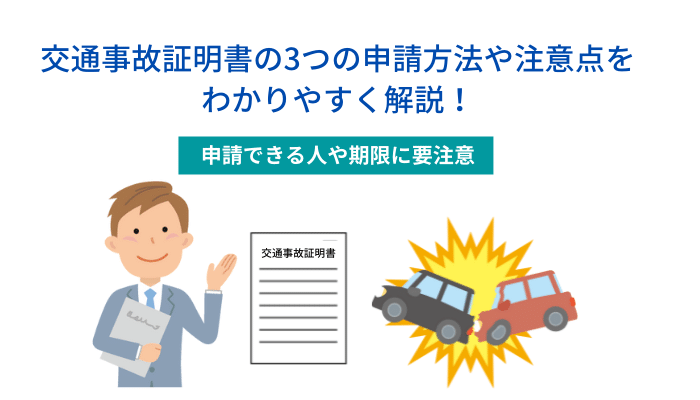 交通事故証明書の3つの申請方法や注意点をわかりやすく解説!申請できる人や期限に要注意
交通事故証明書の3つの申請方法や注意点をわかりやすく解説!申請できる人や期限に要注意  交通事故における少額訴訟の費用と手順
交通事故における少額訴訟の費用と手順 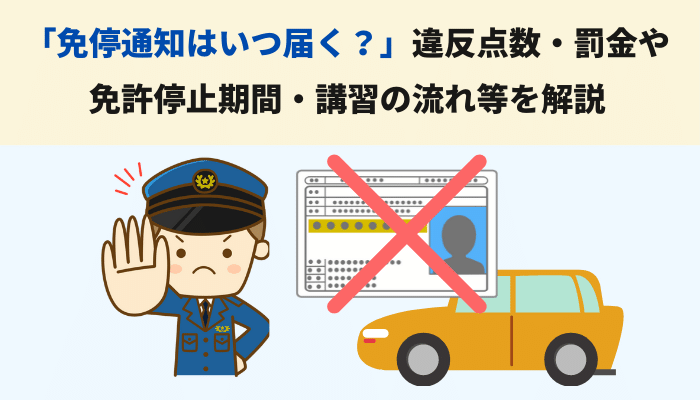 「免停通知はいつ届く?」違反点数・罰金や免許停止期間・講習の流れ等を解説
「免停通知はいつ届く?」違反点数・罰金や免許停止期間・講習の流れ等を解説  都内の自転車事故による死亡事故統計 事故に遭わないために知っておくべき交通ルール
都内の自転車事故による死亡事故統計 事故に遭わないために知っておくべき交通ルール 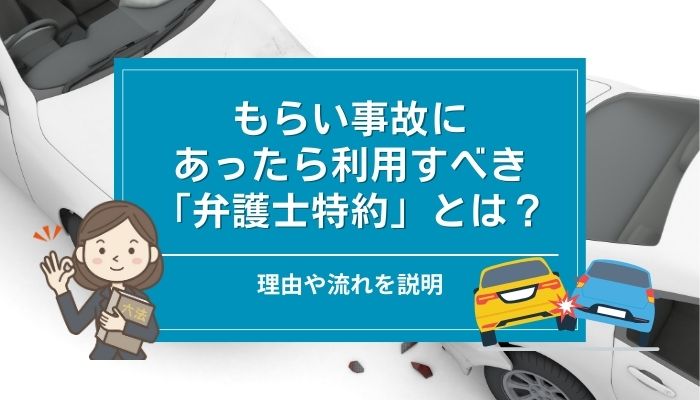 もらい事故にあったら利用すべき「弁護士特約」とは?理由や流れを説明
もらい事故にあったら利用すべき「弁護士特約」とは?理由や流れを説明