

東京弁護士会所属。新潟県出身。
交通事故の影響で怪我や病気になってしまうと、体調の不安に加えて、経済的な不安も発生します。
慰謝料を請求するためには、法律上の知識や、過去の交通事故被害がどのような慰謝料額で解決されてきたかという判例の知識が必要です。
我々はこういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって、妥当な損害賠償金を勝ち取ることが期待できます。是非一度ご相談ください。
PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/kawasaki/
書籍:この1冊でわかる もめない遺産分割の進め方: 相続に精通した弁護士が徹底解説!
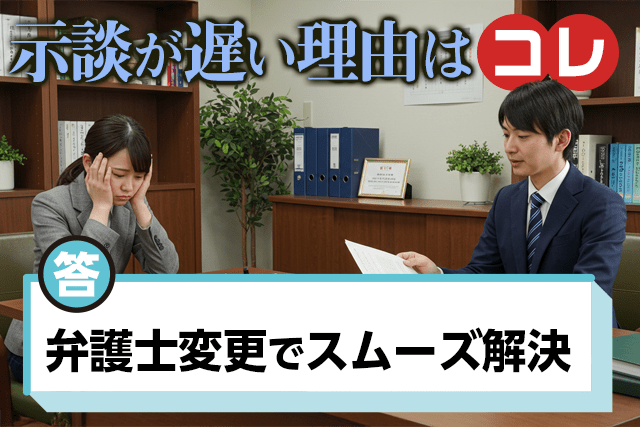
目次
交通事故で弁護士に依頼したにもかかわらず示談が遅い理由は、主に次のとおりです。
正しい対処法を取るためにも、なぜ示談が進まないのかその原因をしっかり把握しておきましょう。
相手方保険会社との示談交渉が揉めている場合、示談成立までに時間がかかる可能性があります。
揉める原因は様々です。被害者の代理人である弁護士は当然賠償金を増額するために示談交渉をおこないますが、加害者側の保険会社は自社の損失を少なくするためにできる限り賠償金の額を減らそうと考えます。両者の立場に違いがある以上、過失割合や判例の解釈などで揉める可能性は十分考えられるでしょう。
また交渉で話し合いがつかない場合、裁判にまで発展する可能性があります。その場合、示談が成立するまでにさらに時間がかかる場合があります。
依頼した弁護士が交通事故の対応に慣れていない弁護士の場合、各種手続きがスムーズに行かず示談が遅れる可能性があります。
外科医、内科医、産婦人科医など医者にも専門があるように、弁護士にもそれぞれ注力している分野があります。
もちろん弁護士である以上、多岐に渡る法律トラブルを解決に導けるのは間違いはありません。しかし、注力してない分野の事件については同じ弁護士であっても対応が遅くなってしまうケースは避けられません。
とくに交通事故の対応には、医学的な知識を含む専門的な知識が必要になります。対応が遅い、納得結果を得られていないと感じたら交通事故に精通している弁護士への変更も検討すべきでしょう。
手続き自体は進んでいるものの、依頼者への連絡を忘れているだけのパターンも考えられます。
弁護士が業務を進めるうえで依頼者とコミュニケーションを密に取るのは当たり前の話です。しかし、残念ながら依頼者ファーストではない弁護士に依頼してしまうと、依頼者に報告せずに手続きを進められてしまう可能性があります。
また、単純に忙しくて連絡を忘れているだけの場合もあるでしょう。
このケースの場合、手続き自体は進んでいるので案件を放置されている心配はしなくても良いでしょう。
ただし、依頼者への事前確認なしに手続きを進める弁護士の場合、依頼者が思う解決内容と弁護士が考える解決内容にズレが生じて依頼を後悔する可能性があります。
依頼した弁護士は滞りなく手続きを進めているものの、交渉の相手方である保険会社の対応が遅くて示談が進まないケースもあります。
保険会社は自社の営利を追求する営利企業です。そのため多少時間がかかっても自社の利益が最大限になるよう対応してくる可能性が高いです。
対応が遅い原因は様々ですが、単純に担当者の業務が手一杯になっている可能性も否定できません。
また法的な判断について顧問弁護士と書面でやり取りしたり、重大な判断について会社の判断を仰ぐような場合にも対応が遅くなるだろうと考えられます。
依頼した弁護士が他の案件で忙しくて対応・連絡が遅れている可能性もあります。
弁護士は1つの案件だけを抱えて対応しているのではなく、何件もの案件を同時並行で進めています。そのため、裁判期日が近いものや時効成立が迫っている案件、厳格な時間制限の下で手続きが進む刑事事件の対応などを優先する傾向にあります。
経験豊富な弁護士であれば全ての案件をスムーズに進める方法を熟知していますが、経験の浅い弁護士の場合、急ぎの案件だけで手一杯になってしまう恐れがあるでしょう。
依頼する弁護士を選ぶ際は、連絡を密に取り不安を感じさせない対応をしてくれるかどうかを見極める必要があるでしょう。
交通事故の示談が遅れると、依頼者が不安を感じるだけでなくさまざまなデメリットがあります。
ここでは交通事故で示談が遅れた場合の主なデメリットを解説していきます。
示談が遅れればその分示談金を受け取るのも遅くなるので、経済的な苦しさから解放されない恐れがあります。
交通事故で被害にあった場合、車の修理費や休んでしまった仕事の給料などを自分で補填する必要があります。示談交渉の進め方によっては示談金の一部を先に受け取れる場合もありますが、基本的には示談が成立したあとでなければ損害の賠償金は受け取れません。
示談金増額のために徹底的に争っているのであればいいですが、単純に業務過多で対応が遅れている場合には、示談を遅らせるデメリットは大きいといえるでしょう。
示談成立までにあまりに時間がかかっている場合には、損害賠償の請求権が時効にかかってしまい賠償金を受け取れなくなる恐れがあります。
交通事故における損害賠償請求権の時効は、次のとおりです。
| 損害 | 時効 | |
|---|---|---|
| 物損 | 車の修理費、車の買い替え費用等 | 事故発生日の翌日から3年 |
| 傷害 | 入通院慰謝料、治療費、休業損害等 | 事故発生日の翌日から5年 |
| 後遺障害 | 後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益 | 症状固定日の翌日から5年 |
| 死亡 | 死亡慰謝料、死亡逸失利益、葬儀費等 | 死亡した日の翌日から5年 |
例外もありますが、基本的には5年(物損部分については3年)で賠償を請求できなくなってしまいます。時効の成立が近いにもかかわらず動きが遅い場合には、早急に対策を施す必要があるでしょう。
交通事故で弁護士に依頼したにもかかわらず対応が遅い場合には、次の3つの対処法を試してみましょう。
まずは依頼している弁護士に進捗状況を確認してください。そのうえで、対応が遅れている理由やいつまでに対応できるのかを確認してみましょう。
相手方の保険会社の対応が遅れている場合であれば問題ないですが、弁護士の業務過多で対応が遅れているのであれば、対応が遅れていることで依頼継続を不安に感じていることを明確に伝えましょう。
弁護士と直接連絡が取れない場合には、事務員に伝言を伝えるのも良いでしょう。担当事務員なら進捗状況を把握している場合も多いので、単純な質問であればその場で回答を得られる可能性もあります。
お金を払って依頼している以上、弁護士への進捗状況の確認を躊躇する必要はありません。不安に感じたら遠慮なく問い合わせをおこないましょう。
弁護士に問い合わせたものの回答を得られない場合や何度言っても状況の改善がみられない場合には、弁護会に相談してみるのも1つの手段です。
全ての弁護士は日本弁護士連合会(弁護士会)に所属しています。
弁護士会には市民窓口が設置されており、弁護士の対応に関する相談や苦情などを伝えることができます。弁護士の活動に納得できない部分があるのであれば、まずは市民窓口で対応が遅いことを相談してみましょう。
場合によっては、弁護士会が間に入って解決の道を探る紛議調停や弁護士の懲戒請求などの手続きを取れる場合もあります。
参照:弁護士とトラブルになったら|日本弁護士連合会
依頼している弁護士と信頼関係を築けないようであれば、交通事故に精通している他の弁護士に変更することも検討しましょう。
弁護士を変更する場合、まずは次の依頼する弁護士を探しましょう。弁護士を選ぶ際は、交通事故に強くコミュニケーションを密にとってくれる弁護士に依頼することが重要です。
弁護士ポータルサイトを利用すれば効率良く弁護士を探せますが、弁護士選びに迷ったら交通事故に強く着手金も無料で対応してくれる”ベンチャーサポート法律事務所”に依頼するのがおすすめです。
依頼する弁護士事務所を決めたら、現在依頼している弁護士事務所に変更する旨を伝え事件の引き継ぎをしてもらいます。引き継ぎは弁護士間でおこなってくれるので、依頼者側で対応することは基本的にありません。
1度依頼した弁護士を変えるのは勇気のいることかもしれませんが、信頼の置けない弁護士に依頼し続けるのは非常にリスキーです。
弁護士を変更するだけで手続きがスムーズに進む場合もあるので、まずは弁護士を変更すべきかどうかについても別の弁護士に相談してみることをおすすめします。
弁護士の対応が遅いと依頼者としては不安が募ります。
不安を抱えたまま不満へと変化する前に、出来る限りの対応をしましょう。
コミュニケーションを取るのがあまり得意な弁護士ではないけれど、よりよい結果を得ることの出来る優秀な弁護士もいます。
そのような場合は、大抵の場合は担当秘書や担当パラリーガルが被害者サイドとのコミュニケーションを図っていることが多いでしょう。
弁護士が業務に集中することができますので、1つの事件を解決していくうえでは役割分担をしているので効率的であるともいえます。
もし弁護士を入れているのに示談の進みが遅いなと感じたら、交通事故に精通している弁護士への依頼を検討してみることをおすすめします。

