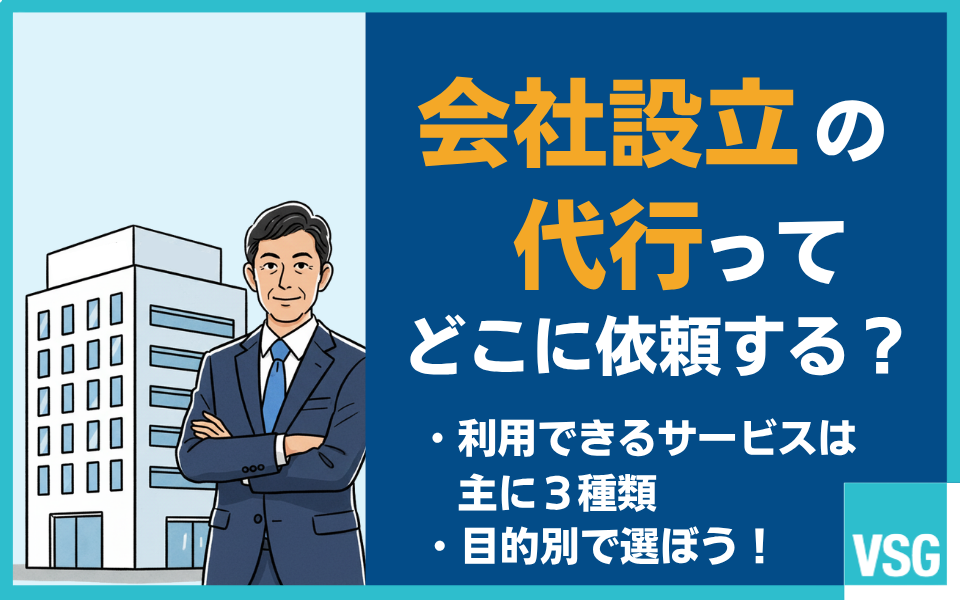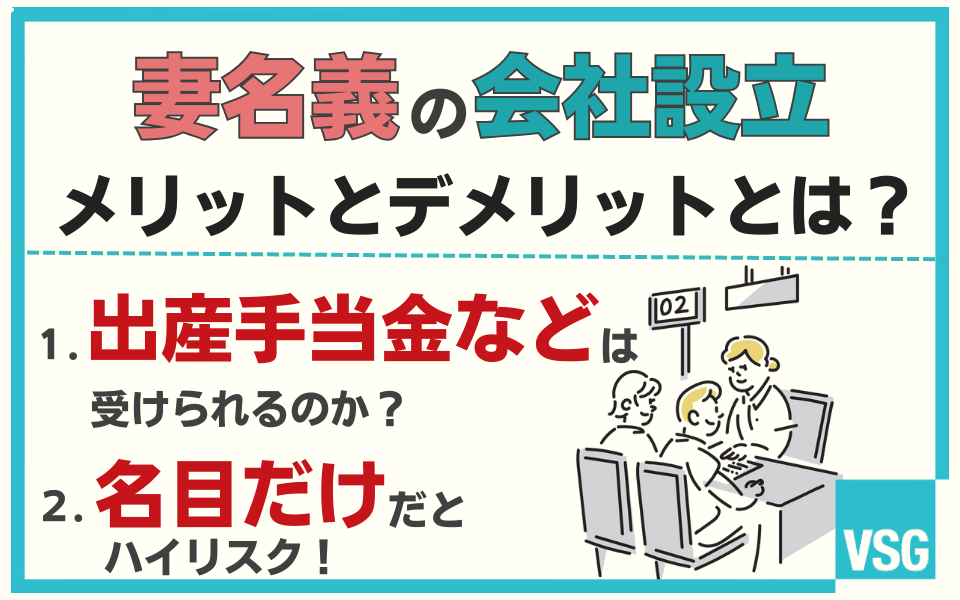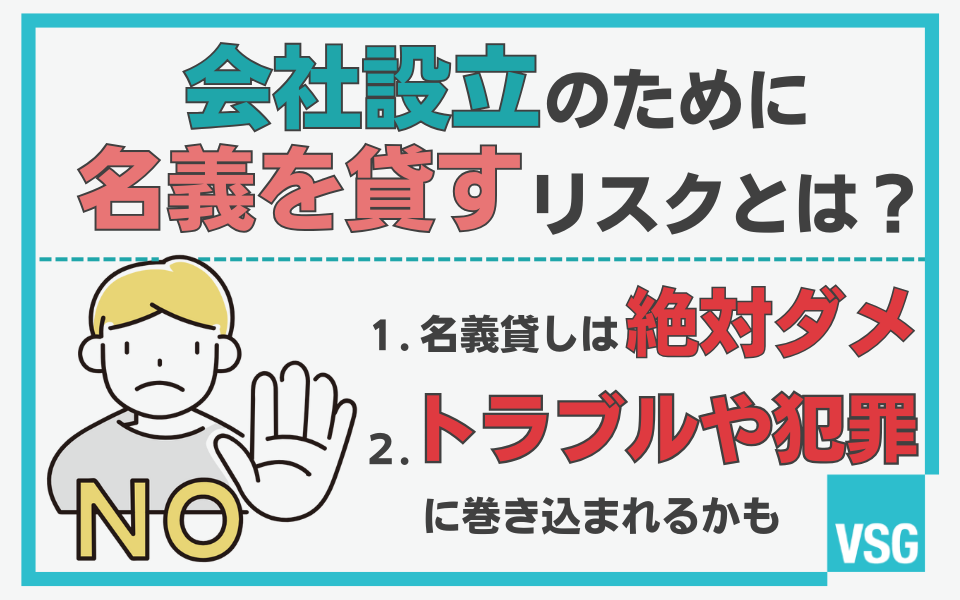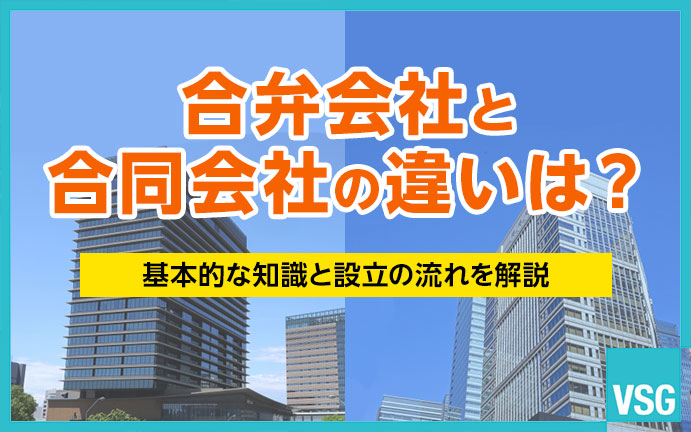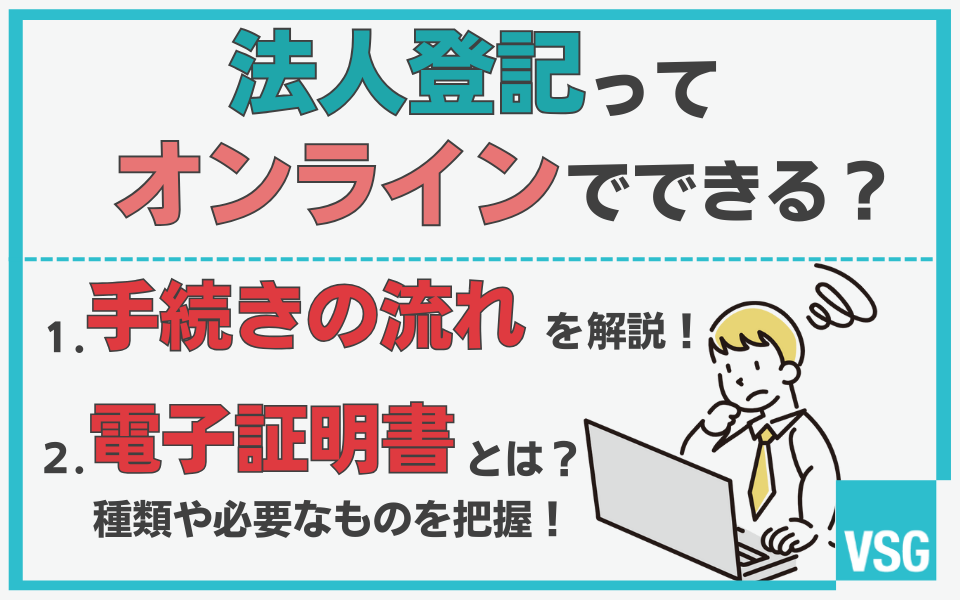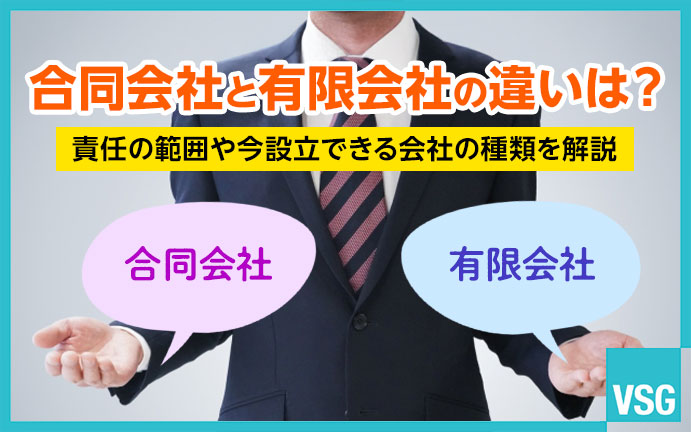最終更新日:2025/12/4
定款認証とは?定款認証の流れや方法を徹底解説します!

ベンチャーサポート税理士法人 大阪オフィス代表税理士。
近畿税理士会 北支部所属(登録番号:121535)
1977年生まれ、奈良県奈良市出身。
起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネルを運営。
PROFILE:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_writing/#p-mori
YouTube:会社設立サポートチャンネル【税理士 森健太郎】
書籍:プロが教える! 失敗しない起業・会社設立のすべて (COSMIC MOOK) ムック
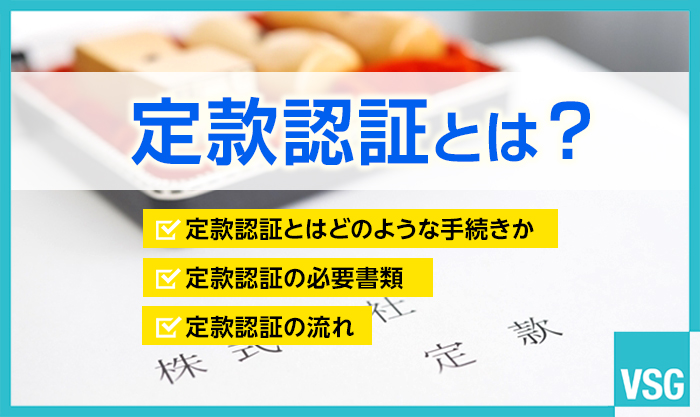
この記事でわかること
- 定款認証とはどのような手続きか
- 定款認証の必要書類
- 定款認証の流れ
会社設立の際に欠かせない手続きが「定款認証(ていかんにんしょう)」です。定款には電子定款と紙定款の2種類があり、どちらでも好きな方を選ぶことができます。
最近では、電子定款を選択する方も増えています。その要因のひとつとして、印紙代4万円を節約できるというメリットがあります。
電子・紙のどちらでも定款のルールは同じですが、いずれの形式を選んでも、定款認証は専門用語も多くハードルが高く感じられるかもしれません。
この記事では、定款認証の必要書類や手続きの流れ、注意点などをわかりやすく解説します。


目次
定款認証は「定款」を認めてもらう手続き
定款認証という言葉はあまり聞き慣れないかもしれません。また、聞いたことはあっても具体的にどのようなものなのかイメージできないという方も多いでしょう。
定款認証とは、会社の基本ルールである定款の内容をチェックしてもらって、公的な「お墨付き」をもらう手続きのことです。
まずは、定款がどんなものでどんな役割があるのかを解説します。その後、定款認証とは何のために行うのか、どのような手続きなのかを見ていきましょう。
定款は会社の基本ルール
定款には、会社の商号や目的、本店所在地、資本金の額などの会社の基本情報が記載されます。
定款はよく「会社のルールブック」と表現されることもありますが、これは会社が定款の内容に従って活動を行うためです。
会社には必ず定款がある
会社を設立する際には、必ず定款を作成する必要があります。
定款がなければ会社の存在そのものが認められないため、定款がない会社は存在しません。設立時に作成する最初の定款は「原始定款」と呼ばれ、会社設立の第一歩は定款作成から始まるともいえます。
そして株式会社の場合は、公証人による定款認証も必要です。合同会社の場合、定款認証は不要ですが、定款の作成は必須になります。
定款は全ての会社にとって極めて重要な書類なのです。
定款の種類
定款には保存方法が異なる2つの種類があります。電子定款と紙定款です。
電子定款とは、パソコンで定款を作成して電子データの状態で保管したものです。定款認証のときの印紙代が不要ということもあり、電子定款で認証する割合は約90%を占めます。
続いて、紙定款は、紙に印刷して保管する定款です。紙定款の場合は、定款認証の際に印紙代4万円が必要になります。
どちらを選んでも、定款の基本的なルールや効力に違いはありません。ただし費用面や利便性を考えると、電子定款の方がメリットがあります。
参考:定款認証に関する実態調査 調査結果(詳細)PDF|法務省民事局
定款認証では何をするのか
定款認証は、会社の定款を作成したあとに公証役場で行う手続きです。
作成した定款をそのまま法務局に提出するのではなく、法律上問題がないかなどを公証人にチェックしてもらってお墨付きをもらいます。
公証人に定款認証をしてもらう
定款は会社の土台となるものであるため、公証人にチェックしてもらいます。これが定款認証です。
公証人は定款の内容を確認して、違法性や内容に不備がないかをチェックします。これにより、定款が適法で内容にも問題がないという証明をしてもらうのです。
合同会社の場合は定款認証は不要
株式会社とは異なり、合同会社の場合は定款認証の手続きが不要です。
ただし、定款の作成は必ず行わなければなりません。作成は義務で認証は省略できるため、株式会社に比べてコストや手間を抑えて設立できるのが合同会社の特徴です。
公証人とは?
公証人とは、法務大臣に任命された専門家です。
公証人は、元裁判官や元弁護士といった法律の専門家が多く、定款の内容を確認し、法的な問題がないかをチェックします。公証人に認証してもらうことで、定款が法的に、そして社会的に信頼できる文書であると証明できるのです。
定款認証が必要なのは一部の株式会社や社団法人
定款認証は、全ての会社に義務付けられているわけではありません。株式会社や一部の社団法人では必須ですが、合同会社や合資会社、合名会社では定款認証は不要です。
どの会社形態を選ぶかで会社設立時に必要な手続きが変わるため、注意が必要です。
48時間以内に定款認証ができる制度がある
令和6年9月20日から、一定の条件を満たした場合に「48時間以内に定款認証手続きを完了させる」という制度が運用されています。
条件はありますが、この方法を利用すると最速3日で会社の設立手続きが完了することになります。スピーディーに手続きをしたいという場合は利用を検討しましょう。
参考:スタートアップ支援のための定款認証に関する新たな取組について|法務局
定款認証が必要な理由
定款認証は、株式会社や一般社団法人、一般財団法人を設立する際に必須の手続きです。
定款認証を受けることで、作成した定款が公的に有効なものと認められ、会社が「法人」として活動できるようになります。定款認証は会社設立において非常に重要なステップなのです。
トラブル防止
定款認証を行う大きな目的のひとつは、トラブルを防止することです。
専門家である公証人が定款の内容を確認し、あいまいな表現や不適切な規定が含まれていないかをチェックします。これにより第三者とのトラブルのリスクを減らすことができます。
定款の内容が合法的だという証明
もうひとつの重要な役割は、定款の内容が法律に違反していないことの証明です。
定款の作成には、会社法で定められたルールがあります。作成された定款が、ルールに沿っているかを確認するためには専門知識が必要です。
公証人に認証してもらうことで、会社のルールが適法であるという証明をしてもらうのです。
定款認証の流れと必要書類
定款認証を受けるためには、必要書類を準備し、定められた流れに沿って手続きを行う必要があります。
電子定款と紙定款では必要書類と費用が異なるため、それぞれの違いを理解しておきましょう。
定款認証の必要書類
定款認証で提出する書類は、電子定款と紙定款で異なります。どちらを選ぶかによって準備する書類が変わるため、注意してください。
電子定款の必要書類
電子定款で定款認証を受ける場合は、次の書類が必要です。
| 印鑑証明書 | 個人の場合:発起人の印鑑証明書
海外在住の個人が発起人:公的機関で発行されたサイン証明書か印鑑証明書。海外在住で印鑑登録制度がない国の場合は、サイン証明書と在留証明書が必要。サイン証明書や印鑑証明書の記載が日本語でない場合は、その日本語訳の用意も必要 発起人が日本の法人:法人の印鑑証明書 |
|---|---|
| 実質的支配者となるべき者の申告書 | 個人・法人を問わず必要。設立する会社の実質的支配者が法人の場合、その出資法人の実質的支配者(筆頭株主)の本人確認書類が必要 |
| 実質的支配者となるべき者の本人確認書類 | 履歴事項全部証明書(登記簿謄本)・株主名簿(法人印での押印)。発起人が法人の場合に必要 |
| 委任状 | 代理人が認証手続きを行う場合に必要 |
| 代理人の本人確認書類 | 代理人が認証を申請する場合に必要 |
| 発起人の身分証明書 | 身分証は原本ではなく写し(コピー)でも可 |
紙定款の必要書類
紙定款で認証を受ける場合には、以下の書類を用意します。
| 定款 | 3部 |
|---|---|
| 印鑑証明と実印 | 発起人全員分が必要 |
| 登記事項証明書 | 発起人が法人の場合、代表者事項証明書・現在事項全部証明書・履歴事項全部証明書のいずれか |
| 実質的支配者となるべき者の申告書 | 個人・法人を問わず必要。設立する会社の実質的支配者が法人の場合、その出資法人の実質的支配者(筆頭株主)の本人確認書類が必要 |
| 実質的支配者となるべき者の本人確認書類 | 個人・法人を問わず必要。マイナンバーカードなど |
| 委任状 | 代理人が認証手続きを行う場合に必要 |
書類に不備があったり、必要書類がそろっていないと定款認証を受けられないため、必ず全ての必要書類をそろえてください。
定款作成から認証までの流れ
公証役場での定款認証の流れも、電子定款と紙定款で異なります。
面談では公証人から質問されるため、正確に答えられるようにしておいてください。
電子定款の定款認証
電子定款の定款認証の流れを確認しましょう。なお、電子定款の認証については以下の記事でも画像付きで詳しく解説しているので参考にしてください。
電子定款の定款認証の流れ
- STEP1公証役場に連絡して詳細を確認・予約
Webで近くの公証役場を探し、電話またはWebフォームから定款認証の事前チェックを依頼する。事前の連絡が必須 - STEP2定款案の送付
あらかじめ作成しておいた電子定款をメールで送付する - STEP3申請用総合ソフトのインストール
公証役場の事前チェックを通過したら、電子認証に進む。電子認証には法務省の「登記・供託オンライン申請システム」を使用する。このシステムを使うため「申請用総合ソフト」のインストールも必要。どちらも無料で利用可能 - STEP4電子認証の申請
「登記・供託オンライン申請システム」で定款の電子認証を申請する - STEP5公証人と面談して認証手続きを行う
- STEP6料金の支払い・定款の原本の受け取り
定款の原本の受け取りは、公証役場に行く方法のほか、ウェブ会議による面談と郵送でも可能です。ただし、電子定款でも直接受け取りに行く人の方が多く、ウェブ会議の利用率は約10%となっています。
紙定款の定款認証
続いて紙定款の認証の流れを解説します。まずは予約をしてください。突然、公証役場に行くのではなく、 事前に公証役場に電話やメールで予約を取りましょう。
紙定款の認証の流れ
- STEP1公証役場の予約
- STEP2受付
公証役場に行ったら受付で必要書類を渡す。多くの公証役場では、入口の近くにカウンターがあり、そこで受付や案内をしてもらえる。書類はカウンターで渡すケースが多いため事前に準備しておく - STEP3公証人と面談
面談では、公証人から、会社名、目的、資本金、取締役など、重要な事項について質問される。絶対的記載事項については、法律に関する質問をされることもある - STEP4認証手続き
公証人が定款の内容に問題がないことを確認し、認証手続きを行う - STEP5手数料の支払い
認証手数料を支払う - STEP6定款の受け取り
認証済みの定款を受け取る
定款認証の費用
定款認証には費用がかかります。この費用に関しては自分で手続きした場合でも必要です。資本金の額に応じた定款認証手数料、そして紙定款を選択した場合は印紙代がかかります。
| 定款認証手数料 | 資本金の額等が100万円未満 | 1万5,000円(発起人が3人以下、法人出資でない、設立時株主が発起人のみ、取締役会がない会社の場合) 上記以外の場合は3万円 |
|---|---|---|
| 資本金の額等が100万円以上300万円未満の場合 | 4万円 | |
| その他の場合 | 5万円 | |
| 収入印紙代 | 4万円(紙定款の場合) | |
※電子定款の場合、データ保存手数料300円や提供手数料1通700円(書面交付では1枚あたり20円加算)を支払います。
定款認証の手数料は2024年12月1日から最低金額が引き下げられました。改訂後は、最も安い場合だと1万5,000円です。
定款認証を自分でするときの注意点
定款認証は自分で手続きすることができます。必ず専門家に依頼しなければならないものではなく、発起人が自ら定款認証を行うケースもあります。
ただし、自分で手続きする場合にはいくつか注意点があるので、ここで確認しておきましょう。
公証役場は予約が必要
定款認証は公証役場で行いますが、公証役場での手続きには予約が必須です。
先に電話などで予約をして、必要な物を持って公証役場に出向くことになります。


電子定款の場合はPCが必要
定款認証を受ける人の約9割が利用している電子定款ですが、定款の作成・認証にはPCとネット環境が必要です。
電子定款を作って公証役場に送付するという一連の作業をするための最低限のPCスキルが必要になります。
パソコンを持っていない場合やパソコンを使えない場合は、電子定款ではなく紙定款を利用することになります。
公証役場には管轄がある
定款認証ができるのは「法人の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局に所属する公証人」に限られています。
公証人法 第五十七条
第五十七条 会社法第三十条第一項(他の法令において準用する場合を含む。)並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第十三条及び第百五十五条の規定による定款の認証の事務は、法人の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局に所属する公証人が取り扱う。
引用元 e-Gov 法令検索
どこの公証役場を利用してもよいわけではないため、事前に管轄の公証役場や予約方法を確認しましょう。
定款認証の相談
定款認証は、資格を持つ専門家に作成から認証手続きまで依頼することができます。
定款認証はあくまで会社設立の手順の一段階に過ぎません。
専門家に依頼すれば、費用はかかりますが手続きは確実です。一方、自分で行う場合は、コストを抑えられますが手間がかかります。手続きの確実さと費用の安さのどちらを重視するかが1つのポイントです。
行政書士
定款認証の作成や手続きは、行政書士に依頼できます。
行政書士は定款認証だけでなく、会社設立に関連する議事録や契約書、申請書類などの作成サポートも可能です。費用を抑えつつ書類の不備による手続きの停滞を避けたい人に適しています。
ただし、行政書士は登記申請を代理することはできません。
司法書士
司法書士に依頼すると、定款認証だけでなく会社設立に必要な登記手続きを一括で任せることができます。
法務局への登記申請や資本金の払込証明の確認、会社実印の届出までトータルでサポートしてもらえるのが大きな特徴です。
司法書士は登記の専門家なので、定款作成から登記完了までスムーズに進めることができ、時間を大幅に短縮できます。「法務局とのやり取りも含めて丸ごと専門家に代行してほしい」という人には最適です。
定款認証は定款にお墨付きをもらう手続き!不安なら専門家に相談しましょう
定款認証は、株式会社や一般社団法人などを設立する際に欠かせない手続きです。
会社のルールブックである定款を公証人に確認してもらい、公的なお墨付きを受けなければ、会社の設立登記はできません。
定款には「電子定款」と「紙定款」という2つの形態があります。どちらを選んでも効力や法的な意味合いは同じです。現在では電子定款を選ぶケースが多数を占めており、電子定款の場合、印紙代が不要となるため費用面で有利です。
定款の作成や認証は自分で行うことも可能ですが、専門的な知識と入念な事前準備が必要です。行政書士などの専門家に依頼すれば、定款の作成から認証までの負担を大幅に減らすことができます。
これから会社設立をする方は、定款認証の必要性や流れを理解したうえで、効率的かつ確実に手続きを進めることが大切です。