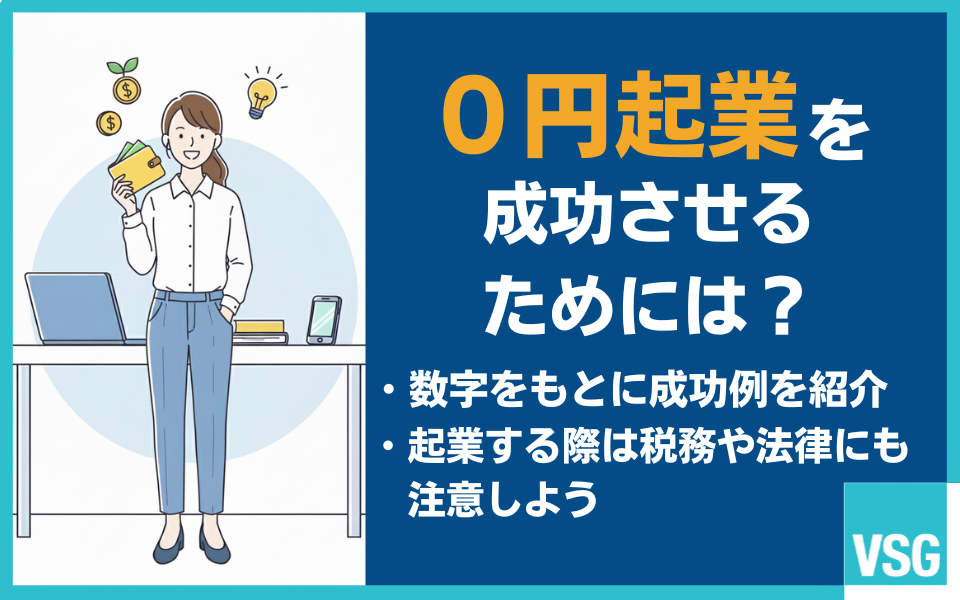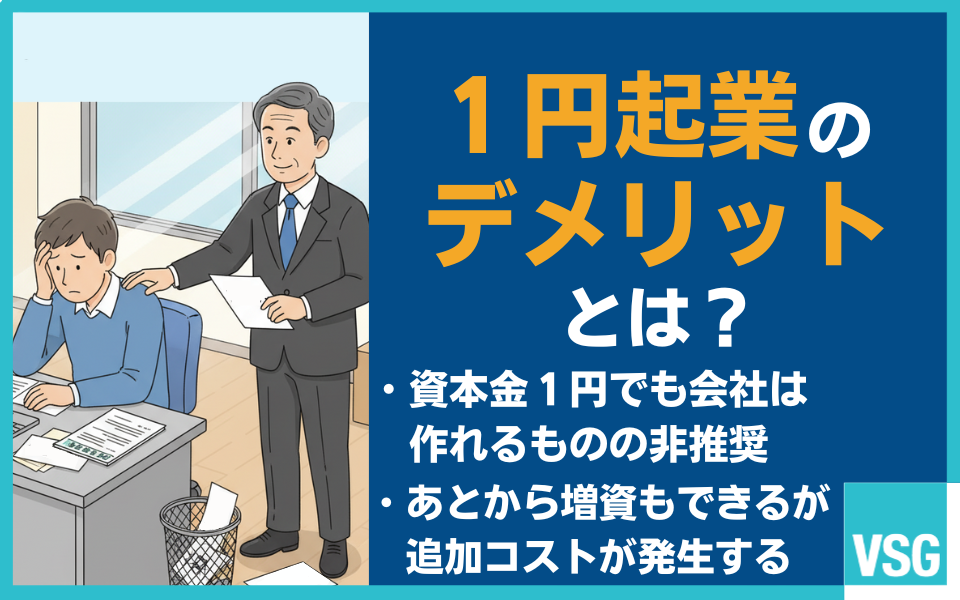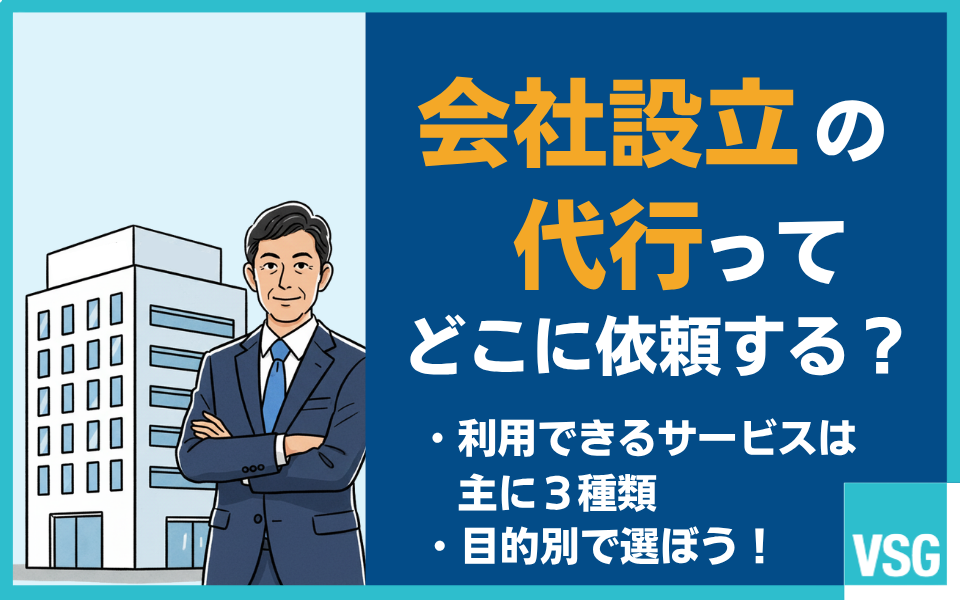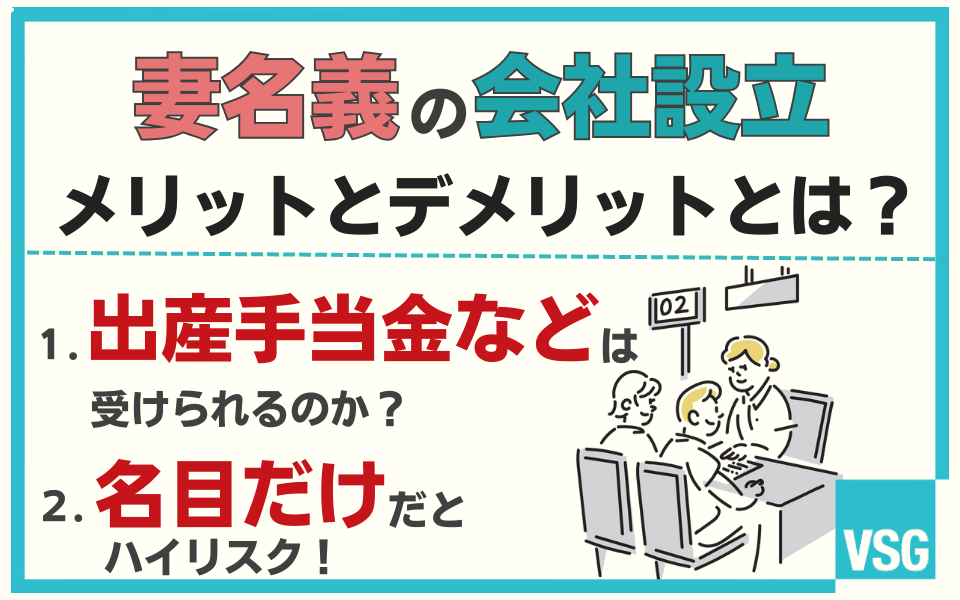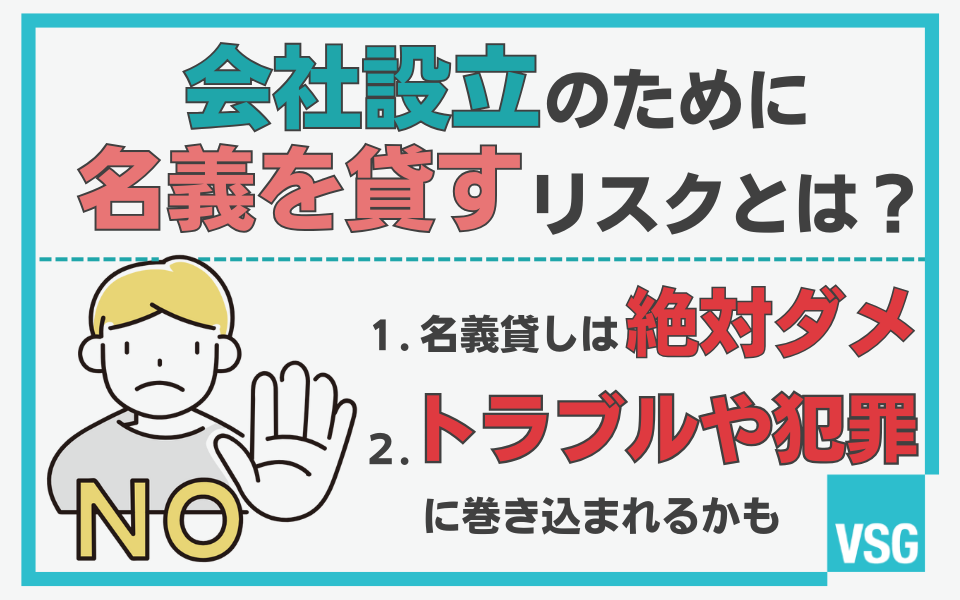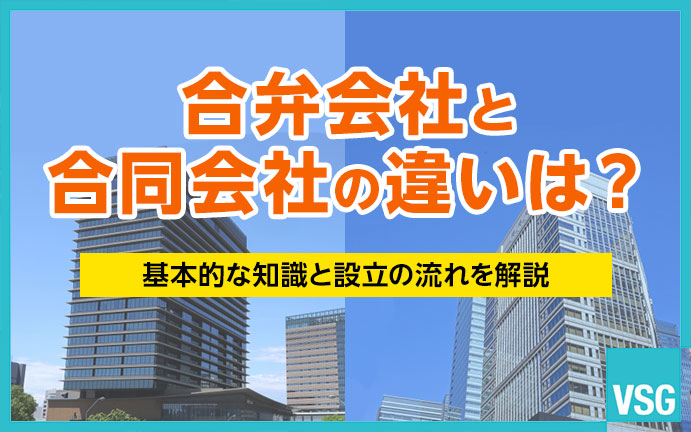最終更新日:2025/7/8
オーナーと社長の違いは?給料・偉さの違いや雇われ社長のトラブルなど網羅解説

ベンチャーサポート税理士法人 大阪オフィス代表税理士。
近畿税理士会 北支部所属(登録番号:121535)
1977年生まれ、奈良県奈良市出身。
起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネルを運営。
PROFILE:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_writing/#p-mori
YouTube:会社設立サポートチャンネル【税理士 森健太郎】
書籍:プロが教える! 失敗しない起業・会社設立のすべて (COSMIC MOOK) ムック

この記事でわかること
- オーナーと社長の違い
- オーナー社長と雇われ社長の違い
- オーナー社長と雇われ社長のメリット・デメリット
- 雇われ社長にありがちな勘違い
- 雇われ社長を辞めたくなる辛いトラブル
オーナーと社長の違いは、一般的に所有者か経営者か、あるいは株式を保有しているかしていないかで説明されます。
しかし、厳密にはオーナーが会社を所有しているわけではありません。また、オーナーと社長の権限・責任の範囲、立場などを正しく理解しておかなければ、恥をかいたり、想定外の事態が生じて困ったりする可能性があります。
この記事では、オーナーと社長の違いを給料(受益形態)や序列(偉さ)、責任の範囲など多様な観点から詳しく解説します。両者の関係性や、オーナー社長と雇われ社長の違いなども解説しています。
オーナーが誰を社長にするか決める際はもちろん、社長が自身の置かれている状況を把握し、適切に行動する際にも役立つはずです。オーナーや社長は何をやっているのか、どちらが偉いのかといった一般的な疑問も解決できるので、ぜひ最後までご覧ください。
近年、ガバナンス強化や事業承継問題への対応などの流れを受け、会社の所有と経営のあり方は実に多様なものとなっています。この記事で解説する内容は一般的なものであり、必ずしもすべての会社に当てはまるわけではない点には注意してください。


目次
オーナーとは?
本来、オーナー(Owner)は英語で「持ち主」や「所有者」の意味がある単語です。
ビジネスにおいては、特に株式会社のオーナーというと、通常は株主を指します。
一般的には、株主のなかで最も持株比率の高い株主、すなわち筆頭株主を指して使われる場合が多いでしょう。
使われ方から見れば、株式会社のオーナーとは、会社の意思決定に大きな影響力を持つ人(場合によっては法人)だといえます。
中小企業では、創業者のほか、その配偶者や子などの親族がオーナーに該当する場合が多いです。
ちなみに、コンビニなどフランチャイズ(FC)システムにおいては、店舗の経営者をオーナーと呼ぶ場合があります。店長がオーナーである場合も少なくありません。
オーナーは会社法などの法律で定義されていない一般的な言葉であり、文脈によって細かな意味合いは異なる可能性があります。
また、厳密には筆頭株主であっても株式会社を所有しているわけではありません。会社には、法律上、独立した人格(法人格)があります。人間が人間を所有するといった概念はないのと同様、会社も独立した存在であり、所有されることはありません。
オーナーは主に筆頭株主を指す言葉として使われますが、厳密な定義はなく文脈によって内容が異なる場合もある点、そして厳密にはオーナーが会社を所有しているわけではなく、いわば比喩的な表現である点は把握しておくべきでしょう。
社長とは?
社長とは、一般的にはその会社の最高責任者(トップ)や代表取締役を指す、会社が任意かつ独自に定めた役職(肩書き)です。
前述の「オーナー」と同様、会社法などの法律で定義されていない一般的な言葉です。
したがって、現実には代表取締役でない社長、代表権のない社長なども存在します。また、会社のトップは実質的に会長で、社長はナンバー2といったケースも少なくありません。
オーナーと社長の違い
オーナーと社長の違いは、下表のとおりです。
| 比較項目 | オーナー | 社長 |
|---|---|---|
| 一般的な地位 | 持株比率の高い株主 (筆頭株主など) |
会社の最高責任者 (代表取締役など) |
| 序列 | 一般的には社長より上 | 一般的にはオーナーより下 |
| 決議事項 | 会社の根幹に関わる重要事項 (取締役会非設置会社ではすべての事項) |
具体的な業務にかかる事項 |
| 責任範囲 | 保有株式の引受価額まで (極めて限定的) |
任務懈怠による実損害 (広範囲) |
| 受益形態 | 配当益、譲渡益 | 委任の報酬 |
ここからは、オーナーと社長の受益形態(給料・年収)や序列(偉さ)、責任範囲の違いについて、より詳しく解説します。
給料・年収
オーナーと社長は、どのように経済的な利益を享受するかという受益形態が異なります。
具体的には、オーナーは会社の活動から生じた利益を配当金などの形で受け取るか、保有する株式を譲渡することで経済的な利益を享受します。一方、社長の経済的利益は、株式会社から受け取る報酬です。
両者が享受する経済的利益の一般的な性質を、下表にまとめました。
| 比較項目 | オーナー | 社長 |
|---|---|---|
| 利益の種類 | 配当益、譲渡益 | 委任の報酬 |
| 利益の性質 | 出資の対価(リターン) | 委任された職務執行の対価 |
| 所得税法上の所得区分 (中小企業を想定したケース) |
配当益:配当所得(総合課税) 譲渡益:一般株式等に係る譲渡所得(申告分離課税) |
給与所得 |
| 税率 | 配当所得:所得税は5~45%の超過累進税率、住民税所得割は10%の比例税率 譲渡所得:所得税は15%、住民税所得割は5%の比例税率 |
所得税は5~45%の超過累進税率、住民税所得割は10%の比例税率 |
| 安定性・変動性 (リスク) |
変動し、安定しにくい | 比較的安定している |
上表の内容、特に所得税法上の所得区分は中小企業における一般的なケースを想定したものであり、具体的な状況によって異なる可能性があります。
オーナーと社長のどちらが経済的利益が大きいかは、一概には言えません。
なお、オーナーと社長の両方の立場を兼ねるオーナー社長の場合、配当金と報酬のどちらも受け取ることが可能です。ただし、社長(役員)への配当金は損金にならない点、法人税と個人所得税・住民税の二重課税となる点などの注意点があります。
社長の給料は売り上げの何パーセントにすべきかなど、社長の給料の決め方を含む役員報酬についてお困りの方は、税理士への相談をおすすめします。
序列の上下関係(偉さ)
オーナーと社長はどっちが上(偉い)かは、明確には定められていません。ただし、一般的にはオーナーのほうが上(偉い)と認識されています。
社長よりオーナーのほうが上(偉い)と認識される理由は、会社法上、社長(一般に取締役)はオーナー(株主)から選ばれ、報酬も株主総会で決議され、ときには解任されることもあるためだといえます。
つまり、社長は報酬を含む人事をオーナーに握られていることが、オーナーのほうが偉いと認識されている理由です。
ただし、株式を1株または100株保有しているだけでは、その会社の社長よりも上(偉い)とは認識されません。そもそも、社長の人事に関する事項を決めるのは株主ではなく株主総会であるためです。
株主総会で行使できる議決権の保有割合が低い場合、社長人事への影響力は極めて限定的です。したがって、そのオーナーと社長との間では、オーナーのほうが偉いとはいえません。
社長よりオーナーのほうが上(偉い)といった認識は、オーナーが筆頭株主であるケースを前提としているといえます。
責任範囲
オーナーと社長は、会社の活動に関して負う責任の範囲が大きく異なります。
前提として、オーナーと社長は、どちらも会社の債務について直接責任を負うことはありません。原則、会社が支払うべき給与・賃金債務や金融機関から借りた資金の返済債務、取引先に対する仕入債務などについて、オーナーや社長が身銭を切ってまで支払う必要はないということです。
しかし、実際に会社の活動に関して負う責任の範囲は、オーナーは極めて限定的である一方、社長は広範囲といえます。
まずオーナーの責任範囲は、会社法104条が定めるとおり、自ら保有する株式の引受価額までです。責任の限度が法定されており、株主の責任は有限責任と表現されます。
- (株主の責任)
第百四条 株主の責任は、その有する株式の引受価額を限度とする。 - 引用:会社法 第百四条|e-Gov 法令検索
一方、社長(取締役)は、任務を怠って損害が生じた場合には、損害賠償責任を負わなければなりません。株主のように限度が定められておらず、実際に生じた損害について責任を負います。
- (役員等の株式会社に対する損害賠償責任)
第四百二十三条 取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人(以下この章において「役員等」という。)は、その任務を怠ったときは、株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 - 引用:会社法 第四百二十三条 第一項|e-Gov 法令検索
ただし、株式会社ではなく第三者に対する損害賠償責任は「悪意又は重大な過失があったとき」に限定されます。
- (役員等の第三者に対する損害賠償責任)
第四百二十九条 役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。 - 引用:会社法 第四百二十九条 第一項|e-Gov 法令検索
例えば、社長(取締役)が法令や定款、株主総会の決議を遵守しないことは、会社法355条が定める忠実義務違反です。この忠実義務違反によって株式会社に損害を生じさせたときは、任務を怠ったとして、損害賠償責任を追及される可能性があります。
また、社長(代表取締役)が自社の経営資源では対応できないことを知っていながら、対応できる旨を示して大規模なプロジェクトを受注したとします。このような行為は職務を行うについて悪意又は重大な過失があるといえる余地があり、その取引先に生じた損害を社長(代表取締役)個人が賠償しなければならない可能性もないわけではありません。
上記のとおり、オーナー(株主)の責任は株式について出資する範囲に限定されます。一方で、社長は自らの任務や職務を十分に把握し、誠実・忠実に、かつ相当の注意を払って職務を執行しなければ、実際に生じた損害について賠償責任を負う可能性があります。
オーナーと社長の関係
オーナー(株主)と社長(取締役)との関係は、一般的には株式会社の実質的な所有者であるオーナーが、社長(取締役)に経営を委任するものとされています。つまり、オーナーは株式会社を所有し、社長は株式会社を経営するといった関係です。
会社法は、上記のように、会社の所有と経営の分離を原則としています。もっとも、必ずしも株式会社の所有と経営が一致しているわけではありません。
一般的には、所有(株主)と経営(取締役)との関係は、以下の2つに大別されます。
- オーナー社長(オーナー経営)
- 雇われ社長(サラリーマン経営または専門家経営)
オーナー社長
オーナー社長とは、オーナーでもある社長です。例えば、その株式会社の筆頭株主であり、自らを社長(代表取締役)とした人をいいます。いわゆる1人社長は、通常、オーナー社長です。
より細かく見ると、オーナー社長は次のように分けられます。
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| 創業者オーナー社長 | 株式会社を設立し、自らを代表取締役とした社長 |
| 創業家オーナー社長 | 創業者の親族である社長 |
| 承継オーナー社長 | 創業者から事業と株式を引き継いだ社長 |
オーナー社長がいるオーナー経営では、株式会社を実質的に所有しながら自ら経営をするため、所有と経営は一致しています。
雇われ社長
雇われ社長とは、オーナーから経営を委任された、オーナーとは別人格の社長です。一般的に創業者の親族や承継者は含まず、次のような社長を指します。
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| 内部昇格社長 (サラリーマン社長) |
社内での実績が認められ、従業員から昇進した社長 |
| 外部招聘社長 (プロ社長) (専門家社長) |
経営経験や専門分野の知見・実績が豊富な、外部から招聘されたプロ社長 |
雇われ社長がいるサラリーマン経営(専門家経営)の場合、所有と経営は分離しています。
ただし実際には、内部昇格社長や外部招聘社長が、株式の一部やストック・オプションを保有しているケースもゼロではありません。このような場合には、所有と経営が完全に分離しているわけではなく、接近しているなどと表現されます。
オーナー社長と雇われ社長の違い
オーナー社長と雇われ社長の最も直接的な違いは、その株式会社の株式の保有状況です。オーナー社長は多くの株式を保有する一方、雇われ社長は全く保有していないか、保有していても少数です。
株式の保有状況が違えば、同じ社長であっても、できることの範囲が異なります。
ここでは、オーナー社長と雇われ社長について、何ができて何ができないのかといった観点でそれぞれの特徴を解説します。
オーナー社長の特徴
オーナー社長は多くの株式を保有しているため、その株式会社の根幹に関わる重要事項を、自らの意思のみで決めることができます。
株主総会の権限を定めた会社法295条の内容は、以下のとおりです。
- (株主総会の権限)
第二百九十五条 株主総会は、この法律に規定する事項及び株式会社の組織、運営、管理その他株式会社に関する一切の事項について決議をすることができる。
2 前項の規定にかかわらず、取締役会設置会社においては、株主総会は、この法律に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができる。
3 この法律の規定により株主総会の決議を必要とする事項について、取締役、執行役、取締役会その他の株主総会以外の機関が決定することができることを内容とする定款の定めは、その効力を有しない。 - 引用:会社法 第二百九十五条|e-Gov 法令検索
取締役会設置会社の場合、株主総会で決議できる事項は制限されますが、以下のような株式会社の根幹に関わる重要事項は、株主総会の決議事項です。
株主総会の決議は原則として出席した株主の議決権の過半数でなされるため、多くの株式(議決権)を保有するオーナー社長は、独断も可能です。
持株比率にもよりますが、とりわけ特別事項の決議要件である3分の2を超える議決権(株式)を保有するオーナー社長は、実質的に株式会社を単独で支配できる強い権限があるといえます。
雇われ社長の特徴
一方、雇われ社長は株式(議決権)を全く保有していないか保有していても少数であり、株式会社の根幹に関わる重要事項は決められません。
特に雇われ社長自身の取締役という地位や報酬は、株主総会の決議事項です。雇われ社長の地位は、いわばオーナーの支配下にあるといえます。
オーナー社長のメリット・デメリット
ここからは、オーナー社長のメリット・デメリットを紹介します。
オーナー社長がご自身の立場を把握したいときはもちろん、従業員や取引先、求職者などが会社の特徴を把握したいときなどにも参考にしてください。
オーナー社長のメリット
オーナー社長のメリットは、以下の3点です。
- 地位が安定している
- 迅速かつ大胆な意思決定ができる
- 大きなリターンも見込める
オーナー社長自身の利益につながるメリットがほとんどといえます。
地位が安定している
雇われ社長と比べたとき、オーナー社長の最も象徴的なメリットは、地位が安定していることです。
雇われ社長は株主総会の決議で解任されたり、任期を短縮されたりする可能性があります。一方、オーナー社長は自らが議決権を保有しているため、自身の地位を維持できます。
もちろん、議決権の源泉である株式を譲渡するかどうかも、決めるのは他人ではなく自分自身です。
立場を他人に左右される可能性がない点で、オーナー社長の立場は非常に安定しているといえるでしょう。
迅速かつ大胆な意思決定ができる
オーナー社長は、雇われ社長と比べて、より迅速かつ大胆な意思決定ができます。
前提として、株式会社に関する意思決定は、法律上、株主総会や取締役(会)の決議を経てなされるものです。
株主総会の議決権の大半を保有するオーナー社長であれば、反対する株主がいても、実質単独で株主総会を決議できる場合があります。
また、オーナー社長には取締役(会)を構成する取締役の解任や報酬を決める人事権があるため、事実上、取締役がオーナー社長の意向に反することは容易ではありません。仮にオーナー社長の意向に反する取締役がいた場合、オーナー社長はその取締役を解任したり、報酬を減額したりすることも不可能ではないためです。
オーナー社長は他の株主や取締役に対して大きな影響力があるため、経営環境の変化に対して迅速に、そして大胆に意思決定できる点がメリットです。
大きなリターンも見込める
オーナー社長と雇われ社長のどちらとも、株式会社から役員報酬を受け取れる点は共通しています。しかし、オーナー社長は、役員報酬に加えて株式の配当金(インカムゲイン)や譲渡益(キャピタルゲイン)も狙えます。
例えば、事業が成功し、会社の規模が拡大したときは、事業譲渡や株式譲渡で大きな利益を出すことも可能です。
このようなインセンティブの違いから、オーナー社長は、雇われ社長と比べて事業経営にかける情熱が大きいケースが多いといえるでしょう。
業績連動報酬やストック・オプションがない雇われ社長の場合、このようなインセンティブはありません。
オーナー社長のデメリット
一方で、オーナー社長のデメリットとして以下の2点があります。
- 事業承継が問題になりやすい
- ワンマン経営に陥りやすい
これらはオーナー社長の経営に対する、客観的な懸念点といえるでしょう。オーナー社長自身も、会社のために注意しておく必要があります。
事業承継が問題になりやすい
事業承継とは、経営権や株式などを後継者に引き継ぐことです。後継者の属性に応じて、以下のような種類があります。
| 種類 | 後継者の属性 |
|---|---|
| 親族内承継 | 配偶者や子、孫、甥などの親族 |
| 従業員承継 | 親族以外の従業員 |
| 社外承継 (M&A) |
創業者や他の会社 |
オーナー社長の場合、会社に対する思い入れが強い、引退への抵抗が大きいなどの理由で、事業承継がスムーズに進まないケースがあります。とりわけ社外承継(M&A)の場合が問題です。
その他、親族内承継を望んでいても、親族の年齢や経験、能力、意欲などの点で適任者を選ぶのが困難なケースも少なくありません。
ワンマン経営に陥りやすい
オーナー社長は、ワンマン経営に陥りやすい点に注意が必要です。
オーナー社長は他人に自身の人事を握られておらず、実質的に他の取締役からの監視を受けにくいこともあります。この点は立場の安定や迅速で大胆な意思決定といったポジティブな影響を及ぼす反面、他者の異なる意見が反映されにくく、独断的なワンマン経営に陥る可能性がある側面も併せ持っています。
客観的に合理的でない判断が放置されれば、会社の経営は傾いてしまうかもしれません。
雇われ社長のメリット・デメリット
続いて、雇われ社長のメリット・デメリットを紹介します。
雇われ社長がご自身の立場を把握したいときはもちろん、従業員や取引先、求職者などが会社の特徴を把握したいときなどにも参考にしてください。
雇われ社長のメリット
雇われ社長のメリットは、以下の2点です。
- スキルや経験が豊富な場合が多い
- 経営の合理性と透明性を確保しやすい
雇われ社長の利益に直結するものではなく、客観的な経営に関するものが多いといえます。
スキルや経験が豊富な場合が多い
雇われ社長は、株主総会の決議で選ばれた人であり、株式会社から委任された人でもあります。また、一般的には株式会社から報酬が支払われます。
こうした性質上、雇われ社長は経営のプロフェッショナルであり、豊富な経験や専門知識を備えている場合が多いといえるでしょう。
ただし、社長の選ばれ方は多様です。必ずしも雇われ社長が経営経験のあるプロフェッショナルとは限りません。
経営の合理性と透明性を確保しやすい
雇われ社長は、オーナー社長と比べて、客観的に合理性のある経営判断をしやすいといえます。その背景にあるものは以下のとおりです。
- 株主総会で説明責任を果たす必要がある(会社法314条)
- 任期短縮のおそれがある(会社法332条1項)
- 解任のおそれがある(会社法339条1項)
- 取締役会議事録等の謄写閲覧請求を受ける可能性がある(会社法371条2項)
- 会計帳簿の閲覧謄写請求を受ける可能性がある(会社法433条1項)
- 株主代表訴訟で責任を追及される可能性がある(会社法847条1項)
雇われ社長は株主総会での説明責任を果たす必要があるほか、取締役会議事録や会計帳簿などを見られる場合もあるため、経営判断の根拠や経営の透明性を確保しなければなりません。問題があれば、解任や責任追及のおそれもあります。
このような法的枠組みにより、雇われ社長は合理的な経営判断をしやすいといえるでしょう。
なお、オーナー社長であっても上記の法律は適用されます。しかし、取締役や株主が同一人物である限り、説明責任や閲覧謄写請求、任期短縮、解任、責任追及の実効性はありません。
雇われ社長のデメリット
雇われ社長のデメリットとして、以下の3点が挙げられます。
- 結果次第で解任のおそれがある
- 意思決定権に限界がある
- 短期的視点に陥りやすい
なお、雇われ社長であっても、株主が多数で議決権の保有割合が分散している場合などは、紹介するデメリットが当てはまらないことがあります。
結果次第で解任のおそれがある
オーナー社長と比べたとき、雇われ社長の最も象徴的なデメリットは、結果次第で解任のおそれがあることです。
解任は株式総会の決議事項であり、株なしの雇われ社長は、他人から解任される可能性があります。株主からクビを切られることもあるということです。
自身の立場を他人(オーナー)に左右される可能性がある点で、雇われ社長の立場は不安定なものです。同時に、結果を出すことへのプレッシャーが大きいといえるでしょう。
意思決定権に限界がある
オーナー社長と比べ、雇われ社長の意思決定権には限界があります。
3人以上の取締役で構成される取締役会において、雇われ社長は大きくとも3分の1の議決権しかなく、単独では過半数に及びません。他の取締役の賛同が必要です。
また、雇われ社長(取締役)がオーナー(株主)に解任される可能性もゼロではありません。オーナーの意向を完全に無視することは、現実的には困難といえるでしょう。
上記のとおり、他の取締役の協力が必要でオーナー(株主)の意向の影響も受けやすい点で、雇われ社長の意思決定権には限界があるといえます。
短期的視点に陥りやすい
オーナー社長と比べ、雇われ社長は短期的視点に陥りやすいといえます。雇われ社長は、原則2年という比較的短期の任期で実現した成果をオーナー(株主)に評価されるからです。
例えば、長期的な成長につながる大規模な設備や研究開発への投資は、短期的には業績を悪化させるかもしれません。
したがって、雇われ社長はこのようなプロジェクトに対して慎重になり、最終的には会社の長期的な成長機会が奪われるおそれがあります。
雇われ社長にありがちな勘違い
雇われ社長にありがちな勘違いは、以下のとおりです。
- 「経営権がある」という勘違い
- 「代表権がある」という勘違い
- 「雇われている」という勘違い
- 「社長であり続けられる」という勘違い
ここでは、上記の雇われ社長にありがちな勘違いについて、それぞれ詳しく解説します。
「経営権がある」という勘違い
雇われ社長は、「社長だから経営権がある」と勘違いしてしまうことがあります。しかし実際には、社長という肩書きがあるからといって、必ずしも経営権があるとは限りません。
そもそも経営権は法律で定義されているものではありませんが、一般的には、会社の経営方針や戦略を決定する権利のように認識されています。
しかし、例えば重要な財産の処分や多額の借財などは、取締役(会)で決める事項です。社長が単独で決められるとは限りません。
また、それほど一般的ではありませんが、そもそも雇われ社長が取締役ですらないケースも考えられます。つまり、雇われ社長が実は取締役(役員)ではなく、使用人(従業員)といったケースです。
一般的に社長は会社のトップと認識されていますが、実際には必ずしも会社のすべてを単独で決定できるわけではない点を把握しておくべきでしょう。
「代表権がある」という勘違い
一般的に社長は代表権がありますが、必ずしもそうとは限りません。実際、上場会社でも代表権のない取締役社長を置く会社が稀に存在します。
代表権がない場合、社長であっても原則として会社名義の契約締結行為ができません。もっとも、株式会社が代表取締役以外の取締役に社長という名称を付した場合は、その社長がした契約締結行為は、実質的に有効となる場合があります。
- (表見代表取締役)
第三百五十四条 株式会社は、代表取締役以外の取締役に社長、副社長その他株式会社を代表する権限を有するものと認められる名称を付した場合には、当該取締役がした行為について、善意の第三者に対してその責任を負う。 - 引用:会社法 第三百五十四条|e-Gov 法令検索
稀ではありますが、社長だからといって代表権がある、すなわち他社と有効に契約を締結できるとは限らない点に注意してください。
「雇われている」という勘違い
実は、雇われ社長といっても、実際に株式会社から雇われている(雇用されている)とは限りません。むしろ、一般的には雇われていません。
なぜなら、一般的に社長は取締役であり、取締役は株式会社と委任関係にあるからです。
- (株式会社と役員等との関係)
第三百三十条 株式会社と役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。 - 引用:会社法 第三百三十条|e-Gov 法令検索
雇用と委任の大きな違いは、株式会社の指揮命令で動くかどうかという点です。雇用だと株式会社の指揮命令の下で労働を提供しますが、委任では株式会社から経営を任されています。
さらに、雇用ではなく委任関係にある場合、基本的には労働法において労働者性は認められず、労災保険や雇用保険の被保険者とはなりません。そして、株式会社に賃金の支払義務はなく、いわゆる残業代などもありません。
雇われ社長はあくまでも「雇われているような社長」といった内容を含む比喩的な表現であり、必ずしも法律上の雇用関係を示すものではない点は把握しておきましょう。
「社長であり続けられる」という勘違い
一度社長になったからといって、今後も社長であり続けられるとは限りません。むしろ、取締役社長の場合、取締役の任期は原則2年と短命です。2年を超えてさらに取締役で居続けられる保証はありません。
そして、従業員が会社内部で昇格して社長となった場合には、特に注意が必要です。オーナーが自身の子や孫、甥などの親族を次期社長に据えたかったところ、まだその親族が若いため、一時的に従業員を内部昇格させて社長に据えたというケースもありえます。
このような場合、仮に内部昇格社長の舵取りで業績が好調でも、時期を見てオーナーの親族が役員に就任し、数年で社長の座を奪われる可能性があります。
内部昇格で社長となった場合は、自身の立場がいわゆる中継ぎ社長(リリーフ社長)である可能性も考慮しておくべきでしょう。
雇われ社長を辞めたくなる辛いトラブル
前述した雇われ社長のデメリットや勘違いに起因して、ときには雇われ社長から「辞めたい」「辛い」といった声を聞くこともあります。
ここでは、雇われ社長を辞めたくなる辛いトラブルを、より具体的に紹介します。
- オーナーの意向に逆らえず不本意な決断を迫られる
- 任期までに成果を出すプレッシャーが大きい
- 古参の従業員・役員との関係構築が難しい
- 汚れ役を担わされる
- 個人保証を負うことになる
- 損害賠償責任を追及される
いずれも実際にあり得るトラブルなので、ぜひ把握しておいてください。
オーナーの意向に逆らえず不本意な決断を迫られる
株式会社によっては、実質的な決定権はオーナー(株主)にあり、オーナーの意向に逆らうことは事実上非常に困難なケースもあります。
このようなケースでは、客観的に合理的ではなく、雇われ社長自身の信念に反する内容でも、表面的には自身の判断として決定しなければなりません。
具体例としては、能力に見合わない縁故採用や人事配置の強要、不採算事業の継続などが挙げられます。
さらには、オーナーの意向であるにもかかわらず、従業員の不満の矛先は雇われ社長に向いているケースがあります。
任期までに成果を出すプレッシャーが大きい
社長の交代は、社内から注目を集めるイベントです。さらに、雇われ社長であることで、任期までにV字回復や急成長といった過度な期待を受ける場合があります。
とりわけ創業者オーナー社長と代わる形で社長に就任した場合、会社経営について創業者オーナーから厳しい追及や叱責を受けることもあります。
雇われ社長の成果を出すことへのプレッシャーは、いつ解任されるかわからないといった立場の不安定さも相まって、決して小さくない負担といえるでしょう。
古参の従業員・役員との関係構築が難しい
社長の交代は、古参の従業員や役員にとって好意的なものとは限りません。例えば、外部招聘社長は「よそ者」として扱われ、非協力的な態度を取られる可能性があります。
内部昇格社長でも、より長いキャリアを持つ古参の従業員・役員の「なぜ自分が選ばれなかったのか」といった不満から、良く思われていないかもしれません。
特に、その会社が長年にわたって築いてきた慣習を変革しようとした場合、強い反発を受ける可能性があります。
汚れ役を担わされる
雇われ社長は、事業存続のための苦渋の決断を迫られることがあります。例えば、リストラや不採算部門の閉鎖です。前述のとおり、オーナーの強い意向がある場合はなおさらだといえます。
雇われ社長の立場からすると、就任やオーナーの意向が示されたタイミングによっては「汚れ役を担わされた」と感じることもあるでしょう。
個人保証を負うことになる
中小企業では、銀行融資の審査・契約にあたり、代表者である社長個人の連帯保証(経営者保証)を求められることがあります。
経営者保証があると、経営の失敗が個人の資産を失うことにつながるおそれがあるため、思い切った経営判断がしにくくなります。また、保証契約の性質上あってはならないことですが、十分な説明を受けたと認識しえない状態で連帯保証債務を負っているケースもありました。
もっとも、近年は2013年に公表された「経営者保証に関するガイドライン」の活用も進み、経営者保証に依存しない融資も増えています。
参考:「経営者保証に関するガイドライン」等の活用実績について(令和6年度の実績)|金融庁
損害賠償責任を追及される
取締役である社長は、株主であるオーナーから、任務を怠ったとして損害賠償責任を追及されることがあります。本来は株式会社が取締役(社長)の責任を追及しますが、一定の条件下で、株主(オーナー)が会社を代表して訴訟を提起できます。
また、訴訟に至らなくても、事実上の責任追及の手段として報酬が減額される可能性も否めません。
オーナーと社長の違いに関するよくある質問(FAQ)
オーナーと社長の違いに関するよくある質問について、それぞれお答えします。
オーナーと経営者の違いは何ですか?
一般的に、オーナーは筆頭株主など持株比率の高い株主を、経営者は社長などの取締役を指します。あくまでも比喩的な表現ですが、オーナーは会社を所有し、経営者は会社を経営するといった点が大きな違いです。
創業期の株式会社では、多くの場合、オーナーと経営者が同じ人物で、所有と経営が一致しています。
オーナーは社長ですか?
オーナー(持株比率の高い株主)が、その会社の社長であるとは限りません。オーナーと社長が同じ人であることもあれば、違う人の場合もあります。
創業期の株式会社では、オーナー自ら社長を務めるケースが一般的です。
社長とオーナーはどっちが偉い?
特にどちらが偉いかの決まりはありません。ただし、社長(取締役)の選任や解任、報酬などの人事は株主総会の決議事項である点から、一般的にはオーナー(持株比率の高い株主)のほうが偉いと認識するのが自然といえます。
社長の人事がオーナーの意向に左右される以上、オーナーより社長のほうが偉いと認識するのは不自然だからです。
もっとも、従業員の立場からは、指揮命令系統のトップにあるのはオーナーではなく社長(取締役)といえます。従業員は、社長の指示に従う必要はあっても、オーナーの指示に従うべき法律上の義務はありません。
オーナーと社長の違いは所有者か経営者かにある
ビジネスにおいて、特に株式会社では、オーナーは筆頭株主など持株比率の高い株主を、社長は代表取締役などその会社のトップを指します。ただし、オーナーと社長はどちらも厳密な定義は定まっていないため、使われる文脈によっては細部が異なる可能性もある点に注意してください。
そもそも株主と社長は比較が難しいほど異なる地位ですが、あえて比較すると、受益形態や責任範囲が大きく異なります。また、オーナーの議決権の保有割合にもよりますが、一般的にはオーナーのほうが偉いと認識されています。
ただし、特に中小企業ではオーナーと社長が同一人物(オーナー社長)の場合も少なくありません。
このような状態は所有と経営の一致と呼ばれ、オーナー社長自身の地位は他人に左右されることなく安定しており、実質的に他人の反対を押し切ってでも迅速かつ大胆な意思決定を実現できるメリットがあります。
一方、客観的にみると、オーナー社長の意思決定プロセスに他者の意見が十分に反映されず、独断的なワンマン経営に陥る可能性がある点はデメリットです。
もちろん、雇われ社長にもメリット・デメリットがあります。オーナーと社長の違い、そしてオーナー社長と雇われ社長それぞれの特徴を把握することで、会社運営上の後悔やトラブルを避けることができるでしょう。