

東京弁護士会所属。
破産をお考えの方にとって、弁護士は、適切な手続きをするための強い味方になります。
特に、周りに相談できず悩まれていたり、負債がかさんでしまいそうで破産を考えていたりする方は、ぜひ検討してみてください。
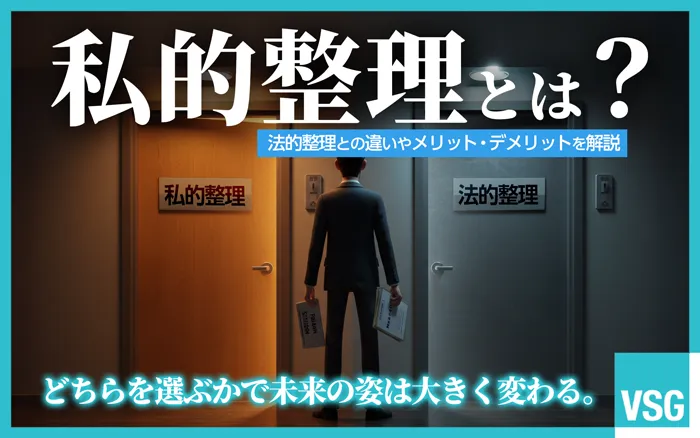
Contents
私的整理とは、債権者と債務者の合意に基づいて債務を整理する方法です。民事再生や破産などのように、裁判所による法的な倒産手続を経ずに手続きを進めます。
事業者は各債権者との交渉により同意を得ることができれば、債務の支払いを軽減することが可能です。私的整理は、法人だけでなく個人でも利用できます。
私的整理は、当事者同士だけで話し合う「純粋私的整理」と、一定のルールに従って進める「準則型私的整理」の大きく2つに分けられます。
| 純粋私的整理 | 任意整理による私的交渉 |
|---|---|
| 準則型私的整理 | 事業再生ADR |
| 整理回収機構(RCC)による企業再生スキーム | |
| 中小企業再生支援協議会による再生支援手続 | |
| 地域経済活性化支援機構(REVIC)の事業再生支援 | |
| 特定調停 | |
| 私的整理ガイドラインに沿った私的整理 |
純粋私的整理では、事業者と債権者が個別に交渉を行うため、突然債権者から差押えされるなど不測の事態も考えられます。法律による縛りがないので柔軟な対応が可能ですが、事業再生計画によっては、合意を成立させることが難しいこともあります。
一方、準則型私的整理では、各債権者にとって公平な合意となるよう、各種ガイドラインや中立的な立場の第三者が関与のもとで手続きを進めます。事業再生ADRやRCC企業再生スキーム、私的整理ガイドラインに沿った私的整理など、さまざまな選択肢があります。制度化されたルールに沿って手続きを進めていくので、事業者および各債権者で共通認識を持つことができ、合意形成を成立させやすいのが特徴です。
事業再生の代表的な方法には、「私的整理」と「法的整理」があります。
私的整理は、裁判所の介入なしに当事者の合意によって行う債務整理です。ガイドラインや中立的な立場の第三者が介入して、事業者と債権者が話し合うことで債務負担を軽減します。
一方、法的整理とは、法律に従って裁判所が行う倒産手続のことです。会社を消滅させる破産や、会社を再建する民事再生、会社更生などが法的整理に当たります。
私的整理と法的整理の主な違いは、以下のとおりです。
| 私的整理 | 法的整理(民事再生) | |
|---|---|---|
| 手続費用 (弁護士費用を除く) | 原則なし | 200万〜 |
| 裁判所の関与の有無 | なし | あり |
| 対象となる債権者 | 債務者が選択した債権者 | 全ての債権者 |
| 債権者の合意 | 対象債権者全員との合意が必須 | 多数決で決定 |
| 透明性・公平性 | 確保しにくい | 確保しやすい |
| 手続きが公になるリスク | 低い | 高い |
適切な事業再生の方法を選択するためにも、私的整理のメリット・デメリットをしっかり把握しておきましょう。
私的整理の主なメリットは、以下のとおりです。
私的整理の大きなメリットとして、事業再生の手続きを進めているという事実が公になりづらい点が挙げられます。
事業再生を検討するうえで心配なのが、信頼性を保てるかという点です。うまく事業を立て直すことができても、取引先や一般債権者の信頼を失えば資金繰りは苦しくなります。
法的整理の場合、全ての債権者が支払免除等の対象となります。経営難の状態が広く知れ渡ってしまうと、「倒産企業」という認識が広まってしまい信頼を失う可能性が高いです。
一方、事業者が債務整理の対象とする債権者(主に大口の金融機関)を指定して行う私的整理であれば、取引先や一般債権者に債務整理の事実が知られにくいというメリットがあります。その結果、事業の価値や信頼を損なわずに債務整理をすることが期待できます。
私的整理では、迅速かつ柔軟な解決が期待できるというメリットがあります。
法的整理の場合、法律で定められた手順に従って、裁判所の関与のもとで手続きを進めていきます。債権の種類や大きさ、実態を問わず、すべての債権者を平等に扱う必要があるため、状況に合わせた柔軟な対応は難しいといえるでしょう。
また、法的整理ではスケジュールも法律で定められているため、融通を利かせることはほぼ不可能です。
これに対して、私的整理は債務者と債権者が主体となって合意を目指すため、債権者ごとの対応が可能です。返済条件や支払い猶予なども、各債権者との合意に基づいて自由に変えることができます。
事業再生の手順も決まっていないため、お互いの意見に合わせて柔軟にスケジュールを組み替えられます。
合意形成が難しい状況では時間がかかることもありますが、債務の規模に合わせて簡素化された手続きで債務整理を進めることも可能です。
私的整理では、法的整理に比べてコストを抑えられるというメリットもあります。
法的整理は法的な手続きなので、裁判所に予納金を納める必要があります。予納金額は事業規模などで変わりますが、法人の民事再生であれば200万円以上の費用がかかります。
一方、私的整理は裁判所を通さない手続きなので、予納金などを負担する必要がありません。法的整理よりもコストを抑えて事業再生を目指せます。
事業者、債権者の双方にメリットの大きい私的整理ですが、次のようなデメリットがあることも理解しておかなければなりません。
私的整理は、債権者と秘密裏に交渉を進めていくことが可能です。
個別交渉を行なった場合、どのような方法でどのような合意になったのか、他の債権者は知ることができません。その結果、手続きの透明性を確保することが難しくなり、他の債権者から疑念を持たれる可能性があるでしょう。
たとえば、特定の債権者のみに有利な内容の合意をすることも可能ですが、これは他の債権者にとっては不利な状況になるということでもあります。すべての債権者を平等に扱う法的整理に比べて、公平性に疑問の残る債務整理になってしまう可能性があります。
債権者のみならず、投資家など債権者以外のステークホルダー(利害関係者)にとっては、企業の価値を見定めるうえでの検討材料が少なくなることにも繋がります。
ただし、近年は私的整理における手続きの不透明性への対策が進められています。「私的整理に関するガイドライン」のほか、「事業再生ADR」や「RCC企業再生スキーム」などを活用すれば、法的整理のように、各債権者にとって公平な合意を目指すことができます。
私的整理では、当事者同士の話合いによって債務の圧縮や弁済方法を取り決めます。そのため、協議する債権者の同意が得られなければ、私的整理を進めることができません。
私的整理には法的な強制力がないため、交渉に応じない債権者に対して合意を強制することはできません。そのため、ある程度の支払い能力がないと債権者との合意形成は難しいといえるでしょう。
また、これまでに何度も債務整理を行っている場合や、借入れをしてから一度も返済をしていない場合など、債権者からの信用がない場合にも合意は困難です。
そもそも私的整理には一切応じないとしている金融機関も存在するため、状況によっては私的整理による債務整理自体が難しいケースもあるでしょう。
法的整理と違い、私的整理では保全処分などの会社財産を保全する制度がありません。そのため、債権者から強制執行などにより財産を差し押さえられたときに対処することができません。
私的整理では、どのような結果になるかは債権者との交渉次第となります。たとえば、最初から低金利で融資を受けていたケースなどでは、大幅な債務カットが認められないケースも多いです。
状況次第では減額の合意に至らないことも考えられるので、注意が必要です。より良い内容で合意するためには、財務DDや事業DDの結果を踏まえて、効果的な交渉を行う必要があります。
事業者だけで対応するのではなく、専門的な知識をもって適切に対応できる弁護士のサポートを受けることをおすすめします。
破産や民事再生などの法的整理であれば、回収できなかった債権を損金処理できます。これにより、債権者は税金を圧縮することが可能になります。
一方で、私的整理の場合、債権放棄額を損金処理できないケースがあります。無税償却できない場合には、再生計画について同意を得ることは難しくなるでしょう。
もっとも、事業再生ADRやRCC企業再生スキーム、私的整理ガイドラインに沿った私的整理であれば、合理的に債権放棄が行われたと判断される可能性が高く、無税償却が可能となります。
私的整理、法的整理のどちらを選択すべきかは、経営状態や事業継続の可能性などから総合的に判断する必要があります。
ここでは私的整理を検討すべき3つのケースについて解説していきます。
私的整理では特定の債権者との話し合いで債務整理を進められるため、事業の経営状態を周囲に知られたくない場合に有効です。
事業を継続するうえで、取引先などステークホルダーの信用はとても重要です。私的整理は法的整理とは違い、情報が公になるリスクが低いため、事業価値を保持したまま経営を立て直すことが期待できます。
ただし、債権者ごとに対応が違うため、それぞれの求める返済計画をプレゼンしていく必要があります。
債権者ごとに柔軟に対応したい場合には、法的整理ではなく私的整理が向いています。
私的整理では、事業者が債務整理の対象とする債権者を指定することができます。たとえば、大口の金融機関とは債務減額や支払猶予を交渉し、それ以外の債権者とは話し合いを保留するといった対応が可能です。
ただし、原則として、私的整理は交渉をしたすべての債権者から合意を得たうえで進める必要があります。
もし差押えなどの法的手続きを強行する債権者がいた場合には、債権者間の公平性を維持するため、法的整理を検討することになります。
すでに事業の経営が傾いている事業者にとって、債務整理にかかるコストは死活問題です。法的整理の場合、選択する手法によっては、1000万円以上の予納金を裁判所に納めなければいけないケースもあります。
一方、私的整理は話し合いがメインなので、基本的に手続き費用がかかりません。できるだけコストを抑えて事業を再生し、再生後の資金を残しておきたい場合は、私的整理を選択するのがおすすめです。
私的整理は法的整理と比べて公になるリスクが低いため、利用しやすい制度です。迅速かつ柔軟にコストを抑えて手続きを進めたい場合には、私的整理を検討しましょう。
ただし、私的整理には手続きの透明性に懸念が残るほか、交渉をした債権者全員の同意が必要になるというデメリットもあります。
私的整理におけるメリットとデメリットを正しく認識し、事業の状況によって最適な債務整理の方法を選ぶようにしましょう。
素人判断でむやみに手続きを進めるのはおすすめできません。相談先に迷ったら、弁護士・税理士・司法書士が連携して対応できる”ベンチャーサポート法律事務所”にぜひお気軽にご相談ください。