

東京弁護士会所属。
破産をお考えの方にとって、弁護士は、適切な手続きをするための強い味方になります。
特に、周りに相談できず悩まれていたり、負債がかさんでしまいそうで破産を考えていたりする方は、ぜひ検討してみてください。

個人再生は、借金の返済が難しくなった場合に、裁判所を通じて借金を大幅に減らす手続きのことです。
住宅資金特別条項を使うことで、住宅を残したまま債務整理ができることが特徴です。
利用には様々な条件があるため、住宅資金特別条項のしくみをよく理解しておくことが大切です。
今回は、個人再生を行う場合に住宅ローンがどうなるのか詳しく解説します。
制度を利用できないケースや、個人再生手続き後の審査についても参考にしてください。
Contents
個人再生は住宅を残して借金を大幅減額できる制度ですが、住宅ローンはどうなるのでしょうか?
ここでは住宅ローンの取り扱いに関係する、住宅資金特別条項について詳しく解説します。
住宅資金特別条項とは、個人再生の手続きにおいて、家を残すための特別なルールです。
通常の個人再生では、すべての借金を整理対象としますが、この条項を使うと住宅ローンだけを対象から外すことができます。
家を手放さずに生活を立て直すことができるため、家族がいる場合や実家を守りたい場合などに有効な手段と言えます。
ただし、住宅ローンの支払いがきちんとできていることが前提となるため、条件を満たさない場合には利用できません。
住宅資金特別条項を利用する場合は、必要な条件をしっかり理解しておきましょう。
住宅資金特別条項を利用する場合の条件は、以下のとおりです。
上記の条件のうち一つでも外れると、住宅資金特別条項は使えません。
ご自身が条件に当てはまっているかどうか、事前にしっかり確認しておきましょう。
住宅資金特別条項には、利用する人の状況に応じて選べる5つの型(パターン)があります。
住宅ローンの滞納状況や保証会社の対応によって、個人再生後にどのように返済を続けるかを調整するためのしくみです。
代表的な5つの型の概要は、以下の通りです。
住宅ローンを滞納せずきちんと支払っている人が、そのまま返済を続けていく方法です。
もっともシンプルで利用されることが多い型です。
ローンの滞納などにより、銀行から一括返済を求められた場合でも、期限の利益回復型を使うと、従来通りの分割で支払う方法に戻すことができます。
①②の方法では返済計画案の認可が見込めない場合に、ローンの支払期限を延長する方法です。
期限が延びることで、月々の返済の負担を軽くすることができます。
③の期限延長だけでは返済が難しい場合に検討する方法です。
支払期限を延長しながら、猶予期間として一定の間、元本の支払いをせず利息のみ返済をしていきます。
債権者の同意を得ることで、支払期限を延長するしくみです。
期限延長型よりも長く延長できることもあります。
自分に合った型を選ぶことで、無理のない返済計画を立てやすくなります。
どの型が適しているかは、状況に応じて専門家と相談しながら決めるといいでしょう。
住宅資金特別条項は便利な制度ですが、すべての住宅ローンに適用できるわけではありません。
次のようなケースに当てはまると、この制度を使って家を残すことが難しくなります。
詳しく見ていきましょう。
住宅ローン以外に、同じ家を担保にしたローンがある場合をダブルローンと言います。
たとえば、住宅ローンとは別にリフォームローンや事業資金の借入があり、住宅が担保として使われている場合などです。
複数のローンが住宅に絡んでいる場合、住宅ローンのみを整理対象から外し、他の債務を整理するという対応ができなくなります。
ダブルローンになっているかどうかは、住宅ローンの契約書や抵当権の登記内容を確認しましょう。
アンダーローンとは、ローンの残債より家の価値のほうが高い状態のことを言います。
たとえば、住宅の査定価格が3000万円で、住宅ローンの残債が2000万円というケースです。
このような場合、家を売却すればローンはすべて完済でき、手元にお金も残ります。
裁判所からすると、住宅資金特別条項を使ってまで守る事情がない、ということになります。
アンダーローンの場合は、家を売って借金を返済することが現実的とみなされることが多いです。
住宅ローンの借り換えをしていても、住宅資金特別条項を利用することは可能です。
しかし、借り換え後のローン契約内容に注意が必要です。
たとえば、住宅ローン以外の用途にも使える内容になっている場合、住宅資金特別条項の対象外になる可能性が高いです。
借り換え時の諸費用を住宅ローン内に組み込んでいる場合などは、利用できない場合があります。
長期間、住宅ローンを滞納している場合は注意が必要です。
滞納者に代わって保証会社がローンを支払うことを、代位弁済と言います。
民事再生法により、代位弁済が行われてから6カ月以内に個人再生を申し立てると、例外的に住宅資金特別条項を利用できると定められています。
しかし6カ月を過ぎると例外は認められず、特別条項を利用できなくなります。
また、マンションなどに住んでいる場合は、管理費の滞納にも注意が必要です。
管理組合から住宅に差押えが入る可能性があり、特別条項の利用が難しくなります。
固定資産税や住民税などの税金を滞納していると、役所から住宅に差押えが入ることがあります。
一度でも差押えが実行されると、住宅の所有権を失うことになり、住宅資金特別条項の利用条件を満たさないことになります。
税金の支払いは国民の義務であるため、債務整理でも減額されることはありません。
滞納している税金があれば、先に支払っておきましょう。
ここでは住宅ローンがある場合に、個人再生を利用することのメリットとデメリットを解説します。
制度のよい面だけでなく、注意点も把握しておくことで、適切な判断がしやすくなります。
そもそも個人再生自体には、業者からの取立てが止まることや、過払い金請求ができることなどメリットが数多くあります。
住宅ローンがある場合に個人再生を行うメリットには、どのようなものがあるのでしょうか。
詳しく解説します。
個人再生の最大のメリットは、家を手放さずに借金だけを大幅に減らせるという点にあります。
自己破産は原則として住宅を手放す必要があり、家族がいる場合や家を守りたい場合は選択することが難しいでしょう。
個人再生を選ぶことで家族とこれまでどおりの生活を守れる、ということは大きな利点です。
住宅ローンを滞納すると、銀行などの金融機関から一括で全額支払を請求されることがあります。
これを期限の利益の喪失と言い、分割で支払いをする権利を失うという意味です。
個人再生を申し立て、住宅資金特別条項を利用することで、ローンの支払いを再び分割払いに戻すことができます。
住宅ローンの数千万円をすぐに払えない場合でも、再び分割払いに戻すことで、競売や退去を避けることができます。
住宅資金特別条項を利用すると、住宅ローンの返済期間を延ばすことができます。
たとえば、残り15年のローンを20年に延ばすことで、月々の返済額を減らすことができ、家計への圧迫を和らげることができます。
返済期間の延長は、裁判所を通じた正式な手続きの中で認められるため、金融機関側が一方的に拒否することはできません。
生活を立て直していく時間を少しでも確保したいという場合には、大変有効な手段です。
元本猶予型を選択すれば、一定期間は元本を据え置いて利息だけを払うことができるため、当面の負担を軽くできます。
失職や病気などで収入が一時的に落ちている場合、年収の回復を待ちながら家計の再建をすることができます。
金融機関との調整が必要なため、弁護士などの専門家に相談してみましょう。
住宅ローンがある人が個人再生を行う場合のデメリットとは、どのようなものがあるでしょうか。
順番に見ていきましょう。
住宅資金特別条項を使うと、住宅ローンの返済はそのまま継続されるため、結果として住宅ローンと個人再生の返済が同時進行することになります。
たとえば、住宅ローンで月8万円、再生計画で月3万円の返済になったとすると、月11万円を毎月支払うことになります。
収入に見合っていない計画を立ててしまうと、結局また滞納することにもなりかねません。
すでに住宅ローンや管理費、税金などを滞納している場合、滞納分も含めて返済計画を立てる必要があります。
ただでさえ生活が苦しい中、過去の滞納分まで数年間で返済することになるため、返済の負担が大きくなります。
裁判所が、継続的な支払い能力がないと判断すれば、再生計画そのものが却下されることもあるため、注意が必要です。
家の評価額がローン残高を上回っている状態の場合、家を売却すればよいとみなされ、住宅資金特別条項が使えない場合があります。
特別条項が利用できない場合、住宅を手放す、または住宅込みで債務整理をする必要がでてきます。
アンダーローンの場合は、住宅を残すことは難しいでしょう。
個人再生後に再び住宅ローンを組むことはできるのでしょうか。
結論から言うと、個人再生後に住宅ローンを組むことは可能ですが、すぐには難しいというのが実情です。
ここでは、個人再生後に住宅ローンを組む方法や注意点について解説します。
個人再生をすると、信用情報機関に事故情報として登録されます。
いわゆるブラックリストに載った状態です。
事故情報が残っている間は、銀行や信用金庫など金融機関の住宅ローン審査には、ほぼ通らないと考えていいでしょう。
事故情報は、完済から5年~7年残ることが一般的です。
そのため最低でも5年程度は、住宅ローンを組むことは難しいと言えま。
事故情報を確認せず住宅ローンを申し込み、審査に落ちた場合も注意が必要です。
一度審査に落ちると、6カ月程度は金融機関の内部に記録として残ります。
事故情報が削除されてから再度申し込みをしても、6カ月程度経過していなければ「審査に落ちた」という事実からローンが通らない可能性があります。
審査を受ける前に、必ず事故情報を確認するようにしましょう。
審査に落ちた場合はすぐに再申し込みをせず、少し時間を空けてからにしましょう。
個人再生で債務整理の対象となった金融機関とは、その後の取引は難しくなります。
たとえブラックリストから情報が消えていても、社内ブラックとして内部記録に残っているケースがあるためです。
そのため住宅ローンを申し込む際には、債務整理をしていない別の金融機関を選ぶことが基本となります。
どうしても早く家を購入したい場合は、自分ではなく家族名義で住宅ローンを組むという選択肢もあります。
個人再生の対象は個人のみです。
家族に個人再生の影響はないため、家族がローンを組むことは問題ありません。
たとえば、配偶者に安定した収入があれば、配偶者名義でローンを組んで家を購入することができます。
個人再生が終わっても、すぐに住宅ローンを組めるわけではありません。
将来また家を購入したいと考えているなら、信用を回復させるための準備を早めに始めることがとても重要です。
ここでは、住宅ローンの審査に通る可能性を少しでも高めるために、やっておいた方がよいことや注意点を具体的に解説します。
まず大前提として、信用情報に事故記録が残っている状態では審査に通りません。
そのため信用情報が回復しているかどうか、必ず確認しておく必要があります。
信用情報は、CIC・JICC・全国銀行個人信用情報センターといった機関に登録されており、自分自身で開示請求ができます。
数百円で郵送やスマホから確認できるので、住宅ローンに申し込む前には必ずチェックしておきましょう。
住宅ローンの審査で最も重視されるのは、収入の安定性です。
どれだけ信用情報が回復していても、毎月の収入がバラバラである場合や、勤続年数が極端に短い場合は、審査に通る可能性は低くなります。
具体的には、以下のようなポイントに注意しましょう。
自営業やフリーランスであっても、3年分程度の確定申告書と収支内訳書を準備し、事業の継続性を証明できれば、ローンが通る可能性はあるでしょう。
住宅ローンの審査では、頭金の額も重要な判断材料になります。
とくに過去に債務整理をしている場合、本当に返済能力があるのか慎重に見られるため、頭金を多めに用意することで信頼を高めることができます。
頭金が多ければその分ローンの借入額も少なくなるため、毎月の返済額も減り、審査にもよい影響があります。
メガバンクや地方銀行の審査が通らなかった場合でも、あきらめる必要はありません。
ノンバンク系と呼ばれる住宅ローン専門の金融機関や、クレジットカード会社などであれば、柔軟に審査してくれることがあります。
ただし、信販会社やノンバンクでも、事故情報が残っている期間はローンを組むことはできないため、事前に信用情報の確認は必要です。
また、銀行より金利が高くなる傾向にあるため、よく確認しましょう。
信用情報や収入に不安がある場合、単独で申し込むのではなく、家族と一緒にローンを組む方法も選択肢になります。
たとえば配偶者と一緒に組むペアローンや、親と子が連携する親子リレーローンがあります。
ただし、誰かと一緒にローンを組む以上、相手の信用情報や収入も重要な審査対象になります。
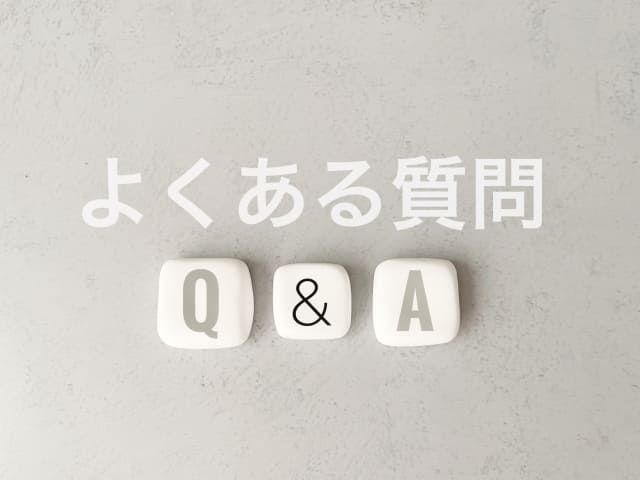
ここでは住宅ローンがある場合の、個人再生手続に関するよくある質問を解説します。
住宅ローンに連帯保証人がついている場合、住宅資金特別条項を利用すると、保証人に影響は出ません。
民事再生法第203条第1項、および第177条第2項により、連帯保証人に対して請求が及ばないことが定められているためです。
住宅ローンに関しては、連帯保証人に迷惑をかけずに債務整理ができるという大きなメリットになります。
ただし、住宅ローン以外の借入に保証人がついている場合は、その保証人に請求がいく可能性があるため注意が必要です。
個人再生後の信用回復までの期間は、約5~7年です。
再生手続きが完了してからではなく、完済してからカウントされることに注意しましょう。
3年間の返済期間がある場合、完済してからさらに5~7年、最長で10年近く信用情報に影響する可能性もあります。
個人再生は住宅ローンがある場合に、家を手放さず借金を整理できる唯一ともいえる手段です。
ただし、住宅資金特別条項の利用には、様々な条件や制限があり、制度が使えないこともあります。
メリットとデメリットのよく理解したうえで、自分の生活設計に合った方法を選ぶことが大切です。
個人再生は手続きが複雑で、将来の生活に大きな影響を与える可能性があります。
早めに専門家に相談するといいでしょう。