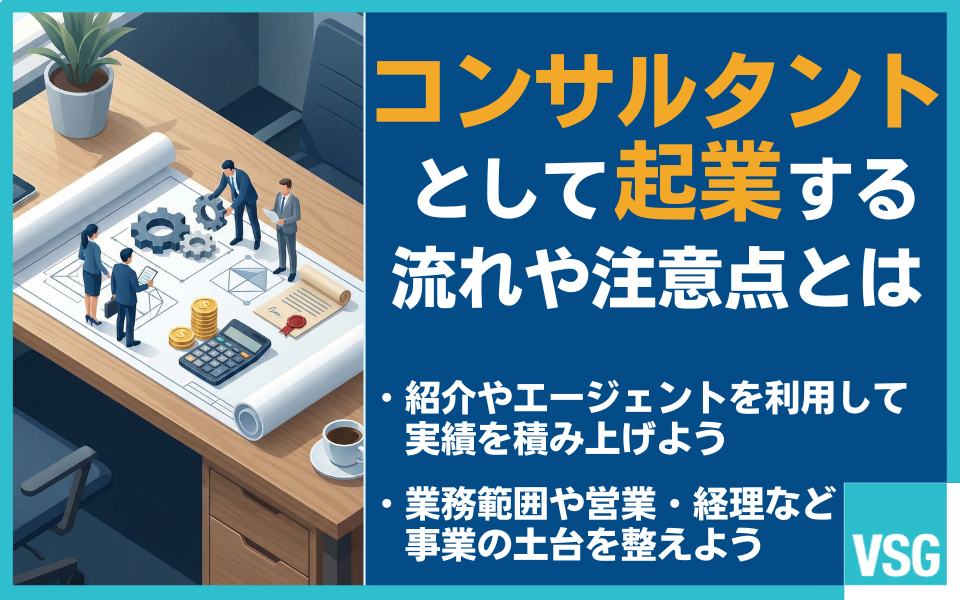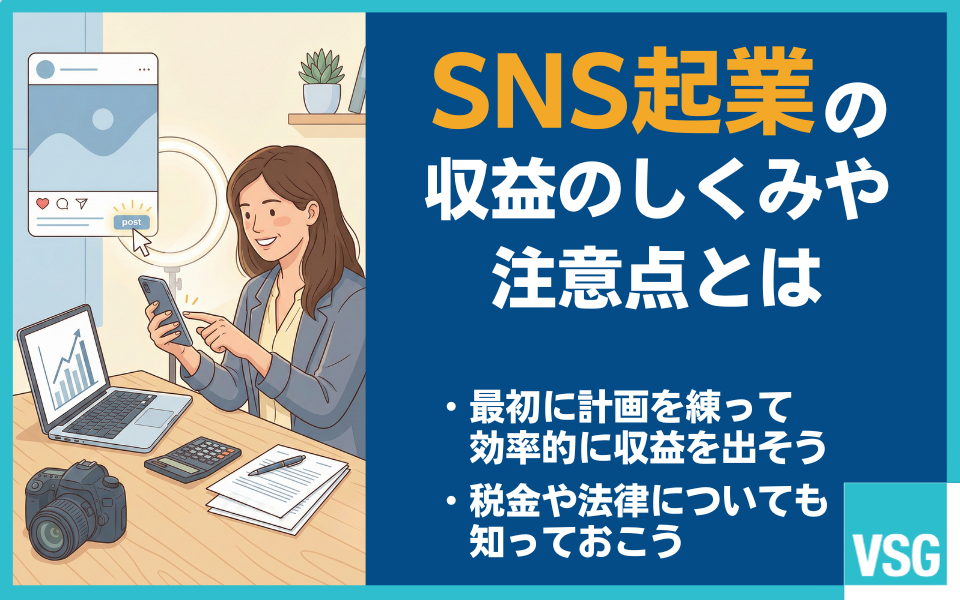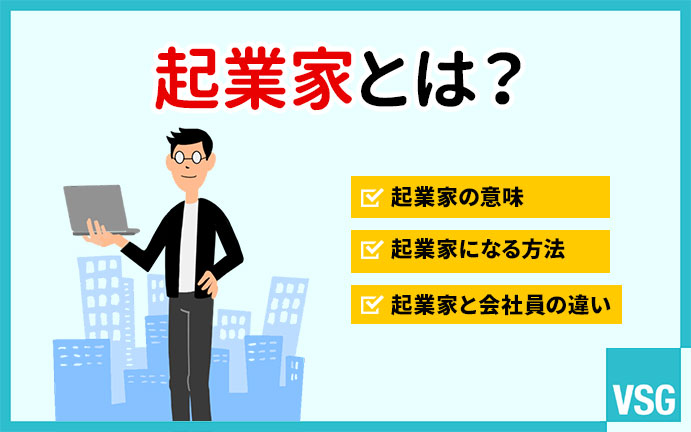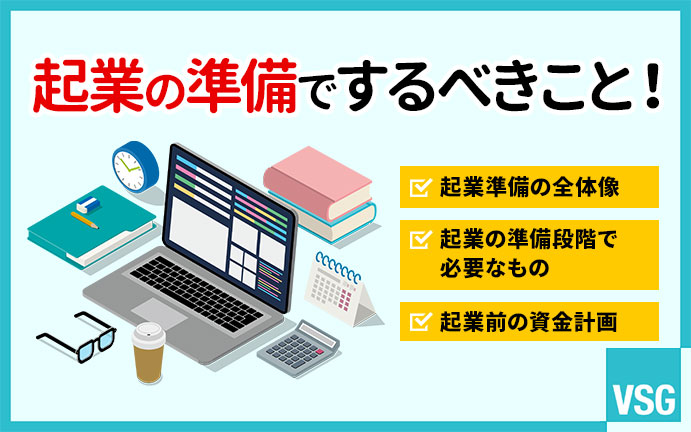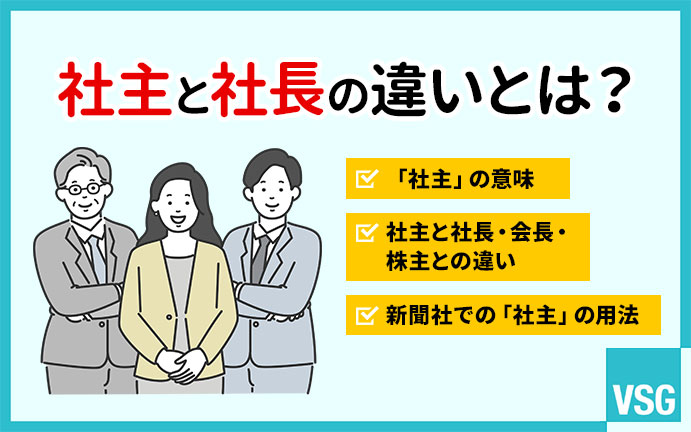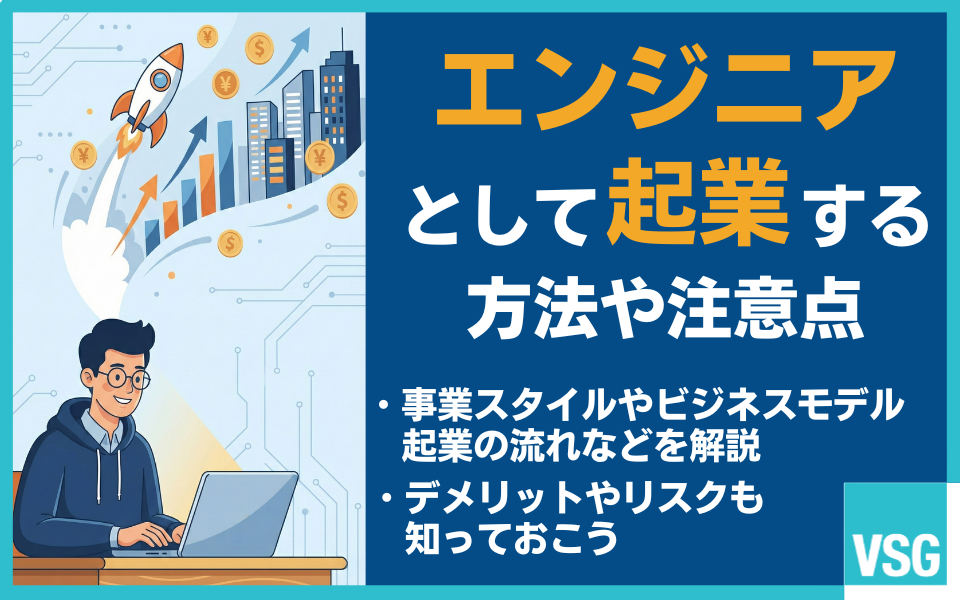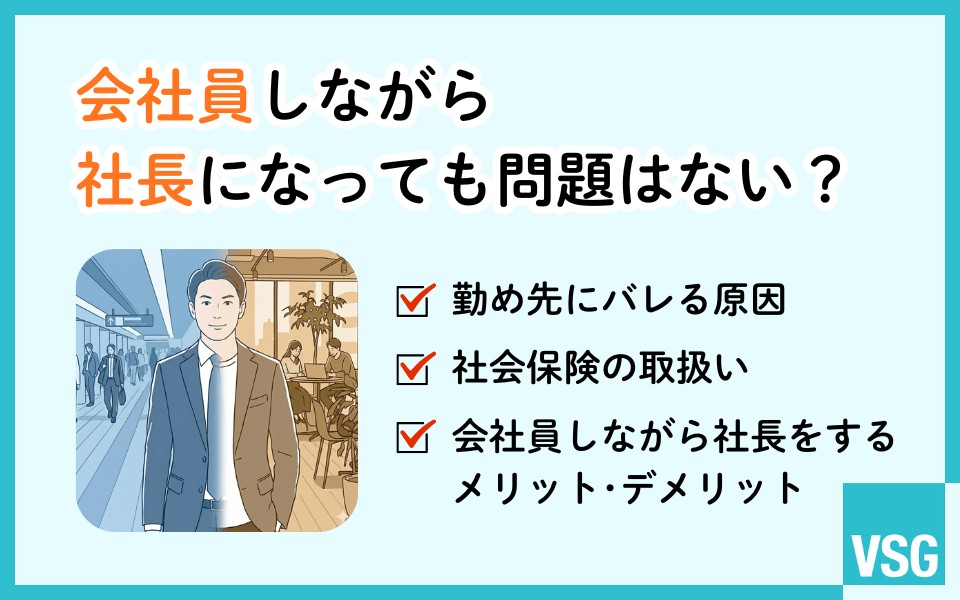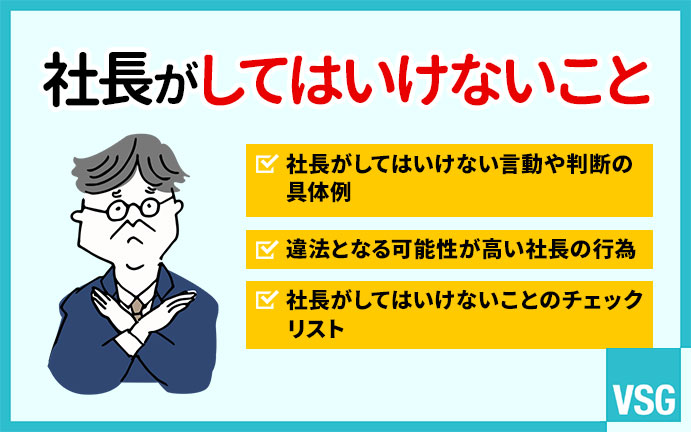最終更新日:2025/9/29
取締役会の招集通知とは?書面のひな形やルールを解説します

ベンチャーサポート税理士法人 大阪オフィス代表税理士。
近畿税理士会 北支部所属(登録番号:121535)
1977年生まれ、奈良県奈良市出身。
起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネルを運営。
PROFILE:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_writing/#p-mori
YouTube:会社設立サポートチャンネル【税理士 森健太郎】
書籍:プロが教える! 失敗しない起業・会社設立のすべて (COSMIC MOOK) ムック
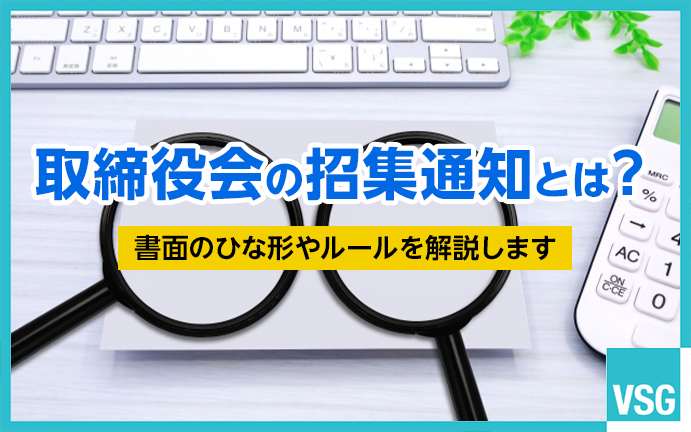
この記事でわかること
- 取締役会の招集通知の基本ルール
- 取締役会の招集通知はメールでもよいこと
- 招集通知のひな形や送付方法
取締役会が設置されている会社では、取締役会を開催する際には「招集通知」を送ることが原則とされています。これは、取締役会のメンバーである取締役に対して会議の日時や場所、議題などを事前に知らせるための手続きです。
招集通知には、送付期限や記載すべき内容など、守らなければならないルールが複数存在します。通知を怠った場合、取締役会の決議が無効と判断される可能性もあるため、注意が必要です。
この記事では、取締役会の招集通知に関する基礎知識、招集通知のひな形、実務で見落としがちな注意点などをわかりやすく解説します。これから会社運営に関わる人にとって役立つ情報をまとめています。


目次
取締役会の招集通知とは?
取締役会を開催する際には、出席すべき取締役や監査役に対して、あらかじめ「開催場所・開催日時・議題」を知らせる必要があります。この知らせを「招集通知」といいます。
招集通知は単なる会議の連絡というだけでなく、取締役会の成立や決議に直結する重要な手続きです。
ここでは、取締役会の招集通知の役割やルールを整理し、押さえておくべき基本事項をわかりやすく解説します。
取締役会の招集通知
取締役会の招集通知とは、取締役会に参加する権利を持つすべての取締役に対して行う正式な案内のことです。
会社法では、原則1週間前までに通知を出すことが義務づけられています。取締役会は会社の重要な方針を決める会議ですので、事前に開催日時や議題などを明示する必要があります。
招集通知の形式は、書面、メール、社内ポータルなど柔軟に対応できますが、通知の遅れや内容の不備があると、会議の正当性が問われる可能性があります。
税理士が取締役会に参加するメリット
会社法上、取締役会は取締役が出席する会議ですが、必要に応じて税理士などの専門家がオブザーバーとして同席することも可能です。
税理士が取締役会に参加すると、取締役は、財務に関する議題(資金調達、決算内容の確認、予算の承認など)について会計や税務の視点からアドバイスを受けられます。これにより、自社にとって有利な経営判断ができるようになるのです。
税理士は決議には参加できませんが、経営判断に必要なデータや税務上の取扱いを説明する役割として非常に有効です。中小企業では、経営と会計の距離が近いため、税理士の参加によって議論がより実質的になるケースも多く見られます。


取締役会の決議事項
取締役会では、会社運営に関するさまざまな事項が話し合われますが、なかでも「決議事項」は特に重要です。
会社法では、以下の項目に関しては取締役会の決議が必要とされています。
- 取締役会設置会社の業務執行の決定
- 取締役の職務執行の監督
- 代表取締役の選定および解職
- 重要な財産の処分および譲受け
- 多額の借財
- 支配人その他の重要な使用人の選任および解任
- 支店その他の重要な組織の設置、変更および廃止
- 募集社債に関する事項
- 業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備
- 定款の定めに基づく責任の免除
- その他の重要な業務執行
これらの重大事項については、代表取締役やその他の取締役が独断で判断できないため、必ず取締役会で決議が行われます。
取締役会の招集通知には、こうした決議事項の概要が明記されるケースが多いです。
取締役会の決議事項については以下の記事を参考にしてください。
取締役会の招集ができるのは誰?
取締役会を開催するときには、誰かが「招集者」となり、取締役や監査役に対して通知を出す必要があります。この役割を担うのが取締役会の招集権者です。
会社法では、原則として各取締役に招集権があるとされています。ただし、実務上は、代表取締役または特定の取締役が招集すると定款で定めているケースが多いです。
招集権者が特定されている場合、他の取締役は取締役会を招集することは原則できません。
しかし、例外として、招集権者以外が取締役会を招集できる場面も会社法では定められています。
招集権者以外の人が招集するケース
例外として、招集権を持たない人が取締役会を招集することもできます。具体的には、以下の場合です。
- 招集権を持つ取締役が正当な理由なく取締役会を開かない場合
招集権を持つ取締役が、必要な取締役会を開こうとしない場合、他の取締役や監査役が取締役会を招集することができます。 - 株主が招集を請求するケース
会社の目的の範囲外の行為や、法令・定款に違反する行為を取締役が行っている場合、株主が取締役会を招集できます。招集の請求から5日以内に招集通知が送付されない(2週間以内を開催日時とする)ときに、株主が取締役会を招集できます。 - 監査役による招集
会社の目的の範囲外の行為や、法令・定款に違反する行為を取締役が行っている場合、株主が取締役会を招集できます。招集の請求から5日以内に招集通知が送付されない(2週間以内を開催日時とする)ときに、株主が取締役会を招集できます。
参考:会社法 第三百六十七条|e-Gov 法令検索
参考:会社法 第三百八十三条|e-Gov 法令検索
取締役会の決議の方法を解説
取締役会では、議題に対して意見を出し合ったあと「決議」という形で最終的な意思決定を行います。決議が有効となるためには、以下の要件を満たす必要があります。
- 議決権のある取締役の過半数の出席(定足数)
- 出席取締役の過半数の賛成(必要賛成数)
また、必ず議事録を作成して保管しなければなりません。
取締役会の招集通知には送付期限がある
取締役会を開催するには、出席者に対して開催の旨を周知して十分な準備期間を設けることが必要です。そのため、招集通知には送付期限があります。
原則として1週間前
取締役会を招集する場合、招集通知は原則「開催日の1週間前まで」に送付しなければなりません。
例外がある
取締役会の招集通知は原則1週間前までに送付するのがルールですが、例外もあります。
- 定款で定めている
- すべての取締役の同意がある
取締役会の招集通知の送付期限は定款で定めることで短縮できます。また、すべての取締役が同意している場合は、招集手続きなしで取締役会を開催できます。
期限の数え方
取締役会の招集通知の期限に関して、送付した初日はカウントしません。例えば、5月8日に取締役会を開催する場合で送付期限が1週間とされているケースでは、5月1日までに招集通知を送付する必要があります。
メールなどで通知してオンラインでもよい
取締役会の招集通知は書面で送付する必要はありません。メールやクラウドシステムを使った通知でも有効です。会社法は取締役会招集通知の「方法」について制限していないため、受け取る側が内容を確認できる方法であれば問題ありません。
重要なのは、通知を受けた取締役が内容を確認できることです。
また、取締役会はオンライン(リモート)での開催でも問題ありません。必ず会議室に集まって話し合わなければならないというルールはありません。オンラインで開催すると、遠隔地にいる取締役もリアルタイムで出席できます。
オンラインで取締役会を開催するなら、決議や意思疎通に支障がないよう通信環境を整えておきましょう。
取締役会の招集通知には何を書く?
招集通知は、取締役会を適切に開催するための重要な書類です。内容は会社法で定められていませんが、単に「取締役会を開きます」という一文だけでは足りず、会議の日時・場所といった、必要な情報を記載しておく必要があります。
招集通知の記載事項
招集通知の内容に関しては会社法上のルールはありません。とはいえ、招集通知である以上、最低でも開催場所と日時は記載するべきでしょう。
取締役会の招集通知には、一般的に次のような項目を記載します。
- 開催日時(例:2025年6月15日10:00〜)
- 開催場所(会議室の場所。オンラインの場合はURLなど)
- 議題
- 回答・連絡方法と期限
こうした最低限の情報を記載することで、取締役に取締役会があることを周知したという事実が生まれます。
取締役会の招集通知の内容
取締役会の招集通知を送る方法として、最近ではLINEやメールなどで通知するケースが多くなっています。
通知の内容は、取締役会の日時と場所といった基本的なものです。
タイトルは「取締役会 招集通知」として作成し、前述の内容を記載するのが一般的です。
取締役会を招集する流れ
取締役会は、通知の送付などの事前準備、当日の運営、議事録の作成・保存といった一定の手順に沿って進められます。
取締役会の招集通知の発送
取締役会を開催する際は、まず議題や資料の作成を行います。次に、会議の開催日時と場所を確定します。オンライン会議の場合は、使用するツールのURLや接続情報も含めて整理しておくことが必要です。
議題や開催日時が確定したら、招集通知を作成し、原則1週間前までに送付します。送付方法は書面、メール、クラウド共有など、自社の実情に応じた方法で問題ありません。送信履歴や到達状況が確認できる手段を選ぶとよいでしょう。
招集手続きをしなくてもいいケース
招集通知を送付することなく取締役会を開催できる例外として「すべての取締役が同意している場合」があります。
招集通知の送付は原則必要ですが、取締役会に参加する取締役全員が同意していれば、招集通知なしで取締役会を開催し決議を行うことができます。
取締役会の招集手続きが無効になるケース
取締役の招集通知の欠陥が原因で招集手続きが無効になったという判例があります。
招集通知が一部の取締役に送られていなかった
株式会社の取締役会の招集通知が一部の取締役に送られていなかった場合、最高裁では決議は原則として無効になると判断されています。
ただし、招集通知が届いていなかった取締役が仮に反対していても決議の結果が変わらない場合は有効であるとしています。例えば、1人の取締役に招集通知が届いていない状態で行われた取締役会の決議が満場一致だった場合は、決議の結果に影響しないため「有効」とされるわけです。
株主総会と取締役会の違い
会社の重要な意思決定の場として「株主総会」と「取締役会」があります。どちらも会社運営にとって必要不可欠ですが、目的・構成・決定事項の範囲は大きく異なります。
取締役会
取締役会は、株主から経営を委任された取締役によって行われる会議です。経営判断のために開催されるもので、会社の所有者が集まる株主総会とは異なります。
開催頻度は最低でも年に4回で、状況によってはさらに多くなることもあります。
株主総会
株主総会は会社に出資した株主、つまり会社の所有者が集まって決議を行う総会です。開催頻度は最低年に1回で、取締役の選任などを決議します。
取締役会も株主総会も招集通知などの手続きを経て開催されますが、その役割や参加者の立場は大きく異なります。
取締役会の招集通知は重要な手続き
取締役会を開催するには、原則として招集通知の送付が必要です。招集通知の送付に関するルールを守ることは、単なる形式ではなく、取締役会の決議の有効性を担保するために必要な要件となります。
また、招集者の資格や出席者全員の同意によって手続きを省略できるといった会社法上のルールを理解することも重要です。ひな形や判例を参考にしながら、自社に合った運営方法を整える必要があります。