

東京弁護士会所属。
交通事故の程度によっては、入院が必要になったり、定期的な通院、精神的にも疾患を負ったり、PTSDとして現れることもあります。
こうした状況の中で、交渉ごとを被害者本人でまとめようとすることは非常に大変です。
弁護士に示談交渉を依頼することで、直接示談交渉をしたり、資料を準備したりする精神的負担が軽減できます。
つらい事故から一日でもはやく立ち直るためにも、示談交渉は弁護士に任せて、治療に専念してください。

「運転中、突然飛び出してきた自転車をとっさに避けたら、ガードレールにぶつかった!」
このように、加害者と被害者が物理的な接触はしていないが、加害者の行為が被害を誘発した場合の事故を「非接触事故(誘因事故)」と呼びます。
実は非接触事故では、被害者の損賠が加害者の過失の結果であるという因果関係が成り立てば、被害者は加害者に損害賠償を請求することができます。
非接触事故については様々な議論があり、正しい知識を持っている人は多くないのが現状です。
この記事では、どのような場合が非接触事故に該当するのか、具体例を挙げながら詳しく説明します。
さらに、万が一非接触事故にあってしまった場合に是非知っておきたい過失割合の考え方や、加害者が立ち去ってしまった場合の対処法についても解説します。
非接触事故(誘因事故)とは、その名の通り、相手方の行為に起因して、加害者と被害者が直接接触しないで起こった交通事故のことをいいます。
相手方の危険行為により事故が起きそうになり、回避しようとしてとった行動の結果、被害者がケガをしたというような場合が該当します。
ここでは具体的な事例を用いて、どんな場合が非接触事故に当たるのか分かりやすくご紹介します。
非接触事故の一例として、以下のような場合が挙げられます。
いずれも「ぶつかりそうになった」ためにハンドル操作や急ブレーキを余儀なくされています。
加害者と被害者の接触がなくとも、交通事故が発生した以上は非接触事故も警察への報告が必要です。
ケガの自覚症状がない場合や、相手方が事故に気が付かず立ち去ったりしてしまった場合も、必ず警察への連絡はしなくてはなりません。
報告をしなかった場合、道路交通法72条違反に問われる可能性があります。
下記に義務を定めた条文をご紹介しますので、ご参考ください。
引用:
(交通事故の場合の措置)
第七十二条交通事故があつたときは、…当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。同項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置(第七十五条の二十三第一項及び第三項において「交通事故発生日時等」という。)を報告しなければならない。
引用:e-gov法令検索
いざ非接触事故にあってしまった場合、不慣れな状況からどのように対処したらよいか焦ってしまうでしょう。
緊急事態に備え、事故後の対応の流れをおさらいしましょう。
上記の通り、警察への報告は義務ですので、まずは警察へ連絡を入れます。
警察に連絡を入れることで、交通事故証明書を発行してもらえるようになります。
交通事故証明書は、損害賠償請求や慰謝料請求を行う際、また、保険会社への保険金請求の際にも必須となる書類のため、きちんと入手出来るように段取りしておきましょう。
この時、万が一事故が起きてすぐに加害者が立ち去ろうとしている場合は、後から加害者を特定できるよう、ナンバープレートをメモするなどして情報を残しておくことをおすすめします。
また、加害者が残留した場合でも、警察への連絡を拒む場合があるかもしれません。
そのような場合でも、警察への報告は法的に定められたドライバーの義務であることを説明し、必ず連絡をするようにしましょう。
非接触事故にあってしまった場合、あわせて早めに連絡しておきたいのが保険会社です。
タイミングを見て、時間が空かないうちに一報をいれておくと安心です。
相手方がその場にいる場合は、相手方の任意保険会社にも連絡を入れてもらうように伝えるとよいです。
非接触事故にあってしまった際、「ケガの自覚症状がなければ病院へは行かなくてもよい」と考える方がいらっしゃるかもしれません。
しかし、自身が気付いていないケガが潜んでいたり、後から症状が出始めたりすることも考えられるため、ご自身の身体のためにも病院は速やかに受診しましょう。
また、非接触事故では、危険行為と損害の発生の因果関係が鍵となります。
因果関係の立証のためにも、日を置かずに病院を受診しておくことが、後々の賠償請求時に大きなメリットとなります。
症状固定とは、これ以上治療を続けても回復が見込めないと医師が判断した状態をいいます。
病院を受診する際には、「完治」もしくは「症状固定」の診断が出るまで治療を続けます。
症状固定となった場合には、それを前提に後遺障害等級認定を受けた上で保険金の請求が可能となるため、受け取れる保険金が増える可能性があります。
後の損害賠償請求などを見据え、証拠集めをしておくことも重要です。
危険行為と損害の発生の因果関係を証明するためには、危険行為があった際の状況を示す証拠をできるだけ多く集めることが大切になります。
ドライブレコーダーの映像を保存しておく、現場に居合わせた目撃者の証言を集めておくなど、証拠の収集を治療と並行してできる限り進めます。
証拠と医師による診断が出揃ったら、相手方へ損害賠償請求を行います。
相手方の保険会社と示談交渉し、過失割合などをもとに損害賠償金額を算定します。
無事合意に至れば、相手方保険会社を通じて被害者に損害賠償金が支払われます、
ただ、非接触事故に関しては、因果関係の有無が争点となり当事者間では合意が難しいのも実情です。
その場合は、交通事故紛争処理センター(ADR)や弁護士に相談し、解決の糸口を探すことをおすすめします。
代表的な非接触事故の相手方への損害賠償請求費目には、以下のようなものがあります。
この他の費用についても請求が可能な場合があります。
| 傷害に関する費目 | 治療関係費 |
| 休業損害(働けなかった分の減収補償) | |
| 入院雑費 | |
| 通院交通費 | |
| 慰謝料(ケガをしたことの精神的苦痛に対する補償) | |
| 後遺障害に関する費目 | 逸失利益(生涯減収の補償) |
| 慰謝料(後遺障害を負ったことの精神的苦痛に対する補償) | |
| 物損に関する費目 | 車両の修理費用 |
| 代車費用 |
過失割合とは、交通事故を引き起こした責任が、加害者・被害者間でそれぞれどの程度あったかを示す割合のことをいいます。
交通事故の発生原因や事故の被害拡大について、被害者に過失があると認められると、その過失割合に応じて、加害者が支払う損害賠償額が減額されるという仕組みです。
交通事故の基本的な過失割合は、判例の蓄積から一定の基準が定められています。
しかし、非接触事故については、事故の重大な要素として「被害者の回避行動」を含むため、状況に合わせて類型化された過失割合に修正を加えることが一般的です。
非接触事故では、特に被害者の過失割合がキーポイントとなり、「危険行為を避けるためにした被害者の行動が適切で、やむを得ないものであったかどうか」という視点で被害者の回避行動が評価されます。
加害者側が、被害者の回避行動が不適切であり事故の被害を拡大させた旨の主張をし、賠償額の軽減を試みることも多いです。
そのため、非接触事故の被害者は、収集した証拠等をもとに、以下の両方を証明することが求められることになります。
以下の書籍は、判例の蓄積から、交通事故の過失割合基準をまとめています。
過失割合基準について調べたい時に参考にされるとよいでしょう。
非接触事故の場合、善意悪意を問わず、加害者が立ち去ってしまうという事態が考えられます。
たとえ非接触であっても、損害が発生しているにも関わらず加害者が立ち去った場合は、ひき逃げ・当て逃げに該当します。
被害者の方は泣き寝入りせず、毅然とした態度で下記に挙げる措置をとることをおすすめします。
非接触事故で相手方の立ち去りにあいそうになった場合、最低限相手の車の車種とナンバーを記録し、警察に伝えられるようにしましょう。
被害にあった際車に乗っていて、ドライブレコーダーの映像がある場合には、映像も合わせて提出できればなおよいです。
ドライブレコーダーを搭載していなかった場合や、歩行者であったため記録しているものが何もない場合でも、交通事故現場周辺の防犯カメラの映像を参照することで、相手方の情報が得られる場合があります。
できる限りの策を講じ、立ち去った加害者の特定を目指すことが大切です。
もし事故現場の目撃者がいた場合は、連絡先を交換してもらい、示談交渉や捜査への協力を依頼しておきます。
必要に応じて、目撃者からも証拠を提供してもらう可能性等をあわせて伝えておけるとなおよいです。
立ち去った加害者が見つかるまでの間も、ケガの治療費や車の修理代など、費用が発生する場合があります。
その場合は、自身の加入している保険を活用することを検討しましょう。
たとえば自動車保険の人身傷害保険は、治療費や休業損害の補償を受け取ることができますし、無保険車傷害保険は、相手方が無保険や不明であるときに、補償を受けることができるものとして知られています。
非接触事故でも自身の加入している保険が活用可能かどうか、早めに保険会社とコンタクトをとり確認しておくことで、安心感にも繋がります。
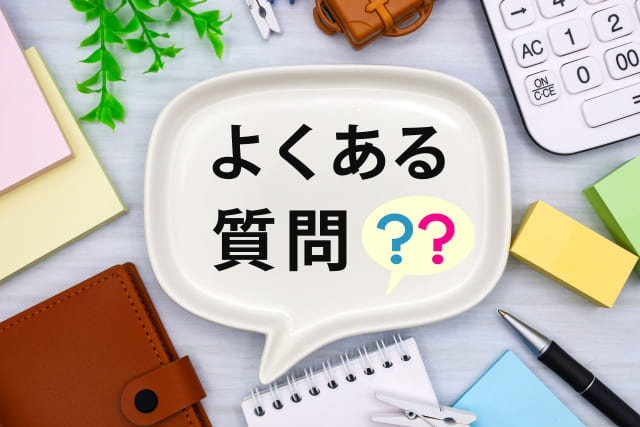
非接触事故は、通常の事故と比べても特殊な点が多いです。
ここでは、非接触事故に関してよくある質問を取り上げますので、皆さんの疑問解決の一助となれば幸いです。
非接触事故では、ケガをしていなくても、物損について損害賠償請求をすることができます。
ただ、物損についても、加害者の危険行為との因果関係が重要になるほか、物損が避けられない状況であったことの証明が必要となります。
しっかりと証拠保全をすることが大切です。
非接触事故は接触事故と比べ、相手方から「言いがかりだ」「自分のせいではなく、被害者が勝手に転倒しただけ」などと主張される可能性も高くなります。
この場合、「加害車両の運行が予測を裏切るような常軌を逸したもの」(最高裁判所判例 昭和47年5月30日)であったことを証明することが求められます。
加害車両の運転の危険性を証明するには、ドライブレコーダーや防犯カメラの映像資料、目撃者の証言など、裏付けるための証拠の保全が鍵になります。
事故に遭った際は気持ちが焦りがちですが、落ち着いて必要な対処を着実にしておくことが重要です。
また、加害者の運転の危険性や、被害者の回避措置の妥当性を証明するのは一般の交通事故と比べても難しいと言えます。
できるだけ早く専門知識を持った弁護士などに相談をし、アドバイスを受けることをおすすめします。
「後になって警察から連絡が来るのではないか…」と不安に思っている方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、非接触事故が起きた当時に当事者双方が警察へ連絡を入れ、事故扱いとしない形で終結していた場合、後から連絡が来る可能性は低いでしょう。
心配しすぎず、もし連絡があった際には警察の指示に従って対応すれば問題ありません。
反対に、相手方のみが警察へ連絡していた場合や、そもそも自分が非接触事故が起こったことに気が付いていなかった場合は、ひき逃げ・当て逃げの疑いで警察から連絡が来ることも考えられます。
ひき逃げ・当て逃げに該当しないことは、自身で証拠の提示をもって証明する必要があります。
もし上記に該当する心当たりがある場合は、以下のように警察の指示に応じて、真摯に捜査に協力することをおすすめします。
非接触事故では、加害者と被害者が直接接触していなくても損害賠償請求をすることが可能です。
通常の交通事故にも増して、加害者による危険行為と被害者の受けた損害の間の因果関係が問われるほか、被害者の過失割合が争点となることが考えられます。
そのため、非接触事故においては、何よりも証拠の保全が賠償請求や保険金請求時の鍵となります。
事故に遭わないよう注意を払って過ごすのは勿論のこと、万が一非接触事故に遭ってしまった際には、ぜひこの記事で解説した内容を思い出し、落ち着いて対処してください。

