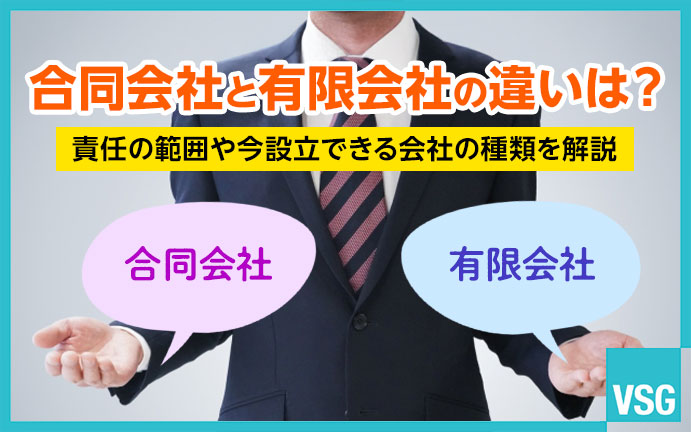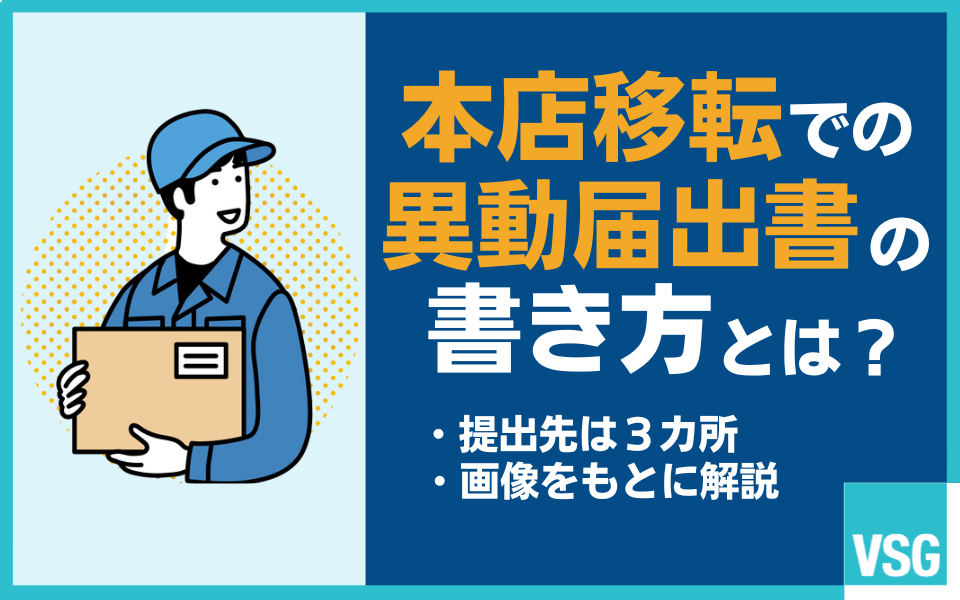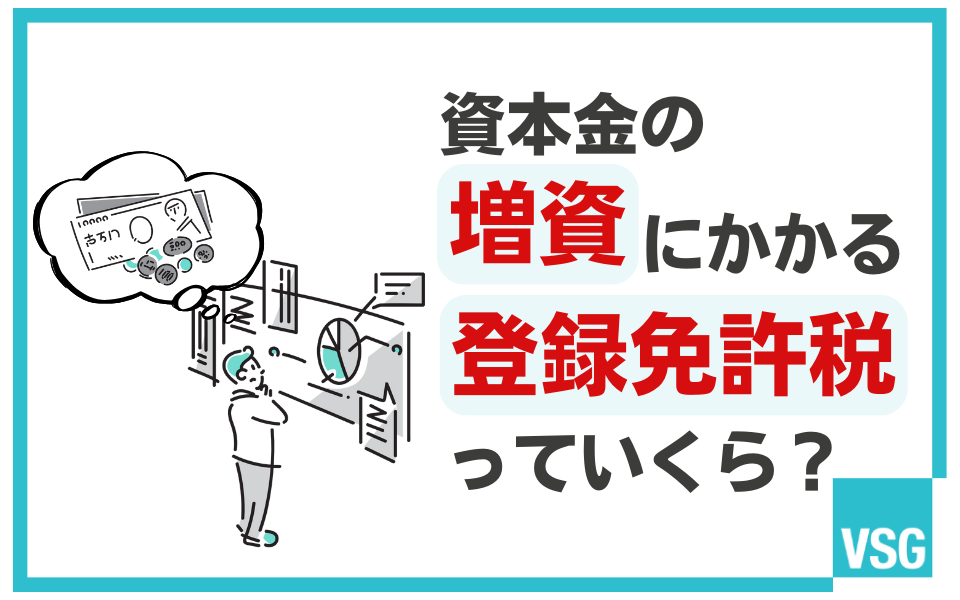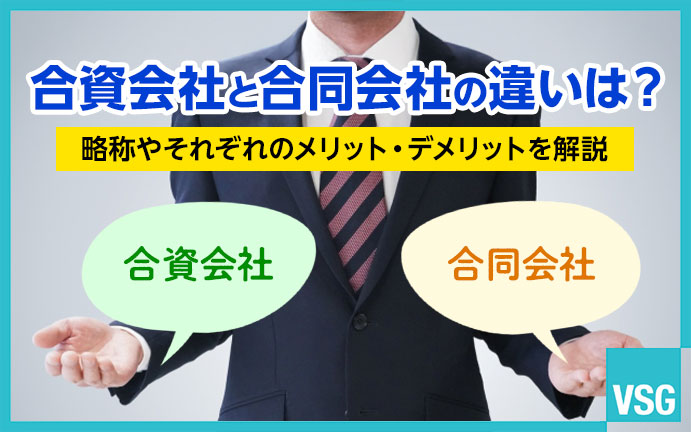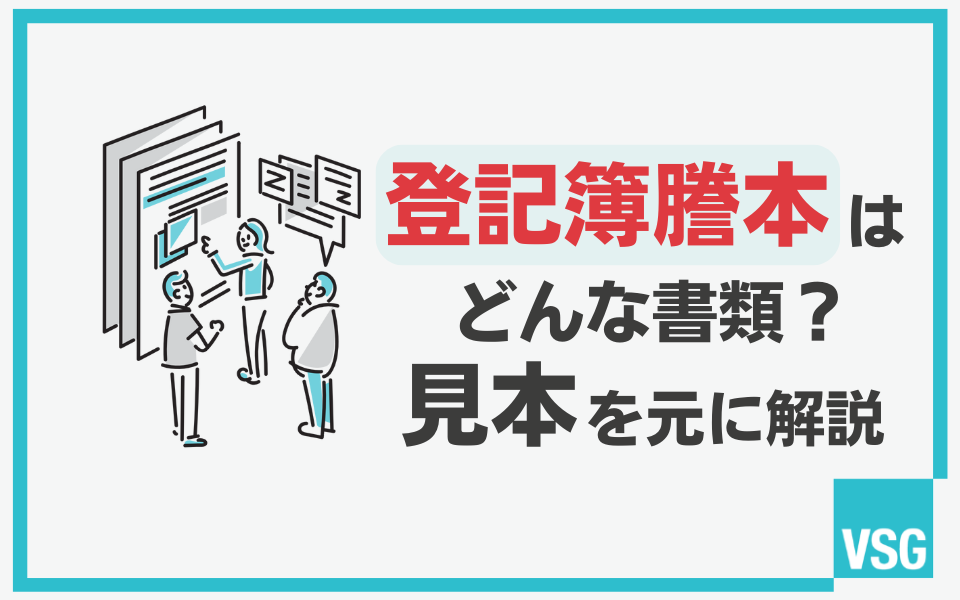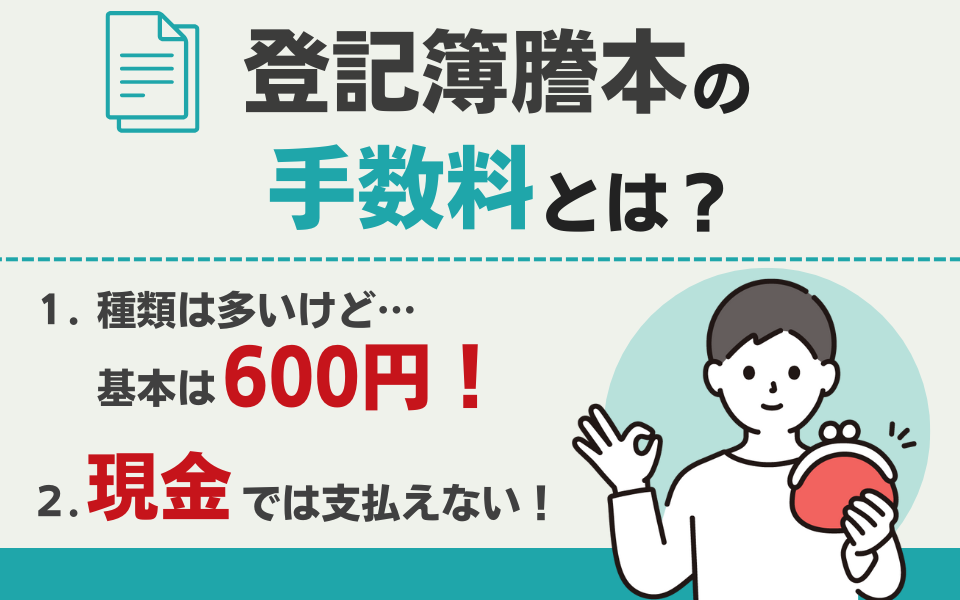最終更新日:2025/3/26
代表権のない取締役とは?権限や責任、注意点を徹底解説

ベンチャーサポート税理士法人 大阪オフィス代表税理士。
近畿税理士会 北支部所属(登録番号:121535)
1977年生まれ、奈良県奈良市出身。
起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネルを運営。
PROFILE:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_writing/#p-mori
YouTube:会社設立サポートチャンネル【税理士 森健太郎】
書籍:プロが教える! 失敗しない起業・会社設立のすべて (COSMIC MOOK) ムック
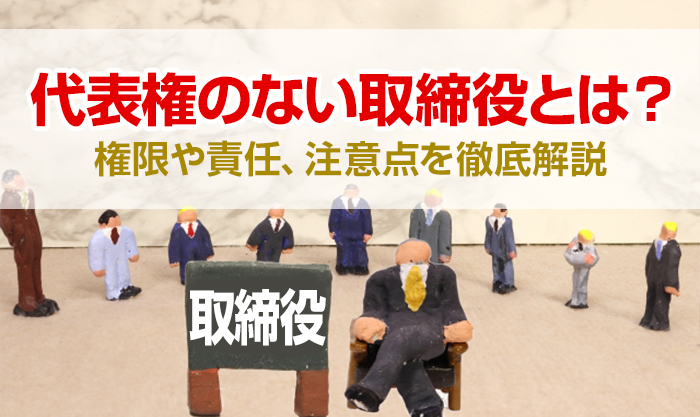
この記事でわかること
- 代表権のない取締役の会社法上の定義
- 代表権のない取締役が存在するケース
- 代表権のない取締役の権限範囲(できること・できないこと)
- 代表権のない取締役の責任
- 代表権のない取締役の注意点
株式会社の設立や従業員の取締役昇任のほか、売買・賃貸借などの取引においても代表権のない取締役が問題になることがあります。
企業経営におけるガバナンスへの意識が高まっているなか、代表権のない取締役の権限や責任、注意点の把握は欠かせません。
実際、代表権のない取締役について理解が不十分であったために、取引先からの信用を失い、損害賠償責任を負うことになった事例もあります。
この記事では、代表権のない取締役の権限や責任、注意点について詳しく解説します。会社経営者や株主のほか、これから取締役に就任する方は、ぜひ最後までご覧ください。


目次
代表権のない取締役とは?
代表権のない取締役とは、代表取締役など株式会社の代表者を定めた場合に存在する、代表権を有しない取締役のことです。
法律上、取締役の各自は、本来的に株式会社を代表します。しかし、定款や定款の定めに基づく取締役の互選、株主総会の決議によって代表者を定めると、代表者以外の取締役は代表する権限を喪失し、定めた代表者(代表取締役)のみが代表する権限を有します(会社法 第349条)。
- (株式会社の代表)
第三百四十九条 取締役は、株式会社を代表する。ただし、他に代表取締役その他株式会社を代表する者を定めた場合は、この限りでない。 - 2 前項本文の取締役が二人以上ある場合には、取締役は、各自、株式会社を代表する。
- 3 株式会社(取締役会設置会社を除く。)は、定款、定款の定めに基づく取締役の互選又は株主総会の決議によって、取締役の中から代表取締役を定めることができる。
- 4 代表取締役は、株式会社の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
- 5 前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
- 引用:会社法 第三百四十九条|e-Gov 法令検索
そのため、代表権のない取締役は、代表取締役以外の取締役です。
代表権のない取締役は、業務執行権限はあるものの、代表権がないために契約締結など対外的な法律行為を有効に行うことはできません。
代表権のない取締役と代表権のある取締役(代表取締役)の違いなどについてより深く理解するためには、代表権や取締役それぞれの意味合いも把握しなければなりません。
ここからは、そもそも取締役とはどのような存在なのか、代表権とは何かについて解説します。
取締役
取締役とは、株主総会の決議によって選任される、株式会社に必ず置かれる機関(会社法 第326条 第1項)です。
- (株主総会以外の機関の設置)
第三百二十六条 株式会社には、一人又は二人以上の取締役を置かなければならない。 - 引用:会社法 第三百二十六条 第一項|e-Gov 法令検索
取締役の基本的な職務内容は、業務執行の意思決定です。その内容は多岐にわたりますが、特に重要なものとして経営方針や事業計画の決定、リスク管理体制の整備・構築など、会社経営の重要事項を決定する役割を担っています。
具体的な意思決定の方法は、取締役会の有無に応じて以下のとおりです(会社法 第348条 第2項、第362条 第2項)。
| 取締役会の有無 | 意思決定の方法 |
|---|---|
| 取締役会を置いていない | 定款に別段の定めがある場合を除いて取締役の過半数 |
| 取締役会を置いている (取締役会設置会社) |
取締役会の決議 |
上記のほか、取締役の権限や責任の詳細については後述しています。
代表権
代表権とは、株式会社などに権利義務を帰属させる行為(法律行為)や、原告あるいは被告としての株式会社に訴訟法上の効果を帰属させる行為(訴訟行為)を、有効にすることができる権限です。
会社法 第349条 第4項における裁判外の行為がいわゆる法律行為、同項の裁判上の行為はいわゆる訴訟行為に該当します。
- 4 代表取締役は、株式会社の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
- 引用:会社法 第三百四十九条 第四項|e-Gov 法令検索
株式会社などの法人は実体としての存在がないため、契約締結などの法律行為や、訴えや主張などの訴訟行為を自ら行うことができません。
実体がない株式会社では、代表権を有する者(代表者)が契約締結などの法律行為(裁判外の行為)をすることで、株式会社にその契約上の権利義務(法律効果)が帰属することとなります。
反対に、代表権がない取締役が契約締結などの法律行為(裁判外の行為)をしても、後述する第三者を保護するためのルール(表見代表取締役)などの適用がない限り、株式会社にその契約上の権利義務(法律効果)は帰属しません。
代表権のない取締役が存在するケース
代表権のない取締役が存在するケースは、以下のとおりです。
- 代表取締役を定めた
- 指名委員会等設置会社とした
ただし、上記のケースであっても、取締役の全員に代表権がある可能性もゼロではありません。あくまでも代表権のない取締役が存在する一般的なケースとして参考にしてください。
ここからは、上記のケースで代表権のない取締役が存在する理由を紹介します。
代表取締役を定めた
代表取締役を定めると、他の取締役については株式会社を代表する権限は失われます(会社法 第349条 第1項 但書)。
なお、取締役会設置会社の取締役は3人以上必要(会社法 第331条 第5項)で、かつ代表取締役の選定義務(会社法 第362条 第3項)があります。したがって、取締役の全員を代表取締役とする場合を除き、代表取締役ではない取締役に代表権はありません。
なお、代表取締役は必ず1人にすべきというものではなく、定款で代表取締役の員数を2人などと定めることができます(会社法 第351条 第1項)。
代表取締役が複数人である株式会社の具体例として、JR東海の代表取締役の員数は6人です。
指名委員会等設置会社とした
指名委員会等設置会社では、株式会社の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代表執行役を必ず選定するため、取締役に代表権はありません。
もっとも、取締役と執行役は兼任が可能であるため、例えば取締役兼代表執行役であれば、間接的ではあるものの代表権のある取締役といえます。
取締役兼代表執行役を置く会社の実例として、株式会社ゆうちょ銀行などがあります。
指名委員会等設置会社とは、指名委員会、監査委員会、報酬委員会といった3つの委員会を置く会社のことです(会社法 第2条 第1項 第12号)。3つの委員会には経営監督機能があり、業務の執行は取締役ではなく執行役が行う(会社法 第415条、会社法 第418条)といった特徴があります。
代表権のない取締役の権限範囲
代表権のない取締役の権限範囲、すなわち何ができて何ができないかのポイントは以下のとおりです。
- 原則として契約締結などの対外行為はできない
- 重要な経営判断に関与できる
- 株式会社の業務を執行できる
代表権のない取締役でも、重要な経営判断など、会社の業務に関する意思決定に関与することはできます。しかし、売買や賃貸借といった対外的な業務の実行権限は、原則として制限されています。
原則として契約締結などの対外行為はできない
前述のとおり、代表権のない取締役は代表権がないことから、原則として契約締結などの対外行為はできません。
ただし、すべての契約締結に代表取締役が関与すると、効率面で問題が生じるおそれがあります。
そのため、実務上は代表権のない取締役にも契約締結権限を付与するといった対応をとるケースも少なくありません。詳細は後述しているので、参考にしてください。
重要な経営判断に関与する
代表権がなくても、取締役である限り、原則として株式会社の重要な経営判断に関与します。会社法の規定は以下のとおりです。
- (業務の執行)
第三百四十八条 取締役は、定款に別段の定めがある場合を除き、株式会社(取締役会設置会社を除く。以下この条において同じ。)の業務を執行する。 - 2 取締役が二人以上ある場合には、株式会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数をもって決定する。
- 引用:会社法 第三百四十八条|e-Gov 法令検索
- 2 取締役会は、次に掲げる職務を行う。
- 一 取締役会設置会社の業務執行の決定
- 二 取締役の職務の執行の監督
- 三 代表取締役の選定及び解職
- 引用:会社法 第三百六十二条第ニ項|e-Gov 法令検索
もっとも、取締役が常に単独で業務執行の決定を行えるわけではありません。
代表権のない取締役がいる状態は取締役が2人以上いる場合に該当するのが一般的であるため、各取締役は議決権を行使し、取締役という機関の意思決定に関与します。
業務執行の決定とは、以下の内容を含むさまざまな事項についての意思決定です。
- 重要な人事戦略
- 重要な拠点戦略
- 重要な取引(金融・信用取引を含む)の締結
- ガバナンス確保
- 事業運営にかかるリスクマネジメント
- 経営改善・効率化に関する戦略
代表取締役でなくても、取締役は経営者・経営幹部として重要な経営判断に関与する大切な役割を担っています。
取締役(会)が決定した事項を執行する
会社によって異なりますが、代表権のない取締役が業務を執行する役割を担うことがあります。具体的には、予算の編成や帳簿作成などの業務です。
代表権のない取締役は、原則として売買や賃貸借といった対外的な取引行為はできません。
ただし、取締役会設置会社における取締役会の決議で業務執行取締役と選定された場合などは、代表権のない取締役でも対外的な行為を実行することがあります。
なお、取締役会を置いていない株式会社では、あえて代表取締役を定めない限りすべての取締役に代表権があり、また、定款に別段の定めがない限り、すべての取締役に業務執行権限があります。
代表権のない取締役の責任
代表権のない取締役にも、法律上、以下の義務・責任があります。
- 善管注意義務
- 報告義務
- 忠実義務
- 任務懈怠責任
- 対第三者責任
取締役は、代表権がなくても、株式会社の利益を損なわないよう注意して職務を行う義務があり、この義務を怠った場合には株式会社に対して損害賠償責任を負います。
したがって、取締役としての職務について必要な注意が欠けていれば、結果として引き起こした株式会社の赤字や不祥事などについて、代表権のない取締役が損害賠償責任を負う可能性もゼロではありません。
善管注意義務
代表権のない取締役の善管注意義務とは、株式会社(株主)からの委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって職務を行うべき義務です(会社法 第330条、民法 第644条)。
委任によって、取締役には株式会社のさまざまな事項の処理を担う権限が与えられます。取締役は、株式会社の経営を赤字にする、不祥事を起こすなど、株式会社の利益や価値をそのつもりがあってもなくても損なうことができる地位です。
当然、株式会社と取締役との委任関係は、不祥事や赤字経営でも構わないから経営を任せるといった趣旨ではありません。
善管注意義務は、経営を任された取締役が、委任者である株式会社(株主)の利益や価値を損なわないように注意して職務を行う義務があることを意味します。そしてその注意の程度を抽象的・規範的・概念的に定める意義もあります。
善管注意義務違反は、取締役が法令や定款に違反した場合に該当し、取締役として通常要求される注意力を基準に判断されます。
具体的には、株式会社の利益や価値を損なわないために必要な情報を収集したか、収集した情報に基づく判断・行為が不合理といえないかなどが判断基準です。
報告義務
代表権のない取締役の報告義務とは、株式会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは直ちに、委任者からの請求があるときは遅滞なく状況を報告しなければならない義務です(会社法 第330条、民法 第645条、会社法 第357条)。
取締役は株式会社という他人の事務を処理しているため、委任者である株式会社や選任者である株主に処理状況を報告しなければなりません。
また、報告対象となる株式会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実には、他の取締役の不正・不合理な職務も含まれると考えられています。したがって、他の取締役の職務の監督も取締役の職務に含まれます。
忠実義務
代表権のない取締役の忠実義務とは、法令、定款、株主総会の決議を遵守し、株式会社のため忠実にその職務を行わなければならないという義務です(会社法 第355条)。
善管注意義務は委任に伴う義務として民法が定めていますが、忠実義務は会社法が定めています。
善管注意義務と忠実義務はまったく別個の義務ではなく、善管注意義務をより具体的・注意的に定めたものが忠実義務という考え方が一般的です。
善管注意義務だけでは法令、定款、株式会社の決議を遵守し、株式会社のために職務を行うことは明確にされていませんが、忠実義務によって明確となりました。
任務懈怠責任
代表権のない取締役の任務懈怠(けたい)責任とは、その取締役が自己の任務を怠ったときは、株式会社に対し任務懈怠によって生じた損害を賠償する責任です(会社法 第423条 第1項)。
前述した善管注意義務や報告義務、忠実義務の違反は任務懈怠とされ、取締役はその責任を追及されます。
取締役に義務を課すことで、株式会社の利益や価値を保護し、義務違反で損害が生じた場合は事後的・個別的に賠償による回復を図るといった考え方です。
対第三者責任
代表権のない取締役の対第三者責任とは、職務について悪意または重大な過失があったときは、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任です(会社法 第429条)。
株式会社の活動は取締役の職務執行に依るところが大きい点を考慮して、第三者を特別に保護するため、取締役を含む役員の第三者損害賠償責任が特に定められました。
取締役の立場では、職務について悪意または重大な過失があれば、株式会社だけでなく、第三者に生じた損害についても責任が及ぶこととなります。
第三者の立場では、株式会社だけでなく、職務について悪意または重大な過失がある取締役にも責任の追及が可能です。
代表権のない取締役に関する注意点と対策
代表権のない取締役に関する注意点は、以下のとおりです。
- 登記義務がある
- 委任がなければ契約・押印ができない
- 肩書きで契約が有効になる場合がある
- 決算書を見る権限がある
- 給与の損金算入について制限が厳しい
- 割増賃金が適用されない
ここからは、各注意点の詳細と対策を解説します。
登記義務がある
取締役の氏名は、株式会社の設立登記における登記事項(会社法 第911条 第3項 第13号)であり、変更の登記をする義務(会社法 第915条)もあります。
登記申請では、添付書類として臨時株主総会議事録や株主リスト、就任承諾書などが必要です。
登記申請にかかる登録免許税の額は、資本金の額が1億円を超える場合は3万円、1億円以下の場合は1万円です。
代表権のない取締役も対象であるため、登記義務に違反しないよう注意してください。
委任がなければ契約・押印ができない
代表権のない取締役は、代表権がないことから、原則として株式会社のために対外的な契約手続きを行い、有効とすることはできません。
ただし、規模が大きくなるほど、株式会社のすべての契約手続きを代表者が対応すると、円滑な取引をするうえで問題が生じます。
そこで、代表権のない取締役にも対外的な契約締結権限を与えるために、取締役会の決議や代表取締役の委任により、契約締結権限を与えるといった対応がとられます。
肩書きで契約が有効になる場合がある
代表権のない取締役は原則として契約手続きを有効にできませんが、例外的に契約が有効になる場合があります。
表見代表取締役制度は、その例外の1つです。
- (表見代表取締役)
第三百五十四条 株式会社は、代表取締役以外の取締役に社長、副社長その他株式会社を代表する権限を有するものと認められる名称を付した場合には、当該取締役がした行為について、善意の第三者に対してその責任を負う。 - 引用:会社法第三百五十四条|e-Gov 法令検索
例えば、株式会社が代表取締役以外の取締役に副社長の肩書きを与えている場合、その副社長が締結した契約は実質的に有効となります。
そもそも、取引相手の立場では取引相手の取締役に代表権があるかどうかを直ちに把握することは困難です。
代表者事項証明書の取得で代表取締役の氏名などは確認できますが、実際には証明書に記載されていない代表取締役以外の取締役が契約締結権限を有している場合もあります。
とはいえ、取引先の取締役に対して代表取締役からの委任状や取締役会議事録を見せてほしいといったやり取りをすることも現実的ではないでしょう。
表見代表取締役は、取引における権限調査について過大な負担を要求せず、外観の信頼を保護することにより、円滑かつ安定した取引を図る制度です。
安易に名称(肩書き)の使用を認めていると、背信的な取締役があえて株式会社にとって不利益な契約を締結する可能性もゼロではありません。
代表権のない取締役は、その肩書き次第で、実質的に代表権を行使できる結果となる可能性があるため注意が必要です。
決算書を見る権限がある
代表権がない取締役でも、取締役である限り、その職務の内容として決算書を見ることができます。
また、取締役会設置会社においては、決算書について取締役会の承認を受けなければなりません(会社法 第436条 第3項)。
従業員を代表権のない取締役とする場合は、その取締役に決算書を見られる可能性がある点に注意が必要です。
給与の損金算入について制限が厳しい
取締役に支払う給与は、従業員に支払う給与に比べて、税法上の損金算入について厳しい制限があります。
基本的に、1ヶ月以下の一定期間ごとに支給する給与は、事業年度内で同額にしなければなりません(定期同額給与)。この定期給与額の改定は、原則として事業年度の期首から3ヶ月以内に限られています。
また、賞与を支給する場合は、事前に税務署に届出をした内容にしなければなりません(事前確定届出給与)。
上記のほか、損金算入が認められるものとして業績連動型給与があります。
使用人兼取締役とする場合など、従業員を代表権のない取締役とする際は税務上の問題も少なくありません。詳しくは税理士にご相談ください。
割増賃金が適用されない
取締役は原則として労働法上の労働者に該当しないため、会社には従業員と同様に割増賃金を支払う義務がありません。
いわゆる残業や休日出勤をしても通常は給与に影響しないため、新たに就任する取締役にはその旨を理解してもらう必要があります。
代表権のない取締役に関する質問(FAQ)
ここでは、代表権のない取締役に関する質問について、回答をまとめます。
取締役に代表権はありますか?
代表取締役には原則として代表権がありますが、制限がかけられている場合もあります。また、代表取締役以外の取締役については、授権の有無やその内容によって異なります。
代表取締役を定めた場合、原則、代表取締役以外の取締役には代表権がありません。
ただし、代表取締役の代表権の内容が制限されているケースもあります(会社法 第349条 第5項)。
また、代表取締役の委任や取締役会の決議で、代表権の内容を代表取締役以外の取締役に個別に授権することは可能です。
代表権の確認方法は?
株式会社の代表者を確認する方法として、登記事項証明書の一種である代表者事項証明書を取得する方法があります。
ただし、代表者事項証明書だけでは、代表権を持たない取締役が個別に契約締結等の権限を与えられているかどうかを確認することはできません。
会社内部でされる個別の授権の内容は、委任状や取締役会議事録などの内部資料で確認する必要があります。
代表取締役は1人でも2人でもいいですか?
代表取締役の人数(員数)は、1人に限らず、2人や3人など複数人とすることができます(会社法 第351条 第1項)。
代表権はどうやってなくしますか?
取締役会を置いていない株式会社では、代表取締役を定めることにより、他の取締役は代表権を喪失します(会社法 第349条 第1項 但書)。
また、株主総会の決議による(代表)取締役の解任(会社法 第339条 第1項)や任期満了による退任、辞任の後で新任者が就任した場合(会社法 第346条 第1項、第351条 第1項)も代表権の喪失事由です。
また、代表取締役からの委任や取締役会決議による授権については、その委任の解除や決議の変更も代表権喪失事由といえるでしょう。
代表権のない取締役に関する疑問点は専門家に相談しよう
委任や取締役会の決議による授権などがない限り、代表取締役以外の取締役に代表権はありません。
ただし、代表権のない取締役でも、株式会社が「社長」や「副社長」など代表権があると認められる肩書きの使用を認めている場合は、第三者保護の規定(表見代表取締役)により契約が有効とされるなど、実質的に代表権があるのと同等の結果となる場合があります。
さらに、任務懈怠責任や対第三者損害賠償責任を負う可能性があるなど、取締役としての責任は軽いものではありません。給与の損金算入にかかる制限や割増賃金の適用対象外など、税法や労働法に関しても注意が必要です。
この記事で挙げた内容の他にも、代表権のない取締役については多くの注意点があります。会社設立時や従業員の取締役昇任時などは、ぜひ専門家の協力を得ることも検討してください。