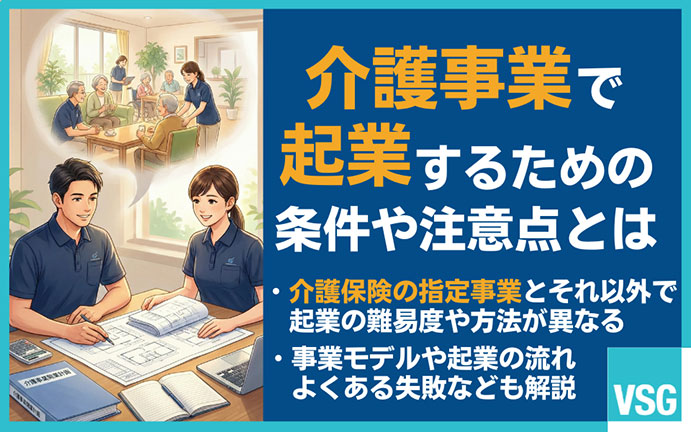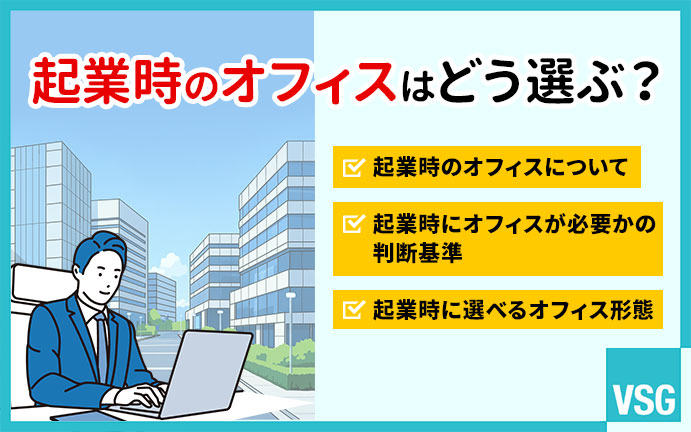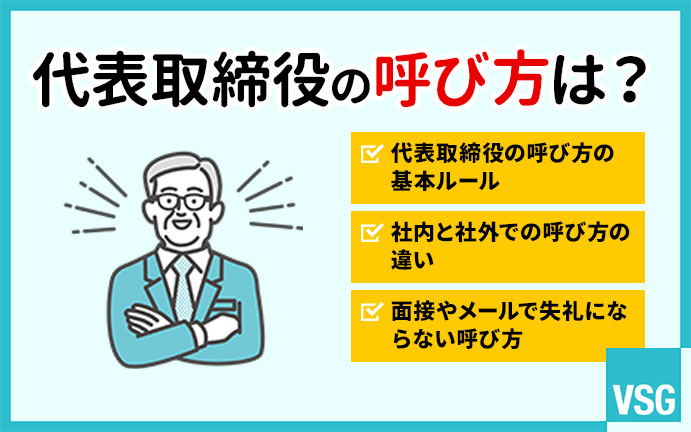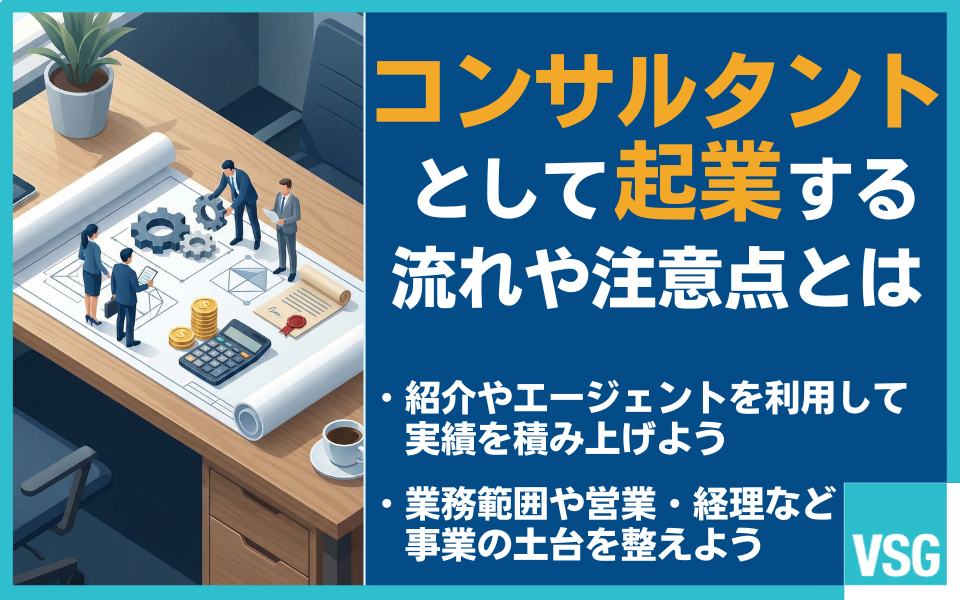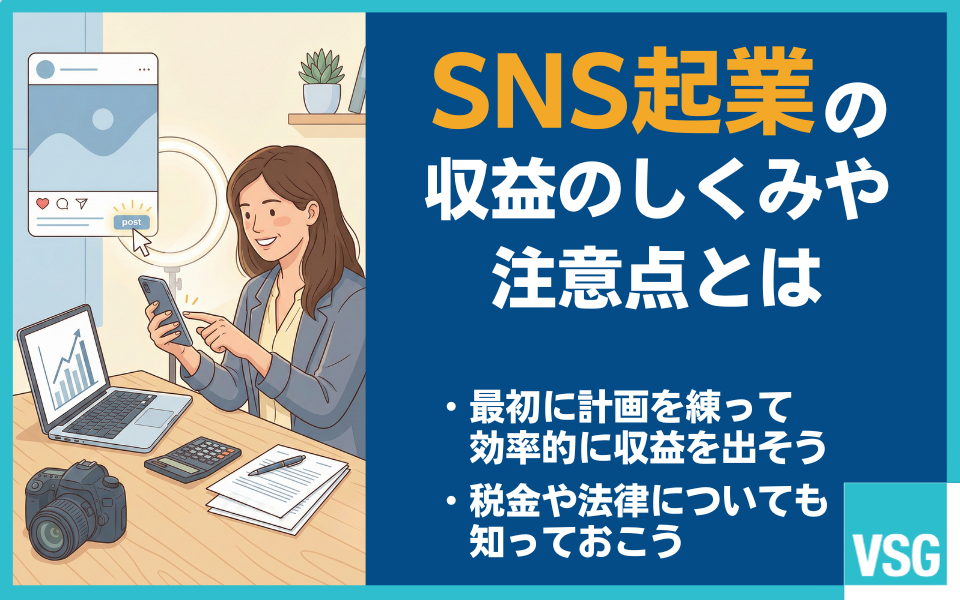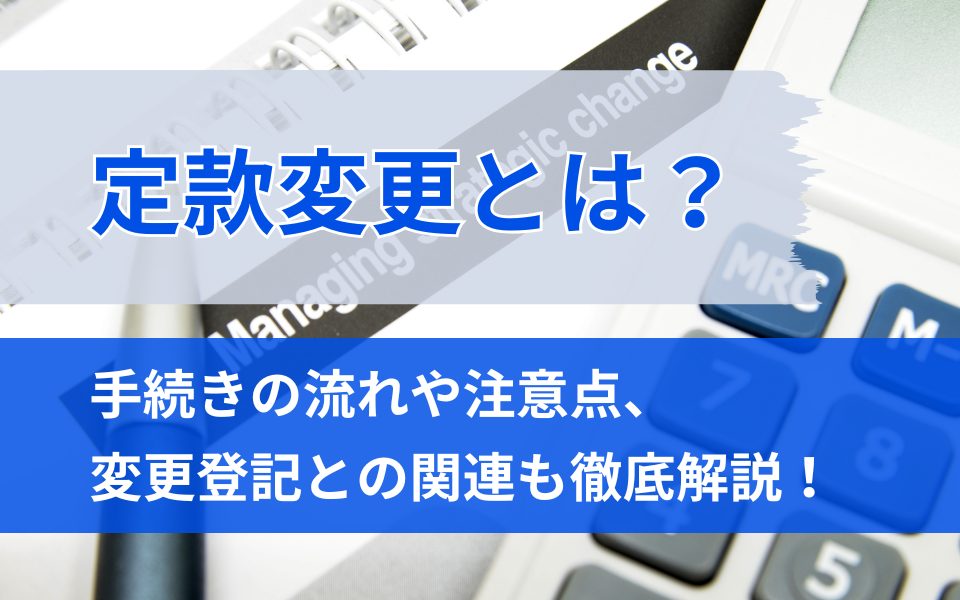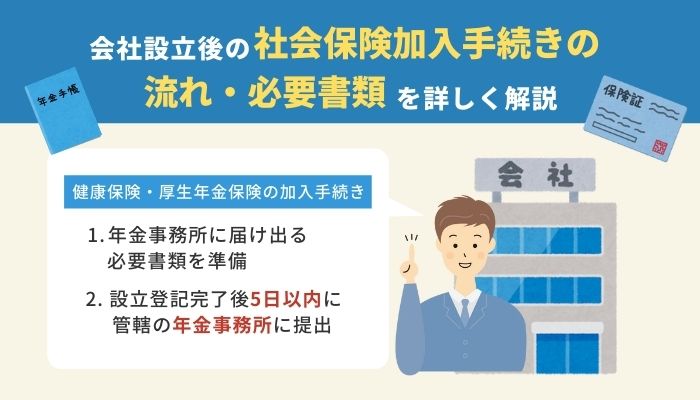最終更新日:2025/11/25
【役員報酬0円】合法性・社会保険・融資への影響から総額最小を実現する最適解

ベンチャーサポート税理士法人 大阪オフィス代表税理士。
近畿税理士会 北支部所属(登録番号:121535)
1977年生まれ、奈良県奈良市出身。
起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネルを運営。
PROFILE:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_writing/#p-mori
YouTube:会社設立サポートチャンネル【税理士 森健太郎】
書籍:プロが教える! 失敗しない起業・会社設立のすべて (COSMIC MOOK) ムック
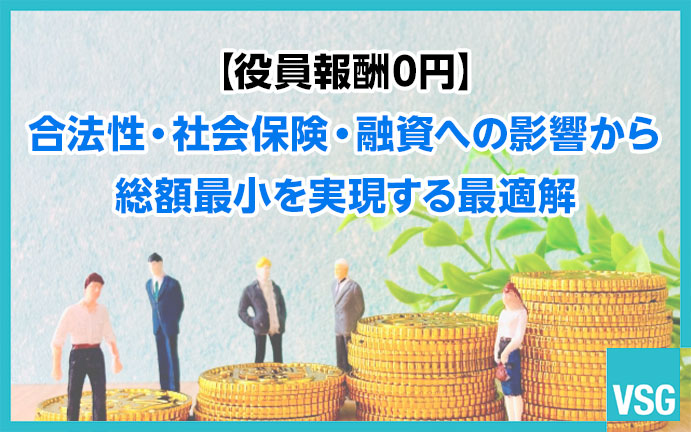
この記事でわかること
- 役員報酬0円が税金・融資・社保に与える影響
- 総額最小を実現する最適な報酬額
- 役員報酬0円の手続きと注意点
会社設立を控え、資金繰りを最優先に考える方は、「役員報酬0円」を選択肢に入れているはずです。
「報酬をゼロにすれば、社会保険料の会社負担分(標準報酬月額50万円の場合、年間約104万円)が節約できる。個人も保険料を払わなくて済む」という判断は、設立直後の資金確保には合理的です。
しかし、この選択は税務・社会保険・融資の三方面で、設立直後の会社にとって致命的なリスクを内包します。
多くの社長が見落としがちなのが、役員報酬を経費から外した結果、法人税が増加し、トータルで税・社保の総額負担が大きくなる可能性がある点です。また、報酬がないことで、日本政策金融公庫などの金融機関から「経営者家計の不安定さ」を指摘され、融資審査で不利になる現実もあります。
この記事では、会社設立を考えている人の不安に対し、国税庁・日本年金機構の公式見解に基づいた最適解を探っていきます。


目次
役員報酬0円の結論と4大リスク
役員報酬を0円に設定すること自体は可能です。
しかし、資金繰りが楽になる半面、この選択は税務上の優遇措置の喪失や社会保障、そして将来の融資審査において、長期的なリスクを伴います。将来的に会社と個人にどのような影響をもたらすのか確認していきましょう。
1. 役員報酬0円は「合法」か?
結論としては、株式会社か合同会社かを問わず、役員報酬を0円(無報酬)にすることは、会社法上も税務上も合法であり、可能です。
役員の給料は、従業員の給料とは異なり、株主総会などの会議で自由に決められます。そのため、「今期は0円にする」と決定すること自体は問題ありません。
ただし、一度決めた役員報酬の額は、「事業年度開始から3か月以内」という税務署のルールに従って管理しなければなりません。このルールを破ると、後で税金が増えることになります。
2. 最重要チェック!役員報酬0円の4大リスクと対応策
役員報酬0円は、一時的に会社の資金流出を防ぎますが、後で年間数十万円単位の損や会社の信用低下を招く4つの大きな問題を抱えています。
- 税金が増える
- 社会保険(社保)に入れない
- 銀行融資が難しくなる
- 手続きを間違える
以下の表でリスクと対策を把握してください。
| リスク | 具体的な問題点 | 対策 |
|---|---|---|
| 税金が増える | 「節税」のつもりが、会社の法人税が予想以上に増えてしまい、個人と会社の税金・保険料の合計額(総額)が高くなる。 | 月額10万円など、低額で設定することが総額最小の最適解です(詳細後述) |
| 社会保険(社保)に入れない | 無報酬役員のみの法人は、社会保険の適用事業所として認められず、役員が健康保険・厚生年金保険に加入できない。結果、傷病手当金などの補償を失う。 | 最低報酬(58,000円)で加入するか、国民健康保険料の翌年負担を資金計画に織り込む。 |
| 銀行融資が難しくなる | 銀行や日本政策金融公庫から「社長の生活は安定しているのか?」と疑われ、融資の審査で不利になることがある。 | 配偶者の収入証明や個人預金残高(目安は240万円以上)で、家計の安定性を証明する。 |
| 手続きを間違える | 報酬を変える際、「事業年度開始から3か月以内」という税務署のルール(3か月ルール)を守らないと、増やした分が全額経費として認められない。 | 設立直後に報酬額を決定し、株主総会議事録を必ず作成し保管する。 |
役員報酬0円の是非と総額負担の真実:税務・社保における0円の可否
役員報酬の決定には、「いつまでに」「どう決めるか」というルールに加え、「税金」と「社会保険料」の総額負担を最も抑えられる金額を見極めることが極めて重要です。
ここでは、法人税、個人税、そして社会保険料の3つの観点から例をあげて説明していきます。
1. 役員報酬0円の「法的可否」と「税務上の原則」
税務上の大原則:「定期同額給与」の要件
役員報酬を会社の経費(損金)として認めてもらうための、税務署の最も大事なルールが「定期同額給与」です。
これは「毎月、決まった同じ額を支給してください」というシンプルなルールです。会社が勝手に利益操作(例えば、「今月は儲かったから役員報酬を増やそう」)をするのを防ぐためにあります。
役員報酬0円は、毎月0円で同じ額ですから、この定期同額給与のルールを満たしており、税務上の問題はありません。
報酬改定の原則:「3か月ルール」の厳格な要件
一度決めた役員報酬(0円を含む)を途中で変更する際に、会社が経費として認めてもらうためには、厳しい期限があります。
その期限が「3か月ルール」です。
役員報酬の額を変更できるのは、原則として事業年度が始まってから3か月以内だけです。
たとえば、4月1日から事業年度が始まる会社の場合、6月30日までに株主総会で新しい報酬額を決め、7月1日から支給を始めなければなりません。この期限を1日でも過ぎて報酬を増やした場合、その増やした額は会社の経費として認められず、法人税が余計にかかってしまいます。


2. 社会保険(社保)の可否判定
役員報酬を0円にする大きな理由の一つが「社会保険料の会社負担分をゼロにしたい」という点です。この点は、日本年金機構が定める適用事業所のルールによって、会社の社保加入の可否が分かれる最も複雑で重要な論点です。
無報酬役員=適用不可の可能性がある(新規適用不可)
法人は原則として社会保険の強制適用事業所ですが、日本年金機構は、「役員報酬が0円」で「他に社会保険に加入する従業員が一人もいない」法人の場合、新規に適用事業所として認めないケースが多数存在します。
0円の代償:国保・国年への加入と補償リスク
役員報酬0円で社会保険に加入できない場合、個人で国民健康保険と国民年金に加入することになります。
この選択には、将来のリスクが伴います。
- 将来の年金受給額の減少
- 高額な国民健康保険料の翌年負担
- 補償の手薄さ(傷病手当金の喪失)
1.将来の年金受給額の減少
厚生年金は国民年金に上乗せされる形で支給されますが、0円では厚生年金の保険料納付額がゼロになるため、その期間の将来の年金受給額が減少します。
2.高額な国民健康保険料の翌年負担
国民健康保険料は、前年の所得に基づいて計算されます。もし会社設立前に高額な給与を得ていた場合、創業期で役員報酬0円でも、翌年は前職の所得をベースにした高額な国民健康保険料の支払いが突然発生し、資金繰りを圧迫します。
3.補償の手薄さ(傷病手当金の喪失)
最も大きな代償は、傷病手当金を失うことです。健康保険・厚生年金保険に加入していれば、病気やケガで働けなくなった場合、給与の約3分の2にあたる金額が最大1年6か月にわたり支給されます。しかし、国民健康保険にはこの手当がないため、万一の際の生活保障がゼロになります。


3.【ケース別年次比較】役員報酬0円の「総額最小」シミュレーション
役員報酬の最適な額は、法人税・個人税・社会保険料(社保)の3つの要素の合計(総額)が最も小さくなる地点です。
創業期(設立から1〜2年目)は、法人税率と個人の所得税率のバランスが変わるため、この総額最小化が特に重要になります。
ここでは、「会社の年間利益が500万円」という一般的な創業期の利益を想定し、報酬額ごとの総額負担を比較します(※概算シミュレーションであり、住民税均等割や特定の控除は含みません)。
- 会社の利益(報酬控除前): 500万円
- 法人税率: 800万円以下の利益に対し約15%で計算
- 個人所得税・住民税: 最低税率(所得税5%+住民税10%)を基に計算
- 社会保険:
- 健康保険・厚生年金保険の最低等級(月額58,000円)で加入した場合:年間約35.8万円(会社負担分を含まない個人負担分)
- 国民健康保険・国民年金(国保・国年):年間約30万円(概算)
| 月額報酬 | 会社利益(報酬控除後) | 法人税の負担額(約15%) | 個人の手取り | 個人が負担する税・社保総額 | 会社と個人の総額負担(年間) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0円 | 500万円 | 75万円 | 0円 | 国保・国年で約30万円 | 105万円 |
| 10万円 | 380万円 | 57万円 | 70万円 | 国保・国年で約18万円 | 75万円 |
| 30万円 | 140万円 | 21万円 | 252万円 | 健保・厚生年金で約71.6万円 | 92.6万円 |
役員報酬を0円にすると、その分会社の利益が増え、法人税が75万円もかかってしまうため、総額負担は105万円と最も高くなります。
最適解は、月額10万円(年間120万円)を支払うことで、法人税を57万円に抑えられ、会社と個人の合計負担が75万円で一番安くなります。
資金繰り優先の創業期は、 役員報酬0円ではなく、月額10万円〜20万円の 「超低額固定」 に設定するほうが、税金・社保の総額が最小になるケースが多いです。
融資・信用と意思決定フレーム:将来を見据えた最適な戦略
次に、銀行や日本政策金融公庫といった外部の視点から見て、信用を損なわないための適切な役員報酬の設定について、確認していきましょう。
銀行・投資家から見た「役員報酬0円」の評価と対策
信用評価の現実:融資に不利になる可能性
日本政策金融公庫などの融資担当者は、会社の事業計画だけでなく、「経営者(社長)の家計が安定しているか」を非常に重要視します。
役員報酬が0円である場合、「社長はどこから生活費を得ているのか?」という疑問が生じ、私的な資金繰りのために公的な融資金を流用するリスクが高いと判断され、融資のマイナス要因となります。
【融資対策パック】融資に耐えるためのチェックリスト
役員報酬を超低額(例:10万円など)または0円に設定している場合でも、以下の具体的な資料を提出し、社長の家計が安定していることを客観的に証明できれば、融資審査を通過する可能性を高められます。
| 対策資料 | 目的と具体的な内容 |
|---|---|
| 家計資金計画書 | 役員報酬以外の資金源を明示します。配偶者の年間所得(例:350万円)や、不動産収入(例:年間120万円)など、報酬なしでも生活できる根拠を提示します。 |
| 他所得の証憑 | 上記の資金源を証明するための配偶者の源泉徴収票や、賃貸借契約書のコピーなど、具体的な書類を提出します。 |
| 預金残高証明書 | 経営者個人の預金口座に、少なくとも1年分の生活費(例:月20万円×12か月で240万円以上)が残っていることを示す、直近3か月分の残高証明を提出します。 |
| 役員貸付金契約書 | 会社設立時に自己資金を会社に貸し付けた場合、その金銭消費貸借契約書を提示することで、会社から資金を引き出す合法的な根拠(役員貸付金の返済)を示します。 |


【意思決定フレーム】自社最適な報酬水準を見つける4つの分析
前述の総額シミュレーションで「月額10万円〜20万円の超低額固定が最適解」と結論付けましたが、最終的な報酬決定は、以下の「短期的な資金繰り」と「長期的な信用・保証」の二つの視点から総合的に判断すべきです。
| 資金繰り・税務 | 会社の資金温存を最優先。法人税率(約15%)と個人の実質税率を比較し、総額最小となる低額(10〜20万円)を設定し、資金流出を最小化する。 |
|---|---|
| 信用・社保 | 融資対策として、家計安定の資料準備を徹底する。社会保険は国民健康保険・国民年金で対応し、当面の資金を確保する。 |
| 資金繰り・税務 | 利益の配分を重視。利益が安定すれば、役員報酬を経費として支払い、高額な法人税を節税することを検討する。 |
|---|---|
| 信用・社保 | 健康保険・厚生年金保険への加入を検討する。これにより、会社の対外的な信用力が向上し、社長自身の傷病手当金などの手厚い補償を確保する。 |


実務手順と議事録テンプレ:合法的に0円を実施する手続き
役員報酬を0円または低額に設定する際、最も失敗が許されないのが、この手続きです。3か月ルールの期限を守り、必要な証拠書類を整備することで、後の税務調査で「損金不算入」という最悪の事態を防ぐことができます。
役員報酬0円への手続きロードマップ
役員報酬を0円または低額に設定する場合、以下の4つのステップを設立後3か月ルールの期限内に完了させる必要があります。
手続きロードマップ
- STEP1決議
株主総会(または社員総会)で、役員報酬を金0円とすることを正式に決議します。
実施時期:会社設立後、速やかに(3か月以内) - STEP2証拠保全
決議内容を明確に記載した議事録を作成し、会社に10年間保管します。税務調査で最も重要な証拠です。
実施時期:決議後、速やかに - STEP3税務署への届出
設立後2か月以内に法人設立届出書などを提出します。報酬0円であっても、翌年1月末には給与支払報告書(0円)を自治体に提出する義務があります
実施時期:必要に応じて速やかに
株主総会議事録ひな形テンプレートと重要記載事項
役員報酬の決定は、必ず書面(議事録)として残さなければなりません。口頭での合意は、税務調査では一切通用しません。
【議事録テンプレートと重要記載事項】
- 日時と場所:決議した具体的な日付(3か月以内の日付であること)と場所を記載。
- 決議事項(要約):議長より、当期における役員報酬額について、資金繰りの状況に鑑み、金0円と決定したい旨を提案。議場一同、これを満場一致で承認した。
- 承認された報酬額:代表取締役の当事業年度における報酬月額を金0円とする。
- 議事録作成者:会社法に基づき、議事録作成者が署名または記名押印する。
決定事項以外の「NG行動と国税庁の指摘事例」
役員報酬を0円に設定した場合、最も注意すべきは、「定期同額給与」のルールを意図せず破ってしまうことです。以下のNG行動を取ると、国税庁から指摘を受け、全額損金不算入となるリスクがあります。
| NG行動 | 税務調査での指摘内容 | 損金不算入額(税負担) |
|---|---|---|
| 不定期支給 | 会社に資金ができたため、「今月はボーナスとして20万円を社長に支給した」というケース。 | 支給した20万円全額が損金不算入となり、法人税が課税されます。 |
| 遡及改定 | 期末になってから、「期首(事業年度開始時)に遡って月額10万円に増額していたことにする」と議事録を作成するケース。 | 遡及した年間120万円すべてが損金不算入となり、法人税が課税されます。 |


まとめ:本記事の要点と最終確認チェックリスト
会社設立を考えている人にとって、役員報酬0円の判断は、資金繰りの最優先事項であると同時に、税務・社保・融資という将来の経営の盤石性を左右する重要な選択です。
この記事で解説した「総額最小の最適解」を実現するため、最終確認を行いましょう。
【最終確認チェックリスト】
- 0円設定で年間30万円も損をするというリスクを回避し、総額最小を実現するために、役員報酬を月額10万円〜20万円の超低額固定で決定したか?
- 税務上の3か月ルールを守り、将来の報酬増額時の損金不算入リスクを回避するため、会社設立後3か月以内に報酬決定の議事録を作成・保管したか?
- 報酬が低額または0円であることによる融資のマイナス評価を払拭し、資金調達を成功させるため、融資審査に備えて、個人預金残高(240万円目安)や家計資金計画書を準備したか?
これらを考えて実行することで、税務上のリスクを完全に回避し、融資にも耐えうる盤石な経営基盤を築くことができます。