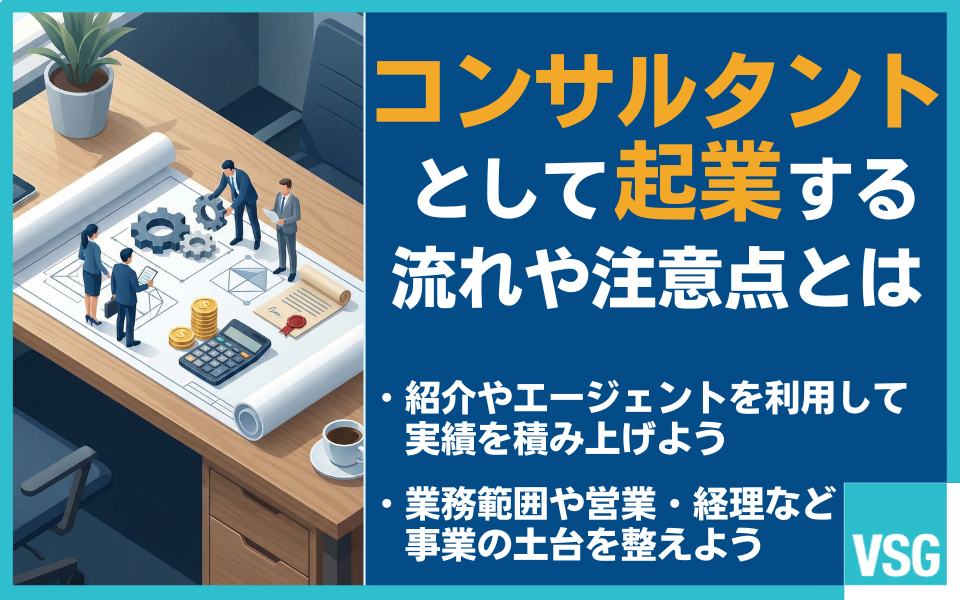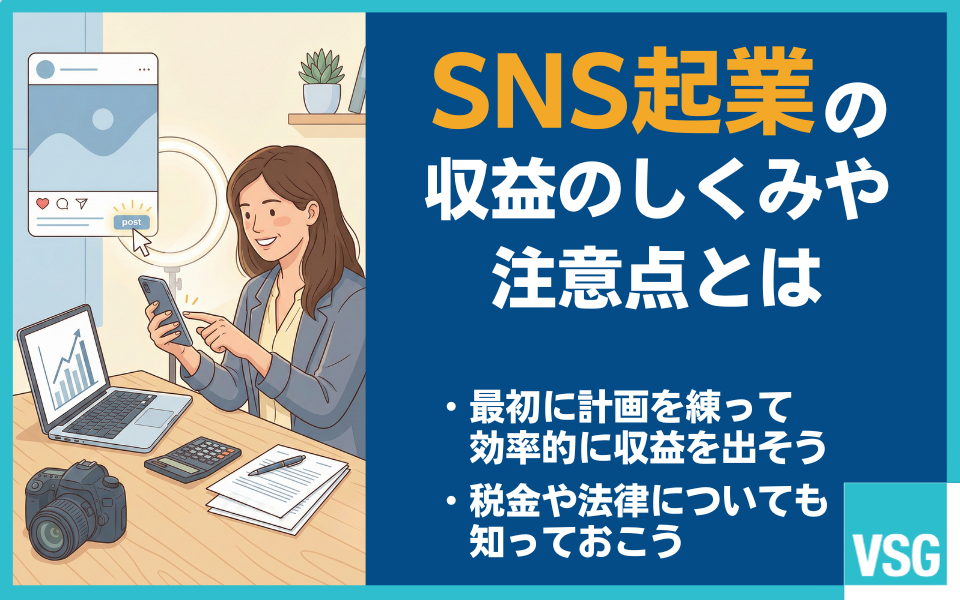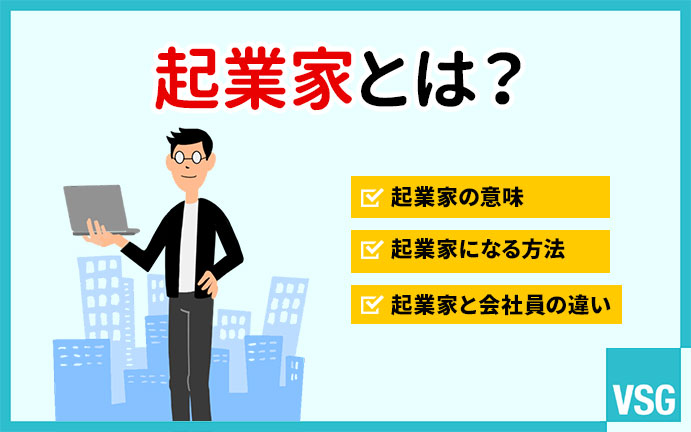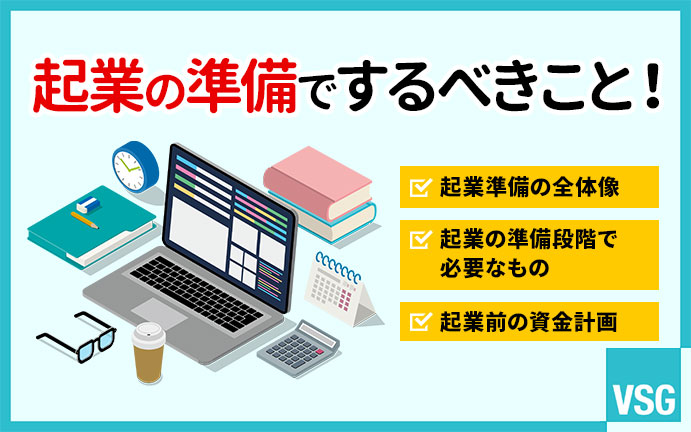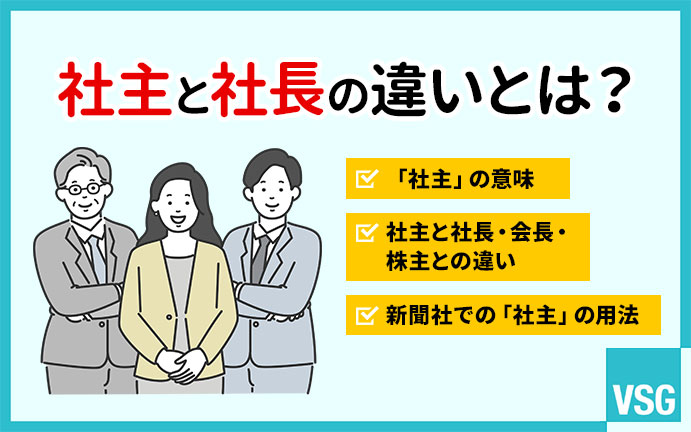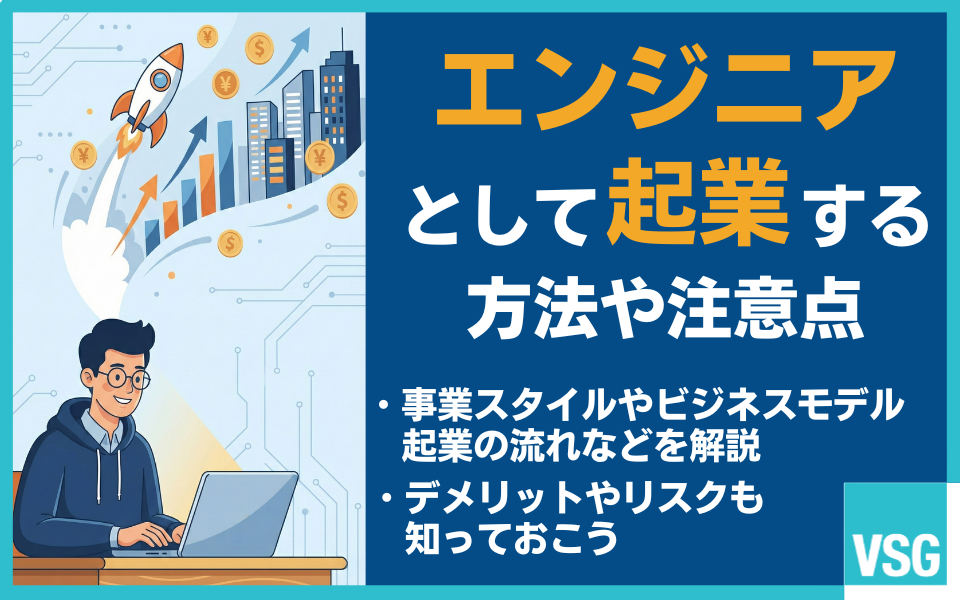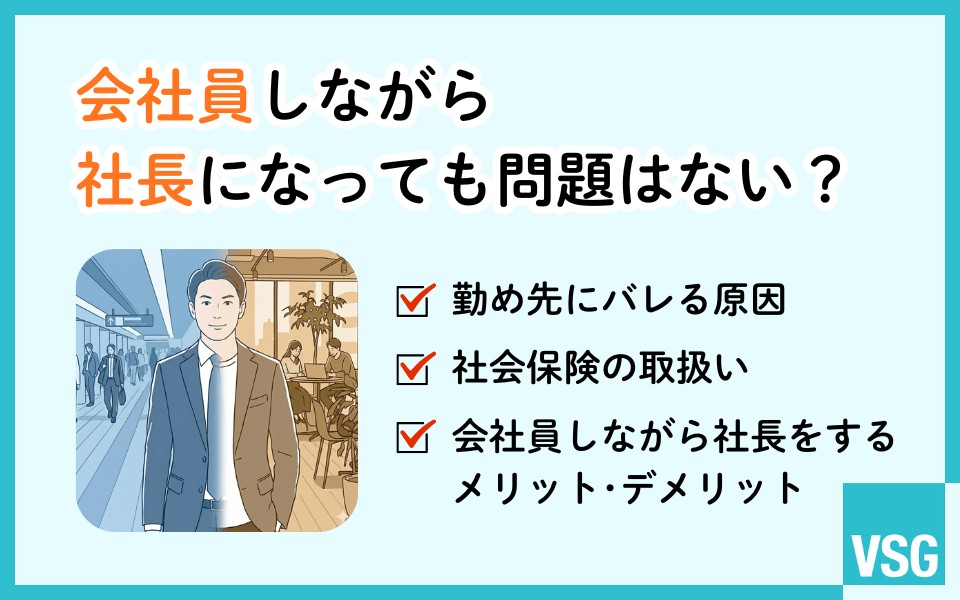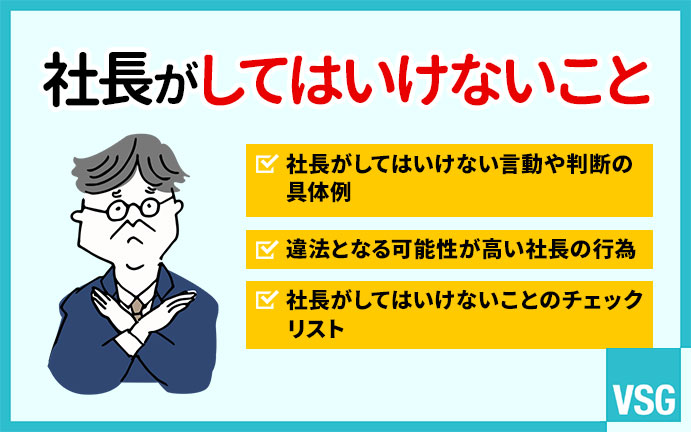最終更新日:2025/8/5
経営者と社長の違いは?仕事内容やどちらが偉いかなどを解説します

ベンチャーサポート税理士法人 大阪オフィス代表税理士。
近畿税理士会 北支部所属(登録番号:121535)
1977年生まれ、奈良県奈良市出身。
起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネルを運営。
PROFILE:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_writing/#p-mori
YouTube:会社設立サポートチャンネル【税理士 森健太郎】
書籍:プロが教える! 失敗しない起業・会社設立のすべて (COSMIC MOOK) ムック

この記事でわかること
- 経営者と社長の違い
- 経営者と社長はどっちが偉いか
- 経営者の仕事内容
- 経営者に向いている人の特徴
- ダメな経営者の特徴
- 経営者になる方法
経営者と社長の違いは果物とりんごの違いのようなもので、違いを追求することに大きな意義はありません。ただし、それぞれの言葉が示す内容や範囲には違いがあるため、経営者とは何か、社長とは何かを把握することは大切です。
この記事では、経営者と社長はどっちが偉いかを含めて、両者の意味や違いを深掘りします。
経営者の仕事内容や向いている人の特徴、経営者になる方法などもわかるので、経営者や社長に興味がある人はぜひ最後までご覧ください。


目次
経営者と社長の違い
経営者と社長は、それぞれ異なる意味を持つ言葉です。一般的に、経営者は会社などを経営する人、社長は会社の業務執行の最高責任者と認識されています。
| 用語 | 一般的な認識 |
|---|---|
| 経営者 | 会社などを経営する人 |
| 社長 | 会社の業務執行の最高責任者 |
上記のとおり、経営者と社長は、会社の経営(業務執行)に関与する点が共通点です。
社長は組織上の地位(役職)を、経営者は属性・カテゴリーを指すものと捉えるケースもあります。社長という地位・役職は、経営者という属性・カテゴリーに含まれるといった具合です。
一般的に社長は経営者であり、両者には強い結びつきがあります。しかし、経営者は社長だけではない点に注意する必要があります。
言葉としての両者の関係をわかりやすく示すなら、例えば経営者は果物、社長はりんごのようなものだといえるでしょう。果物(経営者)とりんご(社長)は、それぞれの言葉が指す内容が違います。しかし、りんご(社長)は果物(経営者)の一種です。
上記のとおり、「経営者と社長の違い」は、言葉としては「果物とりんごの違い」と同じようなものです。
どちらも法的根拠(定義)はない
経営者と社長は、どちらも会社法などの法律では定義されておらず、直接的には法的根拠のない言葉です。誰を経営者と呼ぶのか、経営者と社長は何が異なるのかといった問題は、厳密には正解がない問題といえます。
例えば、実際には会社ではない個人事業主でも、自身を社長と呼び、名刺に社長という肩書きを付けることも不可能ではありません。主催者の運用次第ですが、「社長向けセミナー」に個人事業主が参加することもありえます。
上記のとおり、社長と経営者は、いずれも厳格に定義されているわけではありません。
一般的に社長は経営者と認識される
一般的に、社長は経営者と認識されています。社長とは、一般的に会社の業務執行に関する最高責任者を示す役職名です。
社長は、経営陣の中でも一層高い序列や責任を有しているケースがあります。
社長以外でも経営者と呼ばれることがある
社長以外でも、経営者と呼ばれることがあります。「社長以外の経営者」の具体例は、以下のとおりです。
- CEO(最高経営責任者)
- 取締役(平取締役)
- 執行役
- 会長
- 副社長
- 常務
- 専務
- 執行役員
- 個人事業主
個人事業主には妥当しませんが、例えば「経営陣」や「経営幹部」のように一括りにして呼ばれるケースがあります。
経営者というと社長が想定されるケースが多いですが、実際には社長に限りません。
経営者との違いまとめ
ビジネスシーンでは、社長や経営者に関連して、CEOや代表取締役、理事長など多くの言葉が使われます。
ここでは、経営者や社長と並べて使われることが多い言葉について、それぞれ解説します。
経営者と社員の違い
社員とは、一般的には会社に雇用されている従業員を指します。経営者と社員の大きな違いは、会社との関係性(雇用関係の有無)です。
雇用関係の有無により、それぞれの業務遂行について会社からの指揮命令を受けるか受けないか、労働法の保護を受けるか受けないかなどが異なります。
| 経営者 | 社員(従業員) | |
|---|---|---|
| 関係 | 委任契約 | 雇用契約 (労働契約) |
| 会社からの指揮命令 | 原則として受けない | 受ける |
| 労働法の保護 | 対象外 | 対象 |
なお、「雇われ社長」のように、あたかも社長(経営者)が会社から雇用されているかのような表現がされることもあります。しかし、雇われ社長はあくまでも会社や株主(オーナー)から雇われているような社長といった比喩的な表現であり、実際に雇用関係があるわけではありません。
経営者と代表取締役の違い
代表取締役とは、株式会社を代表する権限のある取締役です。取締役(会)の監督下にある、代表権のある業務執行者(経営者)ともいえます。
株式会社そのものは、実体がないため契約締結などの法律行為ができません。そこで、代表する権限を有する者(代表者)が、株式会社のために契約締結などの行為をします。
代表取締役は、株式会社の経営者として認識される代表的な地位です。
経営者と取締役の違い
取締役とは、株主総会の決議で選任された株式会社の機関です。各取締役の監督や株式会社の業務について意思決定を行う機能などがあります。
各取締役は株式会社の業務の意思決定に関与するほか、実際に業務を執行する場合もあることから、まさに経営者と呼ぶのにふさわしいといえるでしょう。
したがって、取締役は一般的に経営者として認識される地位の1つです。
経営者と役員の違い
役員とは、会社法では以下3つの機関・地位を指します(会社法329条1項括弧書)。
- 取締役
- 会計参与
- 監査役
また、「役員等」とは、会社法の役員に執行役と会計監査人を加えたものです(会社法423条1項など)。
さらに、会社法の役員や役員等には該当しませんが、実務上、会社の役員には執行役員も含む場合があります。
役員のうち、取締役は経営者として広く認識されています。しかし、取締役以外の役員がそれぞれ経営者といえるかどうかには議論があります。
| 役員等 | 職務 | 経営者に該当するか |
|---|---|---|
| 会計参与 | 取締役と共同して計算書類を作成し、信頼性を高める | 経営への関与は間接的で、経営者とは言い難い |
| 監査役 | 取締役の職務の執行を監査する | 経営を監督する立場で、経営者とは言い難い |
| 執行役 | 委任の範囲内で意思決定を行い、業務を執行する | 業務執行を担う点で、経営者といえる |
| 会計監査人 | 計算書類を監査する | その会社とは独立した存在で、経営には関与しない |
| 執行役員 | 一般的に、特定部門の責任者として業務を執行する | 実質、業務執行を担う点で経営者といえる |
上記のとおり、取締役以外の役員のうち経営者といえる可能性が高いのは、執行役と執行役員です。
会社の役員だからといって、直ちにその役員が経営者といえるとは限りません。
経営者と理事長の違い
理事長とは、学校法人や医療法人など、特定の種類の法人や団体における代表取締役のような役職です。例えば、一般社団法人における代表理事は、一般社団法人を代表します。
理事長も代表取締役と同様の地位があり、法人の経営者として認識されるのが一般的です。
経営者とCEO(最高経営責任者)の違い
CEO(最高経営責任者)は、会社法などの法律で定義されていない、会社が独自に定める役職です。そのため、経営者とCEOの違いも、厳密には会社が定めた定義によります。
もっとも、CEOも社長と同じく、一般的には経営者と認識される具体的な役職の1つです。
経営者とプレジデントの違い
プレジデント(President)は、日本でいう社長を指す英語圏の役職名です。一部の会社では、社長の名刺などに、英語での肩書きとして「President」の記載があります。
したがって、プレジデントも社長と同様に経営者ということができ、両者にほとんど違いはありません。
経営者と個人事業主の違い
経営者と個人事業主は、個人事業主が個人事業の経営者である点で同じです。
経営者というと、一般的には会社の経営者、すなわち代表取締役や社長、CEOをイメージする人が多いでしょう。
しかし、法人格こそないものの、個人事業主も事業計画を策定したり、経営資源を管理したりします。従業員を雇用することも可能です。
上記のとおり、社長や代表取締役、CEOと同様に、個人事業主も一般的には経営者と認識されます。
経営者と自営業者の違い
経営者と自営業者は、自営業者も経営者といえる点で同じです。自営業者も、事業計画を策定したり、経営資源を管理したり、従業員を雇用したりといった経営を行います。
ただし、自営業者と言う場合、会社(法人)の経営者を指すことはほとんどありません。いわゆる一人社長を自営業者と呼ぶこともあります。
経営者とオーナーの違い
株式会社のオーナー(Owner)とは、通常は株主を指す言葉です。
しかし、株主(オーナー)になったからといって、その株式会社の経営に関与するとは限りません。むしろ、原則としてオーナー(株主)は経営者ではないといえます。
会社法は、株主と経営者が別人物であること、つまり所有と経営の分離を原則としているからです。経営者は会社を経営する立場であるのに対し、オーナーは会社を所有するような立場であり、両者は会社に対する立場が大きく異なります。
しかし、特に中小企業では、オーナー自ら経営者として会社を運営するケースも少なくありません。このような場合、経営者とオーナーの人格が一致している以上、両者に違いはないと捉えることもできます。
経営者と起業家の違い
起業家とは、事業を立ち上げる人、すなわち創業者を指す言葉です。
言葉としての「経営者」は事業の運営に焦点を置いている一方、「起業家」は事業の立ち上げに焦点を置いている点に違いがあります。
また、経営者と起業家の人格が同一であるとも限りません。例えば、起業家が会社を設立しても、経営は他者に任せることができます。
経営者と実業家の違い
実業家とは、一般的に、自ら事業を営んで成功を収めた人物を指す言葉です。単に創業者や起業家という場合に比べて、より積極的に経営手腕を高く評価するニュアンスが含まれているといえます。
経営者と実業家は、それぞれの言葉が持つニュアンスの違いはあるものの、経営とは切り離して語れない点では同じです。
一方で、同じ会社に勤めたキャリアが長く、内部で昇格して社長となった内部昇格社長などは、経営者であっても実業家とは呼ばないことがあります。
経営者と実業家は、いずれも経営と密接に関連する言葉です。しかし、経営者であれば誰もが実業家と呼ばれるわけではない点で、実業家が指す範囲はより限定的といえます。
経営者と店長の違い
店長とは、一般的に、店舗の運営責任者です。店長は、担当店舗の売上や利益といった経営指標のほか、商品やスタッフの管理なども行う場合があります。
企業・組織全体を担当する経営者とは範囲が異なるものの、店長の職務内容はほとんど経営者と同様といえるでしょう。店長は会社の経営者とまでは言えなくても、担当する店舗の経営者であるといえます。
経営者と社長はどっちが偉い?
経営者と社長はどっちが偉いかといった疑問について、掘り下げて解説します。
そもそも偉さの比較にはなじまない
結論、経営者と社長は、結局は同一人物を指すケースもあり、どちらが偉いかを比較するのにはなじみません。例えるなら、果物とりんごはどっちが美味しいかと比較するようなものです。
また、社内で経営者と呼ばれる人が複数人いたとしても、法律でどちらが偉いか決まっているわけではありません。結局、経営者と社長のどちらが偉いかという問題は、何を基準に偉さを決めるのか、その会社での実態はどうかといった複雑な事情によって異なります。
ここからは、社長を含む経営者間で、一般的にどちらが偉いと認識されているかの例を紹介します。実際にはその会社の実態で決まるものなので、あくまでも参考程度の情報としてください。
平取締役(ヒラトリ)と社長では一般的に社長
経営者の中でも、平取締役(ヒラトリ)と社長とでは、一般的には社長のほうが偉いと認識されています。
一般的には社長も取締役です。したがって、両者は社長という役職のある取締役と役職のない平(ヒラ)の取締役として比較できます。結局、役職がある社長のほうが偉いという理解です。
社長という役職こそ社内における序列の最上位を示すものであり、役職の有無以前に社長が最も偉いといった考え方もあります。
会長と社長では一般的に会長
経営者の中でも、会長と社長とでは、一般的には会長のほうが偉いと認識されています。
会長は、一般的には、創業者などが社長職を退任した後のポストとなることの多い役職です。以下の表のとおり、会長の役割は大きく2種類に分かれます。
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| 実権型の会長 | 社長の上に立ち、経営について大きな影響力を維持する会長 |
| 名誉職型の会長 | 日々の経営からは一線を画し、対外的な活動や社長へのアドバイスをするにとどまる会長 |
上場会社では、コーポレートガバナンス強化の観点から、実権のある会長よりも名誉職型の会長が多いといえるでしょう。
もっとも、会長の権限や役割は、必ずしも上記の2種類で説明しきれるものではなく、会社によって大きく異なります。一般的に社長よりも会長のほうが偉いとされますが、反対のケースもある点は把握しておきましょう。
なお、日々の経営にほとんど関与しない会長については、そもそも経営者とはいえないケースがあります。
経営者とは?仕事内容を簡単に解説
ここでは、経営者とはどのような人を指しているのか、経営者の仕事内容は何なのかなど、経営者に関する基礎知識を解説します。
結論、経営者とは、企業運営の舵取りをする人です。一般的には代表取締役社長が該当します。
経営者の仕事内容は非常に多様であり、厳密には定まっていません。しかし、株主から選ばれている点で、経営者に課せられた基本的なミッションは企業価値の向上だといえます。
以降では、経営者の主な仕事内容を紹介します。
- 情報収集と環境分析
- 経営方針・戦略の策定
- 財務・資金調達
- 従業員の採用や配置、育成・評価
- 業務プロセスの構築と改善
- 業績管理
- リスクマネジメント
情報収集と環境分析
経営者は、後述する経営方針・戦略の策定や日々の経営判断(意思決定)を適切に行うためにも、情報収集と環境分析が欠かせません。
具体的には、自社が参入する市場の動向や競合、技術、法規制などの外部環境を常に把握する必要があります。反対に、経営者なのに市場や競合の動向、技術や法規制の状況を把握していないのは問題といえるでしょう。
具体的な情報収集の方法はさまざまですが、例えば以下のような方法が考えられます。
- 業界・経済ニュースをチェックする
- 競合他社のニュースリリースやIR情報をチェックする
- 業界誌や専門書籍を読む
- セミナーや展示会に参加する
- 専門家と交流する
- 社内から報告を受ける
情報収集と環境分析は、創業時に1回だけ行えばよいものではなく、日々の経営判断(意思決定)を適切に行うため、継続的に行う必要があります。
経営方針・戦略の策定
経営者、特に創業者である経営者は、企業の存在意義や社会に提供する価値といった根本的な目的を明確にします。中長期視点の経営計画・事業計画の策定も、経営者の仕事内容の1つです。
ざっくりいうと、企業の方向性を決めることが、経営者の仕事といえるでしょう。このような企業の方向性は、一般にMVV(ミッション・ビジョン・バリュー)と呼ばれることがあります。
| 通称 | 内容 |
|---|---|
| ミッション (Mission) |
企業が果たそうとする使命や存在意義 |
| ビジョン (Vision) |
企業の理想像、中長期的な目標 |
| バリュー (Value) |
ミッションやビジョンを達成するための具体的な行動指針 |
こうした企業の方向性(MVV)は、自社の内部環境はもちろん、外部環境も把握していなければ適切な内容を定めることができません。
財務・資金調達
会社を経営していくためには、資金調達などを含む財務が欠かせません。財務は、事業活動の血液ともいえる資金を管理する大切な業務です。
経営者が行う財務に関する仕事内容には、以下のようなものがあります。
- 銀行融資や社債発行、増資などによる資金調達
- 策定した予算と実績との差異把握、管理
- キャッシュフロー(現金の流れ)の管理
- 設備や研究開発への投資など、大規模な投資判断
銀行から融資を引くときやキャッシュフローを分析するとき、投資判断をするときなどは、いずれも財務諸表を読み解くスキルが必要です。
財務スキルに不安がある場合は、税理士や公認会計士といった外部専門家の力を借りることも検討しましょう。仮に経営者自ら財務に関する知識があっても、外部専門家の力を借りることは、財務健全性の確保や対外的な信用力獲得の観点から大きな意義があります。
従業員の採用や配置、育成・評価
強固な財務基盤も重要ですが、それだけでは事業を経営できません。人材(従業員)も、資金と同程度に重要な経営資源です。経営戦略の実行役ともいえるでしょう。
日常的な人事業務は人事部門や管理職に権限を委譲するとしても、以下のような人事に関する事項は、経営者が実行するケースがあります。
- 戦略を実行するために最適な組織構造(部門編成)を決める
- どのようなスキル・経験・価値観を持つ人材を求めるかを定義する
- 採用だけでなく、配置、育成、評価、報酬といった人事制度の基本方針を設計する
- 部門長など重要な人事には直接関与する
- 次の経営幹部候補の発掘と育成に関与する
業務プロセスの構築と改善
業務プロセスの構築と改善も、経営者の重要な仕事内容といえます。経営戦略の効率的かつ効果的な実行には、最適化された業務プロセスが不可欠だからです。非効率なプロセスでは納期遅延や品質低下などを招き、経営目標の達成から遠のいてしまいます。
よく耳にする「DX(デジタルトランスフォーメーション)」も、業務プロセス改善の一種といえるでしょう。
業績管理
業績管理は、経営者の仕事の結果を管理するものであり、極めて重要な仕事内容です。
経営者は、会社の売上や利益、市場シェアなど経営上の重要な指標(KGI:重要目標達成指標)を定期的に把握しなければなりません。KGIを達成するための中間的な指標といえるKPI(重要業績評価指標)の設定やモニタリングも大切です。
定期的にKGIやKPIといった指標の状況を確認するなどして業績を管理することで、問題を早期に発見し、適切な軌道修正ができるようになります。業績悪化に気づくのが遅れて適切な対応ができなければ、任務懈怠で業績を悪化させたとして、責任を追及される可能性があります。
リスクマネジメント
リスクマネジメントも、経営者にとって極めて重要な仕事内容です。
事業経営は、常にリスクを負っているといえます。事業経営上のリスクは非常に多様ですが、例を挙げると以下のとおりです。
- 景気の悪化
- 競合の値下げ(価格競争)
- 資金のショート
- 自然災害
- 法改正
- 情報漏えい(セキュリティー)
- 新技術の開発・普及
上記のようなリスクが現実化して初めて対応の検討を始めるようでは、経営者として対応が遅すぎたとの評価を免れないでしょう。最悪の場合、事業の継続が困難となり、破産や解散をせざるを得ない事態に陥ってしまいます。
起こり得るリスクを事前に想定(予見)し、リスクの大きさや頻度を評価したうえで回避・低減・移転・受容といった対応を決定する必要があります。
経営者に向いている人の特徴
仕事や責任の内容を考慮すると、経営者に向いている人の特徴として以下の6点が挙げられます。
- 向上心が強い
- 責任感が強く自責思考である
- コミュニケーション能力が高い
- リーダーシップがある
- 変化に対して柔軟に適応できる
- 論理的思考力がある
言い換えれば、社長に向いている人、経営者になる人の特徴ともいえるでしょう。なぜ上記のような人が経営者に向いているのか、詳しく解説します。
向上心が強い
経営者には、強い向上心が求められます。企業の経営環境は常に変化しており、その変化に対応するためには、現状に満足せず向上を続けることが大切だからです。
そもそも「事業を成長させたい」という強い気持ちがなければ、事業を成長させることは難しいでしょう。決して現状維持を許さず、さらなる高みを目指す経営者の姿勢は、企業の成長の源泉といえます。
責任感が強く自責思考である
経営者には、強い責任感と自責思考が求められます。経営者は企業の重要な事項を決定する立場であり、その決定には相応の責任を伴うからです。
経営判断に誤りがあり、業績が悪化した場合には、株主などから責任を追及されることがあります。当然、経営者である以上、他人に責任をなすりつけるわけにはいきません。
また、自責思考の重要性は、経営者が持続的な成長を求められている点からも説明できます。他責思考では、問題や失敗から学び、成長につなげることができません。
コミュニケーション能力が高い
経営者は、以下のとおり社内外の非常に多くの人と関わる必要があるため、高いコミュニケーション能力が求められます。
- 他の経営者
- 従業員
- 取引先(クライアント・顧客)
- 金融機関
- 株主(オーナー・投資家)
例えば、金融機関との間で十分なコミュニケーションができなければ、本来なら獲得できるはずの融資条件を引き出せないかもしれません。
リーダーシップがある
そもそもリーダーシップとは、目的の達成に向けて集団を導く機能と言われます。経営者は、業績の向上など企業共通の目的の達成に向けて企業を率いる立場であり、まさに企業のリーダーといえるでしょう。
具体的にどのようなスタイルで集団を導くかという点に、正解はありません。ただし、少なくとも他人に良い影響を与えられる存在であることが大切です。
変化に対して柔軟に適応できる
経営環境は常に変化しているため、経営者は常に変化と向き合わなければなりません。もし経営者が変化に適応できなければ、機会を捉えられず成長できないばかりか、市場での競争力を失う可能性があります。
消極的には市場の変化に取り残されて競争力を失ってしまわないため、積極的には変化を機会と捉えて成長を得るため、経営者には変化への適応力が必要です。
論理的思考力がある
論理的思考力とは、物事を筋道立てて整理し、合理的な結論を導き出す力です。
同じ情報でも、その情報からどのような判断を導くかは経営者によって異なります。また、なぜそのような判断に至ったのかといったプロセスも異なります。
極端な例では、経営者が感情的に、あるいは思いつきだけで経営判断をしているかもしれません。このような経営判断は、客観的に見て合理性や根拠が欠けている点で問題です。
論理的思考力があれば、適切に情報を整理・分析したうえで、根拠のある合理的な経営判断ができます。
経営者になってはいけない、ダメな経営者の特徴とは?
経営者になってはいけない、ダメな経営者の特徴は以下のとおりです。ほとんど、前述した経営者に向いている人の特徴の裏返しといえるでしょう。
| 特徴 | 理由 |
|---|---|
| 変化を嫌う | 市場の変化に取り残され、競争力を失う |
| 向上心がない | 時代遅れの知識やスキルで経営判断を行い、誤った方向に導く可能性がある |
| 感情的な判断が多い | 経営判断に合理性や根拠がない |
| 人の意見を聞かない | 誤った判断をするリスクが高まる |
| 約束を守らない | 取引先や従業員からの信用を失う |
| 失敗を他人のせいにする | 従業員の信頼を失うほか、問題の根本的な解決ができない |
| ビジョンや目標を示せない | 組織の方向性が曖昧で、リーダーシップを発揮できない |
| 自己中心的である | 従業員や取引先、社会全体の利益を軽視し、企業の成長を損なう |
経営者になるには?
経営者になるために資格や経験は必須ではなく、経営者になる方法は多様です。
ここでは、経営者になりたい人に向けて、資格や学歴の必要性、あると良いもの、経営者になる経緯(ルート)などを解説します。
資格や学歴がなくても経営者になれる
経営者になるために必要な資格や学歴はありません。例えば、運転免許を含めて何の資格もない中卒であっても、経営者になることは可能です。
経営者に必要なのは、資格や学歴といった形式的なものではなく、前述した以下のような能力といえます。
- 向上心
- 責任感
- コミュニケーション能力
- リーダーシップ
- 変化に対する適応力
- 論理的思考力
もっとも、資格や学歴にまったく意味がないわけではありません。MBA(経営学修士)のように、経営に関する知識を体系的に学べるなど、経営に役立てられるものもあります。
経営に役立つ、経営と関連性があると言われている資格は、以下のとおりです。
- MBA(経営学修士)
- 中小企業診断士
- 経営士
- 公認会計士
- 税理士
- 社会保険労務士
- 日商簿記検定
- ビジネス実務法務検定
- ビジネスマネジャー検定
経営者に必要な知識を身につけるための手段として、資格の取得を検討してもよいでしょう。
ビジネスの経験や人脈はあるとよい
経営者として成功するためには、ビジネスの経験や人脈を備えておくことが望まれます。
社会人としての経験や人脈がない学生でも、起業して経営者になることは可能です。しかし、参入する業界の実務経験がなければ、顧客や競合を把握するためにも、業界を理解することから始めなければなりません。
また、人脈がなければ、経営についてアドバイスをしてくれるメンターや専門家もゼロから探す必要があります。
経営者になるにあたって、資格や学歴、経験、人脈は必須ではありません。しかし、どれも経営にあたって軽視できない重要な要素であることは、理解しておくべきでしょう。
起業だけでなく内部昇格や雇われ、承継の選択肢もある
「経営者になるためには起業しなければならない」と考えている人も少なくありません。しかし実際には、経営者になる原因は起業の他にも多数あります。
- 開業する
- フランチャイズ契約で独立する
- 内部昇格で社長などの経営者になる
- 外部招聘で社長などの経営者になる
- 事業承継で経営者になる
そもそも起業するとは、創業すること、ビジネスを始めることです。一般的には株式会社などの会社を設立して事業を始めることがイメージされますが、個人事業主としての起業(開業)もありえます。
フランチャイズ契約で独立するとは、フランチャイズ本部のチェーン店の経営者兼オーナーとなることです。ゼロから起業するわけではなく、商標や経営ノウハウなどが本部から提供されます。
しかし、これらの対価として、本部にロイヤルティーと呼ばれる費用(フィー)を支払わなければなりません。
例えば、あるコンビニフランチャイズでは、土地や建物、内装設備工事費用は本部が負担しますが、加盟要件として同居親族の2名で専業できること、契約時必要資金として150万円以上を用意できることなどがあります。
本部へのフィーは、契約内容によって異なりますが、おおむね営業利益の40~60%程度です。
その他、従業員から会社の役員や社長などの経営者に昇格するケース、プロ経営者として外部招聘されるケース、事業承継で経営者になるケースなどがあります。
経営者と社長の違いに関するよくある質問(FAQ)
ここでは、経営者と社長の違いに関する質問について、それぞれお答えします。
社長は経営者ですか?
社長は経営者と考えるのが一般的です。むしろ、社長は経営者の代表格ともいえるでしょう。
オーナーと社長はどちらが偉いですか?
オーナーと社長は、一般的にはオーナーのほうが偉いと認識されています。なぜなら、オーナーは社長の解任や報酬といった人事を把握しているからです。
ただし、直接的に社長の人事を決定するのは株主総会であって、オーナーの決定権は間接的です。
経営者と社長の違いは果物とりんごのようなもの
社長と経営者は、社長が具体的な役職位を指す言葉であるのに対し、経営者は経営をする人といった属性を指す言葉である点に違いがあります。もっとも、現実を見ると社長は経営者であり、両者が同一人物であるケースも少なくありません。
両者の関係をわかりやすく示すなら、経営者は果物、社長はりんごのようなものだといえるでしょう。
りんご(社長)だけでなく、いちご(取締役)やぶどう(執行役)も同じ果物(経営者)です。そして、果物(経営者)とりんご(社長)はどっちが美味しいか(偉いか)といった疑問も、やや的外れなものといえるでしょう。