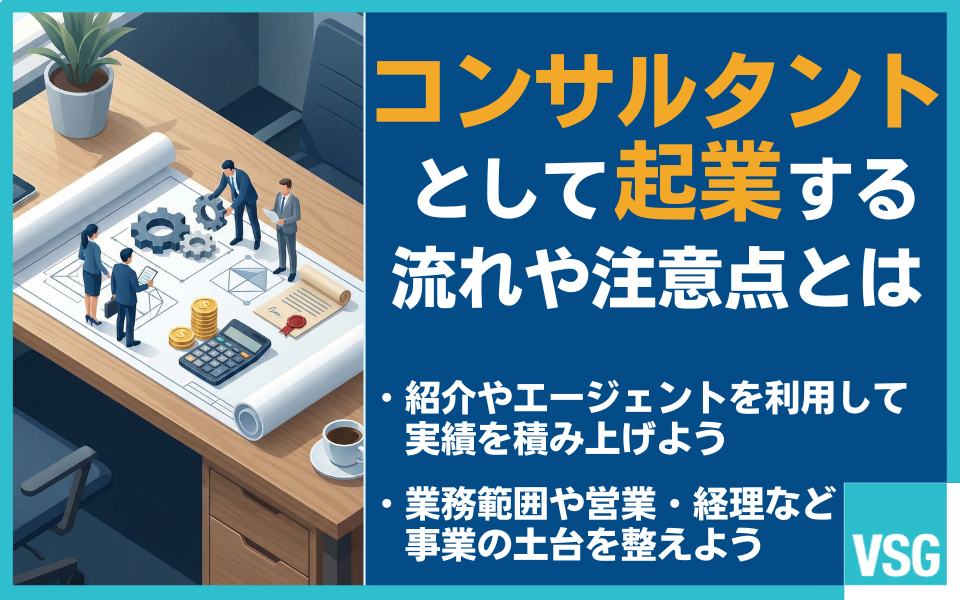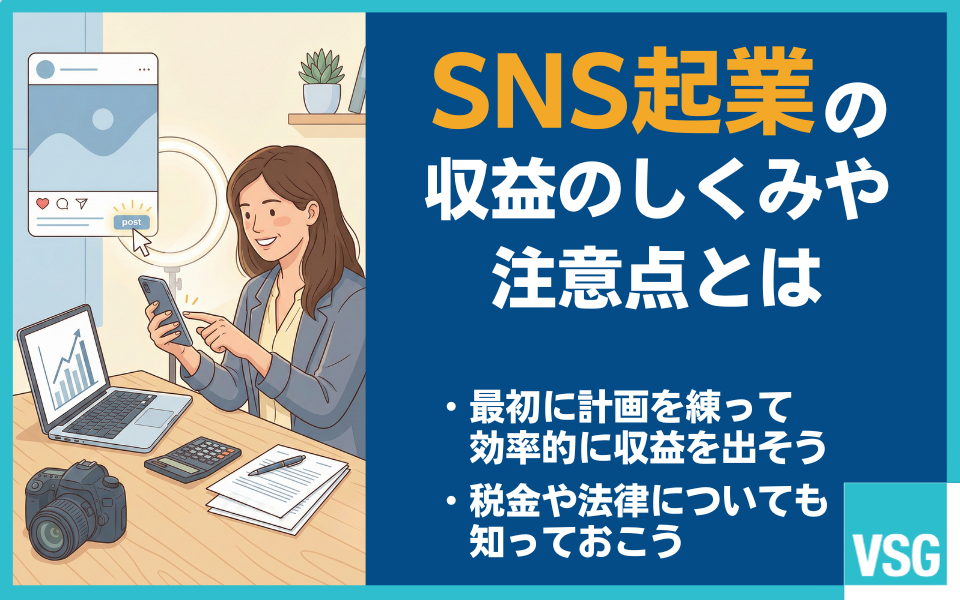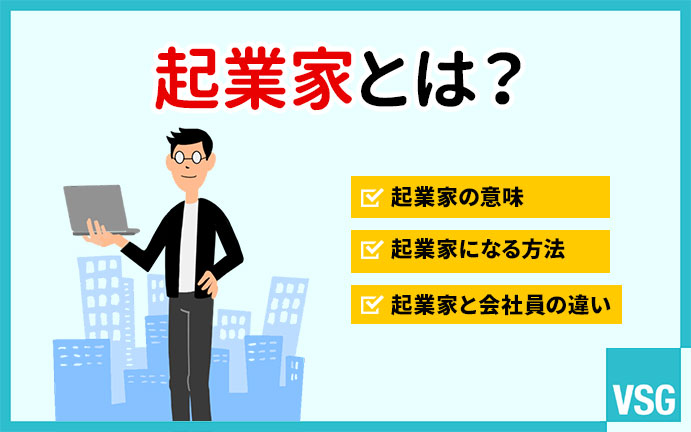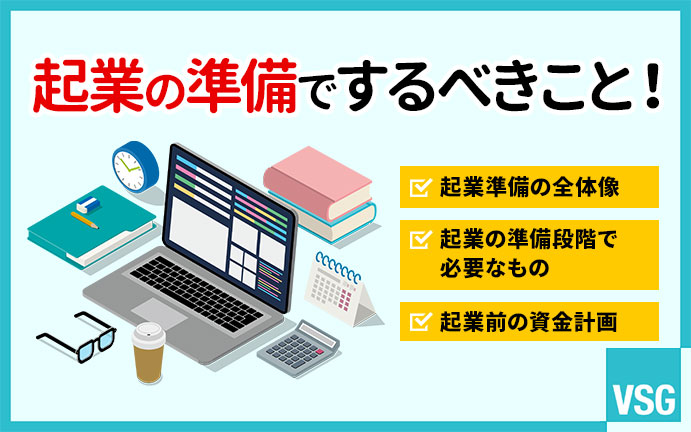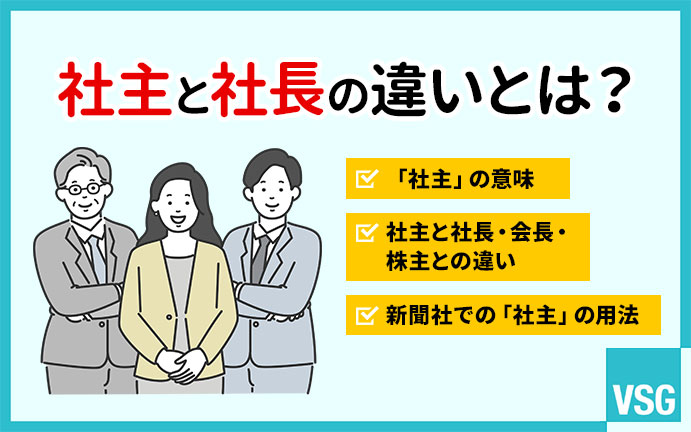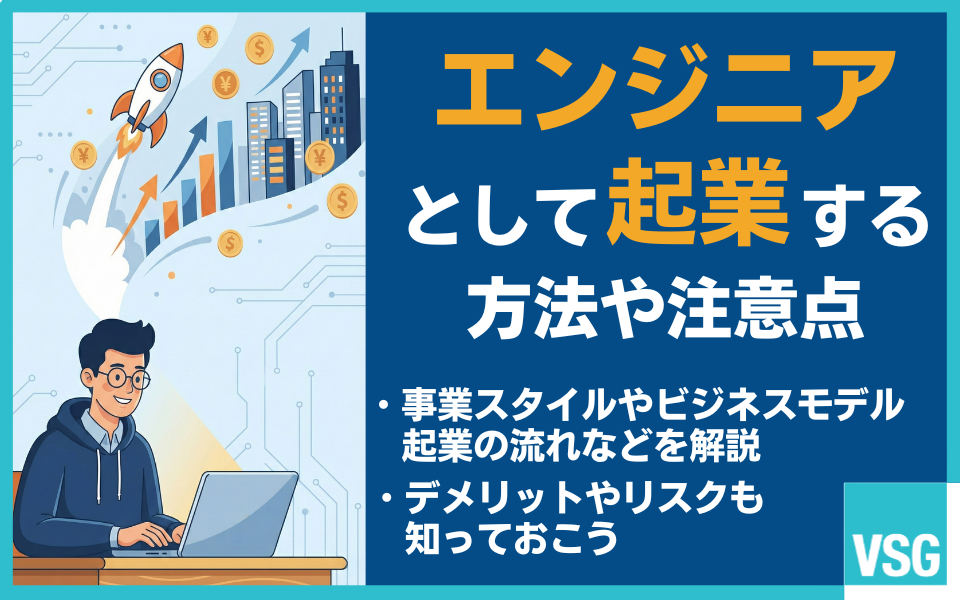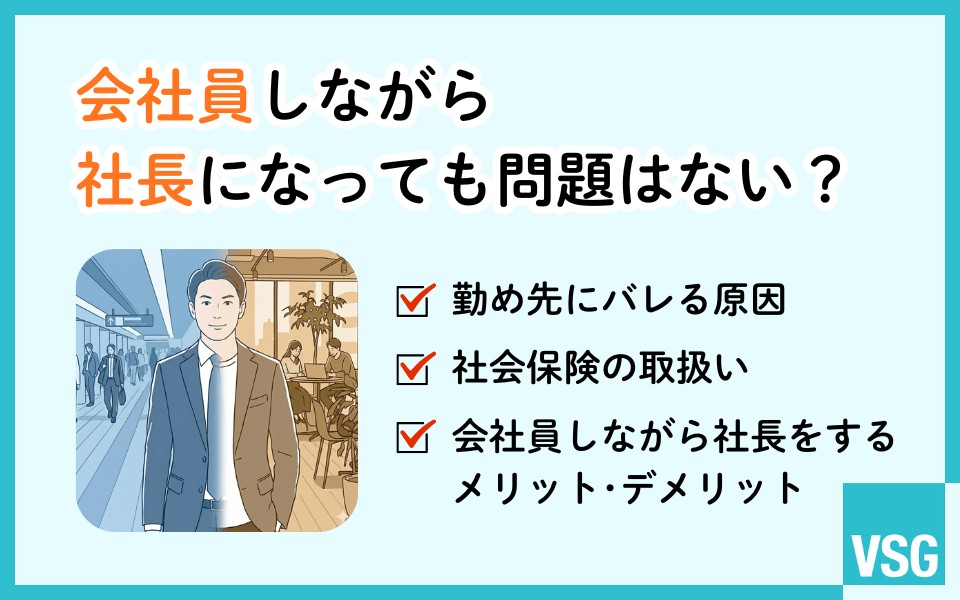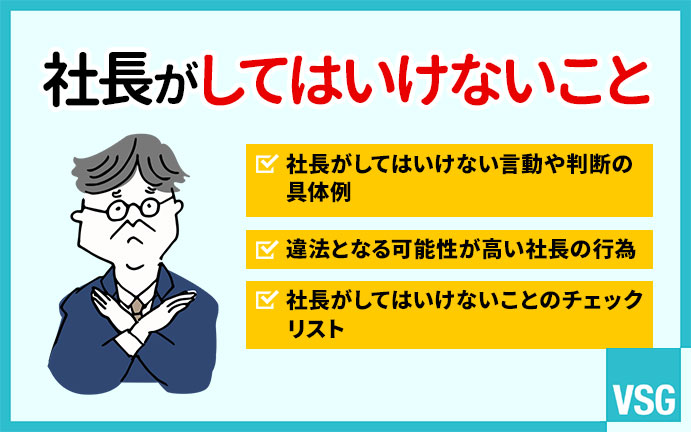最終更新日:2025/11/20
妻名義の会社設立のメリットとデメリットとは?節税効果や保険関係などを解説

ベンチャーサポート税理士法人 大阪オフィス代表税理士。
近畿税理士会 北支部所属(登録番号:121535)
1977年生まれ、奈良県奈良市出身。
起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネルを運営。
PROFILE:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_writing/#p-mori
YouTube:会社設立サポートチャンネル【税理士 森健太郎】
書籍:プロが教える! 失敗しない起業・会社設立のすべて (COSMIC MOOK) ムック
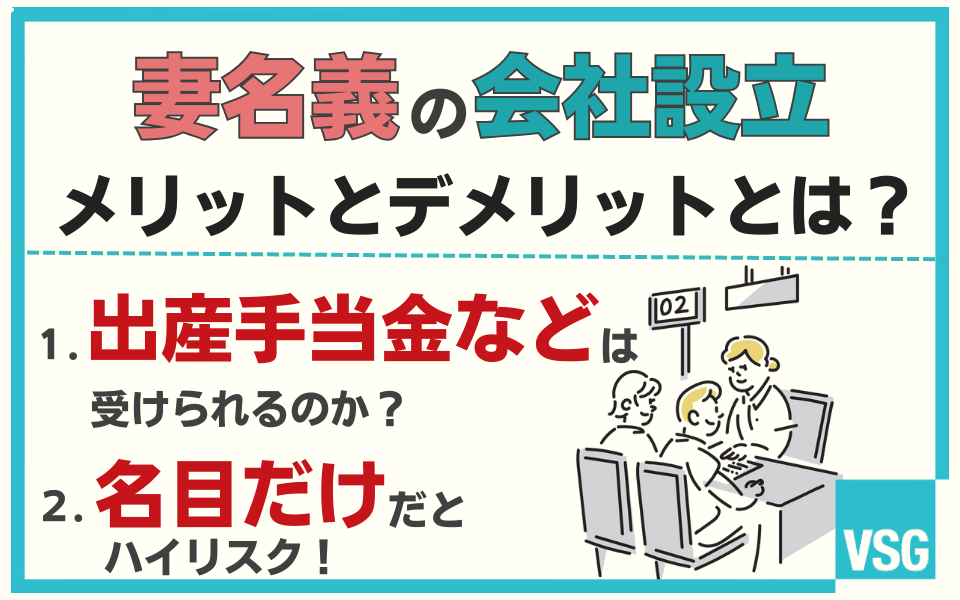
会社を設立する際に、妻の名義を借りて設立する人もいます。
こうしたケースでは、節税などの効果を得られることもありますが、場合によっては会社の運営上で大きなリスクとなるかもしれません。
この記事では、会社設立を妻名義で行うことのメリットとデメリットについて詳しく解説します。
出産や育児に関わる制度や補助金を、妻を役員とした場合にも受けられるのかなどについても触れるので、夫婦で起業を考えている人はぜひご覧ください。


妻名義で会社を設立するメリット
妻を役員などにして会社設立を行う場合、いくつかのメリットがあります。
ただし、ここで挙げているメリットは個々の事情によって当てはまるかどうかが異なるので、慎重に検討してください。
所得を分散することで節税につながる
夫がすでに本業がある場合、新たに設立した会社からも役員報酬を得ると、そのぶん所得が増え、支払う所得税の額も大きくなります。
会社設立の際に妻を代表取締役にして、役員報酬を適切な額に設定すれば、一家の中で所得が分散し、支払う所得税の額を抑えられます。
ただしこれは、妻が事業に参加している実態があることが前提です。
事業に一切関わっていない妻を代表取締役にした場合、後々で追徴課税などが発生し、節税どころか不必要な出費の原因となってしまうこともあります。
妻に肩書がつくので保育園に子どもを預けやすくなる
認可保育園を利用するためには、月に48~64時間以上の就労が前提条件になります。
妻を社長にして会社を設立した場合、役員の労働時間は自由に決められるため、保育園の利用条件を容易に満たすことができます。
ただし、保育園の入園審査においては「事業を行っている実態があるか」などがポイントになります。
必ずしも入園できるわけではない点には注意してください。
本業の勤め先にバレる可能性が低くなる
ほかの収入源があると、支払う住民税の額が増加し、それが原因で副業を行っていると勤め先にバレてしまうことがあります。
そうした場合、設立する会社の社長を妻にして、妻にのみ役員報酬を支払う形にすれば、夫側の住民税は変化しないため勤め先にバレにくくなります。
また、会社の代表者の氏名や住所は登記簿謄本に記載されるので、誰でも確認可能です。
あらかじめ妻を代表者としておけば、登記簿謄本に自分の名前が載らないため、会社にバレるリスクを抑えることができます。
妻名義で会社設立をするデメリットとリスク
妻名義での会社設立は、その実態によっては大きなデメリットやリスクとなることもあります。
ぜひ一度目を通し、確認してください。
妻に事業の知識がないと経営上問題になりやすい
妻を社長にする場合、それが名目的なものであったとしても、税務調査や金融機関との面談、創業融資の審査などの対応は妻が行うことになります。
その際に妻が実際の事業にまったく関与していないと、相手からの質問にうまく答えることは不可能です。
妻が実質的な経営者でないと発覚した場合は、融資が受けにくくなるほか、その実態によっては役員報酬の支払い自体が不当と税務署に判断され、追徴課税や損金算入の否認につながる可能性もあります。
妻には名義を貸しただけで、実務はすべて夫が行う場合は、後々こうした問題になりやすいため、妻を名目上の代表取締役とすることは認められないと考えてください。
社会保険には入れるが国民保険より節税できるわけではない
「妻の国民保険の支払いが厳しいので、会社を妻名義で設立して社会保険に加入させ、役員報酬を最低限にすることで保険にかかる税金を安くしたい」と考える人もいますが、これは有効な手段ではありません。
たしかに社会保険料は月ごとの給与や報酬の額によって決まりますが、その基準となる「標準報酬月額」には下限があります。
たとえ役員報酬を月額数千円ほどにしても、5万8,000円以下の月収にかかる社会保険料はすべて同じ計算式で算出されます。
結果としてかかる社会保険料は月額で1.1万円ほど、設立した会社が支払う分も合わせると2.2万円ほどになります。
また、赤字であったとしても支払う義務がある「法人住民税の均等割」が年間7万円ほどかかります。
さらに設立にかかるコストや手間、その他諸々の経費を考えると、国民保険の場合とさほど変わらないか、ケースによってはより高額の納付が必要になるでしょう。
さらに肝心の厚生年金や、健康保険にまつわる出産手当金なども、元々の標準報酬月額が低いと受け取れる額も少なくなります。
結果として、手間がかかる割にそれほど効果的な節税にはなりません。
参考:標準報酬月額・標準賞与額とは?|全国健康保険協会 協会けんぽ
「第3号被保険者」に加入できるか確かめよう
妻の国民保険の支払いが難しいという場合は、「第3号被保険者」に加入すれば、保険料の負担がなくなります。
第3号被保険者に加入できる条件は、以下のとおりです。
- 日本国内に在住している
- 会社員・公務員などの「第2号被保険者」に配偶者として扶養されている
- 年収が130万円未満かつ厚生年金に加入していない
- 20歳以上60歳未満
第3号被保険者に加入する際には、配偶者の勤め先から届出を提出する必要があります。
条件を満たしているのに保険料を払い続けている場合は、まず配偶者の人事・総務担当に届出状況を確認しましょう。
正しい種別へ変更できれば、保険料を払わずに済むはずです。
家庭内トラブルの際に問題が大きくなりやすい
会社の実質的な運営を夫が行っているものの、社長は妻名義となっている場合、仮に夫婦間でトラブルがあって関係が悪化した際に、大きな問題に発展するリスクがあります。
会社の代表者は、単独でさまざまな契約を結んだり、資金を移動させる権限を持っています。
これが名目上のものであったとしても、実務上は妻がある程度自由にこれらの行為を行うことができます。
妻に銀行口座や法人印を押さえられてしまうと、資金の引き出しや契約変更を止められません。
妻名義で会社を設立する際は、関係が悪化した場合の対応もあらかじめ想定しておくべきです。
離婚したときの株式譲渡や、代表者をどちらにするかなどは、夫婦間であらかじめ公正証書で取り決めておくとよいでしょう。
妻名義で会社を設立する際のよくある質問
会社を妻名義で設立する人が疑問に思いやすい点や、よくある質問についてまとめました。
妻名義での会社設立に不安がある人は、ぜひチェックしてください。
妻の名義で会社を設立するのはそもそも違法なのか
会社を設立する際に、妻を名義上の代表取締役として登記すること自体は、法律上は違法ではありません。
しかし、さまざまなリスクや管理上の問題が生じるため、家族や親友間であっても「名義貸し」行為は行わないのが基本です。
もっとも、夫婦で事業に取り組んでおり、妻が自社の事業内容や経営に関してしっかりと理解して説明ができるのであれば、妻を代表にしてもまったく問題ありません。
代表者の選出は、「事業の実態に関わり、その内容を理解していること」が重要なポイントです。
妻が役員だと育休や補助金を受けられるのか
社長などの会社役員は、法律上は労働者として定義されていないため、労働基準法や育児介護休業法が適用されません。
育児介護休業法では、主に以下の4つの制度が定められています。
- 育児休業:1歳未満の子どもの育児のために取得可能
- 子どもの看護休暇:子どもの看護が必要な日に取得可能
- 介護休業:介護のために2週間以上の休業が必要なときに取得可能
- 介護休暇:介護が必要な日に取得可能
妻を社長、あるいは役員として会社設立した場合、これらの制度を利用できなくなってしまいます。
しかし、そもそも労働者でないということは「自分の労働時間や日数を自分で決められる」ということでもあるので、子どもが成長するまでの間は、柔軟に休みを取ることもできるでしょう。
また、役員であっても社会保険に加入しているのであれば、社会保険料の一時免除や出産手当金、出産育児一時金を受け取ることができます。
ただし、これらの制度は「出産・育児に伴う対象期間に仕事をしておらず、給与も出ていないこと」が要件となっています。
そのため、あらかじめ取締役会規程や役員報酬規程を作成し、そのなかで出産・育児期間中の休業の期間や、役員報酬が支払われない旨を定めておきましょう。


設立後に妻を解任して夫が代表になることはできるのか
代表者の変更は、決議したうえで登記変更などの手続きを行えば、基本的には問題なく実行できます。
しかし、代表者が変更したことで銀行の与信審査がやり直しになるなど、経営には大きな影響が出ます。
また、代表者の変更登記には「旧代表の実印と印鑑証明」が必要になります。
仮に妻が代表者の変更に応じなかった場合、変更登記が行えないという事態に陥るかもしれません。
この記事のまとめ
妻名義で会社を設立する場合、いくつかメリットもあるものの、関係が悪化した際の対応の難しさといったデメリットもあります。
また、妻が事業に一切関与しないのに名目上の役員になっていた場合、税務署からの追徴課税など、大きなリスクにもつながってしまいます。
妻名義で会社設立を行うのであれば、これらのリスクを考慮したうえで判断しましょう。
妻名義で会社を設立すべきか迷ったら税理士や司法書士に相談しよう
妻名義での会社設立は、夫婦で事業に取り組んでいるのであれば有力な選択肢ですが、そうでない場合は避けるべきです。
妻にしっかりとした実務の知識と経験があるとしても、役員報酬の額や出産などのライフイベントを考慮した社内規程の設定、税務署からの税務調査が来たときの対応などに不安を感じる人も多いでしょう。
妻名義での会社設立に悩みがあるときは、一度税理士などの会社設立の専門家に相談してください。
ベンチャーサポート税理士法人では、会社設立・運営に関する無料相談を実施しています。
税理士だけでなく行政書士や司法書士、社労士も在籍しているためワンストップで相談が可能です。
レスポンスの速さにも定評があるため、初めての方もお気軽にご相談ください。