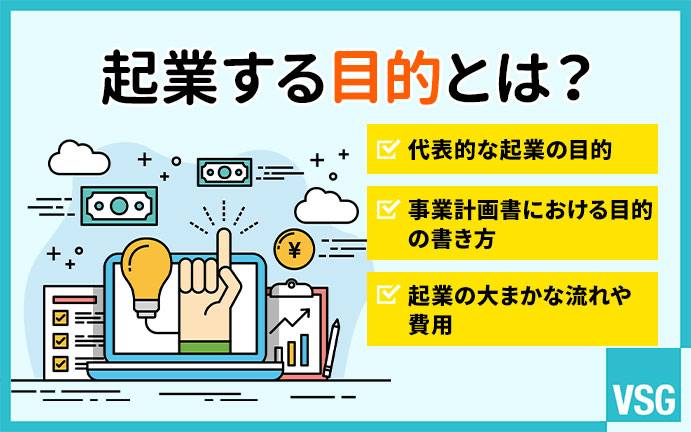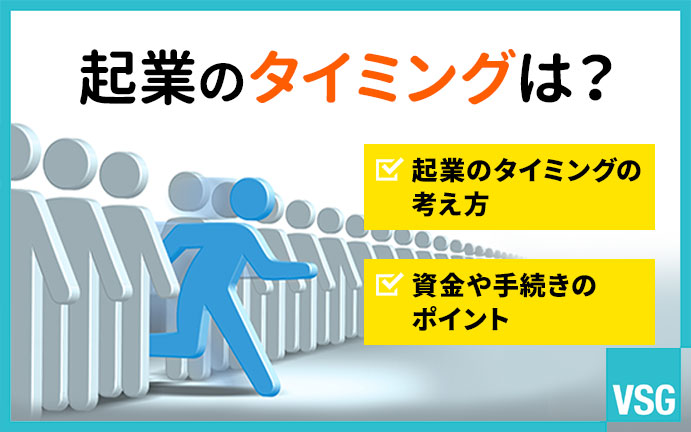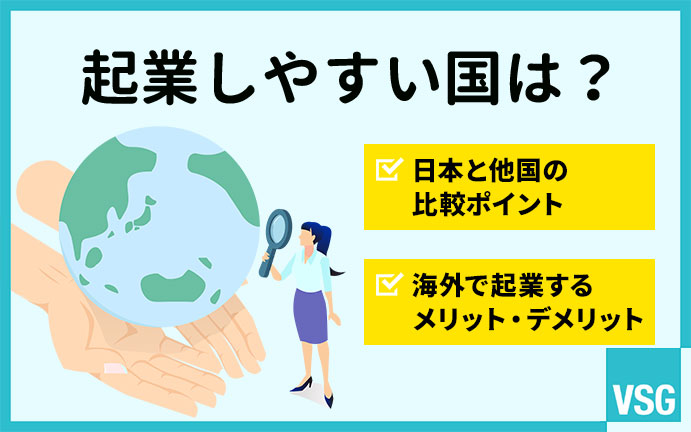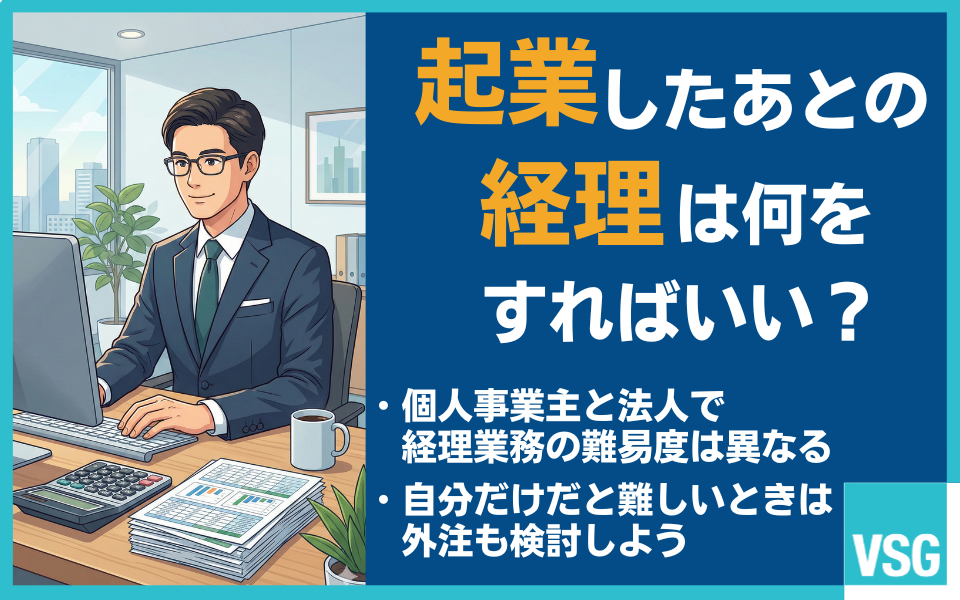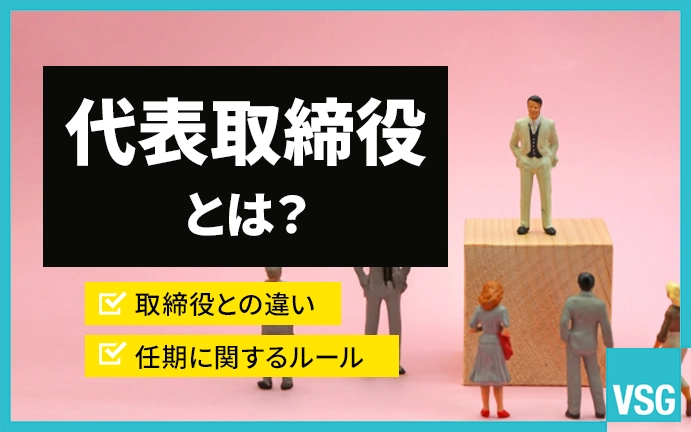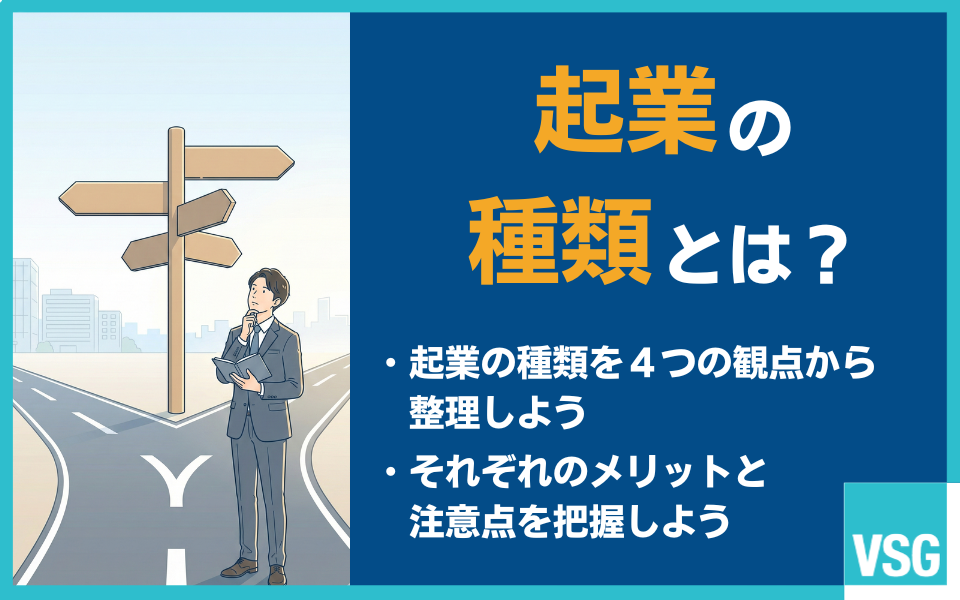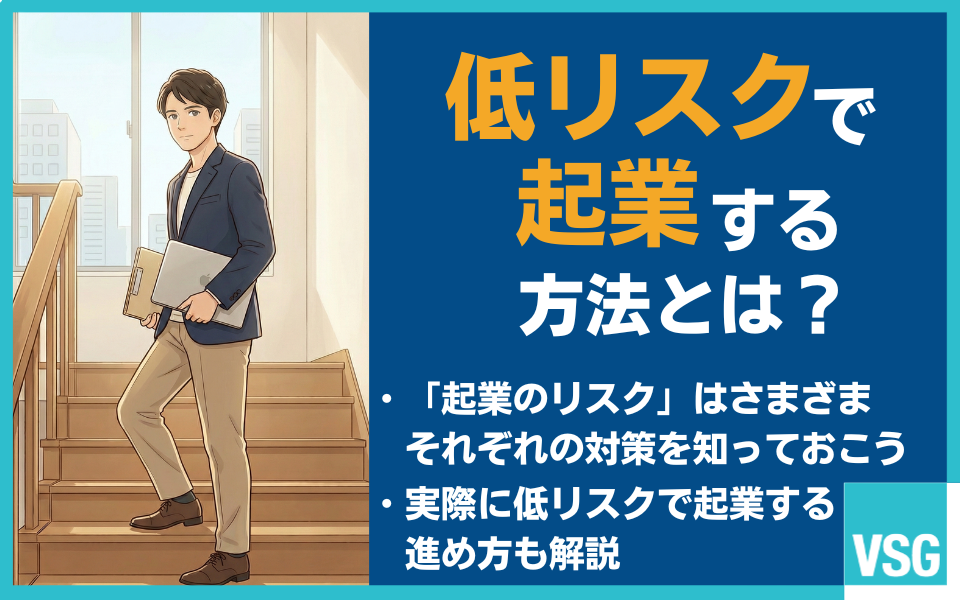最終更新日:2025/11/20
名義貸しで法人の代表になるのは危険!会社設立での名義貸しのリスクを解説

ベンチャーサポート税理士法人 大阪オフィス代表税理士。
近畿税理士会 北支部所属(登録番号:121535)
1977年生まれ、奈良県奈良市出身。
起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネルを運営。
PROFILE:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_writing/#p-mori
YouTube:会社設立サポートチャンネル【税理士 森健太郎】
書籍:プロが教える! 失敗しない起業・会社設立のすべて (COSMIC MOOK) ムック
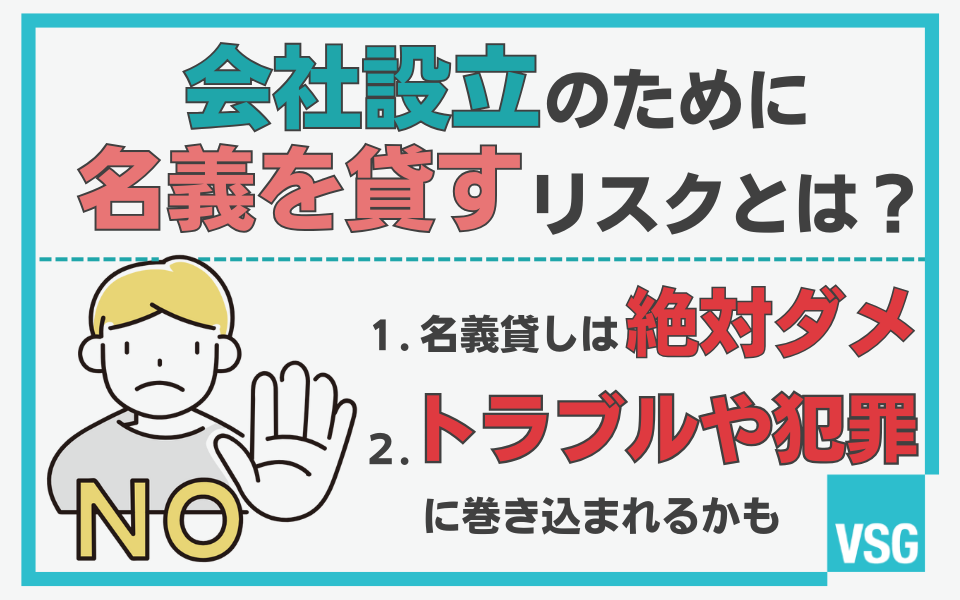
「会社を設立したいので、名義を貸して欲しい」
知り合いにこうした話を持ちかけられ、つい承諾してしまう人もいますが、これは非常に危険な行為です。
名義だけを貸して、実態のわからない会社の代表取締役などの役員になってしまうと、あとで訴訟や損害賠償、場合によっては逮捕されてしまうこともあります。
この記事では、会社設立のために名義を貸す行為のリスクについて詳しく解説します。
会社設立の名義貸しがなぜ行われるのか、その危険性や、実際に名義を貸してしまった場合の対処法などについても解説しています。
会社設立に関わる名義貸しで悩んでいる人は、ぜひ一度目を通してください。


目次
名義貸しでの会社設立は非常に危険
誰かに自分の名義を貸して会社設立を行い、その経営の実態には関わらない場合、税務上や刑法上でさまざまなリスクを背負うことになります。
名義を貸して、名目上だけ取締役や代表取締役になった人のことを名目的取締役と言いますが、その場合でも取締役としてのさまざまな義務や責任は免除されません。
取締役が負う責任には、主に任務懈怠責任と第三者責任、監視義務があります。
取締役としての責任1.任務懈怠責任
任務懈怠(けたい)責任とは、取締役がその任務を怠ったことによって会社に損害が生じた場合、その損害を賠償する責任のことです。
たとえば、明らかに不合理な投資などによって大幅な赤字となったり、何らかの法令に違反する行為をした場合、実際の業務を行わずに善良な管理者としての注意義務(善管注意義務)を怠った場合などが当てはまります。
取締役としての責任2.第三者責任
第三者責任とは、取締役が職務において悪意または重大な過失があったとき、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任のことです。
資金がなく支払いができないのに、商品を手形で購入するなどして取引先に損害を与えた場合や、詐欺的な投資勧誘を行った場合などに第三者責任が問われます。
また、取締役が経営や管理監督に関わらないといった任務懈怠によって会社に損害が生じ、結果として株主などの第三者に損害が生じた場合も、賠償責任が発生するものとされています。
つまり、名義貸しだけして取締役になったものの経営には全く関わらないというのは、それだけで第三者からの訴訟リスクを抱え込むことになるのです。
取締役としての責任3.監視義務
「名義を貸しただけで、自分は何も悪いことはしていない」という場合でも、同じ会社の取締役が会社または第三者に対して損害を与えた場合、ほかの取締役にもそれらを監視する義務があるとして、賠償責任が発生するケースもあります。
名目的取締役の場合、通常の取締役に比べて、監視義務違反が問題になったときの責任が軽くなる傾向がありますが、一定のリスクは存在します。
名義貸しが行われる理由
そもそもなぜ、わざわざ名義を貸し借りしたうえで会社設立が行われるのでしょうか。
想定できる事情をまとめてみました。
以前は株式会社設立に取締役が3人必要だった
旧会社法では、株式会社を設立する際には必ず取締役会を設置し、取締役を最低でも3人、監査役を1人選任しなければいけませんでした。
そのため、「どうしても株式会社を設立したいけれど、必要条件である取締役の人数が足りないので家族や友人から名義を借りる」といった、致し方ないケースも存在しました。
しかし、2006年5月1日に施行された新会社法によって、株式会社の設立に取締役会の設置は必須ではなくなりました。
これに伴って、設立時取締役の数も最低3人から1人に緩和されています。
現在でも取締役会を設置する場合は、取締役が3人以上必要です。
とはいえ取締役会は、中小企業のほとんどが設置していない機関です。複数名で起業するからといって必ず設置しなければいけないわけではありません。
「取締役会を設置したいから名義を貸してほしい」と言われたときは、取締役会がなくてもいいと知らないか、ほかの目的があると考えたほうがいいでしょう。
名義を借りる側がリスクを回避するため
法律に違反する事業やリスクの高いビジネス、クレームが多く出ることが予想されるような商売を行う際に、名義を借りる側がそれらの責任から逃れるために名義貸しを依頼してくることがあります。
ときには名義貸しを複数人に依頼していくつも会社を設立し、1つの会社で事業を続けられなくなったら、即座に別の会社で同じような事業を続けるといったケースもあります。
こうした場合、依頼者側は最初から名義貸しをした人に責任をなすりつける目的があるため、多くの場合で名義を貸した人は大きなトラブルに巻き込まれます。
銀行のブラックリストに載っていて、設立しても融資を受けられないため
クレジットカードやローンの返済の長期滞納や、自己破産などの債務整理を行った場合、銀行などの金融機関にはその情報が出回ります。
こうした履歴があると、いざ会社を設立しても銀行から融資を受けられなかったり、法人口座を開設できないといった不都合があります。
これらを回避するために、知人などに名義貸しを依頼するケースもあります。
架空外注の受け皿として利用するため
すでに会社を設立した人が、名義を借りて新しい会社を作り、実態のない業務委託契約を結ぶなどの「架空外注」のために利用するケースもあります。
架空外注の手伝いをしたとして、名義を貸した側も責任を追及される可能性もあるでしょう。
名義貸しをした場合のリスク
名義貸しを行った場合、非常に多くのリスクを負うことになります。
具体的なリスクの内容について解説します。
勝手な契約を結ばれる
名義を貸した際に、会社の代表者印や印鑑カードを相手に預けると、それらを利用して勝手な契約を結ばれる可能性が大いにあります。
名義を借りた側が会社を利用して詐欺を行い、そのまま逃げてしまった場合は、賠償責任や訴訟のリスクは名義を貸した人が背負うことになります。
また、会社の設立に必要だからと言いくるめられ、個人の実印まで預けてしまった場合は、
本人の預かり知らぬ所で連帯保証人になったり、多額の借金を背負わされてしまうといった事態に陥るかもしれません。
トラブルや犯罪に巻き込まれる
上記のとおり、名義貸しを依頼してくる側は何らかの犯罪や脱税行為を行う意図がある場合がほとんどです。
不用意にこれらの話に関わると、名義を貸した側も多額の賠償や刑事責任に問われる可能性があります。
名義貸しの範囲によっては貸した時点で犯罪になる
会社を設立する際には、事業内容によっては資格や実務経験が必要になることもあります。これらの条件を満たさない人に対して資格などを持った人が名義を貸すと、その資格に関わる法令に違反してしまいます。
また、銀行口座の開設や賃貸契約のための名義貸しも、犯罪収益移転防止法違反や詐欺罪に当たる可能性があります。
税務調査などにも対応しなければならない
たとえ名ばかりの社長だとしても、登記簿上で代表取締役となっている場合は、税務署からの税務調査や銀行からの審査に立ち会わなくてはいけません。
詳しい事業の内容について何も知らされていない場合、相手側からの質問に答えることは不可能です。
結果として名義貸しを行っていたこともバレるため、より徹底した調査が行われ、追徴課税や損害賠償責任が発生することもあります。
名義貸しをしてしまったときの対処法
会社設立での名義貸し自体は違法ではないものの、名義を借りた相手が行った行為によっては、貸した側も各種法律で定められた罰則を受ける可能性があります。
最悪の場合、犯罪行為を犯したとして逮捕されることもあるので、名義貸しをしてしまった際には慎重かつ迅速に対応しなければいけません。
まずは、こうしたトラブルに強い弁護士に相談し、状況を伝えましょう。
現状を把握したうえで、どのような対策を打つべきか、あるいは自首するべきかといったアドバイスを受けることができます。
また、会社設立は税金とも深く関わる行為ですので、税理士にも一度相談しておくといいでしょう。
名義貸しで設立してしまった会社の閉鎖方法
名義を貸していた相手と急に連絡が取れなくなり、自分名義の会社だけ残されるといったケースは決して少なくありません。
株式会社や合同会社などの法人は、一切活動していなかったとしても、年におよそ7万円の法人住民税の均等割という税金が発生します。
また、それまで何をしていたかもわからない会社の役員で居続けることは、後々のトラブルにも繋がります。
こうした場合は、会社の清算(閉鎖)を検討しましょう。
会社の清算にかかる時間と費用
会社の清算はすぐにできる作業ではありません。登記変更や清算人の選定、債権者保護手続きなど、さまざまな手順を経る必要があります。
特に債権者保護手続きは、公告と個別催告を行ってから最低2カ月の間、継続して行わなくてはいけません。
そのため、会社の清算はどれほど早くても2.5カ月から3カ月、もし訴訟や未納の税金の対応が絡んだ場合は1年以上かかることもあります。
また、解散登記と清算人登記、さらに清算結了登記を行う際にはそれぞれ登録免許税が発生します。
これに、解散を官報で知らせる場合の公告料などを合わせると、安くとも8万円前後の費用がかかります。
司法書士や税理士、場合によっては弁護士といった専門家に依頼をすると、さらに10万~20万円、ときにはそれ以上に高額な費用がかかることもあります。
状況によっては清算できないケースもある
名義を貸した相手が会社の株を持ち逃げした場合や、第三者に売却していた場合、知らぬ間にほかの役員が多数選任されていた場合などは、清算手続きを取れない事態もありえます。
会社の清算には、株式会社であれば株主総会の特別決議が必要になります。
これには総議決権の過半数が出席したうえで、出席株主の3分の2以上が賛成しなければいけませんが、株主構成や議決権の比率が不明な場合、このフローが踏めない可能性があります。
こうした場合、裁判所で特別な手続きが必要になることもあるので、まずは弁護士に相談しましょう。
会社設立の名義貸しでよくある質問
会社設立の名義貸しは、実際の業務でも相談件数が多く、悩む人が後を絶ちません。
よくある質問と、その回答をまとめたので、名義貸しについて悩んでいる方はチェックしてみてください。
名義貸しの際に「自分は責任を負わない」という契約を交わせば問題ないのか
たとえあらかじめ「会社の一切に責任を負わない」という契約を交わし、書面を作っていたとしても、それだけで責任を回避することはできません。
法律上、名義を貸した本人は「実質的に経営を監督・管理している」とみなされるため、契約書1枚で第三者(取引先や債権者、行政機関など)に対する責任まで消すことは不可能です。
また、会社法では株式会社に対する損害賠償責任の免除についても記載があり、そこでは株式会社に対する責任は、総株主の同意がなければ免除することができないとされています。
いずれにせよ、あらかじめ個人間で役員の責任配分などについて取り決めを行ったとしても、法律上はほとんど意味をなさないことが多いです。
親子や兄弟の間の名義貸しもやらないほうがいいのか
たとえ肉親相手であっても、名義貸しは避けるべきです。
法律上の責任は変わらないので、借りた側の行動によっては、貸した側が損害賠償や刑事罰を受けるリスクは発生します。
また、場合によっては名義貸しによって得た利益や資産が「贈与」とみなされることもあり、税務上や相続上のトラブルに繋がります。
前提として、名義貸しは本来行わなくてもいい行為です。
たとえ信頼できる相手から名義貸しを依頼されたとしても、不用意に承諾しないようにしてください。
名義を貸す側に何らかのメリットはあるのか
たとえ名義を貸して名目的取締役になったとしても、経営に参加した実態がない以上、何らかの社会的地位の向上などのメリットを受けることはできません。
ケースによっては、名義貸しを依頼する側から、月額数万の依頼料が支払われることもあります。
しかし、名義貸しをしたことによってトラブルに巻き込まれた際には、それ以上の費用が発生するでしょう。
銀行口座の管理などを経理担当に任せることも名義貸しになるのか
会社の運営や業務に深く関与し、経営実態があるうえで、その業務の一部を従業員に委託することは名義貸しには当たりません。
ただし、経理担当の個人口座に会社の資金をプールするなど、取引先や金融機関、税務署を欺く目的があった場合は、名義貸しと判断される可能性もあります。
何かあっても会社を清算すれば問題ないのか
たとえ会社を清算したとしても、個人の法的責任は残ります。
それまでに発生した税金の支払いなどは、多くの場合で名義を貸した人物が行わなくてはいけません。
訴訟を起こされた場合には、訴訟内容に対する責任を追及されますし、処罰を受ける可能性もあります。
会社の清算はあくまで「これ以上のリスクを抑えるため」であり、すでに発生してしまった事案に関しては、個別で適切な対応が求められます。
この記事のまとめ
会社設立の際に名義だけを貸してほしいと言われた場合、不用意に応じてしまうと、あとで思いも寄らないトラブルに巻き込まれるかもしれません。
名義貸しは通常は行う必要がなく、何らかの悪意があって依頼していることがほとんどです。
犯罪行為に利用されるケースも多いため、必ずその場では応じないようにしましょう。
万が一、断りきれずに名義を貸してしまった場合は、できるだけ早めに弁護士に相談し、対応を検討してください。
名義貸しについて悩んだら弁護士に相談しよう
家族や恋人、友人から会社設立のための名義貸しを依頼されたというケースは、現在も頻繁に発生しています。
しかしそれを承諾してしまうと、実態のわからない会社の責任を負うという、非常に危険な状態になってしまいます。
「つい名義を貸してしまったが、今後どうなるかわからなくて不安」「名義を貸していた相手と連絡が取れなくなってしまった」といった場合は、できるだけ早く弁護士に相談しましょう。