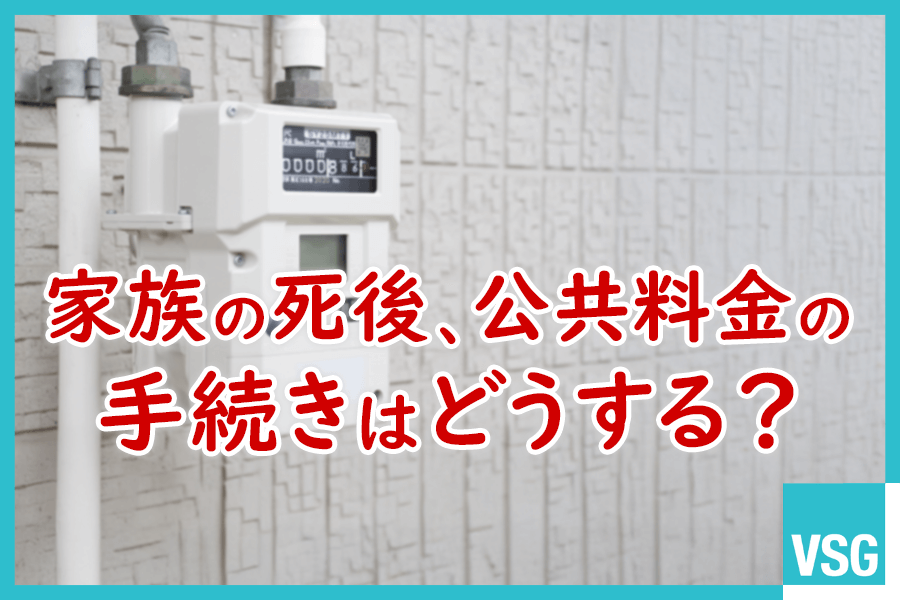記事の要約
- 公共料金の支払い関係では、その後の利用状況によって「名義変更」か「解約」の手続きが必要
- 電気・ガス・水道に加えて、クレジットカードや保険、サブスクなどの手続きも忘れないようにする
「家族が亡くなった後、公共料金の支払い関係では、どんな手続きが必要なの?」
このような疑問をお持ちの方へ向けて、本記事では「公共料金に関する手続きの流れ」や「手続きが必要なサービス一覧」をお伝えします。
なお、VSG相続税理士法人では、相続に関するご相談を無料で受け付けております。ご不明なことがございましたら、下記からお気軽にご連絡ください。
目次
相続発生時の公共料金に関する手続きの流れ
ご家族が亡くなられた後、公共料金に関する手続きは、下記の流れで進めましょう。
ここでは、ステップごとに詳しく見ていきます。
ステップ1:今後の方針を決める
故人が住んでいた家に「今後も、ご家族の誰かが住み続ける」か「誰も住まなくなるのか」によって、公共サービスの手続きの方針は、次のように変わります。
| 家の状況 | 手続きの方針 |
|---|---|
| 誰かが住み続ける | 亡くなった方から新しく利用する方に、契約者の「名義変更」の手続きをする |
| 誰も住まなくなる | サービスの利用を止める「解約」の手続きをする |
まずは、ご自身のケースでどのような手続きが必要なのか確認してみてください。
なお、今後の家の使い方が未定で、いったん空き家になる場合には「一時停止」という選択肢もあります。
一時停止の手続きをすることで、月々の基本料金の負担を軽くできることもありますので、各サービス会社に相談してみましょう。
ステップ2:手続きに必要な情報を探す
方針が決まったら、次は手続きをするために必要となる「サービス会社の名称」と「お客様番号(または契約番号)」の2つを特定しましょう。
これらは、「利用明細」や「使用量のお知らせ」といった故人宛の郵便物に記載されていることがほとんどです。
ただし、近年はペーパーレスを推奨しているサービス会社も増えてきています。
このため、故人のスマートフォン・パソコンを確認できるなら、メールやブックマークのなかから「サービス会社名」と「お客様番号」を探すのも有効です。
ステップ3:各サービス会社に連絡する
故人が契約していた「サービス会社名」がわかったら、その企業に連絡します。
電話やWebサイトから、「契約者が亡くなったため、名義変更・解約の手続きをしたい」と伝えてください。
このとき、あらかじめ調べておいた「お客様番号」を伝えると、手続きがスムーズに進みます。
その後は、サービス会社の担当者が「今後の流れ」や「必要書類」を案内してくれるので、それに従って手続きを完了させましょう。
相続発生後に手続きが必要なサービス一覧
ご家族が亡くなった際には、下記のようなサービスで、名義変更や解約の手続きをしなければなりません。
ご家庭によって、契約しているサービスはさまざまです。一つひとつ確認して、漏れがないように手続きをしましょう。
以下では、それぞれのサービスで必要な対応をお伝えします。
電気・ガス・水道の公共料金
生活に欠かせない「電気・ガス・水道」は、ほとんどのご家庭で手続きが必要です。
故人が契約していた電力会社・ガス会社と、お住まいの自治体の水道局へ、電話やWebサイトから連絡しましょう。
なお、ガスについては、解約や一時停止をする際に「閉栓作業の立ち会い」が必要になる場合があります。
クレジットカード
故人が使っていたクレジットカードは、不正利用を防ぐためにも、できるだけ早く手続きをすべきです。
カードの裏面に書かれている電話番号に連絡し、契約者が亡くなったことを伝えて、解約の手続きを進めてください。
なお、解約するカードで月々の支払いをしていたものは、すべて引き落としが止まるため、問題がないか事前によく確認しておきましょう。
住まいに関する契約
故人のお住まいに関する契約も、手続きが必要かどうか確認しましょう。
持ち家の場合は「火災保険」や「地震保険」、賃貸の場合は「家賃・管理費の契約」などで、名義変更などの手続きが必要になるケースがあります。
保険会社や管理会社に連絡をして、今後の手続きについて相談してみてください。
車に関する契約
故人が車をお持ちだった場合は、車に関連する契約も見直しましょう。
特に自動車保険は、車を今後もご家族が乗り続ける場合は「名義変更」、売却する場合には「解約」の手続きが必要になります。
また、駐車場を借りていたのであれば、管理会社に連絡して、必要な手続きを確認してください。
固定電話・携帯電話
ご家庭の固定電話や、故人が使っていた携帯電話(スマートフォン)も手続きが必要です。
手続きは電話やWebサイトのほか、携帯電話の場合はショップの窓口でも受け付けています。
なお、スマートフォンの端末を分割払いで購入していて、支払いが残っている場合、その残額は「債務」として相続の対象になります。
インターネット回線
ご自宅でインターネットを利用していたのであれば、プロバイダーや回線事業者への連絡が必要です。
解約する場合は、レンタルしていたルーターやモデムの返却が必要なケースもあるため、案内に従って忘れずに対応しましょう。
NHK受信料
見落としがちですが、NHKの受信料に関しても手続きが必要です。
引き続きご家族がテレビを見るのであれば「契約者変更」、誰も家に住まなくなってテレビもなくなる場合は「解約」の手続きをしましょう。
手続きの方法は、「NHKふれあいセンター」に電話すると、案内してもらえます。
定額制サービス(サブスクリプション)
最近は、月々や年単位で料金を支払う「定額制サービス(サブスクリプション)」を利用している方も増えています。
亡くなられた方も、次のようなサービスに加入している可能性があるため、特定して解約の手続きをしなければなりません。
| 種類 | 具体的なサービス名 |
|---|---|
| 有料テレビ放送 | スカパー!、WOWOW、J:COM(ケーブルTV) など |
| 動画配信サービス | Netflix、Amazonプライム、Hulu、Disney+、U-NEXT、NHKオンデマンド など |
| 音楽配信サービス | Apple Music、Spotify、Amazon Music Unlimited、LINE MUSIC など |
| 新聞・雑誌サービス | 各新聞・雑誌の定期購読、dマガジン、楽天マガジン など |
これらはクレジットカードの利用明細や銀行の引き落とし履歴から、契約の有無を確認できます。
公共料金などの相続手続きをする際の注意点
実際に、公共料金などの手続きをする際は、下記の2点に注意が必要です。
それぞれについて、詳しく見ていきましょう。
注意点1:「口座凍結」の手続きとセットで進める
故人が亡くなった際には、預金を守るために金融機関の口座を「凍結」することが一般的です。
口座が凍結されると、その口座からの引き落としはすべてストップします。
このため、電気・ガス・水道などのサービスを今後も使い続ける場合、引き落とし口座を変更していないと、支払いが滞ってしまいます。
そこで、「口座凍結の手続き」と「公共料金などの手続き」は、問題が発生しないように注意しながら、同時進行で進めるようにしましょう。
注意点2:「故人の預金」から未払い料金を払わない
故人に借金が多く、「相続放棄」を検討している場合は、未払いの公共料金などを「故人の預金」から支払わないことをおすすめします。
これは、故人の預金に手をつけると、「借金も含めたすべての財産を相続する意思がある(単純承認)」と見なされ、相続放棄ができなくなるおそれがあるからです。
そこで、未払い料金を支払う際は「相続人自身のお金」から支払うようにしましょう。その際に立て替えたお金は、遺産分割協議で精算できます。
公共料金などの相続手続きに関するよくある質問
最後に、公共料金などの相続手続きに関して、よくある次の質問にお答えします。
Q1:手続きはいつまでに済ませるべき?
公共料金などの相続手続きには、法律で定められた明確な期限はありません。
しかし、支払いが滞ってサービスが止まってしまったり、連絡が遅れて余計な基本料金を払い続けたりすることを避けるためにも、気づいた時点ですぐに着手することをおすすめします。
Q2:契約しているサービスが全部わからないときは?
まずは、故人宛の郵便物や預金通帳、スマートフォンのメールなど、基本的な手がかりを探してみましょう。
それでも契約していたサービスが不明な場合、最終手段として「銀行口座の凍結とクレジットカードの解約を先に進めてしまう」という方法もあります。
これにより、引き落とし先を失ったサービス会社から、新たな支払い方法を求める通知や請求書が届くため、そこで故人が使っていたサービスを把握できます。
Q3:「お客様番号」などが書かれた書類が見つからないときは?
「お客様番号」などが書かれた書類が見つからなくても、手続き自体は可能です。
サービス会社に電話で「お客様番号がわからない」旨を伝えれば、故人の氏名・住所・電話番号といった情報で本人確認を行い、手続きを進めてくれるケースがほとんどです。
公共料金などの手続きは漏れなく済ませましょう
本記事では、ご家族が亡くなった際の公共料金などの手続きについて紹介しました。ここでお伝えしたことを一つひとつ確認しながら進めていけば、手続きは決して難しいものではありません。
しかし、ご家族が亡くなって間もないなかで、各手続きを進めるのは、精神的な負担になることもあります。
そこで、相続手続きに関してお困りのことがございましたら、一人で抱え込まずに専門家の力も上手に借りることをおすすめします。