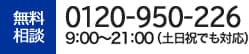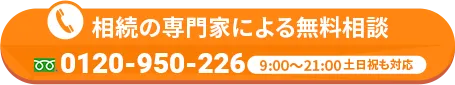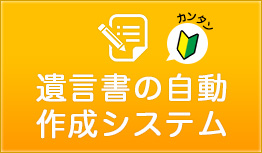この記事でわかること
- 認知症であっても、遺言書は直ちに無効とはならない
- 遺言書の有効性を判断するときのポイント
- 認知症の人が遺言書を作成するときのポイント
- 遺言が有効か無効か、疑問に思ったときの対応
認知症だった親が生前に遺言書を残していた場合、その遺言書は有効なのでしょうか。
そもそも、認知症になった後に遺言書を作成することはできるのでしょうか。
認知症の人が書いた遺言書は、さまざまな情報をもとに有効性を判断します。
また、遺言書の有効性を巡り、当事者間でトラブルが起こる可能性もあります。
今回は、認知症の人が書いた遺言書の有効性を判断するポイントや、認知性の人が遺言書を作成する際のコツ、「遺言書が無効では」と思ったときの対応について解説します。
目次
認知症であっても、遺言書は直ちに無効とはならない
「遺言」とは、遺言者(遺言を残す人)が、自分が亡くなった後の財産について「誰にどのように遺したいか」意思表示をすることです。
また、自分の死後に財産をどのように分けるか指定した書類のことを「遺言書」と言います。
民法では、満15歳以上で、かつ遺言能力があれば誰でも遺言を残せると定めています。
(遺言能力)
遺言能力(条文)
第961条 15歳に達した者は、遺言をすることができる。
第963条 遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない。引用元 e-Gov法令検索
認知症の人でも、年齢基準を満たしており、かつ遺言事項を判断する能力があれば、法律上有効な遺言書を作成することができます。
そのため、遺言者が認知症だからといって、直ちに遺言書が無効だとは判断できません。
なお、遺言書が有効か無効か、判断をするのは裁判官です。
裁判官は、遺言書が作成された時点の状況を精査したうえで、遺言者の遺言能力の有無を総合的に判断します。重度の認知症と診断されていた場合でも、一概に「遺言書は無効」になるとは限りません。
過去には、認知症が相当進んでいたにもかかわらず、他者とのコミュニケーション能力などが勘案され「遺言書は有効」と認められた事例もあります。
判例
京都地方裁判所判決/平成12年(ワ)第2475号(公正証書遺言無効確認等請求事件)
裁判所の判断:遺言書は有効である
- 長谷川式簡易知能評価スケール(※後述)による検査結果では4点(非常に高度な痴呆※)という結果が出ていた。
- しかしながら、看護婦※と交わした会話の内容をみると、遺言作成当時、他者とのコミュニケーション能力や、自己の置かれた状況を把握する能力を相当程度保持していたと考えられる。
- ※
- 判決文のまま
遺言能力とは何か
「遺言能力」とは、遺言の内容を理解し、自分が遺言を残した場合の結果を適切に判断できる能力のことです。
また遺言を残すには、自分の法律行為や結果を理解し、正常に意思決定を行える能力である「意思能力」が必要です。遺言能力は意思能力の一種であり、遺言者に遺言能力がない場合、その遺言は無効となります。
認知症の人が遺言書を残していた場合は、遺言能力の有無を精査した上で、遺言書の有効性を判断します。
遺言書の有効性を判断するときのポイント
認知症の人が作成した遺言書の有効性は、具体的にはどのように判断するのでしょうか。
認知症の人が作成した遺言書は、さまざまな判断材料から客観的・総合的に有効性を判断します。
- 医師の診断書や当時の介護記録を確認する
- 遺言書の内容を理解しているか確認する
- 遺言書の内容が合理的か確認する
- 遺言書作成の動機や経緯を確認する
医師の診断書や当時の介護記録を確認する
遺言者に認知症の症状があった場合は、医師による診断書や当時の介護記録を参考に遺言能力を推察します。
主な確認事項
- 医師によるカルテや診断書があるか
- 精神的医学疾患があったか。精神的医学疾患があった場合、どの程度・頻度で症状が出ていたのか
- 介護サービスは受けていたか。介護サービスを受けていた場合、当時の介護記録にはどのように記載されているか
医師によるカルテや診断書に認知症の症状に言及する記録が残っていたり、脳が萎縮して認知症が進んでいることが分かるMRI検査画像が残っていたりする場合は、「遺言者には遺言能力はなかったのではないか」という疑いが強まります。
介護の必要性の程度を表す「要介護度」や、介護保険のサービスを受けた際に書かれた介護記録の内容も、遺言者の遺言能力の有無を判断する材料になります。
判例
東京地方裁判所判決/令和2年(ワ)第3325号
裁判所の判断:遺言書は有効である
- 遺言書作成当時、認知症の影響により、判断能力、弁識能力、意思伝達能力が著しく減退していたとまで認めるのは困難というべき。
- 遺言書作成当時、遺言能力を欠いていたとまでは認めがたく、他にこれを認めるに足りる証拠はない。
「長谷川式認知症スケール」での検査について
「長谷川式認知症スケール(改訂長谷川式簡易知能評価スケール:HDS-R)」とは、認知症の疑いはないか、認知症の場合はどの程度の症状かを調べられる、簡易的な検査です。
日本の多くの医療機関で、信頼性の高い認知機能テストとして用いられています。
長谷川式認知症スケールは合計30点満点の検査であり、点数が20点以下の場合は認知症の疑いがあると判断されます。
一概には言えませんが、点数が10点以下の場合は重度の認知症として「遺言能力がない」と判断される可能性が高いです。
長谷川式認知症スケールのほかにも、認知症の検査には「ミニメンタルステート検査(MMSE)」や「認知症機能評価別病期分類(FAST)」などが用いられています。
遺言書の内容を理解しているか確認する
遺言能力の有無を判断するには、遺言書を作成した当時、遺言者は遺言書の内容を理解していたかどうかも確認します。
例えば「すべての財産を長男A男に相続する」といった単純な遺言内容であれば、遺言者は遺言書の内容を理解していたと判断される可能性が高まります。
一方「A市にある土地は長男A男に相続する」「B銀行にある預金は長女B子に相続する」など、複数の相続人に対して複数の財産を指定している遺言書を残すためには、高い遺言能力が必要です。
重度の認知症であるにもかかわらず、遺言書の内容が細かく複雑であったことから「遺言者は遺言の内容を理解、判断することはできない」として、遺言書は無効であると判断された判例もあります(東京高等裁判所平成12年3月16日判決)。
遺言書の内容が不自然でないか確認する
遺言者の普段の言動や交流関係と、遺言書の内容との整合性が取れているかも、遺言能力の有無を判断する際には考慮します。
例えば、遺言者が普段から「A市にある土地は長男A男に渡す」と発言しており、遺言書にも同様の内容が記載されていたとします。この場合は、言動と遺言書の内容が一致しているため、遺言内容は不自然ではないと判断されやすいでしょう。
一方、遺言者の普段の言動と遺言書の内容が一致していない場合は、遺言書は無効と判断されることがあります。
また遺言書が不自然なほど何度も書き換えられたり、内容も大きく変更していたりする場合は、不合理であるとされることもあります。
判例
東京地方裁判所判決/平成31年(ワ)第8489号
裁判所の判断:遺言書は有効である
- 生前の言動と異なる遺言書が残されていたが、遺言者の交流の状況を踏まえると、遺言内容が相続に関する被相続人の意向を示すものとして不自然であるとか不合理であるということはできない。
遺言書作成の動機や経緯を確認する
専門家に相談を積み重ねてきた履歴や経緯、相談内容が分かるメモも、遺言書の有効性を判断する材料になります。
遺言書と同じ内容の自筆メモが残されている場合、遺言者には適切な遺言能力があり、自らの意思で遺言書を作成したと判断される可能性が高まります。
成年被後見人でも遺言書を作成できる場合がある
「成年被後見人」とは、精神上の障害により判断能力を欠くとして、家庭裁判所から後見開始の審判を受けた人のことです。認知症などにより判断能力が欠けているのが通常の状態にある場合は成年被後見人の認定を受け、財産管理や身上監護などの支援を受けることができます。
原則として、成年被後見人には遺言能力はありません。
しかし以下の要件を満たした場合は、成年被後見人でも遺言能力が認められ、遺言書を作成できる場合があります。
(成年被後見人の遺言書)
第973条 成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、医師二人以上の立会いがなければならない。
2 遺言に立ち会った医師は、遺言者が遺言をする時において精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記して、これに署名し、印を押さなければならない。ただし、秘密証書による遺言にあっては、その封紙にその旨の記載をし、署名し、印を押さなければならない。引用元 e-Gov法令検索
成年被後見人が、事理弁識能力を一時的にでも回復した場合は、遺言書を作成することができます。
遺言書を作成する場合は、必ず医師2人以上が立ち会わなければなりません。
遺言書作成に立ち会った医師は、「遺言者には、遺言書作成時において事理弁識能力があった」旨を遺言書に付記し、署名捺印をします。
認知症の人が遺言書を作成するときのポイント
認知症の人が遺言書を作成する場合は、希望どおりの相続がされるよう生前に対策をしておきましょう。
ここからは、認知症の人が作成した遺言書が無効と判断されないよう、作成時のポイントを紹介します。
- 遺言能力のあるうちに遺言書を作成する
- 公正証書遺言を作成する
- 遺言書の内容をシンプルにする
- 認知症検査をする
- 遺言能力を証明する資料を保管しておく
- 遺言執行者を指定する
遺言能力のあるうちに遺言書を作成する
最善の方法は、認知症と診断された場合でも遺言能力があるうちに遺言書を作成しておくことです。
認知症の症状が進んでから遺言書を作成した場合は、有効性に疑義が生じる場合があります。そのため、できる限り早めに遺言書を作成しましょう。
公正証書遺言を作成する
「公正証書遺言」とは、法律の専門家である公証人が作成する遺言書です。
遺言者は遺言の内容を口授し、公証人が筆記する形で作成します。
公正証書遺言は、公証人が本人の意思を確認する点で証拠能力が高く、また内容が明確な遺言書を作成できます。
ただし公正証書遺言であっても、認知症の人による遺言書が必ずしも有効と判断されるわけではありません。公正証書遺言の形式で作成された遺言書が「無効」とされた事例もありますので、他の方法も活用しながら遺言書を作成していきましょう。
判例
名古屋高等裁判所判決/平成13年(ネ)第376号(遺言無効確認請求控訴)
裁判所の判断:遺言書は無効である
- 遺言書作成について、遺言者が公証人に対して遺言の内容を口授していない(控訴人の当審主張)。
- 遺言者に、自らの死後のことを自ら考慮し、何らかの形で自らの相続の意思を示しておかなければならないと考える精神的能力があったとは考えられず、また、遺言書に署名捺印するという行為の意味を正しく理解できる精神状態にあったとは考えられない。
遺言書の内容をシンプルにする
認知症の人が複雑な内容の遺言書を残した場合、「この遺言書は誰かに書かされたものではないか」といった疑いを持たれる可能性があります。
過去には、遺言者が重度の認知症であるにもかかわらず、複雑な内容の遺言書が作成されていたことから「遺言書は無効である」と判断された事例もあります。
そのため、遺言書は短い文章で簡単な内容で作成したほうが無難です。
シンプルな内容であれば、遺言書の内容を理解して作成したものだと判断されやすいでしょう。
認知症検査をする
認知症になった後に遺言書を作成する場合は、改めて認知症検査を受けておきましょう。
診断書に「他者とのコミュニケーションが取れている」といった記載があれば、遺言能力があると判断されやすくなります。
また認知症の症状が進んでいた場合でも、認知症の検査日と、遺言書の作成日を照合することで、遺言書作成当時には遺言能力があったと証明できます。
なお、遺言書を作成した後に認知症を発症した場合、悪意のある相続人や第三者によって新しい遺言書が偽造される可能性もあります。
通常、遺言書は日付の新しいものが優先されます。しかし遺言書の有効性に疑いが生じた場合、認知症の診断履歴や医師の診断書は、どれが有効な遺言書か判断するうえで大切な証拠になります。
遺言能力を証明する資料を保管しておく
遺言者に遺言能力があったことを証明するには、遺言書を作成する様子を録画・録音に残しておく方法もあります。
また、遺言者の普段の言動や、遺言書を作成する動機や経緯を記録・保存しておくことで、遺言書には合理性があるという証拠になります。
公正証書遺言で遺言書を作成する場合は、公証人と意思疎通ができていたことが 分かるような資料を残しておきましょう。
遺言執行者を指定する
「遺言執行者」とは、遺言内容を実現するために必要な手続きを行う人です。遺言書で指定された人が遺言執行人の役割を担いますが、家庭裁判所が遺言執行者を選任するケースもあります。また、相続人を遺言執行者に指定することもできます。
遺言執行者は、遺言書の内容に従い、相続財産の管理や名義変更、預貯金の払い戻しなどの相続手続きを行います。
認知症の症状が進行した場合、意思疎通が図りにくくなることも考えられます。
遺言能力のあるうちに遺言書を作成し、遺言執行者を指定しておくことで、生前に希望していた内容でスムーズに相続の手続きを進めることができます。
【 参考】家族信託について
「家族信託」とは、家族に財産の管理を任せる信託契約のことです。
認知症になると預貯金の引き出しや口座解約などができなくなりますが、代わりに家族が財産を管理することができます。
原則として、認知症の人は家族信託を結べません。しかし契約内容を理解できる場合など、認知症の程度や症状によっては利用できることがあります。
認知症の人が家族信託を検討する場合は、後日契約の成立を争うことがないように、公正証書での作成がより適切です。
なお、家族信託を結べない場合は「成年後見人制度」を利用して財産管理を任せることができます。
信頼できる家族に、財産管理を任せることができる家族信託。認知症のリスクの備えとして、知っておきたい方法の一つです。
遺言が有効か無効か、疑問に思ったときの対応
生前の言動と明らかに異なっていたり、意思疎通ができないはずなのに複雑な内容の遺言書が見つかったりした場合、「この遺言書は無効ではないか」と疑うケースもあるでしょう。
ここからは、偽造が疑われる遺言書が見つかった場合の対応を紹介します。
法定相続人全員で協議し、遺言書の内容を変更する
遺言書の内容を変更したい場合は、法定相続人全員で遺産分割協議をします。そこで法定相続人全員が合意すれば、遺産分割の内容や割合を変更できます。
法定相続人以外の第三者に遺贈がされている場合は、受遺者(遺贈をされた人)にも遺産分割協議に参加してもらい、合意を得る必要があります。
ただし、遺言書で遺言執行者が選任されている場合には注意が必要です。遺言執行者には、遺言書に記載されている内容を実現する義務があるためです。
遺言執行者がいる場合に遺言書の内容と異なる遺産分割をする際は、遺言執行者の同意も必要です。
遺言無効確認調停・訴訟を起こす
当事者間の協議で折り合いがつかない場合は、裁判所で遺言書の有効性を争います。
遺言の無効を主張したい場合、法定相続人や受遺者は、家庭裁判所に対し「遺言無効確認調停」を申し立てます。調停では、仲介役である調停委員の助言を得ながら合意に向けた話し合いをします。
調停でも解決しない場合、地方裁判所に対し「遺言無効確認訴訟」を起こします。訴訟を起こした人は、法廷の場で「遺言者に遺言能力はなかったという証拠」を提出し、遺言書の無効を主張します。
証拠となる材料には、遺言者のカルテや診断書、介護記録などがあります。また遺言書が偽造された可能性がある場合は、筆跡鑑定が行われることもあります。
訴訟の結果、遺言書は無効と判断された場合は、改めて遺産分割協議を行い、遺産を分配します。
遺言書の有効性が疑われた場合、すべての相続が終わるまでには多くの時間と労力がかかります。
トラブルを防ぐためにも、遺言能力のあるうちに遺言書を作成し、相続に向けた対策や準備をしておくとよいでしょう。
認知症の人からの相続については専門家に相談しよう
遺言書の有効性は、遺言者の遺言能力の有無で判断されます。
遺言能力の有無は、さまざまな観点から総合的に判断していきます。
認知症の人でも遺言能力があると認められるケースもあります。認知症は個人差が大きいため、検査結果だけでは、遺言能力は判断できません。
認知症検査では同じ点数でも、遺言能力の有無では判決の結果が異なる事例もあります。
また、認知症になった後に遺言書を作成する場合は、無効な遺言書と判断されないための対策が必要です。
相続に関する専門家に相談をしながら、遺言能力を証明する資料を多く揃えましょう。
相続専門税理士の無料相談をご利用ください

ご家族の相続は突然起こり、何から手をつけていいか分からない方がほとんどです。相続税についてはとくに複雑で、どう進めればいいのか? 税務署に目をつけられてしまうのか? 疑問や不安が山ほど出てくると思います。
我々VSG相続税理士法人は、相続人の皆さまのお悩みについて平日夜21時まで、土日祝も休まず無料相談を受け付けております。
具体的なご相談は無料面談にて対応します。弊社にてお手伝いできることがある場合は、その場でお見積り書をお渡ししますので、持ち帰ってじっくりとご検討ください。
対応エリアは全国で、オフィスは東京、埼玉、千葉、横浜、名古屋、大阪、神戸、福岡の主要駅前に構えております。ぜひお気軽にお問い合わせください。