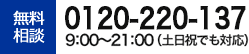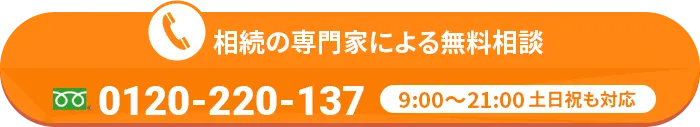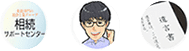目次
相続放棄とは、身内が亡くなって残された財産(プラスのものも、借金のようなマイナスのものも)を相続できる法定相続人に該当する人が、亡くなった人の財産を一切受け取らない(義務は負わない)と家庭裁判所に申し出ることをいいます。
相続放棄の手続きを行えるタイミングは、身内が亡くなったことを知った日から3カ月以内です。そのため、生前に相続放棄をすることは不可能です。
ただ、「相続放棄」の用語は法律的に正しく用いられることは少なく、多くの方は「相続財産を一切受け取らない意思表示」という意味的な解釈をしています。
自分自身が相続財産を一切受け取りたくないということをゴールに考えると、相続放棄以外に実質的に目的を達成できる行動の余地があるのも事実です。
事前にどういった工夫をしておけば、遺産相続に加わらなくて済むか、この記事で解説しますので確認してみてください。
取り得る方法(1)遺留分の放棄
遺留分とはわかりやすくいうと、相続人に法律上守られた最低分の相続権です。
父や母・祖父母のような直系尊属は3分の1、配偶者や子には2分の1の遺留分があります。
遺言や生前贈与等があって自分の相続分がキープできないような場合に遺留分減殺請求という形で問題が起こるのですが、この遺留分を放棄することで生前の相続放棄に近い効果を得ることが考えられます。
ただ、この遺留分の生前放棄には被相続人の生存中に家庭裁判所の許可を受けることが必要となります。
申立をする人は遺留分を放棄したいと考えている推定相続人です。
この手続きは死後に相続放棄の手続きをするよりもレアなケースであり、家庭裁判所の審問等が予定されています。
難航することが予想されるので弁護士等の専門家に依頼する方が良いと思います。
また、遺留分の放棄をたとえ手続きして家庭裁判所の許可を得たとしても、通常の相続はできます。
遺言等で誰かに相続や遺贈等が行われた場合には遺留分減殺請求ができないという法律効果は発生しますが、そのようなものがなければ相続できるという結論になります。
死後に行う相続放棄は全く相続できないのに対し、ニュアンスが異なるので注意してください。
取り得る方法(2)遺言の作成
法定の相続を修正するものとして遺言があります。
遺言があると、法定相続分に則った相続よりも優先されるので、これを作成してもらうことで相続放棄に近い結論を得ることができます。
ただ遺言の作成は被相続人自身で作成してもらう必要があります。
公正証書で遺言をすることも考えられますが、それも遺言者自身の意思が必要です。
本人の代わりに作成した遺言は無効ですから、本人の関与なくしてこの手続きを進めることはできません。
また遺言はプラスの財産を相続したくないような場合は有用ですが、債務等のマイナスの財産については遺言で指定することはできません。
もっとも「すべてを○○に相続する(遺贈する)」というような包括遺贈の場合は、マイナスの財産も含めてその受遺者に引き継がれることが想定できますが、他のプラスの財産のみを記載した遺言であれば、マイナスの財産は通常の法定相続に則って継承されていきます。
プラスの財産が要らないような場合は有用ですが、マイナスの財産は遺言で指定することは難しいのが実情です。
取り得る方法(3)被相続人の債務整理
これも被相続人の生前にしてもらう必要がありますが、被相続人の債務を生前に整理してもらうのです。
借金等が多くて返済が苦しいような場合は、法律事務所や司法書士事務所に依頼して債務の整理を始めましょう。
債務整理を専門家に依頼すると、債務整理開始通知が債権者に届いた時点で債権者からの督促が止まります。
それだけでも心理的な負担は大きく緩和されるのではないでしょうか。
法律専門家がその間することは、依頼者の負債がどれだけあり、どれだけの支払の原資があるのかという調査です。
その結果、債務整理をする方針を相談者と確認し決定します。
主な内容は、
- A.任意整理
- B.過払返還
- C.民事再生
- D.破産
です。
おおよそ収入がどれだけあって支払可能な金額はどれ位あるのか、その金額を約36カ月(3年)元金分割で支払って返済できるのかが大きなポイントになります。
これで支払ができるのであれば任意整理、できなければ破産を選ぶ方向になります。
過払返還は最近は少なくなりましたが、法律で定めた以上の利息を取っていた場合は、法定利率で再計算していくと利息・元金が減り、元金が残っていない場合に起こる事象です。
この場合は貸金業者に過払返還の交渉や裁判を専門家に依頼することになります。
このような方法で、被相続人の生前に債務の整理をしていただければ生前の放棄に近い状態になります。
ただ、これは先ほどの遺言作成と同様、本人の関与なしには進められません。
また依頼した際に債権者の漏れがあると、そこからは督促もありますのでご注意下さい。
相続放棄

ここまで生前に相続の放棄はできるのか、その方法について検証してきました。
それぞれの対策を行うことである程度の効果は得られるのですが、被相続人の死後に行う相続放棄の手続きに比較すると、完全な被相続人の相続権放棄は得られない点をご理解いただけたかと思います。
それでは、相続放棄の手続きについて説明していきたいと思います。
相続放棄とは、被相続人が亡くなったことを知ったときから3カ月以内に家庭裁判所に申述をする手続きを言います。
この申述が家庭裁判所で受理されたら相続人ではなかったことになります。
そのためプラスの財産もマイナスの財産も相続することはできません。
それでは、相続放棄の具体的な手続きについて見ていきましょう。
管轄
まず管轄は被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所です。
例えば、被相続人の住んで居たところが東京、死亡地が大阪、相続人の住所地が名古屋の場合の管轄は東京になります。
必要な書類
必要な書類を記す前提として相続の順位について説明します。
相続の順位は、(1)子や孫、(2)父や母、祖父母、(3)兄弟姉妹です。
配偶者は常に相続人となります。
そして(1)が死亡したり相続放棄をしたような場合は(2)が相続人となり、(2)が死亡したり相続放棄をしたような場合は(3)が相続人となります。
(1)が居るのに(2)や(3)が相続放棄をしようとしても、その手続きは認められません。
また誰が相続放棄するかによって、必要となる書類が変わってきます。
まず誰が手続きをしても必要となる書類から、相続順位に従って説明していきます。
(1)共通書類
- ・相続放棄の申述書
※家庭裁判所のホームページからダウンロードできます。 - ・被相続人の住民票除票または戸籍付票
- ・放棄する人の戸籍謄本
(2)放棄する人が配偶者の場合
- ・被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本
(3)放棄する人が子または孫の場合
- ・被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
- ・放棄する人が孫(代襲相続人)の場合、本来の相続人である子が死亡した旨の記載がある戸籍謄本
(4)放棄する人が父母・祖父母の場合
- ・被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本
- ・被相続人の子や孫が死亡している場合は、その旨の記載がある戸籍謄本
- ・祖父母が相続放棄する場合は、被相続人の父や母が死亡している旨の記載がある戸籍謄本
(5)放棄する人が兄弟姉妹の場合
- ・被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本
- ・被相続人の子や孫が死亡している場合は、その子や孫の出生から死亡までの戸籍謄本
- ・被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本
- ・放棄する人が甥や姪の場合、その親(被相続人の兄弟、甥姪の親)の死亡の記載のある戸籍謄本
ここまで必要な書類を列挙してきました。
ちなみに戸籍謄本とありますが、戸籍とは一言でいっても除籍謄本・改製原戸籍等の種類があります。
ここで「出生から死亡までのすべての戸籍」と記載されているものは除籍や改製原戸籍を含みます。
これらの書類が求められるのは相続人が他に居ないのかを調べるためです。
また、謄本と抄本の違いは何か?という問題もありますが、謄本は戸籍に書いてある者全員の記載があるものに対し、抄本は請求した人の筆頭者と請求した人のことしか書いていない書類です。
相続放棄で必要となるのは概ね謄本と思っていただいて良いでしょう。
また印紙は一人につき800円です。
切手は家庭裁判所毎に内訳が違いますので、申立前に事前に家庭裁判所で確認して下さい。
大抵の家庭裁判所には中で印紙と切手を購入できますので、申立と同時に購入して納めることができます。
申立を済ませると
必要書類をそろえて家庭裁判所で相続放棄の申立を行ったとします。
ちなみに相続放棄の申立は郵送で行うこともできます。
そうすると事件の受付がなされ、1カ月ほどすると家庭裁判所から相続放棄の意思を問う書面が送られてきます。
期限が記載されていますので、その期間内に提出しましょう。
最初に提出した申述書と概ね同じ内容の質問です。
それを返送し、しばらくすると相続放棄の受理通知が送られてくることが多いです。
この受理通知が届くと相続放棄の手続きは終わります。
なお、相続放棄の手続きで家庭裁判所に出頭が求められることは、通常のケースでは少ないです。
また、債権者の中には相続放棄の申述受理証明書を要求してくるところがあります。
この申述受理証明書は相続放棄の手続きをした家庭裁判所が発行する書類で、運転免許証のコピーなど本人確認の書類と合わせて請求します。
1枚につき収入印紙150円が必要となります。
このような場合はどうなるの?
ここまで家庭裁判所の相続放棄の手続きについて見てきました。
それではこのような場合はどうなるのか?個別の問題や注意点について見ていきます。
(1)私は被相続人の姉です。
亡くなったのは知っていたのですが、弟の配偶者や子どもが相続放棄をしていて、親も死亡していないので自分が相続人であることがつい最近わかりました。
既に3カ月は過ぎています。
このような場合、相続放棄は可能でしょうか?
結論から申し上げると可能です。
相続放棄は「被相続人が亡くなったことを知ったときから」ですが、具体的には自分が相続人であることがわかってからとなります。
亡くなった事実を知っていても自分が相続人とは知らなかった場合は、まだ相続放棄をできる余地はあります。
ただ、兄弟姉妹の相続放棄のような場合は、集める戸籍等の書類が子や配偶者が手続きをする場合に比べ、膨大になります。
3カ月を過ぎないよう注意して下さい。
また3カ月以内にできなかった理由を家庭裁判所から問われることがありますので、その理由付けを明確にして下さい。
(2)相続放棄の手続きをして家庭裁判所で認められました。
ですが、被相続人に多くの遺産があることがわかりましたので、撤回したいと思います。
それは認められるのでしょうか?
撤回は認められません。
相続放棄の手続きは他人の詐欺や強迫行為があった場合は取消ができますが、そのような事情のない撤回はできません。
このような事態が起こらないよう事前に被相続人の遺産は確認して手続きして下さい。
(3)相続放棄の注意点はどのようなものでしょうか?
相続放棄すると相続の順位が変わります。
子が相続放棄をすると、直系尊属に、または兄弟姉妹に相続権が移ります。
場合によっては、相続人と次順位の相続人等関係者全員で相続放棄をする方が効率的な場合もあります。
限定承認って何ですか?
相続放棄は被相続人の全ての遺産を引き継がない場合に取り得る手続きでした。
それに対して限定承認は相続人全員で家庭裁判所にて手続きをするものです。
これは被相続人のマイナスの財産は相続しないけれど、プラスの財産は相続するというものです。
被相続人の死亡したことを知ったときから3カ月という要件は相続放棄と同じですが、相続人全員でしなければならない点が相続放棄と異なります。
まとめ
これまで相続放棄の手続きを中心に、生前放棄や限定承認等の手続きについてみてきました。
制度そのものが違いますので、その注意点に留意しながらそれぞれの手続きを選んでいただけたらと思います。