

東京弁護士会所属。新潟県出身。
破産してしまうかもしれないという不安から、心身の健康を損ねてしまう場合があります。
破産は一般的にネガティブなイメージですが、次のステップへのスタート準備とも言えます。
そのためには、法律上の知識や、過去の法人破産がどのように解決されてきたかという知識が必要です。
法人破産分野を取り扱ってきた弁護士は、こういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって納得のいく措置をとることができます。
PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/kawasaki/
書籍:この1冊でわかる もめない遺産分割の進め方: 相続に精通した弁護士が徹底解説!

「借金が減額できる」と聞いて期待を抱きながらも、「もし失敗したら…」という不安が頭をよぎっていませんか?
小規模個人再生は借金問題を解決する強力な味方ですが、約7.5%の人が手続きに失敗しているという現実もあります。その境界線を分けるのは何なのでしょうか。
この記事では、実際の統計データをもとに、個人再生が失敗する主な理由と、成功するための具体的な対策を解説します。
Contents
小規模個人再生の成功率と失敗率を正確に把握するには、司法統計の分析が有効です。
令和5年の司法統計によると、小規模個人再生の申立て総数8,552件のうち、終結に至った件数は7,909件で、終結に至らなかった割合は約7.5%となっています。
つまり、申立てを行った10人中9人以上は手続きを成功させているという実態が確認できます。
参考:「令和5年司法統計年報」 P.88(最高裁判所事務総局)
小規模個人再生は92%以上の人が借金の減額に成功している制度ですが、一部のケースでは失敗することもあります。
裁判所の審査過程ではいくつかの要件を満たす必要があり、これが満たせないと手続きが進まなくなります。
再生計画案が現実的でない場合や債権者から必要な同意を得られない場合は認可されません。
また、期限内に必要書類を提出できない場合や、安定した収入源を証明できない場合は、手続きの途中で打ち切られることがあります。
ここでは、実際に小規模個人再生が失敗する典型的なケースとその対策について詳しく解説します。
小規模個人再生の申立ては、裁判所の審査で要件を満たさないと判断された場合、手続開始前の段階で棄却や却下となることがあります。
法律上の基本要件として、借金総額(住宅ローンを除く)が5,000万円を超える場合は小規模個人再生の対象外となり、申立ては認められません。
また、裁判所から選任された個人再生委員が申立て内容を調査し、「再生手続きを行う必要性や相当性がない」という意見書を提出することもあります。
この場合、裁判所はその専門的見解を重視して棄却の決定を下すことがあります。
このような初期段階での棄却を避けるためには、申立て前の入念な準備と専門家への相談が重要です。
個人再生手続が開始された後でも、途中で手続きが打ち切られることがあります。
手続開始後は、定められた期限内に必要書類を提出する義務があります。
東京地方裁判所破産再生部の運用では、開始決定から14週間以内に中間報告書および再生計画案を裁判所と個人再生委員に提出することが求められています。
この期限を過ぎても再生計画案の提出がない場合は、手続の進行が困難と判断され、個人再生手続自体が廃止される結果となります。
提出期限を正確に把握し、計画案を速やかに作成することは、手続の継続と再生計画の認可に向けて重要な要素です。
期限管理の不備が手続廃止の主要な原因となるため、特に注意が必要です。
個人再生手続においては、提出された再生計画案が裁判所の定める要件を満たしていることが求められます。
裁判所は計画案を厳格に審査し、要件適合性を判断します。
計画案の内容が遂行可能であるか、また清算価値保障原則に適合しているかが重要な審査ポイントとなります。
清算価値保障原則とは、債権者が自己破産の場合に受け取れる金額以上の返済が確保されているかを確認する基準です。
これらの要件を満たしていないと判断された場合、裁判所は再生計画案を不認可とします。
不認可となれば、債務の減額効果は得られず、債務整理の目的が達成できません。
再生計画が不認可となる主な理由について、解説します。
小規模個人再生では、債権者から再生計画案の同意を得ることが認可の重要な要件です。
債権者数の過半数が不同意を示した場合、または債権総額の過半数を有する債権者が反対した場合、再生計画は認可されません。
債権者にとって合理的な計画案を作成し、理解と協力を得るための丁寧な対応が成功への鍵となります。
再生計画が裁判所に認可されるためには、計画どおりに返済できる見込みがあることが前提です。
収入がない場合や継続的な収入が見込めないと判断される場合は、返済原資が確保できず不認可となりやすくなります。
また、収入があっても生活費を差し引いた可処分所得が計画上の返済額を下回ると判断された場合も認可されません。
再生計画提出時には、安定した収入の見通しとその根拠を具体的に示すことが重要です。
小規模個人再生を成功させるには、失敗要因を事前に把握することが重要です。
裁判所の定めた期限内に再生計画案や必要書類を提出し、手続き上の不備を避けましょう。
また、安定した収入があるか、返済可能な見通しが立っているかを事前に検討することも必須です。
ここでは、これらの失敗を回避するための具体的な対策を解説します。
小規模個人再生の手続きは法律や裁判所の運用に関する高度な専門知識を要するため、債務者本人が単独で対応することは簡単ではありません。
債務整理に精通した弁護士は、申立て書類の作成から裁判所とのやりとり、個人再生委員との面談対応、再生計画案の作成まで一貫してサポートします。
豊富な実務経験を持つ弁護士の支援により、認可される可能性が大幅に高まるため、債務整理に実績のある弁護士への依頼が最も効果的な対策といえます。
個人再生の手続きでは弁護士に依頼した場合でも、債務者自身が果たす役割があります。
家計簿の記録や必要書類の整理といった日常的な作業は手続きの信頼性を高めるだけでなく、全体の進行をスムーズにします。
また、書類提出や積立金納付などの期限遵守は不認可を避けるための最重要事項です。
裁判所が定めた期限を一度でも守れないと手続きが廃止されるリスクがあり、それまでの努力や費用が無駄になってしまいます。
弁護士に任せきりにせず主体的に取り組み、適切に連携することで、個人再生の成功率を高めることができます。
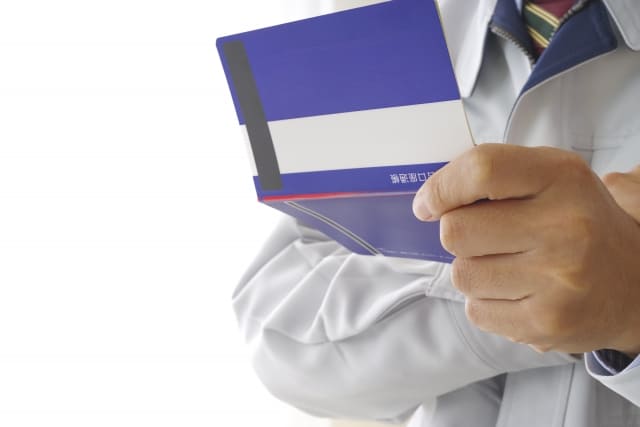
小規模個人再生に失敗した場合、借金の減額効果は得られず、元の返済義務がそのまま残ります。
生活再建が困難となれば、自己破産など他の債務整理手続へ移行することも検討する必要があります。
万が一の事態に備え、失敗した場合の影響と次の対応策を理解しておくことが重要です。
ここでは、小規模個人再生が失敗した場合について解説します。
小規模個人再生に失敗した場合、借金の減額効果は一切得られず、借入額は申立て前と同じ状態のままとなります。
さらに、手続き期間中は多くの場合、債権者への返済が中断されています。
返済が中断している間に発生した利息や遅延損害金が債務に上乗せされ、結果的に総額が手続き前よりも増加してしまうケースも少なくありません。
このような状況に陥った場合は、債務問題をさらに悪化させないためにも、自己破産などの代替となる債務整理手段を検討することが重要です。
小規模個人再生が不認可となった場合でも、裁判所に支払った申立て手数料や予納金などの実費は返還されません。
弁護士費用の返金については契約内容により異なり、事務所ごとに対応が分かれます。
再度個人再生を申し立てる場合や、自己破産へ移行する際に弁護士費用が割引されるケースもあります。契約時に費用の取り扱いについて事前確認することが重要です。
個人再生が不認可となった場合でも、自己破産に切り替えることで借金の免責を受けられる可能性があります。
自己破産は借金返済能力がないと裁判所に認められれば、原則としてすべての債務の支払い義務が免除されるという大きなメリットがあります。
ただし、ローン返済中の住宅など一定の財産が差押えの対象となり、手放す必要が生じる点には注意が必要です。
住宅を残したい場合は、個人再生と自己破産の違いを十分理解した上で判断することが重要です。
小規模個人再生は借金の大幅な減額と生活再建を実現する効果的な手段ですが、約7.5%の確率で失敗するリスクがあります。
手続きが失敗すると借金は減額されず、支払った費用も返金されないため、慎重な準備と適切な対応が不可欠です。
成功率を高めるためには、債務整理に精通した弁護士への相談と、債務者自身の積極的な取り組みが重要です。
不安を感じている方は早めに専門家に相談し、最適な債務整理方法を選択することをお勧めします。