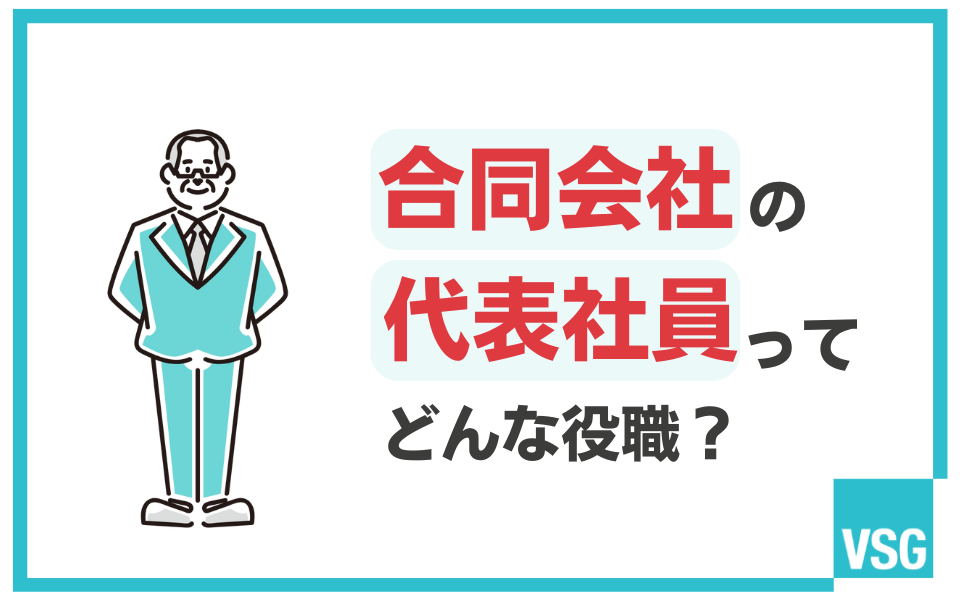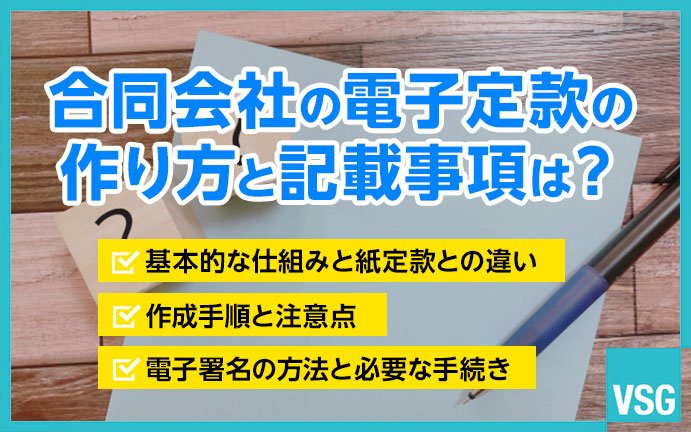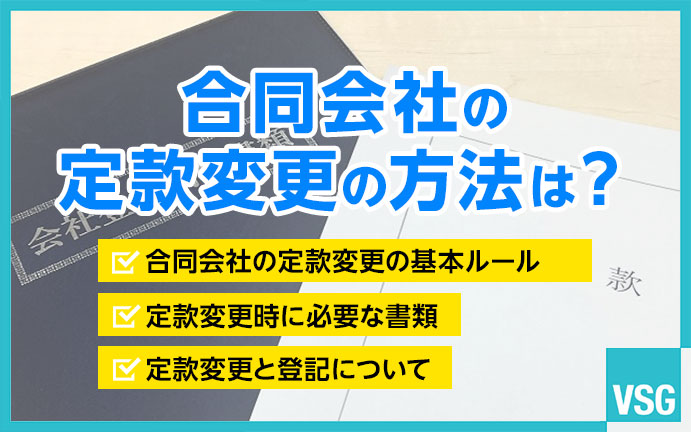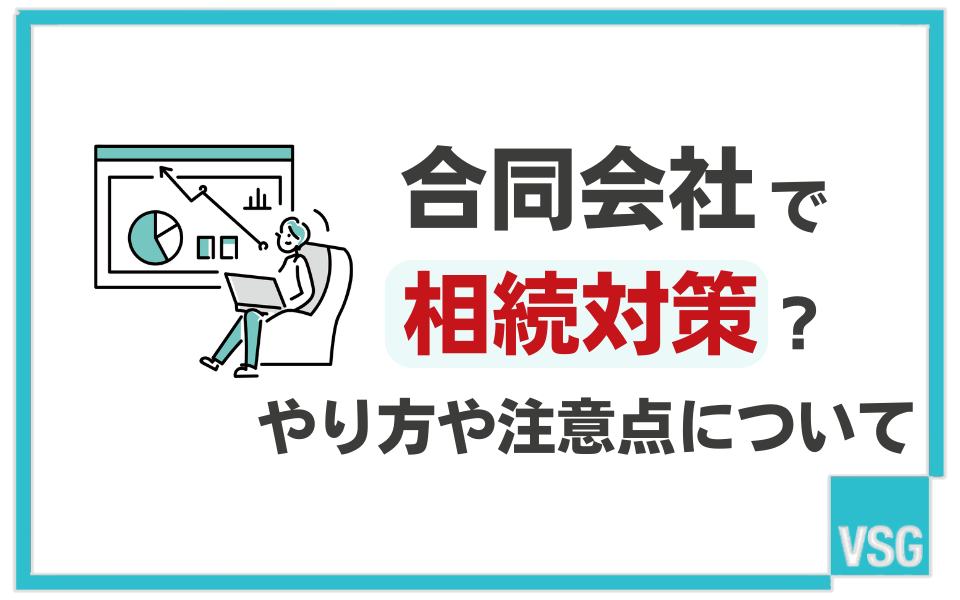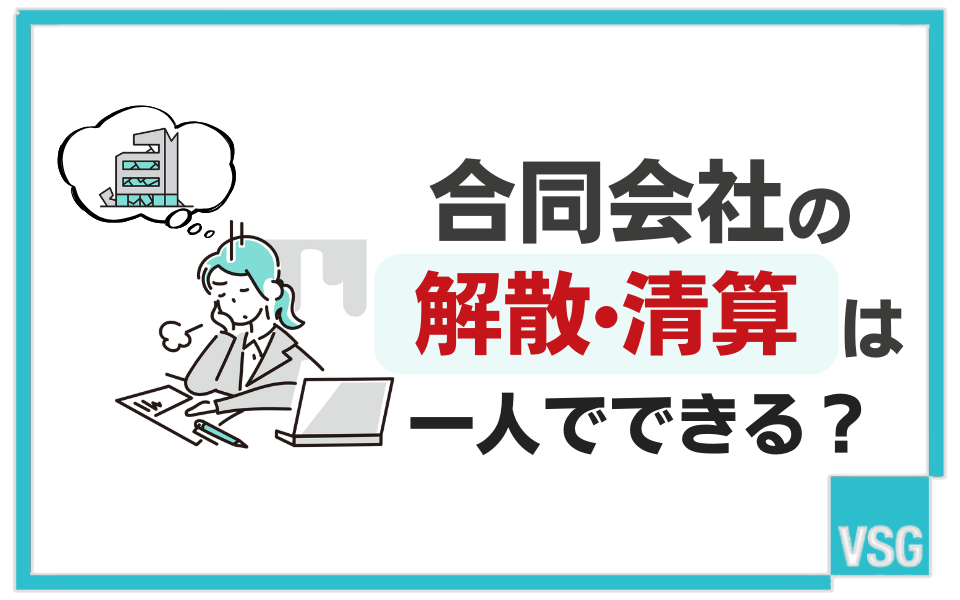最終更新日:2025/10/28
合同会社設立の必要書類一覧!法務局での登記など手続きについて解説します

ベンチャーサポート税理士法人 大阪オフィス代表税理士。
近畿税理士会 北支部所属(登録番号:121535)
1977年生まれ、奈良県奈良市出身。
起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネルを運営。
PROFILE:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_writing/#p-mori
YouTube:会社設立サポートチャンネル【税理士 森健太郎】
書籍:プロが教える! 失敗しない起業・会社設立のすべて (COSMIC MOOK) ムック
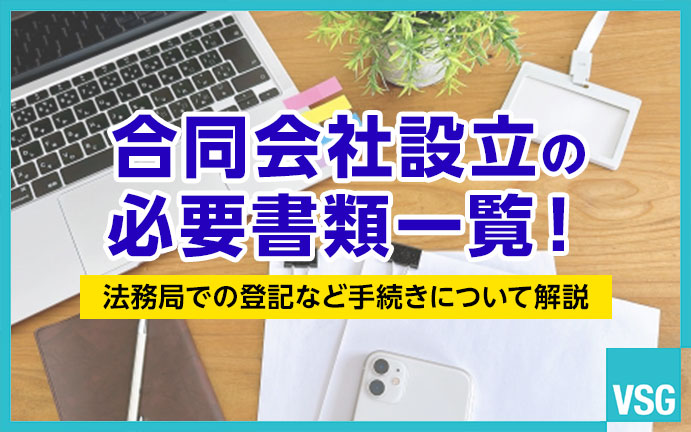
この記事でわかること
- 合同会社を設立する際に必要な書類
- 合同会社を設立する手続きの流れ
合同会社は個人事業主の法人化の際に選ばれることも多く「自分で設立したい」と考える人もいるでしょう。合同会社を設立する際には、定款の作成や登記申請など、複数の書類を用意して提出する必要があります。
この記事では、合同会社の設立時に必要な書類をわかりやすく解説します。あわせて各書類の役割や記載内容をチェックして、自分で準備できるかどうかの判断ポイントも整理します。
合同会社の設立をスムーズに進めるためには、手続きの流れや提出書類の内容を正確に理解することが重要です。この記事を参考に、合同会社設立に必要な書類をそろえていきましょう。


合同会社を設立するときの必要書類
合同会社を設立するときは、定款や登記申請書といった書類をすべて準備する必要があります。
ここでは、合同会社の設立時に必要な書類の一覧と、それぞれの書類のポイントをわかりやすく説明していきます。
合同会社設立の際に用意する必要書類一覧
合同会社設立時には、以下の書類をすべて準備して、法務局に提出して設立登記という手続きを行います。この登記が終了したら合同会社という法人として契約などができる「法人格」が与えられます。
- 合同会社設立登記申請書
- 定款
- 代表社員の印鑑登録証明書
- 会社の印鑑届書
- 登録免許税納付用台紙
- 出資金の払込証明書
- 「登記すべき事項」
合同会社設立登記申請書
合同会社設立登記申請書は、合同会社を設立するときに必ず法務局に提出する書類です。
会社の名称や所在地、代表社員の氏名、業務内容などを記載します。フォーマットは法務局のホームページでも確認できるので、法務局に行く前にチェックしておくといいでしょう。
定款
定款とは、「会社の憲法」とも言われる会社のルールブックのことです。会社の根本規則を定めた重要書類で、会社を設立するときには必ず作成します。
合同会社の場合は、公証役場での定款認証を受ける必要はありません。定款は自作でもよいですが、専門家に依頼して作成することもできます。
最近では、電子データで定款を作成して保存する電子定款の利用も増えています。
代表社員の印鑑登録証明書
代表社員の印鑑証明書も必要書類のひとつです。注意したいのは印鑑証明の日付です。合同会社の設立登記の申請日から3カ月以内に発行されたものでなければなりません。
印鑑証明は、市区町村の窓口やマイナンバーカードを使ったコンビニ交付で取得できます。
会社の印鑑届書
ここでの印鑑届書は、代表社員の印鑑ではなく会社の印鑑のものです。新たに作成した会社の実印を法務局に届け出るための書類で、法務局に設置されている専用の用紙を使用します。この印鑑届書には代表社員の印鑑を押す必要があります。
登録免許税納付用台紙
設立登記の際に支払う登録免許税の収入印紙を貼り付けるための台紙です。登録免許税は、資本金の額の0.7%もしくは6万円の高い方となります。つまり最低でも6万円は必要ということです。
出資金の払込証明書
設立する会社の資本金の払込みを証明するための書類です。出資金は口座に振り込む形で記録し、通帳のコピーを添付して証明書を作成します。
出資金が会社の資金として支払われたことを証明する重要な書類です。
「登記すべき事項」
「登記すべき事項」とは、登記事項である会社名や本店所在地、代表社員、資本金を記載した書類のことです。CD-Rで提出する方法と紙で提出する方法があり、どちらでも構いません。
参考:商業・法人登記申請における登記すべき事項を記録した電磁的記録媒体の提出について|法務省
自分で作る書類と入手する書類
合同会社の設立にあたって必要な書類には、自分で作成するものと入手するものの2種類があります。以下の表にまとめたのでチェックしましょう。
| 書類名 | 作成・取得先 |
|---|---|
| 合同会社設立登記申請書 | 自分で作成 |
| 定款 | 自分で作成 |
| 出資金の払込証明書 | 自分で作成 |
| 登記すべき事項 | 自分で作成 |
| 登録免許税納付用台紙 | 自分で作成 |
| 代表社員の印鑑登録証明書 | 市区町村役場など |
| 会社代表者印の印鑑届書 | 法務局のホームページなど |
必要書類のうち、公的機関から交付を受ける書類は印鑑証明書のみということになります。
上記以外の書類が必要になるケース
合同会社設立の基本の書類は前述のとおりですが、追加書類が必要なこともあるのでチェックしましょう。
業務執行社員から代表社員を選んだ場合
複数の社員の中から代表社員を選出した場合は「代表社員に就任することに同意する」という趣旨の書類が必要です。代表社員就任承諾書は、登記申請時に提出しなければなりません。
ひとりで合同会社を設立する場合は、この承諾書は不要です。
定款に資本金の総額の記載がない
定款に出資額の総額を明記していない場合は、出資金の総額を示す書類が必要です。代表社員、本店所在地、資本金の額を決定したことを証明する「代表社員・本店所在地および資本金決定書」を用意します。
現物出資をする場合
現金ではなく現物(車など)を合同会社に出資する場合は、「資本金の額の計上に関する証明書」と「財産引継書」が必要です。
この書類で「何が現物出資されたのか」や「現物出資されたものが確実に会社に引き継かれたこと」を証明します。
合同会社設立の流れ
ここまで、合同会社設立の書類をひと通り確認しました。ここからは合同会社設立の一般的な流れをわかりやすく解説します。
必要書類だけでなく手続きの流れの全体像を把握しておきましょう。
合同会社を設立するときのフローチャート
合同会社の設立までの主な流れをフローチャートで解説します。スムーズに手続きを進められるように、時系列で設立の流れを確認していきましょう。
合同会社設立のフローチャート
- STEP1会社の基本事項を決める(商号、所在地、事業目的、出資、代表社員など)
- STEP2定款を作成する(公証人による認証は不要。出資者全員の記名と押印)
- STEP3出資金を払い込む(個人口座に振込み。通帳のコピーと払込証明書の作成)
- STEP4必要書類をすべてそろえる(定款、印鑑届書、印鑑証明書など)
- STEP5法務局に設立登記の申請をする(本店所在地を管轄する法務局へ)
登記を終えたら、法人番号が与えられて正式に「合同会社」という法人となります。設立登記のあとで税務署などに届出をします。
合同会社設立の際のポイント
合同会社を設立する際には、必要書類をすべてそろえる以外にも注意点があります。特に自分で設立する場合は注意しましょう。
定款認証を受ける必要はないが定款は作成する
合同会社を設立する場合は、公証人による定款認証を受ける必要はありません。そのため、定款認証にかかる費用と手間を抑えることができます。
ただし、定款認証が必要ないというだけで定款を作らなくてもいいということではありません。会社を設立する際には必ず定款を作成します。
定款は、会社の基本ルールを定める重要書類であり、会社を運営する上で不可欠な書類です。また、合同会社の設立登記でも定款は必要です。
定款には以下のような事項を記載します。
- 会社名(商号)
- 事業目的
- 本店所在地
- 社員(出資者)と出資の内容
- 業務執行社員
- 代表社員
定款は自分で作成できる書類ですが、内容に不備があると手続きがスムーズに進まないことがあります。会社法で定められた記載事項は必ず記載しなければなりません。
印鑑証明書の有効期限に注意
合同会社の設立登記で必要な「印鑑登録証明書」は、発行後3カ月以内のものを提出する必要があります。
書類を準備する最初の段階で取得すると、手続きまでに3カ月が経過してしまうケースもあります。印鑑証明書は必ず3カ月以内のものを登記申請時に添付するようにしましょう。
また、複数の代表社員がいる場合は、全員分の印鑑証明書が必要です。社員全員に明示したたうえで、発行から3カ月以内の印鑑証明書をそろえるようにしてください。
合同会社はどんな会社?
合同会社の設立について解説しましたが、ここでそもそも「合同会社とはどんな会社なのか」について簡単に整理しましょう。
会社の所有者と経営者が同じ
合同会社の特徴は「会社の所有者である出資者」と「経営者」が同じであるということです。出資者とは、言うまでもなく「お金を出した人」のことです。株式会社では「株主」といいますが、合同会社では「社員」といいます。
合同会社の「社員」とは、従業員ではなく出資者であり、かつ会社の経営判断を行う人のことです。株式会社では株主と経験者(役員)は分離していますが、合同会社では同一なのです。ただし、株式会社でも役員が自社の株式を保有しているケースはあります。
株式の発行はできない
合同会社では、資金調達のための株式の発行はできません。株で資金調達ができないため、資金調達をする際には銀行融資や制度融資、補助金などを活用することになります。
役員の任期がない
株式会社の場合は、役員の任期が定められています(最長10年)。そのため、必ず一定の期間ごとに役員の登記をしなければなりません。
ですが、合同会社には役員の任期の定めがないため、登記事項に変更がない限りは変更登記をする必要はありません。
また、役員の任期がないため、みなし解散のリスクもないということになります。
設立時の手続きや費用面でメリットがある
合同会社には、設立時の手続きが株式会社より簡素で低コストであるというメリットがあります。設立時の最大のメリットは定款認証が不要という点でしょう。定款認証にかかる手間と費用をカットできます。
また、設立時に求められる手続きが比較的シンプルであり、初めて会社を立ち上げる人にとってはハードルが低いといえます。
今、設立できる会社は「株式会社」「合同会社」「合資会社」「合名会社」ですが、新しく設立する会社のほとんどは株式会社か合同会社です。合資会社や合名会社は制度としては残されていますが、無限責任社員が必要でありリスクが大きく、メリットはないため選ばれるケースは極めてまれです。
合同会社設立は自分でできる?
合同会社の設立は、必要書類をそろえれば自分だけでもできます。とはいえ定款などの書類の作成や法務局での登記申請には知識や慣れが必要となるため、初心者の場合は戸惑うこともあるでしょう。
ここでは、自分で設立するときのポイントと、専門家に依頼する場合との違いを解説します。
必要書類をそろえれば自分でできる
合同会社の設立は、書類をすべてそろえて、法務局で会社の設立登記をすることで完了します。特に合同会社は定款認証が不要であるため、株式会社より手順が少なくシンプルです。
ただし、以下の点には注意が必要です。
注意点
- 定款の内容に不備がないか(絶対的記載事項は記載されているか)
- 印鑑証明書の有効期限が切れていないか
- 資本金の払込証明書の内容が正確か
- その他の申請書類がそろっているか
ひとつでも書類に不備があると登記ができないため、何度もチェックする必要があります。書類の作成には法律の知識が求められるため、初心者にとってはハードルが高く感じられるかもしれません。
専門家に依頼するとよりスムーズ
スムーズに合同会社を設立したい人や、書類作成に不安がある人は、行政書士や司法書士などの専門家に依頼する選択肢もあります。専門家に依頼すると費用がかかりますが、そのぶんメリットもあります。
メリット
- 書類作成を依頼できる
- スケジュール通りに進められる
- 定款の内容について法的なアドバイスが得られる
費用面だけで考えれば、自分で設立するのが最も低コストです。とはいえ、書類作成の手間が省け、定款の内容についてアドバイスがもらえるというメリットは決して小さくありません。
必要書類を確認して「わけがわからない」という場合は、専門家への依頼を検討しましょう。
合同会社設立の必要書類を把握して手続きしよう
合同会社設立に必要な書類は定款や登記申請書などです。
合同会社は、設立手続きが比較的簡単で費用も抑えられるため、個人事業主の法人化や中小企業が新しく会社を作る際には魅力的な法人形態です。
合同会社の設立は、必要書類をそろえることで自分だけでも可能ですが、書類の不備や手続きの遅れが起こるリスクもあります。
スムーズに会社を設立したい人は、専門家に相談することでリスクを軽減し、設立後の経営につながるサポートを受けられます。