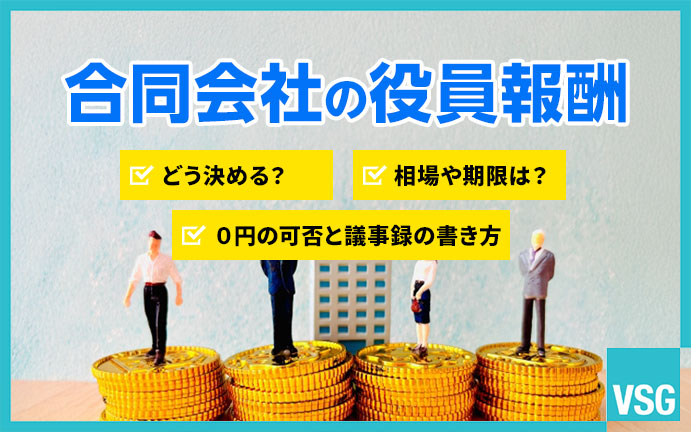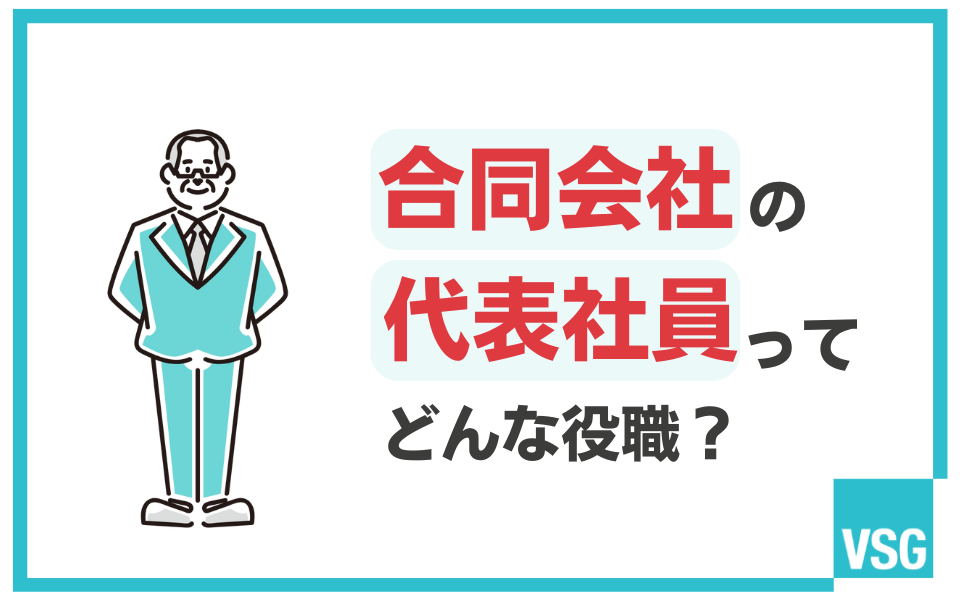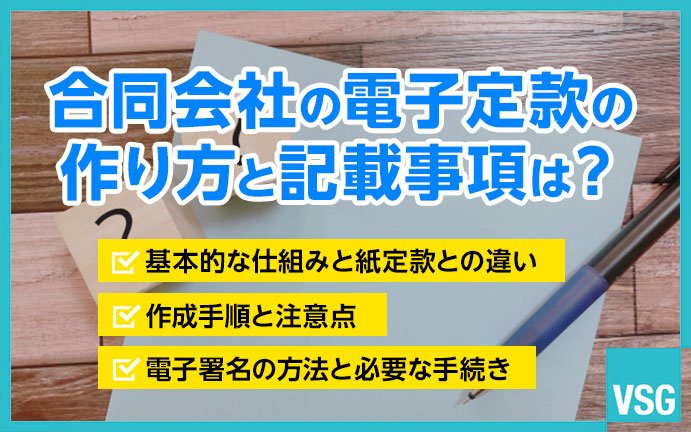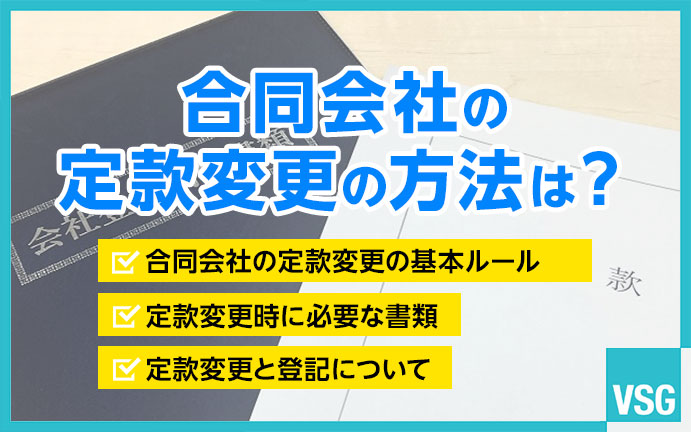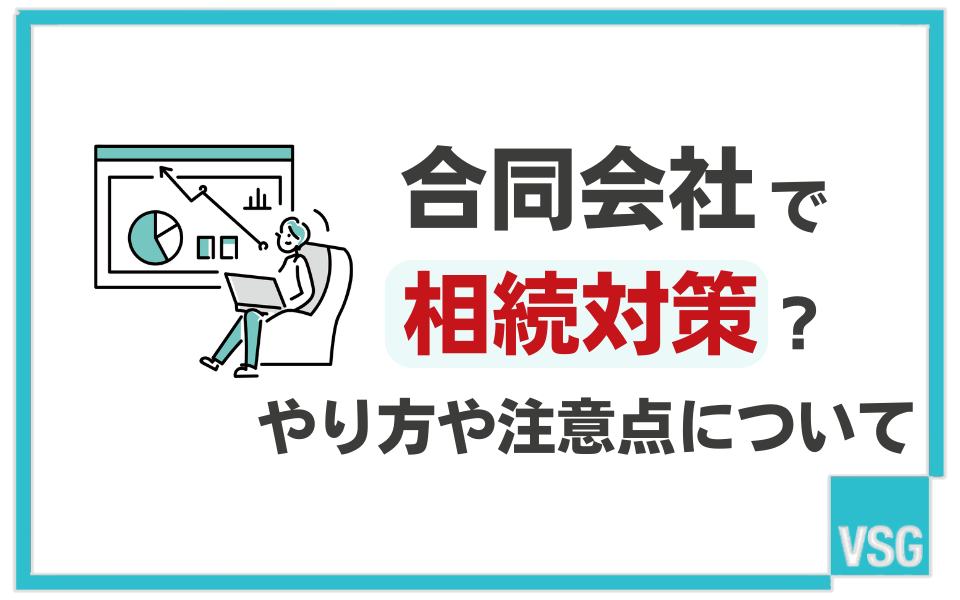最終更新日:2025/9/4
合同会社の役員とは?肩書きの種類や登記のルールを徹底解説

ベンチャーサポート税理士法人 大阪オフィス代表税理士。
近畿税理士会 北支部所属(登録番号:121535)
1977年生まれ、奈良県奈良市出身。
起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネルを運営。
PROFILE:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_writing/#p-mori
YouTube:会社設立サポートチャンネル【税理士 森健太郎】
書籍:プロが教える! 失敗しない起業・会社設立のすべて (COSMIC MOOK) ムック

この記事でわかること
- 合同会社における「役員」とは
- 合同会社で使われる肩書きの種類
- 株式会社の役員との違い
「役員」という言葉を耳にすることがあります。くだけた表現をするなら「会社の偉い人」ということですが、実は会社の種類によって役員の呼び方や役割は変わります。合同会社の場合「役員」という言葉は法律上は存在していません。慣習的に「役員」と言う呼称が使われているだけです。
合同会社には、取締役会や株主総会など、株式会社にあるような組織が存在しません。また、会社の所有者と経営者が同じという特徴もあります。
この記事では、合同会社における「役員」の位置づけから、代表社員や業務執行社員といった法的な役職、一般的によく使われる肩書きの種類、登記事項に関する注意点などを解説します。株式会社との違いを踏まえながら実務に役立つ知識を整理していきましょう。


目次
合同会社の役員とは
合同会社には、「取締役」や「監査役」といった役員は存在しません。
合同会社では、出資者がそのまま「社員」となり、経営権を持っています。これが株式会社との大きな違いです。ここでは、合同会社における実質的な役員とされている役職について解説します。
合同会社では「役員」とは言わない
合同会社には会社法上の「役員」は存在しません。会社法上の「役員」は株式会社における取締役や監査役などを指しているため、合同会社には会社法上の役員はいないのです。
ただし、実務では「経営をする人」という意味で合同会社の経営陣を「役員」と呼ぶ場面は多くあります。たとえば、取引先とのやりとりの中で「役員の方」という表現が出ることもあるでしょう。これはあくまで慣習的なもので、法律上の区別とは異なることを理解しておく必要があります。


合同会社の社員とは出資した人
合同会社の「社員」とは、会社に出資をした人のことを指します。この合同会社の「社員」は、株式会社の「株主」と似た立場ですが、合同会社の場合は単に出資するだけでなく、経営に関する意思決定も行っているという点で異なります。
つまり、合同会社では「出資者=経営者」という構造になっており、社員が自ら会社の業務を執行する仕組みです。出資と経営が一体となっている点は、株式会社との大きな違いのひとつです。
合同会社では社員=従業員ではない
「社員」という言葉は、日常的には「従業員(雇用されて働く人)」という意味で使われています。ですが、合同会社における法律上の社員はまったく異なる意味となります。
会社法における社員は、出資者であり、経営に直接関与するという立場です。つまり雇用契約をして働いている労働者ではありません。
したがって、同じ「社員」という言葉でも、法的な意味と一般用語としての意味は大きく異なるのです。ただし、合同会社でも従業員のことを「社員」と呼ぶケースはよくあるため注意しましょう。
合同会社は所有と経営が同じ
合同会社の特徴のひとつが、出資した人(社員)がそのまま経営を行うという点です。合同会社では、経営判断が取締役に委任されている株式会社とは異なり、所有と経営が一致しているのです。
そのため、合同会社では、意思決定がスピーディーで、経営の自由度が高い傾向があります。ここでは、株式会社との違いを比較しつつ解説します。
株式会社は所有と経営が分離している
株式会社では出資者である「株主」が会社の所有者です。取締役は、株主総会で選任されて委任契約のもとで業務を執行します。つまり、お金を出す人(株主)と、経営判断をする人(取締役)が別なのです。
これを「所有と経営の分離」というのですが、株主は出資するというリスクを引き受けつつ、経営には直接関与しないケースがほとんどです。株主は、経営をその道のプロに任せて自身は「投資する」のです。
ただし、中小企業やオーナー企業では、株主がそのまま取締役となって経営を行っていることも多く、分離が形式的になるケースもあります。もちろん、大企業であっても、取締役が自社の株を保有して株主と取締役の両方の立場になることに問題はありません。
合同会社は所有と経営が同一
一方で、合同会社では、出資した人がそのまま社員となって、会社の経営判断や評価を行います。このように、お金を出す人と経営をする人が一致しているという点が、合同会社の特徴です。
経営と所有が同一であるため、外部からの干渉が少なく安定した経営ができるだけでなく、意思決定がスムーズに進められます。
ただ、経営には関与しない第三者からの出資を受けたい場合や、経営には関与させたくないが出資はしてほしいという関係を築きたい場合には、合同会社の仕組みでは対応が難しくなることもあります。
合同会社は、少人数で機動的に運営する家族経営などに向いており、所有と経営が同じであるというシンプルな仕組みになっています。
合同会社の肩書き一覧
合同会社では、法的に定められた役職名だけでなく、実務上で柔軟に使われている肩書きがあります。法的な意味合いについて正しく理解することが重要です。
法律で決まっている肩書き
合同会社における役職のうち、法律で定められているものには以下の4つがあります。これらは会社法上の呼称であり、登記や責任の範囲に関わる重要な役職です。
代表社員
代表社員とは、合同会社を代表する権限を持つ社員です。株式会社での「代表取締役」のような立場です。
会社法上、社員が複数いる場合に代表社員を定めない場合は出資者全員が代表社員となります。全員が代表社員となると、対外的な手続きやビジネスが適切に行えなくなる可能性があるため、設立時点で選任されるケースがほとんどです。
社員
合同会社での会社法上の「社員」とは、出資した人のことです。そして、社員は原則として経営に参加する権限を持っています。社員は、株式会社における「株主」の性質を持っていますが、経営と所有が一致しているため、社員はお金を出しただけの人ではありません。
この「社員」という言葉は一般的には「従業員」と混同されがちなため、しっかり理解しておきたいポイントです。
業務執行社員
業務執行社員とは、合同会社の中で実際に業務を執行する社員のことです。株式会社における取締役に近いといえます。業務執行社員は、出資者(社員)の中から定める役職で、とくに定めがない場合は、社員全員が業務執行社員となります。
定款で業務執行を行う社員を特定することで、役割分担を明確にできます。
職務執行者
職務執行者は、合同会社の出資者(社員)が法人というケースで、その法人の意思を反映させるために設置される役職です。たとえば、親会社が合同会社を設立して社員(出資者)となるケースでは、実際に合同会社で経営判断をする人が必要となるため、職務執行者を定めます。
代表社員と業務執行社員はどう違うのか
合同会社の役職の「代表社員」と「業務執行社員」は、どちらも会社の運営に関与する立場ですが、両者には違いがあります。
業務執行社員は、社内の業務を進める役割を持っていますが、代表社員は、会社を代表して外部との契約などを行う権限を持っています。
代表権の有無
「代表社員」と「業務執行社員」の大きな違いは代表権の有無です。
代表社員には、会社を対外的に代表する代表権があります。代表社員がその会社の顔ということです。つまり、代表社員の行動や判断は、原則として会社のものとみなされます。
一方、業務執行社員には原則として代表権はありません。出資した社員として、社内の業務執行の権限はあるものの、会社を代表することはありません。
実務上は「代表社員=実質的な代表者(社長)」とするケースが多く、名刺などに「社長」という肩書きが使われることが一般的です。
合同会社でもよく使用される役職
合同会社では、実務上よく使われる通称の役職名があります。「社長」「代表」「CEO」などがその代表例です。
これらの役職名は、法律で定められているものではなく、任意で使用される役職名です。
社長
一般的に「社長」は、会社の最高経営責任者(CEO)として広く認識されています。ですが、会社法には「社長」という役職名は存在しません。
合同会社においても「社長」という呼称はよく使われています。法的には「業務執行社員」や「代表社員」といった役職名が用いられますが、対外的なわかりやすさや慣習の観点から「社長」という肩書きを名乗るケースが多いです。
特に少人数で運営される合同会社では、役職の柔軟な運用が可能であり、代表者が「社長」として活動することで、社内外との円滑なコミュニケーションが図られています。
一方で、株式会社では、取締役の中から選定される「代表取締役」が経営の中心となります。実務では「代表取締役社長」と名刺などに表記されるケースが多くなります。
合同会社でも株式会社でも同じ「社長」という役職が使用されるケースが多いのです。
代表
「代表」という肩書きも、合同会社でよく使われる表現のひとつです。会社法上の「代表社員」として登記されている人物が代表とされるケースが多くなります。
前述した「社長」ではなくあえて「代表」という役職名にすることで、合同会社の仕組みと役職のイメージがより近いものになります。
CEO(Chief Executive Officer)
CEOは「最高経営責任者」としての立場を表す役職です。合同会社においても、経営責任の所在を明確にするためにCEOという名称を用いるケースがあります。
ただし、これも法的な役職名ではないため、会社法上は「代表社員」となります。
COO(Chief Operating Officer)
COOは「最高執行責任者」のことで、日常業務の責任者です。合同会社でも用いられることがあります。
ただし、これも任意の肩書きであり、登記簿に記載されるものではありません。あくまで社内での役割を表すために使用するものである点は押さえておきましょう。
合同会社の役員の人数のルール
合同会社は、役員の人数に関する制限がないため、自由に役員の人数を設定できます。一人でも複数人でも問題はありません。
ここでは、合同会社における役員の基本ルールについて確認しておきましょう。
一人でも複数でもどちらでも可能
合同会社は「合同」という言葉から一人ではできないようなイメージがあるかもしれません。ですが、実際には合同会社を一人で設立・運営することができます。この点は株式会社と同様です。
一人で運営する場合は、設立時の出資者・業務執行者・代表社員がすべて同一人物に集約されます。そのため、意志決定のスピードが速くなり小規模ビジネスに適しています。
もちろん、複数人で出資して合同会社を共同経営することもできます。
この自由度の高さが合同会社の特徴です。
代表社員が複数でもよい
合同会社では、代表社員が一人である必要はありません。複数名を代表社員として選任することもできますし、全社員が代表社員という形態も可能です。
ただし、代表権を複数の人物が持つことで混乱が起きるリスクがあるため注意が必要です。
役員登記について
会社法上の役員は法務局に登記する義務があります。これは、会社の基本情報として公示されます。
ここからは合同会社の登記について解説します。
代表社員・業務執行社員は登記が必要
会社法の規定により、合同会社では原則として全社員を登記する必要があります。ただし、定款で「業務を執行しない社員」を定めている場合は、業務を執行しない社員を登記する必要はありません。
登記の期限は変更から2週間以内で、これは株式会社と同様です。
登記懈怠になると罰則がある
合同会社においても、登記が必要な場合に登記をせずにいると登記懈怠(けたい)という違法な状態になります。法律上の義務を果たしていない状態であるため、罰則もあります。
場合によっては、100万円以下の過料となるケースがあるため注意しましょう。
株式会社の役員と合同会社の社員の違い
合同会社と株式会社は、意思決定の仕組みや資金調達の方法など、さまさまな点で異なります。
ここでは、株式会社の株主や取締役と、合同会社の社員との違いを比較してポイントを整理します。
合同会社の場合は社員は必ず出資者
合同会社の「社員」は、出資した人や法人のことです。合同会社では出資した人は社員となり、経営にも関わることになります。原則として「経営に関与しない出資者」はいないということです(所有と経営の一致)。
合同会社の出資者は経営にも関与するため、外部からの出資には慎重さが求められます。
株主総会の有無
株式会社では、株主が決議を行う「株主総会」があります。定款変更や取締役の選任などは株主総会で決議します。株主は経営に直接関与しませんが、株主総会の議決権を通じて取締役をコントロールしているのです。
一方、合同会社は株を発行しないため、株主総会が存在しません。出資者である社員全員が経営に関わり、共同で経営判断を行います。
登記事項の違い
株式会社と合同会社では、登記事項にも違いがあります。
株式会社の場合、役員の情報は登記されますが、株主の情報は登記事項ではありません。一方で、合同会社の場合は原則すべての社員が登記されます。
合同会社は役員ではなく出資者が社員として経営判断を行う
合同会社には、法律が定める「役員」は存在しません。正式な役職名としては「代表社員」「業務執行社員」があります。ただ、ビジネスの現場では「役員」「社長」という役職名が使用されています。
また、合同会社では、会社法上、出資者を社員といいます。この社員は従業員ではありません。
一般的に使用される役職名と会社法上の役職名が異なるため混乱してしまうかもしれませんが、合同会社と株式会社では組織の仕組みや登記事項が異なるため、違いをしっかり理解することが大切です。