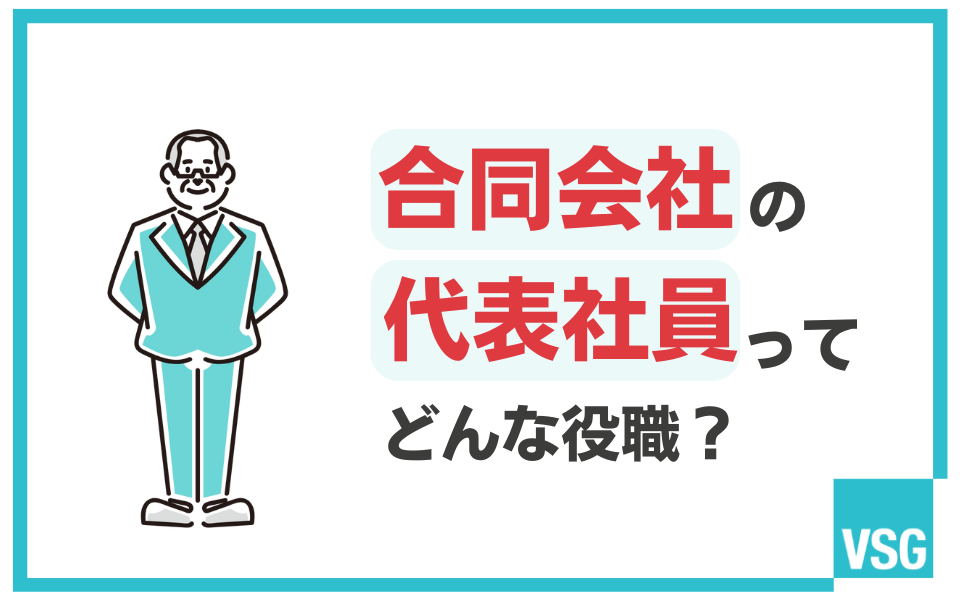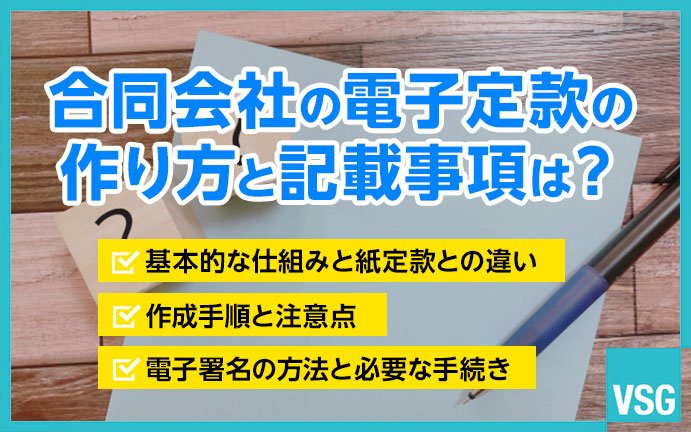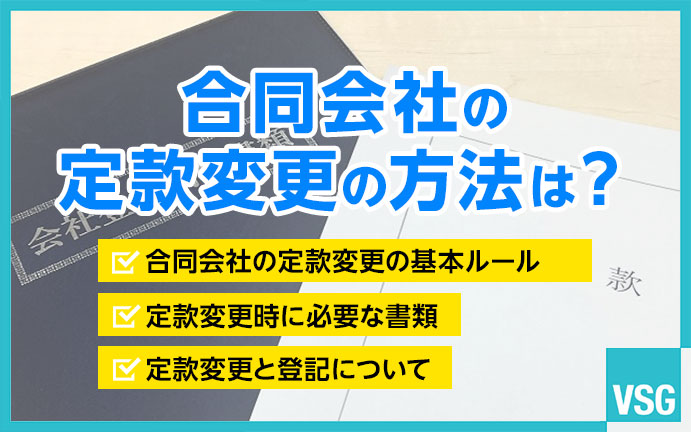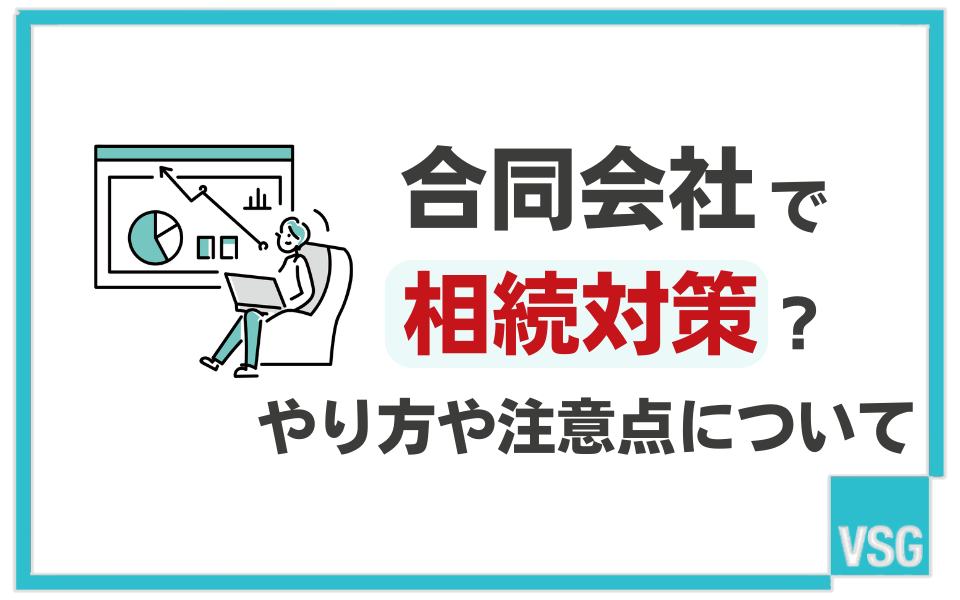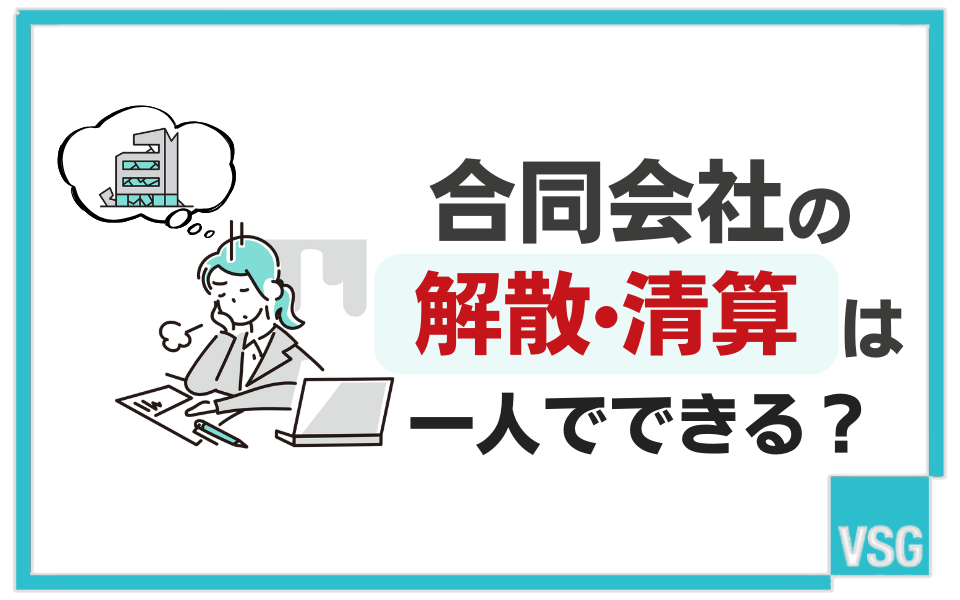最終更新日:2025/9/11
合同会社は代表社員2名でも設立できる!合同会社の代表社員について解説します

ベンチャーサポート税理士法人 大阪オフィス代表税理士。
近畿税理士会 北支部所属(登録番号:121535)
1977年生まれ、奈良県奈良市出身。
起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネルを運営。
PROFILE:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_writing/#p-mori
YouTube:会社設立サポートチャンネル【税理士 森健太郎】
書籍:プロが教える! 失敗しない起業・会社設立のすべて (COSMIC MOOK) ムック
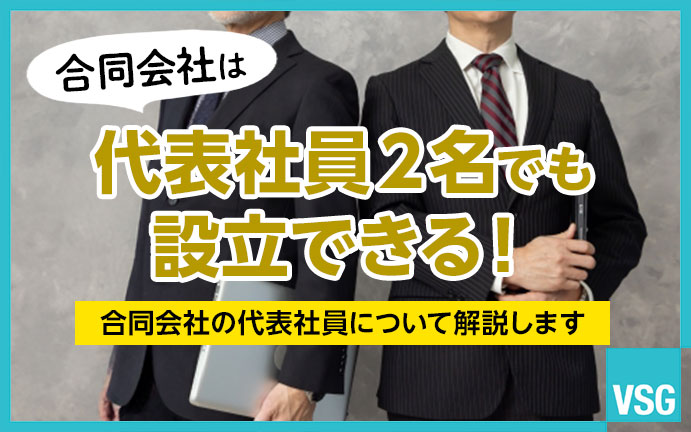
この記事でわかること
- 合同会社の代表社員は2名でも設立できる
- 複数名の代表社員を置くことのメリット・デメリット
- 代表社員の給与と役割
合同会社の設立を検討していると「代表社員は何人必要なのか」「2名の代表社員を置く共同経営はできるのか」といった疑問を持つ人が多くいます。
合同会社では、代表社員が2名でも法律上は問題ありません。ただし、実際には役割や報酬、意思決定の取り決めをあいまいにすると思わぬトラブルに発展することもあります。
この記事では、合同会社における代表社員制度の基本から、2名の代表社員を置くメリット・デメリット、株式会社との違い、代表社員の給与の決め方までわかりやすく解説します。


目次
合同会社の代表社員は2名でも問題はない
合同会社は、代表社員が2名という体制でも問題なく設立可能です。1名でも2名以上の複数名でも設立できます。
合同会社は株式会社より柔軟に運営でき、代表の人数についても法律上の制限はありません。以下では、代表社員の人数やパターンごとの特徴を解説します。
合同会社の社員の人数と出資比率
合同会社では、出資者が「社員」と呼ばれます。ここでいう社員は、雇用契約のもとで働く従業員ではなく、出資者であり、そのまま会社の経営者となります。社員の人数に下限も上限も設定されておらず、1人でも複数人でも合同会社の設立が可能です。
合同会社の社員は、株式会社における株主とは異なり、会社の経営に携わる立場なのです。
また、合同会社では、出資額に関係なく原則1人1票の議決権があります。出資額が多くても議決権は増えません。そのため、重要な意思決定をする場合は社員間での合意が重要となります。
代表社員が1名のケースもある
合同会社では、代表社員が1名というケースもあります。
代表が1名の場合、意思決定はスムーズであり、運営コストも抑えやすい点がメリットです。ただし、経営判断の偏りなどのリスクも考えられるため、補佐役や外部の助言を受けるようにするといいでしょう。
複数名で代表社員になってもよい
一方で、合同会社の代表社員を2名以上にすることも可能です。
たとえば2名の代表社員を置く場合、両者がそれぞれ契約権限を持ち、日常業務を分担しながら経営にあたることになります。
このように代表権を2名以上にすることで、万が一どちらかが不在でも会社としての対応が可能になるというメリットがあります。ただし、後述するように、デメリットもあるため注意しましょう。
法人を代表社員にしてもよい
合同会社では、法人(たとえば別の会社)を代表社員として登記することも可能です。
ただし、法人が代表社員となる場合、その法人そのものを登記するのではなく、その法人から選任された個人が「業務執行者」として氏名や住所の登記を行います。業務執行者が、合同会社の経営判断も行います。
こうした仕組みは、グループ会社の設立や出資先の管理会社として合同会社を作る際に活用できます。
合同会社の代表社員を2名にするメリットとデメリット
合同会社では、代表社員を2名にすることに法律上の問題はありません。ただ、実務面ではメリットとデメリットがあります。ここでは、2名以上の代表社員を置くことのメリットとデメリットを整理します。
メリット
代表社員を2名にすると以下のようなメリットがあります。
- 一方が不在の際にフォローできる
- 得意分野を分けて業務ができる
- 重要な意思決定を共有して多角的な判断ができる
代表社員が2人いることで、経営判断を行う際に多角的な視点を取り入れることができます。また、1人で経営を担う場合よりも互いにフォローし合いながら意思決定できる点もメリットです。
信頼関係のある者同士であれば、互いの得意分野を活かしながら柔軟な経営が可能です。
デメリット
一方、代表社員が2名いることで混乱や対立が生じやすくなるというデメリットもあります。特に、合同会社では出資比率に関係なく「1人1票」の議決権が与えられているため、2名以上の代表社員で意見が割れてしまった場合、どちらの意思を優先するかが問題になることがあります。
その他のデメリットとしては、以下のようなものがあります。
- 意思決定のたびに話し合いが必要でスピード感に欠ける
- 役所への届出書類に代表者欄が1名分しかないケースが多い
- 銀行の印鑑証明などが1人の代表向けに設計されている
- 日常業務で責任の所在があいまいになる
まず、代表社員が2名いると、重要な意思決定のたびに必ず話し合いが必要です。スピード感のある判断が求められる場面では、これがネックになることもあるでしょう。
また、税務や行政手続きにおいても、代表者の欄が1名分しかないことが多く、代表社員が2名いるケースではどちらか1名を選ばざるを得ないことがあります。
このような場合、事実上の「代表権の偏り」が発生し、トラブルの原因になり得ます。


代替案としての株式会社
合同会社の代表社員を2名以上にすることで、もめてしまうケースが多いのは事実です。こうしたトラブルの回避策として、株式会社を設立するという選択肢もあります。
株式会社では、持株比率によって議決権が決まります。代表社員を2名にしても、出資額に比例して意思決定権をどちらか一方に設定できるのです。
また、代表取締役を1名として、もう1名を取締役にするという方法もあります。たとえば次のような方法です。
共同代表にしたい場合:出資比率に差をつけたうえで2名とも代表取締役にする
共同代表にしない場合:代表取締役は1名、もう1名は取締役にすることで最終決定権の所在を明確にする
また、会社の規模が大きくなったら、取締役会や監査役を置いて、チェック機能を強化するという方法もあります。
合同会社は役員や代表社員などの自由度が高い一方で、そのときの感情や複雑な人間関係に左右されやすい構造でもあります。トラブルを回避するために、株式会社の方が安定的な運営につながる可能性もあります。
合同会社とは
合同会社とは、出資者が経営にも直接関与する会社形態です。株式会社より比較的自由度が高く、設立費用も抑えられる点が特徴です。
ここでは、合同会社の仕組みと、株式会社との違いを項目ごとにわかりやすく解説します。
出資者が会社の経営者
合同会社では、原則として出資者がそのまま経営に携わる「社員」となります。株式会社のように所有と経営が分離されていないのが合同会社です。
この社員は、株式会社における「株主」と「取締役」の両方の役割を持ち、一般的な「社員」という意味の従業員とは異なります。社員は、会社に出資している所有者でありつつ、経営判断にも携わっています。
所有と経営を分離しないという仕組みにより、株主の意向に左右されることなく経営権が出資者に集約されるのが合同会社の特徴です。特に、少人数で効率的に経営を行いたい人にとっては、非常に扱いやすい法人形態といえます。
株式会社との違い
合同会社と株式会社は、どちらも会社法で定められた会社形態です。その仕組みにはさまざまな違いがあります。
会社の持ち主と経営者
株式会社の構造は、出資者であり所有者である「株主」と、株主から経営を委任されている「取締役」に分かれています。
一方、合同会社は、出資者(社員)がそのまま経営を行うため、会社の所有や出資の責任、そして意思決定が同一人物に集約されるという構造です。
この違いにより、合同会社の方が経営のスピードや柔軟性に優れていますが、合同会社は株式の発行はできないため第三者からの出資を受けにくいという面もあります。
意思決定の方法
株式会社では、株主総会での決議や取締役会によって重要な意見決定が行われます。一方、合同会社では社員全員の合意が原則です。代表社員が1名の場合は合同会社の方がスピード感のある判断が可能ですが、2名以上の代表社員を置く場合は意思決定のスピードはやや遅くなります。
ただし、合同会社でも、定款で定めることで、一部の社員にのみ業務執行権限を与える柔軟な設計も可能です。
定款認証の有無
定款とは会社の基本的なルールを定めたものです。株式会社でも合同会社でも必ず設立時に定款を作成しなければなりません。
株式会社の設立時には、公証役場で定款認証を受ける必要もあります。合同会社の場合、定款認証は不要です。
この違いにより、合同会社は設立費用が安く、手続きが簡素で時間も手間も短縮できます。
役員の任期の有無
合同会社には、株式会社の取締役にあるような任期の制限がありません。そもそも合同会社には会社法上の役員は存在しないのです。そのため、役員の重任(再任)手続きも不要となります。株式会社では必ず必要になる役員の重任登記の手間や費用を抑えることができます。
こうした制度は、長期的に同じメンバーで経営を続けていく家族経営の仲間同士で会社を作るケースで、大きなメリットとなります。
経営者の呼び方
経営者の呼び方は、必ずしも会社法上の役職名と同じではありません。
合同会社で代表社員を2名にする場合、会社法上は2人とも同じ立場となります。ビジネスをするうえで同じ役職の人物が2人いると混乱する場合もあるため、それぞれ違う呼び方をしても問題ありません。
株式会社では「代表取締役社長」といった呼び方や肩書きが一般的ですが、合同会社の代表社員の場合は「社長」や「代表」といった呼称が一般的です。
代表社員と業務執行社員について
合同会社では、出資者である社員の中でも、対外的に会社を代表する人と、内部的に業務を執行する人を区別できます。ここからは代表社員と業務執行社員の違いを整理します。
代表社員
代表社員とは、会社の代表権を持つ社員のことです。契約書への署名や行政への届出など、会社名義での意思決定を行うことができます。
合同会社では、原則として社員全員が業務執行権を持ち、すべての社員が登記されます。そして定款で定めることで、特定の社員だけを代表社員として指定することもできます。株式会社や有限会社でいうところの「代表取締役」のような立場です。
代表社員を明確に定めておくことで、外部との取引もスムーズになり、社内の責任範囲も整理されます。
なお、定款に定めることで「業務執行をしない社員」を置くこともできます。この場合、当該社員は出資するのみで経営には関わらず、登記もされません。
業務執行社員
業務執行社員とは、会社の日常業務を執行する権限を持っている社員のことです。代表社員と異なり代表権はありませんが、意思決定や業務運営は可能です。株式会社の取締役のような立場です。
たとえば、代表社員1名が代表権を持って対外的な意思決定を担い、もう1名の業務執行社員が開発やマーケティングを行うという役割分担もできます。
つまり、合同会社では、2名以上の社員に業務執行権限を持たせることも、1名のみに権限を集中させることも可能ということです。
こうした柔軟な設計が可能な点が、合同会社の大きな魅力です。ただし、定款の記載内容と登記の整合性を保つことが重要となります。
合同会社の代表社員の給与について
合同会社の代表社員が受け取る報酬には、ルールがあります。
ここでは、給与の決定方法、時期、変更制限など、知っておくべき実務上のポイントを解説します。
合同会社の給与は社員総会もしくは定款で決定する
合同会社では、社員の給与は社員全員による同意もしくは、定款の定めで決定します。社員全体の意思もしくは定款で報酬額を決めるわけです。
定款で報酬決定の方法を別途定めていない場合は、社員全員の合意が原則です。できるだけ会社設立時に報酬額を決めておくのが望ましいとされます。
会社設立してから3カ月以内
合同会社を設立した場合には、設立から3カ月以内に代表社員の給与額を決定しなければなりません。
報酬は増額や減額が可能ですが、条件があります。増額する場合は損金算入されないケースがあるため注意が必要です。設立後に売上の見通しが立ってから代表社員の報酬を決めたいというケースもあるかもしれませんが、あらかじめ事業計画を立てて無理のない範囲で報酬額を設定しておくことが重要です。
原則、報酬は「定期同額給与」になるため、毎月同じ金額が支給されます。
原則として1年は変更できない
代表社員の給与は、年の途中で金額を変更することが原則として認められていません。
期中に報酬を変更した場合は、全額損金不算入となり税務上のデメリットがあります。事業の利益が上がってきたため報酬を増やしたいという場合でも、基本的には翌事業年度まで待つ必要があります。
例外として報酬を変更できるのは以下のような場合です。
- 業績悪化による改定
- 病気のため職務が執行できない
報酬の変更を検討する場合には、税理士などの専門家と相談のうえ慎重に進めることが大切です。
合同会社は代表社員2名で設立・運営できる
合同会社では、代表社員を2名にすることができます。
合同会社の出資者がそのまま経営者になる仕組みと、株式会社との制度的な違いを理解することで、最適な運営ができます。
一方、代表社員を2名にした場合の意思決定の複雑さや、給与の決定・変更時期に関する税務ルールなど、デメリットも多く存在します。
設立後のトラブルや不利益を避けるためにも、あらかじめ会社法のルールや社員同士の役割分担を明確にし、必要に応じて税理士などの専門家に相談することが大切です。
事業の安定と信頼性のある経営体制を築くためにも、制度の理解と計画性は欠かせません。