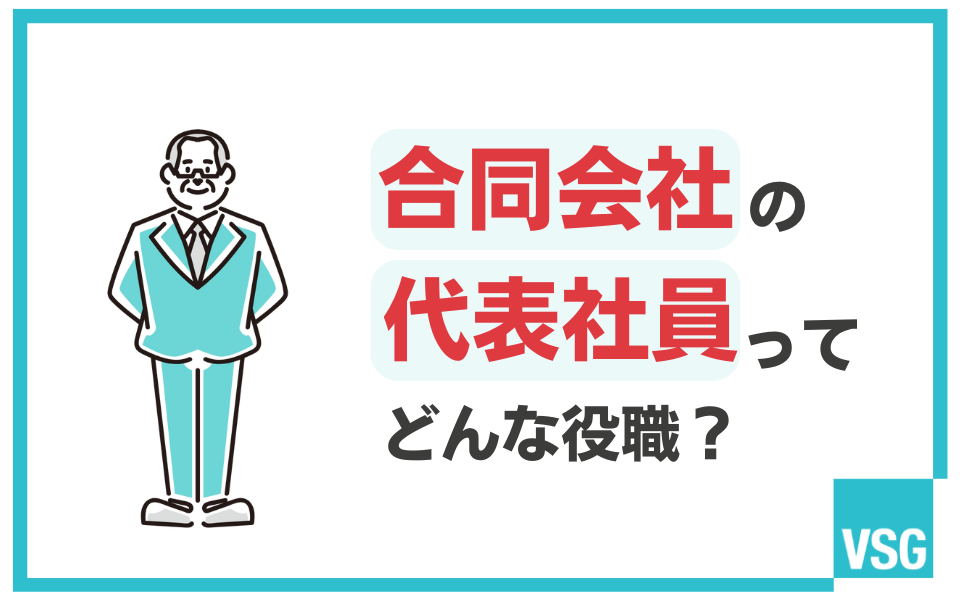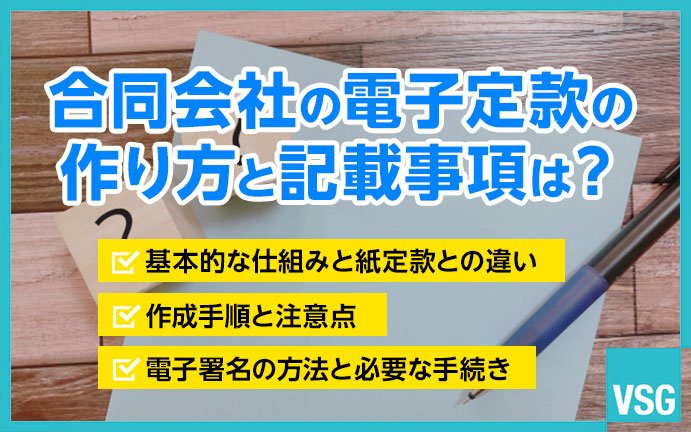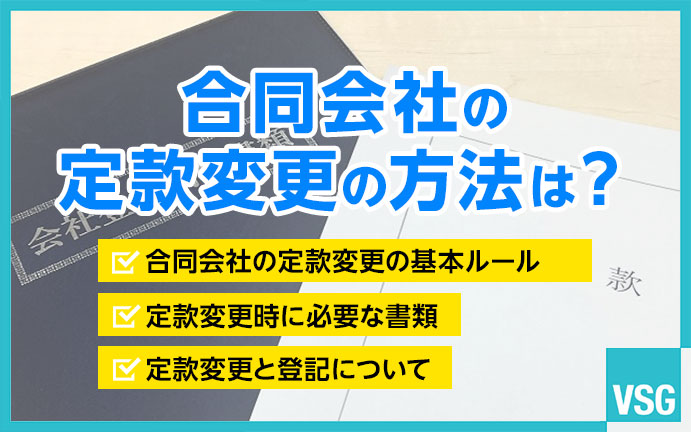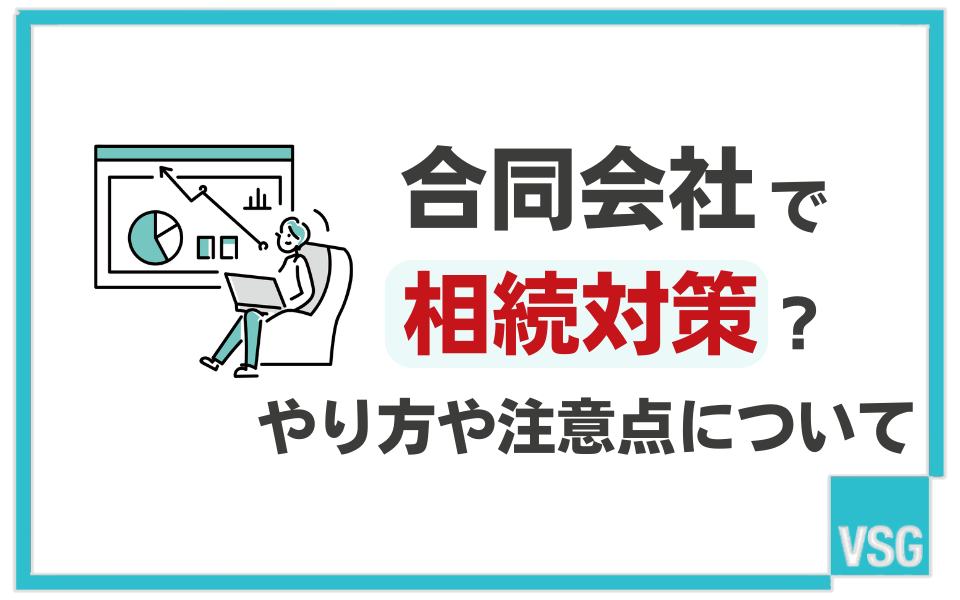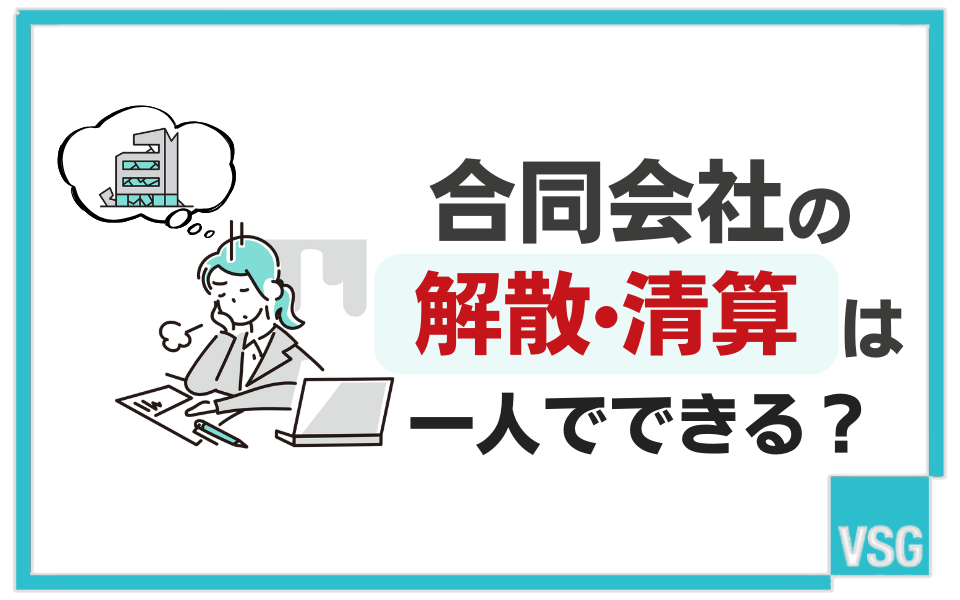最終更新日:2025/11/21
合同会社は決算公告を行う義務がない?行わないメリットなどについて解説

ベンチャーサポート税理士法人 大阪オフィス代表税理士。
近畿税理士会 北支部所属(登録番号:121535)
1977年生まれ、奈良県奈良市出身。
起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネルを運営。
PROFILE:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_writing/#p-mori
YouTube:会社設立サポートチャンネル【税理士 森健太郎】
書籍:プロが教える! 失敗しない起業・会社設立のすべて (COSMIC MOOK) ムック

すべての法人は決算を行いますが、その内容を公告で一般に公開する義務があるかは、会社の形態によって異なります。
近年設立数が増加している合同会社は、決算公告を行わなくてもよいとされています。
しかし、なぜ合同会社は決算公告を行う義務がないのでしょうか。また、決算公告を行わないことでどのようなメリットがあるのでしょうか。
この記事では、合同会社が決算公告を行わないメリットなどについて解説しています。
また、決算公告と法定公告の違いや、公告を行う際の方法と費用、よくある質問などもまとめて解説しているので、合同会社を設立する方はぜひ一度ご覧ください。


目次
決算公告とは
決算公告とは、法人が行った決算から簡易的な貸借対照表などを作り、公告に記載して一般に公開することを指します。
これを確認することで、債権者や取引先、従業員などのステークホルダー(利害関係者)はその法人の経営状態などを確認することができます。
株式会社は会社法440条にて、決算公告を行うことを定められています。
合同会社には決算公告の義務がない
合同会社は、会社法などの法律で決算公告を行うことを定められていません。
実際、決算公告を行わなくても特段の不利益は生じないため、ほとんどの合同会社は決算公告を実施していません。
この決算公告義務の有無は、合同会社と株式会社の大きな違いの1つです。
決算そのものは合同会社も行う必要がある
合同会社は決算公告を行う義務はありませんが、決算そのものは必ず行い、税務申告をしなければいけません。
決算を怠ると、会社法976条2項により個人に対して100万円以下の過料が科される可能性があります。
また、取引先や金融機関からの信用を大きく損ね、普段の業務にも大きな影響を及ぼします。
必ず決算日の翌日から2カ月以内に決算を行い、確定申告書を税務署に提出して納税するようにしましょう。
なぜ合同会社には決算公告の義務がないのか
合同会社に決算公告の義務がない大きな理由としては、株式会社と違って外部の人から出資を受けることがなく、債権者を保護する必要性が薄い点があげられます。
また、合同会社は、会社法の改正によって有限会社が新設できなくなった際に、それを引き継ぐ形で創設されました。
有限会社にも決算公告義務はなかったため、それを踏襲した合同会社にも決算公告義務が免除されているのです。
参考:会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第二十八条|e-Gov 法令検索
決算公告を「行わない」メリットとは
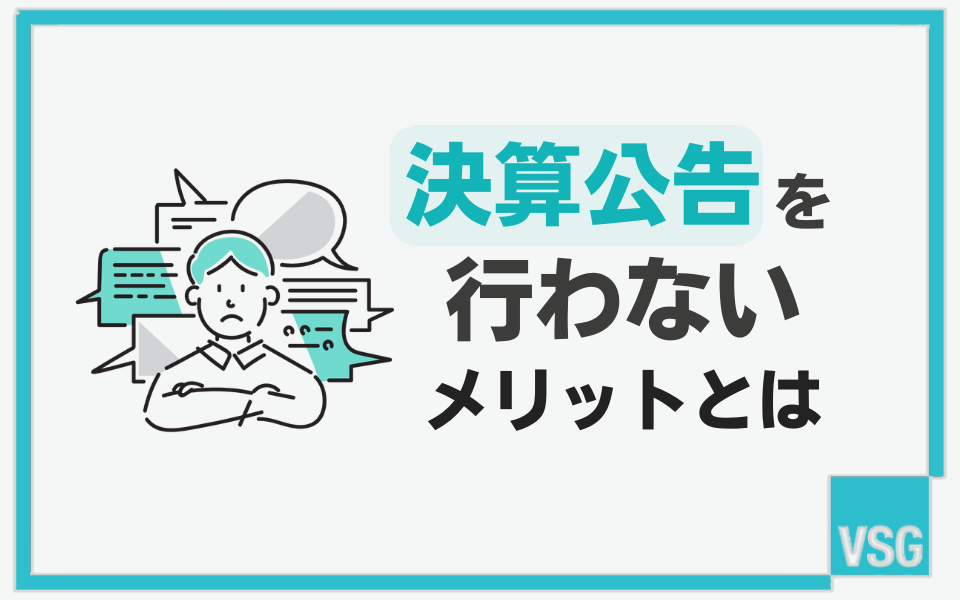
合同会社が決算公告を行わないメリットには、書類作成の手間や公告費用が不要になる以外にもさまざまなものがあります。
- 財務諸表を交渉材料にされにくくなる
- 経営悪化や負債を取引先などに知られにくくなる
- 会社の戦略がバレにくくなる
- 給与水準が把握されにくくなる
これらは株式会社にはない、合同会社ならではのメリットとも言えます。


財務諸表を交渉材料にされにくくなる
決算公告では財務諸表という、会社の財務状況や経営状態などに関する書類を公開します(上場している株式会社の場合)。
粗利率や販管費率からは、取引価格の値下げをする余地があるかどうかを読み取ることができるため、これらが価格交渉などの材料にされることがあります。
決算公告を行わないことで、これらの情報が相手に渡ることを予防できます。
経営悪化や負債を取引先などに知られにくくなる
財務諸表からは、その会社が黒字なのか、負債がどれくらいあるのかなども読み取ることができます。
会社の経営が思わしくないときに、これらの情報が取引先や金融機関に伝わると、融資や取引に悪影響を及ぼす可能性があります。
決算公告を行わないことで、一時的にはこうした影響を回避できるでしょう。
会社の戦略がバレにくくなる
財務諸表からは投資の割合や、広告宣伝や研究開発などにいくら費用をかけているかも読み取ることができます。
競合他社などにこの情報がバレてしまうと、それを前提とした対策を打たれてしまうかもしれません。そうした場合は、経営戦略がうまくいかなくなる要因になり得ます。
合同会社が行わなければいけない公告とは
合同会社には決算公告の義務はありませんが、資本金額の減少や吸収合併、解散、株式会社と合同会社の組織変更などの際には、公告を行うことが法律によって義務づけられています。
これらは「法定公告」と呼ばれ、債権者を保護する目的で行われます。
たとえ債権者が自分一人しかいない場合でも、法定公告は行わないといけません。
公告の方法は定款の「任意的記載事項」
多くの合同会社は、定款に公告の方法について記載しています。
もっとも、公告の方法は記載するかどうかを自分で選ぶことのできる「任意的記載事項」のため、定款作成時に定めなくても問題ありません。
ただしその場合、「公告は官報にて行う」と自動的に決定されてしまうので、新聞やWebで公告を行いたい場合は注意しましょう。
また、設立登記申請を行う際には「登記すべき事項」に公告の方法を記載しなければいけません。
合同会社でも法定公告は行わなければならないことや、会社設立の前には決定しなければならない事項であることを考慮して、早めにどのような方法で公告を行うかを決めておくといいでしょう。
公告の方法と費用
公告は主に以下の3種類の方法で行います。
- 官報
- 電子公告
- 新聞公告
官報とは国が発行している新聞のようなものであり、最も一般的な公告方法です。
決算公告を官報で行う場合、貸借対照表の全文ではなく、要旨のみを掲載すればよいとされています。
費用はおよそ7万円ほどです。
電子公告は、自社のWebページに公告内容を記載する方法です。
自社内で公告を公開する場所を用意できるため、一見するとコストを抑えられる公告方法に見えます。
しかし、決算公告を電子公告で行う場合は、貸借対照表の全文を掲載しなくてはならず、また5年間もの間、掲載し続ける必要があります。
さらに法定公告では、公告した内容についての登記申請を行う際に「公告をしたことを証する書面」が必要になります。
これは外部の調査会社に発行してもらわなければならず、費用として数万~数十万円がかかります。
合同会社がそもそも決算公告を行う必要がないことを考えると、電子公告を公告手段とするメリットは薄いと言えるでしょう。
新聞公告は、日刊新聞紙に公告内容を掲載する方法です。
全国紙でも地方紙でも問題はありませんが、ほかの公告方法と比べて割高になるため、ほとんど利用されることはありません。
公告方法については以下の記事でも解説しています。
合同会社の公告でよくある質問
合同会社の公告について、よくある疑問や質問をまとめました。
公告費用は経費になるのか
公告費用は、主に「広告宣伝費」として経費にすることができます。
官報や新聞での公告の場合はすべて広告宣伝費で計上できますが、電子公告を行う場合はサーバー料を「支払手数料」として計上するなど、かかった費用によって取扱いが変わることもあるので注意してください。
また、公告は消費税課税取引のため、「租税公課」科目にはならない点にも注意が必要です(ただし、官報のみ非課税です)。
どれくらいの合同会社が決算公告を行っているのか
公的なデータなどは集計されていませんが、決算公告を行う株式会社がわずか1~2%ほどであることを考慮すると、合同会社はそれ以下の割合になるでしょう。
Google合同会社やAmazonジャパン合同会社などの有名企業も決算公告を行っておらず、基本的に合同会社は決算公告を行わないものと考えて問題ありません。
決算公告では何を公表するのか
株式会社の決算公告では、大会社は貸借対照表および損益計算書を、中小会社は貸借対照表を公表します。
また、上場している株式会社はこれらの決算公告義務が免除されています。
その代わり、金融商品取引法24条にて「有価証券報告書」という、より詳しく会社の実情が把握できる書類を公表しなければならないと定められています。
合同会社の場合、そもそも決算公告の義務がないので、どのような書類を公表するかは事業者自身で判断することになります。
合同会社が決算公告を行うことにメリットはあるのか
会社の財務状況や経営状況を公表することで、取引先や金融機関から一定の信用は得られるかもしれません。
もっとも、現状でほとんどの合同会社が決算公告を行わずに経営していることや、そもそも取引先や金融機関が直接企業に決算書の提出を求めることもあることを考えると、合同会社が決算公告を行うメリットはあまりないと言えるでしょう。
この記事のまとめ
合同会社は決算公告を行う義務がなく、また行わないことで生じるデメリットも特にありません。
むしろ自社の情報を外部に知られずに済むため、ほとんどの合同会社は決算公告を行っていません。
ただし、合同会社であっても合併や解散、株式会社への変更などの際には、債権者保護の観点から「法定公告」を行う必要があります。
公告方法は官報と電子公告、新聞公告から選べますが、法定公告のみを行うのであれば、官報が最も一般的かつトータルでのコストを抑えられる方法です。
合同会社の決算や公告について悩んだら税理士に相談しよう
合同会社は決算公告を行う必要はありませんが、決算は必ず行わなくてはいけません。
公告に関しても、株式会社と比べて機会は少ないとはいえ、行うべきタイミングや方法については把握しておく必要があります。
決算などは特に作業の手間も大きく、自社だけで行うのが難しいこともあるでしょう。
経理に関する作業だけでなく、会社の設立や運営上の疑問や不安があるときは、会社設立を専門とする税理士や司法書士に一度相談してみてください。
ベンチャーサポート税理士法人では、会社設立・運営に関する無料相談を実施しています。
税理士だけでなく行政書士や司法書士、社労士も在籍しているため、税金や許認可、登記申請など、会社に関する悩みについてワンストップで相談が可能です。
レスポンスの速さにも定評があるため、初めての方もお気軽にご相談ください。