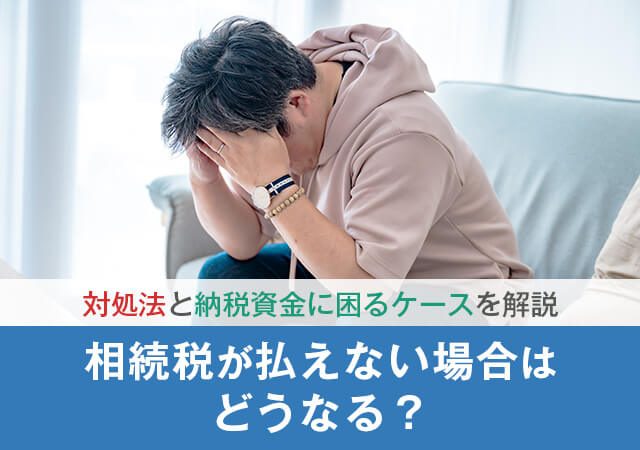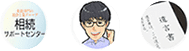この記事でわかること
- 相続税の支払いが難しくなるケース
- 相続税が払えない場合の対処方法
- 相続税の納付が遅れるとどうなるか
相続税は現金一括払いが原則です。
しかし、相続財産が主に不動産であるなど納税資金が準備できない場合はどうすればいいのでしょうか。
相続税が払えないときの主な方法として、「金融機関からの借入」「相続財産の売却」「延納・物納制度の利用」がありますが、それぞれに注意点があります。
今回の記事では、それぞれの納税資金調達方法の内容と注意すべき点、相続税の納付が遅れた場合はどうなるのかをご説明します。
目次
相続税の納税資金に困る代表的なケース
相続税は、被相続人が亡くなった時点で持っていた財産額が一定額を超えると納税義務が発生します。
相続税の最高税率は55%であり、相続した財産額よりも多い税額となることはありませんが、現金一括納付が原則です。
また、納付期限は短く、相続発生を知った日の翌日から10カ月後です。
そのため、相続した財産の種類や相続人の状況によっては納税に苦慮することがあります。
相続財産の多くが不動産である
相続財産が不動産のようにすぐに換金できないもの、流動性の低いものが大半を占めている場合、納税資金が用意できないことがあります。
不動産は、すぐに売却できない資産の代表格です。
売却までに多くの手間と時間がかかる、納得のいく金額ではないといったことから、相続税の申告・納税の期限までに現金の用意が間に合わないケースも想定されます。
相続財産の多くが非上場株式である
相続財産の大半が非上場株式である場合も、相続発生時に多額の相続税が発生する一方で、納税資金が足りないことがあります。
多くの企業では、役員退職金や生命保険金による資金確保、事業承継税制の活用などで納税資金を確保できるよう、生前から相続税の対策を検討していることでしょう。
しかし、会社にも資金がない場合、株式が現金化できず納税に苦慮する可能性もあります。
遺産分割協議不成立により被相続人の預金が引き出せない
遺言書がないときは、相続人全員で誰がどの財産を取得するのかを話し合います。
その話し合いを遺産分割協議といいますが、協議が成立しない場合、被相続人の預貯金は一定額までしか引き出すことができません(遺産分割前の相続預金の払戻し制度)。
金融機関は、口座の名義人の死亡を知ると、口座を凍結して引き出せないようにします。
被相続人が多額の預貯金を持っていたとしても、「誰が何をいくら相続する」という話し合いがつかない限り、その預貯金を使うことはできないのです。
また、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例はそれぞれ、配偶者が何を相続するか、土地を誰が相続するかが決まらないと適用できません。
遺産分割協議が不成立でこれらの制度も適用できないと、相続税額が高くなってしまう上に被相続人の預貯金が下ろせず、納税に苦慮することになります。
遺産分割協議の結果、十分な現預金を確保できなかった
例えば遺産分割協議が成立した後、被相続人の自宅に同居していた相続人が、今後も住み続けるためにその自宅を相続したとします。
しかし、自宅の評価額だけで自身の法定相続分に達してしまい、結果としてその人は預貯金を相続できませんでした。
このような場合、自宅を引き継いだ相続人が既に十分な預貯金を保有していれば問題ありませんが、そうでない場合には、相続税の納税資金を準備できず、資金繰りに困る恐れがあります。
相続税が払えない場合の対処方法
相続財産や手持ちの資金で納税ができない場合は、金融機関からの借り入れ、相続財産の売却、延納・物納制度を利用する方法が考えられます。
相続財産の一部を売却する
不動産や上場株式、車両、貴金属など、相続したものの自分で使わない財産であれば、売却して納税資金に充てることも一案です。
譲渡所得を生じるものを売却した場合、譲渡所得税を納付することになりますが、相続税の申告期限の翌日以後3年を経過するまでの間(通常は相続発生から3年10カ月)に売却したのであれば、譲渡所得を計算するときに、相続税の一部を取得費として差し引くことのできる特例があります。
不動産などは売却に時間がかかる可能性があるので注意
相続した財産を売却するといっても、特に不動産の場合は仲介業者に買主を探してもらい、双方納得する値段で売買契約が成立するまでに時間がかかります。
その場合は、金融機関から融資を受けて納税をしたのち、時間をかけて納得のいく買い手を探すという方法もあります。
延納・物納の申請をする
現金一括納付が原則といえども、納税資金が準備できない人のために、相続税においては延納(分割納付)・物納(キャッシュでなくモノで納める)の方法が用意されています。
延納・物納は平成18年の税制改正で要件が厳しくなり、相続した現預金に加え、納税者固有の現預金から当面の生活費などを控除した額を納税に回し、それでも払いきれない場合に延納・物納を申請できるとされました。
また、令和5年度における許可件数は、延納が864件、物納が16件です。
申請すれば必ず通るわけではないことを覚えておいてください。
延納の適用要件
延納の適用要件は以下のとおりです。
- 相続税額が10万円を超えること
- 金銭で納付することを困難とする事由があり、かつ、その納付を困難とする金額の範囲内であること
- 延納税額および利子税の額に相当する担保を提供すること(※担保不要となる条件もあり)
- 延納申請に係る相続税の納期限または納付すべき日(延納申請期限)までに、延納申請書に担保提供関係書類を添付して税務署長に提出すること
まず、延納ができるかどうかの入口は「相続税額が10万円を超えること」です。相続税額が10万円未満の場合、延納はできません。
延納額は、「金銭で納付することが困難な金額の範囲内」である必要があります。
相続した現預金や、納税者がもともと持っていた固有の現預金から当面の生活費などを差し引いた残額は「納税に回すことのできる金額」とみなされ、税額から納税に回すことのできる金額を差し引いた額が延納対象額となります。
延納には担保提供が必要であり、必要な担保額は「延納税額+第1回目の分納期間にかかる利子税の額✕3」です。
第三者が所有する財産も担保として提供できますが、担保物所有者の承諾書などが必要となります。
なお、延納税額が100万円以下で、延納期間が3年以下である場合には担保提供は必要ありません。
延納を希望する場合は、「延納申請書」と「担保提供関係書類」を相続税の申告期限までに提出する必要があります。
延納申請書は提出期限の延長はできませんが、担保提供関係書類は提出期限の延長が可能です。
もし、申請期限までに担保提供関係書類を提供することができない場合は、「担保提供関係書類提出期限延長届出書」を提出することにより、1回につき3カ月を限度として、最長6か月まで担保提供関係書類の提出期限を延長することができます。
なお、延納中は利子税がかかります。
物納の適用要件
物納の適用要件は、以下のとおりです。
- 延納によっても金銭で納付することが不可能であること
- 申告期限までに物納申請書を提出し、所轄税務署長の許可を受けること
- 物納申請できる財産は、原則として相続により取得した財産であり、物納申請額を超えない価額であること
物納は、延納でも納付できない税額がある場合に認められる納税方法です。
物納できる財産には制限があります。
相続時精算課税の適用を受けた財産、贈与税の納税猶予の特例の適用を受けた非上場株式等および、個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予の特例の適用を受けた事業用資産は、物納の対象になりません。
また、物納できる財産は日本国内にあるものに限られ、順位が定められており、先順位のものから選定します。
物納できる財産であっても不適格とされるもの(担保権の設定の登記がされている不動産や、権利の帰属について争いがある不動産など)もありますので注意が必要です(管理処分不適格財産)。
| 優先順位 | 物納に充てることができる財産の種類 |
|---|---|
| 第1順位 | 1.不動産、船舶、国債証券、地方債証券、上場株式等 |
| 2.不動産および上場株式のうち物納劣後財産に該当するもの | |
| 第2順位 | 3.非上場株式等 |
| 4.非上場株式のうち物納劣後財産に該当するもの | |
| 第3順位 | 5.動産 |
物納財産を国が収納するときの価額は、原則として相続税の課税価格計算の基礎となったその財産の価額になります。
例えば、小規模宅地等の特例を適用を受けた相続財産を物納する場合の収納価額は、特例適用後の価額となります。
物納を希望する場合は、「物納申請書」と「物納手続関係書類」を相続税の申告期限までに提出します。
物納申請書は期限が過ぎると却下されてしまうため、必ず期限内に行う必要があります。
申請期限までに物納手続関係書類を提出することができない場合は、「物納手続関係書類提出期限延長届出書」を提出することにより、1回につき3カ月を限度として、最長で1年まで物納手続関係書類の提出期限を延長することができます。
また、物納も利子税がかかる点には注意しましょう。
物納が許可されると「相続税の納期限または納付すべき日から収納の日までの期間」について、物納が却下された場合などは「却下された日までの期間」について、利子税がかかります。
金融機関から借り入れをする
金融機関は、相続税納税手段としての融資商品を用意しています。
資金の使い道は幅広く、相続税の納税だけでなく代償分割の支払いや事業承継に必要な株式取得、弁護士、税理士、司法書士などの報酬費用の支払いなどにも充てることができます。
相続を乗り切るために役立つ融資商品ですが、利用するには保証人を要することが多く、担保への抵当権設定の費用が発生したり、融資審査に時間がかかったりすることもあります。
また、途中で繰り上げ返済をする場合、繰り上げ返済手数料が発生します。
金融機関によっては、相続財産が未分割の状態だと融資を受けられないこともあるため、事前に確認しておきましょう。
期限日までに相続税を払わないとどうなるか
相続税の納付期限は、相続税申告書の提出期限と同日です。
申告期限日を過ぎて申告・納税をしていない場合、ペナルティーが発生します。
また、相続税においては、「連帯納付義務」があるため、自分の納税は済ませていても、自分以外の相続人が納税しなかった場合、納税義務が発生します。
ペナルティーの税金が課される
相続税申告書の提出期限までに申告・納税をしないと、無申告加算税と延滞税が課されます。
無申告加算税の税率は、税務調査の事前通知の前に自主的に期限後申告をした場合には、税率5%です。
税務調査の事前通知の後に期限後申告をした場合(調査による決定を予知する前の期限後申告)は税率10%、税務調査を受けた後に期限後申告をした場合(調査による決定を予知した期限後申告)には税率15%となり、50万円を超える部分に対してはさらに税率が上がります。
ただし、期限後申告であっても、次の要件をすべて満たす場合には無申告加算税はかかりません。
- その期限後申告が、法定申告期限から1カ月以内に自主的に行われていること
- 期限内申告をする意思があったと認められる一定の場合に該当すること
延滞税は、法定納期限の翌日から2カ月を経過する日までの期間は年2.4%(令和7年6月現在)、2カ月を経過した日以後は年8.7%(令和7年6月現在)が課されます。
自分以外の相続人が納めていない分も納税義務がある
複数の相続人がいる場合、相続税の納付に関して「連帯納付義務」が課されます。
連帯納付義務とは、自分の納税が済んでいたとしても、他の相続人が納税していない場合は、その人の代わりに納めなければならないという制度です。
代わりに納める額は、その相続で得た利益の範囲内となり、自分の私財をもってしてまで負担しなければいけないわけではありません。
通常、期限までに相続税が納められなかった相続人に対しては、税務署が本人に対し督促を行います。
しかし、その相続人からの納付が困難であると認められる場合には、税務署は他の相続人に通知を出して、代わりに納付させることが可能とされています。
なお、この連帯納付義務により納める税額については、延納や物納を利用することはできず、現金での一括納付が原則とされています。
本税だけでなく、利子税が生じている場合も同様です。
相続税の納税資金に困ったら早めに税理士に相談しよう
相続税の納税には延納・物納という制度があるものの、手続きの煩雑さに加え、当面の生活費を超える手持ちの現預金を納税に回し、それでも払いきれない税額に対して制度を利用できるとされています。
そのため、手元資金が手薄になることを不安に思い、延納・物納制度の利用をあきらめる人が非常に多いのが実情です。
相続税の納税資金が足りないときは、相続財産を売却して資金を確保するか、金融機関から融資を受ける方法が考えられます。
特に相続財産を売却する場合は、相続税と譲渡所得税というダブルの税負担を出来る限り軽減させるため、取得費加算の特例や空き家特例などの特例制度を利用したいところになります。
VSG相続税理士法人では、グループ内の不動産会社で売却のお手伝いが可能です。
また、相続税の申告、譲渡所得税の申告、不動産の登記まで、グループ全体ですべてワンストップでサポートいたします。
相続税の納税に不安を感じたら、ぜひ一度ご相談ください。
相続専門税理士の無料相談をご利用ください

ご家族の相続は突然起こり、何から手をつけていいか分からない方がほとんどです。相続税についてはとくに複雑で、どう進めればいいのか? 税務署に目をつけられてしまうのか? 疑問や不安が山ほど出てくると思います。
我々VSG相続税理士法人は、相続人の皆さまのお悩みについて平日夜21時まで、土日祝も休まず無料相談を受け付けております。
具体的なご相談は無料面談にて対応します。弊社にてお手伝いできることがある場合は、その場でお見積り書をお渡ししますので、持ち帰ってじっくりとご検討ください。
対応エリアは全国で、オフィスは東京、埼玉、千葉、横浜、名古屋、大阪、神戸、福岡の主要駅前に構えております。ぜひお気軽にお問い合わせください。