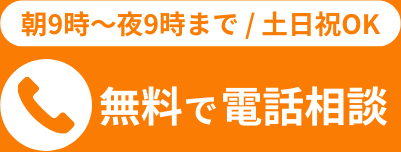この記事でわかること
- 家を相続するときは、相続税の申告・納付や相続登記など、複数の手続きが必要になる
- 「相続税の納付」「相続登記」「家の維持・売却」をするときには、それぞれ安くない費用がかかる
「実家を相続することになったものの、何から手をつければいいのかわからない……」
このようにお悩みの方へ向けて、本記事では、家を相続する際の「基本的な手続きの流れ」と「かかる費用」をお伝えします。
相続に関する不安を解消し、落ち着いて手続きを進めるための第一歩として、ぜひ最後までお読みください。
目次
家を相続したらまず何をする?名義変更・相続税・登記の手続きと費用を相続専門税理士がわかりやすく解説
動画の要約家を相続する際に必要な手続きや費用について、相続専門税理士が詳しく解説しています。遺言書の確認、遺産の全体像の把握、相続人の調査、分割協議、相続税の申告、そして相続登記の手続きが必要です。また、相続に関わる費用や特例についても説明されており、専門家への相談を推奨しています。
家を相続するときの手続きの流れ
まずは、家(土地・家屋)を相続したときに必要な手続きの流れを見ていきましょう。
「住宅と宅地」に限らず、不動産の相続手続きは、基本的に次の4ステップで進めます。
| ステップ | 概要 |
|---|---|
| 相続人・遺産の調査 | ・誰が相続人で、被相続人に財産がどれだけあるかを調査する ・この調査が、後の遺産分割や相続税計算の基礎になる |
| 遺産分割協議 | ・遺言書がない場合は、相続人全員で遺産の分け方を話し合う ・遺産の分割方法に全員が合意したら、その内容を「遺産分割協議書」にまとめる ・なお、遺言書があれば、原則としてその内容に従って相続を進める |
| 相続税の申告・納付 | ・相続財産の総額が、一定の金額(基礎控除額)を超える場合は、相続税の申告と納付が必要 ・期限は、原則として「相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内」 |
| 相続登記 | ・相続した不動産(家、土地、マンションなど)の所有者の名義を、亡くなった方から相続人へ変更する ・相続登記は、原則として「相続により不動産の取得を知った日から3年以内」に申請しなければならない |
以上の不動産に関する相続手続きの詳細は、下記の記事でお伝えしています。
なお、相続に関する手続きは複雑で手間もかかります。そこで、手続きをスムーズに進めたい場合は、税理士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
家を相続した際にかかる費用
ここでは、家を相続した際にかかる費用を次の4つに分けて紹介します。
- 相続税申告にかかる費用
- 相続登記にかかる費用
- 家を所有することでかかる費用
- 家を売却するときにかかる費用
それぞれ詳しく見ていきましょう。
費用1. 相続税申告にかかる費用
相続する財産の総額が基礎控除額を超える場合、相続税の申告・納付が必要です。
相続税の基礎控除額 = 3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)
この相続税の申告・納付の手続きに関連して、主に以下の費用が発生します。
| 費用 | 概要 |
|---|---|
| 書類の取得費用 | ・相続税の申告には、亡くなった方や相続人の戸籍謄本など、多くの書類が必要になる ・これらの書類を取得する際、役所や金融機関などで手数料がかかる ・1通あたり数百円程度だが、必要な書類が多い場合は、合計で「数千円~1万円程度」になることもある |
| 税理士への報酬 | ・自分で申告するのが難しい場合は、税理士に依頼することになる ・税理士への報酬は、遺産総額や財産の内容、依頼する業務範囲によって異なるが、「数十万円~」が相場となる |
| 相続税 | ・遺産の総額から基礎控除額を差し引いた金額がプラスになる場合、そのプラス部分(課税遺産総額)に対して相続税が課される ・納付する相続税額は、課税遺産総額や各相続人が取得する財産の割合に応じて計算される |
上記のうち、「相続税」の金額を算出するうえでは、家を「土地」と「家屋」に分けて、それぞれの価値を評価する必要があります。その評価方法は、次のとおりです。
| 種類 | 評価方法 |
|---|---|
| 土地 | ・「路線価方式」または「倍率方式」で評価する ・路線価は国税庁が毎年公表しており、土地が面する道路ごとに価格が定められている |
| 家屋 | ・原則として、市町村が定める「固定資産税評価額」と同額で評価する |
なお、亡くなった方が住んでいた実家などの土地を、配偶者や同居していた子どもなどが相続する場合、一定の要件を満たせば、その土地の評価額を最大80%減額できる「小規模宅地等の特例」を適用できます。
小規模宅地等の特例を活用することで、相続税の負担を大幅に軽減できる可能性があります。
費用2. 相続登記にかかる費用
相続した家(土地・家屋)の名義を、亡くなった方から相続人へ変更する「相続登記」の手続きをする際も、次のような費用がかかります。
| 費用 | 概要 |
|---|---|
| 書類の取得費用 | ・相続登記の申請には、亡くなった方と相続人全員の戸籍謄本などが必要になる ・これらの書類は、役所などで取得する際に手数料がかかる ・1通あたり数百円程度で、合計「数千円~1万円程度」になることが一般的 |
| 司法書士への報酬 | ・相続登記の手続きは、必要書類の収集や申請書の作成など、専門的な知識が求められる ・司法書士に依頼する場合、報酬の支払いが必要になる ・報酬額は、不動産の数や評価額、手続きの難易度などによって異なるが、一般的には「数万円~10数万円」ほどが相場 |
| 登録免許税 | ・相続登記を申請する際に、法務局へ納める税金 ・税額は「不動産の固定資産税評価額 × 0.4%」で計算される |
なお、このうち登録免許税は、2027年3月31日まで免除措置を受けられます。
具体的には、相続した土地の価額※が100万円以下の場合、登録免許税は免除されます。また同じ期限まで、土地を相続した方が登記手続きをする前に亡くなった場合も、その亡くなった方への登記について登録免許税は課されません。
- ※
- 土地の価額は、原則として固定資産課税台帳に登録された価格を指し、価格がない場合は登記官が認定する
費用3. 家を所有することでかかる費用
家の相続手続きが完了した後も、その家を所有し続ける限り、継続的に発生する費用があります。代表的なものは、以下の税金です。
| 税金 | 概要 |
|---|---|
| 固定資産税 | ・毎年1月1日時点で土地や家屋などの固定資産を所有している人に課される税金 ・通常、毎年4月~6月頃に納税通知書が送られてきて、4回に分けて納付するか、一括で納付する ・税額は「固定資産税評価額 × 標準税率1.4%※」が基本 |
| 都市計画税 | ・市街化区域内に土地や家屋を所有している場合に、固定資産税と併せて課される税金 ・税額は「固定資産税評価額 × 制限税率0.3%※」で計算される |
また、上記の税金以外にも、家を所有し続けると次のような費用がかかる可能性があります。
| 費用 | 概要 |
|---|---|
| 火災・地震保険料 | 万が一の災害に備えるための保険料 |
| 修繕費 | 壁塗装や屋根の修理など、経年劣化に伴うメンテナンス費用 |
| 管理費・修繕積立金 | マンションを相続した場合に、毎月かかる費用 |
| 町内会費・自治会費 | 家のある地域によっては必要な費用 |
- ※
- 固定資産税と都市計画税の税率は、市町村によっては、異なる税率が定められている場合がある
費用4. 家を売却するときにかかる費用
家を相続したものの住む予定がない場合は、「売却」することが選択肢の1つになります。
ただし、不動産を売るときには、以下のような費用や税金がかかります。
| 費用 | 概要 |
|---|---|
| 仲介手数料 | ・不動産会社に買主を探してもらい、売買契約が成立した場合に、成功報酬として支払う費用 ・売却価格によっては、「数十万円~百万円以上」になることもある |
| 印紙税 | ・家を売買する際に作成する「売買契約書」に対してかかる税金 ・契約金額に応じて税額が決まっており、詳細は国税庁のWebサイトで確認できる |
| 譲渡所得税 | ・不動産や株式などの資産を売却して得た利益(譲渡所得)に対して課される税金 ・売却益に応じて、所得税と住民税が課される ・税額は、譲渡所得に所得税と住民税の税率をかけて計算する |
なお、譲渡所得税については、譲渡所得から最大3,000万円まで控除できる「空き家特例」があります。詳細は、下記の記事をご参照ください。
家の相続に関するよくある質問
最後に、家の相続に関してよくある質問にお答えします。
Q1. 家を公平に分割する方法は?
家(不動産)の主な遺産分割の方法には、次の4つがあります。
| 分割方法 | 概要 |
|---|---|
| 現物分割 | ・特定の相続人が土地・家屋をそのまま相続する方法 ・手続きは比較的シンプルな一方、家を相続する人としない人の間で、相続する財産の価値に差が出やすく、不公平感が生じることがある |
| 換価分割 | ・家を売却してお金に換え、その現金を相続人で分ける方法 ・現金で分けるため、最も公平な分割がしやすい方法といえるが、売却には時間や手間、仲介手数料などの費用がかかる |
| 代償分割 | ・特定の相続人が家を相続する代わりに、ほかの相続人に対して、相続分の不足額に相当する代償金を自己の財産から支払う方法 ・家を残しながら相続人同士の公平性を保てるものの、家を相続する人に、代償金を支払えるだけの資力が必要 |
| 共有分割 | ・1つの家を、複数の相続人が共有名義で相続する方法 ・持分割合に応じて分けるため、一見公平に見えるが、将来的に問題が起こりやすい |
上記の方法から、ご自身の状況に合せてもっとも公平だと思えるものを選んでください。
Q2. 家の相続でもめたときの対処法は?
相続人同士での話し合いがまとまらず、家の相続で意見が対立した場合は、以下の解決策を検討してみてください。
| 解決方法 | 概要 |
|---|---|
| 弁護士に相談・依頼する | ・相続トラブルに詳しい弁護士に相談し、代理人として、ほかの相続人との交渉を依頼する方法 ・弁護士が間に入ることで、感情的な対立を避け、法的な根拠に基づいて冷静に話し合いを進められる可能性がある ・後の調停や審判を見据えたアドバイスを受けることも可能 |
| 遺産分割調停を利用する | ・家庭裁判所に申立てを行い、調停委員が間に入って、相続人全員の話を聞きながら、合意を目指して話し合いを進める手続き ・調停はあくまで話し合いの場であり、強制力はないものの、中立的な第三者が関わることで解決の糸口が見つかることがある ・調停でも話し合いがまとまらない場合、「審判」の手続きに移行する |
Q3. 家を相続したくないときは?
「老朽化が激しく維持費がかさむ」「親に借金があった」など、さまざまな理由で家を含めた財産を相続したくない場合も考えられます。そのようなときに検討するのが「相続放棄」です。
相続放棄とは、亡くなった方の「プラスの財産(家、預貯金など)」も「マイナスの財産(借入金など)」も、一切引き継がないという意思表示をする手続きです。
家庭裁判所で手続きをして相続放棄が認められると、その人は初めから相続人ではなかったものとして扱われます。
Q4. 相続した実家に誰も住まない場合は?
相続した実家に、「ご自身やほかの相続人が住む予定がない」というケースがあります。
しかし、空き家のまま放置することには、次のようなリスクが伴います。
| リスク | 概要 |
|---|---|
| 維持費の負担が発生する | ・誰も住んでいなくても、固定資産税や都市計画税は毎年かかる ・火災保険料や最低限の光熱費、庭の手入れ費用なども必要になる場合がある |
| 建物が劣化する | ・定期的な換気やメンテナンスをしないと、湿気によるカビや腐食などで建物が急速に傷む |
| 防犯・防災上の問題が生じる | ・空き家を放置すると、空き巣に入られたり、放火されたりするリスクが高まる ・老朽化による倒壊や、台風などで屋根材が飛散することで、近隣に被害を与える可能性もある |
| 特定空家等に指定される | ・管理不全な状態が続くと、自治体から「特定空家等」に指定されて、固定資産税の軽減措置が受けられなくなるなど、負担が大幅に増えることがある |
以上のリスクを理解したうえで、空き家になるのであれば必要に応じて「家の売却」などをご検討ください。
Q5. 不動産を相続したら、不動産取得税はかかる?
不動産取得税は、「売買・贈与・新築」などで不動産を取得した際に、その取得者に対して課される税金です。
「相続(遺産分割や法定相続)」によって不動産を取得した場合は、不動産取得税の課税対象外となります。
ただし、以下のようなケースでは、不動産取得税がかかることがあります。
| ケース | 概要 |
|---|---|
| 特定遺贈 | 遺言によって、相続人以外の人(例:孫、お世話になった人など)が不動産を受け取った |
| 死因贈与 | 「私が死んだら、この不動産をあなたにあげる」といった契約に基づいて不動産を取得した |
Q6. 配偶者居住権ってなに?
配偶者居住権とは、亡くなった方の所有していた建物(自宅)に、配偶者が無償で住み続けられる権利のことです。
たとえば、夫が亡くなり、妻と子どもが相続人となった場合、従来は妻が自宅を相続すると、その価額が高いためにほかの財産を十分に相続できず、老後の生活資金に困ってしまうケースがありました。
このような問題を解決するため、自宅の「所有権」と別に「自宅に住む権利」として配偶者居住権を設定することで、配偶者は自宅に住み続けながら、生活資金などもより多く相続しやすくなっています。
配偶者居住権の詳しい内容は、下記の記事をご参照ください。
家の相続が不安な方は専門家に相談しよう!
この記事では、家を相続する際の基本的な手続きの流れと費用についてお伝えしました。
家の相続手続きは、複雑で手間がかかるため、ご自身のみで進めるのは難しいと感じる方もいらっしゃるかと思います。
もし、家の相続手続きに関して少しでも不安を感じることがあれば、一人で抱え込まずに専門家に相談しましょう。
相続専門の弁護士・税理士・司法書士などに相談すれば、ご自身の状況に合わせた最適な手続きの進め方をアドバイスしてもらえます。
事務所によっては無料相談を実施していることもあるので、まずは「どのようなサポートが受けられるのか?」「費用はどのくらいか?」などを確認してみてはいかがでしょうか。