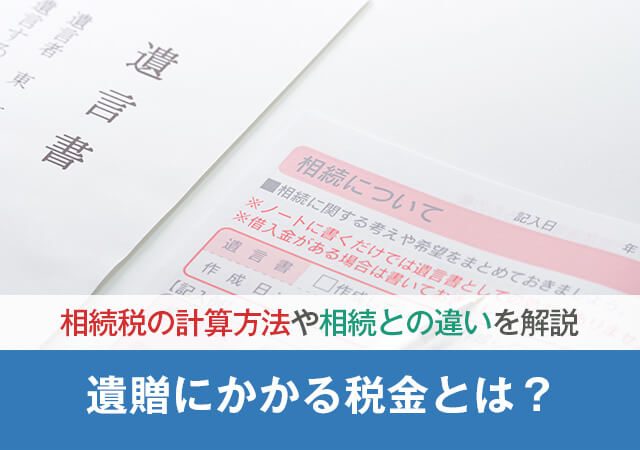この記事でわかること
- 遺贈とは何か、遺贈と相続の違い
- 相続税の計算方法と注意点
- 不動産や有価証券の遺贈や遺贈寄付でかかる税金
内縁の夫が残した遺言書に「全財産を内縁の妻A子に遺贈する」と明記されていたり、祖父母から遺産を引き継ぐことになったりしたら……。
その財産は「遺贈」扱いになります。
「遺贈」とはどのような制度でしょうか?また、遺贈を受けるとどのような税金がかかるのでしょうか。
この記事では「遺贈」の概要や相続税の計算方法、相続との違い、注意点を解説します。
目次
「遺贈」とは何か
「遺贈」とは、被相続人(亡くなった人)の遺言書によって、個人や法人・団体に対し財産の一部もしくはすべてを譲ることです。
被相続人の財産は、基本的には法定相続人(民法で定められた被相続人の財産を引き継ぐ権利のある人)が引き継ぎます。
何の対応もしなければ、そのまま法定相続人が財産を引き継ぐことになり、お世話になった人や思い入れのある法人などに、財産を遺すことはできません。
そこで遺言書に、たとえば「全財産をホームヘルパーB子に遺贈する」と記載することで、法定相続人以外の人にも財産を引き継ぐことができるのです。
また、遺贈するには遺言書で意思表示をすればよく、双方の合意は必要ありません。
遺言書がある場合は、原則としてその遺言書の内容どおりに遺産分割を行います。
そのため遺贈は、法定相続人以外の人などにも財産を遺せる、被相続人の意向を反映した遺産分割方法といえます。
なお遺贈には、「特定遺贈」と「包括遺贈」の2種類があります。
「特定遺贈」は、遺言書で財産を具体的に指定して引き継ぐ方法のことです。
「〇〇市にある土地を孫C男に遺贈する」などのように、あらかじめ譲る財産が特定されています。
遺言書に記載のない限り、受遺者(財産を受け取る人)が借入金などのマイナスの財産を引き継ぐことはありません。
一方「包括遺贈」は、遺言書で財産の全部または一定の割合のみを指定して引き継ぐ方法のことです。
「財産の30%を内縁の妻A子に遺贈する」「財産の2分の1を孫C男に遺贈する」などのように、割合は記載しますが、どの財産かは指定しません。
そのため包括遺贈の場合は、借入金などのマイナスの財産も引き継ぐ可能性があります。
特定遺贈と包括遺贈では、「相続放棄」の流れにも違いがあります。
特定遺贈の場合は、他の相続人に対して放棄の意思表示をすれば事足りますが、包括遺贈の場合は、相続開始を知ったときから3カ月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。
「相続」との違い
「相続」とは、被相続人の死亡をもって、法定相続人に財産を引き継ぐことです。
相続の手続きは民法で定められており、遺言書がある場合は原則として遺言書の内容どおりに、遺言書がない場合は相続人全員で遺産分割協議を行って、遺産を引き継ぎます。
法定相続人となる人の優先順位も定められています。
遺言書がなくても相続できますが、被相続人としての意思を遺言書で残しておくことで、遺産分割をスムーズに行い、相続人同士の争いを防ぎうるメリットがあります。
遺贈は「相続税」の課税対象
「贈」の文字が入っていますが、遺贈は贈与税ではなく「相続税」の課税対象です。
遺贈は相続と同様、被相続人の財産を引き継ぐことに変わりはありません。
また遺言書は生きているときに書きますが、実際に財産の引き継ぎが発生するのは被相続人が亡くなったときです。
そのため遺贈は贈与ではないとされ、相続税が課されます。
さてここで少し、「贈与」について補足します。
贈与は、財産を無償で他人に与える行為であり、贈与者と受贈者の双方の合意が必要です。
ここが遺贈や相続と異なる点です。
贈与のうち、「生前贈与」は、被相続人の生前に双方で贈与契約を結び、財産の引き渡しまで行うことです。贈与者と受贈者のどちらかが亡くなっている場合には生前贈与は成立しません。
一方「死因贈与」では、贈与契約は生前に結ぶものの、贈与の効力は実際に亡くなったときに発生します。
死因贈与も贈与契約を締結しているため贈与税の対象になりそうですが、亡くなってから財産が移転することからその経済的な効果は相続と変わりません。そのため相続税の課税対象とされています。
遺贈による相続税の計算方法と注意点
遺贈を受けた場合に支払う相続税の計算方法は、通常の相続があった場合に支払う相続税の計算方法と基本的な違いはありません。
ここでは遺贈を受けた場合の相続税の計算方法について、大まかな流れや注意点を確認しておきましょう。
正味の遺産額を計算する
- プラスの財産、マイナスの財産双方を入れて財産をリストアップする
- 生命保険金や死亡退職金などの「みなし相続財産」も計算に入れる
- 墓地や墓石、仏壇、仏具などは非課税
相続税を計算するうえで最も重要なのは、相続財産を漏れなく洗い出し、適正な相続税評価額を計算することです。
財産をすべて把握できていないと、後から遺産分割協議がやり直しになる可能性もあり、相続税の計算も本来の税額と異なります。
相続財産として預貯金、不動産、有価証券などはすぐに思い浮かびやすいですが、生命保険やゴルフ会員権など、相続財産になるものは数多くあるため、漏れのないようにしましょう。
課税遺産総額、相続税の総額を算出する
- 正味の遺産額から、相続税の基礎控除額を差し引いて課税遺産総額を求める
- 次に課税遺産総額を法定相続分どおりに取得したものと仮定して、各相続人の相続税額を求める
- 各相続人の相続税額合計額が相続税の総額となる
相続税の基礎控除額は、以下の式で算出します。
計算式
相続税の基礎控除額=3,000万円+
(600万円×法定相続人の数)
法定相続人3人・法定相続人以外1人の計4人が、被相続人の遺産を引き継いだ場合、相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×3人=4,800万円」となります。
このように、法定相続人でない人は、相続税の基礎控除額の計算に含めることはできませんので、気をつけましょう。
相続税の基礎控除額を求めたら、課税遺産総額を法定相続分どおりに取得したものと仮定して、相続税の総額を算出します。
まずは、課税遺産総額を法定相続分で按分します。この計算においても法定相続人でない人を含めないように注意しましょう。
法定相続分で按分したら、相続税の速算表を用いて各相続人の相続税額を計算します。
| 法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | - |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
この計算過程で、相続人全員で納付する相続税の総額が算出できます。
ただし、この段階ではまだ、実際に各相続人がいくらの相続税を納付するかが決まった訳ではありません。
各相続人の納付税額を算出する
- 求めた相続税の総額を、実際に各相続人が取得した財産に応じて按分する
- そこから、利用できる税額控除があれば控除額を差し引いて、各々の納税額を算出する
各相続人の相続税の納付税額は、その相続人が実際に取得した財産の割合に応じて決まります。全体の相続税の総額を、それぞれの相続人が実際に取得した財産の額に応じて按分して相続人ごとの納付税額を算出します。このときは、法定相続人だけでなく財産を引き継ぐすべての人で相続税の総額を按分します。
「遺贈」があった場合の注意点
相続税の計算方法は相続の場合と基本的に変わりませんが、遺贈があった場合は、相続税の計算過程で注意しなければならない点がいくつかあります。
遺留分を侵害しないようにすること
「遺留分」とは、法律上定められた兄弟姉妹以外の法定相続人が最低限相続できる割合のことです。
遺留分は、遺族の生活を保障するための制度であり、たとえ被相続人が遺言書を残していたとしても、遺留分をはく奪することはできません。
もし、遺贈によって遺留分が侵害されることがあった場合、侵害された相続人は「遺留分侵害額請求」を行うことができます。
遺留分を侵害された相続人と受遺者との間で、トラブルに発展する可能性もあるため、遺贈の際は、遺留分を侵害しないように注意が必要です。
法定相続人でない受遺者は、法定相続人の数に「含めない」
相続税の基礎控除額の計算や、相続税の総額の計算において課税遺産総額を法定相続分で按分する際には、「法定相続人以外の人」は、計算式の法定相続人の数に含めることはできません。
たとえば、被相続人の財産を引き継いだ人が4人でも、うち1人が法定相続人でない場合、相続税の基礎控除額は法定相続人の3人、「3,000万円+(600万円×3人)」で計算します。
遺贈を受けた人が法定相続人でない場合は、相続税の基礎控除額の計算に含められませんので注意してください。
相続税の総額を各相続人に按分するとき
実際に財産を取得した割合に応じて、各相続人に相続税の総額を振り分ける際には、「法定相続人以外の人」も含めます。
実際に相続税を納付するのは、財産を取得した人です。
そのため、法定相続人でない人も遺贈により財産を取得しているのであれば、相続税を納税することとなります。
相続税額の2割加算について
相続や遺贈、相続時精算課税にかかる贈与によって財産を取得した人が被相続人の一親等の血族および配偶者以外の人である場合、相続税額が2割加算となります。
つまり遺贈の場合だけでなく、法定相続人であっても、兄弟姉妹が相続する場合にはこの2割加算の対象となるため、注意が必要です。
遺贈では、孫などが財産を取得するケースも多いため、通常の相続税より負担が増えることに注意しなければなりません。
不動産を遺贈された場合
法定相続人以外の人が不動産を遺贈された場合、相続税のほかに不動産取得税・登録免許税がかかる可能性があります。
また、相続登記の義務化により、所定の手続きが必要になります。
「不動産取得税」と「登録免許税」がかかる場合も
不動産取得税
不動産取得税とは、土地や家屋などの不動産を取得したときに、取得した人に対してかかる税金です。
不動産を法定相続人以外の人に特定遺贈する場合は、不動産取得税が発生しますので注意が必要です。
なお、包括遺贈の場合、不動産取得税はかかりません。
不動産取得税は、以下の計算式で算出されます。
不動産取得税の計算式
固定資産税評価額×税率
不動産取得税の税率は、土地や家屋(住宅)の場合は3%、家屋(住宅以外)の場合は4%です。
登録免許税
登録免許税は、不動産の登記(名義変更)をする際にかかる税金です。
特定遺贈、包括遺贈、いずれの場合も登録免許税がかかります。
登録免許税の計算式
固定資産税評価額×税率
登録免許税の税率は、相続人以外の人に対する遺贈の場合は2%です。
なお、相続で不動産を取得した場合の登録免許税は「固定資産税評価額×0.4%」ですので、それよりも重い税率がかかります。
特に特定遺贈の場合は、法定相続人ではない受遺者は不動産取得税と登録免許税の両方を負担することになるため、注意が必要です。
また、不動産の所有者をはっきりさせるため、相続や遺贈によって不動産を取得した人は「不動産を取得したことを知った日から3年以内」に相続登記や遺贈登記の申請が義務づけられています。
正当な理由なくして義務に違反した場合は、10万円以下の過料の適用対象となります。
不動産を引き継ぐ際は注意しましょう。
遺贈寄付で相続税が非課税になる?
被相続人の財産は、個人だけではなく、法人・団体にも遺贈することができます。
法人・団体に寄付することを「遺贈寄付」といいます。
遺贈寄付は、自身に関心のある分野に対し、遺産を通して社会貢献ができる制度です。
遺贈寄付をした財産は、相続税の控除対象に含まれます。
また、公益性の高い税制優遇団体に遺贈した場合は、被相続人の準確定申告をすることで所得税の寄付金控除を受けることができます。
なお、遺贈を受けた法人・団体には、原則として相続税は発生しません。
相続税はあくまでも個人に対して課税される税金です。
法人が遺贈を受けた場合は、原則として法人税の対象となります。
ただし、非営利型法人である公益法人や認定NPO法人などは、遺贈寄付を受けたとしても収益事業にあたらないため、法人税は課税されません。
なお、特定遺贈によって法人に不動産や有価証券を遺贈した場合、相続開始日に法人へ譲渡したとみなされ、含み益に対して「みなし譲渡所得税」が発生することがあります。
この場合、不動産や有価証券の相続開始日の時価で譲渡所得税を計算し、準確定申告や納税の手続きをしなければなりません。
寄付をしたのに税金がかかる事態を避けるため、不動産などを寄付しようと考えている方は、「みなし譲渡所得税」の対策も必要です。
遺贈の相続税で困ったら専門家に相談しよう
遺贈でかかる税金は相続税です。
不動産を取得した場合には、不動産取得税や登録免許税がかかることがあります。
また、遺贈が行われると、相続税の2割加算の対象となるケースが多くあります。
相続税の額が2割増えるとかなり負担が大きくなるため、そのことを理解したうえで遺産の分割案を検討し、遺言書を作成するようにしましょう。
不動産を引き継ぐ場合は、書類を揃えたり手続きを行ったりするのが煩雑なこともあります。
遺贈の相続税で困ったら、相続専門の税理士への相談がおすすめです。
専門家であれば、相続税の計算から節税する方法まで、適切にアドバイスをくれます。
自力で相続税の申告手続きも可能ですが、法的な専門知識が必要になるため、最初から専門家に任せたほうが確実でしょう。
初回の相談を無料で受け付けている専門家も多いため、まずは無料相談から利用するのがおすすめです。