

東京弁護士会所属。新潟県出身。
交通事故の影響で怪我や病気になってしまうと、体調の不安に加えて、経済的な不安も発生します。
慰謝料を請求するためには、法律上の知識や、過去の交通事故被害がどのような慰謝料額で解決されてきたかという判例の知識が必要です。
我々はこういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって、妥当な損害賠償金を勝ち取ることが期待できます。是非一度ご相談ください。
PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/kawasaki/
書籍:この1冊でわかる もめない遺産分割の進め方: 相続に精通した弁護士が徹底解説!
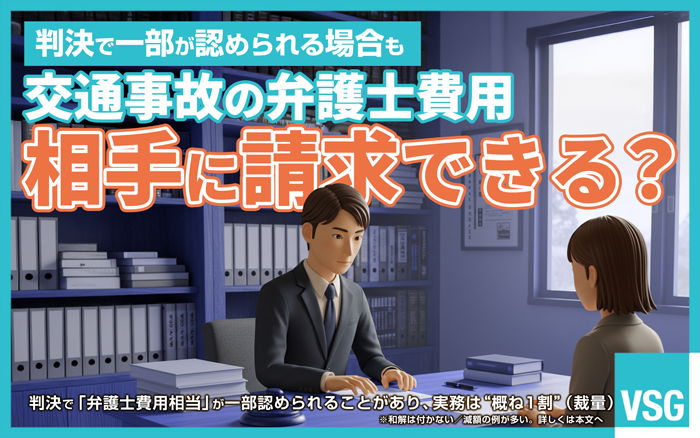
目次
交通事故でかかる弁護士費用は、本来であれば支払うことのなかったお金です。賠償金を支払ってもらっても、弁護士費用がかかってしまっては費用倒れになってしまう恐れもあるでしょう。
交通事故の弁護士費用を請求できるかは、「示談交渉」と「裁判」で異なります。
保険会社との示談交渉では、弁護士費用を支払ってもらうことはできません。
加害者が賠償義務を負うのは、交通事故で通常発生するであろう損害の賠償に限られます。弁護士に依頼するかどうかは被害者の任意なので、弁護士費用は交通事故の損害には含まれないことになるのです。
加害者に直接、弁護士費用を請求したとしても、素直に支払ってくれるケースはほとんどないでしょう。
一方で、裁判なら弁護士費用を加害者側に支払ってもらうことも可能です。
裁判は、弁護士に依頼せずに被害者自身で提起できます。そのため、弁護士費用も相手に請求できないのが原則です。しかし、裁判に適切に対応するには非常に高い専門性が必要であり、一般的にも弁護士に依頼するケースがほとんどです。これらの理由から、裁判では弁護士費用を相手に請求することが認められているのです。
なお、裁判所から和解案を提示されて、お互いの合意のうえで裁判を終わらせる場合には、弁護士費用は「調整金」という項目で支払われるケースが多いです。
たとえ裁判であっても、弁護士費用の全額を請求することはできません。裁判所が個別のケースごとに、適切な金額を算定します。
裁判で認められる弁護士費用は、法律で明確に規定されている訳ではありません。
ただし、多くのケースでは、裁判で認められた賠償額の10%程度が弁護士費用として認められます。たとえば、裁判所が100万円の賠償金を認めた場合、弁護士費用として請求できるのは10万円になります。
実費全額を相手に請求できる訳ではないので、注意が必要です。
裁判であれば、加害者に遅延損害金も請求できます。
本来、交通事故の加害者は、事故時点で損害を賠償する義務を負います。そのため、賠償金の支払いが遅れたことによる損害の賠償を負う義務も生じます。
遅延損害金の計算方法は、次のとおりです。
裁判をおこなうためにかかる費用については、基本的に裁判で負けた側が支払い義務を負います。
訴訟費用は、収入印紙代金や切手代金、書類作成費用など、裁判を円滑に進行するためにかかる諸経費です。
裁判に負けた側が訴訟費用をいくら支払うことになるのかは、個別のケースごとに異なります。
請求する金額が大きい場合、その分、訴訟を提起する際にかかる収入印紙代も高額になります。示談交渉で揉めて裁判を起こす場合には、敗訴して訴訟費用を負担するリスクを下げるために、事前準備をしっかりおこなうことが重要になるでしょう。
交通事故の加害者側に弁護士費用を請求するには、裁判を起こす必要があります。
請求する賠償額や弁護士費用を記載した訴状を作成し、管轄する裁判所に提出しましょう。弁護士費用は、全体の損害額から過失相殺や損益相殺などの処理をしたうえで、その金額の10%程度を請求額として記載することになります。
裁判を起こしたからといって、必ずしも勝訴できる訳ではありません。裁判官からの和解案に従って示談するケースも多いですし、場合によっては適切な反論ができずに敗訴してしまう場合もあるでしょう。
敗訴すれば弁護士費用も請求できず、訴訟費用を負担する義務も生じてしまいます。1人で対応が難しければ、専門家である弁護士に早めに相談することをおすすめします。
交通事故で裁判に発展する主なケースは、以下のとおりです。
裁判を起こすかどうかは、交渉の進捗状況や賠償額を増額できる可能性などを総合的に判断する必要があります。裁判になればその分、賠償金の受け取りも遅くなるので、そういったデメリットも加味したうえで慎重に判断する必要があるでしょう。
保険会社との示談で話がまとまる場合、加害者側に弁護士費用を請求できません。そのため、獲得できる賠償金が少ない場合には、弁護士に依頼することで赤字になってしまう恐れもあるのです。
たとえば、次のようなケースでは、費用倒れになるリスクがあります。
弁護士への相談時に費用倒れのリスクも説明してくれるので、依頼すべきかどうかは弁護士にアドバイスをもらうのがよいでしょう。
被害者や家族などが加入している保険に弁護士費用特約が付帯していれば、弁護士への依頼費用を保険会社が支払ってくれます。
上限金額は定められていますが、多くの場合、実質負担ゼロで弁護士に依頼できます。特約を使えば費用倒れの心配もありません。また、裁判では弁護士費用特約を使っている場合でも、弁護士費用の支払いを保険会社に命じたケースもあります。
特約を使うことで保険料が上がるなどのリスクはないので、弁護士に依頼する前に1度、保険証券などで特約の有無を確認してみましょう。
交通事故の弁護士費用は、裁判になれば請求することが可能です。ただし、認められた賠償額の10%程度しか請求できないケースが多いです。
示談交渉では請求できませんが、裁判をおこなう手間や勝訴の可能性を考えると、示談交渉で話しをまとめた方がメリットが大きい場合もあります。
交通事故で弁護士に依頼するメリットは大きいですが、費用倒れになるリスクもあります。裁判にすべきかどうかは、交通事故に精通した弁護士に相談してみましょう。

