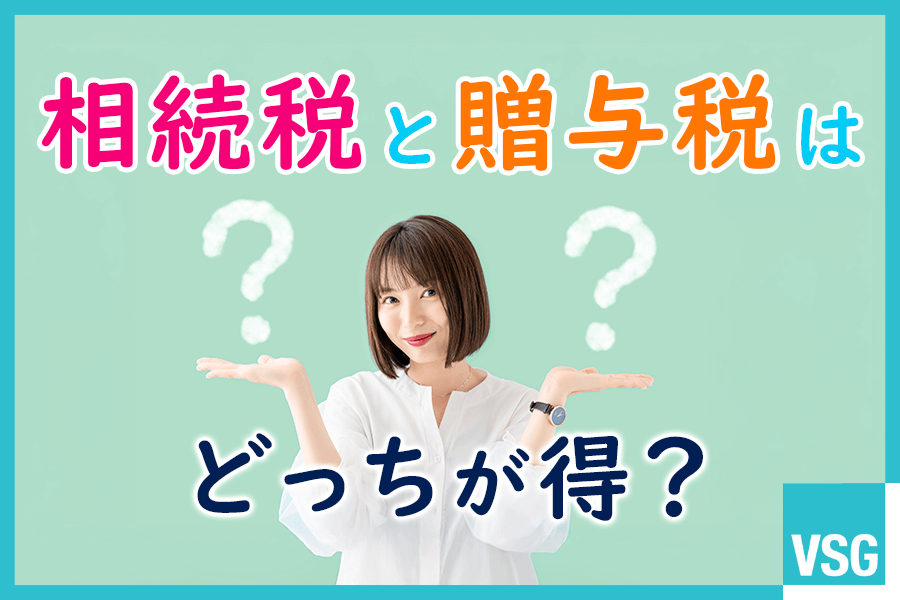この記事でわかること
- 相続税と贈与税の税率や控除額などの具体的な違い
- 生前贈与で活用できる非課税制度の種類と使い方
- 【ケース別】どちらが得になるかのシミュレーションと比較
「子供たちに迷惑をかけず、築いてきた財産を少しでも多く遺したい」
「親が元気なうちに、将来の相続について家族で話し合っておきたい」
この記事をお読みいただいている方は、大切な家族を想うからこそ、「相続」という大きなテーマについて考え始めたのではないでしょうか。
しかし、「相続税と贈与税は、どう違うの?」「生前贈与が有効と聞くけれど、贈与税が高いのでは?」といった疑問は尽きないものです。
ご安心ください。この記事では、相続専門の税理士が最新の税法に基づき、具体的な解決策をどこよりも分かりやすく解説します。
先に結論からお伝えすると、多くの場合、相続税対策は計画的な「生前贈与」が極めて有効な手段となります。
なぜなら、相続税は亡くなった時点での「財産の総額」に対して課税されるため、生前のうちに贈与をして将来の相続財産そのものを減らしておくことが、最も効果の高い節税策となるからです。
ただし、最適な方法はあなたの資産状況や「誰に」「何を遺すか」によって変わります。この記事を通じて、ご自身とご家族にとって最善の相続対策を見つけてください。
目次
第1章:まずは基本から!相続税と贈与税の仕組み
相続税も贈与税も、「財産の無償の移動」に対して課される税金ですが、課税タイミングと目的が大きく異なります。
- 相続税:人が亡くなったときに、その財産を受け取った際に課される税金
- 贈与税:生きている間に財産をあげた際に、財産を受け取った人(受贈者)に課される税金
相続税は、亡くなった人が財産を持っていなければ課されません。
例えば、生前に財産をすべて他人へあげてしまえば、原則として相続税はかかりません。
なお、生きている間に他の人へ財産を引き継ぐことを「生前贈与」と言います。
ただし、国は生前贈与によって相続税の負担を免れることを防ぐため、贈与税の税率を相続税よりも高めに設定しています。
しかし、この原則だけにとらわれず、さまざまな非課税制度や控除を理解し活用することが、賢い相続対策の第一歩となります。
第2章:相続税と贈与税の6つの違い
相続税と贈与税には、具体的にどのような違いがあるのでしょうか。特に重要な6つのポイントを分かりやすく解説します。
違い①:税金を納める人
相続税は、「相続」で財産を取得した人に対して課されます。
一方、贈与税は「贈与」で財産を取得した人に課されます。
違い②基礎控除額(非課税枠)【相続税のほうが大きい!】
相続税と贈与税の基礎控除額は、以下のとおりです。
- 相続税
- 基礎控除額: 3,000万円+(600万円✕法定相続人の数)
- 贈与税
- 基礎控除額:110万円/年
なお、法定相続人とは、民法で定められた「遺産を相続する権利がある人」のことです。
違い③:税率と税率を掛ける課税標準
- 相続税
- 税率は10%から55%までの累進課税です。
- 贈与税
- 贈与税の課税方法には「暦年課税」と「相続時精算課税制度」の2種類があります。
- 1.暦年課税
- 税率は10%から55%までの累進課税です。
贈与者が受贈者の直系卑属(子、孫、ひ孫など)である場合と、そうでない場合とで、贈与額に乗じる税率が変わります。
「違い②」のとおり、相続税よりも贈与税のほうが、基礎控除額が小さいため、同じ税率であっても税額に大きな差が出ます。 - 2.相続時精算課税制度
- 税率は20%です。
累計2,500万円までの特別控除と、年間110万円の基礎控除があります。
基礎控除を超えた贈与は、特別控除2,500万円まで贈与時には贈与税がかからず、特別控除2,500万円を超えた贈与に対しては一律20%の税率が適用されます。
なお相続が発生した際、基礎控除を超えた贈与分は、相続財産に加算されて相続税が計算されます。
違い④:財産を渡すタイミング
相続税は、人が亡くなった時の財産に対して課されます。財産を渡すタイミングは1回きりで、時期を選ぶことはできません。
一方、贈与税が課されるタイミングは生きている間に財産をあげた時です。財産は、あげたい時に何度でも渡すことができます。
違い⑤:不動産取得時の税金
不動産を取得すると、「不動産取得税」と「登録免許税」がかかります。いずれの税率も、相続で不動産を取得した場合のほうが優遇されています。
- 相続:非課税
- 贈与:1,000分の15~40
- 相続:1,000分の4
- 贈与:1,000分の20
違い⑥:申告と納税の時期
- 相続税:相続が開始したこと知った日の翌日から10カ月以内
- 贈与税:贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日まで
相続税はこの期間内で、財産調査や遺産分割協議なども行います。
第3章:【ケース別】生前贈与と相続、どちらを選ぶべきか徹底シミュレーション
「結局、自分の場合はどうなの?」という疑問に答えるため、具体的な家族構成や財産額を想定したシミュレーションを見ていきましょう。
なお、被相続人が亡くなった年は、いずれも2031年とします。
ケース1:財産5,000万円(法定相続人子2人、相続税の基礎控除4,200万円)の場合
この場合、何の対策もしなければ相続税は80万円かかります。
それでは、10年間、子2人に毎年110万円ずつ生前贈与した場合はどうなるでしょうか。
① 暦年課税を利用した場合
110万円✕10年ー(110万円✕7年ー100万円*)=430万円
5,000万円ー430万円=4,570万円>基礎控除4,200万円
4,570万円-4,200万円=370万円
370万円✕1/2(法定相続分)=185万円
185万円✕税率10%=18.5万円ー控除額0円
18.5万円✕子2人=37万円
相続税額は「37万円」
相続時精算課税を利用した場合
110万円✕10年=1,100万円
5,000万円ー1,100万円=3,900万円<基礎控除4,200万円
相続税額は「0円」
贈与税はいずれのパターンでもかかりません。
相続税については、(*)のとおり、暦年課税には、相続開始7年以内の贈与は相続財産に持ち戻して相続税を計算する決まりがあります(生前贈与加算)。
ただし、相続開始前4年から7年の間の贈与の持ち戻しからは、100万円控除できることになっています。
財産額が相続税の基礎控除額に近い場合、相続時精算課税で贈与税の基礎控除以下の贈与を長期間行い、財産額を基礎控除額以下にすることで、相続税も贈与税も負担することなく次世代への財産移転が可能となります。
ケース2:財産1億円(法定相続人子2人)の場合
- 何もしなければ相続税は770万円かかる
- 0年間、子2人に毎年110万円ずつ生前贈与した場合
①暦年課税
110万円✕10年ー(110万円✕7年ー100万円*)=430万円
1億円ー430万円=9,570万円>4,200万円
9,570万円ー4,200万円=5,370万円
5,370万円✕1/2=2,685万円
2,685万円✕15%=402.75万円ー50万円=352.75万円
352.75万円✕2人=705.5万円
相続税額は「705.5万円」
②相続時精算課税
110万円✕10年=1,100万円
1億円ー1,100万円=8,900万円>4,200万円
8,900万円-4,200万円=4,700万円
4,700万円✕1/2=2,350万円
2,350万円✕15%=352.5万円ー50万円
302.5万円✕2人=605万円
相続税額は「605万円」
暦年課税では相続開始前7年以内の贈与が相続財産に持ち戻されるため、節税効果が限定的になります。
一方、相続時精算課税制度を利用すれば、基礎控除内の贈与については持ち戻しが不要となるため、結果として相続税額を抑えることが可能です。
ケース3:財産1億円、子2人のうち特定の子供に多くの財産(2,500万円)を渡した場合で、贈与後8年経過後に相続が発生した場合
①暦年課税
2,500万円-110万円=2,390万円✕税率50%-控除額250万円=945万円
相続税:
(1億円ー2,500万円)ー4,200万円✕1/2=1,650万円
1,650万円✕15%ー50万円=197.5万円✕2人=395万円
贈与税と相続税の合計:1,340万円
②相続時精算課税
2,500万円-110万円=2,390万円<特別控除2,500万円
贈与税は0円
相続税:
(1億円ー2,500万円)+2,390万円ー4,200万円✕1/2=2,845万円
(2,845万円✕15%ー50万円)✕2人=753.5万円
贈与税と相続税の合計:753.5万円
暦年課税で2,500万円を一度に贈与すると、贈与税率は50%にもなります。
しかし、相続時精算課税を利用すれば、贈与時に高額な税金を支払うことなく財産を渡すことができます。
そのため、ケース3では贈与税と相続税を合計した負担額が、暦年課税よりも少なくなります。
ケース4:財産13億円、子2人のうち特定の子供に多くの財産(2,500万円)を渡したい場合で、贈与後8年経過後に相続が発生した場合
①暦年課税
2,500万円-110万円=2,390万円✕50%-250万円=945万円
相続税:
(13億円-2,500万円)-4,200万円)✕1/2=61,650万円
(61,650万円✕55%-7200万円)✕2人=5億3,415万円
贈与税と相続税の合計:5億4,360万円
②相続時精算課税
贈与税は0円
相続税:
(13億円ー2,500万円)+2,390万円)ー4,200万円✕1/2=6億2,845万円(6億2,845万円✕55%ー7,200万円)✕2人=5億4,729.5万円
贈与税と相続税の合計:5億4,729.5万円
相続税率が高い超富裕層の場合、暦年課税で「持ち戻しの対象とならない贈与」を行えば、贈与税を負担したとしても、結果的に暦年課税のほうが税負担が少なくすみます。
一方、相続時精算課税では、基礎控除を超える贈与はすべて相続財産に持ち戻されるため、節税効果が限定的です。
したがって、上記のケースでは暦年課税のほうが有利になります。
第4章:必ず知っておきたい!贈与税が非課税になる3つの特例制度
生前贈与を有利に進めるには、国が用意した非課税制度を活用しましょう。ここでは代表的な制度をどんな人におすすめかも含めて解説します。
【基本】暦年課税制度(年間110万円まで非課税)
財産の贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与税の申告をします。
届出も不要で最も手軽で基本的な節税策といえますが、相続開始前7年以内の贈与は基礎控除以下の贈与であっても相続財産に持ち戻すことになりますので、7年以内に贈与者がなくなった場合は、相続税対策とはならなくなります。
【2024年改正】新しくなった「相続時精算課税制度」を徹底解説
2024年(令和6年)の税制改正により、「相続時精算課税制度」が大きく変わりました。
制度の仕組みは以下のとおりです。
- 贈与者(財産をあげる人):贈与年の1月1日時点で60歳以上の父母または祖父母
- 受贈者(財産をもらう人):贈与年の1月1日時点で18歳以上の子または孫(養子を含む、直系卑属の推定相続人)
- 控除額:特別控除 2,500万円、基礎控除 110万円(2024年から新設)
改正のポイント
2023年までの制度では「基礎控除」がなく、贈与した財産はすべて相続時に持ち戻して相続税を計算していました。
2024年の改正により新たに「年間110万円の基礎控除」が設けられ、この範囲内の贈与は相続財産に持ち戻されず、非課税となりました。
つまり、年間110万円までの贈与であれば、暦年課税よりも有利に財産を移転できます。
税金の扱い
「特別控除2,500万円以内+基礎控除110万円以内」であれば、贈与税はかかりません。
2,500万円を超える部分については、一律20%の贈与税率が適用されます。
ただし、将来相続が発生した場合には、基礎控除を超えた贈与分が相続財産に加算されて相続税が計算されます。
この制度は、税金の支払いを将来に繰り延べる仕組みです。
注意点
この制度を利用した場合、贈与の翌年3月15日までに届出を提出する必要があります。
また、一度相続時精算課税制度を選択すると、暦年課税へ戻すことはできません。
どんな人が使うべきか?
相続時精算課税制度は、暦年課税と異なり7年以内の持ち戻しがありません。
そのため、比較的高齢であっても、少額の贈与をコツコツ積み重ね、相続税対策を進めたい人にとっては利用しやすい制度です。
また、この制度では、贈与財産を相続財産に持ち戻すときに「贈与時の時価」で評価されます。
したがって、将来の値上がりが見込まれる財産を贈与するときに利用するとよいでしょう。
【目的別】特定の目的で使える非課税制度
特定の目的で行う贈与には、下記の優遇措置が設けられています。
- ① 住宅取得等資金の贈与
- ② 教育資金の一括贈与
- ③ 結婚・子育て資金の一括贈与
| 制度名 | 非課税限度額 | 主な要件とポイント | こんな方におすすめ |
|---|---|---|---|
| 住宅取得等資金の贈与 | 最大1,000万円 | 子や孫がマイホームを新築・取得・増改築するための資金。省エネ等、質の高い住宅の場合に限度額1,000万円が適用される。(2025年9月現在) | 子や孫のマイホーム購入を資金面で大きくサポートしたい父母・祖父母 |
| 教育資金の一括贈与 | 最大1,500万円 | 30歳未満の子や孫の教育資金(入学金、授業料など)として贈与できる。なお、金融機関に信託等する必要がある。 | 孫などの将来の学費を、自身が元気なうちに確実に確保してあげたい祖父母 |
| 結婚・子育て資金の一括贈与 | 最大1,000万円 | 18歳以上50歳未満の子や孫の結婚・出産・育児費用として贈与できる。教育資金の一括贈与と同様、金融機関での手続きが必要。 | 子どもの結婚式や孫の誕生に合わせて、まとまった資金援助をしたい父母・祖父母 |
これらの贈与特例を利用すると、一定額の贈与までは贈与税がかからないため、子や孫を金銭面で支援しやすくなります。
ただし、②の教育資金の一括贈与と③の結婚・子育て資金の一括贈与は、まとまった額を一度に贈与し、一定期間の間で贈与財産を費消していく仕組みですが、一定期間の間に使い切らずに残額があると残額に贈与税がかかります。
また、一定期間内に贈与者が亡くなり相続が発生すると、そのときの残高を相続財産に持ち戻さなくてはならないケースがあり、相続税対策とはならないことがあります。
第5章:【失敗事例から学ぶ】生前贈与でやりがちな3つの落とし穴
良かれと思って行った生前贈与が、税務署に否認されてしまうケースもあります。よくある失敗事例とその対策を知っておきましょう。
注意点①:「名義預金」とみなされ贈与が認められない
事例
祖父母が孫名義の通帳を管理しているだけでは贈与にならない!
名義預金とは、実際の出資者と口座の名義人が一致しない預金のことです。
祖父母が孫名義の預金口座を開設し、毎年基礎控除以下の金額を振り込めば、贈与税はかからないと考えている方もいます。しかし、その預金通帳、印鑑、キャッシュカードを祖父母が管理しており、孫が自由に預金を使えない状態の場合、贈与は成立していません。
例えば、500万円が貯まった段階でその預金通帳、印鑑、キャッシュカードをまとめて孫に渡した場合、渡した時点で500万円に対して贈与税が課税されることになります。また、その時点で相続が発生したら、500万円は相続財産として扱われ、課税対象となります。
事例
専業主婦のへそくりは夫のもの
生活費の負担者は仕事をしている夫であり、専業主婦である妻は渡された生活費をやりくりしてへそくりを貯めていたとします。
この場合において、夫に相続が発生したとき、そのへそくりが妻の預金口座に入っていたとしても、夫の相続財産として計上することになります。
生活費の残りを夫自身の老後資金と考えていたか、妻にあげたつもりだったのかは夫自身にしか分からないことであり、そのような場合、資金の所有者は出捐者(しゅつえんしゃ)である夫と考えます。
注意点②:贈与契約書を作成していない
贈与は口頭でも成立しますが、贈与契約書を作成しておくほうが望ましいです。贈与契約書は贈与の意思を明確に示すものですので、後々のトラブル防止につながります。
例えば、税務調査で被相続人と相続人の口座間に多額の資金移動が確認された場合、贈与税の時効期間を過ぎていると、「貸付金として相続財産に計上すべき」と指摘されることがあります。
ここで、贈与契約書があれば「贈与があった」と判断できるため、貸付金とされる可能性は低くなります。
また、へそくりのように家庭内で資金を移す場合も、「毎年年末に生活費の残額を妻に贈与する」として贈与契約書を作成していれば贈与の意思が認められ、へそくりは妻の財産として認められます。
注意点③:相続開始前7年以内の贈与は相続財産に加算される【2024年改正】
これは、第4章でも触れた2024年からのルール改正で、最も注意すべき点です。
「もうすぐ相続が発生しそうだから、今のうちに贈与して相続財産を減らそう」という、駆け込みの節税対策を防ぐため、相続開始前の贈与は一定期間さかのぼって相続財産に加算されます。
具体的には、亡くなった日からさかのぼって7年間に行われた暦年贈与は、すべて相続財産に持ち戻して相続税を計算し直す必要があります。
2023年までは相続開始前3年以内の暦年贈与が対象でしたが、2024年1月1日以降の贈与から7年以内になりました。
| 贈与の時期 | 相続財産への加算 |
|---|---|
| 死亡日からさかのぼって7年より前 | 加算されない |
| 死亡日からさかのぼって7年以内 | 加算される |
毎年110万円の非課税枠を利用して贈与を続けても、亡くなる直前の7年間分は、結果的に相続税の課税対象となってしまうのです(※ただし、死亡前4〜7年以内に行われた贈与については、合計額から100万円を控除できる経過措置があります)。
そのため、相続税対策として基礎控除以下の金額を贈与するのであれば、相続時精算課税を選択して贈与をすることをおすすめします。
一方、相続税負担の大きい超富裕層が、生前のうちに多額の財産を贈与して相続税対策をしたいのであれば、相続開始7年以内の贈与とならないように、贈与者が若いうちから暦年贈与で贈与をする必要があります。
ここから分かることは、「相続対策は、元気なうちから、一日でも早く、長期的な計画で始めるべき」という、ただ一つの真実です。
思い立ったが吉日。この記事を読み終えた今日が、あなたの家族にとって最適なスタート地点です。
もし具体的な進め方に迷ったら、一人で悩まず、ぜひ私たちのような専門家にご相談ください。
まとめ:最適な選択は十人十色。迷ったら専門家へ相談を
本記事では、相続税と贈与税の違いから、どちらが得になるかの判断基準、具体的な節税策までを解説しました。
生前贈与や相続対策は、財産額や相続人の人数、被相続人と相続人の関係など、ご家庭の状況によって最適な方法が大きく異なります。
基本的な知識を身につけた上で、「自分の場合はどうだろう?」と少しでも疑問や不安を感じたら、一度税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
専門家は、あなたの家族にとって最善の選択肢を一緒に見つけてくれるはずです。