記事の要約
- 相続した宝石・貴金属は、相続税の課税対象となる
- 相続税申告をする際の評価額は、「自分で調べる方法」と「専門家に査定してもらう方法」がある
「亡くなった家族が遺した宝石にも、相続税はかかるの?」
宝石や貴金属も、預貯金・不動産などと同じように「相続財産」として、相続税の課税対象になります。
この記事では、相続税に関することを含め、「宝石・貴金属を相続したときに知っておきたいこと」をお伝えします。
なお、VSG相続税理士法人では、相続に関する相談を無料で受け付けておりますので、下記からお気軽にご連絡ください。
目次
宝石・貴金属を相続したら知っておきたいルール
まずは、宝石・貴金属を相続したときに知っておきたいルールとして、次の3つを紹介します。
それぞれ詳しく見ていきましょう。
ルール1:相続税申告が必要かは「遺産の総額」で決まる
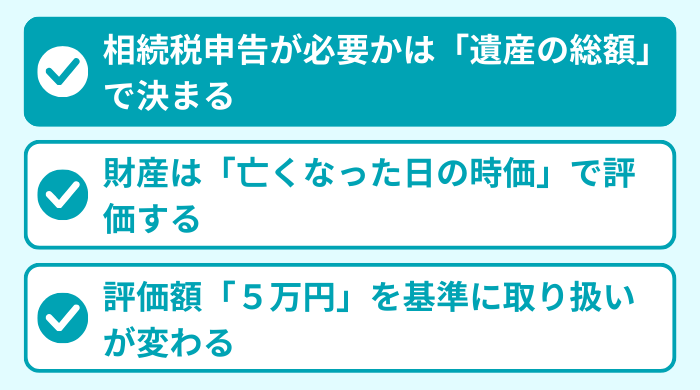
相続税の申告が必要かどうかは、「宝石一つ」の値段で決まるわけではありません。
宝石や貴金属を含め、亡くなった方が遺した「預貯金・不動産・有価証券」など、すべての財産の合計額をもとに判断します。
具体的には、「正味の遺産額※1」が「基礎控除額」を超えた場合に、相続税の申告・納税が必要です。
基礎控除額の計算式
- ※1
- 預貯金や不動産などの「プラスの財産」から、負債などの「マイナスの財産」を差し引いた金額
ルール2:財産は「亡くなった日の時価」で評価する
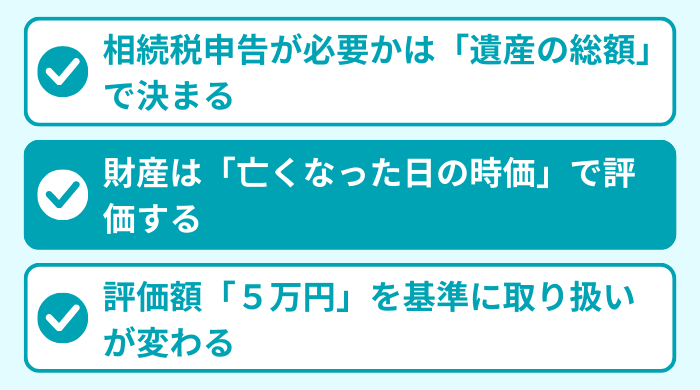
ルール1で出てきた「正味の遺産額」を計算するためには、宝石や貴金属に「いくらの価値があるのか」を正しく評価しなければなりません。
このとき、評価額となるのは「購入したときの価格」ではなく、「故人が亡くなった日の価格(時価)」です。
何十年も前に購入した宝石は、価値が当時と大きく変わっている可能性があるため、ご注意ください。
具体的な宝石・貴金属の評価方法は、「宝石の評価額を調べる方法」と「貴金属の評価額を調べる方法」の見出しでそれぞれお伝えします。
ルール3:評価額「5万円」を基準に取り扱いが変わる
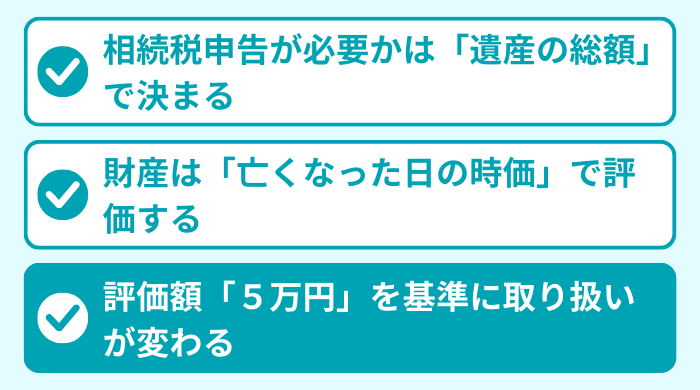
宝石と貴金属は「評価額が5万円を超えるかどうか」で、相続税の手続きをするうえでの取り扱いが、下記のように変わります。
| 評価額 | 取り扱い |
|---|---|
| 5万円以下 |
・ほかの家庭用財産(家具や衣類など)とまとめて、「家財一式」として取り扱う ・具体的には「家財一式 5万円」として、税額を計算したり、申告書に記載したりすることが多い |
| 5万円を超える | ・「指輪(ルビー) 30万円」といったように、1つずつ個別の財産として取り扱う |
宝石の評価額を調べる方法

相続した「ダイヤのネックレス」や「ルビーの指輪」などの宝石の評価額を把握するには、「自分で調べる方法」と「専門家に依頼する方法」の2つがあります。
それぞれの方法をを詳しく見ていきましょう。
方法1:自分で調べる
自分で評価額を調べたいときは、まずその宝石の情報を集めましょう。
故人の自宅に、宝石の「鑑定書・鑑別書・保証書」などが残っていれば、下記のような評価の手がかりがつかめます。
| 手がかり | 概要 |
|---|---|
| 宝石の種類 | ダイヤモンド・ルビー・サファイヤなど、宝石そのものの希少性や人気で価値が決まる |
| 重さ(カラット) | 一般的に、重い(大きい)ほど価値が高くなる |
| 色や透明度 | 美しい色で、キズや内包物(インクルージョン)が少ないものほど価値が高くなる |
| カット(形) | ダイヤモンドなどでは、輝きを引き出す美しいカットほど、評価が高くなる |
| 産地 | 同じ種類の宝石でも、産地によって評価が変わることがある |
| 加工の有無 | 「非加熱(ノーヒート)」など、人の手が加えられていない天然の宝石は価値が高くなる |
ある程度の情報がつかめたら、中古の宝飾品を扱うWebサイトなどで、評価したい宝石と似た商品の販売価格を調べてみましょう。
ただし、この方法で調べられるのは、あくまで「時価の目安」であり、実際の宝石の状態(傷の有無やデザインの新旧)は考慮されません。
ここで本来の時価よりも高く評価してしまった場合、相続税の負担が重くなるおそれがあります。
方法2:専門家に依頼する
宝石の評価額を正確に知りたいのであれば、「買取専門業者」や「質屋」に実物を査定してもらうことをおすすめします。
査定された宝石には「査定書」が発行され、相続税の申告をする際に、「時価を証明する書類」として使えます。
なお、実際に査定を依頼する際は、「相続税の申告で使う」ことを必ず伝えましょう。
「買い取り」を希望していると誤解された場合、本来の評価額よりも低く査定されるおそれがあります。
貴金属の評価額を調べる方法

「金(ゴールド)・プラチナ・銀(シルバー)」といった貴金属の製品を評価するときも、「自分で調べる方法」と「専門家に依頼する方法」があります。
以下では、それぞれの方法を詳しく見ていきます。
方法1:自分で調べる
自分で調べる場合、まずはその製品が「どの貴金属で作られていて、どれほどの純度か」を確認します。
これは、製品に打たれている「刻印」を見るとわかります。
| 金属の種類 | 代表的な刻印と純度 |
|---|---|
| 金 |
・K24、999.9→ほぼ100% ・K18、750→75% |
| プラチナ |
・Pt1000、999→ほぼ100% ・Pt900→90% |
| 銀 |
・SV1000、999→ほぼ100% ・SV925→92.5% |
続いて、下表を参考にしながら、評価したい製品の「重さ」を確認してください。
| 製品の種類 | 重さの確認方法 |
|---|---|
| インゴット(延べ棒)・金貨 | 製品に重さが刻印されている |
| 指輪やネックレスなどのアクセサリー | キッチンスケール(料理用のはかり)などで計測する |
製品の純度と重さがわかったら、買取専門業者のWebサイトなどで「1gあたりの買取相場」を調べましょう。このとき、次の2点にご注意ください。
- 「故人が亡くなった日」の価格を調べる
- 「小売価格」ではなく、「買取価格」をチェックする
ここまでの情報をすべて把握できたら、下記の式で製品の評価額を求められます。
計算式
方法2:専門家に依頼する
より正確な評価額を知りたい場合は、「買取専門業者」や「質屋」に査定してもらいましょう。
特に、アクセサリーを評価するときは、ご自身で正確な重さを測ることが難しいため、専門家に依頼することをおすすめします。
その他の調査方法
ただし、故人の遺産は、遺産分割協議が終わるまでは「相続人全員の共有財産」です。
相続人全員の同意なく勝手に売却すると、後でトラブルの原因になりかねないため、十分にご注意ください。
宝石・貴金属の相続に関するよくある質問
最後に、宝石や貴金属の相続に関して、よくある次の質問にお答えします。
Q1:相続税の申告後に、新たな宝石などが見つかったら?
相続税の申告後に新しく宝石や貴金属が出てきたら、「修正申告」をして、その評価額に応じた追加の納税をしてください。
税務署から指摘される前に自主的に申告すれば、申告漏れがあったことに対するペナルティは軽くなります。
Q2:宝石などの申告が漏れたら、税務署にはバレる?
相続税申告の際に、宝石や貴金属の計上漏れがあった場合、税務署に指摘される可能性は非常に高いです。
税務署は、被相続人が持っていた金融機関の口座の動きをチェックできる権限を持っています。
そこで、多額の「預金の引き出し」や「クレジットカードの引き落とし」が確認されたときには、その用途を徹底的に調べ上げます。
この過程で、過去に宝石や貴金属を購入していたことが発覚し、それが相続税の申告書に載っていないと、税務調査で指摘されることはほぼ確実です。
また、相続した宝石や貴金属を売却したときには、買取業者への調査(反面調査)によって、税務署にバレるケースもあります。
申告が漏れていた場合、本来の税金に加えて「延滞税」や「無申告加算税」といったペナルティが課されます。
さらに、「意図的に財産を隠した」と判断された場合は、もっとも税率が重い「重加算税」を課されるため、はじめから漏れなく申告するようにしましょう。
Q3:相続した金を売却したとき、税金はかかる?
相続した金(ゴールド)などを売ったときに利益が出ると、「所得税」がかかります。
具体的には、下記の式で「利益」がプラスになる場合には、所得税が課されます。
計算式
式のなかの「売却にかかった費用」とは、買取業者に支払った手数料などを指します。
たとえば、「故人が100万円で買った金」を「手数料1万円」かけて「150万円」で売った場合、「49万円」が利益となり、この部分に税金がかかります。
Q4:銀のスプーンや食器は、どう評価すればいい?
銀のスプーンや食器も、基本的には「貴金属の評価額を調べる方法」でお伝えしたのと同じやり方で評価できます。
ただし、次の2点に注意が必要です。
- 銀メッキの場合には、貴金属としての価値はほとんどない
- 有名ブランドや古いアンティークの品は、素材の価値以上の評価になる
なお、「SP」などの刻印がある製品は銀メッキです。
Q5:「純金でできた仏像」は課税対象になる?
ご先祖を祀るために日常的に礼拝しているような「祭祀財産」は、基本的に「非課税財産」として扱われ、相続税はかかりません。
ただし、純金製で美術品としての価値が高かったり、明らかに投資目的や節税対策で購入されていたりした場合には、課税対象になる可能性があります。
相続税の申告をする際、判断に迷うのであれば、税理士に相談しましょう。
宝石・貴金属の相続手続きを正しく進めましょう
この記事では、宝石や貴金属を相続した際に、知っておくべきことをお伝えしました。
相続手続きでは、専門的な知識が必要になる場面も多くあります。少しでも不安を感じたときは一人で抱え込まず、弊社まで気軽にご相談ください。



















